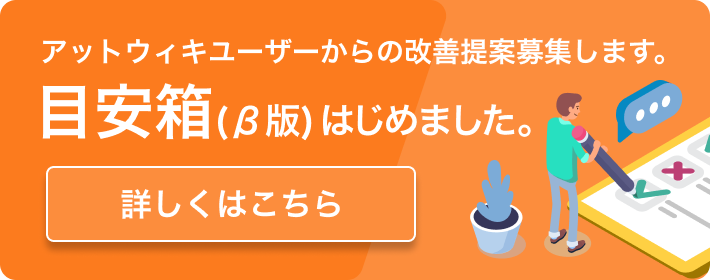【春日権三郎御寵愛ノ事】
「――春日(かすが)権源太が嫡子、吟千代! 烏帽子親、原式部殿! 前へ!」
「はっ!」
「……はっ!」
緊張に唇を引き結びながら、吟千代は主君の前へ進み出る。
この日のためにあつらえた礼服の素襖(すおう)が肩に重く感じる。
吟千代は、まだ十歳であり、本来であれば元服は二、三年先のことであった。
しかし父の権源太頼昌が中気を患い急逝したため、春日氏の家督を継ぐことになったのである。
上総国庁南城主、武田家において、春日氏は原氏、白井氏とともに三家老と称される重臣である。
幼少の吟千代よりも、頼昌の弟で勇猛をもって知られる源八郎昌清を後継の家老に推す声も家中にはあった。
だが、主君である武田三郎信輝はこれを一蹴。
三家老の一人で頼昌の朋友でもあった原式部を烏帽子親として、吟千代の元服式を断行したのである。
元服式の進行役を務めるのは、もう一人の家老である白井大学。
主君信輝と、原、白井という家中の両実力者の後ろ盾を得て、吟千代は元服を果たすことになったのだ。
そのほか家臣の主立った者が立会人として、庁南城の広間を埋めている。
ただし吟千代の叔父、昌清の姿はこの場にない。
吟千代が春日家の後継と決まって以来、昌清は病と称して出仕していない。
信輝の見守る前で、吟千代は原式部と向かい合って着座した。
御屋形様――信輝の視線が、痛い。
信輝は齢十九、上背があって精悍な面構えの美丈夫である。
しかし決して張り子の虎ではなく、十五で家督を継いで以来、十数度の合戦で無敗を誇る。
庁南武田家中では「信玄公の再来」とまで称賛されている。
信玄公とは言わずと知れた甲斐の虎、徳栄軒信玄のこと。
その三男、西保三郎信之が遠縁である上総武田家に養嗣子として迎えられて庁南城主となった。
信輝は信之の孫であり、信玄から数えれば曾孫に当たる。
三郎の名乗りは信之以来、庁南武田家の当主が受け継いでいるものだ。
吟千代は、もともと信輝の小姓として側近くに仕えていた。
合戦に際しても主君に付き従うことを、これまで何度も望んだが、元服前であるため許されなかった。
元服を済ませれば、戦場でも信輝のために働くことができる。
父の死は悲しむべきことだが、それとは別に、元服は吟千代にとって待ち望んだ機会である。
そうではあるのだが……やはり、緊張してしまう。
「……吟千代」
原式部が穏やかに呼びかけてきた。
「そなたは、これより春日家の長となる。父祖に恥じない武者働きをいたせ」
「はっ……!」
吟千代は会釈する。
それから、小姓が運んで来た折烏帽子を原式部が手にとり、吟千代にかぶせた。
「されば御屋形様の諱より一字を頂戴し、権三郎輝昌と名乗るがよい」
「……ごん、ざぶろう……?」
吟千代は思わず顔を上げて、まじまじと原式部を見た。
だが、元服式の場で烏帽子親が冗談を言う筈もない。
「その名も儂がつけた」
信輝が言って、吟千代は「え……?」と声を上げ、主君を仰ぎ見る。
にやりと信輝は笑って、
「三郎の側近くに仕える者が権三郎であって何が悪い。おぬしは、これからも儂の手足となって働くのじゃ」
「は……ははっ!」
吟千代は主君に向き直り、平伏した。
感極まって涙がこみ上げてきたが、それを見られてしまえば、信輝にからかわれるだろう。
「さあっ、それでは、権三郎殿の元服祝いじゃ!」
白井大学が呼びかけ、広間に集まった家臣たちが「応ッ!」と声を上げた。
あらかじめ用意していたのだろう、小姓たちが酒肴の膳を運んで来て、すぐに宴が始まった。
「はっ!」
「……はっ!」
緊張に唇を引き結びながら、吟千代は主君の前へ進み出る。
この日のためにあつらえた礼服の素襖(すおう)が肩に重く感じる。
吟千代は、まだ十歳であり、本来であれば元服は二、三年先のことであった。
しかし父の権源太頼昌が中気を患い急逝したため、春日氏の家督を継ぐことになったのである。
上総国庁南城主、武田家において、春日氏は原氏、白井氏とともに三家老と称される重臣である。
幼少の吟千代よりも、頼昌の弟で勇猛をもって知られる源八郎昌清を後継の家老に推す声も家中にはあった。
だが、主君である武田三郎信輝はこれを一蹴。
三家老の一人で頼昌の朋友でもあった原式部を烏帽子親として、吟千代の元服式を断行したのである。
元服式の進行役を務めるのは、もう一人の家老である白井大学。
主君信輝と、原、白井という家中の両実力者の後ろ盾を得て、吟千代は元服を果たすことになったのだ。
そのほか家臣の主立った者が立会人として、庁南城の広間を埋めている。
ただし吟千代の叔父、昌清の姿はこの場にない。
吟千代が春日家の後継と決まって以来、昌清は病と称して出仕していない。
信輝の見守る前で、吟千代は原式部と向かい合って着座した。
御屋形様――信輝の視線が、痛い。
信輝は齢十九、上背があって精悍な面構えの美丈夫である。
しかし決して張り子の虎ではなく、十五で家督を継いで以来、十数度の合戦で無敗を誇る。
庁南武田家中では「信玄公の再来」とまで称賛されている。
信玄公とは言わずと知れた甲斐の虎、徳栄軒信玄のこと。
その三男、西保三郎信之が遠縁である上総武田家に養嗣子として迎えられて庁南城主となった。
信輝は信之の孫であり、信玄から数えれば曾孫に当たる。
三郎の名乗りは信之以来、庁南武田家の当主が受け継いでいるものだ。
吟千代は、もともと信輝の小姓として側近くに仕えていた。
合戦に際しても主君に付き従うことを、これまで何度も望んだが、元服前であるため許されなかった。
元服を済ませれば、戦場でも信輝のために働くことができる。
父の死は悲しむべきことだが、それとは別に、元服は吟千代にとって待ち望んだ機会である。
そうではあるのだが……やはり、緊張してしまう。
「……吟千代」
原式部が穏やかに呼びかけてきた。
「そなたは、これより春日家の長となる。父祖に恥じない武者働きをいたせ」
「はっ……!」
吟千代は会釈する。
それから、小姓が運んで来た折烏帽子を原式部が手にとり、吟千代にかぶせた。
「されば御屋形様の諱より一字を頂戴し、権三郎輝昌と名乗るがよい」
「……ごん、ざぶろう……?」
吟千代は思わず顔を上げて、まじまじと原式部を見た。
だが、元服式の場で烏帽子親が冗談を言う筈もない。
「その名も儂がつけた」
信輝が言って、吟千代は「え……?」と声を上げ、主君を仰ぎ見る。
にやりと信輝は笑って、
「三郎の側近くに仕える者が権三郎であって何が悪い。おぬしは、これからも儂の手足となって働くのじゃ」
「は……ははっ!」
吟千代は主君に向き直り、平伏した。
感極まって涙がこみ上げてきたが、それを見られてしまえば、信輝にからかわれるだろう。
「さあっ、それでは、権三郎殿の元服祝いじゃ!」
白井大学が呼びかけ、広間に集まった家臣たちが「応ッ!」と声を上げた。
あらかじめ用意していたのだろう、小姓たちが酒肴の膳を運んで来て、すぐに宴が始まった。
* * *
その夜。
吟千代改め権三郎は、庁南城内の信輝の居所である東の丸に召し出された。
信輝は古河公方足利家から百合姫という正室を迎えて、一男一女を儲けていた。
他に二人の側室との間にも男児を一人ずつ得ている。
しかし百合姫は北の丸に住まわせ、側室たちは城外に屋敷を与えて、普段は側に置いていなかった。
いつも信輝の寝所で伽を務めてきたのは、吟千代である。
そして、今夜も――
吟千代改め権三郎は、庁南城内の信輝の居所である東の丸に召し出された。
信輝は古河公方足利家から百合姫という正室を迎えて、一男一女を儲けていた。
他に二人の側室との間にも男児を一人ずつ得ている。
しかし百合姫は北の丸に住まわせ、側室たちは城外に屋敷を与えて、普段は側に置いていなかった。
いつも信輝の寝所で伽を務めてきたのは、吟千代である。
そして、今夜も――
* * *
「……やはり、おぬしには烏帽子などより、その姿が似合うな」
寝所で権三郎を迎えた信輝は、すでに下帯一枚で逞しい半裸身を晒していた。
剛毅な信輝だが暗闇は嫌い、寝所には充分な燈火を灯させている。
「そ……それがしも、このほうが落ち着きまする……」
答えて言った権三郎は、髷を稚児風に結い直し、水干を纏った童子姿。
絵巻物の牛若丸さながらの出で立ちである。
寝所で権三郎を迎えた信輝は、すでに下帯一枚で逞しい半裸身を晒していた。
剛毅な信輝だが暗闇は嫌い、寝所には充分な燈火を灯させている。
「そ……それがしも、このほうが落ち着きまする……」
答えて言った権三郎は、髷を稚児風に結い直し、水干を纏った童子姿。
絵巻物の牛若丸さながらの出で立ちである。
この姿で吟千代は毎夜、信輝に求められるままに伽を務めてきた。
ちなみに、同じ衣装を女性が纏えば白拍子――すなわち遊女の姿となる。
信輝は権三郎の腰に手を回し、抱き寄せた。
「権三郎……それとも二人きりのときは、まだ吟千代と呼んだほうがよいか?」
「ど……どちらでも……」
権三郎は赤くなりながら、どぎまぎと視線を逸らす。
「どちらも、御屋形様から頂戴した名にござりますれば……」
「愛(う)い奴じゃ。さればこの場は吟千代と呼んでおこうか」
にやりと信輝は笑い、権三郎いや吟千代に口づけした。
「んんっ……」
吟千代が吐息を漏らした隙に、するりと信輝の舌が、口中を犯してくる。
触れ合う舌が、こそばゆい。
上顎と、頬の内側とを舌先でくすぐられ、思わず身をよじる。
「んぅっ……んあっ……!」
「愛い奴じゃ、愛い奴じゃのぅ……」
頬から首筋を指でなぞられ、ぞくぞくと痺れが走る。吟千代は早くも陶然となった。
幼い彼は、快感に弱い。敬愛する主君に与えられるものなら尚更だ。
襟の隙間から信輝の手が滑りこんできた。
水干は緩やかな作りの衣服だ。
くびかみ(襟元)の紐を解けば脱がせることも、たやすい。
吟千代は、きめ細やかな肌をしており、その手触りは絹のようだと信輝は常々、言っていた。
自分の身体がそこまで上等なものか、吟千代自身には、よくわからない。
しかし主君を愉しませているのであれば、それは吟千代にとっても悦ばしいことだ。
「御屋形、様ぁ……」
信輝に身体中を愛撫され、吟千代は幼いその身をわななかせた。
水干を脱がされた。袴も引き下ろされてしまった。
吟千代は華奢な裸身を主君の前に晒すことになった。
羞恥などない。吟千代は身も心も信輝に捧げているから。
この身体は信輝の所有物で、信輝の意のままに扱われることが絶対的に正しいのだから。
「小賢しいのぅ……皮かむりの癖して、天を指すその態度ばかりは立派じゃ」
くっくっと信輝は笑いながら、吟千代の未成熟な陰茎に触れた。
びくっと、吟千代は身を震わせる。
「ああっ……お赦し下さいませ、御屋形様……」
堅く強ばり天を指し仰いでいるが、いまだ白い包皮に覆われた吟千代の陰茎は幼子さながらだ。
無論、陰毛も生えてはいない。
まだ筋肉のついていない胸から腰まで、つるりとしてなめらかな有り様であった。
あるいは清らかと表現してもいいであろう。
その吟千代の裸身を、信輝は愛している。
「どれ……この皮かむりを、儂の口で元服させてやろう」
言うなり信輝は、吟千代の小さな肉茎を口に含んだ。
「……ひゃうっ!? お……御屋形様、それはなりませぬ……汚のうござります!」
慌てて叫ぶ吟千代に、信輝は、れろれろと舌先で幼い吟千代自身を愛でながら、
「何が汚いものか。おぬしは、儂の逸物を咥えるときに汚いなどと考えるのか?」
「め……滅相もござりませぬ!」
「されば同じことよ。愛いと思うておればこそ、儂は吟千代の身体のどこにでも舌を這わせられるぞ」
「お、御屋形様ぁ……!」
涙がこみ上げ、ぼろぼろと頬を伝って落ちる。
愛する主君、信輝と相思相愛であるのだと、あらためて感じさせられたのだ。
「さて……元服じゃ、覚悟いたすがよい」
信輝は、ちゅぱちゅぱと音を立てて吟千代の陰茎を吸いながら、ゆっくりとその包皮を剥いていった。
「あああああっ……!? くぅっ……!!」
吟千代は実のところ、自分が何をされているのかよくわかっていなかった。
ただ、陰茎の先が引き攣れたように痛い。
ぎゅっとつむった眼から、先ほどまでの歓びによるものとは別の涙がこぼれてしまう。
とはいえ、痛みは信輝に陰茎自体をしゃぶられているおかげで和らげられてもいる。
きっと吟千代が痛くないように、してくれていることなのだ。
「ほぉれ、すっかり剥けたわ。これで、まことの元服じゃ。おのれの眼で確かめるがよい」
信輝が吟千代の肉茎から口を離した。
眼を開けた吟千代は、愕然と声を上げる。
「ああっ……!」
包皮を剥がれた幼い肉茎の先は、赤々と血肉の色に照り光っていた。
痛いわけである。皮膚を剥がれたのだから。
「何を驚いておるのじゃ。儂と同じようになっただけであろうが」
くっくっと笑いながら信輝は下帯を解き、すでに猛々しく天を指した怒張を露わにした。
なるほど、言われてみれば。
信輝の陽根の亀の頭にも似た先端部分と、吟千代自身のそれとは、形ばかりは似て見えないこともない。
鋼のごとく黒光りした信輝の逸物ほどの雄々しさは、吟千代自身には備わっていないが。
「おぬしのものも、いずれは儂が如き色艶に変わるのであろうな」
信輝は舌を伸ばし、吟千代の肉茎の先を、れろりと舐めた。
「……ひゃうぅっ!?」
吟千代は腰が抜けそうになった。包皮を剥かれたばかりの幼い肉茎は、ひどく敏感だった。
「おっ、御屋形様ぁ……!」
切なく声を上げ、信輝にすがりつく。
愛する主君にされることなら、どんなことでも受け入れる覚悟だ。
でも……できれば、あまり意地悪はしないでほしい。
吟千代は、ずっとずっと御屋形様の側近くにお仕えしたいから。
陰茎が壊れてしまったら、御屋形様の役に立てなくなってしまわないだろうか。
それとも……尻の穴さえあれば、伽の務めは果たせるだろうか。
「剥いたばかりじゃ、心地よさより痛みが強いのであろうかのぅ」
信輝は身体を起こし、ちゅっと吟千代の頬に口づけした。
「少しずつ慣らしていくことじゃな。元服したおぬしに、いつまでも儂の伽の相手ばかりさせてもおれん」
「ええっ……!?」
吟千代は信輝の顔を見た。
愛しい主君の顔を見ている筈なのに、眼の前が真っ暗になって、何も見えていないように感じる……
「権三郎、嫁を取れ。原式部が息女、お万。齢は十三、いまは百合に仕えておる」
「い……嫌でござりまする!」
吟千代は声を張り上げた。
「元服した権三郎は用済みにござりまするか!? なれば吟千代に戻りまする!」
「何を申しておるのじゃ」
信輝は笑う。
「儂が、お吟を手放すものか。なれど春日家の当主ともなれば世継ぎを儲けねばならぬであろう?」
「養子を迎えまする! そ……それがしは女子などに、御屋形様以外に肌身を許したくありませぬ!」
「お吟ッ!」
信輝は声を荒らげた。
「これは武家の習いじゃ! 春日と原が縁組いたせば、家中に太い柱が生まれる!」
「な……なれば養子を迎えるのは原殿の家から……!」
「まだ申すか! 儂とて女子に興味はない! それは百合も同じじゃ! あれも男に興味はないと申す!」
「北の方様が……?」
唖然として問い返す吟千代に、信輝は頷き、
「百合と儂とは政略のための婚儀じゃ。男児が一人生まれれば、もはや情を交わさぬ約定」
「それでは……」
百合姫が産んだ第一子は女子であった。そのため二人目の子を為すことになったのであろう。
そうして嫡男の菊千代が生まれ、信輝と百合姫は互いの務めを果たし終えたわけである。
側室たちにも男児を産ませたのは、菊千代に万が一の事態が起きたときに備えてのことか。
「百合と儂は似た者同士。愛こそ感じぬが、朋友と思うておる」
信輝は言った。
「あれが男であれば、あるいは良き念友になり得たかも知らぬがの……」
「お……御屋形様ぁ……」
吟千代の眼から、ぼろぼろと涙が落ちる。
信輝が他の相手を愛したかもしれないなどと、仮定の話でも聞きたくない。
その吟千代の様子を見て、にやりと信輝は笑った。
「何じゃ、妬いておるのか? 吟千代は、まことに愛い奴じゃのぅ」
「御屋形様は意地が悪うござりまする。吟千代の嫌がることばかり申されて……」
吟千代は涙が止まらない。
自分は一心不乱に御屋形様を愛しているのに。
御屋形様の愛情を疑うつもりはないけど、戯れにしても心を苛めるのは、やめてほしいのだ。
身体を苛められるのは、嫌いでは、ないのだけど……
「わかった、わかった。この話は棚上げといたそう」
信輝は苦笑いで言った。
「なれば吟千代に、あらためて命じる。『戦支度』じゃ!」
「は……、はいっ!」
吟千代は慌てて涙を拭った。
信輝が話を棚上げといい、また『戦支度』を命じたからには、すぐに頭を切り替えなければならない。
剛毅果断が信輝の特質であり、それは閨にあっても同じであった。
信輝に心酔している吟千代もまた、それに倣うことを心がけている。
そんな吟千代を好ましく思うからこそ、信輝の寵愛が続いているともいえよう。
百合姫への嫉妬を意識の外に追いやり、吟千代は『戦支度』のため、信輝の前で胡坐をかいた。
包皮を剥かれたまま天を指した幼根が、ひくひくといやらしく震えてしまう。
これで『戦支度』は何度めだろう。
それをしようと思うだけで、浅ましい気持ちが湧き起こるようになってしまった。
吟千代自身には見えていないが、幼根の下では小さな菊のすぼまりが同じように、ひくついている。
「んっ……、あふ……」
吟千代は左右の手指を交互に口にくわえ、唾液で濡らした。
それから、その手を自らの股間に導き。
左の人差し指と中指で菊花を割り広げて、そこに右手の人差し指、中指、薬指を突き当てた。
何度も信輝を受け入れて、こなれている菊花は、たやすく三本の指を呑み込んだ。
「あっ……、ああっ……、御屋形、様ぁ……!」
「ふふっ……愛い奴じゃ」
にやりと笑うと信輝は、吟千代の前で膝立ちになり、腰を突き出す――
つまり、屹立した陽根を寵童の眼前に突きつけた。
「あ……んぐぁ……」
吟千代は自らの菊花を指でほぐしながら、主君の肉茎を口に咥えて、丹念に濡らすことになった。
そうして互いの準備を整え、信輝の怒張を口から離し、
「御屋形様……これにて、よろしゅうござりまするか……?」
「うむ……されば『馬を引け』!」
「はいっ……」
吟千代は馬のように四つん這いになり、主君を迎え入れる体勢をとった。
信輝は膝立ちのままその後ろに回ると、幼い家臣の小さな尻を抱え、
「我が『肉一文字』……喰らうがよいぞ!」
ぐいとばかりに、怒張を突き立てた。
「ああああっ……御屋形様ぁっ……!」
吟千代は随喜の涙を流す。
信輝は、ぐいぐいと腰を突き上げ始めた。吟千代の限界は理解している。
この程度の荒事であれば、充分に吟千代は受け入れる。
「ああっ! ああっ! ああ……御屋形様っ! 御屋形様ぁっ!」
馬に揺られているがごとく、吟千代の幼い裸身が跳ねる。
「んむっ! んっ! んくっ! んむぅっ……!」
信輝は猛々しく吟千代を攻め立てる。
青年武将と幼い家臣、二人の荒い呼吸が閨に響き――やがて。
「ま……参るぞっ、吟千代っ!」
「お……お越し下さりませっ、御屋形様っ!」
「むっ……むぅぅぅぅぅん……っ!」
信輝の熱い精が、どくどくと吟千代の腸腔に注がれた。
「あっ……あああああっ……!」
そして吟千代の幼い精もまた辺りに撒き散らされた。
未成熟な肉茎からほとばしる精は、水に似て透明に近く、きらきらと輝いていた――
ちなみに、同じ衣装を女性が纏えば白拍子――すなわち遊女の姿となる。
信輝は権三郎の腰に手を回し、抱き寄せた。
「権三郎……それとも二人きりのときは、まだ吟千代と呼んだほうがよいか?」
「ど……どちらでも……」
権三郎は赤くなりながら、どぎまぎと視線を逸らす。
「どちらも、御屋形様から頂戴した名にござりますれば……」
「愛(う)い奴じゃ。さればこの場は吟千代と呼んでおこうか」
にやりと信輝は笑い、権三郎いや吟千代に口づけした。
「んんっ……」
吟千代が吐息を漏らした隙に、するりと信輝の舌が、口中を犯してくる。
触れ合う舌が、こそばゆい。
上顎と、頬の内側とを舌先でくすぐられ、思わず身をよじる。
「んぅっ……んあっ……!」
「愛い奴じゃ、愛い奴じゃのぅ……」
頬から首筋を指でなぞられ、ぞくぞくと痺れが走る。吟千代は早くも陶然となった。
幼い彼は、快感に弱い。敬愛する主君に与えられるものなら尚更だ。
襟の隙間から信輝の手が滑りこんできた。
水干は緩やかな作りの衣服だ。
くびかみ(襟元)の紐を解けば脱がせることも、たやすい。
吟千代は、きめ細やかな肌をしており、その手触りは絹のようだと信輝は常々、言っていた。
自分の身体がそこまで上等なものか、吟千代自身には、よくわからない。
しかし主君を愉しませているのであれば、それは吟千代にとっても悦ばしいことだ。
「御屋形、様ぁ……」
信輝に身体中を愛撫され、吟千代は幼いその身をわななかせた。
水干を脱がされた。袴も引き下ろされてしまった。
吟千代は華奢な裸身を主君の前に晒すことになった。
羞恥などない。吟千代は身も心も信輝に捧げているから。
この身体は信輝の所有物で、信輝の意のままに扱われることが絶対的に正しいのだから。
「小賢しいのぅ……皮かむりの癖して、天を指すその態度ばかりは立派じゃ」
くっくっと信輝は笑いながら、吟千代の未成熟な陰茎に触れた。
びくっと、吟千代は身を震わせる。
「ああっ……お赦し下さいませ、御屋形様……」
堅く強ばり天を指し仰いでいるが、いまだ白い包皮に覆われた吟千代の陰茎は幼子さながらだ。
無論、陰毛も生えてはいない。
まだ筋肉のついていない胸から腰まで、つるりとしてなめらかな有り様であった。
あるいは清らかと表現してもいいであろう。
その吟千代の裸身を、信輝は愛している。
「どれ……この皮かむりを、儂の口で元服させてやろう」
言うなり信輝は、吟千代の小さな肉茎を口に含んだ。
「……ひゃうっ!? お……御屋形様、それはなりませぬ……汚のうござります!」
慌てて叫ぶ吟千代に、信輝は、れろれろと舌先で幼い吟千代自身を愛でながら、
「何が汚いものか。おぬしは、儂の逸物を咥えるときに汚いなどと考えるのか?」
「め……滅相もござりませぬ!」
「されば同じことよ。愛いと思うておればこそ、儂は吟千代の身体のどこにでも舌を這わせられるぞ」
「お、御屋形様ぁ……!」
涙がこみ上げ、ぼろぼろと頬を伝って落ちる。
愛する主君、信輝と相思相愛であるのだと、あらためて感じさせられたのだ。
「さて……元服じゃ、覚悟いたすがよい」
信輝は、ちゅぱちゅぱと音を立てて吟千代の陰茎を吸いながら、ゆっくりとその包皮を剥いていった。
「あああああっ……!? くぅっ……!!」
吟千代は実のところ、自分が何をされているのかよくわかっていなかった。
ただ、陰茎の先が引き攣れたように痛い。
ぎゅっとつむった眼から、先ほどまでの歓びによるものとは別の涙がこぼれてしまう。
とはいえ、痛みは信輝に陰茎自体をしゃぶられているおかげで和らげられてもいる。
きっと吟千代が痛くないように、してくれていることなのだ。
「ほぉれ、すっかり剥けたわ。これで、まことの元服じゃ。おのれの眼で確かめるがよい」
信輝が吟千代の肉茎から口を離した。
眼を開けた吟千代は、愕然と声を上げる。
「ああっ……!」
包皮を剥がれた幼い肉茎の先は、赤々と血肉の色に照り光っていた。
痛いわけである。皮膚を剥がれたのだから。
「何を驚いておるのじゃ。儂と同じようになっただけであろうが」
くっくっと笑いながら信輝は下帯を解き、すでに猛々しく天を指した怒張を露わにした。
なるほど、言われてみれば。
信輝の陽根の亀の頭にも似た先端部分と、吟千代自身のそれとは、形ばかりは似て見えないこともない。
鋼のごとく黒光りした信輝の逸物ほどの雄々しさは、吟千代自身には備わっていないが。
「おぬしのものも、いずれは儂が如き色艶に変わるのであろうな」
信輝は舌を伸ばし、吟千代の肉茎の先を、れろりと舐めた。
「……ひゃうぅっ!?」
吟千代は腰が抜けそうになった。包皮を剥かれたばかりの幼い肉茎は、ひどく敏感だった。
「おっ、御屋形様ぁ……!」
切なく声を上げ、信輝にすがりつく。
愛する主君にされることなら、どんなことでも受け入れる覚悟だ。
でも……できれば、あまり意地悪はしないでほしい。
吟千代は、ずっとずっと御屋形様の側近くにお仕えしたいから。
陰茎が壊れてしまったら、御屋形様の役に立てなくなってしまわないだろうか。
それとも……尻の穴さえあれば、伽の務めは果たせるだろうか。
「剥いたばかりじゃ、心地よさより痛みが強いのであろうかのぅ」
信輝は身体を起こし、ちゅっと吟千代の頬に口づけした。
「少しずつ慣らしていくことじゃな。元服したおぬしに、いつまでも儂の伽の相手ばかりさせてもおれん」
「ええっ……!?」
吟千代は信輝の顔を見た。
愛しい主君の顔を見ている筈なのに、眼の前が真っ暗になって、何も見えていないように感じる……
「権三郎、嫁を取れ。原式部が息女、お万。齢は十三、いまは百合に仕えておる」
「い……嫌でござりまする!」
吟千代は声を張り上げた。
「元服した権三郎は用済みにござりまするか!? なれば吟千代に戻りまする!」
「何を申しておるのじゃ」
信輝は笑う。
「儂が、お吟を手放すものか。なれど春日家の当主ともなれば世継ぎを儲けねばならぬであろう?」
「養子を迎えまする! そ……それがしは女子などに、御屋形様以外に肌身を許したくありませぬ!」
「お吟ッ!」
信輝は声を荒らげた。
「これは武家の習いじゃ! 春日と原が縁組いたせば、家中に太い柱が生まれる!」
「な……なれば養子を迎えるのは原殿の家から……!」
「まだ申すか! 儂とて女子に興味はない! それは百合も同じじゃ! あれも男に興味はないと申す!」
「北の方様が……?」
唖然として問い返す吟千代に、信輝は頷き、
「百合と儂とは政略のための婚儀じゃ。男児が一人生まれれば、もはや情を交わさぬ約定」
「それでは……」
百合姫が産んだ第一子は女子であった。そのため二人目の子を為すことになったのであろう。
そうして嫡男の菊千代が生まれ、信輝と百合姫は互いの務めを果たし終えたわけである。
側室たちにも男児を産ませたのは、菊千代に万が一の事態が起きたときに備えてのことか。
「百合と儂は似た者同士。愛こそ感じぬが、朋友と思うておる」
信輝は言った。
「あれが男であれば、あるいは良き念友になり得たかも知らぬがの……」
「お……御屋形様ぁ……」
吟千代の眼から、ぼろぼろと涙が落ちる。
信輝が他の相手を愛したかもしれないなどと、仮定の話でも聞きたくない。
その吟千代の様子を見て、にやりと信輝は笑った。
「何じゃ、妬いておるのか? 吟千代は、まことに愛い奴じゃのぅ」
「御屋形様は意地が悪うござりまする。吟千代の嫌がることばかり申されて……」
吟千代は涙が止まらない。
自分は一心不乱に御屋形様を愛しているのに。
御屋形様の愛情を疑うつもりはないけど、戯れにしても心を苛めるのは、やめてほしいのだ。
身体を苛められるのは、嫌いでは、ないのだけど……
「わかった、わかった。この話は棚上げといたそう」
信輝は苦笑いで言った。
「なれば吟千代に、あらためて命じる。『戦支度』じゃ!」
「は……、はいっ!」
吟千代は慌てて涙を拭った。
信輝が話を棚上げといい、また『戦支度』を命じたからには、すぐに頭を切り替えなければならない。
剛毅果断が信輝の特質であり、それは閨にあっても同じであった。
信輝に心酔している吟千代もまた、それに倣うことを心がけている。
そんな吟千代を好ましく思うからこそ、信輝の寵愛が続いているともいえよう。
百合姫への嫉妬を意識の外に追いやり、吟千代は『戦支度』のため、信輝の前で胡坐をかいた。
包皮を剥かれたまま天を指した幼根が、ひくひくといやらしく震えてしまう。
これで『戦支度』は何度めだろう。
それをしようと思うだけで、浅ましい気持ちが湧き起こるようになってしまった。
吟千代自身には見えていないが、幼根の下では小さな菊のすぼまりが同じように、ひくついている。
「んっ……、あふ……」
吟千代は左右の手指を交互に口にくわえ、唾液で濡らした。
それから、その手を自らの股間に導き。
左の人差し指と中指で菊花を割り広げて、そこに右手の人差し指、中指、薬指を突き当てた。
何度も信輝を受け入れて、こなれている菊花は、たやすく三本の指を呑み込んだ。
「あっ……、ああっ……、御屋形、様ぁ……!」
「ふふっ……愛い奴じゃ」
にやりと笑うと信輝は、吟千代の前で膝立ちになり、腰を突き出す――
つまり、屹立した陽根を寵童の眼前に突きつけた。
「あ……んぐぁ……」
吟千代は自らの菊花を指でほぐしながら、主君の肉茎を口に咥えて、丹念に濡らすことになった。
そうして互いの準備を整え、信輝の怒張を口から離し、
「御屋形様……これにて、よろしゅうござりまするか……?」
「うむ……されば『馬を引け』!」
「はいっ……」
吟千代は馬のように四つん這いになり、主君を迎え入れる体勢をとった。
信輝は膝立ちのままその後ろに回ると、幼い家臣の小さな尻を抱え、
「我が『肉一文字』……喰らうがよいぞ!」
ぐいとばかりに、怒張を突き立てた。
「ああああっ……御屋形様ぁっ……!」
吟千代は随喜の涙を流す。
信輝は、ぐいぐいと腰を突き上げ始めた。吟千代の限界は理解している。
この程度の荒事であれば、充分に吟千代は受け入れる。
「ああっ! ああっ! ああ……御屋形様っ! 御屋形様ぁっ!」
馬に揺られているがごとく、吟千代の幼い裸身が跳ねる。
「んむっ! んっ! んくっ! んむぅっ……!」
信輝は猛々しく吟千代を攻め立てる。
青年武将と幼い家臣、二人の荒い呼吸が閨に響き――やがて。
「ま……参るぞっ、吟千代っ!」
「お……お越し下さりませっ、御屋形様っ!」
「むっ……むぅぅぅぅぅん……っ!」
信輝の熱い精が、どくどくと吟千代の腸腔に注がれた。
「あっ……あああああっ……!」
そして吟千代の幼い精もまた辺りに撒き散らされた。
未成熟な肉茎からほとばしる精は、水に似て透明に近く、きらきらと輝いていた――
* * *
ともに果てたのち、抱き合って眠る、信輝と吟千代。
そこに寝所の外から、小姓の呼びかける声がした。
「申し上げまする! 池和田城代、和田越中殿より火急のお使者、参られましてござりまする!」
信輝は吟千代の身体を離し、跳ね起きた。
吟千代も慌てて、眠たい眼を強くこすりながら起き上がる。
「構わぬ! ここに通せ!」
信輝は答えると、吟千代に向かって、
「稚児装束でよいわ、そのまま服を着よ! 吟千代も使者の口上、聞いておけ!」
「えっ? はっ……はいっ!」
童子水干は信輝の前でしか身に着けたことのないものだ。その姿を他の家臣の前で見せることになるとは。
それより何よりも、大事な使者からの話を自分などが耳にしていいものか。
吟千代の疑問を吹っ切るように、下帯を着け直しながら信輝が言った。
「閨では儂の愛妾、吟千代じゃが……家中でのおぬしは儂の右腕、家老の春日権三郎なのじゃ!」
「は……はいっ!」
主君の右腕と言われたことが、吟千代には嬉しかった。
稚児姿を主君以外に見られてしまうくらい、何ほどのことだろう。
信輝と吟千代が慌ただしく衣服を身に着け終えたところに、次の間に使者を通したことを小姓が告げた。
寝所を出た信輝と吟千代は、次の間に控えていた使者の前に立った。
使者は具足姿――本物の戦支度であった。
「申せ!」
信輝に促され、使者は「はっ!」と一礼し、言上した。
「春日源八郎殿、謀叛! 兵三百にて池和田城へ攻め寄せ、和田越中守殿以下の城兵は城外へ退散!」
「叔父上殿が……!?」
吟千代は愕然としたが、信輝は驚きの色を見せず使者に命じる。
「御苦労! 急ぎ立ち戻り、かねての手筈通りと越中に伝えよ!」
「ははっ!」
使者は再び一礼すると、素早く立ち上がって次の間を出て行った。
信輝の態度と「手筈通り」という言葉で、この事態を主君が予期していたことを吟千代は理解した。
「あの……御屋形様、我が叔父の謀叛は……?」
「うむ。源八郎の狢(むじな)めが、ついに本性を現したのよ」
くっくっと信輝は笑い、
「なれど兵が三百とはのぅ。あ奴の子飼いは、せいぜい百ばかり。あとは里見の兵を引き入れたか」
「安房の里見が!?」
「その後ろにおるのは、上杉管領よ。これは大戦(おおいくさ)になるやも知れぬわ」
「……御意」
吟千代には、ほかに答えが浮かばない。
自分の元服をきっかけに叔父が謀叛を起こし、それが里見や上杉との戦に繋がるとは……
「吟千代!」
信輝が呼ばわった。
「儂とともに出陣いたし、春日党の忠義を示せ! まずは狢の源八郎退治じゃ!」
「は……ははっ!」
頭を下げた吟千代は、感極まって涙を溢れさせた。
ついに信輝とともに戦場に出る機会を得たのである。
「さて、これから忙しくなるぞ。夜伽は閨ではなく合戦場でいたすことになろうかのぅ」
にやりと笑って信輝は言うと、吟千代の尻を、するりと撫でた。
「御屋形様っ!?」
吟千代が真っ赤になって声を上げると、信輝は高らかに笑う。つられて吟千代も笑ってしまった。
この御屋形様を、自分は心の底から愛しているのだと、吟千代はあらためて思うのであった。
そこに寝所の外から、小姓の呼びかける声がした。
「申し上げまする! 池和田城代、和田越中殿より火急のお使者、参られましてござりまする!」
信輝は吟千代の身体を離し、跳ね起きた。
吟千代も慌てて、眠たい眼を強くこすりながら起き上がる。
「構わぬ! ここに通せ!」
信輝は答えると、吟千代に向かって、
「稚児装束でよいわ、そのまま服を着よ! 吟千代も使者の口上、聞いておけ!」
「えっ? はっ……はいっ!」
童子水干は信輝の前でしか身に着けたことのないものだ。その姿を他の家臣の前で見せることになるとは。
それより何よりも、大事な使者からの話を自分などが耳にしていいものか。
吟千代の疑問を吹っ切るように、下帯を着け直しながら信輝が言った。
「閨では儂の愛妾、吟千代じゃが……家中でのおぬしは儂の右腕、家老の春日権三郎なのじゃ!」
「は……はいっ!」
主君の右腕と言われたことが、吟千代には嬉しかった。
稚児姿を主君以外に見られてしまうくらい、何ほどのことだろう。
信輝と吟千代が慌ただしく衣服を身に着け終えたところに、次の間に使者を通したことを小姓が告げた。
寝所を出た信輝と吟千代は、次の間に控えていた使者の前に立った。
使者は具足姿――本物の戦支度であった。
「申せ!」
信輝に促され、使者は「はっ!」と一礼し、言上した。
「春日源八郎殿、謀叛! 兵三百にて池和田城へ攻め寄せ、和田越中守殿以下の城兵は城外へ退散!」
「叔父上殿が……!?」
吟千代は愕然としたが、信輝は驚きの色を見せず使者に命じる。
「御苦労! 急ぎ立ち戻り、かねての手筈通りと越中に伝えよ!」
「ははっ!」
使者は再び一礼すると、素早く立ち上がって次の間を出て行った。
信輝の態度と「手筈通り」という言葉で、この事態を主君が予期していたことを吟千代は理解した。
「あの……御屋形様、我が叔父の謀叛は……?」
「うむ。源八郎の狢(むじな)めが、ついに本性を現したのよ」
くっくっと信輝は笑い、
「なれど兵が三百とはのぅ。あ奴の子飼いは、せいぜい百ばかり。あとは里見の兵を引き入れたか」
「安房の里見が!?」
「その後ろにおるのは、上杉管領よ。これは大戦(おおいくさ)になるやも知れぬわ」
「……御意」
吟千代には、ほかに答えが浮かばない。
自分の元服をきっかけに叔父が謀叛を起こし、それが里見や上杉との戦に繋がるとは……
「吟千代!」
信輝が呼ばわった。
「儂とともに出陣いたし、春日党の忠義を示せ! まずは狢の源八郎退治じゃ!」
「は……ははっ!」
頭を下げた吟千代は、感極まって涙を溢れさせた。
ついに信輝とともに戦場に出る機会を得たのである。
「さて、これから忙しくなるぞ。夜伽は閨ではなく合戦場でいたすことになろうかのぅ」
にやりと笑って信輝は言うと、吟千代の尻を、するりと撫でた。
「御屋形様っ!?」
吟千代が真っ赤になって声を上げると、信輝は高らかに笑う。つられて吟千代も笑ってしまった。
この御屋形様を、自分は心の底から愛しているのだと、吟千代はあらためて思うのであった。
【終わり】