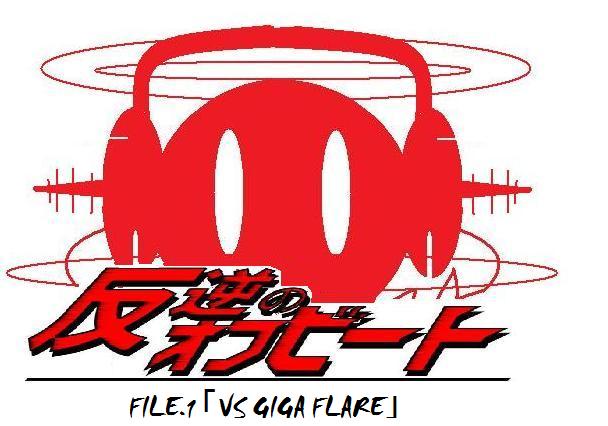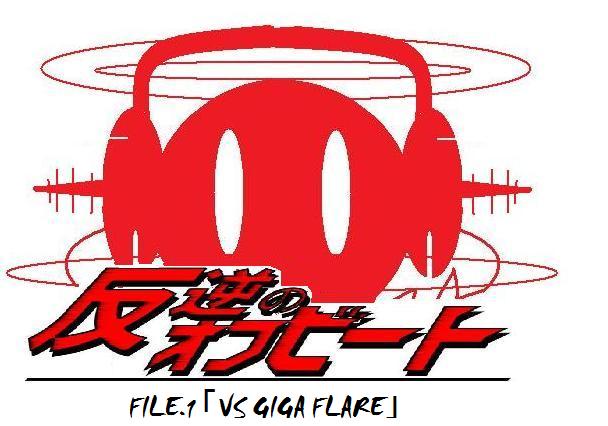
FILE.1〈粛炎のギガフレア〉
双葉学園都市と本州を繋ぐ唯一の接点である細く長い橋、そこに一台の高級車が学園に向かって走っていた。
運転席にはスーツ姿の若い女が座っており、助手席には短髪のあどけない顔をした少年が窓を眺めながら座っている。首に下げている真っ赤なヘッドフォンが特徴的だ。
(これが海ってやつか。思ったよりいやな色をしてるな)
少年は橋の外に広がる薄汚れた東京湾の海に落胆していた。彼が見てきた液晶の中の海は透き通るように青かった。
「あら、海がそんなに珍しいのかしらオフビート。まるで子供ね。あら失礼、あなたも今日から高校生なんだからそんなこと言っちゃ駄目ね」
“調子っぱずれ(オフビート)”と呼ばれたこの少年は、女の嫌味のような言葉に少しだけイラつきながら視線を女に向ける。
「ふん、別にわざわざ入学する必要なんてあったのかよアンダンテ」
「学校ではその名前で呼んじゃ駄目よ。ちゃんと木津先生と呼びなさい」
「あんたが教師ってたまかよ。なんか違和感あるんだよな。それにあんたも俺のことをオフビートなんて呼ぶなよ、今日から俺の名前は――」
少年は制服の胸ポケットから生徒手帳を取り出す。そこには彼の名前が書かれている。
「斯波涼一――か、悪くない名前だ」
感慨深そうに呟く少年を横目で見やり、女は厳しい口調で彼を窘める。
「コードネーム以外の名前をもらったのはこれが初めてかしら。でも勘違いしちゃ駄目よ。あなたはあくまで私たち『オメガサークル』の所有物であり戦闘兵器なんだから、決して本当の学生のように生きることはできないのよ」
そんな言葉にも少年は「わかってるよ」と返すだけで、特に気分を害した様子はない。彼もそんなことは十分わかっている、わかりすぎているのだろう。
「まあ、この学園の醒徒会には私たちが造ったお人形がいるんだけどね。アレはもう私たちの手を離れてしまった。創造主を裏切るなんてとんだ失敗作よ。力だけがありすぎて処分もできないしね」
醒徒会とは双葉学園における最強の七人のことである。少年にとってある意味“兄”と呼べる存在がその中の一人にいるのである。少年は自分をがんじがらめにしているこの組織から離れることができたその存在に少し思うところがあるようだ。
少年はヘッドフォンを耳にあてがい、端末をいじって曲を流す。ヘッドフォンから流れる物悲しくもテンポのいい曲は、十年ほど前に死んだ伝説のポップアーティストの歌だ。
少年は思わず曲にあわせて歌詞を口ずさむ。
「あいつらは僕等を見ちゃいないんだ、もうこんなのは沢山なんだよ――」
音痴な彼の、調子外れな歌が車内を包んだ。
「まったく、ここの生活もつまんないわねぇ」
学園都市内のオープンカフェテラスで二人の少女がパフェを食べながら話をしている。
「ええー。私とのお喋りつまんないの、伊万里ちゃん? 」
「いやいや、そういうわけじゃなくて――って泣かないでよ弥生! 」
伊万里と呼ばれた少女は綺麗なセミロングの赤髪で、どこか近寄りがたい高飛車なイメージのある少女だった。それに対して、片方の困り顔の少女、弥生は地味な感じのする黒髪で、髪を二つに縛って結っており、幼さを強調している。二人とも双葉学園高等部一年の生徒である。
「そりゃ弥生や、クラスのみんなと遊んでるのは楽しいよ。でも、なんだかイメージしてた世界と違うなーって」
伊万里は溜息をつきながら目の前のパフェをぱくつく。カロリーなど気にしてない様子だが、彼女はずいぶん細身である。だからといって胸に栄養がいってるわけではないようだ。逆に弥生は地味な雰囲気とは別に豊満な身体をしているようで、伊万里は妬ましそうに彼女を見ている。
「へえ、伊万里ちゃんはここの生活で何を望んでたの? 」
「うーん。もっとこう、天才の私が世界平和のために大活躍! って予定だったんだけどなー。なんだか中学の頃と何も変らない生活よねぇ」
異能者である彼女は、学園に来るまでは自分のことを選ばれた存在だと信じていた。しかし、それはこの学園においては精々並程度であり、彼女以上の能力者はうじゃうじゃといるのだが、それが彼女には面白くないらしい。
「いいじゃない伊万里ちゃんはまだ能力があるだけ、私みたいな一般人はここじゃ肩身狭いもの。醒徒会の水分副会長みたいにかっこよくなりたいなぁ」
異能者を育てる双葉学園にも一般生徒は在籍する。それらの非能力者はラルヴァとの戦いにおける補助要員の育成を含めている。弥生も伊万里と同じクラスで、小等部からの長い付き合いである。ちなみに弥生は醒徒会副会長である水分理緒の、非公式ファンクラブの会員である。彼女はその美しさと上品な物腰でファンが多いようだ。
「それに伊万里ちゃんの能力は貴重だよ。予知能力者なんてそんなにいないもの」
「予知能力っても、あんまり約に立たないけどね。ラルヴァ戦では必要ないから未だにまだ一度も戦場に出されたことないし。ほとんど弥生と変らない一般人よ」
「いいじゃない、ラルヴァとの戦いなんて怖いもん。それにもし伊万里ちゃんが怪我なんてしたら私イヤだもん」
「弥生・・・・・・」
伊万里にもしものことがあったら、という想像でまたも涙ぐむ弥生を見て、伊万里は少し頬が緩む。まぁ、こんな日常も悪くないか――そんな表情だった。
「さて、そろそろ昼休みも終わるし、学校にもど・・・・・・」
伊万里が鞄を手に取り席を立とうとした瞬間、彼女はこの世で最も見たくないものを目にする。
「どうしたの伊万里ちゃん? 」
伊万里には屈託の無い笑顔を向ける弥生の頭に、旗が見えていた。
これが彼女の予知能力『アウト・フラッグス』である。伊万里は人の死を予知することができ、その死の象徴は、わかりやすくその人物の頭に旗が現れる。その、死の旗が彼女の親友である弥生の頭に現れていた。
(そんな、嘘でしょ・・・・・・)
今こんなに元気な弥生がなぜ死ぬのか、彼女にはわからなかった。彼女が混乱の最中、ふと周りを見渡すと、
「な、なによこれ! 」
その商店街にいる全ての人間の頭に旗が現れている。店の店員も、生徒も、教師も、能力者も、非能力者も、全て。
伊万里はさっとショーウインドウのガラスで自分の姿を確認する。
やはりそこに映っている自分の頭の上にも死の旗が現れていた。
伊万里は確信した。今ここにいる全ての人間が死ぬのだ、と。
伊万里たちから少し離れた場所のベンチに一人の男子生徒が座っていた。
細身のメガネが似合っている少年で、ベンチに座りながら携帯ゲームをプレイしているようだ。しかし、その顔にはかすかに歪んだ笑みが漏れていた。
(楽しみだ。あと数分でここが火の海になるんだ。久しぶりに肉の焼き焦げた臭いが胸いっぱいに嗅げるんだ。ああ、ぞくぞくする)
恍惚の表情でうっとりしているこの少年からはどこか危なげな雰囲気が漂っている。普段から化け物たちと戦っているここの生徒よりももっと邪悪な殺気。
純粋な殺意。
彼の鋭い瞳は、殺し屋のそれだった。
制服からわかるように、双葉学園の高等部三年生であるが、その名も身分も全てが偽りである。
世界の全てを燃やし尽くす、彼の真の名は――
「『ギガフレア』、それが彼の名前よ。もっとも、それ以外は性別も容姿もここでの名前はわからないわ。ただギガフレアがこの学校に潜んでいることは確かね」
スーツ姿の女アンダンテと、ヘッドフォンの少年オフビートは学園都市内のオープンカフェテラスで軽めの昼食を食べていた。オフビートが転校生として正式に学園に入るのは明日である。急いで学校にいく必要もないため、ひとまず昼食を済ませようと考えていたのだ。それに対してオフビートは、「教師と生徒がこんな風に飯食べてたら変な誤解されないか」と聞いたが「残念。私とあなたは従姉弟同士ということになっているのよ、だからそんなラブい誤解はないわ。わかったかしら涼一君」
そんなニヤついた彼女の言葉にオフビートは「従姉弟ねぇ、叔母と甥じゃないのか」と毒づいてアンダンテにはたかれた。アンダンテはまだ二十代前半である。
「それで、俺は何をすればいいんだ。そのギガフレアって奴を見つけて始末すればいいのか? 」
始末、などとおよそ平和なカフェテラスに似つかわしくない単語を平気で発するオフビートだが、周りの客たちは自分たちの会話に夢中で誰もこの物騒な会話には気づかない。「いえ、あなたの任務はもっと重要よ。あなたにはある少女の護衛をしてもらうわ」
「護衛? なんだって俺がそんなことを」
「その少女の命を狙っているのがギガフレアよ。勿論ギガフレア自身に何か理由があって彼女を殺そうとしているわけじゃないでしょうね。ギガフレアもただ組織に囲われているだけ。オメガサークルの情報によるとギガフレアは『聖痕(スティグマ)』の殺し屋よ。どうやら双葉学園に潜んで機会を待っているようね」
「スティグマか。名前だけは演習のときに聞いたことがあるな」
ラルヴァ信仰団体スティグマ。ラルヴァを神の使いと崇め、それを駆逐する異能者たちを排除しようと目しており、そこに所属する異能者は対ラルヴァではなく、対能力者に特化した殺し屋集団である。
「ある意味、科学機関であるオメガサークルとは対をなしているわね」
「しかしなんでスティグマの殺し屋がその――少女とかいったな、女の子を狙ってるんだ。それにだからとって俺たちがその子を護る理由がわからないぞ」
オフビートは疑問を投げかけながらカツサンドに被りつく。アンダンテはあまり食べ物に手を出さず紅茶ばかり飲んでいる。
「詳細は末端であるあなたが知る必要はないわ。まあ、ただ言えることはその少女が私たちの研究に必要だからよ。そして、その少女の能力がスティグマたちに都合が悪い、といったところかしら」
アンダンテは鞄から数枚の写真を取り出した。そこにはその少女の姿が映っている。オフビートはそれを受け取りざっと眺める。
「ふぅん。なかなか可愛いじゃないか」
「あら意外ね。あなたも女の子に興味あるのね」
「別に、ただ美的センスが無いわけじゃないってだけだ」
「なによ味気ないわね。ちなみにその子はあなたと同じクラスよ。私が無理矢理ねじ込んであげたわ。ちなみにその子の名前は――」
アンダンテの声は後ろの席から聞こえてきた大声にかき消された。
「な、なによこれ!」
どうやら女子生徒が何か騒いでいるようだ。アンダンテは少し鬱陶しそうにしているが、ここでは教師である以上生徒の騒々しさには多少慣れている。しかしその女子生徒は驚くことを口にする。
「み、みんな今すぐここから離れて! じゃないとみんな死んじゃうわ! 」
その言葉にアンダンテは振り向く、オフビートも写真とその少女の顔を見比べた。
「お、おいあの子もしかして」
「巣鴨伊万里・・・・・・まさか! 」
彼女はまるで何かに怯えるように慌てている。オフビートは初めて見るアンダンテの焦燥の表情に何か鬼気迫るものを感じていた。
「み、みんな今すぐここから離れて! じゃないとみんな死んじゃうわ! 」
伊万里は大声で周りの人たちに呼びかけた。しかし当然ながら皆は唖然として彼女を見ているだけだ。そんな中弥生だけがその危機を理解していた。
「伊万里ちゃん、嘘でしょ・・・・・・」
「早くここから逃げないとまずいわよ弥生。今ここにいる人みんなに旗が見えるのよ。何が起こるのかわからないけどみんな死んじゃうわ! 」
その言葉に弥生は青くなる。見えも触れもしない頭の旗を確認するように手を頭の上にやっている。当然掴めるわけもない。
「はやく皆さんも逃げてください! 私には人の死が見えるんです、だから早く!」
再び周囲の人間に呼びかけるが、誰一人それを本気と受け取ってはいない。どこか嘲笑まじりで彼女たちを遠巻きに見ているだけだ。それも無理はない。予知能力は稀な能力でただの一生徒である彼女の能力を皆が知っているわけではないのだから。
しかし伊万里の言葉のためかわからないが、伊万里の前の席に座っていたスーツ姿の女性がその場から離れていった。だがその席に一緒に座っていた生徒であろう少年はまだそこに残っていた。
(もう、なんで誰も私の言うこと信じてくれないの――)
伊万里は焦りとイラつきで混乱していた。なまじ伊万里の能力の信憑性を知っているために弥生も恐怖で動けなくなっていた。
(でもこんなに平和な場所で、どうやったらみんなが死ぬようなことが起きるのかしら)
それは彼女にもわからなかった。あくまですぐそこにある死を感知することしか伊万里にはできないのである。どこからか迫る死の恐怖。具体的な脅威がわからないことが逆に何よりも恐ろしい。
「おい、そこのお前」
と、突然前の席に座っていた男子生徒が馴れ馴れしく話しかけてきた。赤いヘッドフォンが特徴的な、わりと小柄な少年だった。彼にも死の旗が見えていた。
「な、何よ。あんたも早く逃げなさいよ!」
「お前巣鴨伊万里だよな。俺はお前を護らなきゃならない。すぐにこの場から離れるぞ。お前の話が本当ならここはすぐに死の空間になるんだろ」
「なんであんた私の能力知ってるのよ。誰なの?」
いきなり見も知らず少年に話しかけられて、伊万里は怪訝な表情になる。同じ年くらいの少年のようだが、彼の顔など一度も見かけたこともない。
「俺のことはどうでもいい。とりあえずここから逃げるぞ。ここの人間はどうせお前の言ってることを理解できないさ、ほっとけ。まあそこの友人くらいは連れてってもいいだろうけど・・・・・・」
と、弥生を指差す。ただでさえ男子に慣れていない弥生は突然に初対面の男子に指を指されて「ひっ!」と声を上げてしまった。
「何言ってるのよ、あんたが誰か知らないけど、死ぬと解っていて皆をほっとけるわけないでしょ!」
伊万里は彼の自分勝手な発言に怒りを抑えられなかった。芯の通ったその瞳で黒く淀んだ少年の目を見つめる。
しかし彼らが口論する間もなく突然の爆風により視界は奪われることになった。
アンダンテはオフビートに早口で伊万里の能力について説明をしていた。
「あの子は人の死が見えるのよ。そのあの子があんなこと言っているってことはまず間違いなくここにいる全員が死ぬ。ギガフレアは殲滅タイプよ、目撃者も無関係者も全てを燃やしつくす男よ。私はここからすぐに離れるわ。あなたはなんとしてでも巣鴨伊万里だけは護りなさい。他の人間は捨て置いていいわ」
そう言ってアンダンテは自分だけどこかに逃げてしまった。仕方なく伊万里に話しかけるも彼女はそれを怒りの眼差しで断った。オフビートは理解できなかった。なぜ自分の命だけでも大事にしないのか。
伊万里に怒鳴られながらも感性を極限にまで高めていたオフビートは、一瞬空気が凝固していることを肌で感じていた。少しだけ空気が冷えるような感覚。そしてこの感覚の次に起こることを彼は演習でいやというほど学んできた。
(爆発・・・・・・か――)
凝固した空気が拡散したかと思うと、それは大きな炎のうねりとなってそのカフェテリアを吹き飛ばした。机や椅子が一瞬で灰になり、ガラスがあたりに飛び散り、見事な半壊状態となっていた。
普通の人間ならば一瞬で燃え尽きてしまっただろう。
あたりが騒然として爆煙の中を見つめている。何が起こったのかわからながあの爆発では死んでしまったのではないか、と誰もが感じていた。しかしそこには人影が雄雄しく立っていた。
「ふぅ、判断が遅れたら全員死んでたな」
そこにはオフビートが両の手を広げ、伊万里と弥生を爆風から護るように爆風に立ち塞がっていたのだ。。
「な、なんですか一体!」
けほけほ、と熱と灰で咳き込む弥生に、ただ唖然と彼を見つめている伊万里。
「あんた何が起こるかわかってたの?」
「別に、何が起こるか知ってたのどっちかってとお前の方だろ。俺はただ瞬間的に危機を感じただけだ」
そう言うオフビートには余裕が感じられた。あの炎を手で防いでも手には火傷一つついておらず、後ろにいた伊万里と弥生も怪我一つ負っていない。
『オフビート・スタッカート(調子外れの切断符)』。
これが彼のコードネームの由来にもなっている異能力である。両手から高周波のシールドを展開させ、彼の両手に触れるものはその全てが遮断される。たとえそれが巨大な炎であろうと無関係に全てを切り離す。触れるものを拒絶するこの能力は彼の“兄”にもよく似ている。
「あんた能力者ね、まあ礼は言うわ」
伊万里は頬の煤をこすりながらオフビートを見つめる。どうやら敵意はなくなったようだ。オフビートは一つ深い溜息をついて、また伊万里を説得する。
「礼ならここを脱出してからにしてくれ。これでわかったろここは危ない」
オフビートは伊万里の手を引っ張ろうとするが伊万里はその手を振り払った。
「私だけ逃げるわけにはいかないわ。まだみんなの死の旗が消えてない。まだ脅威は去ってないんだわ!」
伊万里は周囲の人間に向けてまた非難を促そうと街を見返したその瞬間またもや爆風が街を包んだ。次は伊万里にではなく、少し離れた場所で炎が舞い上がったのだ。その炎の勢いでその飲食店は見事に吹き飛んでしまった。幸い人気の無い店で、客は誰一人いなかった。店員も奥にたようで、何事かと今さら顔を覗かせた。
これに驚いたのは伊万里でも弥生でもなくオフビート自身だった。
(なんだ、なぜあそこが爆発したんだ。ギガフレアは殲滅タイプといったな、目撃者も全員殺すと。それはこの巣鴨伊万里を殺した後ならわかるが、なぜいま他の連中を攻撃する必要があるんだ。まずはこの子狙うのがセオリーじゃないのか)
その二度目の爆発でようやく周囲の人々は危機を感じていた。みなパニックになってちりぢりに逃げていく。しかし時遅く、続けて三度目、四度目の炎の柱が当たり一面に燃え盛る。辺りからは人々の悲鳴や悲鳴で混沌と化していた。
どうやらこの商店街を炎がぐるりと包んでしまったようで、誰もここから逃げることはできなくなっていた。
(だが俺のオフビート・スタッカートならこの炎を突破できる。少なくとも巣鴨伊万里だけは護れるはずだ)
無理矢理にでも連れ去ろうと伊万里に目を向けると、彼女は真剣な目で何かを考えているようだ。その眼差しは、オフビートが見たことも無いほどに強いものだった。
「この炎は自然的なものじゃないわね・・・・・・だとするとラルヴァ・・・・・・いえ、こんな力をもったラルヴァなら神那岐システムの網に引っかかるはずよね・・・・・・だとすると能力者の仕業・・・・・・なら手はあるわ!」
ぶつぶつと何やら呟いているかと思うと、何かを決意したように伊万里はその場から駆け出した。
「お、おいどこに行くんだ! やめろ、そっちは危ない!」
「あんたは弥生を頼むわ、私は炎を操ってる奴を見つけるわ!」
(ギガフレアを見つけるだって? そんなことは危険すぎる――)
オフビートが彼女を制止しようとしたのも虚しく、伊万里とオフビートの間に炎が流れ込み、視界が奪われる。オフビートはすぐに手で炎を振り払い、能力で炎を弾くが、既に伊万里の姿は見えなくなっていた。
(あのバカ女何考えてんだ!)
と、彼も駆け出そうとした瞬間誰かに腰を掴まれた。
「ふぇ〜〜ん一人にしないでくださ〜い」
弥生が泣きながらしがみついてきた。彼女の豊満な胸が彼の腰にあたるが、それをありがたがっている暇はない。オフビートがどうしたものかと途方にくれていると、雄雄しくも凛々しい声がその場に鳴り響き、一瞬だけ人々の混乱は止まった。
「みなさん落ち着いてください! 周りの人と協力して下さい、上級生は下級生を護るように、誰か異能者がいたら炎を防いでください!」
炎の海に包まれた空間から現れたのは黒髪の綺麗な少女だった。
どこかおっとりしている顔立ちだが、その物腰には鋭いものを感じる。
オフビートは彼女をオメガサークルに渡された双葉学園の資料で見たことがあった。
最強の異能力者で構成されている醒徒会。その副会長であり、水系能力者の頂点である彼女の名前は――
「私は醒徒会副会長の水分理緒です。みなさん私の指示に従ってください!」
オフビートのもとから駆け出し、伊万里は考えていた。
(もし、もしこの付近にこの炎を操っている奴がいるなら、そいつだけは死の旗が見えていないはず・・・・・・)
そう、彼女の考えは犯人は死ぬことはないはずで、そこに死の旗がなはずである。逆に言えば死の旗が見えない人物こそ、犯人であるはずなのだ。
強引な推理ではあるが、今の彼女に頼れるのは自分自身の能力だけだった。
まだ見ぬ犯人を求めて伊万里は炎の街を駆け抜けた。どこで炎が巻き上がるかわからない中を彼女は走った。汗でもう服はベドベトだ。墨で身体は汚れ、少しだが火傷も所々にできてしまった。それで伊万里はこの地獄を止めるために犯人を捜していた。
(でもおかしい、異能の炎にしては動きが不規則だわ。だからといって自然の炎でもない・・・・・・。もし異能の炎できちんと炎を操れてるなら既に死人がいっぱいのはずなのに)
それにも関わらず今のところ炎で焼かれた人はいなかった。炎の動きが大雑把なために、不意打ちでもない限り避けることができるようだ。勿論それは双葉学園の生徒が異能の力に対しての対処が教え込まれてるということもある。だがそこには何か違和感があった。
(もしかして犯人はこちらが見えていない――?)
酸素が足りなくなってきて思考が鈍くなっている。伊万里は一度足を止めて深呼吸する。間違って煙を吸い込み咳き込んでしまった。
(うう、でももしこっちが見えていないってことはそれなりの理由があるはずよね。そうか、たとえ炎を操れても酸素の薄さや煙の危険を考えて自分だけ安全な場所にいるんじゃないのか。しかもこれほどの能力となると必然的に遠くからは操作できないはず――つまりこの近くで煙の心配の無い場所に犯人はいる!)
伊万里は目の前の建物を凝視する。そこはただの本屋で、既に炎で焼かれてしまってる。しかしその地下にはゲームセンターがあった。
その地下には一切炎が侵入していない。
(ここが唯一の地下、これがハズレならもう時間がない)
伊万里は迷わずその地下の怪談をゆっくりと降りていく。そこは外とはまるで別世界のようにひんやりとしており、当然ながら煙も侵入してはいない。伊万里はゲームセンターの自動ドアを潜ってゲームセンターに到着した。ここにはまだ電源が通っているのか小うるさいゲームの音があたりに鳴り響いている。
そこに制服姿の少年がゲームの筐体に向かって座っていた。
その少年は画面に落ちてくる四角形の物体を重ねて消すという大昔のゲームをしていた。少年の頭には死の旗が無かった。それを見た伊万里は背中越しに話しかける。
「あなた、今外がどうなってるのかわかってるの。それとも知ってて自分だけ安全な場所にいるのかな」
伊万里はすぐそこで拾ったビリヤードのキューを手に構えていた。伊万里の言葉に驚くこともなく少年はこちらを振り返った。メガネが良く似合う細身の少年。
伊万里はその名前を知らないが、紛れもなく彼がギガフレアだった。
「へえ、まさか僕の居場所を突き止めるなんてやるじゃないか。さすがは死の巫女といったわけだ。どうりで司教があんたを危険視するわけだよ」
意味の解らない言葉を発する少年に、伊万里は全てを確信した。
「自分が犯人だって認めるのかしら。だったら今すぐこの炎を止めなさい!」
キューを薙刀のように構え、ギガフレアと対峙する。
しかし片や予知能力のある普通の女子高生。
片や本職の殺し屋。
相手になるはずもなかった。しかし伊万里には勝算があった。
(この狭い場所で炎を使うことは出来ないはず。自分もその被害を受けるからね)
そんな風に考えてたがギガフレアは顔色一つ変えずに、
「おいおいここでは僕が炎を使えないって油断してないかい。確かに炎は使えない。だけど僕が凄腕のヒットマンということに違いはないんだぜ。戦闘系異能者相手ならともかく、非力な予知能力者、それも女に負けるかよ」
と、ポケットからごついナイフを取りだした。
それにはさすがの伊万里も顔を強張らせた。
突然に学園最強の一人と出会いオフビートは戸惑った。
しかしこれはこの危機を脱するには都合がいいと考えていた。
水操作系の頂点である水分理緒は、肌に触れた水を自在に操れることが出来るとオメガサークルの報告で聞いている。ならばこの炎を鎮めるには適役ではないか。
「あ、あの副会長。あんたならこの炎を能力でなんとか出来ないのか」
水分は周りに指示をしながら、見慣れぬ男子生徒であるオフビートの顔を見た。その表情は曇っていた。
「残念ながら私の能力は水を操ることしかできないの。いまここにはもう水が無いわ。だからどうしようもないの。あるのは精々私の予備のペットボトル一杯分・・・・・・」
と言いかけたところで目の前から女の子の悲鳴が聞こえた。小等部であろう女の子が転んで泣いていたのだ。そこにギガフレアの炎が迫っていた。
「あ、危ない!」
瞬時に水分は反応し、ペットボトルの蓋を開け、自分の腕にかける。すると水はまるで生命が宿ったかのように炎の方に飛んでいった。
女の子の身体に炎が当たる寸前に、その炎は水分の水によってかき消された。
「はぁ・・・・・・よかった・・・」
しかしこれで最後のペットボトルの水もなくなってしまった。
「打つ手・・・・・・無しか」
オフビートは舌打ちをした。伊万里もどこかにいってしまい、今や炎が強すぎて彼の能力ではここを脱出できるかどうかも怪しい。おそらく手で炎を防いでも、身体が焼かれてしまうだろう。
「いや、まてよ。確かここは海の上に建っているんだよな、水ならありあまってるじゃないか」
オフビートは顎に手を置いて何かを考えてる。それを水分も見ていた。
「確かにそうよ。でもどうやってここに海水をもってくるというの? もう私たちは救助を待つしか手は・・・・・」
「いや、海水ならあるさ、この真下にな!」
オフビートは両手を天に掲げ、思い切り地面に振り下ろした。
「オフビート・スタッカート全開!」
地面に両手をつき、高周波のシールドを展開させる。それは全てを切り離す最強の盾である。耳をつんざく高音があたりに鳴り響く、水分も耳を抑えながらオフビートの行動を見守っていた。
数秒後破壊音とともに地面は崩壊をきたした。コンクリートは何メートルもある分厚さであるにも関わらず、それを全て破壊したのだ。あくまで掌サイズの穴であるが、確かに海面と繋がったのである。
「これがキミの異能なの・・・・・・?」
「ああ、もうこれ以上コンクリートを突き破るほどの能力は酷使できないけどな。そんなことより早くこの海水を使って・・・」
「まだ駄目よ」
「は?」
オフビートは水分を見返すが、冗談を言っている様子ではない。それどころかその表情は曇っていた。
「私の能力はあくまで肌に触れないと発動しないの。この穴じゃ海面までは何メートルもあるからとても手が届かないわ」
その言葉で再びオフビートも絶望の表情になっていく。しかし、水分はきっと顔を凛々しくさせて懐から小刀を取り出した。
「大丈夫よ。まだ、手はある。私の腕に触れた水を海面の水に結合できればそれを操ることもできるわ」
「だ、だけどもう手持ちの水はもう無いんだろう・・・・・・」
「いえ、ここにあるわ。血は水よりも濃いのよ!」
そう言いながら水分は小刀の刃を手首に押し当てた。
一瞬だけ地下が揺れるのを伊万里は感じていた。
「何? 地震?」
そこにはわりと余裕の表情の伊万里と、床に組み伏せられていたギガフレアがいた。
「な、なんだてめえ! 本当に予知能力者なのか、なんで俺が負けるんだ!」
伊万里はそう叫ぶギガフレアの頭をキューで小突く。
残念ね、私は戦闘系能力者にバカにされないように剣道部で鍛錬を積んでるのよ。あんたみたいなこんな遠くからこそこそとしてる奴に負けるわけないでしょ!」
と、再びキューで頭を殴った。むごいが、これも当然の報いである。
「さあ早く炎を止めなさいじゃないともっと痛い目にあわせるわよ」
「ははは、もう無駄だよ。僕の能力は大雑把でね、僕にもあまりきちんとした制御はできないんだよ。だからああして闇雲に炎を巻き散らすしかなかったわけだからね」
「な、なんですって!」
つまり彼を倒そうが殺そうが、その炎が消えるわけではない、ということだ。
伊万里が苦い顔をしてると、また地下全体が揺れ始めた、さっきよりも大きい揺れた。その揺れで体制を崩した伊万里を見て、チャンスだと感じたギガフレアはすぐさま起き上がり出口に向かって逃げていった。
「あ、待ちなさい!」
すぐさまギガフレアを追いかけるが、全体的に疲労の溜まってる伊万里は足が思うように動かなかった。伊万里を放置して、とにかくこの場から離れることだけを考えているようで、全力で地下から外への階段を駆け上がった。
彼が逃げれるだけの炎の制御はかろうじて出来るため、とにかく再度のチャンスのために今回は捕まるわけにはいかなかった。
しかしギガフレアは外に出た瞬間、驚くべき光景を目の当たりにしていた。
まるでそれは例えるならば水龍がうねっているかのような凄まじいものだった。大量の海水が一本の柱になり空に向かっていった。そして限界まで上に昇りきったと思うと、轟音とともに破裂して、それはさながらゲリラ豪雨のように街全体に降り注いだ。
一瞬にしてギガフレアの作り出した炎の空間は消え去ってしまった。
(さすがは醒徒会、そのナンバー2といったところか)
水分は自分の手首から流れ出る血を海面と直結して操ったのである。貧血状態でありながら、何トンもの水を操るのは並大抵ではないはず、いや、それこそそんなことが出来るのはこの学園では彼女だけだろう。しかし彼女の能力は精神を酷使するために、そして極度の貧血状態も相まってその場に倒れこんでしまった。
「副会長さま〜〜!」
弥生が水分のもとにすぐ駆けつけて鞄から包帯を取り出して彼女の手首に巻いていく。なかなか手際がいい。
「大丈夫なのか副会長は?」
「は、はい。出血は酷いですけど安静にしてれば三日くらいで元気になるかと・・・・・・」
オフビートは水分の能力と自分の身体を省みない決断力を見て心底敬服した。オメガサークルに能力を強化された自分とは圧倒的に異なるその存在に、彼は慄いていた。
炎が消え去り、皆が安堵の表情で歓声を上げている中、地下から出てきた男子生徒だけが呆然としていた。オフビートはその少年の目に見覚えがあった。
あれは殺し屋の目。オフビートは直感で彼がギガフレアだと確信した。
ギガフレアもオフビートの視線に気づく。彼もオフビートのことは知らないはずだが、その視線に殺意を感じ、彼はその場から駆け出した。
瞬時にオフビートもギガフレアを追いかけようと走り出す。そこに地下から出てきた伊万里と出くわす。オフビートは伊万里と目が合った。
「あ、あいつがこの事件の犯人よ!」
「ああ、わかってるさ!」
しかし、その刹那オフビートの脳髄に激痛が走った。
オメガサークルにより能力強化のために脳を弄繰り回された彼は、能力を限界まで使用すると後遺症が現れるのである。あまりの激痛に彼はその場にへたり込んでしまう。あと少しで敵を捉えられたとうのに。
「ちょ、ちょっとあんた何して・・・・・・あんたどうしたの?」
伊万里もそんな彼の異変に気付いた。唸りながら頭を抑えるオフビートを伊万里はそっと抱きしめた。
「なんだか解らないけど、ちょっと大人しくしといたほうがいいわね。ほら、体支えててあげるから」
「いや、それよりも奴を・・・・・・じゃないとまた・・・・・・」
それでも無理に立ち上がろうとするオフビートを、伊万里は制止する。
「大丈夫よ。むしろ可哀想なのはあいつのほうよ。みんなの死の旗が消えた瞬間、あいつの頭に死の旗が現れたの。多分あいつはもうすぐ死ぬわ」
身体を海水の雨で濡らしながらもギガフレアは裏道を走っていた。
走りながら、彼はヘッドフォンの少年のことを思い返す。あの少年が頭を抑えていたことに彼は心当たりがあった。
(あれは脳改造の後遺症の症状じゃないのか、だとするとあいつはオメガサークルのモルモットか。どうやら醒徒会以外にも厄介なやつがいるようだな)
彼の所属するスティグマと対を成す科学機関であるオメガサークルは、この双葉学園に二年前まで存在していた対ラルヴァ用兵器開発局の残党により結成されたシステムである。
オメガサークルはスティグマとはまったく真逆で、そこに利益や思想は存在しない。そこにあるのは未知の力に対する知的好奇心。その名の通り“究極”を追い求める、それだけの科学機関である。ある種、そのような存在が一番恐ろしい物である。
二年前に禁忌である「人工的に能力者を作り出すための人造人間の製造」を犯したためにとり潰しにあったのだ。結局数万体の失敗作の中から一体だけ、異能力をもつ人造人間を生み出すことに成功した。その人造人間は兵器開発局が消滅したために、双葉学園に在籍することになった。
それが今ではその人造人間が醒徒会に存在するなんて皮肉なことだ。
オメガサークルが次に手を出した研究は、人工的に異能者の能力を底上げすることであった。オフビートはその実験で生まれた存在である。その人造人間をベースに、彼の能力は開発、精製されていった。ある意味ではその人造人間がオフビートの“兄”とも言える存在である。
(顔を知られた以上ここにはいられないな、一度組織に戻って――)
と、逃げ切れることを確信していたギガフレアの前に人影が立ち塞がった。
そこには見覚えがある、青いサングラスをかけた男が立っていた。
それこそがオメガサークルの前身である兵器開発局が生み出した究極の人間兵器であり、醒徒会の一員でもある男だった。
「そこのキミ、ここで何をしている」
(エヌR・ルール! まさか日に二度も醒徒会に出会うとは――)
むしろルールがこんな路地裏にいることに疑問をもったが、ルールが抱えている子猫を見て苦笑した。どうやら彼はここで捨て猫を拾ったらしい。
「い、いや。さっきの放火事件はもうルール先輩も知っているでしょう。僕はそこから逃げてきたんですよ。いやあまさか雨で火が消えるなんて」
「嘘、だな。ぼくの目は誤魔化すことはできない。お前がその事件の犯人なんだろう」
その青いレンズ越しの鷹のような瞳に射抜かれ、ギガフレアは驚愕する。ルールの性能は、彼が思っている以上であることを証明していた。
「ぼくの頭には全生徒のデータベースが詰められている。それによると、キミの顔に一致するものは一つもない。それにキミがあの火の海から逃げてきたというわりには炭も焦げ跡も一切無い。そして何より、どんなに誤魔化そうとしても、殺し屋の匂いは消すことはできない」
「へえ、さすがは人造人間だな。化け物め」
ギガフレアは考える。恐らく彼の炎では奴の粒子分解の能力『ザ・フリッカー』には一切通じないであろう。だが、ギガフレアもルールの能力を調べていた。その弱点もよく知っている。
ギガフレアは小さな炎を掌に作り出し、それをルールの目に向けて放った。
「ぐっ!」
爆発が起こり、ルールの顔が飛散する。勿論能力により、粒子分解した彼にダメージは無い。しかし、
(それでも目くらましにはなるだろう、いまだ!)
ルールが再構築をしているうちに全力で駆け出した。ルールの能力は自分以外も分解可能ではあるが、それは両の手で掴まなければ意味が無い。つまりルールの手に触れられなければ逃げ切れる、そう考えていた。
しかし走り出したギガフレアの身体が突然がくんと傾き、いつの間にか地面に転がってしまった。こんな何もないところで転ぶなんて間抜けだ――と思うかと知れないが、彼は転んだわけではなかった。
恐る恐る自分の足を見ると、膝から下の両足が消し飛んでいた。
痛みはない、血も出ていない。これはルールの能力の干渉だとすぐに気づいた。
(しかしなぜだ、ルールからは離れているのに)
焦りながらも分析を開始するギガフレアは、ルールの両腕が無いことに気づいた。そう、ルールは自分の両手を粒子分解し、逃げるギガフレアに向けて飛ばしたのである。
そして彼の足元で再構築を果たし、触れ、ギガフレアの両足を奪い去ったのである。
「ぼくから逃げることはできない、諦めろ。拷問なんて下品な真似はしたくない。素直にキミの目的と素性を話すんだ。今ならまだキミの足の再構築も可能だ」
「ははは、さすがエヌR・ルール。僕にどうにか出来る相手じゃなかったか。どうやら僕はこれまでのようだな」
そこにあるのは諦めの狂気の笑いであった。ルールは彼を無表情で見下ろす。
「いいだろう、ヒントを教えてやる。僕たちの目的は『彼女』さ」
「『彼女』? 誰のことだ」
彼女、勿論そのニュアンスは彼の標的であった伊万里のことではない。ギガフレアの言葉には何か信仰心を感じるものがあった。
「誰? ははは、人間なんて汚らしい存在じゃないよ『彼女』は。ただ、僕らの言語では『彼女』の名前を発音できないからね、便宜上そう呼ばせてもらっている。そうだな、キミたちがラルヴァと呼んでいる存在と同一ではあるが、そんな低俗なものではない。『彼女』は僕らの神であり希望であり未来だ。『彼女』の封印を解くにはあの死の巫女が邪魔だったのさ」
「神・・・・・・死の巫女? 何のことだ」
「これ以上は冥土にもってかせてもらうよ。精々僕の後任たちに気をつけるんだな。じゃあな人造人間。さよならだ」
「お、おい待て!」
突然ギガフレアの身体が光ったかと思うと、煌々とその身体は火に包まれた。彼は最後の瞬間を自分の能力で幕を下ろしたのだ。どちらにしろしくじった彼を組織が頬ってはいなかっただろう。ルールの制止も虚しく、ギガフレアは灰になり消えた。
「ちっ、バカ野郎・・・・・・」
そこにはルールだけが残された。
ルールはからりと晴れた空を見上げ、これから起こる“何か”に向けて決意を決めていた。
――――――To Be Continued?
最終更新:2009年07月26日 23:01