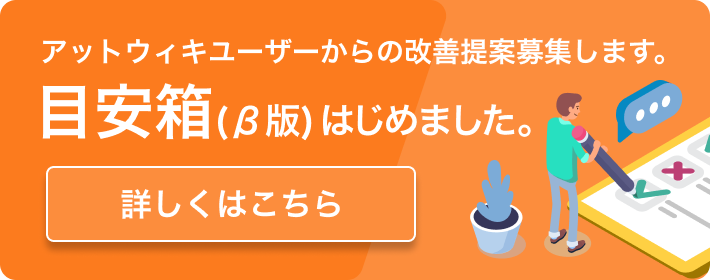「六章 玉虫色」(2008/09/18 (木) 01:12:01) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
気がついたら、俺とロイは比較的明るい白い光に満たされた小部屋にいて、
ちょうど真四角なそこの中心にへたり込んでいた。
癒えない傷をなぞるような感覚で思い出せば、俺たちはあの大部屋の床には下りず、
そのまま高台通路を奥へ走ってここへ逃げ込んだことが朧に浮かんできた。
(……ディーア)
目の前に投げ出している足は熱を持ってがくがく震えるし、
頭は熱病にかかったようにぼうっと重い。
両手ですがりつく『雨の弓』が無かったら、
俺は間違い無く床に突っ伏していたんじゃないだろうか。
歯が突き刺さるほど噛みしめた唇から血が流れるのも気にせず、俺はさらに歯を食いしばった。
悔しかった。なにかに向かって、こんなのはウソだと絶叫したかった。
なんてことだ。俺が、甘過ぎたんだ。
「……グランド、立てる?」
かすれた低い声がした。苦くて重い感情がこもった、聞いたことも無い声だった。
あんまり違う様子だったんで、俺はそれがロイの声だと気付くのにしばらくかかった。
横を見ると、紙のように白い顔をしたロイと目が合った。
なんだよ、まるで死人みたいじゃないか。
そして、彼の深く澄んだグリーンの瞳に映った俺を見て、その言葉を飲み込んだ。
…俺の方がよっぽどひどい顔をしている。目は泣き腫らして真っ赤だし、顔面は蒼白。
墓から出てきたばっかりだと言っても通じる顔だぜ。
俺はふうっと溜め息をつく。
「いや、悪い。しばらく無理だ」
それだけ言うのにも恐ろしく体力を使った。
目をロイからそらして、割れ目一つ無い遺跡の床を、俺は見つめた。
「甘かった。…現役ディグアウターのロイに言うのもなんだけどさ、ほんと。」
胸の内を、後悔と無力感と切り裂くような痛みが降り積もる。
「弓漁師やってたから、多少は命の危険にも慣れてると思ってた。
…死者が全くでない職業じゃないし。現に俺のじいさんは崖で死んだ。
それでも俺は弓漁師になったし、
家族の誰も、いや島の誰も弓漁師を辞めろなんて言い出すやつはいなかった。
必要なことだって誰でも知ってたし、なによりじいさん本人の覚悟があった。
…ディグアウターもそうだろ。人類にとって必要不可欠だ。誰かがやらなきゃいけない。
でも、死といつも隣り合わせだ」
ロイは隣で静かに聞いている。
どう思っているだろう?いきなりこんなことをぺらぺら話し出す俺を。どこかおかしくなったと思うだろうか。
「俺、たぶんいつもの弓漁より、こっちの方が安全だって心のどこかで気を抜いていた。
夢だった初ディグアウトで浮かれてたせいもあるだろうけど、
言い訳にはならないな。
俺はディーアが一人前になるまで導く役目だった。護ってやらなきゃならなかった。
今ならわかる。…あいつの死は、俺の責任だ」
弓漁の途中で、波にさらわれて死んだのならまだ俺は納得していた。
ディーアでさえ何の文句もなかっただろう。…だからこそ、悔しいし辛い。
こんなふうに、いいわけを言うなんて、…俺、最悪だ。
床に突き立てていた『雨の弓』をずるずると引き寄せ、
膝の上に抱き上げながら俺はその場に座り込んだ。
「ロイ、ここから帰れなんて言うなよな」
「……えっ」
あきらかに動揺を押し殺した声。
今のロイは俺と同じ立場だ。弓漁師として経験の浅いディーアを導かなければならなかった、
俺と同じ立場。責任ある経験者の立場だ。
ディグアウター初心者の俺を、もうこのままにして置けない気持ちは痛いほどにわかる。
―――でも。
「俺はディグアウターとしての覚悟が足りなかった。
ディーアの死の責任は、俺がディグアウターとしてとらなきゃならない。
俺が遺跡に入った目的は、ディフレクターを手にするため。ディーアもそうだ。
今ここで何も手にせず帰ること、それはあいつの死を無駄にすることだ。
危ないとか怖いとかの理由で、ましてやあいつが死んだからなんてのを理由にして逃げ帰ったら
…俺はきっと、この先すべてからあいつの死を理由に逃げ続ける人生を送ってしまう」
そんなのは、ディーアに対する侮辱だろう。あいつの家族にとっても。
そこまでを一気にしゃべって、俺は全身の力をこめてロイを見上げた。
「…俺はあの蛇をぶったおして、この遺跡のディフレクターを手に入れる!
それが俺の責任の取りかただ。ロイ、俺を無責任なやつにさせないでくれ」
ロイは喉まで出かかった何かを言おうとして、思いとどまるようにその口を閉じた。
眉間に寄せた気の強そうな眉が震えるのは、悲しみのためだろうか。怒りのためだろうか。
『…ねえ、グランド…もう、私の声、聞こえる?』
ジッと音を立てた無線機から、ロールの声が響いた。
そういえば、あの混乱の中彼女の声を何回か聞いたように思う。
ああ、しまったな。全然返事をしてなかった。
「悪い。大丈夫、もう聞こえる」
『ディーアくんのことは、私も、…ロイも辛い。
本当なら、私たちディグアウターとしてはグランドにすぐにでも地上にもどってもらいたいわ。
それが義務だし…。でも、ちょっと…ね。
私たちも、あなたに帰ってもらうわけに行かなくなっちゃったの』
彼女の声は、なにかをためらっている様子だった。
俺は、それに漠然とした不安を感じた。胸の奥がざわつく。
これ以上の悪いことが、ほかにあるとでも…?
「グランド、きみ……この扉どうやって開けた?」
言葉を継いだのはロイだった。いつのまにか俺たちが入ってきた、この部屋唯一の扉のそばに立っている。
その扉は薄緑色で、ほぼ正方形をしていた。
遺跡のほかの扉の例に漏れず、ひとたび通りぬけたら自動的に閉まる仕組みで
今はぴったりと境目もわからないほどに閉まっている。
でもな。俺は苦笑した。その扉は、触れるだけで開くんだ。いわゆる自動扉というやつ。
ここに来るまでにだって、何枚も通ってきたじゃないか。
「何言ってるんだよ。そんなもの触れば開くだろ」
俺を見返したロイの瞳が、何かを確かめるようにキラリと光った。
彼はそのまま、片手をのばして扉に触れる。
「おっおいっ!! むこうにはまだあの蛇が居るかも知れ…」
(なんだって!?)
扉はぴくりとも動かなかった。そのかわり、いきなり狭い室内に合成音声らしき声が響き渡った。
【警告・警告・ロックマンアリアおよび、ガードリーバード・エンテ以外のいかなる通行も禁じます。
ここは特殊区域に指定されています。緊急時はヘヴンの…】
それ以降は難しい言葉ばっかりで俺には理解できなかった。
へヴンがどうの、司政官ろっくまんがどうの、
いままでまるっきり聞いたことのない単語の羅列に脳が付いて行けなかった。
なんだなんだ一体!?
「…この扉は、ロックマン・アリアかその守護リーバードにしか開けられないって言ってるんだよ。
そのどちらでもないのに、扉を開けた。…グランド、君は誰だ?」
ロイが扉から手を離すと、声もすっと消えてしまった。…繰り返すけど、扉は開かない。
思わず思考が停止しかけた。ロイの真剣そのものの目を見つめて、
あまりの事に泣いていいのか笑っていいのか、それとも困惑すべきなのか分からなくなった。
俺はその場に呆然と立ちあがり、ただ首を横に降った。
こっちが聞きたい。まるでタチの悪い詐欺にあったような気分だった。
「何が言いたい!? 二人して、俺が…なんだっていうんだ。こんな時に、…冗談かよ!?」
俺は悲鳴のように叫びながら後ずさっていた。
何もかもが分からなくなってきた。この遺跡も、ロイも、ロールも、自分自身も。
「じゃあ、後ろを見て。
遺跡の壁はそこらの技術じゃ傷一つ着けられないくらい強固な材質で構成されてる。
僕のバスターを何発撃ちこんだって焦げ目すらつかないんだ。
そこに刻まれたものなら、この部屋が作られた当初からのものだってわかるよね?
きっと、なんの冗談でもないことがわかると思う」
「…後ろ?」
半信半疑で、俺はまずロイの方を向いたまま、弓を持っていない方の手で壁を探った。
ひやりとした冷たさと、わずかなざらつき。他の壁面と違って細かい凹凸がある。
…確かに何か、刻まれているようだが。
覚悟を決め、一気に振り返る。
(…これは!)
目に飛び込んできたのは壁画だった。色鮮やかな、…人物画。
一人の人物が、リーバードらしきものと共に描かれている。それほど大きい絵じゃない。
俺が身体で隠そうと思ったらあっさり覆ってしまえる程度の絵だ。
絵の周りには細かな文字が書き連ねてあるようだ。
本でよく見た遺跡内の壁画に雰囲気がよく似てる。
写実性は無いけれど、肌の色や髪の色、瞳の色はちゃんと見て取れるものだった。
―――褐色の肌。水色の髪。…藍色の…瞳。
(ん?)
俺は片手を絵の上について、もう片手に持っていた弓を慎重に背に回した。
ゆっくりと壁に両手を這わせ、顔を近づけてよくよく見る。
……なんだろう?なにか、とても懐かしい気が…。
壁画の人物は片手に水色の弓を持ち、もう片手に開いた書物を持っている。
リーバードの方は、これはどう見てもさっきの蛇だった。
人物を護るように真紅のとぐろを巻き、あの変幻自在の刃を体中から逆立てている。
(司政官・アリアと、守護リーバード…エンテ?)
雷鳴のような直感だった。一瞬の光が頭の中に射し込んで、それが俺に確信させた。
「俺は…知っている!?」
低く漏れた声は自分で驚くほど、奇妙にしゃがれていた。
名も知れない悪魔にささやかれたような気分だった。壁の凹凸をなでる手が震える。
古代の象形文字に似た、まったく現代のものからかけ離れた文字の形だった。
…なのに!
俺は、小さい子供が習い始めた文字を読むように、
その得体の知れない文字をなぞりながら読み上げていた。
「…緊急の折に望んで…書き残す…わたしは、司政官アリア。・・・」
たどたどしい俺の言葉に、ロイの声が背後から重なった。
『ヘヴンに背いた心弱きロックマン。…ロックマン・アリア』
慎重なロイの声が、なおも背後から続く。
「僕はロックマン・アリアの姿かたちについては、
他の部屋の端末から読み出してすでに知ってた。
ロールちゃんにも伝えておいたから、君が現れるより前には、二人とも知っていたんだ」
だからロールちゃんは君を見て驚いた。と、ロイは小さくつぶやいた。
「僕もロールちゃんも、きみがこの島の司政官ロックマンだと思った。
僕を知っている可能性がある。…かつて、ヘヴンで粛清官のロックマンだった僕を。
粛清官は、上が異端《イレギュラー》と判断した相手を処理するのが役目。
もちろん今はそうじゃないけど、いきなり君に敵対されるわけにはいかない。
…だから、偽名を使わせてもらった。そうしておいたら、少なくとも他人の空似で通せる」
またしばし間があく。ロイは迷っているようだった。
…たぶん、真実を告げるのを。
俺と敵対するのを、というより、彼は誰かと敵になることを嫌がっている。
きっと誰とも本当は争いたくなんかない。
…そういう気配のする声だった。
「僕の本当の名前はロック・ヴォルナット。
…昔『ロックマン・トリッガー』って呼ばれていた。…元、ヘヴンの粛清官だ」
――《ロックマン》――?
それは、かつて俺の秘密に鍵をかけた言葉だった。
心の鍵穴にその言葉がはまり込んで、俺はまだ見えぬ記憶の存在に怯えた。
それは、楽園を閉ざす鍵だ。
この島を…辺鄙だけれども、自然の美しい、のんびりした天国のようなこの島から俺を遠ざける、悪夢の鍵。
同時に、俺を天国に近づける鍵。かつて去った空のあちらへ、俺をつなげる…。
俺は、静かにただ、まぶたを閉じた。
今まで現実だったものが遠ざかり、夢物語が、真実になる。
(…後戻りは、もうできない、か)
あきらめのような、決意のような、悲しみのような。
…なんだろうな、ものすごくごちゃごちゃした気持ちが俺の胸をいっぱいにした。
わけがわからないはずなのに、頭のどこか冷静な部分が、
本当はわかっているだろう。と、厳しく俺を怒鳴りつけている。
「キー・ワードとはよく言ったもんだ
…ロイ、いや、ロックか。君はヘヴンからの使者なのか」
「……!」
振り返ると、ロイと名乗っていたヘヴンの元粛清官は目を見開いて凍りついていた。
彼の深いエメラルド色の瞳が、驚きのためにか、色がわずか薄まる。
「じゃ、君は……やっぱり……!?」
確信を、もう一度確かめるような押し殺した言い方だ。
ロックはやはり最初から気づいていたんだろう。
でなきゃ、ロックのような手馴れたディグアウターが危険な遺跡に素人を巻きこむものか。
偽名を名乗る判断は、俺が合流するまでに無線で打ち合わせでもしたんだろう。
俺はうなずいた。
「俺は、このロードアイランドの元司政官。ロックマンアリア」
あの年齢不詳で、物見高い俺のオヤジも、心配性で物静かな母も。
弓漁師として代々続いてきた家、無口でやけに誇り高くて、弓漁師として命を落とした俺の爺さんも。
あの全部と、俺は本当は何のつながりも無かったなんて。
俺は肩にかけた弓の重さを意識した。
…この弓でさえ、オヤジから受け継いだものじゃなかった。
強力な暗示で自分と家族にそう思い込ませていただけで。
「……元・司政官? 今は違う?」
ロックが不審そうに、だけど静かに聞いてきた。全身がわずかに身構えて硬くなっている。
俺は苦笑した。それを話そうと思ったら、長い話を覚悟しなくちゃならない。
それに、俺、自分のことを話すのは得意じゃないんだ。
なんか、そういうのって照れくさいだろう?
…そう、あのことはまだ、人に語れるほど過去になってしまったわけじゃない。
だから、今の事実だけを話すことにする。少し俺は笑って、壁画を目で示してみせた。
「よく見てくれ。何か俺とちがうだろ」
「?」
ロイ、いや、ロックだっけ。彼はしばしきょとんと壁画と俺とを見比べる。
…なんだか気恥ずかしいが、やがて気付くはず。
「あ! …。いや、ええ!??」
人差し指を壁画に突きつけ、次に俺に突きつけてロックは奇声を上げた。
壁画のロックマン・アリアの体つきは、微妙にだが、女性のラインをしている。
身に付けているアーマーが一番わかりやすいだろう。よくみれば女性用のデザインをしているんだ。
「そ。ロックマン・アリアは女性体。俺はごらんの通り男…」
『オカマ!?』
ロックと、無線のロールが嫌なハモリを披露してくれた。
長年の悩みをなんでこんなとこで味わわなければならないんだか。
俺は激しく頭痛がしはじめた頭をさりげなく押さえながら、溜め息をついた。
「ああ、俺は髪も長いし言いたいことはわかる! …わかるが、違うからな!!」
たぶん、その瞬間俺は凄い顔していたらしい。ロックが目に見えて怯えた表情をしたんだ。
…そんなつもりはなかったんだけど。すまん。
しかし、子供の頃からの悩み、『童顔』ってやつの原因がこんなとこにあったとは。
もともとが女性型の司政官だったから、なんて想像外にもほどがあるぜ。
ああ、しかしオヤジのせいじゃなかったんだなぁ。
「あ、で、でもありえないよ! …いくらボディのリセットが起こって、
子供からやり直すことになったからっていっても、最初に設定された性別が変わるなんて!!」
司政官や粛清官。その他ロックマンと呼ばれていたヘヴンの住人は、
怪我などで身体を激しく損なっても『リセット』を行うことで生き延びることができる。
記憶は失われるものの、基本的な人格や能力はそのまま、
肉体を一度赤子に戻して、そこからやり直すことができる。
これはあくまでも緊急の最終手段だ。なにしろ記憶が失われてしまうんだから。
だから、性別はそのままになる。
男性の人格を持つものが女性体としてリセットされてしまったら、大変な混乱が起こるだろ。
「僕も、一度リセットしたらしいからわかる。
トリッガーだった僕と、今の僕は違う。でもそれは育った環境が違うせいだ。
でも! …性別までは絶対にかわりっこない」
そこまで叫ぶように言って、ロックはごくりと喉を動かした。
「…グランド、きみは、本当に誰なんだ!?」
わずかにバスターが動く。俺が敵だとわかったその瞬間に打ち込める体勢だ。
…さすが元粛清官。
その真剣な瞳に俺が写っている。水色の髪、褐色の肌、藍色の瞳。
色はそのままにして、もう少し骨格を華奢にすれば…司政官ロックマンアリアの顔だ。
それは俺本来の顔じゃない。俺は、本当はロックマンなんかじゃなかった。
心臓のあたりに差し込むような哀しみを感じて、何気なくそこを手でおさえる。
…もう、全て思い出した。どうして記憶を失っていたのかも。そしてなぜ、今思い出したのかも。
―――どうして。
俺と、そして、アリアにとてつもない事件が起こったからだ。
俺は眉を寄せて考え込んだ。
…まったく、ややこしい説明になりそうだ。だから説明とかは苦手だってのに。
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: