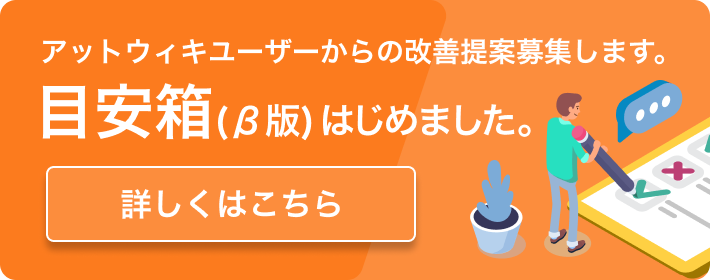「最終章~闇への扉 明日への鍵/嵐の前/嵐へ」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「最終章~闇への扉 明日への鍵/嵐の前/嵐へ」(2008/09/18 (木) 01:15:12) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
最終章~闇への扉 明日への鍵
蛍火のごとく、蒼い光が雨の弓から立ち昇る。
それは暗闇を溶かし、どこから差すともしれない、扉を照らす白い光と交じり合う。
まるで、スローモーションのかかった、青色の炎。
ピン!と、どこかで何か金属質のものがはぜる音がして、
巨大な一枚岩のような黄色い扉が身震いした。弓と扉が交信しているんだ。
―――あれはこの鍵で開く唯一の扉。これはあの扉を開く唯一の鍵。―――
記憶されている信号が、扉と雨の弓の間で交わされる。
「俺は、ヘヴンからいらないといわれたけれど、消されることは無かった。
アリアも居てくれた。だけど、この島の実験体のデコイたちは?
少しでも『人間』と違う数値がでれば、地上の建物ごと焼きつくされる。
それをするのは俺と、アリアだ。もう何回滅ぼしただろう。
地下で実験を行っている新種のリーバードたちをこの際とばかりに放ってデータを取った。
つかまえて来ては俺の前に放ち、思うさま狩った。今思うと恐ろしくて震えてくる。
あの殺戮に、俺は何の疑問も持たなかったなんて。
デコイたちには自我があったのじゃなかったか? 人格があった。今の俺みたいに、大切な人も、家族も」
雨の弓から光が消え、代りに扉の割れ目に金色の光が灯った。
最初はただのペンの先でついたような光の点。
それから炎が燃え広がるように、何の模様もなかった黄色い扉の全面に複雑な紋様が現れはじめた。
俺が立っているところを中心にして。
「俺自身がそういう立場に立ってはじめて。
俺はそれを思ったんだ。嫌になるくらい気付くのがおそかったけど」
苦笑して、俺はもう元の透明に透き通っただけの弓に戻った雨の弓で
扉をコン、コンと2回叩く。
ざああっ!・・・・
むりやり音を当てるとしたらそんな感じか。
扉の全面に浮いた複雑な紋様に金の光が注がれる。中心から周囲へ。砂へ染み込む水のように。
「すごい…!」
話の深刻さも瞬間的に吹き飛んだのか、ロックが扉を仰ぐ。
その肩、胸、顔、前面が金の光に染まって、
彼の深い緑の瞳は金の光をちりばめた木洩れ日の色になった。
そのほんっとに少年少年した表情を見て、俺は思った。
…この島に来たロックマンが、こいつでよかった。おぼろげな記憶の中から、島を定期的に訪れる無表情のヘヴン職員達を思い出す。
・・・よかった。感動を覚えることができる相手で。
苦笑しつつ、俺も紋様を仰ぎ見る。
複雑な黄金の光の線画。それはアリアの刻んだ物。
島民だったら一目でわかるだろう。これは、この島の絵だった。
おおまかな輪郭と、特徴的な一つの山。その山は俺が子供の頃から『クラウン・ガリア』って呼んでた山だ。
島の連中なら誰だってそう呼んでいる。
山頂の形が冠に似ていて、だから『クラウン(冠)』。
『ガリア』が何かは誰も知らないってのがおかしかったっけ。それから、湖だ。
手漕ぎの小船で30分もあれば一周できてしまう、池みたいな湖。
よく他のやつらと泳いだ。夏になると藻がびっしり浮いて、カエルがやかましく鳴く。
藻でべたべたになってしまうのは気持ち悪かったけど、それでも意地で遊んだのは何でだろう?
三日月の形に湾曲しているのは、唯一の浜。ロックたちの飛空船が留まっていたな。
夕日が綺麗に見える場所だから、一人で考え事したいときにはぴったりの場所なんだぜ。
それから、それから。
…俺が今思ったような詳細は、何ひとつ描いていない。
だけど…よく地上のデコイを観察していた彼女には、デコイたちにとってどこが心に残る地なのか、
分かっていたに違いない。極めて簡略化された絵に記された最低限の地形の、
そのどれにも…思い出深くない場所なんか無かった。
・・・それとも。かつてのエンテと違って地上を歩くことを許されていたアリアは、
それらの場所を実際にこっそり歩いてみたことがあるのかもしれない。
波線と渦で示された海洋に、結界は無い。
そのかわりそこには、美しい曲線を描く七つの線。
「虹だね」
ロックが指差しながら、嬉しそうに言う。
「アリアがこの島に最初に来た時…まだ結界で覆われる前。この島で虹を見たんだってさ。
あまりに綺麗で、思わずメモリーに永久保存してしまったとか…言ってた」
俺は片手を伸ばして絵に触れた。
ぎしぎしときしる音がして、巨大な扉は内側に開いてゆく。
扉が開ききった瞬間、俺とロックはなんとなく沈黙した。
うまく言い表せないのが歯がゆいけれど、…それは予感、のようなもので胸がいっぱいになったからだ。
いい予感と悪い予感が同時に渦潮になって痛いくらいに胸のうちを締め付ける。
最終章~嵐の前
扉の向こうは暗闇に沈んでいた。
指を伸ばせばその指先から闇に染まりそうな静かな獰猛さを感じた気がして、俺は思わ
ず鳥肌を立てた。
そこは、長い間幽閉されていた者の締め殺されるような苛立ちと怒りに満ちているよう
な、そんな錯覚を覚えさせる。
いや、錯覚なんかじゃない。これは俺が・・・リーバードだったころ、この暗闇に抱いた
想いだ。
再沸騰してきた黒い泥のようなそれに、胸が焼けそうになる。
(懐かしくて、それなのにに恐い。じっとしていたらここに満ちる感情に染め直されてしまうかも…)
はは、バカな。思い過ごし。大丈夫だ。俺は頭を振って嫌な気持ちを追い払う。
俺とロックは慎重に、でも大胆に足を踏み出した。
数歩進むと、ばたん。と背後で扉が閉まり、俺たちは目をふさがれたような暗闇に閉じ込められた。
そういえば、遺跡の内部の扉は全て自動扉。開き方もスムーズだったのに、
ここだけ前時代がかった両開きの扉とは。あらためて考えると不思議な気がした。
これもアリアの趣味だろうか。
ふぅっと周りの気温が一段下がったような感じがする。肌に当たる空気が冷たい。
前髪の一本一本にまで神経が通ってしまったんじゃないかと思うくらいに、
俺はぴりぴりと緊張していた。
必死にエンテだったころの記憶を呼び覚ます。
・・・そうだ。明かりがあったなら右へ行く通路と左へ行く通路が目の前に伸びているはずだ。
通路の高さは20メートルほど。幅もかなりある。エンテが思う存分暴れられるためだ。
「赤は紅蓮。逆巻く炎・・・・か」
呟きながら、ロックがガチャリと特殊武器を切り替える音がした。
「ロールちゃん、リーバード反応は?」
無線の電源を示す小さな赤いランプにわずか照らし出されたロックが、前方の闇を見据えたまま言った。
すぐに暗闇に無線のランプが緑に灯り、音が鳴る。
『今のところないみたい。だけど、充分注意して!…必ず、隠れてるはず…』
緊張しているんだな。ロールの声はいくぶん低く聞こえた。
混じる雑音の合間にカタカタとキーを叩く音がする。
あのテーブルの上にあった機械類のどれかをロールが操作しているんだろう。
『グランド、なにかガードがあるみたいでマップが表示されないわ。中の様子を教えてくれる?』
俺は一歩右のほうの通路へ進み出、無言で頷いた。目の前の暗闇をにらみながら。
「この通路は先へ行くほどだんだん下っている。
下りきるとゆるやかな右カーブを描いてまたこの位置まで上り、俺たちの少し後方で×字に交差。
そして、通路はまた相似形を描く。・・・つまり、ここは∞の記号の形をした通路なんだ。
明かりは一切無く。戦いにくく、逃げられない。
あいつを倒さない限り、俺達はどこへも行けない」
ひゅ、と隣で息を飲む音がした。
「いくら何でもまっ暗闇だなんて・・・。どうやって戦えば良いのか・・・」
ロックが戸惑っている。そりゃそうだ。目隠しして戦えって言われたようなものだぜ?
そういえばエンテだったときはこの闇に不自由をした覚えはない。
…どうしてだっけ。よく思い出せない。
「うん、だからロールにナビを頼むよ。精密なリーバード反応の位置を」
『・・・わたし?わかった、任せて!』
綱渡りの戦いになる。誰も無傷で帰れない戦いに!
だけど、ロックならやるだろう。
あの二体のシャルクルスをいちどに葬り去った戦闘センスを、俺は忘れてない。
決意と共に握りしめた拳が少し熱かった。
「止まっててもしょうがない。歩こう」
「うん」
俺とロックは、できるだけ足音を殺しながら右手の通路を歩き始めた。
全身がびりびりするほど周囲に気を配り、暗闇を進む。もう、どこから襲ってきてもおかしくないんだ。
気をつけるに越したことはない。
(・・・・・!?)
なんだ?殺気!!?
俺はいきなり刺し貫くような殺意を感じて立ち止まる。
瞬間、暗闇に真珠の粒を並べたような光列が走った。
悪寒を感じる間もなく、俺は隣りに立っていたロックの襟首を捕まえて引きずり倒す。
「うわっ!?」
なすすべも無く、ロックがひっくり返った。
その鼻先わずか1センチを鋭く何かが通り過ぎていった。
ひゅっとその動きに引き込まれた空気が動いた。覚えがある。憶えてる!!
「気をつけろ!エンテの攻撃自在突起だ。射程は最大で約10m、繰り出す時に音はしない!」
引き倒されたロックは速やかに床を転がって立ち上がり、油断無く特殊武器を構えた。
さすがはロック。と言いたいところだけど、エンテはすでに用心深く射程から逃れ去ってしまっている。
リーバード反応を捕らえることができない、ギリギリの外に退避したはずだ。
『そんなのどうやって避けるの!?』
無線がロールの悲鳴をあげる。
「勘だよ!」
『そんな!勘なんて当てにしないでよ!
・・・・・グランド、渡したバッグの中にボールが何個かあるよね?』
まいったね。俺は暗闇の中で思わず首をかしげてしまった。
勘ていうか、鋭敏な感覚・・・第六感みたいなものは
ディグアウターに限らず弓漁師にも欠かせない能力なんだけど、それを『そんな』って言われたら
…どう反応して良いんだろう。
ああそうだ、ボール?いつの間に!
俺はあらためて特殊武器を入れてきたバックパックを探る。
オレンジくらいの大きさのボールが3つ出てきた。自分の手の先さえ見えないまったくの暗闇なので、
色も何もわからないが、これって…?
『あった?それをエンテにぶつけるの!中は蛍光塗料だから、きっと暗闇で目印になるわ!』
(・・・・・・蛍光?)
俺とロックは気配で視線を交わしあった。
「…ロールちゃん」
ロックが低い声を出した。
それから、ロックと俺は二人同時に叫んでいた。
『意味無いよそれ!』
ザギャッ!
エンテの攻撃突起が足元に突き刺さるのを無難に飛び越えて、俺は付け足した。
「ロール、蛍光ってのは反射するべき光がないと光らないんだ!」
5メートルほど離れた上空からロックの声が降る。
「うん。…ここ、なんの光も無いんだよ。自分の前髪だって見えないくらいなんだ」
スタン、と着地する音がして、ロックは暗闇を薙ぐ刃物めいたエンテの攻撃を鮮やかによけてゆく。
闇の中、複雑に響くロックのシューズの音。
目標を外し、床や壁を薙ぐエンテの攻撃突起が金に銀に火花を散らす。
俺は深く呼吸して、全身を神経の塊みたいにして気配を感じようと努力した。
空気の流れを読むんだ。エンテはあの巨体。動けば必ず空気も動く!
読みきれないことは無いはずだ。・・・読めなきゃ、死ぬだけだ。
『ロック…、グランド…。無理しないで。 必ず帰ってきて』
空中半ひねりをしてエンテの攻撃をかわしている最中に、腰の無線がそうつぶやいた。
「大丈夫。そのために俺がいる。あいつは昔の俺だ。戦いのくせなんか、全部知ってるんだ!」
タン。と地面に着地してから、俺は目立たないように、
エンテの気を引かないていどにささやいて答えた。
この言葉が…どれだけ虚しいもんかってのは…
言ってる俺が一番良くわかってる。戦いに絶対なんてないんだ。
だけど言わなければならない言葉、その瞬間っていうのがある。
俺は俺にできるせいいっぱいの言葉を言ったつもりだった。…だけど。
無線は沈黙したっきりだ。とても安心させてあげられたとは思えない。ああ、俺って不器用だよな。
女の子ひとり安心させることもできやしないとは。…しかたないか。彼女もいないし。
「待ってて、ロールちゃん。いつもみたいに」
どこか離れた所からロックの声がした。明るく、笑っているような気配だ。
声は続く。楽しげに。
「僕はいつもみたいに帰ってくる!」
『うん。…うん!わかった。ゴメン、弱気になっちゃってたみたい。
帰ったら、いつかみたいにイチゴのパイ作ってあげるから。一緒に食べよ!』
無線の声は、嬉しさにひと跳ねしたみたいに聞こえた。
俺は思わず舌打ちして苦笑い。
ディグアウターとサポートっていう慣れた関係だって部分を割り引いたって、これは…。
ロック…器用な奴め。
最終章~嵐へ
「さて、反撃…っていきたいけど、攻撃はロック。あんたにまかす!」
「えっ!?」
通路いっぱいを使って回転突進攻撃をしてきたエンテの上を、俺はジャンプで飛び越しながらそう叫んだ。
体の幅ぎりぎりを刃物状になったエンテの攻撃突起が通過していく。
対してロックの声は予想もつかない方向から聞えた。床の極めて低い方…そのあたりから声がする。
ってことは、理由はひとつしかない。
ロックは高速回転するエンテの太い胴体の間を潜り抜けているんだ。
何も見えない暗闇だってのに、なんて身体感覚だろう。
俺は内心、あらためて感心した。
こうでなくっちゃいけない。こういう力こそがきっと、この島を開放してくれる。
ごくりと口中にわいてきた唾を飲み下して、俺は続けた。
「アリアはエンテに絶対に勝てない…さっき、あの壁画の部屋で俺は言ったよな」
「うん…」
ぶわあっと空気が大量に動いて、
二人にかすりもしなかったエンテの巨体が通路の先へ勢い良くふっ飛んでいった。
…体勢をあいつが立て直すまで、すこし時間が空く。ほんの数秒か。
その隙を逃さないように。俺は息を深く吸い込んだ。
「七色の攻撃手段を踏まずに、アリアがエンテに攻撃を加えようとした場合
…アリアの全関節は強制ロックされてしまう。
その機能は、リセットしても殺せなかった。今も動いている」
「なんだって!?」
ゴアアアアアアッ!
しなやかに首だけ俺たちを振り返ったエンテの口から吐かれた青白い炎が一瞬、暗闇を溶かした。
炎は予想以上に伸びて燃え上がり、その揺らめく舌が俺の間近まで伸びてきた。
あまりの熱に顔の産毛がちりちりと燃え、あわてて顔をかばった両腕に、びりっと痛みが走る。
しまった、火傷したか?
そのまま燃え出した袖のあたりを無理やり引きちぎって捨て、俺は通路を奥へ走りだした。
慌ててロックが追いついてくる。
「『赤は紅蓮。逆巻く炎・橙は広がりゆく熱。四散し猛る強き爆炎・・・』」
口の中で呪文のように唱えながら、
暗闇の中、ロックは俺にもわかるようにぽんと肩を叩いて言った。
「まかせて!」
俺は無言で頷く。それから。
「頼む。七色の攻撃の、青の部分からは俺がやる。
この雨の弓による攻撃が鍵になってるんだ。緑までの攻撃がすんでようやく、
俺は攻撃に参加できる…。 大丈夫、今度こそは、足を引っ張らない」
振り返ってみて、青白い炎の余炎の中答えたのはロックの、柔らかな笑顔だった。
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: