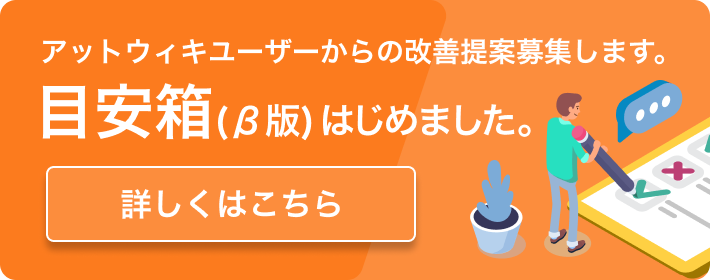最終章~星を映す海の藍
「グランドッ!!」
はっと気付くとエンテの鋭い牙が目前にあった。
しまった、思いにふけり過ぎたっ!
瞬間、鮮烈な青に煌めいた矢は一条の光線めいて超至近距離からエンテの身体を貫いた!
大きく開いた口蓋の鋭い牙がことごとく砕け散り、矢は喉の奥を突き破る。
生き物で言うなら延髄の部分を爆発するように貫いて、しかしなお勢いは止まらない。
青い光条は天井にぶち当たり、それを深々とえぐり抜いた。
轟音と共に、遺跡全体がごうっと揺れる音がした。…ような。
――矢を受けたなら…もう、エンテは終わり――
記憶の彼方、いつものカフェオレ色の肌色を紙のようにして、彼女は震える唇で言った。
哀しみと自己嫌悪に眉を曇らせていてなお、美しく。
――最初に定められた通りに。…そう。ヘヴンの誰かが決めたとおりに。エンテは炎を吐いて――
《藍は力。彼の放つ無類の技なり》
あちこちショートする火花の光を撒き散らしながら、エンテは壊れたあぎとをさらにぐあっと開いた。
青白い炎が・・・通常の炎の倍も温度の高い炎の息がどっと俺を襲い、肉も骨も残さず焼き尽くす
…はずだった。エンテが普通の状態だったなら。
延髄の傷からも炎をもらし、さらにそれだけで収まらず。
体のあちこちから青く燃える炎を上げて、エンテは最後の炎の息を吐きかけてきた。
空気が焦げて、熱風に俺の前髪がことごとく巻き上げられる。
顔面に痛いほどの温度がぶち当たる。俺は歯を食いしばって、それに耐えた。もう少しだ。
・・・・もう少し!
―――弓は、それを跳ね返すでしょう―――
俺が前に突き出した雨の弓からとたんに空色に輝く障壁が生まれ、
ドーム状に広がって俺と俺の後ろのロックを守った。
水面にぶつかって跳ね返る滝の水のようにエンテの炎がそこで遮断された。
目の前は藍色に輝く炎一色に塗りつぶされて、何が起きているのか俺には詳細を知る術はなかったけれど。
障壁のおかげで空気が波立つ音も聞こえない。この静寂の中で、
…なにか、胸の中心に鋭い悲しみが貫いた気がして俺は目を見開いた。
炎を見通すことはさすがの俺にもできない。だけど俺はそこに何かを見ようとした。
地響き。
そして、ふつっ。と炎の流れが止まった。
「・・・・エンテ」
弓を下ろすと障壁は自然に消えた。
いつのまにか、暗闇だった通路は薄い白光に照らされていた。
霧の立ち込める朝のような光加減で、見通しはあまりよくない。
見下ろすと、使い古して表面のけばだった俺のサンダルの先3センチからむこう、
障壁の外だった床はあまりの高熱に溶けて一部流れたようになっていた。まだ湯気も上がっている。
俺は腕を振って、なんとかまとわりつく湯気と匂いを振り払おうとした。
床材が溶け燃える臭いはエンテの体を覆っていた液体金属の匂いとあいまって、
あたりは思わずぐっと息詰まるような異臭に満ちていたんだ。
天井からは、溶けた壁材がぽたりぽたりと滴ってくる。湯気の向こうにごろりと転がっている、
溶け焦げた金属の塊のようなあれは…?あれがエンテか?
最終章~揺れる菫だけが朝を知る
《菫は粛清。天からの使者なる証をたてよ》
呆然と立ち止まっていた俺の左横を抜けて、ロックが引きずる足どりでエンテに近づいていった。
俺もあわてて重い足をしかりつけるようにして後を追う。
近づいて判った、エンテの惨状。
エンテは黒焦げた床に長く横たわり、その胴体と首は焼き切れて別々の場所にあった。
骨の白さをしていたその体に、今はもう白い所は見付からない。
俺とロックは無言で頭部に近寄る。下あごは粉砕されたのか何処にもなかった。
リーバードの瞳だけが赤く息づくようにわずか明滅しているだけ。
ロックが俺の顔を振り返り・・・俺は頷いた。
最後のひとつ。
『ロックマン』による直接攻撃が…エンテを完全に破壊する。
「エンテを見逃すってことは…できないのかな」
「・・・・」
俺は首を横に振った。それができたなら、よかったのに。
「『エンテを倒せるのは、アリア以外のロックマンが、定められた手順でエンテに攻撃を加えた時だけ』
…上位のロックマンが反乱を起こしたという可能性を想定して、エンテには安全策が組み込まれてる。
7つの手順のうち5つめまでこなしておきながらエンテにとどめが刺されないと、
エンテのメモリーは自動的にヘブンにバックアップされて、警戒警報が出される。
地上において反乱あり、…とね。
雨の弓における攻撃が当たった時点で、引き返せなくなってしまっているんだ。
そして、速やかにトドメが刺されない場合…エンテは自爆する。
データが盗まれないように、虹色のディフレクターを持ち去られないように。
なにより反乱者を殺すために。通路ももちろん開かないから、俺たちは死んでしまうな」
ロックが黙ってエンテの方に顔を戻した。後ろから見える濃茶の後ろ髪の向こうの頬が、ぴりっと震えた。
歯を食いしばったのかも…しれない。
――――メキッ。
リーバードの瞳に向けて振り下ろされたロックの拳が、やすやすとそれを砕いた。
飛び散った破片が周りに散って、澄んだガラスのような音を立てる。
さっと拳を引き抜いて、ロックはくるりとこちらを向いた。
疲れと、批判と悲しい色の篭もった目だった。
斜め下を向いて吐き捨てられた言葉は、今まで聴いたことも無いくらいかすれていた。
「まったく、誰だよ。こんな酷いプログラム書いたのは」
「・・・だから俺たちは背こうと決めたんだ。」
「!マスターは…」
俺は焼けて引きちぎったそでのあった場所と、火傷した腕を軽く押さえてただ言葉を続けた。
「俺もアリアも、マスターと言葉を交わしたこともない。だからどうとはいえないけれど」
ヘヴンを出るときにだけ、ちらっと見かけた…あの姿が脳裏をよぎる。
「俺はあの時見たマスターの瞳の色を信じている」
「・・・目の色?」
信じるに足る、理由だと思わないか?
俺は、その問いは口に出さず、ただ肩をすくめて笑いかけるだけにとどめておいた。
「グランドッ!!」
はっと気付くとエンテの鋭い牙が目前にあった。
しまった、思いにふけり過ぎたっ!
瞬間、鮮烈な青に煌めいた矢は一条の光線めいて超至近距離からエンテの身体を貫いた!
大きく開いた口蓋の鋭い牙がことごとく砕け散り、矢は喉の奥を突き破る。
生き物で言うなら延髄の部分を爆発するように貫いて、しかしなお勢いは止まらない。
青い光条は天井にぶち当たり、それを深々とえぐり抜いた。
轟音と共に、遺跡全体がごうっと揺れる音がした。…ような。
――矢を受けたなら…もう、エンテは終わり――
記憶の彼方、いつものカフェオレ色の肌色を紙のようにして、彼女は震える唇で言った。
哀しみと自己嫌悪に眉を曇らせていてなお、美しく。
――最初に定められた通りに。…そう。ヘヴンの誰かが決めたとおりに。エンテは炎を吐いて――
《藍は力。彼の放つ無類の技なり》
あちこちショートする火花の光を撒き散らしながら、エンテは壊れたあぎとをさらにぐあっと開いた。
青白い炎が・・・通常の炎の倍も温度の高い炎の息がどっと俺を襲い、肉も骨も残さず焼き尽くす
…はずだった。エンテが普通の状態だったなら。
延髄の傷からも炎をもらし、さらにそれだけで収まらず。
体のあちこちから青く燃える炎を上げて、エンテは最後の炎の息を吐きかけてきた。
空気が焦げて、熱風に俺の前髪がことごとく巻き上げられる。
顔面に痛いほどの温度がぶち当たる。俺は歯を食いしばって、それに耐えた。もう少しだ。
・・・・もう少し!
―――弓は、それを跳ね返すでしょう―――
俺が前に突き出した雨の弓からとたんに空色に輝く障壁が生まれ、
ドーム状に広がって俺と俺の後ろのロックを守った。
水面にぶつかって跳ね返る滝の水のようにエンテの炎がそこで遮断された。
目の前は藍色に輝く炎一色に塗りつぶされて、何が起きているのか俺には詳細を知る術はなかったけれど。
障壁のおかげで空気が波立つ音も聞こえない。この静寂の中で、
…なにか、胸の中心に鋭い悲しみが貫いた気がして俺は目を見開いた。
炎を見通すことはさすがの俺にもできない。だけど俺はそこに何かを見ようとした。
地響き。
そして、ふつっ。と炎の流れが止まった。
「・・・・エンテ」
弓を下ろすと障壁は自然に消えた。
いつのまにか、暗闇だった通路は薄い白光に照らされていた。
霧の立ち込める朝のような光加減で、見通しはあまりよくない。
見下ろすと、使い古して表面のけばだった俺のサンダルの先3センチからむこう、
障壁の外だった床はあまりの高熱に溶けて一部流れたようになっていた。まだ湯気も上がっている。
俺は腕を振って、なんとかまとわりつく湯気と匂いを振り払おうとした。
床材が溶け燃える臭いはエンテの体を覆っていた液体金属の匂いとあいまって、
あたりは思わずぐっと息詰まるような異臭に満ちていたんだ。
天井からは、溶けた壁材がぽたりぽたりと滴ってくる。湯気の向こうにごろりと転がっている、
溶け焦げた金属の塊のようなあれは…?あれがエンテか?
最終章~揺れる菫だけが朝を知る
《菫は粛清。天からの使者なる証をたてよ》
呆然と立ち止まっていた俺の左横を抜けて、ロックが引きずる足どりでエンテに近づいていった。
俺もあわてて重い足をしかりつけるようにして後を追う。
近づいて判った、エンテの惨状。
エンテは黒焦げた床に長く横たわり、その胴体と首は焼き切れて別々の場所にあった。
骨の白さをしていたその体に、今はもう白い所は見付からない。
俺とロックは無言で頭部に近寄る。下あごは粉砕されたのか何処にもなかった。
リーバードの瞳だけが赤く息づくようにわずか明滅しているだけ。
ロックが俺の顔を振り返り・・・俺は頷いた。
最後のひとつ。
『ロックマン』による直接攻撃が…エンテを完全に破壊する。
「エンテを見逃すってことは…できないのかな」
「・・・・」
俺は首を横に振った。それができたなら、よかったのに。
「『エンテを倒せるのは、アリア以外のロックマンが、定められた手順でエンテに攻撃を加えた時だけ』
…上位のロックマンが反乱を起こしたという可能性を想定して、エンテには安全策が組み込まれてる。
7つの手順のうち5つめまでこなしておきながらエンテにとどめが刺されないと、
エンテのメモリーは自動的にヘブンにバックアップされて、警戒警報が出される。
地上において反乱あり、…とね。
雨の弓における攻撃が当たった時点で、引き返せなくなってしまっているんだ。
そして、速やかにトドメが刺されない場合…エンテは自爆する。
データが盗まれないように、虹色のディフレクターを持ち去られないように。
なにより反乱者を殺すために。通路ももちろん開かないから、俺たちは死んでしまうな」
ロックが黙ってエンテの方に顔を戻した。後ろから見える濃茶の後ろ髪の向こうの頬が、ぴりっと震えた。
歯を食いしばったのかも…しれない。
――――メキッ。
リーバードの瞳に向けて振り下ろされたロックの拳が、やすやすとそれを砕いた。
飛び散った破片が周りに散って、澄んだガラスのような音を立てる。
さっと拳を引き抜いて、ロックはくるりとこちらを向いた。
疲れと、批判と悲しい色の篭もった目だった。
斜め下を向いて吐き捨てられた言葉は、今まで聴いたことも無いくらいかすれていた。
「まったく、誰だよ。こんな酷いプログラム書いたのは」
「・・・だから俺たちは背こうと決めたんだ。」
「!マスターは…」
俺は焼けて引きちぎったそでのあった場所と、火傷した腕を軽く押さえてただ言葉を続けた。
「俺もアリアも、マスターと言葉を交わしたこともない。だからどうとはいえないけれど」
ヘヴンを出るときにだけ、ちらっと見かけた…あの姿が脳裏をよぎる。
「俺はあの時見たマスターの瞳の色を信じている」
「・・・目の色?」
信じるに足る、理由だと思わないか?
俺は、その問いは口に出さず、ただ肩をすくめて笑いかけるだけにとどめておいた。