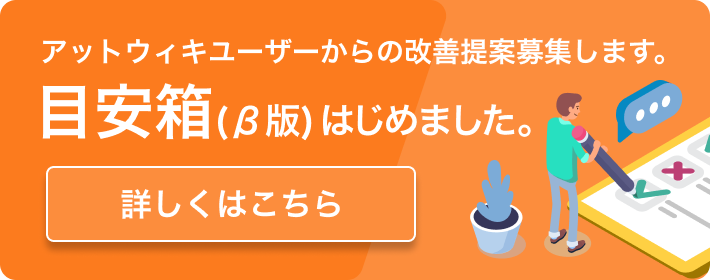V.S.タイダル・マッコイーン①
アメリカ合衆国・メキシコ湾────
かつて、多くの生物で賑わったこの海も、過去の幾度にも渡る大戦の影響を受け、
もはや見る影もない死の海と化してしまった───完全にではないが、
そう言っても差し支えはない。
太古の昔から体を進化させずに生きてきた海のギャング、サメ類でさえも今や
希少動物と成り下がり、その頭数が毎年減り続けている。
とはいえ、全く生き物がいない訳ではない。だから、そうした希少動物を狙う密猟者も
後を絶たないはずがなかった。
通常、こういった密猟者はレプリシーフォース(レプリフォース海軍)が取締りを
行っているはずだが────このメキシコ湾だけは例外だった。
何せ、この海には彼らなど必要としない守護神が存在していたからだ。
タイダル・マッコイーン───州立メキシコ湾海底博物館の館長であり、
何よりこの海を人一倍愛する男。さすがに彼だけではこの海を守るには広すぎるので、
大半はメカニロイド潜水艦「デスエベンジ」がその任に就いている。
密猟者の逮捕や海の監視以外にも、海洋生物の生態系のデータ収集なども目的の一つだ。
もっとも、滅びゆくこの海にとって、その行為は無意味に等しかったが。
だが、守護神であるマッコイーン自身は海の復興を諦めようとはしなかった。
その強い思いが逆に他人にとっては迷惑以外の何物でもないと受け取られ、
レプリシーフォースや地元漁民とはイザコザが絶えることはなかったらしい。
まあ、要するに───そういったレプリロイドであった。
だが、数日前の∑ウィルスの拡散の被害が、無論この海にのみ及んでいないはずが
なかった。既にデスエベンジは乗組員を乗せたまま暴走し、この海への侵入者を
無差別に破壊する──ただのイレギュラーと成り下がっていた。
終わりである────守護神が破壊神に凶変してしまったこの海に、
希望の未来など微塵もあったものではない。
ならば、ひと思いにその命の灯火を消してやることが、
せめてもの供養であろう──ゼロはそう考えていた。
彼に与えられた任務はただ一つ。この海に蔓延る(はびこる)全イレギュラーの排除。
アメリカ合衆国・メキシコ湾────
かつて、多くの生物で賑わったこの海も、過去の幾度にも渡る大戦の影響を受け、
もはや見る影もない死の海と化してしまった───完全にではないが、
そう言っても差し支えはない。
太古の昔から体を進化させずに生きてきた海のギャング、サメ類でさえも今や
希少動物と成り下がり、その頭数が毎年減り続けている。
とはいえ、全く生き物がいない訳ではない。だから、そうした希少動物を狙う密猟者も
後を絶たないはずがなかった。
通常、こういった密猟者はレプリシーフォース(レプリフォース海軍)が取締りを
行っているはずだが────このメキシコ湾だけは例外だった。
何せ、この海には彼らなど必要としない守護神が存在していたからだ。
タイダル・マッコイーン───州立メキシコ湾海底博物館の館長であり、
何よりこの海を人一倍愛する男。さすがに彼だけではこの海を守るには広すぎるので、
大半はメカニロイド潜水艦「デスエベンジ」がその任に就いている。
密猟者の逮捕や海の監視以外にも、海洋生物の生態系のデータ収集なども目的の一つだ。
もっとも、滅びゆくこの海にとって、その行為は無意味に等しかったが。
だが、守護神であるマッコイーン自身は海の復興を諦めようとはしなかった。
その強い思いが逆に他人にとっては迷惑以外の何物でもないと受け取られ、
レプリシーフォースや地元漁民とはイザコザが絶えることはなかったらしい。
まあ、要するに───そういったレプリロイドであった。
だが、数日前の∑ウィルスの拡散の被害が、無論この海にのみ及んでいないはずが
なかった。既にデスエベンジは乗組員を乗せたまま暴走し、この海への侵入者を
無差別に破壊する──ただのイレギュラーと成り下がっていた。
終わりである────守護神が破壊神に凶変してしまったこの海に、
希望の未来など微塵もあったものではない。
ならば、ひと思いにその命の灯火を消してやることが、
せめてもの供養であろう──ゼロはそう考えていた。
彼に与えられた任務はただ一つ。この海に蔓延る(はびこる)全イレギュラーの排除。
V.S.タイダル・マッコイーン②
エニグマの発射時に燃料となる大量の水素を最も手近に入手できるのは、この海である。
近いだけなら五大湖でもいいが、何しろ絶対的な水素の量が足りない。
やはり海が一番適しているのだが、その辺の海からだと急激な水質の変化に耐えられず
大量の生物が死滅してしまう可能性が高いのだ。
という訳で、生物が最も少なく滅びかけているこのメキシコ湾を、
いわゆる『生け贄』にするのがハンター本部の意図なのだが───当然、守護神は
この海が滅びるのを黙ってみていることなどできないだろう。
デスエベンジの暴走はむしろ彼にとって好都合だったかもしれない。
勝手にこの海を守っていてくれるのだから。
(じゃあ・・・・奴が直接出て来ないのはどうしてだ?かつてないこの海の
危機だというのに・・・・)
ゼロにはただ、それだけが気がかりだった。
レプリシーフォースと言い争うことができる肝の太い精神の持ち主である
マッコイーンが、今回の沙汰で自らが直々に海の防衛に当たらないはずがないのだ。
(こちらから会って確かめるしかないか・・・・)
覚悟を決めて────ゼロはゼットセイバーを横薙ぎに一閃した。
薙ぎ払われた装甲が剥がれていずこかの海中へと漂流していく。
瞬間、自分の後方に溜まっていた空気が無数の気泡となって前へと押し出される。
その流れに乗るようにして、ゼロとその後ろに続く救助したデスエベンジの乗組員が、
デスエベンジの外──海中へと脱出した。
彼らの目の前にあるのは、蒼く澄み切った海ではない。過去の大戦及び人類の
度重なる環境汚染によって汚された、心持ち淀んだ海である。
濁って煤けた黒───とでも言えば良いだろうか。
とにかくそんなあまり心地の良くない海の水をかき分けながら、
「急げ!こっちだ!」
海中用ではないため水圧に苦しんでいる乗組員達を力の限り叫んで、ゼロは誘導する。
もがいている彼らが声を耳にすると、必死の思いで指示された方向へと逃れて行った。
ひとしきり見終えてから、ゼロは先程まで自分達が乗り込んでいた
潜水艦──デスエベンジへと向き直った。
「おっと。お前の相手はあいつらじゃない。この俺だ」
チャキ、と剣先をデスエベンジの眉間らしき部分に突きつける。
続けてゼロは不敵な笑みを浮かべて言い放つ。
「さあ、マッコイーンの意図を洗いざらい喋ってもらおうか!!」
威勢の良い掛け声と共に彼は前転しつつサーベルで円を形作って、目の前の
メカニロイド潜水艦へと突撃して行った。
「三日月ざぁぁあああああああんっ!」
エニグマの発射時に燃料となる大量の水素を最も手近に入手できるのは、この海である。
近いだけなら五大湖でもいいが、何しろ絶対的な水素の量が足りない。
やはり海が一番適しているのだが、その辺の海からだと急激な水質の変化に耐えられず
大量の生物が死滅してしまう可能性が高いのだ。
という訳で、生物が最も少なく滅びかけているこのメキシコ湾を、
いわゆる『生け贄』にするのがハンター本部の意図なのだが───当然、守護神は
この海が滅びるのを黙ってみていることなどできないだろう。
デスエベンジの暴走はむしろ彼にとって好都合だったかもしれない。
勝手にこの海を守っていてくれるのだから。
(じゃあ・・・・奴が直接出て来ないのはどうしてだ?かつてないこの海の
危機だというのに・・・・)
ゼロにはただ、それだけが気がかりだった。
レプリシーフォースと言い争うことができる肝の太い精神の持ち主である
マッコイーンが、今回の沙汰で自らが直々に海の防衛に当たらないはずがないのだ。
(こちらから会って確かめるしかないか・・・・)
覚悟を決めて────ゼロはゼットセイバーを横薙ぎに一閃した。
薙ぎ払われた装甲が剥がれていずこかの海中へと漂流していく。
瞬間、自分の後方に溜まっていた空気が無数の気泡となって前へと押し出される。
その流れに乗るようにして、ゼロとその後ろに続く救助したデスエベンジの乗組員が、
デスエベンジの外──海中へと脱出した。
彼らの目の前にあるのは、蒼く澄み切った海ではない。過去の大戦及び人類の
度重なる環境汚染によって汚された、心持ち淀んだ海である。
濁って煤けた黒───とでも言えば良いだろうか。
とにかくそんなあまり心地の良くない海の水をかき分けながら、
「急げ!こっちだ!」
海中用ではないため水圧に苦しんでいる乗組員達を力の限り叫んで、ゼロは誘導する。
もがいている彼らが声を耳にすると、必死の思いで指示された方向へと逃れて行った。
ひとしきり見終えてから、ゼロは先程まで自分達が乗り込んでいた
潜水艦──デスエベンジへと向き直った。
「おっと。お前の相手はあいつらじゃない。この俺だ」
チャキ、と剣先をデスエベンジの眉間らしき部分に突きつける。
続けてゼロは不敵な笑みを浮かべて言い放つ。
「さあ、マッコイーンの意図を洗いざらい喋ってもらおうか!!」
威勢の良い掛け声と共に彼は前転しつつサーベルで円を形作って、目の前の
メカニロイド潜水艦へと突撃して行った。
「三日月ざぁぁあああああああんっ!」
V.S.タイダル・マッコイーン③
海底博物館の外で──自分の庭と言っても過言ではないメキシコ湾で鈍く無駄なまでに
大きな音と振動が響いたのを体で感じて、彼、タイダル・マッコイーンは私室で
耐水ガラスの窓の向こうを見やった。海の底であるせいか、光はあまり届かず、
何もかもがぼんやりとしてしか見えない。
だが、さっきの音と振動の原因ははっきりとまでに分かった。10数メートル先に、
不気味に輝くデスエベンジの瞳が見えたからである。どうやら破壊されているらしく、
墜落した位置から微動だにせず、明滅を繰り返すアイカメラが
命がもはや風前の灯火であることを示していた。
しかし、彼は微塵も動揺してはいなかった。もはや、そんな気力も
残っていなかったからだ。それは彼が∑ウィルスに冒されていたからではない。
ただ一つの迷いが彼を支配していたからである。
「守護神・・・・か。ワシに果たして、そんな資格があるのか・・・・・?」
自問する。守護神と言うのは、いわゆるあだ名と言う奴である。
この海を愛し、慈しんで来た彼にとって、密猟者の捕縛や生態系のと言うのは
義務同然だった。それが返って他者からは横暴と受け取られ、いつの間にやら
嫌味の意味を含めた形で『守護神』などと
言われていったのだ。彼にとって、この名前は名誉ではなく、むしろ迷惑でしか
なかったのだが──その守護神たる理由とは正反対の行動を取って見れば──意図的に
そうした訳ではないが──、自ずと後悔の念は積もるものである。
後悔と言うのは説明するまでもなく、∑ウィルスの大拡散によってデスエベンジの
暴走を引き起こしてしまったことである。
全ては自分の管理責任の無さが、このような事態を勃発させる引き金となったのである。
その本来の目的を見失ったデスエベンジは、今や密猟者に対する海の「牙」として
ではなく、ただの無差別破壊マシーンと化してしまった。これでは今まで相手に
してきたレプリフォース、地元漁民、いやそれ以上に、この海に住む全生命に
申し訳が立たない。
「おお・・・海よ・・・このワシの犯した罪を許してくれ・・・」
今にも泣き崩れそうな表情でマッコイーンは悔やんだ。己の、その罪を。
と────
「許すも、許さないもない。進むべき道を決めるのは、お前自身だ」
まるで全てを悟ったかのような声が響くと同時、私室のドアがXの字に切り裂かれ、
蹴り倒された。そこから進み出てくるのは紛れもなく、かつての友──ゼロの
その姿だった。
海底博物館の外で──自分の庭と言っても過言ではないメキシコ湾で鈍く無駄なまでに
大きな音と振動が響いたのを体で感じて、彼、タイダル・マッコイーンは私室で
耐水ガラスの窓の向こうを見やった。海の底であるせいか、光はあまり届かず、
何もかもがぼんやりとしてしか見えない。
だが、さっきの音と振動の原因ははっきりとまでに分かった。10数メートル先に、
不気味に輝くデスエベンジの瞳が見えたからである。どうやら破壊されているらしく、
墜落した位置から微動だにせず、明滅を繰り返すアイカメラが
命がもはや風前の灯火であることを示していた。
しかし、彼は微塵も動揺してはいなかった。もはや、そんな気力も
残っていなかったからだ。それは彼が∑ウィルスに冒されていたからではない。
ただ一つの迷いが彼を支配していたからである。
「守護神・・・・か。ワシに果たして、そんな資格があるのか・・・・・?」
自問する。守護神と言うのは、いわゆるあだ名と言う奴である。
この海を愛し、慈しんで来た彼にとって、密猟者の捕縛や生態系のと言うのは
義務同然だった。それが返って他者からは横暴と受け取られ、いつの間にやら
嫌味の意味を含めた形で『守護神』などと
言われていったのだ。彼にとって、この名前は名誉ではなく、むしろ迷惑でしか
なかったのだが──その守護神たる理由とは正反対の行動を取って見れば──意図的に
そうした訳ではないが──、自ずと後悔の念は積もるものである。
後悔と言うのは説明するまでもなく、∑ウィルスの大拡散によってデスエベンジの
暴走を引き起こしてしまったことである。
全ては自分の管理責任の無さが、このような事態を勃発させる引き金となったのである。
その本来の目的を見失ったデスエベンジは、今や密猟者に対する海の「牙」として
ではなく、ただの無差別破壊マシーンと化してしまった。これでは今まで相手に
してきたレプリフォース、地元漁民、いやそれ以上に、この海に住む全生命に
申し訳が立たない。
「おお・・・海よ・・・このワシの犯した罪を許してくれ・・・」
今にも泣き崩れそうな表情でマッコイーンは悔やんだ。己の、その罪を。
と────
「許すも、許さないもない。進むべき道を決めるのは、お前自身だ」
まるで全てを悟ったかのような声が響くと同時、私室のドアがXの字に切り裂かれ、
蹴り倒された。そこから進み出てくるのは紛れもなく、かつての友──ゼロの
その姿だった。
V.S.タイダル・マッコイーン④
「ゼロ・・・何故ここに?」
きょとんとした表情で、マッコイーンが聞き返す。対してゼロは、
聞くまでもないだろうが、という不満の溜まった目つきを向け、への字に曲げた口を
開ける。
「お前がどういうつもりなのかを知りたかっただけだ。デスエベンジを放り出して、
お前は何をしてるのか・・・・それを、知りたかったんだよ」
そう言うゼロの瞳の色は疑問のそれとは異なっていた。
もっと邪な感情──言うなれば、侮蔑と言ったところだろうか。
不機嫌さを丸出しにしたまま、彼はマッコイーンの元へとつかつか歩み寄る。
ゼロは勢いに任せて左手を振り上げると、そのままマッコイーンの胸倉を掴み上げた。
「分からないんだよ・・・お前の考えてることが!一体何なんだよ、この行為は・・・
デスエベンジを暴走させてこの海を守ろうと思ったのか?それともこの海を守れる
自信が失せたのか?何でこんな所に引きこもって何もしてないんだよ、お前は!!」
今までの鬱憤を晴らすが如く、ゼロは怒鳴りつけた。無論苛立ちの原因は
マッコイーンの矛盾した行動にある。普段は冷静なゼロが、この時ばかりは我を失って
怒りに身を任せている──この男にもそんな感情的な一面があるのか、と
マッコイーンは軽い驚愕を覚えていた。
「お前はそんな優柔不断な男だったのかよ、ええ!?以前俺に言ったよな・・・
男気(おとこぎ)を示してみろ、とな!!その頃のお前はどこに行ったんだよ・・・・
これじゃ俺が腑抜けに励まされた
情けない奴みたいじゃないか・・・」
ゼロの左手が震える。怒りによってではない──悲しみ、哀れみ、
そういった気持ちからである。
ゼロが相手を気遣うなんて、まるで雨でも降りそうだ──そんな愚にもつかない考えを
巡らせ、マッコイーンはただただ感銘を受けて硬直していることしかできなかった。
ゼロの発言の中にあった『男気』──男性の気迫や決断力の強さを示す言葉である。
時代錯誤の格言臭い言葉ではあったが──海の男であるマッコイーンは、
その根性からか、そんな古めかしい言葉が好きだった。
以前、着々と成功を収めるエックスに対して、昔と何も変わっちゃいない自分に
劣等感を覚えたと、ゼロが相談しに来た時があった。
その時に、マッコイーンはこう喋ったのである。
「お前の男気を皆に示してみろ──それだけで、お前の悩みは消え去る」
後にマッコイーンは、美青年であるお前には似つかない言葉だったかな、とだけ
訂正した。その時は「ムサ苦しそうな言葉だな」と思いつつも、ゼロはその
男気とやらを実行に移してみた。
すると、どうだ──皆の自分を見る目が驚くほどに変化したではないか。
心なしか、自分の実力も多少上がったような気がする。挙句には『鬼神』と
呼ばれるまでに自分の功績は向上していた。
特にエックスに至っては、
「今までの君は生きる希望を無くした抜け殻みたいだったけど・・・・今は違う。
瞳が生き生きしているよ」
とまでに。密かにゼロはこの瞬間に喜びを覚えていた。
「ゼロ・・・何故ここに?」
きょとんとした表情で、マッコイーンが聞き返す。対してゼロは、
聞くまでもないだろうが、という不満の溜まった目つきを向け、への字に曲げた口を
開ける。
「お前がどういうつもりなのかを知りたかっただけだ。デスエベンジを放り出して、
お前は何をしてるのか・・・・それを、知りたかったんだよ」
そう言うゼロの瞳の色は疑問のそれとは異なっていた。
もっと邪な感情──言うなれば、侮蔑と言ったところだろうか。
不機嫌さを丸出しにしたまま、彼はマッコイーンの元へとつかつか歩み寄る。
ゼロは勢いに任せて左手を振り上げると、そのままマッコイーンの胸倉を掴み上げた。
「分からないんだよ・・・お前の考えてることが!一体何なんだよ、この行為は・・・
デスエベンジを暴走させてこの海を守ろうと思ったのか?それともこの海を守れる
自信が失せたのか?何でこんな所に引きこもって何もしてないんだよ、お前は!!」
今までの鬱憤を晴らすが如く、ゼロは怒鳴りつけた。無論苛立ちの原因は
マッコイーンの矛盾した行動にある。普段は冷静なゼロが、この時ばかりは我を失って
怒りに身を任せている──この男にもそんな感情的な一面があるのか、と
マッコイーンは軽い驚愕を覚えていた。
「お前はそんな優柔不断な男だったのかよ、ええ!?以前俺に言ったよな・・・
男気(おとこぎ)を示してみろ、とな!!その頃のお前はどこに行ったんだよ・・・・
これじゃ俺が腑抜けに励まされた
情けない奴みたいじゃないか・・・」
ゼロの左手が震える。怒りによってではない──悲しみ、哀れみ、
そういった気持ちからである。
ゼロが相手を気遣うなんて、まるで雨でも降りそうだ──そんな愚にもつかない考えを
巡らせ、マッコイーンはただただ感銘を受けて硬直していることしかできなかった。
ゼロの発言の中にあった『男気』──男性の気迫や決断力の強さを示す言葉である。
時代錯誤の格言臭い言葉ではあったが──海の男であるマッコイーンは、
その根性からか、そんな古めかしい言葉が好きだった。
以前、着々と成功を収めるエックスに対して、昔と何も変わっちゃいない自分に
劣等感を覚えたと、ゼロが相談しに来た時があった。
その時に、マッコイーンはこう喋ったのである。
「お前の男気を皆に示してみろ──それだけで、お前の悩みは消え去る」
後にマッコイーンは、美青年であるお前には似つかない言葉だったかな、とだけ
訂正した。その時は「ムサ苦しそうな言葉だな」と思いつつも、ゼロはその
男気とやらを実行に移してみた。
すると、どうだ──皆の自分を見る目が驚くほどに変化したではないか。
心なしか、自分の実力も多少上がったような気がする。挙句には『鬼神』と
呼ばれるまでに自分の功績は向上していた。
特にエックスに至っては、
「今までの君は生きる希望を無くした抜け殻みたいだったけど・・・・今は違う。
瞳が生き生きしているよ」
とまでに。密かにゼロはこの瞬間に喜びを覚えていた。
V.S.タイダル・マッコイーン⑤
ゼロにとって、マッコイーンは人生の恩師以外の何者でもなかったのだ。
その人物が絶望に打ちひしがれていれば、何とかして前の生命力溢れた人物へ戻して
あげたいと、ゼロはそう誓っていた。
不器用な男だが、ゼロにとってはこれが精一杯の激励なのである。
ようやくゼロの励ましに気づくと、マッコイーンの眼に希望の光が
灯り始めたようだった。
「・・・・人間、立ち直りと言うのは、
些細なことがきっかけになるモンじゃなあ・・・・」
「・・・?」
マッコイーンの焦点の合っていなかった瞳が再び交わる先には───ゼロの双眸が
あった。真摯な眼差しで見つめられ、今度はゼロがきょとんとしてしまったようだった。
すぐに状況を察したゼロは、
「・・・そうだな。俺の時もそうだった」
「男気・・・か。我ながら、良い言葉じゃな・・・・」
「ああ・・・俺達の男気に乾杯、ってところか・・・」
二人で苦笑する。いつの間にか胸を掴んでいた手を外して、
ゼロは大笑いを起こす───直前で、マッコイーンの声がそれを遮った。
「────だが、お互いに譲れないものがある。だから、ワシらは戦わねば
ならんのじゃろう?」
はっと、ゼロは瞬間的に飛び退いていた。マッコイーンの体が突如殺気を
帯びたものに急変したからである。
だが、全身から確かに殺気を放ちつつも、マッコイーンの口調は子供を諭すような
ものから変化してはいなかった。そして、その一種異様な雰囲気に、
ゼロも共感を覚えつつある。
「・・・ああ、そうだ。俺はアイリスとカーネルのようなレプリロイドを生み出さない
世界を造るために戦っている。そのためには───」
今までの好意的な表情を、一気にイレギュラーハンターとしての殺気に変える。
「──例え何を犠牲にしてでもやらねばならない。何かを成すには、何らかの
犠牲が付き物だからな・・・・」
最後の発言は言い訳に近かったが、事実ではあった。
奇麗事だけでは世の中は成り立ってはいかないのだから。
双方、心意気は十分。後は、引き金を引くだけだった。
「だが、本当にいいのか、マッコイーン・・・俺は、お前がこの海を守ることを
潔く諦めようと、文句は言わん。侮蔑も、侮辱もしない。それもまた、
男気の形の1つだと思って受け入れるつもりだ。
それでも、お前は戦うのか・・・・?」
今更何を、と思わせることを、口惜しげにゼロは喋った。
が、マッコイーンの返事はただ1つだけだった。
「何度も言わせるな・・・・ワシは、この海を何としてでも守る。お前さん同様、
どんな犠牲もいとわない・・・・・じゃが、心配するな。お前がワシを殺しても、
ワシはお前を恨んだりはしない・・・誰の中にも、譲れない『正義』が
あるのじゃから・・・・・」
表面上は穏やかなもので、その実深い意味を持たせた話を話す──マッコイーンの、
昔からの特徴だった。それに改めて驚きつつ、ゼロは右手を硬く握って、
拳全体を発光させた。
「・・・その意気や良し。それなら、俺もお前に最大の敬意を払って、
全力で相手をしよう・・・」
そして、その握り拳を床へと叩きつける!
「滅閃光ォォォォォッ!!」
刹那、爆裂四散する部屋の中を、爆発的に増殖した気泡が包み込んでいた。
ゼロにとって、マッコイーンは人生の恩師以外の何者でもなかったのだ。
その人物が絶望に打ちひしがれていれば、何とかして前の生命力溢れた人物へ戻して
あげたいと、ゼロはそう誓っていた。
不器用な男だが、ゼロにとってはこれが精一杯の激励なのである。
ようやくゼロの励ましに気づくと、マッコイーンの眼に希望の光が
灯り始めたようだった。
「・・・・人間、立ち直りと言うのは、
些細なことがきっかけになるモンじゃなあ・・・・」
「・・・?」
マッコイーンの焦点の合っていなかった瞳が再び交わる先には───ゼロの双眸が
あった。真摯な眼差しで見つめられ、今度はゼロがきょとんとしてしまったようだった。
すぐに状況を察したゼロは、
「・・・そうだな。俺の時もそうだった」
「男気・・・か。我ながら、良い言葉じゃな・・・・」
「ああ・・・俺達の男気に乾杯、ってところか・・・」
二人で苦笑する。いつの間にか胸を掴んでいた手を外して、
ゼロは大笑いを起こす───直前で、マッコイーンの声がそれを遮った。
「────だが、お互いに譲れないものがある。だから、ワシらは戦わねば
ならんのじゃろう?」
はっと、ゼロは瞬間的に飛び退いていた。マッコイーンの体が突如殺気を
帯びたものに急変したからである。
だが、全身から確かに殺気を放ちつつも、マッコイーンの口調は子供を諭すような
ものから変化してはいなかった。そして、その一種異様な雰囲気に、
ゼロも共感を覚えつつある。
「・・・ああ、そうだ。俺はアイリスとカーネルのようなレプリロイドを生み出さない
世界を造るために戦っている。そのためには───」
今までの好意的な表情を、一気にイレギュラーハンターとしての殺気に変える。
「──例え何を犠牲にしてでもやらねばならない。何かを成すには、何らかの
犠牲が付き物だからな・・・・」
最後の発言は言い訳に近かったが、事実ではあった。
奇麗事だけでは世の中は成り立ってはいかないのだから。
双方、心意気は十分。後は、引き金を引くだけだった。
「だが、本当にいいのか、マッコイーン・・・俺は、お前がこの海を守ることを
潔く諦めようと、文句は言わん。侮蔑も、侮辱もしない。それもまた、
男気の形の1つだと思って受け入れるつもりだ。
それでも、お前は戦うのか・・・・?」
今更何を、と思わせることを、口惜しげにゼロは喋った。
が、マッコイーンの返事はただ1つだけだった。
「何度も言わせるな・・・・ワシは、この海を何としてでも守る。お前さん同様、
どんな犠牲もいとわない・・・・・じゃが、心配するな。お前がワシを殺しても、
ワシはお前を恨んだりはしない・・・誰の中にも、譲れない『正義』が
あるのじゃから・・・・・」
表面上は穏やかなもので、その実深い意味を持たせた話を話す──マッコイーンの、
昔からの特徴だった。それに改めて驚きつつ、ゼロは右手を硬く握って、
拳全体を発光させた。
「・・・その意気や良し。それなら、俺もお前に最大の敬意を払って、
全力で相手をしよう・・・」
そして、その握り拳を床へと叩きつける!
「滅閃光ォォォォォッ!!」
刹那、爆裂四散する部屋の中を、爆発的に増殖した気泡が包み込んでいた。
V.S.タイダル・マッコイーン⑥
泡の霧がようやく晴れると、ゼロの周りには誰も存在していなかった──ぱっと見だが。
(奴は元々戦闘用ではない・・・・水中用ではあるが、俺より総合的な実力は下だ。
となると、奴は場の状態を最大限に利用して攻撃してくるはずだ。だが、
俺は奴の攻撃方法も、その回避方法も、何も知らない。
ここは一つ、相手の術中にハマってみるか・・・・・)
戦法を決め込むと、ゼロはゼットセイバーの刃を再び生やした。
通常、ビームサーベルと言うものは肉眼で見えることはない。だが陸上では空気中に
数え切れないほどの塵・ホコリが充満しているので、それがビーム部分について
燃焼することによって、初めて肉眼視できるようになるのだ。
ビームの色がそれぞれ違うのは、ビームの波長の違いによるものらしい。
しかし、ここは海中。塵・ホコリは皆無に等しい。その代わり、瞬間的にビームの
高温によって蒸発する水が泡となり、それがビームサーベルを包むので、
海中でもかろうじて見えるようになるのだ。
そのぼんやり可視できる光の刃を握り締めて、ゼロは覚悟を決めた目つきで
辺りを見回した。やはり攻撃の気配はない。まさか、あの爆発に紛れて
逃げたんじゃないだろうな、と邪推していると────背中に何かの圧力を感じた。
気付いて振り向くと、そこにはこちらへと真っ直ぐ向かう、無数の立方体の氷塊が
迫っていた。さっき背中に感じた圧力とは、この氷塊によって押し出された
水だったのだ。
「く・・・舐めるな!」
ゼットセイバーでその群れを必死に斬り刻み、自分への衝突を何としてでも防ぐ。
ただの氷の塊とは言え、これだけのスピードで、しかもこれだけの数でまともに
喰らうと、さすがに無事でいられる保障はなかった。
面倒臭くなったゼロは三日月斬を放ち、残りの氷塊をまとめて斬り飛ばした。
着地して再び周辺を見渡す。が、依然として姿は見えない。
「いずこかに逃げたか・・・・」
ぽつりと呟く。と、彼は自分の足に、何かヒンヤリとするものがこびり付く
感触を感じた。目をそちらへ向けると────
「・・・・凍結されている!?」
いつの間に、といった驚きを顔色に示す。
彼の両足は、凍てついた氷によって固められ、移動することが不可能となっていた。
一つ分かったことは、ついさっき凍結されたばかりだということだ。
冷感を刺激されたのが、数秒前だからだ。
落ちてきたり飛んできたならすぐに察知できるはずだが、そうでないとなると、
地面を滑走してきたとしか考えられない。
「こんなもの・・・・」
左手をゼットバスターにチェンジし、氷を破壊しようと──する直前、彼の背中に
何かがぶち当たった。
「ぐおっ!!」
背の皮を削り取られるような激痛に、彼は悲鳴をあげた。
同時に衝撃で足元を固めていた氷が砕け、彼は今立っていた場所から放り出される。
うつ伏せに倒れた状態から首だけを起こして、状況を確認する。
向こうに、濁った水の中に消えていく影が見えた。
「あの野郎・・・横回転体当たり攻撃か。味な真似を・・・・」
削り取られる感触と言うのは、そういったことだったのだ。
「だが、これでもう・・・読めた」
確信して、軋みをあげる体を無理矢理立たせると、彼は再々度、周りの様子を観察する。
やはり、海底であるせいと汚水で何も見つけることはできなかったが。
泡の霧がようやく晴れると、ゼロの周りには誰も存在していなかった──ぱっと見だが。
(奴は元々戦闘用ではない・・・・水中用ではあるが、俺より総合的な実力は下だ。
となると、奴は場の状態を最大限に利用して攻撃してくるはずだ。だが、
俺は奴の攻撃方法も、その回避方法も、何も知らない。
ここは一つ、相手の術中にハマってみるか・・・・・)
戦法を決め込むと、ゼロはゼットセイバーの刃を再び生やした。
通常、ビームサーベルと言うものは肉眼で見えることはない。だが陸上では空気中に
数え切れないほどの塵・ホコリが充満しているので、それがビーム部分について
燃焼することによって、初めて肉眼視できるようになるのだ。
ビームの色がそれぞれ違うのは、ビームの波長の違いによるものらしい。
しかし、ここは海中。塵・ホコリは皆無に等しい。その代わり、瞬間的にビームの
高温によって蒸発する水が泡となり、それがビームサーベルを包むので、
海中でもかろうじて見えるようになるのだ。
そのぼんやり可視できる光の刃を握り締めて、ゼロは覚悟を決めた目つきで
辺りを見回した。やはり攻撃の気配はない。まさか、あの爆発に紛れて
逃げたんじゃないだろうな、と邪推していると────背中に何かの圧力を感じた。
気付いて振り向くと、そこにはこちらへと真っ直ぐ向かう、無数の立方体の氷塊が
迫っていた。さっき背中に感じた圧力とは、この氷塊によって押し出された
水だったのだ。
「く・・・舐めるな!」
ゼットセイバーでその群れを必死に斬り刻み、自分への衝突を何としてでも防ぐ。
ただの氷の塊とは言え、これだけのスピードで、しかもこれだけの数でまともに
喰らうと、さすがに無事でいられる保障はなかった。
面倒臭くなったゼロは三日月斬を放ち、残りの氷塊をまとめて斬り飛ばした。
着地して再び周辺を見渡す。が、依然として姿は見えない。
「いずこかに逃げたか・・・・」
ぽつりと呟く。と、彼は自分の足に、何かヒンヤリとするものがこびり付く
感触を感じた。目をそちらへ向けると────
「・・・・凍結されている!?」
いつの間に、といった驚きを顔色に示す。
彼の両足は、凍てついた氷によって固められ、移動することが不可能となっていた。
一つ分かったことは、ついさっき凍結されたばかりだということだ。
冷感を刺激されたのが、数秒前だからだ。
落ちてきたり飛んできたならすぐに察知できるはずだが、そうでないとなると、
地面を滑走してきたとしか考えられない。
「こんなもの・・・・」
左手をゼットバスターにチェンジし、氷を破壊しようと──する直前、彼の背中に
何かがぶち当たった。
「ぐおっ!!」
背の皮を削り取られるような激痛に、彼は悲鳴をあげた。
同時に衝撃で足元を固めていた氷が砕け、彼は今立っていた場所から放り出される。
うつ伏せに倒れた状態から首だけを起こして、状況を確認する。
向こうに、濁った水の中に消えていく影が見えた。
「あの野郎・・・横回転体当たり攻撃か。味な真似を・・・・」
削り取られる感触と言うのは、そういったことだったのだ。
「だが、これでもう・・・読めた」
確信して、軋みをあげる体を無理矢理立たせると、彼は再々度、周りの様子を観察する。
やはり、海底であるせいと汚水で何も見つけることはできなかったが。
V.S.タイダル・マッコイーン⑦
(海の闇に紛れて・・・か。しかし・・・・そんなもので、俺の目は眩ません!)
すぐそこまで迫っていた気配を、彼は瞬時に察した。
バスターを背後に向け、あらぬ方向へとショットを発射する。
バン、と着弾した場所には、先程自分が凍結された
攻撃手段───「ジェルシェイバー」があった。一瞬でショットに溶解されると、
ジェルシェイバーは海の藻屑と消えていった。
(そして、フェイントに気を取られた俺に、背後から攻撃を加えようとする者がいる)
何となく──本当に感覚的なものだった──後ろに自分を狙う冷たい視線を感知し、
彼は跳ね返るように振り返った。
案の定向こうから猛スピードで、何十個もの氷塊が急迫してきた。
(それに逆襲するのが、俺の狙いだ!!)
体を縦に回転させ、サーベルで弧を形作る。
そして、そのまま前進を始め────
「三日月・・・ざぁあああああんっ!!」
まるでモーターのように、急速に回転速度を増して突撃していく。
こちらを狙う氷が肉迫する瞬間、それは千切りにされ、海中に消滅していった。
やがて全ての氷を切断した時、十数メートル先に見覚えのある姿が目に入った。
大口を開けて氷を発射していた、タイダル・マッコイーンである。
こちらの姿を目にすると、血相を変えて逃げ出そうとしたようだった。
が、時既に遅し。ゼロはもうマッコイーンが全力をかけて泳いでも逃げ切れない速度に
まで達していたのだった。
「おおぉおぉおぉおお・・・・」
マッコイーンの眼前まで来ると、突然回転を止め、ゼロは一旦セイバーを収納する。
そして────背中の鞘の中で充電し切った光波剣を引き抜き、
一思いにマッコイーンの口蓋を貫通した。
「ごぼっ!!がぼっ・・・・」
マッコイーンの喉の奥から、生々しいオイルがこぼれ出る。
濁水を更に濁らせ、ゼロの装甲を黒々と染めた。
さらに、ゼロの攻撃はこれでは終わらない。もっともっと、とどめを刺すまで───
「雷神撃ィィィィッ!!」
「ぐああああああああ・・・・・」
飛び跳ねるように痙攣するマッコイーン。強烈な痺れが、数秒間続いた。
だがそれでも、マッコイーンの男気とやらは潰える様相を見せない。
その瞳には、未だくすぶる魂の炎が───
「・・・・くっ!!許せ、マッコイーン・・・・」
その形相に畏怖と申し訳なさを痛感して、ゼロは顔を歪ませる。
そして今度こそ、終わらせてみせると決心した。
「────電刃ッ!!」
雷神撃の体勢から、一気に薙ぎ上げる。マッコイーンの頭部は寸断され、
爆発を生じた。決着がついた、その瞬間だった。
もはやマッコイーンは喋らない、怒らない、笑わない、男気を見せたりはしない───
名残惜しさを噛み締めて、ゼロはサーベルを背中に差し込んだ。
「さらばだ、マッコイーン・・・・ありがとう、そして・・・
さようなら。永遠に・・・・・」
悔しそうなゼロの言葉とは裏腹に、マッコイーンの死に顔は、
さっきの闘志に満ちた瞳とは打って変わって、穏やかなものだった。
ゼロは深海へと沈んでいくマッコイーンの亡骸を、もうその体があげる黒煙が
見えなくなるまで、ずっとずっと、見守り続けていた。
(海の闇に紛れて・・・か。しかし・・・・そんなもので、俺の目は眩ません!)
すぐそこまで迫っていた気配を、彼は瞬時に察した。
バスターを背後に向け、あらぬ方向へとショットを発射する。
バン、と着弾した場所には、先程自分が凍結された
攻撃手段───「ジェルシェイバー」があった。一瞬でショットに溶解されると、
ジェルシェイバーは海の藻屑と消えていった。
(そして、フェイントに気を取られた俺に、背後から攻撃を加えようとする者がいる)
何となく──本当に感覚的なものだった──後ろに自分を狙う冷たい視線を感知し、
彼は跳ね返るように振り返った。
案の定向こうから猛スピードで、何十個もの氷塊が急迫してきた。
(それに逆襲するのが、俺の狙いだ!!)
体を縦に回転させ、サーベルで弧を形作る。
そして、そのまま前進を始め────
「三日月・・・ざぁあああああんっ!!」
まるでモーターのように、急速に回転速度を増して突撃していく。
こちらを狙う氷が肉迫する瞬間、それは千切りにされ、海中に消滅していった。
やがて全ての氷を切断した時、十数メートル先に見覚えのある姿が目に入った。
大口を開けて氷を発射していた、タイダル・マッコイーンである。
こちらの姿を目にすると、血相を変えて逃げ出そうとしたようだった。
が、時既に遅し。ゼロはもうマッコイーンが全力をかけて泳いでも逃げ切れない速度に
まで達していたのだった。
「おおぉおぉおぉおお・・・・」
マッコイーンの眼前まで来ると、突然回転を止め、ゼロは一旦セイバーを収納する。
そして────背中の鞘の中で充電し切った光波剣を引き抜き、
一思いにマッコイーンの口蓋を貫通した。
「ごぼっ!!がぼっ・・・・」
マッコイーンの喉の奥から、生々しいオイルがこぼれ出る。
濁水を更に濁らせ、ゼロの装甲を黒々と染めた。
さらに、ゼロの攻撃はこれでは終わらない。もっともっと、とどめを刺すまで───
「雷神撃ィィィィッ!!」
「ぐああああああああ・・・・・」
飛び跳ねるように痙攣するマッコイーン。強烈な痺れが、数秒間続いた。
だがそれでも、マッコイーンの男気とやらは潰える様相を見せない。
その瞳には、未だくすぶる魂の炎が───
「・・・・くっ!!許せ、マッコイーン・・・・」
その形相に畏怖と申し訳なさを痛感して、ゼロは顔を歪ませる。
そして今度こそ、終わらせてみせると決心した。
「────電刃ッ!!」
雷神撃の体勢から、一気に薙ぎ上げる。マッコイーンの頭部は寸断され、
爆発を生じた。決着がついた、その瞬間だった。
もはやマッコイーンは喋らない、怒らない、笑わない、男気を見せたりはしない───
名残惜しさを噛み締めて、ゼロはサーベルを背中に差し込んだ。
「さらばだ、マッコイーン・・・・ありがとう、そして・・・
さようなら。永遠に・・・・・」
悔しそうなゼロの言葉とは裏腹に、マッコイーンの死に顔は、
さっきの闘志に満ちた瞳とは打って変わって、穏やかなものだった。
ゼロは深海へと沈んでいくマッコイーンの亡骸を、もうその体があげる黒煙が
見えなくなるまで、ずっとずっと、見守り続けていた。
第一次作戦開始から5日を経て、ついにゼロも、イレギュラーハンター本部へと
帰還する。エニグマ作戦実行まで、時間はあまり残されていなかった。
そして、∑の命を受けたあの傭兵がやって来る日も、もう間もなくのことだった。
帰還する。エニグマ作戦実行まで、時間はあまり残されていなかった。
そして、∑の命を受けたあの傭兵がやって来る日も、もう間もなくのことだった。
エニグマ発射数分前
第一次作戦開始からまる一週間───ついに、エニグマ発射実行の日がやってきた。
その日、イレギュラーハンター本部基地はいついかなる時よりも緊迫した雰囲気に
包まれていた。基地外はあらん限りの生き残りの部隊が動員され、各々が持てる限りの
武器を装備し、可能な限りオペレーターと通信士がそれらを全面サポートする。
気分はもう第1種戦闘態勢──いや、気分などではなく、事実そうなのだが。
とりあえずはまあ──そういった厳戒態勢が敷かれていた。
無論エックスやゼロもその例外ではなく、彼等は最も重要なエニグマの
格納庫ブロックの警備を任されていた。
何をそんなに警戒しているのかと言えば、あの忘れもしない、人を食ったような口調の
男──ダイナモの襲撃を予想してのことである。予告などという用意周到な芸当を
してくるからには、それなりの覚悟と実力があってのことだろう。
だが、キレ者であるシグナスにもどうしても分からなかったのは、何故あのダイナモと
名乗る男がエニグマの破壊を企んでいるかということだった。
この地球上に住む、生きとし生けるもの全てにとって、いやスペースコロニーの
住民であったとしても、エニグマを壊してユーラシアを地上に落下させることが、
決してメリットになることはない。
冗談でも──あの男の言うことは本気なのか冗談なのかは分からないが──、許して
やれるような問題ではないのだ。
一体彼は何を目的として行動しているのか、その断片すらも理解できるものでは
なかった。
(考えても頭がおかしくなるだけだ。所詮イレギュラーの言う事だ・・・・・
気にする必要は無い。我々が成すべきことは二つ。この地球圏の危機を救うことと、
その邪魔を企てる者を全力を持って排除することだ。
今は、何も考える必要はない・・・)
絡まる思考を強制的に停止させ、シグナスは司令官たる態度に戻ろうとかぶりを振った。
と、そこにエイリアの報告が入る。
「1番ゲートを突破した侵入者を確認!現在Gブロックに戦力を集結させつつ
ありますが・・・・」
そこでエイリアはうつむいて押し黙った。首を傾げたシグナスが、いわゆる司令官の
口調で尋ねる。
「どうしたエイリア。状況を報告しろ」
「はい、どうもそれが・・・・こちらの方が劣勢のようで・・・・」
「何・・・・・・」
シグナスの目が驚愕に見開かれる。まさかとは思っていたが、∑ウィルスの
繁殖によって戦闘員が激減したとはいえ、あの傭兵が何百人もの本部隊員を
撃破してくるなど、シグナスには到底考えられうるはずもなかった。
第一次作戦開始からまる一週間───ついに、エニグマ発射実行の日がやってきた。
その日、イレギュラーハンター本部基地はいついかなる時よりも緊迫した雰囲気に
包まれていた。基地外はあらん限りの生き残りの部隊が動員され、各々が持てる限りの
武器を装備し、可能な限りオペレーターと通信士がそれらを全面サポートする。
気分はもう第1種戦闘態勢──いや、気分などではなく、事実そうなのだが。
とりあえずはまあ──そういった厳戒態勢が敷かれていた。
無論エックスやゼロもその例外ではなく、彼等は最も重要なエニグマの
格納庫ブロックの警備を任されていた。
何をそんなに警戒しているのかと言えば、あの忘れもしない、人を食ったような口調の
男──ダイナモの襲撃を予想してのことである。予告などという用意周到な芸当を
してくるからには、それなりの覚悟と実力があってのことだろう。
だが、キレ者であるシグナスにもどうしても分からなかったのは、何故あのダイナモと
名乗る男がエニグマの破壊を企んでいるかということだった。
この地球上に住む、生きとし生けるもの全てにとって、いやスペースコロニーの
住民であったとしても、エニグマを壊してユーラシアを地上に落下させることが、
決してメリットになることはない。
冗談でも──あの男の言うことは本気なのか冗談なのかは分からないが──、許して
やれるような問題ではないのだ。
一体彼は何を目的として行動しているのか、その断片すらも理解できるものでは
なかった。
(考えても頭がおかしくなるだけだ。所詮イレギュラーの言う事だ・・・・・
気にする必要は無い。我々が成すべきことは二つ。この地球圏の危機を救うことと、
その邪魔を企てる者を全力を持って排除することだ。
今は、何も考える必要はない・・・)
絡まる思考を強制的に停止させ、シグナスは司令官たる態度に戻ろうとかぶりを振った。
と、そこにエイリアの報告が入る。
「1番ゲートを突破した侵入者を確認!現在Gブロックに戦力を集結させつつ
ありますが・・・・」
そこでエイリアはうつむいて押し黙った。首を傾げたシグナスが、いわゆる司令官の
口調で尋ねる。
「どうしたエイリア。状況を報告しろ」
「はい、どうもそれが・・・・こちらの方が劣勢のようで・・・・」
「何・・・・・・」
シグナスの目が驚愕に見開かれる。まさかとは思っていたが、∑ウィルスの
繁殖によって戦闘員が激減したとはいえ、あの傭兵が何百人もの本部隊員を
撃破してくるなど、シグナスには到底考えられうるはずもなかった。