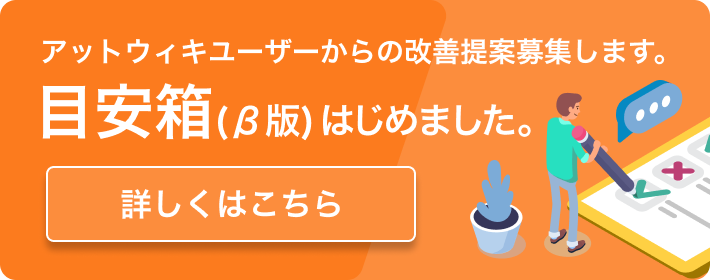『第五階層へ降りるルートはその先だ。急げセイア』
「了解。このまま突っ切る!」
おおよそ現実空間では再現出来そうもないサイバーチックな空間の中、
ロックマン・セイヴァーはそれを楽しむ様子もなく走り続けていた。
辺りには電脳世界独特の光のラインが多々見える。
何を模したのか判らない、言葉では言い表しにくい建造物に囲まれたそこは、現実から離れたもう一つの戦場だった。
これが現実ならば敵機の接近は気配で判るというものを。この世界ではそんな常識が全く通じない。
三百六十度好きな方向から突然姿を現わし、攻撃を仕掛けてくる敵機達は、個々の戦闘力とは裏腹に手強い。
セイアはここに来るまでに、既に幾度かのダメージを負ってしまっていた。慣れない戦場で、上手く実力が発揮出来なかったからだ。
所々に被弾したアーマーを気にかけつつも、セイアはウィドの声に指令されたルートを急ぐ。
が、そんな侵入者の進行を止めようと、セイアの目と鼻の先で巨大な敵機の姿が現れた。
『セイア!』
「判ってる!」
しかしセイアは止まらない。セイアを制止しようとするウィドの声にそう答えつつ、セイアは飛翔した。
エックス・サーベルを抜き放ちつつ、飛燕脚からの推力を利用し、連続的に回転運動を始める。
サーベルを頭上に構えたまま高速回転を始めるセイアは、おのが身体を一つの弾丸とし、そのままゴーレムの様な姿の敵機に突っ込む!
辺りに三日月型のエネルギーを発散しつつ、弾丸となったセイアが敵機を貫いた。三日月斬だ。
『成る程。だが正面にエネミーの反応が多数。陸地タイプだ』
この世界において『陸地』と形容することほどのデタラメは恐らくない。
けれど、ウィドにもセイアにも他にそれを形容する言葉が見つからなかった。
常識の通用しないこの世界で、『地面』と認知させる部分から離れられない敵機のことを、ウィドは『陸地タイプ』と言い表した。
事実上は間違っていようとも、その言葉をしっかりとセイアは理解した。そして、自らがそれに対抗しうる為の最善たる技を瞬時に繰り出す!
「疾風っ!」
急停止するセイア。が、彼の姿を模したエネルギーの塊は、ダッシュの姿勢を保ったままに敵機の大群へと突っ込んでいく。
傷つく恐れも撃ち落とされる恐れもないエネルギーの塊・疾風は、自らに触れるもの全てに、文字どおり疾風のような斬撃を刻んでいく。
疾風牙のスキルを上乗せされた疾風は、この技の元々の持ち主を越える威力で、敵機達を瞬時に破壊せしめて見せた。
「下降ルートを確認。これより第五階層に突入する!」
『了解。しかし第五階層には今までにないエネルギーが確認されている。気を抜くなよセイア』
「判ってる」
疾風が作り出した進路の先に、ポッカリと口を開けるゲートが見える。
一見覗いただけでは下の階が確認出来ない暗黒の穴だが、さっきからこれと同じものを三つも潜ってきたセイアに、今更躊躇いはなかった。
バスターに装填していた特殊武器を通常のバスターモードへと還元しつつ、セイアは思い切り下降ゲートへと飛び込んだ。
第四層から第五層へと景色が変わる。自分自身という存在が別の空間へと飛ばされるような違和感は、四つ目を潜った今でも拭いきれない。
スタンと予期しないうちに足の裏が地面の感触を感じる。地面が知覚出来ないうちに着地してしまうのはなんとも不親切な作りだ。
セイアはそんな風に心の中で愚痴を云いながらも、セイアの口をついて出たのはエクスクラメーションだった。
「くっ・・!?」
『セイア、どうした!』
「なんだこれは・・!?」
全く見覚えのない――ここに来た時点でそんなこと続きだったが――光景に、思わずセイアは声を上げた。
さっきまでの第一層から第四層のいずれにも当てはまらない、特異な空間。
敵機と思える物体は存在していない・・いや、まだ確認出来ないが、その代わりに視界を埋め尽くすものがあった。
「これが・・謎のエネルギーの正体か」
セイアがそう形容したのは、辺りを埋め尽くす程に存在している金色の球体。
今までのような防衛型ではないことは、これらから発せられるエネルギーからも、その唯ならぬ外見からも容易に判断がつく。
機械特有のブーンという異音を発しながら、それらの球体の表面には赤いエネルギーラインが走っていた。
禍々しい・・と、云うのかもしれない。雰囲気的にはあのシグマに近い感じだ。
『こちらのレーダーには何も映っていない。セイア、何が見える!』
「どうやらコイツ等が元凶の一端みたいだ。コイツ等は防衛用じゃない!」
気が付けば、亀のようにのろのろとした動きながらも、空間いっぱいを埋め尽くしていた金の球体は除々にセイアへと集まりつつあった。
バチバチと赤いエネルギーが走る表面は、どう見えても触れてただで済むとは思えない姿だ。
もしコイツ等がこの騒ぎの元となったものならば、破壊するしかない――!
セイアは手始めに一番手前の二つ三つを、エックス・サーベルの斬撃で真っ二つに斬り裂いた――つもりだった。
しかしセイアの意識とは裏腹に、金の球体は何事も無かったかのように近づいてくる。
もう一度サーベルの斬撃を浴びせるが、刃はスッと空気を裂くように球体の表面を擦り抜けてしまう。
「くっ、手応えがない!」
まるで雲を相手にしているような気分だ。
もう片手をバスターに変化させ、手当たり次第に光弾をぶつけてみるが、やはり効果はない。
あっと言う間にセイアは後方の隔壁へと追い込まれてしまっていた。
こうしている間にも、ふわふわと浮遊する金の球体達は、除々に除々にセイアとの距離を縮めていく。
第四階層へと続く上昇ゲートを見上げてみたけれど、既にガッチリと閉鎖されていて、
第四階層へセイアが戻ることを断固として拒否していた。
『何があった!応答しろセイア!』
「バスターもサーベルも通用しないんだ!このままじゃ・・うわっ!?」
『どうした!』
セイアの死角からも迫ってきていた球体が、ついにセイアを捉えた。
最初に呑み込まれたのはサーベルを持つ右手。隙が出来たそこに、我先にと群がる球体が、次々とセイアの身体の各所に食らい付いてくる。
右手、左手、胴、両足。セイアに食らい付いたそれらは、言い様のないエネルギーの奔流を、セイアの体内へと一気に流し込み始めた。
「くっ!離れろ・・!うっ・・うわぁぁぁぁっ!!」
『セイア!セイアっ!!』
「ウィ・・ドっ、ぐぁあぁぁぁぁっ!!」
このまま意識を手放してはいけない!――心の中ではそう理解しつつも、体内を侵し始めたエネルギーは、
セイアの意思とは無関係にその身体を侵食し始めた。
必死にセイアの名を呼ぶウィドの声が少しずつ遠くなっていく。身体に力が入らずに、サーベルの柄がカランという音を立てて足元に転げ落ちた。
駄目押しとばかりに残った部位を埋め尽くしていく金の球体。
最後に残った顔面が呑み込まれたとき、セイアの意識は暗黒の渦へと放り出された。
「うっ・・・・ぁ」
『セイアぁぁっ!!』
現実とはかけ離れたその空間に木霊する悲鳴は途絶え、代わりに相棒の名を絶叫する声だけが響く。
喉を痛めてしまう程に強く叫んでも、それに応えてくれる声はなかった――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「リミテッド。イクス、レイ、イクセ。そして各種リミート・レプリロイドか。これまた厄介なことになったね」
モニタを埋め尽くすデータの羅列にじっくりと目を通したあと、ふとDr.ゲイトが呟いた言葉がそれだった。
Dr.ゲイト。数年前のナイトメア事件発祥の張本人にして、ロックマン・セイヴァー・・セイアの制作者。
以前はゼロの破片を元に作り出したナイトメア・ウィルスによって荒廃した地球の支配を目論んでいたのだが、
事件の終焉の際にエックスによって救出され、それ以来イレギュラー・ハンター専属の研究員として働いている。
つい昨日まで各地のハンター支部を回っていたゲイト。彼が本部に帰るなり知らされた事実とデータは、並の人材ならば卒倒しそうな内容だった。
レプリフォース大戦の最中でエックス・ゼロによって撃破された筈のレプリロイドの再来。
データに残る、リミテッドという名の脅威。そしてそれがセイアに取り憑いたことで誕生した三体の強力な敵。イクス、レイ、イクセ。
「折角ゆっくりと話が出来る機会が出来たというのに、なかなか穏やかじゃないシチュエーションだね、ウィド君?」
「俺は元からコイツ等に立ち向かう為、イレギュラー・ハンターに訪問したんだ」
「ふうむ。まぁ、そういう事にしておこうかな。
それにしても、なかなか厄介な敵が現れたものだよ。ボクの作ったナイトメア・ウィルス以来かな?」
そうおどけた様に云うゲイトの顔は、困惑よりも余裕の二文字が先に出ているように思う。
ウィドが相変わらず食えない奴だと肩を竦めていると、ゲイトは変わらずの微笑を口もとに浮かべたまま、
今度はセイア――今は健次郎の姿だ――の片腕をそっと握った。
「どうだい、セイア?腕は痛むかい?」
「い、いえ。もうすっかり大丈夫です。痣も消えたし」
「うんうん、成る程」
興味深そうに頷きつつ、ゲイトは健次郎の袖を捲る。つい先日・・学校での闘いがあった日以来、腕に痛みは走っていない。
あんなにクッキリとあった痣も綺麗に消えている。逆に不安になる程に。
「リミテッドについてのデータを詳しく読んだことはないから断定は出来ないけど、どうやらそのイクス達三人が君から分離したことで、
同時に君に取り憑いていたリミテッドが剥離したようだね」
「はぁ・・」
「その証拠にここ数日のエネルギー環境も落ち着いている。完全とは云えないかもしれないけど、元には戻ったってことかな」
「・・リミテッドによるパワーアップ効果も同時に消え失せたがな」
ボソリ。ウィドは横から口を挟んだ。
勿論セイア自身の安定性が何より大事であり、あんな風にセイアが暴走することがなくなったことを喜ぶべきであることはウィドにも充分判っていた。
寧ろたった一人の友達であるセイアの命に別状がなくて、大いにホッとしている方だ。
けれど、問題はそれとは別のところにある。
「うーん、そうだね。確かに記録に残る異常な高出力を今のセイアが発揮するとは思えない」
「つまり、僕は・・?」
健次郎が首を傾げると、ゲイトは珍しく口もとの笑みを崩した。
ほんの少し真剣な顔で、そっとセイアの両肩を包み込み、呟く。
「つまり、リミテッドによる異常出力を失ったことで、君はイクス達に対抗しうる力をも同時に失った・・ってことだよ」
「えっ・・」
「残念だが、それは事実だ。あの時のセイアの戦闘力から予測される奴等の力は・・想像を絶すると云っていい。
例えお前が強化アーマーを装備したところで、勝負は見えているんだ」
「なら、僕は奴等に対して何も出来ないっていうの?」
「そうは云っていない。俺とDr.は全力で奴等に対抗しうる為の対策を立てる。
だからお前は、それが完成するまで決して奴等と闘ってはいけないんだ」
「・・奴等が攻撃を仕掛けてきたら?」
健次郎は少し苦い顔で尋ねた。来るべき答えはなんとなく予想出来ていたけれど、尋ねずにはいられなかった。
そしてウィドの代わりにゲイトが、健次郎の予想した通りの応えを口にした。
「その時は、残念だけど逃げるしかないかな」
「そんな・・!奴等がすることを黙って見てろって云うんですか!」
「・・別にお前が勝手に闘いを挑み、犬死にするのは自由だ。だが忘れるな。
奴等に勝てる可能性があるのは、エックスとゼロがいない今・・お前しかいないということを。
もしお前に彼等と同じように人々を護る気があるのなら、我慢することも大切だ」
半分はデタラメだった。ウィドは、自分の本心とは全く逆のことを云っていた。
ウィドだって・・いや、ウィドは健次郎が死ぬのが恐かった。健次郎が敵に殺されるのは何よりも辛い、そして苦しい。
きっと健次郎がそれでも闘いを挑むと云ったなら、半狂乱になって止めるだろう。
それでも健次郎に事の重大さを、そして自らの立場を理解して貰うにはこう云う他なかった。
彼には辛いだろうと理解しつつも兄達の名を出したのはその所為だ。
「ウィド君の云うとおりだよセイア。申しわけないけど、今のボク達は君しか残っていないんだ。
もし本当に奴等に勝ちたいと願うなら、君がするべきことは判っているね?」
「ウィド・・Dr.・・・。・・判りました」
しゅんと項垂れて、健次郎は小さな声で了解の意を呟く。
そんな彼の様子にゲイトはほんの少しの慈愛を含んだ笑みを浮かべつつ、そっとその薄い蒼の髪を撫でる。
ここ数日ロクな手入れも出来ないでいるのだろう。元々細くしなやかな髪は、随分とバリバリになってしまっていた。
髪の手入れも出来ない程に張り詰めていたのだ。そう思うと、ゲイトはつい一年前程前まで元気だった蒼の青年の姿を思い出さずにはいられなかった。
「さぁ。君は少し疲れているんだ。沢山のことが一気に起こったからね。
こっちはウィド君と一緒に作業を続ける。セイアは部屋に戻った休みなさい」
「で、でも・・」
「心配するな。対策も解析もすぐに終わらせる。奴等と闘えるようになってもお前がそんなんじゃあ、結果なんて期待出来ないぞ」
「そうそう。ハンターとして、時には休むことも大切なんだからね」
二人にやんわりと肩を押され、健次郎は諦めたように肩を竦めると、小さくコクンと頷いた。
「判った。僕は一足先に部屋に戻るよ、ウィド。そっちの方・・お願い出来るかな」
「任せとけ。戦闘で殆ど役に立たない分、しっかりお前のサポートをしてやるさ」
「うん。ありがとう」
一つニコッと笑って、健次郎は服の中に隠していたエックス・サーベルとZセイバーを机の上に置くと、会釈と共に研究室を去っていった。
二本の柄をそっと手にしたウィドは、健次郎の背中がドアに覆い尽くされたのを見届けてから、くるりとゲイトの方へと振り返った。
ゲイトはふとウィドの手の中の二本の柄を手にとると、それらをマジマジと見詰めた。少し懐かしそうな視線だった。
「ふうん。これはゼロのセイバーだね。何故これをセイアが?」
「・・そ、それは」
いつも淡々としているウィドが口籠もったのを、ゲイトは見逃さなかった。
けれど敢えて詮索する気はないらしく、ゲイトは余った手をウィドの頭の上に置いた。
「まぁそれは聞かないでおくよ。誰にでもプライバシーというのは存在するからね」
「あ、あぁ」
ウィドはゲイトに何か苦手意識を持っていたが、ようやく今その正体が判ったように思う。
ゲイトはよく相手の心を見透かしたような態度を取る。そしてそれを見透かしながらも敢えて何も知らないような物言いで応える。
他人に対してどちらかというと閉鎖的なウィドにとって、ゲイトのそういった性格は少し刺激というか、新鮮味が強すぎたのかもしれなかった。
「しかし、随分とボロボロになったものだよ。ついこの前新品同様にして上げたというのに」
見事なBy The Way。素知らぬ顔でゲイトが手の中で弄ぶのは、セイアの愛剣であるエックス・サーベルだった。
無数のラーニング技を放ち、沢山の新必殺技の出力変化に耐えてきた光剣の柄は、
今まで彼が潜り抜けてきた闘いがどれ程凄まじいかを一目で物語っている。
これには流石のウィドですら気が付かなかった。今までの沢山の信じ難い事象の中でセイアのサーベルの状態を確認出来るほどの余裕はなかったのだ。
「セイアには辛い闘いを強いることになるね・・」
「・・セイア自身が闘うと云っているんだ。俺達がどうこう云う筋合いはない筈だ」
「ふふ、全く。何を強がっているんだい?」
「つ、強がってるだと?」
「そう」
モニタの前の椅子に腰掛けたゲイトは、丁度ウィドに背を向ける構図になる。
ウィドは振り返らなかった。ただ何も無い廊下へと続くドアを見詰めながら、同じく振り返らないゲイトの声を聞いていた。
相変わらず何かを見透かしたようなゲイトの声は、やはりウィドの心の奥をつんっと刺激した。
「誰よりセイアを心配しているのはウィド君・・君じゃあないか。そんな物言いをしたところで、このボクの目はごまかせないよ」
「べ、別に俺は・・」
「ふふ。まぁ君がそう云うのならかまわないけどね。ただ、セイアは君にとって初めての友人だ。そうだろう?」
一体このナルシストの科学者はどこまで知っているというのだ。
心の中で驚嘆と溜息を同時に放ちつつ、ウィドは面食らう他無かった。
対してゲイトは楽しそうにキーボードを叩きながら、片手でちょいちょいと自分の横の椅子を指さした。
隣に座れ、と云っているらしい。
「・・さて、無駄話もここまでだ。あのリミテッド達に対抗しうる対策を、君は練っているんだろう?それを聞かせてくれないかな」
「やれやれ・・」
ボリボリと後頭部を掻きながら、ウィドは渋々ゲイトの隣の席につく。
服の内ポケットに厳重に保管しておいたデータディスクを手近のスロットルに差し込み、その内容をモニタへと出力させる。
映し出されたプログラムの羅列に、流石のナイトメア・ウィルス開発者も、驚いたように目を見開いていた。
そんなゲイトの顔を見て、ウィドは少しふふんと踏ん反り返った。ようやく一つ勝ったような気がした。
「・・素晴らしいね。確かにこれなら、リミテッドにも対抗出来るかもしれない」
「あぁ。だが、このデータ配列を実現するのはかなりシビアだ。そこで、アンタの力を貸してもらいたい」
「OK。勿論協力させて貰うよ。ただ、かなり高度な作業になるけど、大丈夫かい?」
そう尋ねるゲイトの顔に、ウィドがNOと応えるという憶測は全くなかった。
それはウィドにも判っていることであるから、ウィドはわざと声に出さずに小さく頷いてみせた。
そしてどちらかともなく二人はキーボードをたたき始める。その二人の顔に、今までの冗談混じりの会話の気配は全くない。
天才を越える天才と呼ばれたDr.ゲイトと、若き天才科学者ウィド・ラグナーク。そんな二人の夢の共同作品が、そう遠くない未来で生まれるのだ。
「・・ところでDr.」
「うん、なんだい?」
依然としてキーボードを叩きつつ、ウィドはふとゲイトを呼んだ。そして尋ねた。
「アンタは・・俺のことを知っているのか?」
「さぁ、何のことかな。ボクが知っている君は、謎の天才少年科学者だよ」
「・・」
「そしてボクは、Dr.バーンの幼馴染み。それだけさ」
「・・・!」
やれやれ本当に食えないやつだ。
一人で作業している時とは較べものにならない程スムーズに進む指を認めつつも、ウィドは隣で一人楽しそうな科学者に溜息をつく他無かった。
ロックマン・エックス。そしてゼロは現代の最先端技術をもってしても正体不明のレプリロイドだ。
いや、正確には違う。何故なら『レプリロイド』と称される種族は全てロックマン・エックスを素体として生まれているからだ。
つまりはセイア、ゲイト、そしてあのシグマですら実質的にはロックマン・エックスのコピーに過ぎない。
今のこの世界に存在している者の中で、エックスを始祖としないレプリロイドは一体しかいない。そう、ゼロだ。
かつて紅いイレギュラーとして出現したゼロも、レプリロイドの始祖となるに充分値する脅威的な構造を持つ。
果たしてエックスとゼロ、彼等の本来の制作者は誰で、そしてどういった目的で生み出されたのか。
Dr.ケイン、エックス亡き今、それを知るのは彼等の弟であるロックマン・セイヴァーしか残っていない。
余談だが、一年前の宿命の決着の際にセイアが目の当たりにしたであろう歴史の裏側は、
数々の評論家や科学者から好奇心溢れる視線で見られていたが、セイアが頑なにそれを喋らなかったため、結局は謎のままになったという。
通称『Fusion Cross』。ウィドが捻り出した計画の名前だ。
それは即ちロックマン・セイヴァーがイクセ等ハイパー・リミテッドの脅威に対抗しうる為の強化案。
平たく云えば新たな強化アーマーについての設計図だ。
生みの親のゲイト、そしてウィド自身も大いに認めるセイアの可能性。
当初ゲイトが生み出したときに推定された予想最大出力を遙かに上回る功績を持つ彼は、いまやエックス、ゼロを越えた最強のレプリロイドだ。
だが、それでも所詮は現代の科学者が生み出したエックスとゼロの模造品。初期戦闘力はまだまだエックス達へは及ばない。
なにせブラックボックスだらけだった彼等だ。そんな彼等の限界最大戦闘力を知る者はこの世界に誰一人とていない。
エックスは一年前に没し、ゼロは生還しつつも行方不明になっているのだから。
この『Fusion Cross』内においての主旨。それはズバリ、セイアに対してエックスとゼロの実質的な融合――FUSIONだ。
エックスとゼロが残していった数々の戦闘データを元に、セイアの潜在能力を最大発揮しつつ、その出力に大いに耐えうるアーマーを創り出す。
イクセ等リミテッド達が強化されたセイアの潜在能力の一部だというのなら、セイアにはそれ以上に潜在能力を発揮して貰わなければならないのだ。
勿論そんな無茶な要望に応えうるアーマーを創り出すのは至難の業だ。
一介の科学者ならば、そのコンセプト自体を絶望視し、とっくに破棄しているだろう。
けれどゲイト、ウィド。何よりセイアには後がない。
絶望だの不可能だのと四の五の云う暇があるのなら、それを成し遂げる為の道筋を作った方が余程早い。
それ程にイクセ等ハイパー・リミテッドの力は脅威的なのだ。ウィドとゲイトがさっきセイアに云ったばかりの台詞だが、
リミテッドの剥離した今のセイアが彼等三人に闘いを挑み、勝てる確立は万に一つもない。
例えセイアにエックス・ラーニングシステムが装備されていようとも、セイアを知り尽くしているだろう彼等にはそよ風程の障害に過ぎないと云える。
だからこそウィドとゲイトはハイパー・リミテッドというかつてない強敵に対抗しうる鎧を創り出そうと決意したのだ。
イレギュラー・ハンターとして、被害がこれ以上拡がる前に奴等を倒す為に。そして何より、ゲイトは大切な息子を、ウィドはたった一人の親友の命を護る為に。
「・・しかし君も無謀な男だね」
かなりの間キーボードの叩く音しか聞こえなかった部屋の中で、そんな言葉を口にしたのはゲイトだった。
ブラインドタッチなんて基本中の基本とでも言いたげな見事なタイピングの腕を見せびらかせながらにそう云ったゲイトに、
ウィドも負けないくらい達者なタイピングを披露しつつ、一言云った。
「・・しかしこうでもしない限り、奴等を倒すことは出来ない」
「うんうん。最もな意見だと思うよ。事実セイアも君もそんな顔をしているからね」
プログラムの開発度は、元々ウィドが開発を進めていた五分の一程度に加え、もう五分の一程度まで進んでいる。
流石は天才科学者ゲイトだと思い知らされる速度だ。端から見ればのらりくらりとイライラする程の遅さの進行だが、
これ程膨大なデータ量を的確に処理・構築していく様は、その手の方面を噛ったことのある者ならば、思わず舌を巻かずにはいられないだろう。
「こんな無茶なアーマーを考え出すのは君くらいなものだよ。ボクだったきっともっとマシなコンセプトでいくと思うからね」
「ならアンタならどういった強化を考え出す・・?」
「うーん、そうだね。ナイトメア・ウィルスで相手を混乱させて、その間に攻撃するっていう案はどうだい?」
「・・・本気で云っているのか?」
「勿論冗談だよ。つまり何が云いたいかというと、それくらい馬鹿げた思考でなければ、奴等に我々の力だけで対抗しようとは思わないってことさ」
エックスとゼロがいてくれたら――そう思ってしまうのは不謹慎だろうか。
それでもそう思わずにはいられなかった。彼等はいつだってなんとかしてくれた。どんな脅威をも打ち倒してきた。どんな強敵をもやぶってきた。
「ボクはね、ウィド君。口惜しいんだよ」
「うん?」
「どうしても思ってしまうのさ。何故ボクの息子ばかりこんな目に・・とね」
「・・・」
四年前のナイトメア事件よりも更に少し前、ゲイトの創り出した八人の息子達は処分された。
決して彼等がイレギュラー化したわけではない。彼等は全くの無罪だった・・といっても過言ではなかっただろう。
その当時ゲイトは学会では異質な存在だった。同僚であるエイリア――勿論現在ハンターでオペレータを務めている彼女だ――が語るに、ゲイトは天才過ぎた。
上部からの課題をまもらず、自らが高みを目指すままに次々と高性能レプリロイドを創り上げていく彼。
学会はそんな彼と彼が生み出したレプリロイドの力に恐怖し、嫉妬した。
かつて世界を混乱に陥れたナイトメア事件は、そんな学会の愚かな一面が作り出したのかもしれなかった。
事故に見せかけたとはいえ、彼の息子達を破壊したのは彼を取り巻く世界だった。
一度目は学会の秘密裏の陰謀によって。そして二度目はセイアの兄でもあるエックスの手によって。
それでも決定的に違うのは、彼等の二度目の死は彼等自身が望んで闘ったという点だろう。
ゲイトにとって、息子達を二度失ったことに変わりはなかったのだが。
「だから少し恐いのさ。今度はセイアが自分の意思を貫き、散っていくのではないかってね。
そしてボクは・・散っていく息子の背を押す執行人なんじゃないかとね」
ゲイトがレプリロイドだからだとかそういうことは全くもって意味をなさない陳腐なことだった。
ゲイトはレプリロイドの科学者だけれど、確かに人の親なのだから。
ヤンマークも、シェルダンも、ヒートニックスも、ヴォルファングも、ミジニオンも、タートロイドも、スカラビッチも、プレイヤーも――そしてセイアも。
みんなゲイトの大切な息子達だから。
「・・ふっ、セイアが一度でもアンタに呪いの言葉を吐いたことがあったか?」
「ウィド君・・」
「アンタが自分の息子達の死を哀しむのは勝手だ。だがアンタは彼等にそれを強要したか?違うだろう。
彼等は彼等なりにアンタについていこうとした。そしてセイアも、自分の意思でリミテッドと闘う決意をしたんだ」
セイアの瞳に曇はなかった。彼は云ったのだから。キッパリと。リミテッド達と闘う、と。
付き合いが浅いウィドにでも判る。セイアは自分の痛みを他の誰かの所為にするような愚か者ではない。
「彼等が死んだのを自分の所為にするなんて、これほどの侮辱はない。そうだろう、Dr.?」
「・・そうだね」
そう自嘲気味に笑ったゲイトは、次第にプッと吹き出すと、はははと少し軽い笑いを立てた。
これには流石に手を止めたウィドは、少し不機嫌そうな顔でゲイトを見やった。
全く人が真面目に話を聞いてやっているというのに、なんだコイツは・・と、そんな視線で。
「あははは。いやいやごめん。別に君のことを笑っているわけじゃあないんだよ」
「なら、なんだというんだ」
「他人にこんなことを話したのは初めてだけど、まさか君がそんな風に云ってくれるとは思わなくてね」
ポンッと頭に手を置かれ、ウィドはなんだかむず痒い気持ちで席を立った。
ゲイトに「なにを云って」と抗議しようと思ったのだ。けれどウィドの行動は突然ゲイトが突き出してきた掌によって阻止された。
「ウィド君!」
「な、なんだ突然!」
「どうやらボク達の仕事がまた一つ増えたようだよ」
そう云ってゲイトはPCに差し込んでいたメモリを素早く引き抜いた。恐らくデータのバックアップを隔離する為だろう。
科学者として最終手段とも思える強制隔離の様を見て、ウィドも慌てて手近のモニタを覗き込む。
そこに表示されるエラーメッセージを目にして、ウィドは「ちぃっ」と小さく舌打ちをした。
「こんなときにお客さんみたいだね」
「やれやれ、厄介な時に・・!」
メッセージの内容はアラートだ。大抵こういった類のエラーは外側からの侵入者、或いはウィルスが流された際に作動する。
しかし大抵はハンターの誇るワクチンによって自動的に除去される筈なので、こんな風にアラートを響かせる事態というのはかなりの緊急事態だといえよう。
それもレッドアラートだ。作業を少しでも早く進めなければならない現状だというのに。ウィドが思わず毒づいてしまう気持ちもなんとなくゲイトには判った。
「ワクチンプログラムを受け付けない、か。随分手の込んだ侵入者だな」
「呑気なことを・・」
「マズイ。どうやら敵さんはマザーコンピューターの最下層までアクセスしてしまっているらしい」
カチャカチャとキーボードを弄くっていたゲイトは、慌ててその手を離した。
既にベース内の全てのコンピュータは操作を受け付けないだろう。
下手をすればキーボードを通してレプリロイドであるゲイトにもウィルスが侵食する危険性がある。
そのことはウィド、ゲイト両名が判りきっていたことだ。
例え人間であるウィドが操作を変わったところで結果は変わらない。
「ちっ。これではハンターの遠隔操作型メカニロイドは・・!」
「全体イレギュラー化。ベース内は壮絶な室内戦・・と云ったところかな」
「こんなウィルス如き・・!」
憎々しげに叫ぶウィドの意識とは裏腹に、ドンっと乱暴な音が響き、研究室のドアが派手に吹っ飛んだ。
廊下と較べて若干暗い室内からは逆光で上手く見ることは敵わなかったが、乱暴な来訪者のアイカメラの輝きだけはいやにハッキリと見える。
ウィドはハッとしたように腰のレーザー銃を手にとり、ゲイトはふぅという溜息と共に肩を竦めた。余り焦っている様子はなさそうだった。
うーんと何かを考え込むような仕草でメカニロイド達を見詰めるゲイト。元々科学者型として開発されている彼に武装などある筈がない。
ウィドはじわじわと研究室内に入り込みつつあるメカニロイド達にレーザーの照準を合わせつつ、未だに焦る素振りすら見せないゲイトを怒鳴りちらした。
「ふうむ、成る程。もしかしたらこれもリミテッドの仕業かもしれないな。
ボク達・・そしてセイアのいるハンターベースを直接襲撃する。それもセイアが休息している隙をついて。
かなり大胆な作戦だけど、意外と効果があるものだね」
「呑気に解説をしてないでアンタも構えろ!来るぞ!」
「まぁまぁそんなに力む必要はないよ。それよりボク達はマザーコンピュータに侵入したウィルスを除去することを考えないと」
「この状況が見えないの・・・か・・?」
怒鳴り声を上げようとしたウィドは、別の角度から飛び込んでくる第三者の叫び声に、その怒声を掻き消された。
「おぉぉぉぉっ!!」
その声が聞こえたのは、メカニロイド達の向こう側。つまり廊下の方からだ。
ふふんと余裕なゲイトと、突然の第三者の乱入を尻目に、研究室いっぱいを占拠しつつあったメカニロイド達の機体は次々と宙へ浮かぶと、
スッスッと廊下の方へと消えていく。
どんどん彼等の個体数は減り、遂には廊下が見えた。ウィドが素早く廊下へ駆け出し、メカニロイド達が消えていった方向を覗くと、
そこには暗黒の球体が浮遊していた。天井すれすれに存在するそれに、次々とメカニロイド達が呑まれ、消えていくのだ。
「これは・・!」
新たな敵かと思いきや、その球体は全てのメカニロイドを呑み込み終えると、ふっとその命を散らした。
あとには球体のコアだっただろうメカボールが残っていただけで、そのボール自体もそれを放っただろう人物の方へと還っていった。
「ウィド、大丈夫!?」
「セイアか!」
パシッとボールを掌で受け止めたのはセイアだった。紅のアーマーに身を包み、戦闘形態と姿を変えた健次郎。
そこでウィドはようやく理解した。先程次々とメカニロイド達を呑み込んでいった暗黒の球体の正体を。
バグ・ホールだ。かつてのドップラーの反乱での闘いの際、エックスがグラビティ・ビートブートから入手した特殊武器。
人工的なブラックホールを短時間作り出し、標的を呑み込み、消滅させることの出来る汎用性の高い武器だ。
その規模はほぼ完全に自由とさえ云われていて、最小は微生物レベル、最大は地球サイズをも作り出す。
セイアの放つバグ・ホールは改良が加えられていて、設定した対象のみを標的とし、消滅させることの出来る機能が追加されている。
これによってセイアは大量のメカニロイド達を薙ぎ倒しつつ、研究室まで辿り着いたのだろう。
「補助メカニロイドがイレギュラー化している・・。ウィド、これは一体?」
「どうやらマザーコンピュータをやられたらしくてね」
ウィドが質問に応えるより先にセイアの疑問に答えを手渡したのは、研究室からひょこっと顔を出したゲイトだった。
「マザーコンピュータを!?」
「かなり強力なウィルスを流されたらしいんだ。最善を尽してみたけど、ここでの操作やワクチンは全く通用しなかったよ」
「ならマザールームに直接ワクチンを入力しに・・」
「無理だね」
ウィドの意見はすっぱりと否定された。ゲイトがここまで単刀直入に物事を否定することは珍しい。
それ程までの事態なのだろうということは、容易に想像出来ることだった。
「確かにマザールームに行ってワクチンを入力すれば理論的には平気だろう。
けどボクがマザーにウィルスを流すとしたら、まずはマザールーム自体を完全にシャットアウト。更にあらゆる入口に防御策を張り巡らせるけどね。
君は違うのかい?」
「・・確かに、ご最もだ。だが、他に手は・・」
云いかけて、ウィドは沈黙した。ワクチンという科目において自分と遜色ないゲイトがこうまで云うのだ。
ウィド自身がどうこうしたところで結果は同じだろう。けれど他に手がないこともまた然り。
これにはゲイトも黙ってしまった。いつもの余裕の笑みは相変わらずだが、きっと内心では酷く焦っているのだろう。
セイアがあらかたバグ・ホールでメカニロイド達を掃除してくれたお蔭か、メカニロイド達の追撃はなさそうだったが、このままではどちらにせよまずかった。
メカニロイド達は比較的簡単に倒すことが出来るだろうが、問題なのはデータベースの方だった。
イレギュラー・ハンターのデータベースには、これまでのハンターの歴史や隊員一人一人のデータなどが細かく入力されている。
その中には勿論セイア・・ロックマン・セイヴァーをはじめ、エックスやゼロのデータも残っている。
セイアはいつもこのデータベースから引き出される情報をもとに、メンテナンスやアーマーの修復を行っている。
そして何より、ウィドとゲイトが今まさに誕生させようとしている新兵器も、ここのデータベースに残っているエックスとゼロのデータをフル活用しているのだ。
今ここでデータベースを破壊されれば、もはやリミテッド達と闘う術は消滅してしまう。要約すれば最高の問題はこれだ。
「ウィド、Dr.・・」
これはセイア自身も充分承知している事実だった。
だからかもしれないけれど、セイアは沈黙する二人の科学者に、何かを決意したような瞳を向けた。
「僕が、そのウィルスを倒しに行きます!」
「なんだと!?」
「・・・・セイア、本気で云っているのかい?」
息子の発言に初めて表情を強張らせたゲイトは、いつもよりも数段低い声でそう問いかけた。
普段の彼を知る者ならそのギャップに驚くことだろうが、セイアはただコクンとだけ頷いた。
その仕草が、彼の発言を冗談から出たものではないことを証明してくれた。セイアは本気なのだ。
「僕がマザーコンピュータにダイヴしてウィルスを倒せばなんとかなります!」
「・・それがどれだけ危険なことだか判っているかい?」
「・・・はい」
「セイア。仮にお前がダイヴし、仮想ボディでマザーコンピュータ内に侵入するとしよう。
だがこの状況では一度ダイヴするのが限界だし、そのウィルスを除去するまで戻ってはこれないぞ。
そして・・」
ウィドは敢えて言葉を切った。この続きを云うことが恐ろしかったからだ。
確かにセイア自身のプログラムをマザーコンピュータにダイヴすれば、
セイアはあたかも現実世界での闘いかのように、マザー内でウィルスと対戦することが出来る。
しかしそれは極めて危険な行為だ。ウィドの云うとおり、この状況下でレプリロイドをマザーコンピュータにダイヴさせること自体が自殺行為だ。
下手をすれば仮想ボディが形成される前にウィルスに攻撃され、プログラムが消滅する。
そしてそれは電脳空間内で力尽きることも同意義のことだ。ログアウトが出来ないということは、電脳空間内で瀕死になろうとも決してそこから出ることが出来ず、
仮にそこで力尽きれば、セイアは彼をセイアとして形成している全てのプログラムを失うことになる。
人間で云えばそれは、『死』、だ。
「だけどこの状況を打破しなくちゃいけないのも事実だ!」
「だが・・!」
「ウィド君、やらせて上げよう」
尚も食い下がろうとするウィドを制する為に、ゲイトは彼の肩に手を置く。
表情こは余り崩れてはいなかったが、ウィドの瞳は歪んでいた。これも友を心配してのことだろう。
ゲイトも同じ気持ちだったけれど、ハンター専属の研究員として、マザーコンピュータが破壊されることを見過ごすわけにはいかないのだ。
「だけどね、セイア。一つだけ条件がある。それを呑んでくれなければ、君を電脳世界に送ることは出来ない。いいね?」
「はい」
「ウィルスを撃破し、必ず生還すること。電脳世界内での消滅は許さない」
「判りました。必ず生きて帰ります」
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
サイバー・スペース。一般的に電脳空間のことを指す言葉だ。
この空間はプログラム配列を持つ電子機器全てに存在している。
家庭用の電子レンジから、ハンターベースのマザーコンピュータまでありとあらゆるものに。
その実体は文字どおりプログラム配列だ。サイバー・スペースとは、それを擬似的に現実世界のものに見立てた際の言葉であり、
基本的にコンピュータにレプリロイドやメカニロイドがダイヴ――メインプログラムをインストール――した時にだけ使用される。
プログラム内にダイヴしたレプリロイドは、そこで作用するソフトウェアの力により、
サイバー・スペース内をあたかも現実世界かのように運動することが出来る。
無論それは視覚的・感覚的なものであるから、ダイヴしている本人以外にそれを知覚することは出来ないのだが。
プログラムに直接ダイヴしたレプリロイドは、その場で万能プログラムと化す。
内部のプログラムに攻撃行為を行えばそれを破壊することが出来るし、逆に修理を行うも出来る。
そう・・つまりロックマン・セイヴァーは自らがワクチンとなってウィルスを消去しに向かうのだ。
スペース内に蔓延っているウィルスプログラムを直接攻撃し、消滅させることが出来れば、その時点でマザーコンピュータにアクセスすることが可能となる。
が、そんなダイヴ行為にも、代償としてあらゆる危険が付き纏う。
ダイヴを決行中のレプリロイドは完全無防備だ。ボディやプロテクトといった防御機能が全て外された、いわば丸裸であり、
最もデリケートな部分を露出した状態となる。
しかもプログラム内にインストールするのがメインプログラムである以上、それは実戦よりも遙かに危険なことが明白である。
もし仮にダイヴしたレプリロイドがサイバー・スペース内で撃破されるようなことがあれば、その崩壊は一気にメインプログラムを侵食し、破壊され、
繋ぎ止める間もなくその人格を消去するだろう。
それはつまり人間でいう『死』、だ。ボディが無傷であるから、その死は更に質が悪い。
だがしかし、サイバー・スペース内で死亡したレプリロイドを復活させる手段は確かに存在する。
ボディや頭部が破壊されていない以上、法律上でもそれは『死』とは認識されず、単に行動不能に陥ったと判断されるからだ。
レプリロイドの再生を行う方法は実に単純明確。それは、全く同じプログラムを組み直し、そこに残された記憶メモリを植え付ける。
たったそれだけだ。たったそれだけで、あたかも生前の人格を再生したかのようにそのレプリロイドは復活する。
だが、それは――
「だがそれは・・本物のセイアじゃない。同じ記憶を持った『別人』だ」
セイアのメインプログラムがマザーコンピュータにインストールされ始めた。
ウィドは、ふとゲイトが呟いたレプリロイドの再生方法に対して、そう漏らす。
幸いなのか否なのか。セイアは既に目を瞑っており、彼等の会話は聞こえていないようだった。
「・・そうだね。そうかもしれない」
マザーへのセイアのインストールは、ウィドのモバイルを使用して決行された。
当然だと云えば当然の結果だろう。マザーに直接近づくことが出来ない以上、外部からアクセスするしか手はない。
だがベース内の全てのコンピュータはマザーに直結している為、その全てがウィルスに侵されている。
ただ一つ生き残ったのは、完全隔離状態であったウィドのモバイルだけだ。
だが、それを使用してセイアのインストールを行うことが出来るのもたった一度だけだ。
マザーにアクセスした時点でウィルスが逆流し、瞬く間にプログラム内に侵入していくだろう。
まさに片道切符。セイアが現実世界に戻る為には、マザー内のウィルスを撃破するしか手立てはないという、残酷な一本道。
「セイアのオペレートを行える限界時間は?」
「ウィルスの侵入が思ったよりも素早い。保って三十分といったところかな・・。こちらからのデータ転送も一回が限界だ」
セイアのインストール状況を映し出すバーは、既にその半分以上が完了を意味している。
あと一分もしないうちにセイアはサイバー・スペース内に降り立つだろう。だが問題はそれからだ。
誤作動するウィルス・バスターやファイア・ウォール。迷路のような進路を潜り抜け、セイアを最深部へと導かなければならない。
ウィドが云ったように、その限界時間はたった三十分。セイアがダメージを受けた際に転送出来るリペアプログラムも一回が限界。
もしこれがマザーの暴走という最悪の事態でなければ、他のハンターは絶対に行わない絶望的な作戦だ。
それでもやらなければならないのだ――セイアも、ウィドも、ゲイトも、同じことを考えていた。
「インストール完了・・。よし、セイア。聞こえるか?」
「ここが・・マザーコンピュータ・・」
知識としては持ってはいたものの、セイアがサイバー・スペース内に降り立ったのは生まれてこの方これが始めての経験だった。
辺りはまるで星空のように煌めいている。あちこちに拡がる意味不明の二進数や、破壊されたクズデータの数々。
確かに身体は現実のものと相違無く動かすことが出来るけれど、ここが現実だとはどうにも信じられそうにはなかった。
『セイア、聞こえるか?』
ヘルメットのイヤー部分の通信機――実際は違うが、違和感をなくす為にそう設定されている――から、少し不安げな声が聞こえてくる。
知識ある者独自の不安だろう。辺りから接近する敵影がないことを充分確認してから、セイアは素早く答えた。
「こっちは大丈夫。それよりも、思ったよりデータの崩壊が激しいみたいだ」
『そうか・・。どっちにせよこっちのオペレート時間も限られているんだ。素早く進んでくれ』
「判った!」
そしてセイアは仮想ボディのメットバイザーを下ろした。インストールの際にウィドかゲイトがデータを入力しておいてくれたらしい。
マザーコンピュータのサイバー・スペース空間の見取り図が記されている。
現在セイアが立っているのは第一階層。ウィルスが潜んでいると考えられるエリアは第六階層だ。
それまでには幾つものファイア・ウォールやウィルス・バスターが潜んでいる。下手をすれば第六階層に辿り着く前に撃破されてしまいそうだが、
仲間内のウィルス・バスターに撃破されることよりもみっともないことは無い。一気に潜り抜ける他なさそうだ。
『第二階層へと続く道はマップに入力されている筈だ。ウィルス・バスターが作動したらこちらで報告する』
「・・了解。
第十七精鋭部隊副隊長・ロックマン・セイヴァー。これより任務を開始する。
任務内容はマザーコンピュータ内のウィルスの削除。ならびにそれの奪還である」
他の十七部隊員達はベース内のメカニロイド掃討にかからせているので、
事実上ここに存在する十七部隊隊員はセイアのみだ。
けれどセイアはわざと声に出して報告する。この号令はエックスがいなくなったあとから、一度も欠かすことなくしているものだ。
かつて部隊長であったエックスがそうであったように、セイアもその姿を追い掛けているのかもしれない――
『二時の方向にウィルス・バスター。数は二だ』
「了解・・!」
セイアが走り出したのに合わせるかのように、ウィドの指令がイヤー部分で響く。
セイアは指示通りに二時方向にバスターを放つ。が、流石はマザーのウィルス・バスターというべきか、
セイアの光弾を軽く回避した二体のウィルス・バスターは、現実世界では不可能な動きで、セイアとの間合をグッと詰めた。
「電脳内では自由自在ってことか・・!けど!」
なんとも形容しづらい形の二体のウィルス・バスターを前に、セイアはバックパックに搭載されている二本の柄のうち、左側のものを抜いた。
エックス・サーベルだ。瞬時に刃を具現化したサーベルで、セイアは飛び上がり様に電刃を放った!
現実世界とはほんの少し違う、グラフィックの電撃をまき散らす刃が、右側の敵機を破壊する。
運良く躱した左側だったが、セイアが着地するよりも前に放ったホーミング・トーピードによって、一秒後に粉々に爆散した。
ほぼ同時に足元に落下した二体分の破片は、地面に激突すると共にクズデータとなって崩れ落ちた。
成る程プログラム内では不必要なデータは即座に削除されるのかと納得しつつも、自分が撃破された時は同じ運命を辿ると思うと、
ほんの少し背筋が凍りついた。
『上手く撃破したな、だが第二階層前のゲートにファイア・ウォールがある』
「ファイア・ウォール・・。突破法は?」
『本来なら解除コードを検索し、入力するところだが・・生憎そんな時間はない。正面から突破しろ』
「乱暴な手段になるね・・」
『安心していいよ、セイア。幾ら壊したところで、操作が可能になれば幾らでもリカバリーが可能だろうからね』
通信に割り込んできたゲイトの声は嫌に楽観的だ。
が、それも悪くない。セイアは苦笑混じりの笑みを口もとに浮かべると、そろそろ見えてきた最初のファイア・ウォールを確認した。
流石はファイア・ウォールと名を冠するだけのことはある。セイアは冗談混じりにそう思った。
その外見は文字どおり炎の壁だったからだ。絶えることを知らない、空虚な空間から生み出される灼熱の炎。
確かにあれに無条件で触れれば、大抵のウィルスは地獄の業火に焼き尽くされることだろう。
だがセイアは違う。ファイア・ウォールの真正面で立ち止まると、肩幅に足を開き、両掌を腰の辺りで繋げ、構える。
手首の辺りで繋げられた両掌の間に、蒼と紅のエネルギーが除々に収束されていく。
それは、セイアがついこの前の学校内での闘いの時に新たなに手に入れたスキルだ。
両掌に集中させた高出力圧縮エネルギーを、線ではなく弾として撃ち出す一撃必殺。
その名は――
「波動拳!」
両手を回転させつつセイアがそれを前方に突き出すと、巨大なエネルギー弾が撃ち出された。
綺麗に蒼と紅の染められた炎に似たその弾は、燃え盛る炎の壁に直撃するやいなや、それをガラスが砕け散るかのように破壊せしめた。
見た目とは裏腹にパキンと高音を立てて砕けるファイア・ウォールを尻目に、セイアは走る!
現在位置は第一階層。目指すは第六階層。道のりは・・長い。
「波動拳、使えるなこれ」
『云っておくが今のお前より強い奴はそうそう見つからないぞ』
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
感覚が、薄い。視界は既に真っ黒に塗りつぶされ、指先すらピクリとも動かない。
さっきまでの不快感もない。除々に身体が舞うような浮遊感を憶えつつも、それとは裏腹に酷く身体が怠い。
必死に振り回したつもりの四肢は空を掻く。いや、四肢を動かしているような感覚すらそこにはなかった。
声を出そうとしても何も起こらない。まるで、虚空に自らの精神だけが置き去りにされたように。
あやふやになりつつある自らの記憶の中から、なんとか重大な部分を掘り起こす。
それでもハッキリとはそれが理解出来なくて、彼はもしかしたら自分が死んでしまったのではないかという仮説だけに行き着いた。
死とは無限の虚空。果てない孤独。それについて考えるようになったのは兄が死んでからだ。
自分が死んだとき、一体自分はどうなってしまうのだろうか。人間でもレプリロイドでも、一度はそう考えたことがあるだろう。
ある者は云う。死は絶対の結末だ。死の後には何も残らない、と。
しかしある者は云う。死とは一つの結末であり、一つの始点だと。
だが彼はそのどちらの考えにも同調はしなかった。
死とは無限の虚空。果てない孤独。何も無い真っ暗な空間に、完全に機能しない意識だけが放り出される。そんな、闇の世界。
そこでは身体という感覚も、自分という個体も、他人という存在もなにもありはしない。
あるのはただの真っ暗な空間のみ。そして、それを嘆くことすら許されない空虚な自分。たった、それだけ――
「・・・・・――・・」
声は出ない――当たり前だ――そんなことを考える自分の意識もそろそろぼやけ始めるだろう。
なにせ自分は死に直面しているのだから。その内自分は完全に消滅することも、復活することも許されぬまま闇に同化する。
そう、このまま。
薄ぼんやりとした意識の中で、彼がそんな幻想を許容しようとしているとき、彼とは違う別の声が囁いた。
『ヤァ、セイア』
「・・・・――?」
突然目の前に光球が現れた。ダークグリーンの光球だった。
どうやらその声はそこから発せられているらしく、その声に合わせて光球は点滅する。
光球はふよふよと浮遊し、くるくると自らの周りを回り始めた。彼にはそれが、踊っているかのように軽やかに見えた。
『コンナ真ッ暗ナ場所デ・・君ハ消滅シテシマウノカイ?』
「――・・――・・・」
何かを呟いたつもりだったが、声にはならない。
それが可笑しいのか、光球は更にはしゃいだように点滅し、弾んだ声で彼を誘う。
『勿体ナイナ。君ハマダマダ生キテユケルトイウノニ』
「・・・く・・は」
声が出た。少なくとも、自分の声として知覚出来る音の波が。
まるで光球が彼の周りを回れば回る程、彼の機能が戻っていくかのように。
必死に声を絞りだそうと喘ぐ。が、それでもまだ充分に声は出ない。
けれど意識は急速に鮮明になりつつあった。少しずつ少しずつ、『自分』という感覚が戻っていく。
『君ダッテマダ死ニタクハナイデショウ?』
「・・僕・・は・・っ」
『フフ。ダカラネ、ボクガ君ヲ助ケテアゲルヨ』
「僕を・・助け・・?」
『ソウ。ソウスレバ君ハ、生キルコトガ出来ルヨ。今ヨリモモットモット強クナッテネ』
「・・くっ・・ぅ」
あやふやの意識を、鮮明になりつつ意識が引っ叩いた気がした。
まるで暗闇の中で突然照明をつけられたかのように、意識の電気炉に電気が走る。
拳を握れと身体に命令する。見えはしないけれど、確かに拳という感覚がそれに応えた。身体が重力を感じ始め、半開きの瞳が開かれる。
「・・違・・う!」
違う。これは『死』なんかじゃない。この感覚は以前にも味わったことがあるのだ。
それがいつだったは思い出せない。きっと今思い出す必要もない。
けれど彼、セイアには判った。これは死でもなんでもない。これは――幻想だ!
「これ・・が・・!」
今まで身体を支配していた気怠さを強引に振りほどくように、セイアは全身に力を込めた。
ブチンと何かが弾けた音がして、身体の自由が投げ返される。
今まで楽しそうに踊っていたダークグリーンの光球は、それが不満なのか、ピタリとその動きを止めた。
「・・っ!これがお前の手か!」
そして完全に自らの者となった全身で、セイアは光球にバスターを向けた。
「人の心の隙に付け入って、再びボクを取り込む・・・。確かに有効的な手段かもしれない。
けど、その根性は相変わらずだなっ!」
そして自らの心を惑わそうとした自らの影の名を叫ぶ!
「イクセっ!!」
『・・ふ、あはははは。腐っても鯛だね、セイア?
同じ手を二度も使うなんて、君を舐めてたよ。これは失礼』
光球は人型へと変わった。見たくもない、ダークグリーンと変色したセイアの姿に。
セイアはギリッと歯軋りをしつつもチャージしたバスターを放つ。自らの闇を、そしてこの空間を斬り裂く為に!
「ボクの心はボクのものだ。お前には決して渡さない!」
『ふふふ。楽しみにしているよセイア。君と闘えるときのことをね』
そして蒼と紅のエネルギーは、文字どおり辺りの闇を斬り裂いていった。
「おぉぉおぉぉおぉぉっ!!」
所狭しと仮想ボディに貼り付いた金色の光球が、セイアの叫びと共に次々と砕け散った。
セイアはデタラメに全身を動かしながら、自らを侵す光球達を払っていくと、
さっきまで全く手応えがなかったそれらは、セイアの振り回す手足に砕かれ、クズデータとなってデリートされていく。
「お前等・・ぁっ!」
懲りずに殺到してくる光球を一瞥しつつも、セイアは身を翻した。
バッと全身で前方に何かを撃ち出すような仕草をとるセイアから、彼の輪郭を模した光の人型が前方へと駆け抜けた。
それをターゲットだと誤認した球体はそれに吊られ、激突していくものの、光の人型に触れた途端、それらは砕け散った。
所狭しと駆け巡る光の人型が放たれて僅か十数秒後、辺りの金の球体は数える程になってしまっていた。
「イクセめ・・。厄介なものを」
それはエックスがレプリフォース大戦内でスプリット・マシュラームより入手したソウル・ボディだった。
高圧縮エネルギーによって自らの分身を作り出し、相手にぶつける。その用途は撹乱から奇襲まで様々だ。
そしてなによりの特徴は、そのエネルギー密度。ソウル・ボディを形成するエネルギーの密度は、バスターやサーベルの比ではない。
そう金色の光球の正体は――マザーを脅かすウィルスそのものだ。
バスターやサーベルのエネルギー密度では破壊することが出来ない、非常に柔軟性に富んだ設計の。
だから今までのセイアの攻撃は全て通用しなかった。これを破壊する為には、これよりもエネルギー密度が高く、尚且つ攻撃力の高い武器を使用するしかない。
「もうお前達の弱点は判った。もう・・お前達にボクは止められない!」
残った数体の光球が、セイア目掛けて襲い来る。
が、もはやセイアの瞳に恐れも戸惑いも無い。
空円舞を駆使して空中へと大ジャンプし、追跡する形で追ってきた球体・・いや、ウィルスに天空覇を添加した空円斬を叩き付ける!
数えて七体のウィルスは、その場でスパンと真っ二つにされ、消滅する。
綺麗にスタンと着地するセイア。それとほぼ同じタイミングで、ウィドの通信がイヤー部分に響いた。
『・・ア、セイア!セイアっ!!』
「聞こえるよ、ウィド。五階層のエネミーは全部やっつけ・・」
『馬鹿野郎!』
いきなり怒鳴り付けられて、セイアはハトが豆鉄砲を食らったような顔をしてしまった。
通信の奥のウィドの顔は見えないけれど、その声が尋常でない程怒っているのは、セイアでなくても判る。
ウィルスを相手に戸惑いを見せなかった戦士は、怒った親友に身を縮めつつ、彼の名を呼んだ。
「ウィド・・」
『・・馬鹿野郎。心配かけさせやがって』
「・・ごめんね。でもボクは大丈夫だ」
『・・無事ならいい』
現実世界では、わなわなと震える手でイヤホンマイクを握り締めるウィドの姿があった。
本来なら、そこでゲイトがクスリとでもウィドに笑みを浮かべることだろう。けれど、ウィドも気が付かない間にゲイトの姿はそこにはなかった。
いつの間にいなくなったのか。ウィドがそのことに気が付くのは大分後かもしれなかった。
『全く・・無茶をする。お前も、ゼロも・・』
「え、何か云った?」
『いや、なんでもない。それよりも時間がない。第六階層へ向かうんだ』
「う、うん。了解!」
実際Dr.ゲイトは研究室のドアの前で闘っていた。というよりも、立っているだけに等しかった。
今のイレギュラー・ハンターの隊員数は非常に少ない。最近ようやく部隊制が戻ったといえど、その数は全盛期の半分にも満たないだろう。
だからこそ遠隔操作のメカニロイドが複数配備されているのが現状なのだ。結果的に云えば弱体化し減少した現状のハンター達は、
自らの下僕を止める術を持たない。一体一体ならばどうにかなろうものだが、数の勝負となると圧倒的に不利だ。
これはウィドも考えていなかったことなのだが、セイアがマザーにダイヴするにあたっての最大の問題は研究室の防衛だった。
隊員たちの宿舎から遠いこの研究室は、格好の標的だ。そんな場所で呑気にコンピュータを弄くる時間を与えてくれるメカニロイド達ではない筈だ。
だからこそ、ゲイトがいまここで研究室を護っているのだ。彼曰く『ボクの城』である研究室を。
「ふうむ。やっぱり予算が足りなかったのかな。ボクの作品にしては性能が低いみたいだね」
Dr.ゲイトは科学者型レプリロイドだ。
だがかの有名なナイトメア事件発祥の張本人である彼は、ゼロのDNAデータを元に造り出した自らの鎧でエックスと闘ったという前歴を持つ。
勿論ゲイト本人の戦闘力はハンターであるエックスには遠く及ばない。それでも彼がエックスと闘い、彼を大いに苦しめた理由がこれだった。
「最も一体一体にこのボクのナイトメア・アーマーが破壊されるようなことは有り得ないんだけれどね」
今、ゲイトの全身は金色の鎧に包まれている。おおよそけばけばしいと形容しても過言ではないほど、キンキンに輝くド派手な鎧。
それがゲイトの云うナイトメア・アーマーであり、エックスを大いに苦しめた要因であった。
ゼロのDNAのデータをフル活用して作成されたこの鎧は、かつてのハイマックスの剛性を大きく上回る。
その剛性はエックスのフルチャージの一撃をも全く受け付けない程だ。それ程の剛性を持つ鎧が、たかたが量産型メカニロイド程度に破壊されうる筈もない。
ゲイトはただ単純にある程度のメカニロイドが群がってきたところで、ナイトメア・ボールと名付けられたエネルギー弾を投げるだけで良かった。
「ふふふ。ボクの城には指一本触れさせない。その代わり、君達にはボクの美技をとくと見せて上げようじゃないか!」
今のゲイトを止めることは、恐らくセイアでも不可能であろう。
「ようやくここまで辿り着いた。さぁ、姿を現わせウィルス!」
第六階層へ辿り着くや否や、セイアは声を張り上げた。
声の波というデータは、プログラム配列の隅から隅までを走っていく。現実世界の常識が通用しないここならば、きっとどこまでも声の波は届いたであろう。
マザーコンピュータの第六階層。そこはイレギュラー・ハンターの最も深い領域であり、同時にマザーのCPUの中枢。
確かにここを攻撃されればマザーは容易く墜ちるであろう。問題は、ここまで辿り着く程の強力なプログラムがあるかどうか。
――事実マザーが暴走しているのだから、その答えはYesなのだが。
さっきまでの第一階層から第五階層と較べ、第六階層の作りは偉く単純だった。
簡単に現わすとすれば、真四角のただっ広いフィールド。その側壁にはさっきまでと同じ模様が走っているが、目立った突起物はどこにも見受けられない。
本当に正真正銘の最深部なのだろう。何故かセイアはその作りに納得してしまった。
「・・・!」
セイアの声が隅から隅まで届いたのを見計らったかのように、セイアの斜め上に光の輪郭が現れ始めた。
ブゥンという不可解な効果音を発しながら、それは少しずつその姿を形成していく。
セイアが想像していたものよりも随分と現実味を帯びた姿だと思う。
思いの外それは人型だった。いや、動物をモチーフにした人型レプリロイドといった方が正しいのかもしれない。
赤紫の外装に、大きく伸びた複数の羽。ゲイトのアーマーと同じくらいけばけばしいその姿に、セイアは確かに見覚えがあった。
同時に今までの事柄全てに合点がいく。マザーの暴走も、さっきの複数のウィルスも。
セイアは呟く。ハイパー・リミテッドの恩恵を受けたであろう、黄泉より蘇った電脳世界の狂気の名を。
「サイバー・クジャッカー・・」
自分の名を呼ばれ、クジャッカーはクックックと狂気的な笑みを浮かべる。
するとふっと彼の姿が掻き消え、すぐにセイアの目の前へと現れた。
電脳世界においてクジャッカーは全ての法則を無視して移動することが出来る。
このフィールドは、いわばクジャッカーのクジャッカーによるクジャッカーの為の戦闘領域だ。
現実世界より参入したセイアは、この状況において極めて不利。
それを理解しつつも、セイアはエックス・サーベルを抜くほか無かった。
コイツが暴走の原因である以上、例えここが奴専用のフィールドであろうとも闘わなければならないからだ。
『セイア、もうオペレートの限界時間が迫っている・・!イ・・ア、・・ア!』
「ウィド!・・一人で闘えってことか」
ウィドの声が聞こえたのはほんの数秒だけで、すぐにその声はフィードアウトしてしまった。
本当に限界時間を過ぎてしまったのか、それともクジャッカーがジャミングしたのかは判らない。
けれど確かなことは、ウィドの助言を得ずにコイツを倒さなければならないこと。それだけだ。
「・・けど、それでも構わない。兄さんもたった一人でお前と闘い、お前を倒したんだ。ボクだって!」
戦闘体制を整えたセイアに、クジャッカーは狂気的な笑みでそれを迎える。
リミテッドによって暴走した意識でも理解出来たのだろう。これから楽しい『狩り』が始まる、と。
彼はリミート・レプリロイドにしては珍しく言葉を吐いた。もはや意味を理解することがやっとの、機械的な口調だった。
『オ仕置キノ時間ヨ』
「行くぞ・・!」
気合の声と共に、セイアは地面を蹴る!フルスピードのダッシュの瞬発力を利用し、クジャッカーの懐まで飛び込んだセイアは、
斬り上げる形で燃え盛る龍炎刃を薙ぐ!
データにあるクジャッカーの弱点攻撃はソウル・ボディと龍炎刃。もっと云えば、高エネルギー密度を持つ武器と、炎属性を持つ武器だ。
セイアの武装リストを漁れば、そんな武装は幾らでもある。クジャッカーがエックスと闘ったときよりもパワーアップしていることは明白だが、
セイアには数知れない武装の利がある。
「っ!?」
だがセイアの龍炎刃は空を掻いた。
これが現実世界であれば確実に斬り込まれていただろう刃は、クジャッカーが直前で姿を消した為に外れてしまったのだ。
すぐに着地してクジャッカーの居場所を突き止めようと身体を捩るセイアだが、それよりも早くクジャッカーがセイアの背後に現れ、
その孔雀を模した大きな羽の一撃を彼の背に突き立てた!
落鳳破の元となったクジャッカーの羽の一撃は、成る程確かにエネルギー消耗の激しい技の元となっただけの威力がある。
すれすれで飛燕脚により急所を外したのは幸いだったけれど、このダメージはかなり重い。
飛行途中でバランスを崩され、セイアは地面に激突する形で先程の目的を果たした。
「ぐっ・・!ちぃっ!!」
起き上がり様にチャージ・ショットを見舞うが、やはり直撃の寸前でクジャッカーは姿を消してしまう。
どこだ――セイアはクジャッカーの姿を追うものの見つからない。だとしたら、クジャッカーは・・・自分の背後にいる!
「くっ!」
再び落鳳破の一撃を受けそうになりながらも、咄嗟に発動させた氷狼牙がセイアを救った。
瞬時に天井までの大ジャンプを行い、難を逃れたセイアは、そのまま天井を蹴り、断地炎をクジャッカー向けて放つ!
流石にクジャッカーの処理速度もついてこれなかったのか、断地炎の炎がクジャッカーを包む。
男性型にしては高過ぎる気色の悪い声で悲鳴を上げつつ、炎上したクジャッカーはのたうち回る。
セイアはその隙を見逃さない。すぐに両掌にエネルギーを収束させると、一撃必殺の波動拳を二発!
「時間がないんだ。眠れクジャッカー!」
が、セイアの波動拳が放たれるよりも、クジャッカーが断地炎の炎から逃れる方がほんの少し早かった。
波動拳がクジャッカーの残像を砕く。「なに!」とセイアが声を上げた瞬間には、セイアの背をエネルギーの槍が打っていた。
前につんのめりそうになりながらも、セイアは前転する形でなんとか体制を立て直す。
槍の飛んできた頭上を見上げると、両手を大きく伸したクジャッカーが眼下のセイアを見ていた。槍だと思っていたのはクジャッカーの羽だったのだ。
よくよく見ればセイアの胴の部分にロックオンのグラフィックが重なっている。恐らくあれがエイミング・レーザーの元となった技に違いない。
「くっ・・。人の背後ばかりを狙う戦法は相変わらずか」
エックスが闘ったクジャッカーも、場所は違えどサイバー・スペース内のものだった。
その際もエックスは背後ばかりを取るクジャッカーの戦法に苦しめられた。全く兄弟揃って舐められたものだと、セイアは舌打ちするが、
この状況を打破出来ないのであればどうしようもないこともまた事実だった。
『逃ガサナイワヨ』
「やる気だな・・!」
クジャッカーの無数の羽が、ホーミング弾として次々とセイアを襲う。
ロックオンされた標的をしつこく狙うホーミング弾は、止まることを知らない。データにはエイミング・レーザーには射程距離があると記されているが、
リミテッドによってパワーアップしたクジャッカーにそんなデータは通用しそうもない。躱すか打ち消すしかないのだ。
ある程度ダッシュと三角蹴りを駆使して逃げ回ったセイアだが、留まることを知らないクジャッカーの連射に、いつまでも逃げきることは不可能だった。
二、三発諸に受け止めてしまったセイアは、やがて躱すことを止めた。
真っ直ぐ一番遠い壁までダッシュで移動したセイアは、雨のように群がってくるエネルギーの槍の雨に、
バックパックの右側のセイバー・・ゼット・セイバーを抜いた!
「ボクがいつまでも逃げ回ってると思うなよっ!はぁぁっ!!」
エックス・サーベルとゼット・セイバーの二刀流!両の剣に同時に天空覇を付加し、更に双幻夢を使って己の姿を二つと分ける!
四本の刃が降り注ぐエネルギーの雨にを迎え撃つ。余りにも一瞬の間に数多くのエネルギーがぶつかった為、その付近一帯を爆風がさらった。
勿論双幻夢を駆使したセイアもその爆風に呑まれる。クジャッカーはその様を見てけたけたと腹を抱えて笑った。余りに悪趣味な笑いだった。
やがて爆風が晴れ、ボロボロの仮想ボディを抱えたセイアが姿を現わす。
メット部分のデータが吹き飛び、髪が露出し、肩アーマーは両肩共にない。酷く足りなくなった少年は、立っているのがやっとだった。
二本の剣のうち一本を失ったらしく、その手には申し訳程度に刃を具現化する光学剣が一本しかない。
それを地面に突き刺して杖代わりにしているのだ。今の彼に、攻撃力は殆ど残されていないだろう。
しかしクジャッカーに慈悲という言葉はない。無情にもカーソルをセイアの胴にロックオンすると、
再びエネルギーの雨を降らせた。今度は四つの天空覇など放てないセイアは、次の瞬間には砕け散るだろう。
そして仮想ボディを破壊されたセイアは死ぬ。メインプログラムを破壊され、完璧に消滅するのだ。
『オーッホッホッホッホ!!』
ザンっ!!
「砕けるのは・・・お前の方だ!」
『グギャアッ!?』
クジャッカーの笑いが止まった。
クジャッカーの胴には、光の刃が生えていた。
それを刺しているのは、キラキラと輝く紅の鎧に身を包んだ少年だった。
クジャッカーが悲鳴を上げると共に、雨のようなエネルギーに晒されたボロボロの少年のデータが消滅する。
もはや修復不能にまで破壊されたあのデータは、もう二度と同じ姿には戻らないだろう。
「双幻夢だ・・クジャッカー。お前が例えこの電脳世界で自由に動き回れるとしても、ボクはその更に上を行かせてもらう!」
そのままゼット・セイバーを振るい、クジャッカーを地面に叩き付ける。
そして自らも落下しつつ、ソウル・ボディを発生させる。
空中で停滞したソウル・ボディと、そのまま着地する本体。落下速度がやけにゆっくりだったクジャッカーより、セイア本体が着地する方が早かった。
セイアは握り締めた右の拳に炎を宿す。エックス・ラーニングがフル回転しているのだ。
セイアのプログラム内で、再び二つの技が一つになった。今回チョイスされた必殺技は、昇竜拳と龍炎刃。
共に対空攻撃の頂点に君臨する必殺技の初代と新米。その二つが完全に一つとなった時、
セイアは地面を砕くほど強大な炎と共に飛び上がった。燃え盛る炎を携えた拳と共に!
「神龍拳ーっ!!」
そして同時に神龍拳となった新ラーニング技のデータを転送されたソウル・ボディが、
空へ再び舞い上げられたクジャッカーに、炎の昇竜拳の連撃を見舞う。昇竜裂破だ!
『グギャアッアッァァツァッァァッァ!!』
新たなラーニング技を二発も受けても尚立っていられる程、クジャッカーは頑強ではなかったようだ。
全身にグラフィックの炎を燃え上がらせたクジャッカーは、なんとかそれを振りほどこうと空中でもがくが、セイアの炎は決して甘くはない。
除々にクジャッカーの身体を蝕んでいく炎。それでもクジャッカーはしぶとくセイアを狙おうとしているのか、
セイアの胴にカーソルを合わせた。
「まだ動けるのか・・!?」
が、クジャッカーのエネルギー弾がカーソルに届くことはなかった。
「君はもう用済みだ。足掻くのはみっともないよ」
「・・・!?」
ダークグリーンの閃光がクジャッカーを呑んだ。
余りにも一瞬の出来事だった。気配すら感じさせず、それを放った者はセイアの後ろにいた。
微かに煙の立ち昇るバスターをふりふりと振りながら、やってのけたこととは程遠い笑みでセイアを見る彼。
パラパラと落ちてきたクジャッカーのクズデータを見る目は、その笑みとは裏腹に酷く冷たかった。
「イクセ・・!」
「やぁ・・セイア。何を遊んでいるのかな?早くコイツを倒さないとマザーが危なかったんじゃないの?
その割には随分手を抜いてたみたいだけど。大きなお世話だったかな?あは」
「くっ・・」
「それとも・・これが君の実力だなんて云わないよね。そうだとしたら、ボクはガッカリしちゃうかな」
相変わらずの軽い口調には反吐が出る。云っていることは要約すれば「君はこんなにも弱い」・・ということ。
わざわざここに来たのはセイアに自分との力の差を見せる為か、それとも単に遊びに来たのか。
どちらにしても太刀合わせに来たことは間違いない。セイアは、キッとイクセを睨み付けた。
「あーん恐い恐い。そんなに睨まないで欲しいなぁ。そんなに慌てなくっても、君とはゆっくり遊んで上げるよ」
「何の用だ・・!」
「随分表情が硬いなぁ、セイア。学校に居たときはもっとにこやかだったじゃない。健次郎君」
いちいち人をおちょくったような言動を放つ奴だ。
セイアはカッと全身が熱くなるような感覚を憶えながらも、なんとかそれを抑えつけるコイツを相手に怒りを解放すれば、コイツの思う壺だ。
しかしイクセはセイアの感情を奥の奥まで理解しているのか、また嫌味っらしい蔓延の笑みを浮かべた。
「あれあれ?随分と気が立ってるみたいだね。ボクがそんなに気にくわないかい?」
「・・・」
「あはは。当然かもね。知ってるかい?
人は自分を見ると不愉快になるんだ。だから君はボクを認められない。ボクを見ると不愉快になるんだよ」
「だ、黙れ!ボクと闘いにきたのなら、素直にそう云ったらどうだ!!」
ブンッと頭を振って怒鳴るセイアだったが、それもイクセには通用しない。
イクセにはセイアの全てが判っている。セイアの性格も、セイアの感情も、セイアの闘い方も全て。
もしゼロが今のセイアを見たのなら云ったことだろう。「闘いの中で無闇に感情を乱すことは死を招くことだ」、と。
「闘いたいのは君の方じゃないのかい?うふふ、まぁいいか。どうせボクは君の云うとおり、君と遊びに来たんだから」
「くっ・・勝負だイクセ!!」
マザーの機能が完璧に戻ったというのに、再び闘いは始まってしまった。
セイアはすっかりダイヴアウトのことすら忘れていた。目の前の自分自身の影に、それ以外のものが見えなくなってしまっていたのだ。
『セイア!セイア、応答しろ!』
既に回復した通信で、何度もウィドはセイアに呼びかけていた。が、答えはなかった。
正確に云えば答えの代わりにセイアの怒声だけが聞こえていたと云うべきだろう。
「イクセぇぇぇっ!!」
「あはははは、そんな直情的な攻撃がロックマン・エックスの名を継ぐ者の闘い方かい?大笑いだよ!」
セイアのバスターはイクセを掠るすら出来ない。
紅の光弾の弾道を全て読みきっているのか、イクセはひょいひょいとわざわざセイアを馬鹿にするような動きでそれを躱し、
その度に嫌らしい笑い声を浴びせた。
セイアがゼット・セイバーによる接近戦を仕掛けると、イクセも同じようにバックパックのサーベルを抜き、それに応じた。
だがセイアの斬撃はどれも当たらない。イクセが的確に受け止める刃によって、セイアの斬撃は全て受け流されてしまうからだ。
「つまらない。つまらないなぁ、セイア。もっと本気で闘って欲しいよ」
「黙れ・・黙れぇぇ!」
「それともまだ本気になれないのなら、ボクがさせて上げるよ」
イクセのサーベルの動きが、セイアには全く予想出来なかった。咄嗟にガード・シェルを出して防御したつもりの攻撃が、
いつの間にか背後から放たれていて、セイアは地面に倒れ込んだ。
イクセの突きが、セイアの左胸を深々と裂いたのだ。これが現実世界なら一撃で機能が停止していただろう攻撃だが、
この電脳世界ではどこに心臓部があろうと関係ない。しかし受けたダメージが深刻なことに代わりはなかった。
立ち上がろうと地面に手をついても、ぶるぶると腕が震えて力が入らない。
どれ程の一撃だったのかが一目で判る程のダメージだ。少しずつ視界がぼやけ始めて、嫌らしいイクセの笑みから遠くなっていく。
「くっ・・・そっ・・ぉ」
「・・正直期待外れだよ、セイア。君がボクの宿主だったと思うと、本当に残念だ」
「っ・・ちっく・・しょぉっ・・」
――駄目ダ・・・コイツニハ勝テナイ
頭のどこかで誰かがそっと囁く。それは絶望的な言葉だった。
――コイツハ強スギル・・
自分の攻撃が全く当たらない。どんな技も、的確に躱されてしまう。
――ボクハ・・コイツニ殺サレル・・
視界がぼやけていくほど、頭の中の声は絶望の度合いを増していく。
勝てない。殺される。負ける。強すぎる。恐い。恐い。
コワイコワイコワイコワイコワイコワイコワイ
『諦メルノカ』
「だ・・れ」
もはや意識が半分以上消失したところで、セイアに呼びかける声があった。
ウィドの声ではない。かといってゲイトでも、勿論イクセのものでもない声。
肉声・・ではない。この電脳世界内で肉声というにもおかしな表現だが、ともかくそれは空気が振動して伝わってくる声とは違う気がした。
頭の奥に直接叩き込んでくるその声は、酷く機械的だった。まるで20XX年代のロボットのように。
『私ハ・・マザー』
「マ・・ザー・・?」
『ソウ。トハイエ、私ハソノ末端ニ過ギナイガネ』
「ふふ、どうしたの、もうお終いかい?最初の勢いはどこに行っちゃったのかなぁ」
マザー。そしてそれと話すセイアの声がイクセには聞こえないのか、彼は倒れ伏したセイアを余裕の笑みで見下してくる。
勝利と落胆の入り交じった声で話すイクセの笑みは、セイアには酷く嫌悪感の対象として映るだろう。
けれど今のセイアにそれはない。意識は頭の中で話すマザーの方へ向いてしまっていたからだ。
「ど・・して」
『セイヴァー。君ガウィルスヲ除去シタコトデ君ニアクセススルコトガ出来ルヨウニナッタノダ』
頭の中の声に意識を集中させながらも、セイアはぐっと身体を持ち上げた。
イクセはそんなセイアの抵抗が嬉しくて堪らないのか、ようやく起き上がったばかりのセイアを思い切り蹴飛ばした。
後方の壁まで叩き付けられたセイアは力無く呻く。それでもまだ痛ぶり足りないというのか、イクセはつかつかとセイアに歩み寄ってきた。
『・・セイヴァー、今カラ君ヲダイヴアウトサセル』
「なん・・だって・・!?」
『君モ判ッテイルコトダロウ、セイヴァー。目ノ前ノ敵ニ君ハ手モ足出テイナイ。デリートサレル前ニ・・』
「嫌だっ!」
「・・へぇ」
マザーに向けて怒鳴った声は、どうやら実際にも口に出していたらしい。
イクセは自らの拳を受け止めたセイアが、自分自身に向けて放った言葉だと思ったらしく、クスリと一つ喉で笑う。
力いっぱいの握力でイクセの拳を握り締め、セイアは思い切りそれを引き寄せた。
意外なセイアの握力に驚いたのか、イクセが抵抗するより先に、彼のダークグリーンの鎧が紅蓮の鎧に吸い寄せられる。
セイアは頭の中でマザーに必死で抗議しつつ、もう片方の紅蓮の拳をイクセの顎先目掛けて叩き込んだ!
『馬鹿ナ・・。勝チ目ガナイコトハ判ッテイル筈。ココハ大人シク引クノダ』
「嫌だ・・、嫌だ。コイツから逃げるなんて、僕は・・僕は!」
『マテセイ・・・・・。・・イイダロウ』
なおもセイアを引き留めようとするマザーの台詞は、途中で止まった。
またウィルスが再発したのかと思いきや、それは違う。次に紡いだのは、無謀とも云えるセイアの行動を承認する言葉だった。
「昇竜拳か。ドラグーンなんかより一味も二味も鋭いよ。けど・・それじゃあボクには勝てない」
『外部カラ君ニアクセススル者ガイル。インストール所要時間ハ約三秒。ソノ隙ヲ、私ガツクリダソウ』
昇竜拳を受けたイクセは、吹き飛ぶどころか顎すら仰け反らない。
顎の力だけでセイアの拳を押し返し、お返しとばかりに暗黒の炎を宿した昇竜拳でセイアを天井へと叩き付ける。
打撃の衝撃と衝突の衝撃を諸に受け止めたセイアは、受け身をとることもままならずに地面に激突する。
が、彼はまだ倒れなかった。頭の中で呟いたマザーの言葉を信じ、三度立ち上がったのだ。
「判った・・お願いするよ、マザー」
セイアに直接データをインストールしようとしている者。それは、セイアの予想通りウィドとゲイトだった。
現実世界では今丁度ゲイトがザコ掃除を終え、研究室に戻ってきていた。
ウィドは応答しないセイアに怒鳴り声を上げ続けていて、ゲイトが驚いて状況を確認した、ということだ。
「セイア、セイア!応答しろっ!!」
「ウィド君。そんなに声を上げては喉を壊してしまうよ」
「煩い!セイアが応答しないんだ。今セイアは・・!」
「・・・セイアと同じデータがダイヴした形跡があるね」
「・・何っ?」
ウィドの怒声とは裏腹に、落ち着いた仕草でキーボードを叩いていたゲイトが呟いた言葉だった。
ゲイトは「ふうむ」と疑問符を浮かべている様子だったが、ウィドは違った。
セイアと・・ロックマン・セイヴァーと同じデータ・シグナル。そんなものを持つ者は少なくともウィドの記憶の中では一人しか浮かばなかった。
「・・イクセだ」
「うん?」
「セイアは恐らくイクセと闘っているんだ。奴もマザーにダイヴしていたんだ」
「イクセ・・。ああ、確かセイアにそっくりなリミテッドの名前だったかな」
「・・だとしたら、セイアに勝ち目はない」
セイアは今、殆どなんの追加装備もない状態でマザーにダイヴしている。
各種アーマーのデータも殆どが破損していて、仮想ボディとしてですら強化することがままならなかったからだ。
追加装備があると云えばゼット・セイバーが新たなに追加されたのみで、あとは全くのノーマル状態。
そんな今のセイアがイクセに勝てる確立は殆ど無い。
恐らくはサイバー・クジャッカーとの闘いでエネルギーを消耗しているのだから間違いない。
「今すぐダイヴアウトを!」
「待つんだウィド君」
「なんだ。ダイヴアウトしなければ、セイアがデリートされちまう」
「だが仮想ボディをダイヴアウトの状態に切り替えなければダイヴアウトは不可能だ。
それを無理矢理実行したら、それこそセイアが消去されてしまうよ」
「ならどうしろって云う・・・。・・いや、待てよ」
ゲイトの胸ぐらに掴み掛かりそうな勢いだったウィドだが、何か思い当たる節があったらしく、わたわたと忙しく走り回り始めた。
何かを探し回っているらしかったが、なかなかそれが見つからないらしい。イライラし始めたウィドに、
ゲイトは懐から一枚のデータディスクを取り出して見せた。
「捜し物はこれかい?」
「それだ!」
ほとんどひったくる形でディスクを受け取ったゲイトは、すぐにそれをモバイルのスロットに差し込んだ。
ガチャガチャとキーが潰れそうな勢いでキーボードを叩く姿は、まさに鬼気迫る感じだな。
ゲイトはそう思った。
「その未完成のアーマーをどうするつもりだい?」
「このデータをセイアに転送する。例えこれが未完成でも、奴を退けるだけの力はあるはずだ」
「・・もしデータにエラーがあれば、セイア自身に影響があるかもしれないよ」
「それでもイクセにセイアを倒されるよりはマシだ」
そして黙々とキーボードをたたき続けるウィドに、ゲイトはそれ以上何も言おうとはしなかった。
しかし――ゲイトは思う。果たしてこんなモバイルから、こんな膨大にデータをマザーが受け取ってくれるのだろうか、と。
普通ならば復旧されただろうファイア・ウォールが発生してそれを拒んでしまう。
それを突破するとすればかなりの労力だ。今からそんなことをしていたら恐らく間に合わないだろう。
「よし・・・!」
が、ゲイトの予想とは裏腹に、未完成のアーマーのデータはマザーへと転送されていった。
そんな馬鹿なと頭の中でも思うものの、事実は事実だ。
かつてエックスが云っていた、データだけでは観測できないものがあるというのはこれなのだろうか。
それは単にセイアと会話するマザーがデータをインポートしてくれたに過ぎないのだが、
ウィドやゲイトにとって、それはまさに『奇跡』だった。
『ヨク聞ケ。私ガ床ノ一部ヲ爆破シ、奴ニ隙ヲツクル』
「あははは、それそれそれ!」
イクセのバスターを二刀流の天空覇で打ち消すことが、今のセイアの限界だった。
戦況は防戦一方。セイアは初めから全力で闘い、イクセは依然として余裕な表情を崩さないところを見ると、その力の差は明らかだった。
だが、そんな戦況が一気に覆された。マザーの宣言通りにイクセの足元の床が破裂し、彼に一瞬の隙を作ったからだ。
「うあっ!?」
『ソノ隙ニ一撃ヲ叩キ込ムノダ。三秒間デイイ。奴ヲ食イ止メラレル一撃ヲ』
「うぉぉぉぉぉぉぉっ!」
マザーに後押しされ、セイアは叫ぶ。
咄嗟に両掌にエネルギーを集中し、増幅させ、そして放つ!
今のセイアが出来るであろう全ての力を込めた波動拳だ。
「くっ!」
完全に防御を解かれたイクセが、そのまま後方へと吹き飛び、側壁に激突する。
姿勢を崩しそうになりながらも、セイアはマザーが直接浴びせ掛けたデータを、文字どおり全身で受け止めた。
『Move Cross Armor To Saver』
その瞬間光が迸った。セイアの胴を、四肢を、バスターとサーベル・・セイバーを貫く閃光。
蒼の光。紅の光。それがセイアのアーマーの上に、更に一回り大きな鎧の輪郭を描き始める。
――暖かい。
疲れきった身体を包み込む温もりに、セイアは思わず眼を閉じた。
懐かしい誰かの温もりに抱かれて、ロックマン・セイヴァーは進化する。
そう・・かつての英雄の、兄達の、ロックマン・エックスとゼロの温もりに抱かれて。
――兄さん!
「おぉぉおぉぉぉぉっ!!」
セイアの絶叫と共に、彼の全身を包み込んでいた光が晴れた。
その鎧は、変わっていた。恐らく彼と彼の兄達を知る者ならば、全員が彼等三人全てを連想するだろう不思議な鎧。
セイアの傷も疲労も、全てを包み込む新たな鎧は、セイアが今まで着けてきたどの鎧とも違った。
力が漲るのを肌で感じる。いや、それ以上に荒れ荒んだ心が落ち着いていくのが判った。
「ふふふ、それが君の奥の手かい?面白いじゃないか!」
初めてイクセの表情が変わる。余裕の笑みから、勝敗の判らない闘いへ臨む者の顔へと。
パッパッと埃を払う仕草をするイクセは、やがて真っ直ぐにセイア目掛けてバスターを向けた。
初めてイクセのバスターに光が宿る。通常弾でも恐るべき威力があったイクセのバスターは、果たしてどれ程凶悪な破壊力を吐き出すのか。
さっきまでのセイアなら、その威力に恐れ戦いたことだろう。けれど今は違う。
「兄さん、もう一度ボクに力を貸して・・!」
静かに頭上に掲げるゼット・セイバーから、天をも貫く勢いの巨大な刃が現れる。
このクロス・アーマーのギガ・アタックのエネルギーを全てゼット・セイバーに流し込んで放つ、セイアの奥義。
それはかつてDr.ワイリーとの最終決戦の際に一度だけ放つことを許された禁断の技であり、
二人の兄の最強の必殺技を寄り合わせた究極の一撃。
「勝負だイクセ!」
「さぁ・・見せてご覧よ。君の力をさぁっ!!」
「うぉぉぉぉ!!」
イクセのバスターが火を吹いた。同時に、セイアが振り下ろした巨大なゼット・セイバーから、刃を模した強力なエネルギー波が飛んでいく。
現実では不可能だろう速度で飛翔する二つの力は、二人の丁度真ん中で激突する。
一瞬の均衡のあと、それに勝利したのは・・・――
「ソウル・・ストライクっ!!」
――・・・そして静寂が戻る。
立っていたのは蒼と紅の鎧、残ったのは抉られた電脳の床だった。
セイアは仮想ゼット・セイバーが砕け散り、ガクんと膝をつく。
さっきまでイクセが立っていた場所には・・何も無い。イクセが砕け散ったクズデータも何も。
「・・・・」
セイアは振り返る。本当なら気付きもしないだろう小さな気配に。
「ふふ・・油断したよ」
イクセは立っていた。ザックリと胸に斬り込まれた傷を抱えて。
もしこれが現実世界ならば致命傷になっていただろう傷だが、
余程頑強なデータ構造をしているらしい、デリートには至らなかったようだ。
「イクセ・・」
「まさかこんな隠し玉があるなんてね。流石のボクも吃驚だ。
今回は引くしかないみたいだね。でも、遊びとしては面白すぎたくらいだよ。ありがとうセイア」
けどね・・・、とイクセは付け足す。
ニコッと彼は頬笑んだ。彼を知らない者なら、可愛らしい無邪気な笑顔だと形容するだろう。
けれどセイアは違う。彼の裏側にあるドス黒い部分を知るセイアには、それがただの仮面にしか見えなかった。
そして案の定イクセは言葉を紡ぐ。その空気に触れた血のようなドス黒い表情を表に出しつつ。
「次はないよ」
そしてイクセは消えた。己が光の線となって、天井の方へと。
ダイヴアウトしたのだ。セイアが同じことをすれば、彼と同じようにこの電脳空間から排出されるだろう。
後に残ったのはイクセの笑い声。もはや狂気的という言葉がピッタリかもしれない程、狂った高笑いだった。
「エックス兄さん、ゼロ兄さん・・」
ダイヴアウトすれば消えてしまう、自らを包む二人分の温もり。
セイアはそっと胸の部分に手を当てた。こんなに暖かいのに、
こんなに実感があるのに、現実の世界に戻れば消えてしまう温もりが今のセイアには酷く寂しかった。
けれど同時にセイアは感じていた。兄達の絶大な力を。
その力はきっと、セイアに闘えと云っている。奴等を止めるために。自分達の代わりに、皆を護れと。
セイアは内側から聞こえてくる彼等の声に、静かに頷いた。
自分に課せられた責任を確認するように。自らが彼等を生み出し、そして自分自身で倒さなければならないという決意を胸に。
――うん・・判ったよ兄さん達。ボクはロックマン・セイヴァー。だからボクは・・。
『セイア・・聞こえるか』
「・・ウィド?」
『無事、だな』
「・・・うん、ありがとう」
身を包むクロス・アーマーとの別れを、セイアは感じていた。
ダイヴアウトが近いからだ。けれど、セイアは決してそれを拒否することはしない。
次に現実でこれを身につける時は・・これを着けるに相応しい心でこれを受け止めたいと思うから。
『ダイヴアウトするぞセイア。かなりの疲労が溜まっている筈だ。すぐに休息を取れ』
「判った。任務完了、これよりダイヴアウトします」
己が身体が光の線となるのを感じながら、セイアは一粒の涙をこぼした。
判ってはいたし、覚悟はしていたことだけれど、まるで再び兄達との別離を迫られたような気がしたからだ。
――セイアの感傷を尻目に、光の線となったセイアは、電脳世界の天井へと呑み込まれていった。
次回予告
闘いは終焉へと向かう。
イクセ達リミテッドに捕えられた僕と、呼び出されたウィド。五人の最終決戦が始まる。
違う!お前達は兄さんなんかじゃない!
究極の鎧を再び携えた僕の前に、遂に最凶の敵・デス・リミテッドが立ちはだかる!
これが最後だデス・リミテッド!勝つのは・・・勝つのは僕だ!
次回 ロックマンXセイヴァーⅡ 最終章~君を忘れない~
・・そして少年は・・・――
「了解。このまま突っ切る!」
おおよそ現実空間では再現出来そうもないサイバーチックな空間の中、
ロックマン・セイヴァーはそれを楽しむ様子もなく走り続けていた。
辺りには電脳世界独特の光のラインが多々見える。
何を模したのか判らない、言葉では言い表しにくい建造物に囲まれたそこは、現実から離れたもう一つの戦場だった。
これが現実ならば敵機の接近は気配で判るというものを。この世界ではそんな常識が全く通じない。
三百六十度好きな方向から突然姿を現わし、攻撃を仕掛けてくる敵機達は、個々の戦闘力とは裏腹に手強い。
セイアはここに来るまでに、既に幾度かのダメージを負ってしまっていた。慣れない戦場で、上手く実力が発揮出来なかったからだ。
所々に被弾したアーマーを気にかけつつも、セイアはウィドの声に指令されたルートを急ぐ。
が、そんな侵入者の進行を止めようと、セイアの目と鼻の先で巨大な敵機の姿が現れた。
『セイア!』
「判ってる!」
しかしセイアは止まらない。セイアを制止しようとするウィドの声にそう答えつつ、セイアは飛翔した。
エックス・サーベルを抜き放ちつつ、飛燕脚からの推力を利用し、連続的に回転運動を始める。
サーベルを頭上に構えたまま高速回転を始めるセイアは、おのが身体を一つの弾丸とし、そのままゴーレムの様な姿の敵機に突っ込む!
辺りに三日月型のエネルギーを発散しつつ、弾丸となったセイアが敵機を貫いた。三日月斬だ。
『成る程。だが正面にエネミーの反応が多数。陸地タイプだ』
この世界において『陸地』と形容することほどのデタラメは恐らくない。
けれど、ウィドにもセイアにも他にそれを形容する言葉が見つからなかった。
常識の通用しないこの世界で、『地面』と認知させる部分から離れられない敵機のことを、ウィドは『陸地タイプ』と言い表した。
事実上は間違っていようとも、その言葉をしっかりとセイアは理解した。そして、自らがそれに対抗しうる為の最善たる技を瞬時に繰り出す!
「疾風っ!」
急停止するセイア。が、彼の姿を模したエネルギーの塊は、ダッシュの姿勢を保ったままに敵機の大群へと突っ込んでいく。
傷つく恐れも撃ち落とされる恐れもないエネルギーの塊・疾風は、自らに触れるもの全てに、文字どおり疾風のような斬撃を刻んでいく。
疾風牙のスキルを上乗せされた疾風は、この技の元々の持ち主を越える威力で、敵機達を瞬時に破壊せしめて見せた。
「下降ルートを確認。これより第五階層に突入する!」
『了解。しかし第五階層には今までにないエネルギーが確認されている。気を抜くなよセイア』
「判ってる」
疾風が作り出した進路の先に、ポッカリと口を開けるゲートが見える。
一見覗いただけでは下の階が確認出来ない暗黒の穴だが、さっきからこれと同じものを三つも潜ってきたセイアに、今更躊躇いはなかった。
バスターに装填していた特殊武器を通常のバスターモードへと還元しつつ、セイアは思い切り下降ゲートへと飛び込んだ。
第四層から第五層へと景色が変わる。自分自身という存在が別の空間へと飛ばされるような違和感は、四つ目を潜った今でも拭いきれない。
スタンと予期しないうちに足の裏が地面の感触を感じる。地面が知覚出来ないうちに着地してしまうのはなんとも不親切な作りだ。
セイアはそんな風に心の中で愚痴を云いながらも、セイアの口をついて出たのはエクスクラメーションだった。
「くっ・・!?」
『セイア、どうした!』
「なんだこれは・・!?」
全く見覚えのない――ここに来た時点でそんなこと続きだったが――光景に、思わずセイアは声を上げた。
さっきまでの第一層から第四層のいずれにも当てはまらない、特異な空間。
敵機と思える物体は存在していない・・いや、まだ確認出来ないが、その代わりに視界を埋め尽くすものがあった。
「これが・・謎のエネルギーの正体か」
セイアがそう形容したのは、辺りを埋め尽くす程に存在している金色の球体。
今までのような防衛型ではないことは、これらから発せられるエネルギーからも、その唯ならぬ外見からも容易に判断がつく。
機械特有のブーンという異音を発しながら、それらの球体の表面には赤いエネルギーラインが走っていた。
禍々しい・・と、云うのかもしれない。雰囲気的にはあのシグマに近い感じだ。
『こちらのレーダーには何も映っていない。セイア、何が見える!』
「どうやらコイツ等が元凶の一端みたいだ。コイツ等は防衛用じゃない!」
気が付けば、亀のようにのろのろとした動きながらも、空間いっぱいを埋め尽くしていた金の球体は除々にセイアへと集まりつつあった。
バチバチと赤いエネルギーが走る表面は、どう見えても触れてただで済むとは思えない姿だ。
もしコイツ等がこの騒ぎの元となったものならば、破壊するしかない――!
セイアは手始めに一番手前の二つ三つを、エックス・サーベルの斬撃で真っ二つに斬り裂いた――つもりだった。
しかしセイアの意識とは裏腹に、金の球体は何事も無かったかのように近づいてくる。
もう一度サーベルの斬撃を浴びせるが、刃はスッと空気を裂くように球体の表面を擦り抜けてしまう。
「くっ、手応えがない!」
まるで雲を相手にしているような気分だ。
もう片手をバスターに変化させ、手当たり次第に光弾をぶつけてみるが、やはり効果はない。
あっと言う間にセイアは後方の隔壁へと追い込まれてしまっていた。
こうしている間にも、ふわふわと浮遊する金の球体達は、除々に除々にセイアとの距離を縮めていく。
第四階層へと続く上昇ゲートを見上げてみたけれど、既にガッチリと閉鎖されていて、
第四階層へセイアが戻ることを断固として拒否していた。
『何があった!応答しろセイア!』
「バスターもサーベルも通用しないんだ!このままじゃ・・うわっ!?」
『どうした!』
セイアの死角からも迫ってきていた球体が、ついにセイアを捉えた。
最初に呑み込まれたのはサーベルを持つ右手。隙が出来たそこに、我先にと群がる球体が、次々とセイアの身体の各所に食らい付いてくる。
右手、左手、胴、両足。セイアに食らい付いたそれらは、言い様のないエネルギーの奔流を、セイアの体内へと一気に流し込み始めた。
「くっ!離れろ・・!うっ・・うわぁぁぁぁっ!!」
『セイア!セイアっ!!』
「ウィ・・ドっ、ぐぁあぁぁぁぁっ!!」
このまま意識を手放してはいけない!――心の中ではそう理解しつつも、体内を侵し始めたエネルギーは、
セイアの意思とは無関係にその身体を侵食し始めた。
必死にセイアの名を呼ぶウィドの声が少しずつ遠くなっていく。身体に力が入らずに、サーベルの柄がカランという音を立てて足元に転げ落ちた。
駄目押しとばかりに残った部位を埋め尽くしていく金の球体。
最後に残った顔面が呑み込まれたとき、セイアの意識は暗黒の渦へと放り出された。
「うっ・・・・ぁ」
『セイアぁぁっ!!』
現実とはかけ離れたその空間に木霊する悲鳴は途絶え、代わりに相棒の名を絶叫する声だけが響く。
喉を痛めてしまう程に強く叫んでも、それに応えてくれる声はなかった――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「リミテッド。イクス、レイ、イクセ。そして各種リミート・レプリロイドか。これまた厄介なことになったね」
モニタを埋め尽くすデータの羅列にじっくりと目を通したあと、ふとDr.ゲイトが呟いた言葉がそれだった。
Dr.ゲイト。数年前のナイトメア事件発祥の張本人にして、ロックマン・セイヴァー・・セイアの制作者。
以前はゼロの破片を元に作り出したナイトメア・ウィルスによって荒廃した地球の支配を目論んでいたのだが、
事件の終焉の際にエックスによって救出され、それ以来イレギュラー・ハンター専属の研究員として働いている。
つい昨日まで各地のハンター支部を回っていたゲイト。彼が本部に帰るなり知らされた事実とデータは、並の人材ならば卒倒しそうな内容だった。
レプリフォース大戦の最中でエックス・ゼロによって撃破された筈のレプリロイドの再来。
データに残る、リミテッドという名の脅威。そしてそれがセイアに取り憑いたことで誕生した三体の強力な敵。イクス、レイ、イクセ。
「折角ゆっくりと話が出来る機会が出来たというのに、なかなか穏やかじゃないシチュエーションだね、ウィド君?」
「俺は元からコイツ等に立ち向かう為、イレギュラー・ハンターに訪問したんだ」
「ふうむ。まぁ、そういう事にしておこうかな。
それにしても、なかなか厄介な敵が現れたものだよ。ボクの作ったナイトメア・ウィルス以来かな?」
そうおどけた様に云うゲイトの顔は、困惑よりも余裕の二文字が先に出ているように思う。
ウィドが相変わらず食えない奴だと肩を竦めていると、ゲイトは変わらずの微笑を口もとに浮かべたまま、
今度はセイア――今は健次郎の姿だ――の片腕をそっと握った。
「どうだい、セイア?腕は痛むかい?」
「い、いえ。もうすっかり大丈夫です。痣も消えたし」
「うんうん、成る程」
興味深そうに頷きつつ、ゲイトは健次郎の袖を捲る。つい先日・・学校での闘いがあった日以来、腕に痛みは走っていない。
あんなにクッキリとあった痣も綺麗に消えている。逆に不安になる程に。
「リミテッドについてのデータを詳しく読んだことはないから断定は出来ないけど、どうやらそのイクス達三人が君から分離したことで、
同時に君に取り憑いていたリミテッドが剥離したようだね」
「はぁ・・」
「その証拠にここ数日のエネルギー環境も落ち着いている。完全とは云えないかもしれないけど、元には戻ったってことかな」
「・・リミテッドによるパワーアップ効果も同時に消え失せたがな」
ボソリ。ウィドは横から口を挟んだ。
勿論セイア自身の安定性が何より大事であり、あんな風にセイアが暴走することがなくなったことを喜ぶべきであることはウィドにも充分判っていた。
寧ろたった一人の友達であるセイアの命に別状がなくて、大いにホッとしている方だ。
けれど、問題はそれとは別のところにある。
「うーん、そうだね。確かに記録に残る異常な高出力を今のセイアが発揮するとは思えない」
「つまり、僕は・・?」
健次郎が首を傾げると、ゲイトは珍しく口もとの笑みを崩した。
ほんの少し真剣な顔で、そっとセイアの両肩を包み込み、呟く。
「つまり、リミテッドによる異常出力を失ったことで、君はイクス達に対抗しうる力をも同時に失った・・ってことだよ」
「えっ・・」
「残念だが、それは事実だ。あの時のセイアの戦闘力から予測される奴等の力は・・想像を絶すると云っていい。
例えお前が強化アーマーを装備したところで、勝負は見えているんだ」
「なら、僕は奴等に対して何も出来ないっていうの?」
「そうは云っていない。俺とDr.は全力で奴等に対抗しうる為の対策を立てる。
だからお前は、それが完成するまで決して奴等と闘ってはいけないんだ」
「・・奴等が攻撃を仕掛けてきたら?」
健次郎は少し苦い顔で尋ねた。来るべき答えはなんとなく予想出来ていたけれど、尋ねずにはいられなかった。
そしてウィドの代わりにゲイトが、健次郎の予想した通りの応えを口にした。
「その時は、残念だけど逃げるしかないかな」
「そんな・・!奴等がすることを黙って見てろって云うんですか!」
「・・別にお前が勝手に闘いを挑み、犬死にするのは自由だ。だが忘れるな。
奴等に勝てる可能性があるのは、エックスとゼロがいない今・・お前しかいないということを。
もしお前に彼等と同じように人々を護る気があるのなら、我慢することも大切だ」
半分はデタラメだった。ウィドは、自分の本心とは全く逆のことを云っていた。
ウィドだって・・いや、ウィドは健次郎が死ぬのが恐かった。健次郎が敵に殺されるのは何よりも辛い、そして苦しい。
きっと健次郎がそれでも闘いを挑むと云ったなら、半狂乱になって止めるだろう。
それでも健次郎に事の重大さを、そして自らの立場を理解して貰うにはこう云う他なかった。
彼には辛いだろうと理解しつつも兄達の名を出したのはその所為だ。
「ウィド君の云うとおりだよセイア。申しわけないけど、今のボク達は君しか残っていないんだ。
もし本当に奴等に勝ちたいと願うなら、君がするべきことは判っているね?」
「ウィド・・Dr.・・・。・・判りました」
しゅんと項垂れて、健次郎は小さな声で了解の意を呟く。
そんな彼の様子にゲイトはほんの少しの慈愛を含んだ笑みを浮かべつつ、そっとその薄い蒼の髪を撫でる。
ここ数日ロクな手入れも出来ないでいるのだろう。元々細くしなやかな髪は、随分とバリバリになってしまっていた。
髪の手入れも出来ない程に張り詰めていたのだ。そう思うと、ゲイトはつい一年前程前まで元気だった蒼の青年の姿を思い出さずにはいられなかった。
「さぁ。君は少し疲れているんだ。沢山のことが一気に起こったからね。
こっちはウィド君と一緒に作業を続ける。セイアは部屋に戻った休みなさい」
「で、でも・・」
「心配するな。対策も解析もすぐに終わらせる。奴等と闘えるようになってもお前がそんなんじゃあ、結果なんて期待出来ないぞ」
「そうそう。ハンターとして、時には休むことも大切なんだからね」
二人にやんわりと肩を押され、健次郎は諦めたように肩を竦めると、小さくコクンと頷いた。
「判った。僕は一足先に部屋に戻るよ、ウィド。そっちの方・・お願い出来るかな」
「任せとけ。戦闘で殆ど役に立たない分、しっかりお前のサポートをしてやるさ」
「うん。ありがとう」
一つニコッと笑って、健次郎は服の中に隠していたエックス・サーベルとZセイバーを机の上に置くと、会釈と共に研究室を去っていった。
二本の柄をそっと手にしたウィドは、健次郎の背中がドアに覆い尽くされたのを見届けてから、くるりとゲイトの方へと振り返った。
ゲイトはふとウィドの手の中の二本の柄を手にとると、それらをマジマジと見詰めた。少し懐かしそうな視線だった。
「ふうん。これはゼロのセイバーだね。何故これをセイアが?」
「・・そ、それは」
いつも淡々としているウィドが口籠もったのを、ゲイトは見逃さなかった。
けれど敢えて詮索する気はないらしく、ゲイトは余った手をウィドの頭の上に置いた。
「まぁそれは聞かないでおくよ。誰にでもプライバシーというのは存在するからね」
「あ、あぁ」
ウィドはゲイトに何か苦手意識を持っていたが、ようやく今その正体が判ったように思う。
ゲイトはよく相手の心を見透かしたような態度を取る。そしてそれを見透かしながらも敢えて何も知らないような物言いで応える。
他人に対してどちらかというと閉鎖的なウィドにとって、ゲイトのそういった性格は少し刺激というか、新鮮味が強すぎたのかもしれなかった。
「しかし、随分とボロボロになったものだよ。ついこの前新品同様にして上げたというのに」
見事なBy The Way。素知らぬ顔でゲイトが手の中で弄ぶのは、セイアの愛剣であるエックス・サーベルだった。
無数のラーニング技を放ち、沢山の新必殺技の出力変化に耐えてきた光剣の柄は、
今まで彼が潜り抜けてきた闘いがどれ程凄まじいかを一目で物語っている。
これには流石のウィドですら気が付かなかった。今までの沢山の信じ難い事象の中でセイアのサーベルの状態を確認出来るほどの余裕はなかったのだ。
「セイアには辛い闘いを強いることになるね・・」
「・・セイア自身が闘うと云っているんだ。俺達がどうこう云う筋合いはない筈だ」
「ふふ、全く。何を強がっているんだい?」
「つ、強がってるだと?」
「そう」
モニタの前の椅子に腰掛けたゲイトは、丁度ウィドに背を向ける構図になる。
ウィドは振り返らなかった。ただ何も無い廊下へと続くドアを見詰めながら、同じく振り返らないゲイトの声を聞いていた。
相変わらず何かを見透かしたようなゲイトの声は、やはりウィドの心の奥をつんっと刺激した。
「誰よりセイアを心配しているのはウィド君・・君じゃあないか。そんな物言いをしたところで、このボクの目はごまかせないよ」
「べ、別に俺は・・」
「ふふ。まぁ君がそう云うのならかまわないけどね。ただ、セイアは君にとって初めての友人だ。そうだろう?」
一体このナルシストの科学者はどこまで知っているというのだ。
心の中で驚嘆と溜息を同時に放ちつつ、ウィドは面食らう他無かった。
対してゲイトは楽しそうにキーボードを叩きながら、片手でちょいちょいと自分の横の椅子を指さした。
隣に座れ、と云っているらしい。
「・・さて、無駄話もここまでだ。あのリミテッド達に対抗しうる対策を、君は練っているんだろう?それを聞かせてくれないかな」
「やれやれ・・」
ボリボリと後頭部を掻きながら、ウィドは渋々ゲイトの隣の席につく。
服の内ポケットに厳重に保管しておいたデータディスクを手近のスロットルに差し込み、その内容をモニタへと出力させる。
映し出されたプログラムの羅列に、流石のナイトメア・ウィルス開発者も、驚いたように目を見開いていた。
そんなゲイトの顔を見て、ウィドは少しふふんと踏ん反り返った。ようやく一つ勝ったような気がした。
「・・素晴らしいね。確かにこれなら、リミテッドにも対抗出来るかもしれない」
「あぁ。だが、このデータ配列を実現するのはかなりシビアだ。そこで、アンタの力を貸してもらいたい」
「OK。勿論協力させて貰うよ。ただ、かなり高度な作業になるけど、大丈夫かい?」
そう尋ねるゲイトの顔に、ウィドがNOと応えるという憶測は全くなかった。
それはウィドにも判っていることであるから、ウィドはわざと声に出さずに小さく頷いてみせた。
そしてどちらかともなく二人はキーボードをたたき始める。その二人の顔に、今までの冗談混じりの会話の気配は全くない。
天才を越える天才と呼ばれたDr.ゲイトと、若き天才科学者ウィド・ラグナーク。そんな二人の夢の共同作品が、そう遠くない未来で生まれるのだ。
「・・ところでDr.」
「うん、なんだい?」
依然としてキーボードを叩きつつ、ウィドはふとゲイトを呼んだ。そして尋ねた。
「アンタは・・俺のことを知っているのか?」
「さぁ、何のことかな。ボクが知っている君は、謎の天才少年科学者だよ」
「・・」
「そしてボクは、Dr.バーンの幼馴染み。それだけさ」
「・・・!」
やれやれ本当に食えないやつだ。
一人で作業している時とは較べものにならない程スムーズに進む指を認めつつも、ウィドは隣で一人楽しそうな科学者に溜息をつく他無かった。
ロックマン・エックス。そしてゼロは現代の最先端技術をもってしても正体不明のレプリロイドだ。
いや、正確には違う。何故なら『レプリロイド』と称される種族は全てロックマン・エックスを素体として生まれているからだ。
つまりはセイア、ゲイト、そしてあのシグマですら実質的にはロックマン・エックスのコピーに過ぎない。
今のこの世界に存在している者の中で、エックスを始祖としないレプリロイドは一体しかいない。そう、ゼロだ。
かつて紅いイレギュラーとして出現したゼロも、レプリロイドの始祖となるに充分値する脅威的な構造を持つ。
果たしてエックスとゼロ、彼等の本来の制作者は誰で、そしてどういった目的で生み出されたのか。
Dr.ケイン、エックス亡き今、それを知るのは彼等の弟であるロックマン・セイヴァーしか残っていない。
余談だが、一年前の宿命の決着の際にセイアが目の当たりにしたであろう歴史の裏側は、
数々の評論家や科学者から好奇心溢れる視線で見られていたが、セイアが頑なにそれを喋らなかったため、結局は謎のままになったという。
通称『Fusion Cross』。ウィドが捻り出した計画の名前だ。
それは即ちロックマン・セイヴァーがイクセ等ハイパー・リミテッドの脅威に対抗しうる為の強化案。
平たく云えば新たな強化アーマーについての設計図だ。
生みの親のゲイト、そしてウィド自身も大いに認めるセイアの可能性。
当初ゲイトが生み出したときに推定された予想最大出力を遙かに上回る功績を持つ彼は、いまやエックス、ゼロを越えた最強のレプリロイドだ。
だが、それでも所詮は現代の科学者が生み出したエックスとゼロの模造品。初期戦闘力はまだまだエックス達へは及ばない。
なにせブラックボックスだらけだった彼等だ。そんな彼等の限界最大戦闘力を知る者はこの世界に誰一人とていない。
エックスは一年前に没し、ゼロは生還しつつも行方不明になっているのだから。
この『Fusion Cross』内においての主旨。それはズバリ、セイアに対してエックスとゼロの実質的な融合――FUSIONだ。
エックスとゼロが残していった数々の戦闘データを元に、セイアの潜在能力を最大発揮しつつ、その出力に大いに耐えうるアーマーを創り出す。
イクセ等リミテッド達が強化されたセイアの潜在能力の一部だというのなら、セイアにはそれ以上に潜在能力を発揮して貰わなければならないのだ。
勿論そんな無茶な要望に応えうるアーマーを創り出すのは至難の業だ。
一介の科学者ならば、そのコンセプト自体を絶望視し、とっくに破棄しているだろう。
けれどゲイト、ウィド。何よりセイアには後がない。
絶望だの不可能だのと四の五の云う暇があるのなら、それを成し遂げる為の道筋を作った方が余程早い。
それ程にイクセ等ハイパー・リミテッドの力は脅威的なのだ。ウィドとゲイトがさっきセイアに云ったばかりの台詞だが、
リミテッドの剥離した今のセイアが彼等三人に闘いを挑み、勝てる確立は万に一つもない。
例えセイアにエックス・ラーニングシステムが装備されていようとも、セイアを知り尽くしているだろう彼等にはそよ風程の障害に過ぎないと云える。
だからこそウィドとゲイトはハイパー・リミテッドというかつてない強敵に対抗しうる鎧を創り出そうと決意したのだ。
イレギュラー・ハンターとして、被害がこれ以上拡がる前に奴等を倒す為に。そして何より、ゲイトは大切な息子を、ウィドはたった一人の親友の命を護る為に。
「・・しかし君も無謀な男だね」
かなりの間キーボードの叩く音しか聞こえなかった部屋の中で、そんな言葉を口にしたのはゲイトだった。
ブラインドタッチなんて基本中の基本とでも言いたげな見事なタイピングの腕を見せびらかせながらにそう云ったゲイトに、
ウィドも負けないくらい達者なタイピングを披露しつつ、一言云った。
「・・しかしこうでもしない限り、奴等を倒すことは出来ない」
「うんうん。最もな意見だと思うよ。事実セイアも君もそんな顔をしているからね」
プログラムの開発度は、元々ウィドが開発を進めていた五分の一程度に加え、もう五分の一程度まで進んでいる。
流石は天才科学者ゲイトだと思い知らされる速度だ。端から見ればのらりくらりとイライラする程の遅さの進行だが、
これ程膨大なデータ量を的確に処理・構築していく様は、その手の方面を噛ったことのある者ならば、思わず舌を巻かずにはいられないだろう。
「こんな無茶なアーマーを考え出すのは君くらいなものだよ。ボクだったきっともっとマシなコンセプトでいくと思うからね」
「ならアンタならどういった強化を考え出す・・?」
「うーん、そうだね。ナイトメア・ウィルスで相手を混乱させて、その間に攻撃するっていう案はどうだい?」
「・・・本気で云っているのか?」
「勿論冗談だよ。つまり何が云いたいかというと、それくらい馬鹿げた思考でなければ、奴等に我々の力だけで対抗しようとは思わないってことさ」
エックスとゼロがいてくれたら――そう思ってしまうのは不謹慎だろうか。
それでもそう思わずにはいられなかった。彼等はいつだってなんとかしてくれた。どんな脅威をも打ち倒してきた。どんな強敵をもやぶってきた。
「ボクはね、ウィド君。口惜しいんだよ」
「うん?」
「どうしても思ってしまうのさ。何故ボクの息子ばかりこんな目に・・とね」
「・・・」
四年前のナイトメア事件よりも更に少し前、ゲイトの創り出した八人の息子達は処分された。
決して彼等がイレギュラー化したわけではない。彼等は全くの無罪だった・・といっても過言ではなかっただろう。
その当時ゲイトは学会では異質な存在だった。同僚であるエイリア――勿論現在ハンターでオペレータを務めている彼女だ――が語るに、ゲイトは天才過ぎた。
上部からの課題をまもらず、自らが高みを目指すままに次々と高性能レプリロイドを創り上げていく彼。
学会はそんな彼と彼が生み出したレプリロイドの力に恐怖し、嫉妬した。
かつて世界を混乱に陥れたナイトメア事件は、そんな学会の愚かな一面が作り出したのかもしれなかった。
事故に見せかけたとはいえ、彼の息子達を破壊したのは彼を取り巻く世界だった。
一度目は学会の秘密裏の陰謀によって。そして二度目はセイアの兄でもあるエックスの手によって。
それでも決定的に違うのは、彼等の二度目の死は彼等自身が望んで闘ったという点だろう。
ゲイトにとって、息子達を二度失ったことに変わりはなかったのだが。
「だから少し恐いのさ。今度はセイアが自分の意思を貫き、散っていくのではないかってね。
そしてボクは・・散っていく息子の背を押す執行人なんじゃないかとね」
ゲイトがレプリロイドだからだとかそういうことは全くもって意味をなさない陳腐なことだった。
ゲイトはレプリロイドの科学者だけれど、確かに人の親なのだから。
ヤンマークも、シェルダンも、ヒートニックスも、ヴォルファングも、ミジニオンも、タートロイドも、スカラビッチも、プレイヤーも――そしてセイアも。
みんなゲイトの大切な息子達だから。
「・・ふっ、セイアが一度でもアンタに呪いの言葉を吐いたことがあったか?」
「ウィド君・・」
「アンタが自分の息子達の死を哀しむのは勝手だ。だがアンタは彼等にそれを強要したか?違うだろう。
彼等は彼等なりにアンタについていこうとした。そしてセイアも、自分の意思でリミテッドと闘う決意をしたんだ」
セイアの瞳に曇はなかった。彼は云ったのだから。キッパリと。リミテッド達と闘う、と。
付き合いが浅いウィドにでも判る。セイアは自分の痛みを他の誰かの所為にするような愚か者ではない。
「彼等が死んだのを自分の所為にするなんて、これほどの侮辱はない。そうだろう、Dr.?」
「・・そうだね」
そう自嘲気味に笑ったゲイトは、次第にプッと吹き出すと、はははと少し軽い笑いを立てた。
これには流石に手を止めたウィドは、少し不機嫌そうな顔でゲイトを見やった。
全く人が真面目に話を聞いてやっているというのに、なんだコイツは・・と、そんな視線で。
「あははは。いやいやごめん。別に君のことを笑っているわけじゃあないんだよ」
「なら、なんだというんだ」
「他人にこんなことを話したのは初めてだけど、まさか君がそんな風に云ってくれるとは思わなくてね」
ポンッと頭に手を置かれ、ウィドはなんだかむず痒い気持ちで席を立った。
ゲイトに「なにを云って」と抗議しようと思ったのだ。けれどウィドの行動は突然ゲイトが突き出してきた掌によって阻止された。
「ウィド君!」
「な、なんだ突然!」
「どうやらボク達の仕事がまた一つ増えたようだよ」
そう云ってゲイトはPCに差し込んでいたメモリを素早く引き抜いた。恐らくデータのバックアップを隔離する為だろう。
科学者として最終手段とも思える強制隔離の様を見て、ウィドも慌てて手近のモニタを覗き込む。
そこに表示されるエラーメッセージを目にして、ウィドは「ちぃっ」と小さく舌打ちをした。
「こんなときにお客さんみたいだね」
「やれやれ、厄介な時に・・!」
メッセージの内容はアラートだ。大抵こういった類のエラーは外側からの侵入者、或いはウィルスが流された際に作動する。
しかし大抵はハンターの誇るワクチンによって自動的に除去される筈なので、こんな風にアラートを響かせる事態というのはかなりの緊急事態だといえよう。
それもレッドアラートだ。作業を少しでも早く進めなければならない現状だというのに。ウィドが思わず毒づいてしまう気持ちもなんとなくゲイトには判った。
「ワクチンプログラムを受け付けない、か。随分手の込んだ侵入者だな」
「呑気なことを・・」
「マズイ。どうやら敵さんはマザーコンピューターの最下層までアクセスしてしまっているらしい」
カチャカチャとキーボードを弄くっていたゲイトは、慌ててその手を離した。
既にベース内の全てのコンピュータは操作を受け付けないだろう。
下手をすればキーボードを通してレプリロイドであるゲイトにもウィルスが侵食する危険性がある。
そのことはウィド、ゲイト両名が判りきっていたことだ。
例え人間であるウィドが操作を変わったところで結果は変わらない。
「ちっ。これではハンターの遠隔操作型メカニロイドは・・!」
「全体イレギュラー化。ベース内は壮絶な室内戦・・と云ったところかな」
「こんなウィルス如き・・!」
憎々しげに叫ぶウィドの意識とは裏腹に、ドンっと乱暴な音が響き、研究室のドアが派手に吹っ飛んだ。
廊下と較べて若干暗い室内からは逆光で上手く見ることは敵わなかったが、乱暴な来訪者のアイカメラの輝きだけはいやにハッキリと見える。
ウィドはハッとしたように腰のレーザー銃を手にとり、ゲイトはふぅという溜息と共に肩を竦めた。余り焦っている様子はなさそうだった。
うーんと何かを考え込むような仕草でメカニロイド達を見詰めるゲイト。元々科学者型として開発されている彼に武装などある筈がない。
ウィドはじわじわと研究室内に入り込みつつあるメカニロイド達にレーザーの照準を合わせつつ、未だに焦る素振りすら見せないゲイトを怒鳴りちらした。
「ふうむ、成る程。もしかしたらこれもリミテッドの仕業かもしれないな。
ボク達・・そしてセイアのいるハンターベースを直接襲撃する。それもセイアが休息している隙をついて。
かなり大胆な作戦だけど、意外と効果があるものだね」
「呑気に解説をしてないでアンタも構えろ!来るぞ!」
「まぁまぁそんなに力む必要はないよ。それよりボク達はマザーコンピュータに侵入したウィルスを除去することを考えないと」
「この状況が見えないの・・・か・・?」
怒鳴り声を上げようとしたウィドは、別の角度から飛び込んでくる第三者の叫び声に、その怒声を掻き消された。
「おぉぉぉぉっ!!」
その声が聞こえたのは、メカニロイド達の向こう側。つまり廊下の方からだ。
ふふんと余裕なゲイトと、突然の第三者の乱入を尻目に、研究室いっぱいを占拠しつつあったメカニロイド達の機体は次々と宙へ浮かぶと、
スッスッと廊下の方へと消えていく。
どんどん彼等の個体数は減り、遂には廊下が見えた。ウィドが素早く廊下へ駆け出し、メカニロイド達が消えていった方向を覗くと、
そこには暗黒の球体が浮遊していた。天井すれすれに存在するそれに、次々とメカニロイド達が呑まれ、消えていくのだ。
「これは・・!」
新たな敵かと思いきや、その球体は全てのメカニロイドを呑み込み終えると、ふっとその命を散らした。
あとには球体のコアだっただろうメカボールが残っていただけで、そのボール自体もそれを放っただろう人物の方へと還っていった。
「ウィド、大丈夫!?」
「セイアか!」
パシッとボールを掌で受け止めたのはセイアだった。紅のアーマーに身を包み、戦闘形態と姿を変えた健次郎。
そこでウィドはようやく理解した。先程次々とメカニロイド達を呑み込んでいった暗黒の球体の正体を。
バグ・ホールだ。かつてのドップラーの反乱での闘いの際、エックスがグラビティ・ビートブートから入手した特殊武器。
人工的なブラックホールを短時間作り出し、標的を呑み込み、消滅させることの出来る汎用性の高い武器だ。
その規模はほぼ完全に自由とさえ云われていて、最小は微生物レベル、最大は地球サイズをも作り出す。
セイアの放つバグ・ホールは改良が加えられていて、設定した対象のみを標的とし、消滅させることの出来る機能が追加されている。
これによってセイアは大量のメカニロイド達を薙ぎ倒しつつ、研究室まで辿り着いたのだろう。
「補助メカニロイドがイレギュラー化している・・。ウィド、これは一体?」
「どうやらマザーコンピュータをやられたらしくてね」
ウィドが質問に応えるより先にセイアの疑問に答えを手渡したのは、研究室からひょこっと顔を出したゲイトだった。
「マザーコンピュータを!?」
「かなり強力なウィルスを流されたらしいんだ。最善を尽してみたけど、ここでの操作やワクチンは全く通用しなかったよ」
「ならマザールームに直接ワクチンを入力しに・・」
「無理だね」
ウィドの意見はすっぱりと否定された。ゲイトがここまで単刀直入に物事を否定することは珍しい。
それ程までの事態なのだろうということは、容易に想像出来ることだった。
「確かにマザールームに行ってワクチンを入力すれば理論的には平気だろう。
けどボクがマザーにウィルスを流すとしたら、まずはマザールーム自体を完全にシャットアウト。更にあらゆる入口に防御策を張り巡らせるけどね。
君は違うのかい?」
「・・確かに、ご最もだ。だが、他に手は・・」
云いかけて、ウィドは沈黙した。ワクチンという科目において自分と遜色ないゲイトがこうまで云うのだ。
ウィド自身がどうこうしたところで結果は同じだろう。けれど他に手がないこともまた然り。
これにはゲイトも黙ってしまった。いつもの余裕の笑みは相変わらずだが、きっと内心では酷く焦っているのだろう。
セイアがあらかたバグ・ホールでメカニロイド達を掃除してくれたお蔭か、メカニロイド達の追撃はなさそうだったが、このままではどちらにせよまずかった。
メカニロイド達は比較的簡単に倒すことが出来るだろうが、問題なのはデータベースの方だった。
イレギュラー・ハンターのデータベースには、これまでのハンターの歴史や隊員一人一人のデータなどが細かく入力されている。
その中には勿論セイア・・ロックマン・セイヴァーをはじめ、エックスやゼロのデータも残っている。
セイアはいつもこのデータベースから引き出される情報をもとに、メンテナンスやアーマーの修復を行っている。
そして何より、ウィドとゲイトが今まさに誕生させようとしている新兵器も、ここのデータベースに残っているエックスとゼロのデータをフル活用しているのだ。
今ここでデータベースを破壊されれば、もはやリミテッド達と闘う術は消滅してしまう。要約すれば最高の問題はこれだ。
「ウィド、Dr.・・」
これはセイア自身も充分承知している事実だった。
だからかもしれないけれど、セイアは沈黙する二人の科学者に、何かを決意したような瞳を向けた。
「僕が、そのウィルスを倒しに行きます!」
「なんだと!?」
「・・・・セイア、本気で云っているのかい?」
息子の発言に初めて表情を強張らせたゲイトは、いつもよりも数段低い声でそう問いかけた。
普段の彼を知る者ならそのギャップに驚くことだろうが、セイアはただコクンとだけ頷いた。
その仕草が、彼の発言を冗談から出たものではないことを証明してくれた。セイアは本気なのだ。
「僕がマザーコンピュータにダイヴしてウィルスを倒せばなんとかなります!」
「・・それがどれだけ危険なことだか判っているかい?」
「・・・はい」
「セイア。仮にお前がダイヴし、仮想ボディでマザーコンピュータ内に侵入するとしよう。
だがこの状況では一度ダイヴするのが限界だし、そのウィルスを除去するまで戻ってはこれないぞ。
そして・・」
ウィドは敢えて言葉を切った。この続きを云うことが恐ろしかったからだ。
確かにセイア自身のプログラムをマザーコンピュータにダイヴすれば、
セイアはあたかも現実世界での闘いかのように、マザー内でウィルスと対戦することが出来る。
しかしそれは極めて危険な行為だ。ウィドの云うとおり、この状況下でレプリロイドをマザーコンピュータにダイヴさせること自体が自殺行為だ。
下手をすれば仮想ボディが形成される前にウィルスに攻撃され、プログラムが消滅する。
そしてそれは電脳空間内で力尽きることも同意義のことだ。ログアウトが出来ないということは、電脳空間内で瀕死になろうとも決してそこから出ることが出来ず、
仮にそこで力尽きれば、セイアは彼をセイアとして形成している全てのプログラムを失うことになる。
人間で云えばそれは、『死』、だ。
「だけどこの状況を打破しなくちゃいけないのも事実だ!」
「だが・・!」
「ウィド君、やらせて上げよう」
尚も食い下がろうとするウィドを制する為に、ゲイトは彼の肩に手を置く。
表情こは余り崩れてはいなかったが、ウィドの瞳は歪んでいた。これも友を心配してのことだろう。
ゲイトも同じ気持ちだったけれど、ハンター専属の研究員として、マザーコンピュータが破壊されることを見過ごすわけにはいかないのだ。
「だけどね、セイア。一つだけ条件がある。それを呑んでくれなければ、君を電脳世界に送ることは出来ない。いいね?」
「はい」
「ウィルスを撃破し、必ず生還すること。電脳世界内での消滅は許さない」
「判りました。必ず生きて帰ります」
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
サイバー・スペース。一般的に電脳空間のことを指す言葉だ。
この空間はプログラム配列を持つ電子機器全てに存在している。
家庭用の電子レンジから、ハンターベースのマザーコンピュータまでありとあらゆるものに。
その実体は文字どおりプログラム配列だ。サイバー・スペースとは、それを擬似的に現実世界のものに見立てた際の言葉であり、
基本的にコンピュータにレプリロイドやメカニロイドがダイヴ――メインプログラムをインストール――した時にだけ使用される。
プログラム内にダイヴしたレプリロイドは、そこで作用するソフトウェアの力により、
サイバー・スペース内をあたかも現実世界かのように運動することが出来る。
無論それは視覚的・感覚的なものであるから、ダイヴしている本人以外にそれを知覚することは出来ないのだが。
プログラムに直接ダイヴしたレプリロイドは、その場で万能プログラムと化す。
内部のプログラムに攻撃行為を行えばそれを破壊することが出来るし、逆に修理を行うも出来る。
そう・・つまりロックマン・セイヴァーは自らがワクチンとなってウィルスを消去しに向かうのだ。
スペース内に蔓延っているウィルスプログラムを直接攻撃し、消滅させることが出来れば、その時点でマザーコンピュータにアクセスすることが可能となる。
が、そんなダイヴ行為にも、代償としてあらゆる危険が付き纏う。
ダイヴを決行中のレプリロイドは完全無防備だ。ボディやプロテクトといった防御機能が全て外された、いわば丸裸であり、
最もデリケートな部分を露出した状態となる。
しかもプログラム内にインストールするのがメインプログラムである以上、それは実戦よりも遙かに危険なことが明白である。
もし仮にダイヴしたレプリロイドがサイバー・スペース内で撃破されるようなことがあれば、その崩壊は一気にメインプログラムを侵食し、破壊され、
繋ぎ止める間もなくその人格を消去するだろう。
それはつまり人間でいう『死』、だ。ボディが無傷であるから、その死は更に質が悪い。
だがしかし、サイバー・スペース内で死亡したレプリロイドを復活させる手段は確かに存在する。
ボディや頭部が破壊されていない以上、法律上でもそれは『死』とは認識されず、単に行動不能に陥ったと判断されるからだ。
レプリロイドの再生を行う方法は実に単純明確。それは、全く同じプログラムを組み直し、そこに残された記憶メモリを植え付ける。
たったそれだけだ。たったそれだけで、あたかも生前の人格を再生したかのようにそのレプリロイドは復活する。
だが、それは――
「だがそれは・・本物のセイアじゃない。同じ記憶を持った『別人』だ」
セイアのメインプログラムがマザーコンピュータにインストールされ始めた。
ウィドは、ふとゲイトが呟いたレプリロイドの再生方法に対して、そう漏らす。
幸いなのか否なのか。セイアは既に目を瞑っており、彼等の会話は聞こえていないようだった。
「・・そうだね。そうかもしれない」
マザーへのセイアのインストールは、ウィドのモバイルを使用して決行された。
当然だと云えば当然の結果だろう。マザーに直接近づくことが出来ない以上、外部からアクセスするしか手はない。
だがベース内の全てのコンピュータはマザーに直結している為、その全てがウィルスに侵されている。
ただ一つ生き残ったのは、完全隔離状態であったウィドのモバイルだけだ。
だが、それを使用してセイアのインストールを行うことが出来るのもたった一度だけだ。
マザーにアクセスした時点でウィルスが逆流し、瞬く間にプログラム内に侵入していくだろう。
まさに片道切符。セイアが現実世界に戻る為には、マザー内のウィルスを撃破するしか手立てはないという、残酷な一本道。
「セイアのオペレートを行える限界時間は?」
「ウィルスの侵入が思ったよりも素早い。保って三十分といったところかな・・。こちらからのデータ転送も一回が限界だ」
セイアのインストール状況を映し出すバーは、既にその半分以上が完了を意味している。
あと一分もしないうちにセイアはサイバー・スペース内に降り立つだろう。だが問題はそれからだ。
誤作動するウィルス・バスターやファイア・ウォール。迷路のような進路を潜り抜け、セイアを最深部へと導かなければならない。
ウィドが云ったように、その限界時間はたった三十分。セイアがダメージを受けた際に転送出来るリペアプログラムも一回が限界。
もしこれがマザーの暴走という最悪の事態でなければ、他のハンターは絶対に行わない絶望的な作戦だ。
それでもやらなければならないのだ――セイアも、ウィドも、ゲイトも、同じことを考えていた。
「インストール完了・・。よし、セイア。聞こえるか?」
「ここが・・マザーコンピュータ・・」
知識としては持ってはいたものの、セイアがサイバー・スペース内に降り立ったのは生まれてこの方これが始めての経験だった。
辺りはまるで星空のように煌めいている。あちこちに拡がる意味不明の二進数や、破壊されたクズデータの数々。
確かに身体は現実のものと相違無く動かすことが出来るけれど、ここが現実だとはどうにも信じられそうにはなかった。
『セイア、聞こえるか?』
ヘルメットのイヤー部分の通信機――実際は違うが、違和感をなくす為にそう設定されている――から、少し不安げな声が聞こえてくる。
知識ある者独自の不安だろう。辺りから接近する敵影がないことを充分確認してから、セイアは素早く答えた。
「こっちは大丈夫。それよりも、思ったよりデータの崩壊が激しいみたいだ」
『そうか・・。どっちにせよこっちのオペレート時間も限られているんだ。素早く進んでくれ』
「判った!」
そしてセイアは仮想ボディのメットバイザーを下ろした。インストールの際にウィドかゲイトがデータを入力しておいてくれたらしい。
マザーコンピュータのサイバー・スペース空間の見取り図が記されている。
現在セイアが立っているのは第一階層。ウィルスが潜んでいると考えられるエリアは第六階層だ。
それまでには幾つものファイア・ウォールやウィルス・バスターが潜んでいる。下手をすれば第六階層に辿り着く前に撃破されてしまいそうだが、
仲間内のウィルス・バスターに撃破されることよりもみっともないことは無い。一気に潜り抜ける他なさそうだ。
『第二階層へと続く道はマップに入力されている筈だ。ウィルス・バスターが作動したらこちらで報告する』
「・・了解。
第十七精鋭部隊副隊長・ロックマン・セイヴァー。これより任務を開始する。
任務内容はマザーコンピュータ内のウィルスの削除。ならびにそれの奪還である」
他の十七部隊員達はベース内のメカニロイド掃討にかからせているので、
事実上ここに存在する十七部隊隊員はセイアのみだ。
けれどセイアはわざと声に出して報告する。この号令はエックスがいなくなったあとから、一度も欠かすことなくしているものだ。
かつて部隊長であったエックスがそうであったように、セイアもその姿を追い掛けているのかもしれない――
『二時の方向にウィルス・バスター。数は二だ』
「了解・・!」
セイアが走り出したのに合わせるかのように、ウィドの指令がイヤー部分で響く。
セイアは指示通りに二時方向にバスターを放つ。が、流石はマザーのウィルス・バスターというべきか、
セイアの光弾を軽く回避した二体のウィルス・バスターは、現実世界では不可能な動きで、セイアとの間合をグッと詰めた。
「電脳内では自由自在ってことか・・!けど!」
なんとも形容しづらい形の二体のウィルス・バスターを前に、セイアはバックパックに搭載されている二本の柄のうち、左側のものを抜いた。
エックス・サーベルだ。瞬時に刃を具現化したサーベルで、セイアは飛び上がり様に電刃を放った!
現実世界とはほんの少し違う、グラフィックの電撃をまき散らす刃が、右側の敵機を破壊する。
運良く躱した左側だったが、セイアが着地するよりも前に放ったホーミング・トーピードによって、一秒後に粉々に爆散した。
ほぼ同時に足元に落下した二体分の破片は、地面に激突すると共にクズデータとなって崩れ落ちた。
成る程プログラム内では不必要なデータは即座に削除されるのかと納得しつつも、自分が撃破された時は同じ運命を辿ると思うと、
ほんの少し背筋が凍りついた。
『上手く撃破したな、だが第二階層前のゲートにファイア・ウォールがある』
「ファイア・ウォール・・。突破法は?」
『本来なら解除コードを検索し、入力するところだが・・生憎そんな時間はない。正面から突破しろ』
「乱暴な手段になるね・・」
『安心していいよ、セイア。幾ら壊したところで、操作が可能になれば幾らでもリカバリーが可能だろうからね』
通信に割り込んできたゲイトの声は嫌に楽観的だ。
が、それも悪くない。セイアは苦笑混じりの笑みを口もとに浮かべると、そろそろ見えてきた最初のファイア・ウォールを確認した。
流石はファイア・ウォールと名を冠するだけのことはある。セイアは冗談混じりにそう思った。
その外見は文字どおり炎の壁だったからだ。絶えることを知らない、空虚な空間から生み出される灼熱の炎。
確かにあれに無条件で触れれば、大抵のウィルスは地獄の業火に焼き尽くされることだろう。
だがセイアは違う。ファイア・ウォールの真正面で立ち止まると、肩幅に足を開き、両掌を腰の辺りで繋げ、構える。
手首の辺りで繋げられた両掌の間に、蒼と紅のエネルギーが除々に収束されていく。
それは、セイアがついこの前の学校内での闘いの時に新たなに手に入れたスキルだ。
両掌に集中させた高出力圧縮エネルギーを、線ではなく弾として撃ち出す一撃必殺。
その名は――
「波動拳!」
両手を回転させつつセイアがそれを前方に突き出すと、巨大なエネルギー弾が撃ち出された。
綺麗に蒼と紅の染められた炎に似たその弾は、燃え盛る炎の壁に直撃するやいなや、それをガラスが砕け散るかのように破壊せしめた。
見た目とは裏腹にパキンと高音を立てて砕けるファイア・ウォールを尻目に、セイアは走る!
現在位置は第一階層。目指すは第六階層。道のりは・・長い。
「波動拳、使えるなこれ」
『云っておくが今のお前より強い奴はそうそう見つからないぞ』
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
感覚が、薄い。視界は既に真っ黒に塗りつぶされ、指先すらピクリとも動かない。
さっきまでの不快感もない。除々に身体が舞うような浮遊感を憶えつつも、それとは裏腹に酷く身体が怠い。
必死に振り回したつもりの四肢は空を掻く。いや、四肢を動かしているような感覚すらそこにはなかった。
声を出そうとしても何も起こらない。まるで、虚空に自らの精神だけが置き去りにされたように。
あやふやになりつつある自らの記憶の中から、なんとか重大な部分を掘り起こす。
それでもハッキリとはそれが理解出来なくて、彼はもしかしたら自分が死んでしまったのではないかという仮説だけに行き着いた。
死とは無限の虚空。果てない孤独。それについて考えるようになったのは兄が死んでからだ。
自分が死んだとき、一体自分はどうなってしまうのだろうか。人間でもレプリロイドでも、一度はそう考えたことがあるだろう。
ある者は云う。死は絶対の結末だ。死の後には何も残らない、と。
しかしある者は云う。死とは一つの結末であり、一つの始点だと。
だが彼はそのどちらの考えにも同調はしなかった。
死とは無限の虚空。果てない孤独。何も無い真っ暗な空間に、完全に機能しない意識だけが放り出される。そんな、闇の世界。
そこでは身体という感覚も、自分という個体も、他人という存在もなにもありはしない。
あるのはただの真っ暗な空間のみ。そして、それを嘆くことすら許されない空虚な自分。たった、それだけ――
「・・・・・――・・」
声は出ない――当たり前だ――そんなことを考える自分の意識もそろそろぼやけ始めるだろう。
なにせ自分は死に直面しているのだから。その内自分は完全に消滅することも、復活することも許されぬまま闇に同化する。
そう、このまま。
薄ぼんやりとした意識の中で、彼がそんな幻想を許容しようとしているとき、彼とは違う別の声が囁いた。
『ヤァ、セイア』
「・・・・――?」
突然目の前に光球が現れた。ダークグリーンの光球だった。
どうやらその声はそこから発せられているらしく、その声に合わせて光球は点滅する。
光球はふよふよと浮遊し、くるくると自らの周りを回り始めた。彼にはそれが、踊っているかのように軽やかに見えた。
『コンナ真ッ暗ナ場所デ・・君ハ消滅シテシマウノカイ?』
「――・・――・・・」
何かを呟いたつもりだったが、声にはならない。
それが可笑しいのか、光球は更にはしゃいだように点滅し、弾んだ声で彼を誘う。
『勿体ナイナ。君ハマダマダ生キテユケルトイウノニ』
「・・・く・・は」
声が出た。少なくとも、自分の声として知覚出来る音の波が。
まるで光球が彼の周りを回れば回る程、彼の機能が戻っていくかのように。
必死に声を絞りだそうと喘ぐ。が、それでもまだ充分に声は出ない。
けれど意識は急速に鮮明になりつつあった。少しずつ少しずつ、『自分』という感覚が戻っていく。
『君ダッテマダ死ニタクハナイデショウ?』
「・・僕・・は・・っ」
『フフ。ダカラネ、ボクガ君ヲ助ケテアゲルヨ』
「僕を・・助け・・?」
『ソウ。ソウスレバ君ハ、生キルコトガ出来ルヨ。今ヨリモモットモット強クナッテネ』
「・・くっ・・ぅ」
あやふやの意識を、鮮明になりつつ意識が引っ叩いた気がした。
まるで暗闇の中で突然照明をつけられたかのように、意識の電気炉に電気が走る。
拳を握れと身体に命令する。見えはしないけれど、確かに拳という感覚がそれに応えた。身体が重力を感じ始め、半開きの瞳が開かれる。
「・・違・・う!」
違う。これは『死』なんかじゃない。この感覚は以前にも味わったことがあるのだ。
それがいつだったは思い出せない。きっと今思い出す必要もない。
けれど彼、セイアには判った。これは死でもなんでもない。これは――幻想だ!
「これ・・が・・!」
今まで身体を支配していた気怠さを強引に振りほどくように、セイアは全身に力を込めた。
ブチンと何かが弾けた音がして、身体の自由が投げ返される。
今まで楽しそうに踊っていたダークグリーンの光球は、それが不満なのか、ピタリとその動きを止めた。
「・・っ!これがお前の手か!」
そして完全に自らの者となった全身で、セイアは光球にバスターを向けた。
「人の心の隙に付け入って、再びボクを取り込む・・・。確かに有効的な手段かもしれない。
けど、その根性は相変わらずだなっ!」
そして自らの心を惑わそうとした自らの影の名を叫ぶ!
「イクセっ!!」
『・・ふ、あはははは。腐っても鯛だね、セイア?
同じ手を二度も使うなんて、君を舐めてたよ。これは失礼』
光球は人型へと変わった。見たくもない、ダークグリーンと変色したセイアの姿に。
セイアはギリッと歯軋りをしつつもチャージしたバスターを放つ。自らの闇を、そしてこの空間を斬り裂く為に!
「ボクの心はボクのものだ。お前には決して渡さない!」
『ふふふ。楽しみにしているよセイア。君と闘えるときのことをね』
そして蒼と紅のエネルギーは、文字どおり辺りの闇を斬り裂いていった。
「おぉぉおぉぉおぉぉっ!!」
所狭しと仮想ボディに貼り付いた金色の光球が、セイアの叫びと共に次々と砕け散った。
セイアはデタラメに全身を動かしながら、自らを侵す光球達を払っていくと、
さっきまで全く手応えがなかったそれらは、セイアの振り回す手足に砕かれ、クズデータとなってデリートされていく。
「お前等・・ぁっ!」
懲りずに殺到してくる光球を一瞥しつつも、セイアは身を翻した。
バッと全身で前方に何かを撃ち出すような仕草をとるセイアから、彼の輪郭を模した光の人型が前方へと駆け抜けた。
それをターゲットだと誤認した球体はそれに吊られ、激突していくものの、光の人型に触れた途端、それらは砕け散った。
所狭しと駆け巡る光の人型が放たれて僅か十数秒後、辺りの金の球体は数える程になってしまっていた。
「イクセめ・・。厄介なものを」
それはエックスがレプリフォース大戦内でスプリット・マシュラームより入手したソウル・ボディだった。
高圧縮エネルギーによって自らの分身を作り出し、相手にぶつける。その用途は撹乱から奇襲まで様々だ。
そしてなによりの特徴は、そのエネルギー密度。ソウル・ボディを形成するエネルギーの密度は、バスターやサーベルの比ではない。
そう金色の光球の正体は――マザーを脅かすウィルスそのものだ。
バスターやサーベルのエネルギー密度では破壊することが出来ない、非常に柔軟性に富んだ設計の。
だから今までのセイアの攻撃は全て通用しなかった。これを破壊する為には、これよりもエネルギー密度が高く、尚且つ攻撃力の高い武器を使用するしかない。
「もうお前達の弱点は判った。もう・・お前達にボクは止められない!」
残った数体の光球が、セイア目掛けて襲い来る。
が、もはやセイアの瞳に恐れも戸惑いも無い。
空円舞を駆使して空中へと大ジャンプし、追跡する形で追ってきた球体・・いや、ウィルスに天空覇を添加した空円斬を叩き付ける!
数えて七体のウィルスは、その場でスパンと真っ二つにされ、消滅する。
綺麗にスタンと着地するセイア。それとほぼ同じタイミングで、ウィドの通信がイヤー部分に響いた。
『・・ア、セイア!セイアっ!!』
「聞こえるよ、ウィド。五階層のエネミーは全部やっつけ・・」
『馬鹿野郎!』
いきなり怒鳴り付けられて、セイアはハトが豆鉄砲を食らったような顔をしてしまった。
通信の奥のウィドの顔は見えないけれど、その声が尋常でない程怒っているのは、セイアでなくても判る。
ウィルスを相手に戸惑いを見せなかった戦士は、怒った親友に身を縮めつつ、彼の名を呼んだ。
「ウィド・・」
『・・馬鹿野郎。心配かけさせやがって』
「・・ごめんね。でもボクは大丈夫だ」
『・・無事ならいい』
現実世界では、わなわなと震える手でイヤホンマイクを握り締めるウィドの姿があった。
本来なら、そこでゲイトがクスリとでもウィドに笑みを浮かべることだろう。けれど、ウィドも気が付かない間にゲイトの姿はそこにはなかった。
いつの間にいなくなったのか。ウィドがそのことに気が付くのは大分後かもしれなかった。
『全く・・無茶をする。お前も、ゼロも・・』
「え、何か云った?」
『いや、なんでもない。それよりも時間がない。第六階層へ向かうんだ』
「う、うん。了解!」
実際Dr.ゲイトは研究室のドアの前で闘っていた。というよりも、立っているだけに等しかった。
今のイレギュラー・ハンターの隊員数は非常に少ない。最近ようやく部隊制が戻ったといえど、その数は全盛期の半分にも満たないだろう。
だからこそ遠隔操作のメカニロイドが複数配備されているのが現状なのだ。結果的に云えば弱体化し減少した現状のハンター達は、
自らの下僕を止める術を持たない。一体一体ならばどうにかなろうものだが、数の勝負となると圧倒的に不利だ。
これはウィドも考えていなかったことなのだが、セイアがマザーにダイヴするにあたっての最大の問題は研究室の防衛だった。
隊員たちの宿舎から遠いこの研究室は、格好の標的だ。そんな場所で呑気にコンピュータを弄くる時間を与えてくれるメカニロイド達ではない筈だ。
だからこそ、ゲイトがいまここで研究室を護っているのだ。彼曰く『ボクの城』である研究室を。
「ふうむ。やっぱり予算が足りなかったのかな。ボクの作品にしては性能が低いみたいだね」
Dr.ゲイトは科学者型レプリロイドだ。
だがかの有名なナイトメア事件発祥の張本人である彼は、ゼロのDNAデータを元に造り出した自らの鎧でエックスと闘ったという前歴を持つ。
勿論ゲイト本人の戦闘力はハンターであるエックスには遠く及ばない。それでも彼がエックスと闘い、彼を大いに苦しめた理由がこれだった。
「最も一体一体にこのボクのナイトメア・アーマーが破壊されるようなことは有り得ないんだけれどね」
今、ゲイトの全身は金色の鎧に包まれている。おおよそけばけばしいと形容しても過言ではないほど、キンキンに輝くド派手な鎧。
それがゲイトの云うナイトメア・アーマーであり、エックスを大いに苦しめた要因であった。
ゼロのDNAのデータをフル活用して作成されたこの鎧は、かつてのハイマックスの剛性を大きく上回る。
その剛性はエックスのフルチャージの一撃をも全く受け付けない程だ。それ程の剛性を持つ鎧が、たかたが量産型メカニロイド程度に破壊されうる筈もない。
ゲイトはただ単純にある程度のメカニロイドが群がってきたところで、ナイトメア・ボールと名付けられたエネルギー弾を投げるだけで良かった。
「ふふふ。ボクの城には指一本触れさせない。その代わり、君達にはボクの美技をとくと見せて上げようじゃないか!」
今のゲイトを止めることは、恐らくセイアでも不可能であろう。
「ようやくここまで辿り着いた。さぁ、姿を現わせウィルス!」
第六階層へ辿り着くや否や、セイアは声を張り上げた。
声の波というデータは、プログラム配列の隅から隅までを走っていく。現実世界の常識が通用しないここならば、きっとどこまでも声の波は届いたであろう。
マザーコンピュータの第六階層。そこはイレギュラー・ハンターの最も深い領域であり、同時にマザーのCPUの中枢。
確かにここを攻撃されればマザーは容易く墜ちるであろう。問題は、ここまで辿り着く程の強力なプログラムがあるかどうか。
――事実マザーが暴走しているのだから、その答えはYesなのだが。
さっきまでの第一階層から第五階層と較べ、第六階層の作りは偉く単純だった。
簡単に現わすとすれば、真四角のただっ広いフィールド。その側壁にはさっきまでと同じ模様が走っているが、目立った突起物はどこにも見受けられない。
本当に正真正銘の最深部なのだろう。何故かセイアはその作りに納得してしまった。
「・・・!」
セイアの声が隅から隅まで届いたのを見計らったかのように、セイアの斜め上に光の輪郭が現れ始めた。
ブゥンという不可解な効果音を発しながら、それは少しずつその姿を形成していく。
セイアが想像していたものよりも随分と現実味を帯びた姿だと思う。
思いの外それは人型だった。いや、動物をモチーフにした人型レプリロイドといった方が正しいのかもしれない。
赤紫の外装に、大きく伸びた複数の羽。ゲイトのアーマーと同じくらいけばけばしいその姿に、セイアは確かに見覚えがあった。
同時に今までの事柄全てに合点がいく。マザーの暴走も、さっきの複数のウィルスも。
セイアは呟く。ハイパー・リミテッドの恩恵を受けたであろう、黄泉より蘇った電脳世界の狂気の名を。
「サイバー・クジャッカー・・」
自分の名を呼ばれ、クジャッカーはクックックと狂気的な笑みを浮かべる。
するとふっと彼の姿が掻き消え、すぐにセイアの目の前へと現れた。
電脳世界においてクジャッカーは全ての法則を無視して移動することが出来る。
このフィールドは、いわばクジャッカーのクジャッカーによるクジャッカーの為の戦闘領域だ。
現実世界より参入したセイアは、この状況において極めて不利。
それを理解しつつも、セイアはエックス・サーベルを抜くほか無かった。
コイツが暴走の原因である以上、例えここが奴専用のフィールドであろうとも闘わなければならないからだ。
『セイア、もうオペレートの限界時間が迫っている・・!イ・・ア、・・ア!』
「ウィド!・・一人で闘えってことか」
ウィドの声が聞こえたのはほんの数秒だけで、すぐにその声はフィードアウトしてしまった。
本当に限界時間を過ぎてしまったのか、それともクジャッカーがジャミングしたのかは判らない。
けれど確かなことは、ウィドの助言を得ずにコイツを倒さなければならないこと。それだけだ。
「・・けど、それでも構わない。兄さんもたった一人でお前と闘い、お前を倒したんだ。ボクだって!」
戦闘体制を整えたセイアに、クジャッカーは狂気的な笑みでそれを迎える。
リミテッドによって暴走した意識でも理解出来たのだろう。これから楽しい『狩り』が始まる、と。
彼はリミート・レプリロイドにしては珍しく言葉を吐いた。もはや意味を理解することがやっとの、機械的な口調だった。
『オ仕置キノ時間ヨ』
「行くぞ・・!」
気合の声と共に、セイアは地面を蹴る!フルスピードのダッシュの瞬発力を利用し、クジャッカーの懐まで飛び込んだセイアは、
斬り上げる形で燃え盛る龍炎刃を薙ぐ!
データにあるクジャッカーの弱点攻撃はソウル・ボディと龍炎刃。もっと云えば、高エネルギー密度を持つ武器と、炎属性を持つ武器だ。
セイアの武装リストを漁れば、そんな武装は幾らでもある。クジャッカーがエックスと闘ったときよりもパワーアップしていることは明白だが、
セイアには数知れない武装の利がある。
「っ!?」
だがセイアの龍炎刃は空を掻いた。
これが現実世界であれば確実に斬り込まれていただろう刃は、クジャッカーが直前で姿を消した為に外れてしまったのだ。
すぐに着地してクジャッカーの居場所を突き止めようと身体を捩るセイアだが、それよりも早くクジャッカーがセイアの背後に現れ、
その孔雀を模した大きな羽の一撃を彼の背に突き立てた!
落鳳破の元となったクジャッカーの羽の一撃は、成る程確かにエネルギー消耗の激しい技の元となっただけの威力がある。
すれすれで飛燕脚により急所を外したのは幸いだったけれど、このダメージはかなり重い。
飛行途中でバランスを崩され、セイアは地面に激突する形で先程の目的を果たした。
「ぐっ・・!ちぃっ!!」
起き上がり様にチャージ・ショットを見舞うが、やはり直撃の寸前でクジャッカーは姿を消してしまう。
どこだ――セイアはクジャッカーの姿を追うものの見つからない。だとしたら、クジャッカーは・・・自分の背後にいる!
「くっ!」
再び落鳳破の一撃を受けそうになりながらも、咄嗟に発動させた氷狼牙がセイアを救った。
瞬時に天井までの大ジャンプを行い、難を逃れたセイアは、そのまま天井を蹴り、断地炎をクジャッカー向けて放つ!
流石にクジャッカーの処理速度もついてこれなかったのか、断地炎の炎がクジャッカーを包む。
男性型にしては高過ぎる気色の悪い声で悲鳴を上げつつ、炎上したクジャッカーはのたうち回る。
セイアはその隙を見逃さない。すぐに両掌にエネルギーを収束させると、一撃必殺の波動拳を二発!
「時間がないんだ。眠れクジャッカー!」
が、セイアの波動拳が放たれるよりも、クジャッカーが断地炎の炎から逃れる方がほんの少し早かった。
波動拳がクジャッカーの残像を砕く。「なに!」とセイアが声を上げた瞬間には、セイアの背をエネルギーの槍が打っていた。
前につんのめりそうになりながらも、セイアは前転する形でなんとか体制を立て直す。
槍の飛んできた頭上を見上げると、両手を大きく伸したクジャッカーが眼下のセイアを見ていた。槍だと思っていたのはクジャッカーの羽だったのだ。
よくよく見ればセイアの胴の部分にロックオンのグラフィックが重なっている。恐らくあれがエイミング・レーザーの元となった技に違いない。
「くっ・・。人の背後ばかりを狙う戦法は相変わらずか」
エックスが闘ったクジャッカーも、場所は違えどサイバー・スペース内のものだった。
その際もエックスは背後ばかりを取るクジャッカーの戦法に苦しめられた。全く兄弟揃って舐められたものだと、セイアは舌打ちするが、
この状況を打破出来ないのであればどうしようもないこともまた事実だった。
『逃ガサナイワヨ』
「やる気だな・・!」
クジャッカーの無数の羽が、ホーミング弾として次々とセイアを襲う。
ロックオンされた標的をしつこく狙うホーミング弾は、止まることを知らない。データにはエイミング・レーザーには射程距離があると記されているが、
リミテッドによってパワーアップしたクジャッカーにそんなデータは通用しそうもない。躱すか打ち消すしかないのだ。
ある程度ダッシュと三角蹴りを駆使して逃げ回ったセイアだが、留まることを知らないクジャッカーの連射に、いつまでも逃げきることは不可能だった。
二、三発諸に受け止めてしまったセイアは、やがて躱すことを止めた。
真っ直ぐ一番遠い壁までダッシュで移動したセイアは、雨のように群がってくるエネルギーの槍の雨に、
バックパックの右側のセイバー・・ゼット・セイバーを抜いた!
「ボクがいつまでも逃げ回ってると思うなよっ!はぁぁっ!!」
エックス・サーベルとゼット・セイバーの二刀流!両の剣に同時に天空覇を付加し、更に双幻夢を使って己の姿を二つと分ける!
四本の刃が降り注ぐエネルギーの雨にを迎え撃つ。余りにも一瞬の間に数多くのエネルギーがぶつかった為、その付近一帯を爆風がさらった。
勿論双幻夢を駆使したセイアもその爆風に呑まれる。クジャッカーはその様を見てけたけたと腹を抱えて笑った。余りに悪趣味な笑いだった。
やがて爆風が晴れ、ボロボロの仮想ボディを抱えたセイアが姿を現わす。
メット部分のデータが吹き飛び、髪が露出し、肩アーマーは両肩共にない。酷く足りなくなった少年は、立っているのがやっとだった。
二本の剣のうち一本を失ったらしく、その手には申し訳程度に刃を具現化する光学剣が一本しかない。
それを地面に突き刺して杖代わりにしているのだ。今の彼に、攻撃力は殆ど残されていないだろう。
しかしクジャッカーに慈悲という言葉はない。無情にもカーソルをセイアの胴にロックオンすると、
再びエネルギーの雨を降らせた。今度は四つの天空覇など放てないセイアは、次の瞬間には砕け散るだろう。
そして仮想ボディを破壊されたセイアは死ぬ。メインプログラムを破壊され、完璧に消滅するのだ。
『オーッホッホッホッホ!!』
ザンっ!!
「砕けるのは・・・お前の方だ!」
『グギャアッ!?』
クジャッカーの笑いが止まった。
クジャッカーの胴には、光の刃が生えていた。
それを刺しているのは、キラキラと輝く紅の鎧に身を包んだ少年だった。
クジャッカーが悲鳴を上げると共に、雨のようなエネルギーに晒されたボロボロの少年のデータが消滅する。
もはや修復不能にまで破壊されたあのデータは、もう二度と同じ姿には戻らないだろう。
「双幻夢だ・・クジャッカー。お前が例えこの電脳世界で自由に動き回れるとしても、ボクはその更に上を行かせてもらう!」
そのままゼット・セイバーを振るい、クジャッカーを地面に叩き付ける。
そして自らも落下しつつ、ソウル・ボディを発生させる。
空中で停滞したソウル・ボディと、そのまま着地する本体。落下速度がやけにゆっくりだったクジャッカーより、セイア本体が着地する方が早かった。
セイアは握り締めた右の拳に炎を宿す。エックス・ラーニングがフル回転しているのだ。
セイアのプログラム内で、再び二つの技が一つになった。今回チョイスされた必殺技は、昇竜拳と龍炎刃。
共に対空攻撃の頂点に君臨する必殺技の初代と新米。その二つが完全に一つとなった時、
セイアは地面を砕くほど強大な炎と共に飛び上がった。燃え盛る炎を携えた拳と共に!
「神龍拳ーっ!!」
そして同時に神龍拳となった新ラーニング技のデータを転送されたソウル・ボディが、
空へ再び舞い上げられたクジャッカーに、炎の昇竜拳の連撃を見舞う。昇竜裂破だ!
『グギャアッアッァァツァッァァッァ!!』
新たなラーニング技を二発も受けても尚立っていられる程、クジャッカーは頑強ではなかったようだ。
全身にグラフィックの炎を燃え上がらせたクジャッカーは、なんとかそれを振りほどこうと空中でもがくが、セイアの炎は決して甘くはない。
除々にクジャッカーの身体を蝕んでいく炎。それでもクジャッカーはしぶとくセイアを狙おうとしているのか、
セイアの胴にカーソルを合わせた。
「まだ動けるのか・・!?」
が、クジャッカーのエネルギー弾がカーソルに届くことはなかった。
「君はもう用済みだ。足掻くのはみっともないよ」
「・・・!?」
ダークグリーンの閃光がクジャッカーを呑んだ。
余りにも一瞬の出来事だった。気配すら感じさせず、それを放った者はセイアの後ろにいた。
微かに煙の立ち昇るバスターをふりふりと振りながら、やってのけたこととは程遠い笑みでセイアを見る彼。
パラパラと落ちてきたクジャッカーのクズデータを見る目は、その笑みとは裏腹に酷く冷たかった。
「イクセ・・!」
「やぁ・・セイア。何を遊んでいるのかな?早くコイツを倒さないとマザーが危なかったんじゃないの?
その割には随分手を抜いてたみたいだけど。大きなお世話だったかな?あは」
「くっ・・」
「それとも・・これが君の実力だなんて云わないよね。そうだとしたら、ボクはガッカリしちゃうかな」
相変わらずの軽い口調には反吐が出る。云っていることは要約すれば「君はこんなにも弱い」・・ということ。
わざわざここに来たのはセイアに自分との力の差を見せる為か、それとも単に遊びに来たのか。
どちらにしても太刀合わせに来たことは間違いない。セイアは、キッとイクセを睨み付けた。
「あーん恐い恐い。そんなに睨まないで欲しいなぁ。そんなに慌てなくっても、君とはゆっくり遊んで上げるよ」
「何の用だ・・!」
「随分表情が硬いなぁ、セイア。学校に居たときはもっとにこやかだったじゃない。健次郎君」
いちいち人をおちょくったような言動を放つ奴だ。
セイアはカッと全身が熱くなるような感覚を憶えながらも、なんとかそれを抑えつけるコイツを相手に怒りを解放すれば、コイツの思う壺だ。
しかしイクセはセイアの感情を奥の奥まで理解しているのか、また嫌味っらしい蔓延の笑みを浮かべた。
「あれあれ?随分と気が立ってるみたいだね。ボクがそんなに気にくわないかい?」
「・・・」
「あはは。当然かもね。知ってるかい?
人は自分を見ると不愉快になるんだ。だから君はボクを認められない。ボクを見ると不愉快になるんだよ」
「だ、黙れ!ボクと闘いにきたのなら、素直にそう云ったらどうだ!!」
ブンッと頭を振って怒鳴るセイアだったが、それもイクセには通用しない。
イクセにはセイアの全てが判っている。セイアの性格も、セイアの感情も、セイアの闘い方も全て。
もしゼロが今のセイアを見たのなら云ったことだろう。「闘いの中で無闇に感情を乱すことは死を招くことだ」、と。
「闘いたいのは君の方じゃないのかい?うふふ、まぁいいか。どうせボクは君の云うとおり、君と遊びに来たんだから」
「くっ・・勝負だイクセ!!」
マザーの機能が完璧に戻ったというのに、再び闘いは始まってしまった。
セイアはすっかりダイヴアウトのことすら忘れていた。目の前の自分自身の影に、それ以外のものが見えなくなってしまっていたのだ。
『セイア!セイア、応答しろ!』
既に回復した通信で、何度もウィドはセイアに呼びかけていた。が、答えはなかった。
正確に云えば答えの代わりにセイアの怒声だけが聞こえていたと云うべきだろう。
「イクセぇぇぇっ!!」
「あはははは、そんな直情的な攻撃がロックマン・エックスの名を継ぐ者の闘い方かい?大笑いだよ!」
セイアのバスターはイクセを掠るすら出来ない。
紅の光弾の弾道を全て読みきっているのか、イクセはひょいひょいとわざわざセイアを馬鹿にするような動きでそれを躱し、
その度に嫌らしい笑い声を浴びせた。
セイアがゼット・セイバーによる接近戦を仕掛けると、イクセも同じようにバックパックのサーベルを抜き、それに応じた。
だがセイアの斬撃はどれも当たらない。イクセが的確に受け止める刃によって、セイアの斬撃は全て受け流されてしまうからだ。
「つまらない。つまらないなぁ、セイア。もっと本気で闘って欲しいよ」
「黙れ・・黙れぇぇ!」
「それともまだ本気になれないのなら、ボクがさせて上げるよ」
イクセのサーベルの動きが、セイアには全く予想出来なかった。咄嗟にガード・シェルを出して防御したつもりの攻撃が、
いつの間にか背後から放たれていて、セイアは地面に倒れ込んだ。
イクセの突きが、セイアの左胸を深々と裂いたのだ。これが現実世界なら一撃で機能が停止していただろう攻撃だが、
この電脳世界ではどこに心臓部があろうと関係ない。しかし受けたダメージが深刻なことに代わりはなかった。
立ち上がろうと地面に手をついても、ぶるぶると腕が震えて力が入らない。
どれ程の一撃だったのかが一目で判る程のダメージだ。少しずつ視界がぼやけ始めて、嫌らしいイクセの笑みから遠くなっていく。
「くっ・・・そっ・・ぉ」
「・・正直期待外れだよ、セイア。君がボクの宿主だったと思うと、本当に残念だ」
「っ・・ちっく・・しょぉっ・・」
――駄目ダ・・・コイツニハ勝テナイ
頭のどこかで誰かがそっと囁く。それは絶望的な言葉だった。
――コイツハ強スギル・・
自分の攻撃が全く当たらない。どんな技も、的確に躱されてしまう。
――ボクハ・・コイツニ殺サレル・・
視界がぼやけていくほど、頭の中の声は絶望の度合いを増していく。
勝てない。殺される。負ける。強すぎる。恐い。恐い。
コワイコワイコワイコワイコワイコワイコワイ
『諦メルノカ』
「だ・・れ」
もはや意識が半分以上消失したところで、セイアに呼びかける声があった。
ウィドの声ではない。かといってゲイトでも、勿論イクセのものでもない声。
肉声・・ではない。この電脳世界内で肉声というにもおかしな表現だが、ともかくそれは空気が振動して伝わってくる声とは違う気がした。
頭の奥に直接叩き込んでくるその声は、酷く機械的だった。まるで20XX年代のロボットのように。
『私ハ・・マザー』
「マ・・ザー・・?」
『ソウ。トハイエ、私ハソノ末端ニ過ギナイガネ』
「ふふ、どうしたの、もうお終いかい?最初の勢いはどこに行っちゃったのかなぁ」
マザー。そしてそれと話すセイアの声がイクセには聞こえないのか、彼は倒れ伏したセイアを余裕の笑みで見下してくる。
勝利と落胆の入り交じった声で話すイクセの笑みは、セイアには酷く嫌悪感の対象として映るだろう。
けれど今のセイアにそれはない。意識は頭の中で話すマザーの方へ向いてしまっていたからだ。
「ど・・して」
『セイヴァー。君ガウィルスヲ除去シタコトデ君ニアクセススルコトガ出来ルヨウニナッタノダ』
頭の中の声に意識を集中させながらも、セイアはぐっと身体を持ち上げた。
イクセはそんなセイアの抵抗が嬉しくて堪らないのか、ようやく起き上がったばかりのセイアを思い切り蹴飛ばした。
後方の壁まで叩き付けられたセイアは力無く呻く。それでもまだ痛ぶり足りないというのか、イクセはつかつかとセイアに歩み寄ってきた。
『・・セイヴァー、今カラ君ヲダイヴアウトサセル』
「なん・・だって・・!?」
『君モ判ッテイルコトダロウ、セイヴァー。目ノ前ノ敵ニ君ハ手モ足出テイナイ。デリートサレル前ニ・・』
「嫌だっ!」
「・・へぇ」
マザーに向けて怒鳴った声は、どうやら実際にも口に出していたらしい。
イクセは自らの拳を受け止めたセイアが、自分自身に向けて放った言葉だと思ったらしく、クスリと一つ喉で笑う。
力いっぱいの握力でイクセの拳を握り締め、セイアは思い切りそれを引き寄せた。
意外なセイアの握力に驚いたのか、イクセが抵抗するより先に、彼のダークグリーンの鎧が紅蓮の鎧に吸い寄せられる。
セイアは頭の中でマザーに必死で抗議しつつ、もう片方の紅蓮の拳をイクセの顎先目掛けて叩き込んだ!
『馬鹿ナ・・。勝チ目ガナイコトハ判ッテイル筈。ココハ大人シク引クノダ』
「嫌だ・・、嫌だ。コイツから逃げるなんて、僕は・・僕は!」
『マテセイ・・・・・。・・イイダロウ』
なおもセイアを引き留めようとするマザーの台詞は、途中で止まった。
またウィルスが再発したのかと思いきや、それは違う。次に紡いだのは、無謀とも云えるセイアの行動を承認する言葉だった。
「昇竜拳か。ドラグーンなんかより一味も二味も鋭いよ。けど・・それじゃあボクには勝てない」
『外部カラ君ニアクセススル者ガイル。インストール所要時間ハ約三秒。ソノ隙ヲ、私ガツクリダソウ』
昇竜拳を受けたイクセは、吹き飛ぶどころか顎すら仰け反らない。
顎の力だけでセイアの拳を押し返し、お返しとばかりに暗黒の炎を宿した昇竜拳でセイアを天井へと叩き付ける。
打撃の衝撃と衝突の衝撃を諸に受け止めたセイアは、受け身をとることもままならずに地面に激突する。
が、彼はまだ倒れなかった。頭の中で呟いたマザーの言葉を信じ、三度立ち上がったのだ。
「判った・・お願いするよ、マザー」
セイアに直接データをインストールしようとしている者。それは、セイアの予想通りウィドとゲイトだった。
現実世界では今丁度ゲイトがザコ掃除を終え、研究室に戻ってきていた。
ウィドは応答しないセイアに怒鳴り声を上げ続けていて、ゲイトが驚いて状況を確認した、ということだ。
「セイア、セイア!応答しろっ!!」
「ウィド君。そんなに声を上げては喉を壊してしまうよ」
「煩い!セイアが応答しないんだ。今セイアは・・!」
「・・・セイアと同じデータがダイヴした形跡があるね」
「・・何っ?」
ウィドの怒声とは裏腹に、落ち着いた仕草でキーボードを叩いていたゲイトが呟いた言葉だった。
ゲイトは「ふうむ」と疑問符を浮かべている様子だったが、ウィドは違った。
セイアと・・ロックマン・セイヴァーと同じデータ・シグナル。そんなものを持つ者は少なくともウィドの記憶の中では一人しか浮かばなかった。
「・・イクセだ」
「うん?」
「セイアは恐らくイクセと闘っているんだ。奴もマザーにダイヴしていたんだ」
「イクセ・・。ああ、確かセイアにそっくりなリミテッドの名前だったかな」
「・・だとしたら、セイアに勝ち目はない」
セイアは今、殆どなんの追加装備もない状態でマザーにダイヴしている。
各種アーマーのデータも殆どが破損していて、仮想ボディとしてですら強化することがままならなかったからだ。
追加装備があると云えばゼット・セイバーが新たなに追加されたのみで、あとは全くのノーマル状態。
そんな今のセイアがイクセに勝てる確立は殆ど無い。
恐らくはサイバー・クジャッカーとの闘いでエネルギーを消耗しているのだから間違いない。
「今すぐダイヴアウトを!」
「待つんだウィド君」
「なんだ。ダイヴアウトしなければ、セイアがデリートされちまう」
「だが仮想ボディをダイヴアウトの状態に切り替えなければダイヴアウトは不可能だ。
それを無理矢理実行したら、それこそセイアが消去されてしまうよ」
「ならどうしろって云う・・・。・・いや、待てよ」
ゲイトの胸ぐらに掴み掛かりそうな勢いだったウィドだが、何か思い当たる節があったらしく、わたわたと忙しく走り回り始めた。
何かを探し回っているらしかったが、なかなかそれが見つからないらしい。イライラし始めたウィドに、
ゲイトは懐から一枚のデータディスクを取り出して見せた。
「捜し物はこれかい?」
「それだ!」
ほとんどひったくる形でディスクを受け取ったゲイトは、すぐにそれをモバイルのスロットに差し込んだ。
ガチャガチャとキーが潰れそうな勢いでキーボードを叩く姿は、まさに鬼気迫る感じだな。
ゲイトはそう思った。
「その未完成のアーマーをどうするつもりだい?」
「このデータをセイアに転送する。例えこれが未完成でも、奴を退けるだけの力はあるはずだ」
「・・もしデータにエラーがあれば、セイア自身に影響があるかもしれないよ」
「それでもイクセにセイアを倒されるよりはマシだ」
そして黙々とキーボードをたたき続けるウィドに、ゲイトはそれ以上何も言おうとはしなかった。
しかし――ゲイトは思う。果たしてこんなモバイルから、こんな膨大にデータをマザーが受け取ってくれるのだろうか、と。
普通ならば復旧されただろうファイア・ウォールが発生してそれを拒んでしまう。
それを突破するとすればかなりの労力だ。今からそんなことをしていたら恐らく間に合わないだろう。
「よし・・・!」
が、ゲイトの予想とは裏腹に、未完成のアーマーのデータはマザーへと転送されていった。
そんな馬鹿なと頭の中でも思うものの、事実は事実だ。
かつてエックスが云っていた、データだけでは観測できないものがあるというのはこれなのだろうか。
それは単にセイアと会話するマザーがデータをインポートしてくれたに過ぎないのだが、
ウィドやゲイトにとって、それはまさに『奇跡』だった。
『ヨク聞ケ。私ガ床ノ一部ヲ爆破シ、奴ニ隙ヲツクル』
「あははは、それそれそれ!」
イクセのバスターを二刀流の天空覇で打ち消すことが、今のセイアの限界だった。
戦況は防戦一方。セイアは初めから全力で闘い、イクセは依然として余裕な表情を崩さないところを見ると、その力の差は明らかだった。
だが、そんな戦況が一気に覆された。マザーの宣言通りにイクセの足元の床が破裂し、彼に一瞬の隙を作ったからだ。
「うあっ!?」
『ソノ隙ニ一撃ヲ叩キ込ムノダ。三秒間デイイ。奴ヲ食イ止メラレル一撃ヲ』
「うぉぉぉぉぉぉぉっ!」
マザーに後押しされ、セイアは叫ぶ。
咄嗟に両掌にエネルギーを集中し、増幅させ、そして放つ!
今のセイアが出来るであろう全ての力を込めた波動拳だ。
「くっ!」
完全に防御を解かれたイクセが、そのまま後方へと吹き飛び、側壁に激突する。
姿勢を崩しそうになりながらも、セイアはマザーが直接浴びせ掛けたデータを、文字どおり全身で受け止めた。
『Move Cross Armor To Saver』
その瞬間光が迸った。セイアの胴を、四肢を、バスターとサーベル・・セイバーを貫く閃光。
蒼の光。紅の光。それがセイアのアーマーの上に、更に一回り大きな鎧の輪郭を描き始める。
――暖かい。
疲れきった身体を包み込む温もりに、セイアは思わず眼を閉じた。
懐かしい誰かの温もりに抱かれて、ロックマン・セイヴァーは進化する。
そう・・かつての英雄の、兄達の、ロックマン・エックスとゼロの温もりに抱かれて。
――兄さん!
「おぉぉおぉぉぉぉっ!!」
セイアの絶叫と共に、彼の全身を包み込んでいた光が晴れた。
その鎧は、変わっていた。恐らく彼と彼の兄達を知る者ならば、全員が彼等三人全てを連想するだろう不思議な鎧。
セイアの傷も疲労も、全てを包み込む新たな鎧は、セイアが今まで着けてきたどの鎧とも違った。
力が漲るのを肌で感じる。いや、それ以上に荒れ荒んだ心が落ち着いていくのが判った。
「ふふふ、それが君の奥の手かい?面白いじゃないか!」
初めてイクセの表情が変わる。余裕の笑みから、勝敗の判らない闘いへ臨む者の顔へと。
パッパッと埃を払う仕草をするイクセは、やがて真っ直ぐにセイア目掛けてバスターを向けた。
初めてイクセのバスターに光が宿る。通常弾でも恐るべき威力があったイクセのバスターは、果たしてどれ程凶悪な破壊力を吐き出すのか。
さっきまでのセイアなら、その威力に恐れ戦いたことだろう。けれど今は違う。
「兄さん、もう一度ボクに力を貸して・・!」
静かに頭上に掲げるゼット・セイバーから、天をも貫く勢いの巨大な刃が現れる。
このクロス・アーマーのギガ・アタックのエネルギーを全てゼット・セイバーに流し込んで放つ、セイアの奥義。
それはかつてDr.ワイリーとの最終決戦の際に一度だけ放つことを許された禁断の技であり、
二人の兄の最強の必殺技を寄り合わせた究極の一撃。
「勝負だイクセ!」
「さぁ・・見せてご覧よ。君の力をさぁっ!!」
「うぉぉぉぉ!!」
イクセのバスターが火を吹いた。同時に、セイアが振り下ろした巨大なゼット・セイバーから、刃を模した強力なエネルギー波が飛んでいく。
現実では不可能だろう速度で飛翔する二つの力は、二人の丁度真ん中で激突する。
一瞬の均衡のあと、それに勝利したのは・・・――
「ソウル・・ストライクっ!!」
――・・・そして静寂が戻る。
立っていたのは蒼と紅の鎧、残ったのは抉られた電脳の床だった。
セイアは仮想ゼット・セイバーが砕け散り、ガクんと膝をつく。
さっきまでイクセが立っていた場所には・・何も無い。イクセが砕け散ったクズデータも何も。
「・・・・」
セイアは振り返る。本当なら気付きもしないだろう小さな気配に。
「ふふ・・油断したよ」
イクセは立っていた。ザックリと胸に斬り込まれた傷を抱えて。
もしこれが現実世界ならば致命傷になっていただろう傷だが、
余程頑強なデータ構造をしているらしい、デリートには至らなかったようだ。
「イクセ・・」
「まさかこんな隠し玉があるなんてね。流石のボクも吃驚だ。
今回は引くしかないみたいだね。でも、遊びとしては面白すぎたくらいだよ。ありがとうセイア」
けどね・・・、とイクセは付け足す。
ニコッと彼は頬笑んだ。彼を知らない者なら、可愛らしい無邪気な笑顔だと形容するだろう。
けれどセイアは違う。彼の裏側にあるドス黒い部分を知るセイアには、それがただの仮面にしか見えなかった。
そして案の定イクセは言葉を紡ぐ。その空気に触れた血のようなドス黒い表情を表に出しつつ。
「次はないよ」
そしてイクセは消えた。己が光の線となって、天井の方へと。
ダイヴアウトしたのだ。セイアが同じことをすれば、彼と同じようにこの電脳空間から排出されるだろう。
後に残ったのはイクセの笑い声。もはや狂気的という言葉がピッタリかもしれない程、狂った高笑いだった。
「エックス兄さん、ゼロ兄さん・・」
ダイヴアウトすれば消えてしまう、自らを包む二人分の温もり。
セイアはそっと胸の部分に手を当てた。こんなに暖かいのに、
こんなに実感があるのに、現実の世界に戻れば消えてしまう温もりが今のセイアには酷く寂しかった。
けれど同時にセイアは感じていた。兄達の絶大な力を。
その力はきっと、セイアに闘えと云っている。奴等を止めるために。自分達の代わりに、皆を護れと。
セイアは内側から聞こえてくる彼等の声に、静かに頷いた。
自分に課せられた責任を確認するように。自らが彼等を生み出し、そして自分自身で倒さなければならないという決意を胸に。
――うん・・判ったよ兄さん達。ボクはロックマン・セイヴァー。だからボクは・・。
『セイア・・聞こえるか』
「・・ウィド?」
『無事、だな』
「・・・うん、ありがとう」
身を包むクロス・アーマーとの別れを、セイアは感じていた。
ダイヴアウトが近いからだ。けれど、セイアは決してそれを拒否することはしない。
次に現実でこれを身につける時は・・これを着けるに相応しい心でこれを受け止めたいと思うから。
『ダイヴアウトするぞセイア。かなりの疲労が溜まっている筈だ。すぐに休息を取れ』
「判った。任務完了、これよりダイヴアウトします」
己が身体が光の線となるのを感じながら、セイアは一粒の涙をこぼした。
判ってはいたし、覚悟はしていたことだけれど、まるで再び兄達との別離を迫られたような気がしたからだ。
――セイアの感傷を尻目に、光の線となったセイアは、電脳世界の天井へと呑み込まれていった。
次回予告
闘いは終焉へと向かう。
イクセ達リミテッドに捕えられた僕と、呼び出されたウィド。五人の最終決戦が始まる。
違う!お前達は兄さんなんかじゃない!
究極の鎧を再び携えた僕の前に、遂に最凶の敵・デス・リミテッドが立ちはだかる!
これが最後だデス・リミテッド!勝つのは・・・勝つのは僕だ!
次回 ロックマンXセイヴァーⅡ 最終章~君を忘れない~
・・そして少年は・・・――