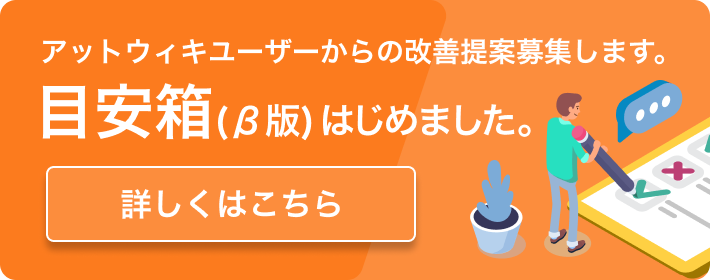「姫・症候群 第一話」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「姫・症候群 第一話」(2008/08/20 (水) 20:54:15) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
子供の頃、つまらない童話が好きだった。囚われのお姫様が、王子様に救い出してもらうストーリー。
まだ私が小さかった頃のことだ。夜眠る前、私は母に読み聞かせてくれるよう、よくせがんだらしい。最初は三日で一冊のペースの、眠る前のわずかな至福に過ぎなかったのが、次第に、二日に一冊、一日に一冊、とペースを上げていった、というのは、私の幼少時を振り返るとき、母がいつも口にするセリフだ。
文字の読みかけははやかった。次第に読み聞かせてもらうだけでは物足りなくなった私は、自ら絵本と格闘するようになり、すぐに読む能力を身につけたからだ。幼稚園での周りの子たちは、まだ本を読むことのできない子ばかりだったので、私は他の子たちに読み聞かせもした。最初は数人の仲間うちだけだったのが、徐々に評判になり、最後には、先生のかわりに読み聞かせを担当することもあったくらいだ。
小学校に上がり、読む本の内容も少しずつ複雑になっていく過程で、しかし私は童話の影から逃れられなかった。私が心を躍らせる本の背後には、いつだって不遇なお姫様がたたずんでいたのだ。
私はなぜ童話が好きなのか、というのは、私の持つ数少ない謎だ。お姫様に共感していたとか、別段そういうわけではない。自分の境遇に不満はなかったし、自分の様々な素材にも、それなりに自信を持っていた。不遇だなどと思ったことは少しもない。同年代の女の子たちが少女漫画の主人公に憧れを抱いていた時期も、私は至極淡白にすごしたくらいだ。
ただ、ある一点のみ、わかっていることがある。私はお姫様たりえないということだ。
童話のお姫様は、押し並べて皆美人だ。私はこれといって美人というわけでもない並の女の子。だからといって、それが不満であることはない。普通であることは、私にとって喜ばしいことだ。一番大きな集団に属していることは、私を安心させる。
普通の私、美しいお姫様。その違いは、確かな。
王子様は来ない。
そんなこと、分かっていた。
それでいいと、思っていた。
***
その高校を選んだのは、カソックのような制服が可愛かったからだ。付け加えるなら、女ばかりの空間というものにも興味があった。
男の子には見せない、底の方に眠っているものが、私にはある。そういったものを曝け出せる三年間も、それはそれで悪くないと思ったのだ。
高校の入学式。聖書の一節が講堂に反響する中で、私の中身は組み変わっていった。底の方にたゆたっていたその得体のしれない液体が、毛穴から体の表面に噴き出してきて、ぬらぬらと肌の上を這い、体を包む。急に、おしりにあたっているイスの感触が固く感じられる。座っているのが、少々息苦しい。講堂の天井が、めまいがするほど高い。おしりの位置を、もぞもぞと微調整。長い方は動きづらそうだから、と選んだ短めのスカートが、なんだか心もとない。スカートから出た膝小僧の白さが、眼球の奥にじんわりとしみ込んでくる。後ろで結った長い髪に、引っ張られるような違和感。かくん、と首が後ろに曲がりそうになる。すずしいうなじが、不安な気持ちを倍増させる。
アーメン、という言葉が耳に入ると同時に、私の視界は宙を舞った。
***
中学からの知人の中にも、一人だけ同じ高校に進学した子がいた。保健室のベッドで眠る私に、その子は、珍しいねと言った。
「珍しいね、結子ちゃんが貧血なんて」
くすりと微笑む。可愛らしい笑い方をする女の子だ。中学時代、彼女の纏う柔らかな空気が苦手だった。体育祭で怪我をしたとき、保健委員だった彼女に冷たくあたってしまったのを思い出す。苦手、という気持ちは、嫌いという気持ちより辛い。胸の中にもやもやとしたものが滞留する。それは、後から思い返すと後悔ばかり生み出す嫌な靄だ。
「そうかしら?」
そう? という私に、その子は再び微笑みかけた。
「うん、珍しいよ。結子ちゃんって、強そうというか……なんていうか、ちょっと気丈なところがあったっていうか……男子ともよく言い合っていたし……あ、別に悪い意味じゃないよ?」
顔をしかめた私の機嫌を取るように、本当だよ、悪い意味じゃないよ、と繰り返す。
「あら、そんな風にみられていたのですね」
たしかにそうね、と微笑みながら言うと、その子は安心したように笑みを取り戻した。
その柔らかな笑顔に癒されながら、この子は苦労するのだろうな、と心の隅で思う。だって、私が顔をしかめたのは、別段彼女に敵意を感じたからではないからだ。
ただ単に、その柔らかな雰囲気を苦手だと感じなかったことを、不思議に思っただけだ。
***
入学式の次の日になると、クラスの女の子たちの中では、私は病弱な子であるという認識が当たり前になっていた。入学式で突然倒れたあげく、その後のホームルームにも顔を出さなかったのだから、それも仕方ないことだろう。大丈夫だった? と、心配したクラスメートたちにこぞって声をかけられる、という初めての体験に多少辟易したが、悪い気はしない。気遣ってもらえるのは、なんだかくすぐったかった。
「入学の次の日から授業だなんて、憂鬱だよね。しかも、今日土曜じゃん?」と話しかけてきたのは、隣の席の松中さんだ。松中さんは、そばかすと広いおでこがよいアクセントになった、たれ目の女の子だ。松中さんは不真面目なのか、授業の最中だろうが、構わずに話をはじめる。私もあまり真面目な方ではないので、その話に付き合った。
けれど、環境というものは不思議なもので、女子高の空気にあてられたのか、私の中には妙にきまりの悪い気持ちがわきあがっていた。だから、松中さんの話もだんだんと上の空になっていったのだ。
そのせいで、松中さんは休み時間に再び話を繰り返すことになった。申し訳ない気持ちで胸がいっぱいになる。
「というか、結子知らなかったんだ、この話。もうクラス中この話で持ち切りなのに」
松中さんが私に聞かせたのは、ありがちな学校の怪談というやつだ。噂が大好きな女の子ばかりの女子高では、やはりこの手の話の広まる速度ははやいのだな、と確認する。
「まぁ、未咲茅さんは昨日いなかったもの。仕方がないわ」
丁寧に言うのは、前の席の内海さん。松中さんと内海さん、そして内海さんのとなりの席の沙紀さん(苗字で呼んだら嫌がられた)、そして私の計四人での会話が自然に成り立ちつつあった。昨日の早退を指摘されて苦笑いする私に、沙紀さんが問いかける。
「結子ちゃんはさ、信じる方? こういう噂」
「ええと、どうでしょう……?」
信じるも何も、と言って、思わず鼻で笑ってしまう。そのせいか、沙紀さんは微妙な表情をした。どうやら、彼女はこういった噂に敏感なタイプらしい。しかし、冷静に考えてありえないだろう。
「というか、冷静に考えてありえないっしょ。図書館の隠し部屋って、それベタすぎじゃん?」
私の気持ちを代弁するように、松中さんは言う。私もその通りだと思う。
「そんなことないって! 隠し部屋がないにしても、なんか噂の原因になるものがあるはずよ! 結子ちゃんもそう思わない?」
「ええ……まぁ」
そうかもね、とおざなりな返答をかえす私に、沙紀さんは詰め寄る。
「だよねだよね! 結子ちゃんは話がわかる子だねぇ!」
「ちょ、結子困ってるじゃん? 沙紀無理やりすぎ」
「未咲茅さん、大丈夫ですか?」
内海さんは気遣ってくれる。昨日倒れたことが原因か、彼女は私のことを気遣ってくれるのだ。
「ええ、大丈夫」
しかし、元々気遣われるような所は何もないのだ。なぜだか罪悪感にかられながら、私はだまったまま頷いておいた。その仕草に満足したのか、内海さんはふんわりと慎ましい笑顔をつくる。
「なにお二人さんいい雰囲気になってるのよ。もしもーし」
「似た者同士だし、気が合うんじゃん?」
「似たもの同士……?」
私と内海さんが? ふんわりした内海さんのもつ雰囲気とは、到底似ても似つかないと思うのだけれど。
「うん。なんていうか、ぽわぽわ、というか……なんていうのか……。つか、結子昨日と髪型違うよね。綺麗な髪だなぁって思ったから、覚えてるんだけど」
ああ、これね、と言って、私は肩から胸にたらした髪を一房つまむ。今朝、いつものように髪を結いあげようとしたのだが、なんとなく気がすすまなくて、今日はおろしたままで来たのだ。
「へー後ろでしばってたんだー。でも結子ちゃん、こっちの方が絶対似合うよ。寡黙な少女っていうか……し、深窓の令嬢?」
沙紀さんの珍発言に、納得してうなずく面々。私の、腰まで届く自慢の長い黒髪は、あらぬイメージを彼女たちに抱かせているらしい。
***
もしかしたら、世間的に見たらこれは、至極自然な流れなのかもしれない。
「いや、ありえないっしょ、流石に」
よかった。同じ考え方の人もいた。
「ありえなくないって。わからないんなら確かめにいく! それが当然でしょ」
話をしたその日の内に実行にうつすあたり、沙紀さんは行動力があるのかもしれない。
休み時間の怪談話は、結局四人で確認にいくという方向でまとまり――というよりも、沙紀さんが無理やりまとめ――こうして授業が終わった今、実際に図書館へと向かっているのだ。
「つかあれ、まともな文脈で考えたら、ネタ提案なんですけど」
「ネタなもんですか! いくったらいくのー!」
前の二人が賑やかに騒ぐのを後ろから見守りながら、内海さんと顔を見合わせた。
「少し、わくわくしますわね」
「ええ、そうですね」
ぽわぽわ、と言う内海さんに、私は言葉を返さず、苦笑だけかえす。わくわくしていた気持ちがなかったわけではない。けれども、私の胸の内に去来したのは、漠然とした不安感だった。
図書館は、驚くほど広かった。蔵書の量も、質も、中学の図書館と比べるまでもない。一階をみるだけでそう思うのに、これが三階まであるというのだから驚きの広さである。もちろん、広さだけではない。確かに、隠し部屋があるかもしれない、という気持ちを抱かせる妙な雰囲気が垂れこめていた。
「で。探すってどうするわけ?」
「これだけ広いんだから、手分けして怪しい部分をチェックしよう!」
沙紀さんの提案に、皆が賛同して、それぞれ別々に探すことになった。内海さんがしきりに私のことを心配してくれたが、心配には及ばない。昨日倒れたのは偶然だし、病弱な体質で確定されても困るので、心配しないように伝えた。
隠し部屋、などと言われても、ピンとこないのが正直なところだ。休み時間に聞いた話によると、それは至極ありがちで、陳腐な話に聞こえた。昔のこと、図書館に居座っていた女の子が、本が好きなあまり、誰にも邪魔されぬよう図書館にあった部屋に鍵をかけ、ひきこもった。その少女はその部屋で本を読み続けたが、次第にその部屋は人様から忘れられて行った。年月がたち、その女の子は亡霊になった今も、その部屋で本を読んでいるのだ、という怪談。怪談ではあるが、大して怖いものではないのが、こんなにもはやくこの話が広まった原因かもしれない。
三階の担当になった私は、エレベーターに乗る。図書館棟にわざわざエレベーターがついている時点で、その大きさがうかがえようというものだ。エレベーターのボタンを押すと、待ちかまえていたかのように、ぐあーと嫌な音をたててドアが開いた。中に入り、「3」と書かれたボタンを押す。エレベーターは、ゆっくりと登り始めた。
***
そろそろ集合、という沙紀からのメールがケータイに届いたのを確認し、私は抱えていた本を一冊ずつ戻した。隠し部屋というくらいなのだから、本棚か何かで隠されているのではないかと思い、壁際の本棚の本を抜いて、本棚の向こう側を確認したのだが、何一つ怪しいものは見当たらなかった。少し残念だが、当然と言えば当然だ。私は、落胆半分安心半分の気持ちで、エレベーターに乗る。のぼるときと同じ、「ぐあー」という気持ちの悪い音をたてて扉が開く。一階のボタンを押すと、エレベーターはゆっくりと下降を開始した。
あまりにゆっくりとした速度なので、時間感覚が麻痺するような気がした。外側のみえる窓が一切ないことも、一役買っているのかもしれない。密室は苦手だ。息が苦しくなる。肺の中にどす黒いコールタールが満たされていく。ぐぐ、と横隔膜が下から押し上げられるような感覚。それは、腸壁を裏返されるような嘔吐感にかわる。このエレベーターは、どうしてこんなにゆっくりしているのだろうか。はやく降りたくて仕方がないのに。
吐き気が、ゆっくりと頭の中を占拠する。エレベーターの緩慢さに負けぬほどののろまさで、吐き気が食道を撫であげた。胃がでんぐりがえるような感覚に、思わず膝がガクンと曲がり、たまらず床に手をつく。額に汗が浮かんでいるのがわかった。続いて、猛烈な浮遊感に肉体を支配される。私の頭は、何か得体の知れない力に掴まれ、上に上にとひっぱられている。気持ちが悪い。こらえきれない吐き気が、ガンガンと頭蓋に響く。はやくおりたい、という意識でいっぱいになり、私はなんとか顔を上げ、エレベーターの表示をみた。
「……!!」
思わず、はぁああ? と叫ぶ。喉がしまる。叫んだはずなのに、喉がしまって、声が出せない。エレベーターの表示は、1から3までの数字を、まるで気が狂ったようにばらばらに点滅し続けている。浮遊感が急速に増加していく。頭が後ろにひかれるような違和感。ゆっくりとしたエレベーターの速度が、異常にはやく感じられる。地球の中心まで一息に駆け下りていくかのような高速を錯覚する。こんなに早いのに、どうして一階にたどりつかないのか!!
ぎゅうっと、頭蓋の中身を締め付ける窮屈感。その感覚を最後の記憶に、私は意識を手放した。
***
意識が蘇ったとき、視界が蘇らないのがおかしいと思った。それから、そこが真っ暗なのだと気付くのに、数分要した。真っ暗なのだと気付くと、連鎖的に自分が倒れていることも分かる。両手をついて体を起こし、私は周囲を見回した。しばらくは何もみえなかったが、じきに暗闇に順応していき、はじめに目に入ったのは、大量の本だった。一瞬、怪談話の本好きの女の子の話が脳裏をよぎったが、すぐにその妄想はかき消された。整然とした本たち。人の手が入っているのは明白だ。閉架というやつだろう。このくらい規模の大きな図書館だと、そういうものがあってもおかしくはない。隠し部屋の噂の元凶は、おそらくここなのだ。隠し部屋、正体見たり、閉架図書。エレベーターの扉にBと書いてあるのを確認し、ここが地下であることがわかる。さっさと上に戻って、沙紀たちに報告してやろうと思った。沙紀たちには、待たせて悪いことをした――ふと、まだ沙紀たちがいるだろうか、という疑問が浮かぶ。一体、私が気絶していたのはどれくらいの間だったのだろう。ケータイを取り出し、時間を確認する。
――22:19。
***
エレベーターのボタンを押し、絶望に身体が冷えていくのを感じた。エレベーターは、ウンともスンとも動かない。夜中は電源が落ちているのか。それとも、先ほどの誤作動で故障しているのか。どちらにせよ、エレベーターは動かないのだ。実感のわかない言葉が、頭の奥の方から聞こえてくる。
“閉じ込められた”。頭の奥から湧きあがってくるその言葉を、しかし私は振り払う。どこかに、他の出口があるはずだ。暗闇に押しつぶされそうになる心を、なんとか奮い立たせる。
***
恐怖と暗闇の相乗効果ですっかり疲弊した精神をやすめるため、私は壁に寄りかかり、そのまま崩れるように座った。ずいぶん長い間探し回った気がしたが、他の出口は何処にもなかった。明日は日曜日だから休みだが、月曜になればきっと誰かがくるだろう。しかし、それは、逆にいえば月曜まで帰れないということで。両親に心配をかけて申し訳ない気持ちや、二十四時間以上も暗闇と格闘することになる恐怖心や、お風呂に入れないのは嫌だなと思う暢気で諦めに満ちた発想が、頭の中でぐるぐる渦を巻いた。それら全てを、絶望というわかりやすい感情がまとめあげている。
何気なく、ケータイを取り出して、時計を確認する。
23:59。
日付の変わる直前。そういえば、シンデレラは十二時になると魔法がとけるのであったか。この非常時に童話のことが脳裏に浮かぶなどと、私は余程童話が好きなのかもしれない。呆れながら、時計の数字を眺め続ける。アニメーションしながら時刻を表示する時計をみながら、知らず知らずのうちに、五十五、五十六、と、私は心の中で秒数を数えていた。
なんだか、眠くなってきた。五十七。
不安と恐怖ですっかり疲れはててしまったのか。五十八。
ぼんやりとケータイの画面を眺めながら。五十九。
ゆっくりと目を閉じ、
00:00 00 (SUN)。
デジタルの数字が、全てゼロを示す。日曜深夜0時が訪れる。
■■■
――そして、時は訪れた。
視界が失われたかのように思えた。突如として眼球を貫く光。蛍光灯の明かりなどではない、あまりに強い光が、暗闇に慣れた私の眼球を焼き尽くした。
なんとか腕で影をつくり、私は光を発する方向に顔を向ける。光源は思いのほか近い。私の足の先にそれがある。すぐにそれが何かわかったが、しかし、それは決して光を発するものではないはずだ。
ガラスの靴。
ガラスの靴が、そこにあった。片足だけの、羽の生えたガラスの靴だ。シンデレラのことなどを考えていたせいで、幻覚がみえているのかもしれない。
――私はあなたの合わせ鏡。あなたと共にある翼。
幻聴にしては妙に生々しい声が、直接脳に響くように聞こえる。
「さぁ、あなたのねがいを言えですの!」
だから、ガラスの靴が甲高くやかましい声を発したところで、今更驚きなんてしなかった。ただ、どうせなら、ガラスの靴の幻覚がみえるくらいなら、救い出してほしいと思った。
童話の、お姫様のように。
「聞き届けた! その創造(ねがい)、しっかりと見守れですの!」
やかましい言葉とともに、突如室内の照明が戻る。今度は、先ほどのような眩しすぎる光ではない。蛍光灯による明かりだ。突然の異変に、ほっぺたをつねって夢じゃないかと確認する暇もなく、聞き覚えのある「ぐあー」という嫌な音が、明るい室内に響きわたった。
エレベーターの扉がゆっくりと開く。
中から、王子様がおりてきたようにみえた。
その王子様は、ゆっくりと私に向かって歩いてくる。
腰が抜けて、私はその光景をただ見守ることしか出来ない。
王子様は私の元までやってきて、放心している私の手をとった。
息が詰まるような気がした。
「あなたの想像(ねがい)は“オヒメサマ”ですの!」
ガラスの靴の甲高い声など、もはや耳に入らない。
王子様は来ない。
そんなこと、分かっていた。
それでいいと、思っていた。
――けれど、王子様は来た。
王子様は私の手をひいて立ち上がらせると、その場で跪いた。
お迎えにあがりました、姫様、という言葉が、やけに大きく反響した。
――姫・症候群 「第一話 日曜0時のお姫様」
【T2S】ver.0.86 公式wiki>http://www39.atwiki.jp/swt2s/
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: