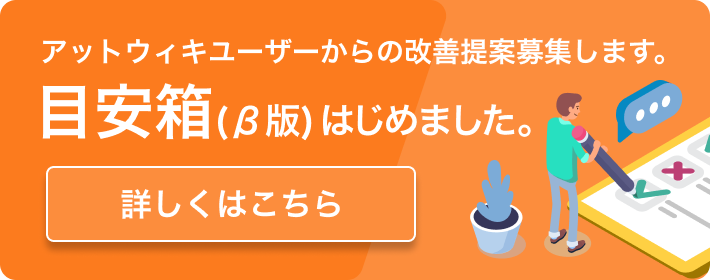王子様は来た。
そんなものは来ないと、来るはずがないと分かっていた私の手をとり、言ったのだ。
お迎えにあがりました、姫様。
それは、童話の中で幾度も繰り返された言葉。
否定しようという気持ちが、当然ないはずがなかった。だが、そんな思考は、もはや胸の高鳴りにかき消されていた。だからその瞬間、私はきっと忘れていたのだ。それがありえないことだってことくらい、とっくの昔に気づいていたはずなのに。
そんなものは来ないと、来るはずがないと分かっていた私の手をとり、言ったのだ。
お迎えにあがりました、姫様。
それは、童話の中で幾度も繰り返された言葉。
否定しようという気持ちが、当然ないはずがなかった。だが、そんな思考は、もはや胸の高鳴りにかき消されていた。だからその瞬間、私はきっと忘れていたのだ。それがありえないことだってことくらい、とっくの昔に気づいていたはずなのに。
***
T2S、という聞き覚えのない言葉が始まりだったように思う。
「簡単に言えば、あなたはT2Sを発症したんですの」
『T2S』というのは、私のような年頃の子どもが患うものらしい。原因は不明。発見された時期も不明だし、当然治療法も見つかっていない、分からないことだらけの病。だが、その症状は分かりやすい。T2Sを発症したものは、『幻覚の中の相棒』が見えるようになる。ぱたぱたと私の周囲を飛び回る、この鬱陶しいガラスの靴のような。
「実害はなさそうですわね。日常生活には」
「日常生活? そんなものはもうありませんですの」
「はぁ?」
「いいですの? あなたは毎週『ゲーム』をクリアしないとダメですの! この『サクヤ』では、それがルールですの!」
「ゲーム? FFとかのことかしら?」
「ゲームと聞いてすぐに家庭用ゲームソフトの名を挙げるとは……しかも国民的RPGを挙げるあたり、中途半端にネクラですのね」
「余計なお世話です! それとサクヤって何かしら? ちゃんと説明してくださらない?」
その言葉に、顔のないはずのガラスの靴が、にやりと笑ったように見えた。
「気になるなら、ついてくるですの」
私をおいて、ぱたぱたよどみなく飛んでいくガラスの靴。私がついてくるとわかっているのだ。
私は感想を改める。日常生活に実害を及ぼすレベルだ、あのウザさは。というか、今ドキ『ですの』はないだろ。
「簡単に言えば、あなたはT2Sを発症したんですの」
『T2S』というのは、私のような年頃の子どもが患うものらしい。原因は不明。発見された時期も不明だし、当然治療法も見つかっていない、分からないことだらけの病。だが、その症状は分かりやすい。T2Sを発症したものは、『幻覚の中の相棒』が見えるようになる。ぱたぱたと私の周囲を飛び回る、この鬱陶しいガラスの靴のような。
「実害はなさそうですわね。日常生活には」
「日常生活? そんなものはもうありませんですの」
「はぁ?」
「いいですの? あなたは毎週『ゲーム』をクリアしないとダメですの! この『サクヤ』では、それがルールですの!」
「ゲーム? FFとかのことかしら?」
「ゲームと聞いてすぐに家庭用ゲームソフトの名を挙げるとは……しかも国民的RPGを挙げるあたり、中途半端にネクラですのね」
「余計なお世話です! それとサクヤって何かしら? ちゃんと説明してくださらない?」
その言葉に、顔のないはずのガラスの靴が、にやりと笑ったように見えた。
「気になるなら、ついてくるですの」
私をおいて、ぱたぱたよどみなく飛んでいくガラスの靴。私がついてくるとわかっているのだ。
私は感想を改める。日常生活に実害を及ぼすレベルだ、あのウザさは。というか、今ドキ『ですの』はないだろ。
***
ついてきた私の周囲を満足げに飛び回りながら、ガラスの靴の解説は続く。
ゲーム、というのは一週間ごとに課される課題のこと。他のT2S発症者も、毎週この課題をこなしている。ちなみに、ゲームをクリア出来ないとどうなるの、とたずねると、大変なことになるですの、とはぐらかされた。
「ゲームには主催者がいるんですの! この町の主催者は学園型のゲームをするようなので……まぁ素人さんのあなたにはうってつけですの」
これからその主催者さんに会いにいくですの、というガラスの靴。そんなわけのわからないものに会うような事態はなるべく避けたいが、見覚えのない場所で迷子になったらたまらない。癪だが、確かにてがかりはこのガラスの靴だけだ。
意識の戻った時、私は既にここにいた。王子様に手を取られた時点で、私の記憶は途絶えている。気が付いたら、ガラスの靴と二人、この場所にいた。王子様は影も形も存在しなかった。まるで最初からいなかったかのように。
もしかしたら、あの光景は夢で、ここは、夢の続きなのかもしれない。
ゲーム、というのは一週間ごとに課される課題のこと。他のT2S発症者も、毎週この課題をこなしている。ちなみに、ゲームをクリア出来ないとどうなるの、とたずねると、大変なことになるですの、とはぐらかされた。
「ゲームには主催者がいるんですの! この町の主催者は学園型のゲームをするようなので……まぁ素人さんのあなたにはうってつけですの」
これからその主催者さんに会いにいくですの、というガラスの靴。そんなわけのわからないものに会うような事態はなるべく避けたいが、見覚えのない場所で迷子になったらたまらない。癪だが、確かにてがかりはこのガラスの靴だけだ。
意識の戻った時、私は既にここにいた。王子様に手を取られた時点で、私の記憶は途絶えている。気が付いたら、ガラスの靴と二人、この場所にいた。王子様は影も形も存在しなかった。まるで最初からいなかったかのように。
もしかしたら、あの光景は夢で、ここは、夢の続きなのかもしれない。
***
ガラスの靴につれていかれたのは、コンサートホールのような場所だった。ステージを取り囲むように、段々に席がつくられたその建築は、初めてみるはずなのに。
「どこか……見覚えのある場所ですね」
「……あなたって、鈍いですの」
何かの催しがあるのか、既に多くの人が集まり、規則性なくばらばらに席に着いていた。ホールには、目に見えない異様な熱気がたちこめている。その妙な熱気を避け、私は一番後ろの席に座った。二日前の入学式が蘇る。あのとき感じた、えもいわれぬ心地の悪さが、かすかにではあるが感じられた。髪をおろしたおかげか、うなじをひかれるような吐き気は催さなかったが、短いスカートへの違和感は復活した。
お尻の位置を何度もなおしたり、膝の上にのせた手の指の先を、のばしたり縮めたりしてしばらくすると、ホールの中央にあるステージに、小さな人影が現れた。
「彼女が主催者ですの」
「ちいさ……」
最初は遠いから小さくみえるだけかと思ったが、そうではない。事実、その少女は小さかった。外見だけで言えば、小学生くらいであろうか。細部までは見て取れないが、明らかにぶかぶかなサクラ色の着物のような衣装が、その小ささをさらに印象づけている。
ぼうっと、少女を眺めていると、八時半になりましたので、全校集会を始めます、というアナウンスが入った。全校集会ということは、ここは学校かなと考えた私の脳裏に、何か引っかかるものがあったが、上手く表現できない。それが何か考える前に、ステージの上の少女が、マイクを通して声をホールに響き渡らせた。
「無事課題をクリアしここに戻りし者よ! 妾はそなたらを祝福する!」
変な口調の一言で、漂い続けていた掴み所のない熱気が実態を伴ってホールに満ちる。湧き上がるような歓声というのを初めて聞いた私は、正直なところ置いてきぼりだ。
「新たにこの『サクヤ』に訪れし者よ! 妾と妾のアドレッセンスは、そなたらを歓迎しようぞ!」
しかし、二言目で私も熱気の海に飲み込まれていた。口調は変だが、他の観客が盛り上がるのも分からないでもない、そういったものをその少女は持っていたのだ。
「まぁ先のゲームは例外的なものだったゆえ、皆ここに揃うておると思うがの。さて……そなたらの中には気付いておる者もおるじゃろ。先の週は塔が顕現しなかったゆえ、臨時で統浪高校を妾の拠点にさせてもらったわけじゃが」
そこで、少女の背後にぶら下げられていた巨大なスクリーンが映像を映し出す。
私は思わず、息をのんだ。膝の上に乗せた手のひらを無意識に握りしめる。
「じゃが! この通り、今週に入り、塔がこの“桜埜女学園”に顕現したのじゃ!」
歓声があがる。
しかし、そのとき私は、再び周囲から取り残されていた。驚愕のあまり、嘘だ、という言葉が喉から先に出てこない。今まで脳裏に封じていた疑問が次々と飛び出した。
見知らぬところにどうして自分はいるのか、と。
いつの間に自分は学校を出たのだろうか、と。
そうして、今となってしまえば、このコンサートホールに感じた妙な既視感の正体はすぐにわかる。わからぬはずがないのだ。
スクリーンの中の学園。中央に見たことのない、異常な高さの塔が聳えているが、しかしその学園は、間違いなく二日前に私が入学した桜埜女学園だ。
そして形は違えど、このコンサートホールの内装は、私が入学式を経験した学園の講堂と同じもの。
「コノハナタワーの顕現に基づき、ここ、桜埜女学園に我が学び舎『アドレッセンス』を降臨する!」
少女の言葉で、学園の姿が変容していく。下から隆起するように、地形が変化していく。
目が覚めたとき見知らぬところにいたのは、私が学校を出たからではない。
変わったのは、学校の方だ。
「これよりこの学園都市『アドレッセンス』を妾の拠点とする!」
中央の塔を取り囲むように、学園はその姿をまったく異なるものへと変えていた。
「どこか……見覚えのある場所ですね」
「……あなたって、鈍いですの」
何かの催しがあるのか、既に多くの人が集まり、規則性なくばらばらに席に着いていた。ホールには、目に見えない異様な熱気がたちこめている。その妙な熱気を避け、私は一番後ろの席に座った。二日前の入学式が蘇る。あのとき感じた、えもいわれぬ心地の悪さが、かすかにではあるが感じられた。髪をおろしたおかげか、うなじをひかれるような吐き気は催さなかったが、短いスカートへの違和感は復活した。
お尻の位置を何度もなおしたり、膝の上にのせた手の指の先を、のばしたり縮めたりしてしばらくすると、ホールの中央にあるステージに、小さな人影が現れた。
「彼女が主催者ですの」
「ちいさ……」
最初は遠いから小さくみえるだけかと思ったが、そうではない。事実、その少女は小さかった。外見だけで言えば、小学生くらいであろうか。細部までは見て取れないが、明らかにぶかぶかなサクラ色の着物のような衣装が、その小ささをさらに印象づけている。
ぼうっと、少女を眺めていると、八時半になりましたので、全校集会を始めます、というアナウンスが入った。全校集会ということは、ここは学校かなと考えた私の脳裏に、何か引っかかるものがあったが、上手く表現できない。それが何か考える前に、ステージの上の少女が、マイクを通して声をホールに響き渡らせた。
「無事課題をクリアしここに戻りし者よ! 妾はそなたらを祝福する!」
変な口調の一言で、漂い続けていた掴み所のない熱気が実態を伴ってホールに満ちる。湧き上がるような歓声というのを初めて聞いた私は、正直なところ置いてきぼりだ。
「新たにこの『サクヤ』に訪れし者よ! 妾と妾のアドレッセンスは、そなたらを歓迎しようぞ!」
しかし、二言目で私も熱気の海に飲み込まれていた。口調は変だが、他の観客が盛り上がるのも分からないでもない、そういったものをその少女は持っていたのだ。
「まぁ先のゲームは例外的なものだったゆえ、皆ここに揃うておると思うがの。さて……そなたらの中には気付いておる者もおるじゃろ。先の週は塔が顕現しなかったゆえ、臨時で統浪高校を妾の拠点にさせてもらったわけじゃが」
そこで、少女の背後にぶら下げられていた巨大なスクリーンが映像を映し出す。
私は思わず、息をのんだ。膝の上に乗せた手のひらを無意識に握りしめる。
「じゃが! この通り、今週に入り、塔がこの“桜埜女学園”に顕現したのじゃ!」
歓声があがる。
しかし、そのとき私は、再び周囲から取り残されていた。驚愕のあまり、嘘だ、という言葉が喉から先に出てこない。今まで脳裏に封じていた疑問が次々と飛び出した。
見知らぬところにどうして自分はいるのか、と。
いつの間に自分は学校を出たのだろうか、と。
そうして、今となってしまえば、このコンサートホールに感じた妙な既視感の正体はすぐにわかる。わからぬはずがないのだ。
スクリーンの中の学園。中央に見たことのない、異常な高さの塔が聳えているが、しかしその学園は、間違いなく二日前に私が入学した桜埜女学園だ。
そして形は違えど、このコンサートホールの内装は、私が入学式を経験した学園の講堂と同じもの。
「コノハナタワーの顕現に基づき、ここ、桜埜女学園に我が学び舎『アドレッセンス』を降臨する!」
少女の言葉で、学園の姿が変容していく。下から隆起するように、地形が変化していく。
目が覚めたとき見知らぬところにいたのは、私が学校を出たからではない。
変わったのは、学校の方だ。
「これよりこの学園都市『アドレッセンス』を妾の拠点とする!」
中央の塔を取り囲むように、学園はその姿をまったく異なるものへと変えていた。
***
これがサクヤですの、という言葉に、私の思考はようやく復旧した。映像を見た衝撃でしばらく呆然としていた私を立たせガラスの靴が連れて行ったのは講堂の外。先ほどの塔の真下だった。
サクヤ。平行差分的仮想現実世界。簡単に言うのなら、違う世界ですの、という信じがたい発言も、あの光景を見せられた今、そして塔を目前にした今となっては、信憑性を疑うことなど出来なかった。
学園の構造は、明らかに変化している。こんなことが起こりうるのなら、たとえここが異世界だろうとそうじゃなかろうと、大差はない。思考の埒外の光景に、私は頭が殴られるような思いがした。
「どうして……私はここに?」
思考がそのまま言葉を成す。質問の答えが欲しかったのか。質問する行為に意味があったのか。どちらの意義が正しいのか、私の理解が追い付かない。唐突な孤独感と喪失感が、全身を巡る。二つの感覚は全身を舐め上げ、筋肉を弛緩させた。立っていることが辛くなり、私は思わず膝をつく。膝にめりこむ小石の尖り。土を握る。ざらりとした手触りは本物だ。
馬鹿げてると思う。ここは現実だ。夢の中のはずがないのに、私は夢である手触りを探している。どうして自分はここにいるのか。放り投げただけのつもりの質問に、ガラスの靴は答える。
「T2Sを発症したからですの」
昨夜の光景が脳裏に浮かぶ。私の前に姿を現した王子様。あの瞬間、私の現実は入れ替わった。
「T2Sとは……何?」
「それは、あなたの願いですの。あなたが心の底に抱えている願いが、力になるですの」
『あなたのねがいはオヒメサマ』。その言葉が無意識に思い出された。昨夜、さして耳にとめなかった言葉。けれど、改めて考えてみると、それはありえないと思う。お姫様の童話は好きだけど、お姫様になりたいと思ってはいない。普通であることが私を安心させる。王子様は来ないもんだってわかっていたし、それでいいとも思っていた。
けれど、王子様は来たのだ。
来て、しまったのだ。
――ありえない。
「こんな世界……嘘ですわ」
ぽつりと呟いてみた言葉が、私の中に詰まった感情を破裂させる。
そもそもでたらめじゃないか。 こんな大きな塔がどうして何もないところから生えてくるのだろう。学園の形が変わってしまうなんて、そもそもそれ自体がおかしいのだ。ここが夢ではなかろうと、この世界はでたらめだ。
「嘘じゃないんだよね、残念だけどさ」
視界に細い足が踏み行ってくる。顔を上げると、その先には見知った顔があった。
「部長……」
中学時代、演劇部で世話になった部長は、久しぶり、と呑気に手を振る。
サクヤ。平行差分的仮想現実世界。簡単に言うのなら、違う世界ですの、という信じがたい発言も、あの光景を見せられた今、そして塔を目前にした今となっては、信憑性を疑うことなど出来なかった。
学園の構造は、明らかに変化している。こんなことが起こりうるのなら、たとえここが異世界だろうとそうじゃなかろうと、大差はない。思考の埒外の光景に、私は頭が殴られるような思いがした。
「どうして……私はここに?」
思考がそのまま言葉を成す。質問の答えが欲しかったのか。質問する行為に意味があったのか。どちらの意義が正しいのか、私の理解が追い付かない。唐突な孤独感と喪失感が、全身を巡る。二つの感覚は全身を舐め上げ、筋肉を弛緩させた。立っていることが辛くなり、私は思わず膝をつく。膝にめりこむ小石の尖り。土を握る。ざらりとした手触りは本物だ。
馬鹿げてると思う。ここは現実だ。夢の中のはずがないのに、私は夢である手触りを探している。どうして自分はここにいるのか。放り投げただけのつもりの質問に、ガラスの靴は答える。
「T2Sを発症したからですの」
昨夜の光景が脳裏に浮かぶ。私の前に姿を現した王子様。あの瞬間、私の現実は入れ替わった。
「T2Sとは……何?」
「それは、あなたの願いですの。あなたが心の底に抱えている願いが、力になるですの」
『あなたのねがいはオヒメサマ』。その言葉が無意識に思い出された。昨夜、さして耳にとめなかった言葉。けれど、改めて考えてみると、それはありえないと思う。お姫様の童話は好きだけど、お姫様になりたいと思ってはいない。普通であることが私を安心させる。王子様は来ないもんだってわかっていたし、それでいいとも思っていた。
けれど、王子様は来たのだ。
来て、しまったのだ。
――ありえない。
「こんな世界……嘘ですわ」
ぽつりと呟いてみた言葉が、私の中に詰まった感情を破裂させる。
そもそもでたらめじゃないか。 こんな大きな塔がどうして何もないところから生えてくるのだろう。学園の形が変わってしまうなんて、そもそもそれ自体がおかしいのだ。ここが夢ではなかろうと、この世界はでたらめだ。
「嘘じゃないんだよね、残念だけどさ」
視界に細い足が踏み行ってくる。顔を上げると、その先には見知った顔があった。
「部長……」
中学時代、演劇部で世話になった部長は、久しぶり、と呑気に手を振る。
***
正直、混乱していたように思う。私より一年先に中学を卒業し、桜埜に入学した部長と出会うのは、あまりにも久しぶりだったから。たまたま私の姿を見かけ、懐かしくて話しかけてしまったのだと部長は説明した。
「嘘じゃないって、どういうことですか?」
「だから、この世界『サクヤ』は本物で、あんたがここにいるのが嘘みたいなホントってわけ」
「そんなわけないです。私、別にお姫様とか憧れていませんし。それに、お姫様なんて、ありえない」
「演劇部のヒロイン常連が何をおっしゃるやら。結子がどう考えるかは自由だけどさ。私にはその言葉の方が嘘に感じるわ。だいたいね、お姫様っていうのは、別に童話に出てくるようなものばかりじゃないのよ? 意味合い的には、選ばれた女の子ってところかしら」
「べ、別に、選ばれたいなんて思ってないですから!」
それは本当のことのはずだ。普通であればいいと思っていた。だから、何かに選ばれたいなんて、そんなこと一度も思ったことがない。他人と自分とに大した差異はないのだ。だから、何かに選ばれたいなんて、そんな高慢な願望は持ったことがない。普通であることが私を一番安心させるのだから。
「じゃあさ」
部長は言う。
「なんで舞台の上の結子は、あんなにきらきらしてたの?」
その言葉は、私を守る鎧を貫くように鋭い。
「嘘じゃないって、どういうことですか?」
「だから、この世界『サクヤ』は本物で、あんたがここにいるのが嘘みたいなホントってわけ」
「そんなわけないです。私、別にお姫様とか憧れていませんし。それに、お姫様なんて、ありえない」
「演劇部のヒロイン常連が何をおっしゃるやら。結子がどう考えるかは自由だけどさ。私にはその言葉の方が嘘に感じるわ。だいたいね、お姫様っていうのは、別に童話に出てくるようなものばかりじゃないのよ? 意味合い的には、選ばれた女の子ってところかしら」
「べ、別に、選ばれたいなんて思ってないですから!」
それは本当のことのはずだ。普通であればいいと思っていた。だから、何かに選ばれたいなんて、そんなこと一度も思ったことがない。他人と自分とに大した差異はないのだ。だから、何かに選ばれたいなんて、そんな高慢な願望は持ったことがない。普通であることが私を一番安心させるのだから。
「じゃあさ」
部長は言う。
「なんで舞台の上の結子は、あんなにきらきらしてたの?」
その言葉は、私を守る鎧を貫くように鋭い。
*
お姫様になりたいと思ってなんかいない。むしろ、お姫様になんかなりたくない、とすら思っていた。
しかし、部長の言葉は私の思考を容易に抉る。それはなぜだろう。
そんな疑問の答えは、心底簡単だということに、私はもう気付いている。それを認める準備が私にないだけだ。
「結子……受け止めなさい。貴女がここにいる。これ以上の証拠はないの」
「こんなの……嘘です」
呟く言葉に反して、頭の中は既にその言葉を受け止める準備に入っていたように思う。だが、最後の最後の部分で、私の意識は踏みとどまる。
「結子……受け入れるですの」
それを決壊させたのは、ガラスの靴の声だ。ひどくウザいはずの声は、このときだけは何処か癒されるような色で。辛そうな響きを湛えている。その声は、私の声に似ていて。どうしてか、心が揺れる。
脳裏に浮かぶのは、昨夜の記憶。王子様に手を取られた瞬間、私は全ての思考を閉ざした。どんな言い訳をしようと、あのとき自分は興奮していたのだ。童話の中のお姫様になったみたいで、私の精神は昂揚していた。舞台の上に立った時と、同じ興奮。
「……わかっていますわ」
わかっていたのだ。自分が、そんな安っぽく高慢な願望を持っているなんて思いたくなかったから、知らないフリをしていただけだ。本当はわかっていたのだ。
最初から、私はお姫様にあこがれていた。普通が一番と取り繕っていたけれど、そんなのは嘘だ。心の奥底では、自分だけが選ばれると信じてやまなかった。お姫様には自分こそが相応しいのだと。
女子校を選んだのだって、自分の中に眠るもう一人の自分がいると思ったからだ。その自分がお姫様なのだと信じ込んでいた。始業式の日、自分の中身が変わったように思えた。しかしそれは、お姫様になりたいという願望の現れに過ぎない。変わったのではなく、自分で意識して変えた。その意識に気がつかないフリをして。
「大丈夫よ、知ってたから」
口調が元に戻っていくのを感じる。
やはり私にお譲様言葉は似合わない。吹っ切れた気分になって顔を上げると、部長はいつの間にか姿を消していた。
まるで、はじめからいなかったかのように。夢のように。そういえば、部長はなぜ私の願望を知っていたのだろうという疑問が一瞬浮かび上がり消えていく。そんなことは、至極どうでもいいことに思えた。
「結子……」
長い髪が鬱陶しい。お姫様みたいな結子は、やはり無理だ。お姫様になりたいと思っているだけの、お姫様らしくない結子でいい。それだけの拙く、みっともない一人にすぎない。
まだ、自分のみっともなさを受け止めるのは難しいけれど、それでも、この願いだけは受け止めよう。とりあえず、みっともない願望を認められない私とはお別れだ。大丈夫、この『決意の剣』なら、それが出来る。
右手に確かな手ごたえを感じる。重い。なによりも重いひと振りのナイフ。
私は、それを軽々と持ち上げた。重くて扱いづらいはずなのに、私は少しも過たぬと自信があった。
しかし、部長の言葉は私の思考を容易に抉る。それはなぜだろう。
そんな疑問の答えは、心底簡単だということに、私はもう気付いている。それを認める準備が私にないだけだ。
「結子……受け止めなさい。貴女がここにいる。これ以上の証拠はないの」
「こんなの……嘘です」
呟く言葉に反して、頭の中は既にその言葉を受け止める準備に入っていたように思う。だが、最後の最後の部分で、私の意識は踏みとどまる。
「結子……受け入れるですの」
それを決壊させたのは、ガラスの靴の声だ。ひどくウザいはずの声は、このときだけは何処か癒されるような色で。辛そうな響きを湛えている。その声は、私の声に似ていて。どうしてか、心が揺れる。
脳裏に浮かぶのは、昨夜の記憶。王子様に手を取られた瞬間、私は全ての思考を閉ざした。どんな言い訳をしようと、あのとき自分は興奮していたのだ。童話の中のお姫様になったみたいで、私の精神は昂揚していた。舞台の上に立った時と、同じ興奮。
「……わかっていますわ」
わかっていたのだ。自分が、そんな安っぽく高慢な願望を持っているなんて思いたくなかったから、知らないフリをしていただけだ。本当はわかっていたのだ。
最初から、私はお姫様にあこがれていた。普通が一番と取り繕っていたけれど、そんなのは嘘だ。心の奥底では、自分だけが選ばれると信じてやまなかった。お姫様には自分こそが相応しいのだと。
女子校を選んだのだって、自分の中に眠るもう一人の自分がいると思ったからだ。その自分がお姫様なのだと信じ込んでいた。始業式の日、自分の中身が変わったように思えた。しかしそれは、お姫様になりたいという願望の現れに過ぎない。変わったのではなく、自分で意識して変えた。その意識に気がつかないフリをして。
「大丈夫よ、知ってたから」
口調が元に戻っていくのを感じる。
やはり私にお譲様言葉は似合わない。吹っ切れた気分になって顔を上げると、部長はいつの間にか姿を消していた。
まるで、はじめからいなかったかのように。夢のように。そういえば、部長はなぜ私の願望を知っていたのだろうという疑問が一瞬浮かび上がり消えていく。そんなことは、至極どうでもいいことに思えた。
「結子……」
長い髪が鬱陶しい。お姫様みたいな結子は、やはり無理だ。お姫様になりたいと思っているだけの、お姫様らしくない結子でいい。それだけの拙く、みっともない一人にすぎない。
まだ、自分のみっともなさを受け止めるのは難しいけれど、それでも、この願いだけは受け止めよう。とりあえず、みっともない願望を認められない私とはお別れだ。大丈夫、この『決意の剣』なら、それが出来る。
右手に確かな手ごたえを感じる。重い。なによりも重いひと振りのナイフ。
私は、それを軽々と持ち上げた。重くて扱いづらいはずなのに、私は少しも過たぬと自信があった。
ザクっと音がして、長い髪が風に流されていった。
――姫・症候群 「第二話 決意の剣」
【T2S】ver.0.93 公式wiki>http://www39.atwiki.jp/swt2s/
【T2S】ver.0.93 公式wiki>http://www39.atwiki.jp/swt2s/