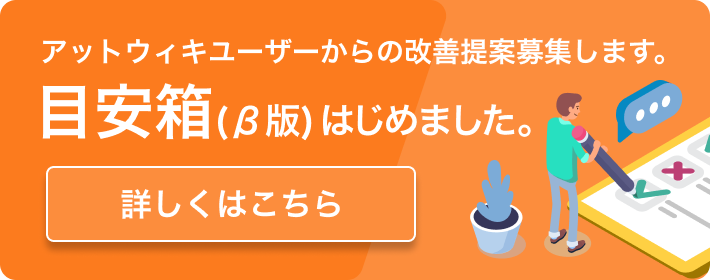「追憶」(2008/09/18 (木) 01:13:21) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
「俺は、今もそうだけど、リーバードだった時もディグアウターになるのが夢だったんだ」
「ええ!?」
たちまち隣で上がる驚愕の声に、俺は苦笑してみせた。
「変なヤツだろ。本を読むのが好きで、
司政官でもないのにデコイたちの生活をのぞきたがって、
あげくの果てにディグアウターになりたいと思った。・・・我ながら相当に変だ」
目を丸くしたまま、ロックが頷いた。その驚きはわかる。
常識で測れば、そんなリーバードなんかありえないもんな。同族狩りもいいところだ。
でも、知性を持つヘブンの人間たちはリーバードを動物のように考えていたから、そこまで背徳的な考えだったわけでもない。
コントロールルーム内部は、大きな卵形をしていた。
その卵の大きさは、エンテ…かつての俺が、
たとえ尻尾の先で伸び上がったところで天井にはるか届かなかったし、
5倍の長さがあったところで端から端まで体を渡すことはできなかっただろう。
常に自然光に近い柔らかな波長の光に満ちて、地表に雨が降るときには、その光も薄くなった。
天井には幾何学的な網目模様が走っている。
…何の意味があり、誰の趣味だったかは、知るよしもないけど。
巨大なメインコンピューターは壁に埋め込まれていて、望めば壁面全てがモニターになる仕組みだった。
アリアは外に出られない俺を気遣って、春には花を、夏には夜空を、秋には枯れ色の野を、冬には雪と鉛色の空を映してくれた。
詩的で、繊細な彼女らしい配慮だったと今も思う。
そんな彼女のもとにいたからそうなったのか、もともとそういう性分だったのか
…運命なんていう手軽な言い訳は嫌いだけど、俺はデコイ達の芸術・文学
・…ことに、晩年ディグアウターについての文学にいたくのめり込んでしまっていた。
ヘヴンの技術である記憶素子に記憶させれば、本なんていう下位のメディアは必要ないというのに、
俺は古びた革表紙や、脆い紙表紙、布張りのもの…そういった本のほうを好んで、
コントロールルームの床に広げては、本来敵を串刺しにしたり斬ったりするはずの攻撃突起を鼻先から鋭く細く伸ばし、
ページを軽く突いてめくって読んでは楽しんでいた。
そう。『読んで』いたんだ。リーバードだった俺には直接メモリーにダウンロードするって方法もあったのに。
『あなたは、変わったリーバードね』
記憶の中に、鈴を振るような声が蘇る。アリアの苦笑混じりの言葉と、
細く整った眉をよせて、小さく首を振る動作が見えるようだ。
彼女はいつも、正面コントロールパネルの前に白い籐の椅子を置いて、そこに座っていた。
空色の髪、ミルクティー色の肌、ふと微笑む華やかな気配。まるで夏色の花束のように。
『そりゃあそうです。なにしろ、俺はディグアウターになるのが夢なんだから!』
快活に言い切った、巨大なリーバード。
さらに微笑む、柳の枝のようにほっそりと美しい司政官。
「待ってよ、グランド!」
俺もロックも足を止める。
ロックが俺の左肘を掴んだ。振り向くと、真剣な緑の瞳と目があった。
「夢を持っていた? エンテが?」
…気付いた。やっぱり…な。
俺は小さく苦笑した。ロックはなおも続けて言う。
「エンテはここのボスリーバードなんだよね?
…変だ。グランドの話じゃ、エンテにはもとから人格があったみたいじゃないか!」
ロックは両手を広げ、わからないよ!?とでもいいたげなジェスチャーをした。
そして一息間をあけ、ごくりと喉を上下させゆっくりと言った。
「グランド、リーバードは人格を持たないし、話さない。夢も見ようが無いはずだよ・・・」
そうだ、普通リーバードに人格は無い。たとえそれが一つの施設を護るボスリーバードであっても。
…でも、それじゃあアリアの身体に乗り変わることなんか、最初から無理だという事になってしまう。
「ロック、『マザー・ガーディアン』という名に覚えは?」
ハッとロックの顔色が変わった。
マザーガーディアン。それは、システム最上位者であるマザーを守護する最高のリーバード。
下位の機械と融合し支配し操る力さえ持つという。そして、時には人の形となりマザーを補佐する。
そのリーバードが持つのは絶対の忠誠心。
たとえ世界の全てがマザーと対立したとしてもそれだけは決してマザーを裏切らない。
岩のごとき究極の忠誠を目指して作られたらしい。
そう。つまり、『マザーガーディアン』とは唯一の、人格持つリーバード。
「エンテも、実験体だったんだ。マザーガーディアンに搭載するAIの。…ただし、失敗作」
「なんだって!? …エンテまで!?」
俺はうなずいて、再び歩き出した。もう黄色い扉は目の前にある。
つんのめるような足音がして、少し遅れてロックがついてきた。
「いつかこの遺跡を改修する工事があって、その時に俺は外へ出られると聞かされてた。
そのときこそ試験期間の終わりで、俺はマザーを護るという、
本来の役目につくんだって信じていた。他ならぬヘヴンのお達しだったし。
…それが、 『お前は失敗作だから、マザー・ガーディアンとして使えない。
そのままこの施設に残り、仕事を続けろ』ときたもんだ」
俺は扉の前に立ち止まった。
あの時の、怒りとも悲しみとも知れない気持ちが胸の奥で暴れている。
動力部からあらゆるエネルギーが抜け落ちてしまったような脱力感。
ああ、あれが絶望ってやつを実感した初めてだった。
「夢見るリーバードは、マザーガーディアンとして失格なんだってさ」
「・・・・・・」
隣で聞いていたロックは、瞬間俺の横顔を見上げ、悲しそうにうつむいた。
粛清官として天上で働いていたロックには、なにか感じるところがあったのかもしれない。
俺は『雨の弓』を肩から外して右手だけで持つ。ひやりと冷たくて、握りなれた感触。
狩りのもうひとりの相棒だ。そして実は、これこそがこの扉を開ける正式な鍵。
鍵はリセットされた俺とともに、常に地上にあった。
だから、ロックがどんなに探し回ってもこの遺跡から鍵が見つかることはなかったんだ。
「自分が実験体だったとわかった、
そのときになってやっと…俺は思い至った。この島で作られては殺されるデコイたちは、どうなんだろうと」
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: