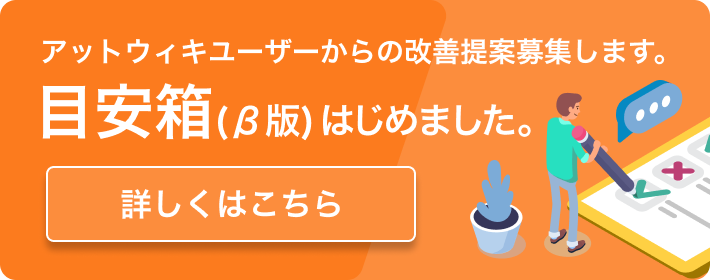頭の中でざっとそこまで考えると、どうしようもなく懐かしかった。
もう戻ることは無い過去であるだけに、よけいにどこか切ない気分がする。
俺にはもう、グランド・リヒトエアとして以外の生き方をする気は全く無い。
「…知ってるだろうけど、この島は実は強力なバリアで隔離されてる。
ここがヘヴンの地上における実験島だったからだ」
ロックがうなずいた。
外からきた彼らは、そのバリアを越えて来たわけだから知らないはずはないもんな。
「外からこの島を見たとき、そこには海しか無いように見えるはずだ。
しかも、ある程度バリアに近づくと、自然とバリアを避けてしまいたくなるような強力な暗示も出ている。
普通の技術力じゃ、まず発見できないしバリアを通過することも出来ない」
無線機が鳴って、得意げな声が聞えた。
『わたしが見つけたの!』
「うん、ロールちゃんの作った新しいレーダーで、偶然この島が写ったんだ。
データが『ヘヴンの施設だ』って叫ぶし、
ロールちゃんは『これだけのバリアだもん、凄いディフレクターあるかも!』って言うしで、
着陸することになったんだけど」
照れたように苦笑いするロック。戦っている時の鋭さとはまるで雰囲気が違う。
そういう表情は、ほとんど普通の少年って感じだった。
「バリアは…ヘヴンの者たちに対しては簡単に開く。すんなり入れただろ?」
「拍子抜けするくらいね」
それで、ディグアウターであるロックたちはまっすぐ遺跡へ向かったわけだ。
一方、粛清官ロックマンの来島を察知した島はすぐさま起動状態に入った。
いつもはワンフロア―しか無いように見せかけていた施設は本性を現し、
島の外縁ではリ―バード・トラップが起動した。
俺とディーアが弓漁に出たとき危うく死にかけたのは、そのせいだ。
それはロックマンの来島でほんの一瞬開くバリアの隙間から島民が出るのを防ぐため。
…あきれるほどの閉鎖ぶり。あらためて嫌になるね。
俺は溜め息をついて、頭を振った。アリアが離反した理由。俺がここにこうしているわけ。
そして、いままで記憶を失っていたわけ。全てのわけはそれにある。
「…結論を言うとな、俺の正体はあれだ。…あの蛇。ガードリーバード・エンテ」
「えっ!? …えええっ!???」
ロックが口を全開にして驚く。そればっかりは予想してなかったらしい。
そりゃそうだ。ヘヴンや粛清官、それにマザーをもあざむくための、俺とアリアの計略だったんだから。
「でも、きみがあのリーバードのわけないよ!! だってさっきいたじゃないか!!」
「あれは抜け殻みたいなもんで、
あれには遺跡とロックマンアリアを守るっていう本能しか残ってない。
…今の俺は、アリアがリセットした体にガードリーバード・エンテの人格を乗せたもの
…になるのかな」
それを聞いて、今度こそロックは声も出ないようだった。
息を飲んだっきり沈黙している。無線機も何の音もしない。
いや、今何かをがらがらと崩したような音がした。ロールも驚いているみたいだった。
「リセットした身体に入ったのが俺っていう男性人格だったからか、
アリアがなにかしたからなのかわからないけど、性別はこの通りだよ」
もと自分だったものがディーアを殺したのかと思うと、また悔しさがこみ上げる。
もう一人の自分が、あるいは自分そっくりのやつが親友を殺したと考えてみなよ?
それは他人がそうしたというより、…何倍も辛いもんなんだ。
俺は奥歯をくいしばって感情を噛み殺した。今すべきなのは、ロックに協力を得ること。自分のことだからわかるんだ。
今の俺じゃあ、あの、リーバードの俺は倒せない。
「ロック、協力して欲しい。あのリーバード・エンテは俺だけじゃ倒せないんだ」
「…? 君は司政官モデルのロックマンなんだよね?
…あ、いや、その中身は違うのかもしれないけど、自分の守護リーバードに勝てないの?」
俺はうなずいた。皮肉っぽく笑って。
司政官。文字通りその島の管理が仕事で、戦いには向いていない。
でも、向いていないと言ってもそれはヘヴンの戦闘型の者たちと比べての話だ。
地上では、そこらの一般人には及びもつかない身体能力を誇る。
それでも、アリアはエンテには勝てないんだ。
「もしアリアがイレギュラー化して、この実験島を開放しようとしたり
ヘヴンにとってまずい行動をとり始めたとき、
いちいちヘヴンから人を派遣していたのでは遅すぎる。
その場合は、そばにいるエンテがアリアを強制停止させる役目を負う。
…アリアは、エンテには絶対に勝てないようにできてるんだよ」
そんな、と言ってロックは顔を苦しそうに歪めた。握りしめた片手が震えている。
もしかして、ロックもヘヴンでやりきれない、辛い思いをしたんだろうか。
「じゃあ、そのエンテがイレギュラー化してしまったときはどうするつもりだったんだろう?
アリアが止められないんじゃあ…」
俺は静かに首を横に振った。
ヘヴンの、この島を隔離するやり方はいやになるほど徹底していたんだ。
「あのエンテの巨体を見たろ? 昔、俺は一度だってこの施設からでられなかった。
この施設はエンテの上に作られた。
もしイレギュラー化しても、地上部分に行けないから影響はないんだとさ。
…エンテがイレギュラー化した場合、即座にヘヴンに連絡がいく。
エンテを倒せるのは、アリア以外のロックマンが、定められた手順でエンテに攻撃を加えた時だけ」
言いながら、俺はもう一度背後の壁画を指した。
「…アリアはその、エンテの倒し方をここに残した。
もしヘヴンからロックマンが派遣されてきたなら、必ず遺跡に降りる。
俺はそれを知ったらそれを追って遺跡に入るように自分に暗示をかけていた。
そして、『ロックマン』という名乗りを聞いた瞬間に記憶が蘇るようにもしておいた。
…あの、昔の俺を倒すためにはヘヴンの、しかも『ロックマン』クラスの協力がいる」
壁画のアリアの絵のすぐ下の文章を、指でなぞる。
『赤は紅蓮。逆巻く炎・
橙は広がりゆく熱。四散し猛る強き爆炎・
黄は灼熱。細く鋭く貫く穿光・
緑は波動。全てを切り裂く力の刃・
青は光。扉の鍵なる雨色の閃光・
藍は力。彼の放つ無類の技なり・
菫は粛清。天からの使者なる証をたてよ
七つの色にて彼を倒せ。虹への道は遠からじ』
読み終わって、俺はちょっとあっけにとられた。
…これって、詩だよ。
まったく、アリアも凝ったことを考えたもんだ。慎重なんだか、馬鹿なんだか。
でも、アリアはそういう奴だった。
デコイたちの詩や音楽を集めては喜んで、自分でも作っては才能の無さに落ち込んだりして。
妙にロマンチストなとこがあったもんな。俺は思わずその様子を思い出して少し笑ってしまった。
「わざわざわかりにくく詩にすることもないのにな。
つまり、上から順番に炎・爆発・ビーム・エネルギーブレード・
俺の持ってる雨の弓…この弓での攻撃・あとあいつは藍色の火を吐くんだけど、
それをそのままはね返しての攻撃、そのあとに力で強引に倒せって意味だよ。
特に最後のとこがわかりにくいな。
『ロックマン』の攻撃じゃなきゃとどめがさせないって書けばいいのに」
ロックは興味深そうにじっくりその詩を眺めて、なんだか嬉しそうに笑った。
「司政官ロックマンにもこういう面白い人がいたんだ。…会ってみたかったな」
「…他の司政官と会ったことが?」
ロックは答えずに、ちらりと悲しそうな苦しそうな笑みを見せた。
「…いや。それより、ちょっと聞きたいんだけどさここ…」
『ここに虹色のディフレクターってある!?』
ロールのやけに喜々とした声がロックの言葉をさえぎった。
…やれやれ。なんて前向き思考。女ってみんなこんなにタフなのかね?
実際、本当は少しうらやましいものを感じるんだけどさ。
ロックの顔をうかがうと、彼はそんな感じ。というふうに肩をすくめて見せた。
アリアはどうだったかな。いつも壊れそうに繊細な印象があったんだけど…。
本当のところは結構強い奴だったのかもしれない。
…う~ん。もう、確かめようはないんだけどな。
「虹色の、ディフレクターね。確かにあるよ」
とたんに、無線が高周波みたいな音をたてた。
…どうやらロールの歓声だったみたいだけど、俺は耳がしばらくおかしくなってしまった。
「ご、ゴメン! …やっぱあのリーバードを倒さなきゃ行けないとこにある…んだよね?」
なぜかロールじゃなくてロックがあやまりながら無線のボリュームを落とした。
「島をすっぽり覆うだけのバリアも張らなきゃいけないし、島民の管理もしている。
ここは莫大なエネルギーを食うから、虹色のディフレクターくらいじゃないとまかなえないんだってさ。
…俺が見たのは、最深部。コントロールルームでだ」
俺はロックマンアリアが淡々と仕事をこなしていた、コントロールルームを思い出した。
清潔で真っ白で、そのころあの巨大なリーバードだった俺でも簡単に入れるくらい広大な空間だった。
部屋の奥に確か巨大な虹色に輝くディフレクターがあったっけ。
…今のガードリーバード・エンテはそこへ行く唯一の通路に住んでいる。
その部屋を守るために、全力で襲ってくるだろう。
『エンテ、ごめんなさい。わたしはヘヴンに背こうと思う』
―――アリア?
『…もう、何百人もの島民を殺してしまうなんて、私にはできない。
でも、彼らを本当に解放するには、私だけの力じゃどうにもならないの』
非力そうな細い手をコントロールパネルに叩きつけて、アリアは引き締めた唇の端を震わせた。
怒りの声か、泣き声を食い殺すように。
決意の光をきらめかせる藍色の瞳。
その先の巨大スクリーンに、たった今届いたヘヴンからの指令が光っていた。
今実行中の実験体デコイを全て破棄すること。それと、その理由が申しわけ程度に述べられた短い文。
『ここの施設は、島民にとってもあなたにとっても、もちろん私にとっても完璧な檻ね』
長く艶やかな水色の髪に覆われた、華奢な肩。その肩越しに彼女は俺を振り返った。
そのときの表情を、俺はきっと一生忘れられない。
『でも、一つだけ方法がある。この島を開く方法』
悲しさと強さが同居した、不思議に惹かれる表情で、いままでに一度もみたことが無かった。
『わたし、そんなに優秀じゃないからこの方法しか思いつかない。こんなにひどい方法しか。だから、あなたには先に謝っておくね』
(…ごめんなさい)
なぜだか急にアリアとの会話を思い出して、俺は胸が痛くなった。
大丈夫、アリア。約束はちゃんと最後まではたすから
武器のチェックをしなおして、ロックが扉の横で俺を見た。
「今持ってる武器でその条件はなんとかなりそうだ。…ほかに何か必要なものは?」
俺は、ゆっくり歩いてその傍へ向かう。
「ありったけの幸運かな」
そう言うと、ロックはにっこり笑ってうなずいた。
「じゃあ大丈夫。いつもどおりだね」
ディグアウターってそんなにハードなんだろうか。それとも、ロックなりの冗談なのか。…いろんな意味で、スゴイやつ。
手を伸ばして扉に触れると、扉は音も無く開いた。
俺の前に、もう一度あの黄色い扉の部屋が広がった。
…今度は、あれを開きに行く。
俺なりの責任を果たすため。そして、昔からの約束を果たすため。
溜め息に似た音を吐いて、薄緑色の扉が開いた。
目の前には、だだっぴろい空間が広がっていた。
幅2mほどの通路の向こうは薄墨色の闇の中に深く落ち込んでいて、
そこから先はサッカーコート一面分ほどもある広い床面が続き、
遠近法に忠実に縮小していく床の終点には、俺たちのちょうど正面にあたる位置に黄色い扉がそびえていた。
ヘヴンの実用一辺倒な主義をそのまま形にしたかのようになんの装飾もなく、
まるで巨人が巨大な刃物で縦に真っ二つに切り裂いたように、すぱりと縦に切れ目が入っているだけ。
白い光の中、偽物の黄金のごとく安い光を反射している。
あいつ…あの守護リーバード、エンテはいない。
あいつがこの広間に出てくるのは、
あの黄色い扉の先のコントロールルームに入る資格のない者が、扉に触れた時だけ。
『鍵』を持たないものを排除する時だけなんだ。それ以外の時はその扉の向こうで静かに待っている。
客と、敵を。
俺の横から顔をのぞかせたロックが、小さく溜め息をついた。
「いないね、エンテ」
「普段はあの扉の向こうに引っ込んでるから」
俺が弓を持たない方の手で扉を示すと、彼はそちらを見て一瞬眉を曇らせた。
明るい緑の瞳と快活そのものの表情が、悲しみに陰った。
…そして、ただ一回のまばたき。祈りのような。
ディーアへの追悼。…百の言葉を積んだより、その一瞬の表情で俺は気持ちが救われた気がした。
だから俺も言葉で返さず、小さな頷きを返した。
―――ありがとう。
「…行くか!」
「行こう!」
俺たちは段差を一気に飛び降りた。
足にかなりの衝撃が来たが、アーマーを着込んだロックにはたいしたことは無いようだ。
…やっぱり、ただの靴ってのは…つくづくディグアウトに向かないな。
実はじんじんする足を無視して、俺とロックはゆっくりと扉に近づいた。
何となく走る気がしないのは、あまりに高すぎる天井、その上のほうにわだかまる闇の重圧のせいか、
…それとも、のしかかるようにそびえるこの黄色い扉のせいかもしれない。
「…俺は、ディグアウターになりたかった」
「?」
いきなり話し出した俺を、ロックが不思議そうに見上げてきた。
「いや、黙ってるのもなんだから」
苦笑いして、俺は扉を、その向こうを仰ぎ見るようにした。
頭の中を、俺がリーバードだった時代のことが流れてゆく。
懐かしく…悲しく…そして、忘れ去るには近すぎる思い出が。
もう戻ることは無い過去であるだけに、よけいにどこか切ない気分がする。
俺にはもう、グランド・リヒトエアとして以外の生き方をする気は全く無い。
「…知ってるだろうけど、この島は実は強力なバリアで隔離されてる。
ここがヘヴンの地上における実験島だったからだ」
ロックがうなずいた。
外からきた彼らは、そのバリアを越えて来たわけだから知らないはずはないもんな。
「外からこの島を見たとき、そこには海しか無いように見えるはずだ。
しかも、ある程度バリアに近づくと、自然とバリアを避けてしまいたくなるような強力な暗示も出ている。
普通の技術力じゃ、まず発見できないしバリアを通過することも出来ない」
無線機が鳴って、得意げな声が聞えた。
『わたしが見つけたの!』
「うん、ロールちゃんの作った新しいレーダーで、偶然この島が写ったんだ。
データが『ヘヴンの施設だ』って叫ぶし、
ロールちゃんは『これだけのバリアだもん、凄いディフレクターあるかも!』って言うしで、
着陸することになったんだけど」
照れたように苦笑いするロック。戦っている時の鋭さとはまるで雰囲気が違う。
そういう表情は、ほとんど普通の少年って感じだった。
「バリアは…ヘヴンの者たちに対しては簡単に開く。すんなり入れただろ?」
「拍子抜けするくらいね」
それで、ディグアウターであるロックたちはまっすぐ遺跡へ向かったわけだ。
一方、粛清官ロックマンの来島を察知した島はすぐさま起動状態に入った。
いつもはワンフロア―しか無いように見せかけていた施設は本性を現し、
島の外縁ではリ―バード・トラップが起動した。
俺とディーアが弓漁に出たとき危うく死にかけたのは、そのせいだ。
それはロックマンの来島でほんの一瞬開くバリアの隙間から島民が出るのを防ぐため。
…あきれるほどの閉鎖ぶり。あらためて嫌になるね。
俺は溜め息をついて、頭を振った。アリアが離反した理由。俺がここにこうしているわけ。
そして、いままで記憶を失っていたわけ。全てのわけはそれにある。
「…結論を言うとな、俺の正体はあれだ。…あの蛇。ガードリーバード・エンテ」
「えっ!? …えええっ!???」
ロックが口を全開にして驚く。そればっかりは予想してなかったらしい。
そりゃそうだ。ヘヴンや粛清官、それにマザーをもあざむくための、俺とアリアの計略だったんだから。
「でも、きみがあのリーバードのわけないよ!! だってさっきいたじゃないか!!」
「あれは抜け殻みたいなもんで、
あれには遺跡とロックマンアリアを守るっていう本能しか残ってない。
…今の俺は、アリアがリセットした体にガードリーバード・エンテの人格を乗せたもの
…になるのかな」
それを聞いて、今度こそロックは声も出ないようだった。
息を飲んだっきり沈黙している。無線機も何の音もしない。
いや、今何かをがらがらと崩したような音がした。ロールも驚いているみたいだった。
「リセットした身体に入ったのが俺っていう男性人格だったからか、
アリアがなにかしたからなのかわからないけど、性別はこの通りだよ」
もと自分だったものがディーアを殺したのかと思うと、また悔しさがこみ上げる。
もう一人の自分が、あるいは自分そっくりのやつが親友を殺したと考えてみなよ?
それは他人がそうしたというより、…何倍も辛いもんなんだ。
俺は奥歯をくいしばって感情を噛み殺した。今すべきなのは、ロックに協力を得ること。自分のことだからわかるんだ。
今の俺じゃあ、あの、リーバードの俺は倒せない。
「ロック、協力して欲しい。あのリーバード・エンテは俺だけじゃ倒せないんだ」
「…? 君は司政官モデルのロックマンなんだよね?
…あ、いや、その中身は違うのかもしれないけど、自分の守護リーバードに勝てないの?」
俺はうなずいた。皮肉っぽく笑って。
司政官。文字通りその島の管理が仕事で、戦いには向いていない。
でも、向いていないと言ってもそれはヘヴンの戦闘型の者たちと比べての話だ。
地上では、そこらの一般人には及びもつかない身体能力を誇る。
それでも、アリアはエンテには勝てないんだ。
「もしアリアがイレギュラー化して、この実験島を開放しようとしたり
ヘヴンにとってまずい行動をとり始めたとき、
いちいちヘヴンから人を派遣していたのでは遅すぎる。
その場合は、そばにいるエンテがアリアを強制停止させる役目を負う。
…アリアは、エンテには絶対に勝てないようにできてるんだよ」
そんな、と言ってロックは顔を苦しそうに歪めた。握りしめた片手が震えている。
もしかして、ロックもヘヴンでやりきれない、辛い思いをしたんだろうか。
「じゃあ、そのエンテがイレギュラー化してしまったときはどうするつもりだったんだろう?
アリアが止められないんじゃあ…」
俺は静かに首を横に振った。
ヘヴンの、この島を隔離するやり方はいやになるほど徹底していたんだ。
「あのエンテの巨体を見たろ? 昔、俺は一度だってこの施設からでられなかった。
この施設はエンテの上に作られた。
もしイレギュラー化しても、地上部分に行けないから影響はないんだとさ。
…エンテがイレギュラー化した場合、即座にヘヴンに連絡がいく。
エンテを倒せるのは、アリア以外のロックマンが、定められた手順でエンテに攻撃を加えた時だけ」
言いながら、俺はもう一度背後の壁画を指した。
「…アリアはその、エンテの倒し方をここに残した。
もしヘヴンからロックマンが派遣されてきたなら、必ず遺跡に降りる。
俺はそれを知ったらそれを追って遺跡に入るように自分に暗示をかけていた。
そして、『ロックマン』という名乗りを聞いた瞬間に記憶が蘇るようにもしておいた。
…あの、昔の俺を倒すためにはヘヴンの、しかも『ロックマン』クラスの協力がいる」
壁画のアリアの絵のすぐ下の文章を、指でなぞる。
『赤は紅蓮。逆巻く炎・
橙は広がりゆく熱。四散し猛る強き爆炎・
黄は灼熱。細く鋭く貫く穿光・
緑は波動。全てを切り裂く力の刃・
青は光。扉の鍵なる雨色の閃光・
藍は力。彼の放つ無類の技なり・
菫は粛清。天からの使者なる証をたてよ
七つの色にて彼を倒せ。虹への道は遠からじ』
読み終わって、俺はちょっとあっけにとられた。
…これって、詩だよ。
まったく、アリアも凝ったことを考えたもんだ。慎重なんだか、馬鹿なんだか。
でも、アリアはそういう奴だった。
デコイたちの詩や音楽を集めては喜んで、自分でも作っては才能の無さに落ち込んだりして。
妙にロマンチストなとこがあったもんな。俺は思わずその様子を思い出して少し笑ってしまった。
「わざわざわかりにくく詩にすることもないのにな。
つまり、上から順番に炎・爆発・ビーム・エネルギーブレード・
俺の持ってる雨の弓…この弓での攻撃・あとあいつは藍色の火を吐くんだけど、
それをそのままはね返しての攻撃、そのあとに力で強引に倒せって意味だよ。
特に最後のとこがわかりにくいな。
『ロックマン』の攻撃じゃなきゃとどめがさせないって書けばいいのに」
ロックは興味深そうにじっくりその詩を眺めて、なんだか嬉しそうに笑った。
「司政官ロックマンにもこういう面白い人がいたんだ。…会ってみたかったな」
「…他の司政官と会ったことが?」
ロックは答えずに、ちらりと悲しそうな苦しそうな笑みを見せた。
「…いや。それより、ちょっと聞きたいんだけどさここ…」
『ここに虹色のディフレクターってある!?』
ロールのやけに喜々とした声がロックの言葉をさえぎった。
…やれやれ。なんて前向き思考。女ってみんなこんなにタフなのかね?
実際、本当は少しうらやましいものを感じるんだけどさ。
ロックの顔をうかがうと、彼はそんな感じ。というふうに肩をすくめて見せた。
アリアはどうだったかな。いつも壊れそうに繊細な印象があったんだけど…。
本当のところは結構強い奴だったのかもしれない。
…う~ん。もう、確かめようはないんだけどな。
「虹色の、ディフレクターね。確かにあるよ」
とたんに、無線が高周波みたいな音をたてた。
…どうやらロールの歓声だったみたいだけど、俺は耳がしばらくおかしくなってしまった。
「ご、ゴメン! …やっぱあのリーバードを倒さなきゃ行けないとこにある…んだよね?」
なぜかロールじゃなくてロックがあやまりながら無線のボリュームを落とした。
「島をすっぽり覆うだけのバリアも張らなきゃいけないし、島民の管理もしている。
ここは莫大なエネルギーを食うから、虹色のディフレクターくらいじゃないとまかなえないんだってさ。
…俺が見たのは、最深部。コントロールルームでだ」
俺はロックマンアリアが淡々と仕事をこなしていた、コントロールルームを思い出した。
清潔で真っ白で、そのころあの巨大なリーバードだった俺でも簡単に入れるくらい広大な空間だった。
部屋の奥に確か巨大な虹色に輝くディフレクターがあったっけ。
…今のガードリーバード・エンテはそこへ行く唯一の通路に住んでいる。
その部屋を守るために、全力で襲ってくるだろう。
『エンテ、ごめんなさい。わたしはヘヴンに背こうと思う』
―――アリア?
『…もう、何百人もの島民を殺してしまうなんて、私にはできない。
でも、彼らを本当に解放するには、私だけの力じゃどうにもならないの』
非力そうな細い手をコントロールパネルに叩きつけて、アリアは引き締めた唇の端を震わせた。
怒りの声か、泣き声を食い殺すように。
決意の光をきらめかせる藍色の瞳。
その先の巨大スクリーンに、たった今届いたヘヴンからの指令が光っていた。
今実行中の実験体デコイを全て破棄すること。それと、その理由が申しわけ程度に述べられた短い文。
『ここの施設は、島民にとってもあなたにとっても、もちろん私にとっても完璧な檻ね』
長く艶やかな水色の髪に覆われた、華奢な肩。その肩越しに彼女は俺を振り返った。
そのときの表情を、俺はきっと一生忘れられない。
『でも、一つだけ方法がある。この島を開く方法』
悲しさと強さが同居した、不思議に惹かれる表情で、いままでに一度もみたことが無かった。
『わたし、そんなに優秀じゃないからこの方法しか思いつかない。こんなにひどい方法しか。だから、あなたには先に謝っておくね』
(…ごめんなさい)
なぜだか急にアリアとの会話を思い出して、俺は胸が痛くなった。
大丈夫、アリア。約束はちゃんと最後まではたすから
武器のチェックをしなおして、ロックが扉の横で俺を見た。
「今持ってる武器でその条件はなんとかなりそうだ。…ほかに何か必要なものは?」
俺は、ゆっくり歩いてその傍へ向かう。
「ありったけの幸運かな」
そう言うと、ロックはにっこり笑ってうなずいた。
「じゃあ大丈夫。いつもどおりだね」
ディグアウターってそんなにハードなんだろうか。それとも、ロックなりの冗談なのか。…いろんな意味で、スゴイやつ。
手を伸ばして扉に触れると、扉は音も無く開いた。
俺の前に、もう一度あの黄色い扉の部屋が広がった。
…今度は、あれを開きに行く。
俺なりの責任を果たすため。そして、昔からの約束を果たすため。
溜め息に似た音を吐いて、薄緑色の扉が開いた。
目の前には、だだっぴろい空間が広がっていた。
幅2mほどの通路の向こうは薄墨色の闇の中に深く落ち込んでいて、
そこから先はサッカーコート一面分ほどもある広い床面が続き、
遠近法に忠実に縮小していく床の終点には、俺たちのちょうど正面にあたる位置に黄色い扉がそびえていた。
ヘヴンの実用一辺倒な主義をそのまま形にしたかのようになんの装飾もなく、
まるで巨人が巨大な刃物で縦に真っ二つに切り裂いたように、すぱりと縦に切れ目が入っているだけ。
白い光の中、偽物の黄金のごとく安い光を反射している。
あいつ…あの守護リーバード、エンテはいない。
あいつがこの広間に出てくるのは、
あの黄色い扉の先のコントロールルームに入る資格のない者が、扉に触れた時だけ。
『鍵』を持たないものを排除する時だけなんだ。それ以外の時はその扉の向こうで静かに待っている。
客と、敵を。
俺の横から顔をのぞかせたロックが、小さく溜め息をついた。
「いないね、エンテ」
「普段はあの扉の向こうに引っ込んでるから」
俺が弓を持たない方の手で扉を示すと、彼はそちらを見て一瞬眉を曇らせた。
明るい緑の瞳と快活そのものの表情が、悲しみに陰った。
…そして、ただ一回のまばたき。祈りのような。
ディーアへの追悼。…百の言葉を積んだより、その一瞬の表情で俺は気持ちが救われた気がした。
だから俺も言葉で返さず、小さな頷きを返した。
―――ありがとう。
「…行くか!」
「行こう!」
俺たちは段差を一気に飛び降りた。
足にかなりの衝撃が来たが、アーマーを着込んだロックにはたいしたことは無いようだ。
…やっぱり、ただの靴ってのは…つくづくディグアウトに向かないな。
実はじんじんする足を無視して、俺とロックはゆっくりと扉に近づいた。
何となく走る気がしないのは、あまりに高すぎる天井、その上のほうにわだかまる闇の重圧のせいか、
…それとも、のしかかるようにそびえるこの黄色い扉のせいかもしれない。
「…俺は、ディグアウターになりたかった」
「?」
いきなり話し出した俺を、ロックが不思議そうに見上げてきた。
「いや、黙ってるのもなんだから」
苦笑いして、俺は扉を、その向こうを仰ぎ見るようにした。
頭の中を、俺がリーバードだった時代のことが流れてゆく。
懐かしく…悲しく…そして、忘れ去るには近すぎる思い出が。