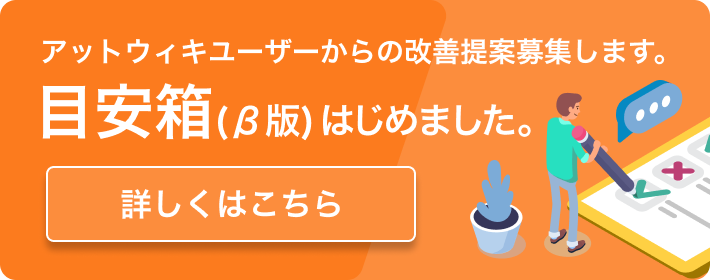ありがとう 兄さんへ――
あなたは沢山のことを教えてくれました 沢山のものをくれました
ありがとう 兄さんへ――
あなたは強い心をくれました あなたは僕に剣をくれました
ありがとう――友人達へ
あなた達は僕を受け入れてくれました あなた達は僕に笑顔をくれました
ありがとう――みなさんへ
あなた達がいてくれたから 僕は楽しかったです
とてもとても楽しかったです
暖かな人生を歩めました 全てが僕の想い出です
ごめんなさい――親友へ
あなたを置いていく僕をどうか許してください
あなたと過ごした時間は 僕の宝物だから...
さようなら――親友へ
君を忘れない
ロックマンXセイヴァーⅡ 最終章~君を忘れない~
「なあ、セイア」
ウィド・ラグナークがふとロックマン・セイヴァーに声をかけたのはいつだったか。
確かウィドが忙しくキーボードを叩いている様を見詰めている時だったように思う。
彼の邪魔にならないように、とこちらから話しかけることを避けていたセイアは驚いた風に返した。
その拍子にぶちまけってしまった砂糖の塊がコーヒーの黒い波の中に呑み込まれる。
もう手遅れだなと諦めつつ、セイアはそれを自分で飲むことに決めた。
「何、ウィド?」
「お前は一番の願いが何かと聞かれたら、どう答える?」
「一番のお願い?」
カチャカチャとスプーンでコーヒーを掻き混ぜ、一口口に含んでみる。
ミルクも入れていないブラックコーヒーは、余程身を投じた砂糖の量が多かったらしい。
甘党のセイアでもうぇっと顔を顰める程に甘かった。こんなものをブラック派のウィドに渡してしまったらと思わず肝を冷やす。
きっとコーヒー独自の味わいが失われただの、豆の美味さを台なしにしているだの云われるのだろう。
幸いウィドはキーボードを叩いた姿勢のまま振り向かないので、その事実は雲隠れしてしまいそうだが。
何やらカチャカチャと慌ただしいセイアの様子をいぶかしげに思ったのか、振り向こうとするウィド。
セイアは慌てて手の中の甘すぎるコーヒーを飲み下した。ウィドが見たのはうぇーと顔を顰めるセイアの顔だけだった。
「・・何してんのお前」
「え、た、たまにはコーヒーでも飲んでみようかなって」
「なんでまたコーヒーなんか飲んでいるんだ、そんなしかめっ面までして」
「えーっと・・ちょっぴり大人さ!みたいな?」
今の答え方は随分だったらしい。呆れたように溜息をつくウィドは、また振り返ってキーボードをたたき始めてしまった。
自分でも今の答え方はないだろうと内心苦笑しつつ、セイアはもう一個のマグカップにコーヒーメーカーからコーヒーを注いだ。
もうかれこれ数時間はキーボードを叩いている友人への労いの為だった。
「・・で?」
暫くの間をおいて、ウィドの疑問の声が飛んでくる。見やるとまたウィドはキーボードを叩いているようだったが、
きっとさっきの質問の続きをしているんだろうとセイアは思った。
「・・・。僕の一番のお願いごとか」
「あぁ」
「なんでまたそんなことを?」
「ただの興味だ。答えたくなければ答えなくてもいい」
不貞腐れたような云い方をするウィドの表情は、セイアには見えない。
だからセイアはきっと自分が答えるのを手間取った為にウィドが機嫌を損ねてしまったんだと思って、
慌てて答えようと口をぱくつかせる。改めて考えた、自分の一番のお願いはなんなんだろうと。
「僕の、僕の一番のお願いは」
「・・・・」
いつの間にかウィドはキーボードを叩くのを止めていた。けれどそのことにセイアは気付かない。
俯くように、そして天井を見上げるようにセイアは云った。ウィドにその顔は見えなかったが、
きっとセイアは心底本音を云ったんだろうと彼は思った。
「落第しないでちゃんと進級して、学校を卒業することかな」
「学校を卒業すること?」
「うん。みんなと一緒に進路はどうしただとか、テストがどうしただとか、
そんな風に普通の会話をしながら学校に行って、みんなと一緒に卒業したいんだ」
ウィドは思わずプッと吹き出した。その答えが最強のイレギュラー・ハンターの発するものだとかは信じ難く、
それと同時に実にセイアらしい答えだったからだ。
本当は腹を抱えて笑いたかったけれど、流石にまずいだろうと懸命に肩を震わせるウィドだが、
笑っていることがばれないわけがない。しっかり答えたつもりのセイアは、顔を真っ赤にしながら怒鳴り声を上げた。
「ちょっと!人が折角本音で答えたってのに笑うことないでしょ!」
「くくくく、いやいやすまん、実にお前らしい答えだと思ったら・・。くっくっくっ」
「全く。もうウィドに何か聞かれても真面目に答えて上げないよ」
べえと舌を出すセイアに、ウィドは振り返って手を合わせた。
それでも彼はなかなか許してくれず、結局その日は仕事が進まなかった。
その所為で次の日は学校に遅刻してしまい、二人揃ってクラスメイトに笑われた。
その時は気付かなかった。その時のセイアの顔に憂いがあったことを、今になってようやく思い出す。
何故あの時は彼はそれを云わなかったのか、ウィドには理由が判らなかった。
その時既にリミテッドは出現していたけれど、まだ比較的危機感を持っていなかったからかもしれない。
「そういうウィドの一番のお願いごとは?」
「秘密さ。人には黙秘権というものがある」
「ちょっ、人に喋らせておいてそりゃーないでしょ!」
「黙秘権の公使は自由権限だ」
ウィドの一番の願いごとは、ゼロを目覚めさせることだった。
「セイア、今思えばあの時お前は何を云いたかったんだ・・?」
今まさにスプリット・マシュラーム・リミテッドの心臓部を貫いたレーザー銃を静かに降ろしながら、
ウィドはあの時の出来事を思い出すように呟いた。煙を上げる銃口とは裏腹に、ウィド自身の意識は全壊したマシュラームへ一片たりとも注がれてはいない。
ウィドの瞳に映っているのはその先の光景だけだった。
余りに自然という単語からかけ離れた世界。木々は一本たりとも生えず、辺りにはもはやレプリロイドだったと判別することも出来ない機械の破片の山。
乾いた風は破片の隙間を通り抜けて不気味に音を発する。それはさながら使者の悲鳴のようで、常人にはお世辞でも居心地がいいと云える場所ではない。
つい十年と少し前までは活気で賑わっていたこの場所は、今はもはや現世の阿鼻叫喚と云えた。
旧イレギュラー・ハンターベース跡。今とは違い、部隊数も隊員数も圧倒的に多かった頃。そう、あのシグマがまだ第十七精鋭部隊の隊長を務めていた頃、
イレギュラー・ハンター達が籍を置いていた場所だ。今となっては見る影もないが、昨今に較べ、
あの頃のイレギュラー・ハンターはなんと安定していたことだろう。そう思うことすら、今となっては虚しい思考に過ぎない。
さりとて旧イレギュラー・ハンターに所属していたわけでもなく、シグマの反乱を目にしたわけでもないウィドにとっては、
そんなことは眼中にすら入らない。ただただ静かに足を進め、一歩一歩とそびえ立つ廃墟へと歩いていく。
巷ではもはや心霊スポットと騒がれることすらない程に不気味な廃墟。深夜に訪れる者なら、その光景を見ただけで背筋を凍りつかせるだろう。
事実、あそこには沢山の魂が散乱しているに違いない。魂というものが実在するかどうかウィドには判断しかねるが。
旧ハンターベース跡で命を落とした者は数知れない。ある者は反乱する者達を止めようと。ある者は反旗を翻し、かつての同胞に撃たれ。
ある者は襲撃を試み、返り討ちにされ。そして襲撃され、闇討ちされた者。
ここが魂の集積所でなければなんなのか。それを形容する言葉も見つからず、さしてや形容する気もなく、ウィドはただ真っ直ぐに歩いていた。
「・・待っていろよ、セイア」
囚われた親友を想う。この先には囚われの親友と最凶の敵がいるのだ。
そう、つい数時間前にウィドはその事実を知らされた。知らされたというよりも一方的に突き付けられたという方が正しかったかもしれない。
マザー内でイクセを退けたクロス・アーマーを現実のものとして完成される為には、材料が圧倒的に不足していたのだ。
鎧の剛性を確保する合金。出力を高めるジェネレータ。安全性を保証するプログラム。その全てが足りなかった。
中でも入手が難しかったのがオリハルコンである。エネルギー出力を増幅させる恰好の材料であると同時に、
鎧の剛性を上げ、更にはその他の資源とは比べ物にならない廃熱力。かつてギガ粒子袍エニグマに利用されただけのことはある、別名奇跡の宝石。
当初オリハルコンを使用する予定はなかったのだが、急速にクロス・アーマーを組み立てるには必要不可欠だった。
更にはマザー内でセイアが使用した奥義・ソウル・ストライクに剛性が追い付いていない事実が発覚し、どちらにせよオリハルコンを使用せざをえなかった。
だがオリハルコンを手に入れさえすれば話は簡単だった。マザーの電脳世界での闘い以来、身体に無理を強いてまで完成させたプログラム、
鎧の型も既に出来ている。あとは鎧を構成する材料があれば良かった。
そしてオリハルコン使用の有効な副産物も発生した。エネルギー増幅力と廃熱力をいかし、ソウル・ストライクのエネルギーの連続的な維持。
つまり事実上の連射が可能となる可能性が出来たのだ。そうなればリミテッド達に勝利する確立もグッと上がる。
なんとしてでもオリハルコンという素材を入手せねばならなくなったのだ。
『大丈夫。すぐ戻ってくるよ』
そう言い残して、セイアは出ていった。オリハルコンを入手する為だ。
オリハルコンが残っている可能性があったのは、廃棄されたレプリフォースの巨大トレーラー。
オリハルコンの輸送中にユーラシア事件に遭い、そのまま廃棄されていた事実が今更になって判ったのだ。
ユーラシア落下の影響で使い物にならなくなっている可能性も否定は出来なかったが、僅かな可能性でも縋る必要があった。
危険性は未知数だった。リミート・レプリロイドが襲ってくる可能性があったからだ。
しかしそれでもセイアは出撃していった。クロス・アーマーを完成させ、リミテッド達を倒したいと思っていたのは、誰よりも彼だったのだ。
出撃の途中、案の定リミート・レプリロイドは姿を現わした。通信機からセイアが漏らした名はビストレオ。
スラッシュ・ビストレオ・リミテッドだった。
レプリフォースの中でもトップクラスの実力者だったビストレオのリミテッドは手強かった。
データを元に弱点をついて闘うセイアだったが、かなりの苦戦を強いられた。が、結果的にビストレオを撃破したセイアは、
予測通り残っていたオリハルコンを入手したと報告をくれた。オリハルコンは一足先にベースに転送装置にて転送され、
セイア自身もすぐにベースへと戻ろうとした矢先。ウィドが予想しながらも考えることを避けていた事態が起きてしまった。
ロックマン・セイヴァーからのイレギュラー・ハンターベースへの連絡が不意に途絶えた。
通信機の故障とは思えなかった。予備の通信機に呼びかけても反応はない。人工衛星を使用して反応を追ったが、セイアの反応は完全にロストしてしまっていた。
『今から帰る』
それがベースに、ウィドに届いたセイアの最後の言葉だった。
別のリミート・レプリロイドが現れたのか。それとも何か別の出来事に巻き込まれたのか。
セイアの反応が消えてから十数時間。使用者不在のクロス・アーマーがようやく完成の兆しを見たとき、ウィドのモバイルが叫び声を上げたのだった。
普段聞いたこともないその音はメール着信音。セイアだろうかと慌てて開いてみると、差出人の欄には彼に似ても似つかぬ翠の悪魔の名前があった。
「イクセ・・・」
タイトルは『焦っているようだね』。人とを小馬鹿にしたような態度は文面でも変わらない。
震える手で本文を開く。ウィドを戦慄させるには充分な文章だった。
『 こんにちは、ウィド・ラグナーク君。
毎日部屋に籠もっての研究ご苦労様。ボク達を倒す打算はまとまったかい?
それともセイアがいなくなって研究どころじゃなく焦っているのかな。おっと確信めいたことを云っておいて問いかけるのはまずかったね、謝るよ。
む、ここで機嫌を損ねてメールを閉じたりしないでね。でないときっと後悔するよ。
いいかい?ここから下の文章は君一人で読むこと、ウィド・ラグナーク。もし別の誰かに見せたりしたら、ボクが機嫌損ねちゃうからね。
しっかり周りに誰もいないことを確認したなら、下にスクロールするといいよ。 』
周りを見る。誰もいない。ゲイトは今ごろクロス・アーマーの制作を続けているのだろう。
奥の方から素材を削る高音が聞こえてくる。彼はどうやらセイアを信じて黙々と制作を続けるつもりらしかった。
もう一度辺りを確認する。やはり誰もいない。ほんの少しの動揺を必死で隠しながら、ウィドはスペースで埋め尽くされた文章を一気にスクロールさせた。
『 頭のいい君ならきっとこれを読んでくれると期待していたよ。あんまり気分がいいからお礼を云うよ、ありがとう。
最も君にとっては焦燥感でどうにかなりそうな状況なんだろうけど、すぐにその焦りを解放して上げよう。
君の大切なお友達、そしてボクにとっては愛しい宿主。セイアはボクのすぐ傍にいるよ。
おっと君の自尊心を傷つけるつもりはないから断るけど、単にボクがセイアを一方的に預かっただけだから安心してよ。
昔のドラマっぽいでしょ?人質を返して欲しくば・・って奴さ。
あ、だからってお金が欲しいわけじゃないし、君に無抵抗で殺されろと云うつもりもない。
要求はただ一つ。セイアを返して欲しいならボク達のところへ一人で遊びにおいで。勿論あのクロス・アーマーとかいう厄介な鎧も持ってくるといい。
場所は旧イレギュラー・ハンターベース。座標くらいは調べればすぐに割り出させるでしょう?とてもロマンチックな場所さ。
心配はいらないと思うけど、先に忠告しておくよ。ボク達が呼んだのは君一人。余計な誰かをくっつけてくるんじゃあないよ。
因みに君が来なくても別に構わない。君を追って行って殺すつもりはないからね。
ただ明日の正午までに君が来なかった場合、君のお友達の身の安全は保証出来ないな。
それじゃあ、君と逢えることを楽しみにしているよ。それじゃあ、バイバイ
P.S.そろそろ君達と遊ぶのも飽きてきた。そろそろ決着をつけよう Byイクセ 』
旧イレギュラー・ハンターベース。その中でも最も広い空間を誇るA級トレーニングルーム。
A級のと現わすことは現存のハンター達には違和感だろう。何故ならバーチャルトレーニングは設定によってランクが上下するのみであり、
基本的な設備はどの部屋も同じだからである。
しかし技術も現在と較べて劣り、ハンターの絶対数も多かった旧ベースは違った。下からC級、B級、A級とランク別にそれぞれトレーニングルームを与えられ、
それぞれ違った設備が施されていたのだ。
現在と較べてなんと贅沢で、無駄の多い施設だったことだろう。
パッと不意に輝いた照明に照らされ、目を細めながらも、ウィドはそんなことを心の隅で考えた。
冷静、とは少し違う。何か理論的なことを考えていれば気持ちが落ち着くからだ。本当ならはらわたが煮えくり返る直前だ。
眼球が光に慣れ、ようやく目を開けられるようになった頃、見計らったように聞き慣れた声が飛んできた。
いや違う。聞き慣れた声と同じながらも、それとは全く違う・・憎悪の対象としか受け取れない声だった。
「やあ、やっぱり来てくれたねウィド。君が来てくれると信じてたよ」
「イクセ・・」
ウィドに対して部屋の丁度反対方向に立っている三体のリミテッド。イクセ、レイ、イクス。
実際に目にするのはこれで二度目だが、奴等の狂気と威圧感を知るには充分過ぎる回数だろう。
リミテッドの三人はそれぞれが口もとに笑みを賛え、ウィドを見詰めている。
だがウィドは三人分の殺気に晒されながらも、イクセ達三人が眼中にないかのように視線を上にした。
恐らく奴等の趣味か何かなのだろう、まるで教会に飾ってあるキリストの絵画のように、十字架に磔にされたセイアの姿がそこにはあった。
「見た所やはり一人か。約束を守る律義な輩なのか、或いはただの馬鹿なのか」
「それは違うさレイ。彼はイクセの言いつけ通りに一人で来たんだ。要はセイアを助ける為さ」
「ふん。成る程な」
「ウィド・ラグナーク。我々の言いつけ通りに一人で来たことを褒めて上げよう。いらっしゃい、旧ハンターベースへ」
ウィドを嘲るレイに対して、イクスは逆にウィドを庇護しているようだった。丁寧に紳士的な挨拶をするイクス。
端から見れば優雅かつ端麗な姿に見えることだろうが、今のウィドにはそれがなんだろうと関係ない。
磔にされたセイアは生きている。微かに呼吸――最もレプリロイドに呼吸は必要ないが――で腹部が上下しているからだ。
見た所目立ったダメージもない。ビストレオと闘った際のものだろう、小さな傷は要所に垣間見ることが出来るが。
ウィドは腰のレーザー銃を抜いた。抜群の狙撃力を誇る銃口が、三体のリミテッド達へと向けられる。
距離にして三十m。決して外す距離ではない。無言のウィドに対しては、イクセは嘲笑を込めた苦笑で応えた。
「随分血の気が盛んなんだね、ウィド君。それはなんのつもりだい?」
「何のつもりだ、だと?訊ねるまでもないだろう。約束通り一人で来てやったんだ。
今すぐにセイアを降ろせ」
「口に気をつけろ、小僧。マシュラーム・リミテッドを倒したことで図に乗っているようだが、貴様一人でオレ達三人を相手にするつもりか」
「レイの云うとおり、君一人で俺達三人の相手をするのは少しばかり力不足だ。ここは大人しくしていた方がいい。
・・その気になれば半瞬後に君の首を飛ばすことだって出来るんだからな」
イクスは至って笑みを崩さずに言い放ったのだったが、それが嘘ではないことはウィドにも判る。
悔しいがリミテッド達の云うことは間違いない。頭に血が上ったウィドは猛りすぎている。
レイの云う通りマシュラーム・リミテッドを撃破したことで少々図に乗っていたのかもしれない。
一瞬強風が吹いたと錯覚する程のリミテッドの殺気にあてられて、ウィドはゾッとするような怖気を感じると共に、それを理解した。
一瞬にして熱を冷まされたウィドは渋々銃を降ろした。それが満足なのかうんうんと嫌味ったらしく頷くイクセは、
いちいち神経を逆撫でする明るい声で続けた。
「うんうん。素直に云うことを聞いて、良い子ちゃんだねえウィド君」
「・・・何か話があるなら手短に済ませたらどうだ」
「うーん、恐いなあそんな事云って。イクス兄さんの云うとおり、君をバラバラの細切れにして上げてもいいけど、それじゃあ折角君を呼んだ意味がない。
ちょっと気乗りしないけど、ボク達とお話する気はない?」
「・・・」
ちっとウィドは想わず舌打ちをした。気乗りしないのはあっちよりもこちらの方だと云ってやりたかったが、
これ以上奴等を刺激すれば結果は見えている。ようやくいつもの計算力を取り戻したウィドは、大人しく奴等の話に乗るしかないと結論づけた。
「・・いいだろう。ただしセイアに危害を加えることはしないと約束しろ」
「うん、いいよ。どうせ後で闘うことになるんだし、セイアが起きたところでボク達には絶対勝てないからそんな約束は意味ないんだけどね」
いちいち勘に障る野郎だ。ウィドは心の隅で吐き捨てた。
これではセイアがあれだけ向きになって斬り掛かっていく理由が判る気がする。真面な神経をした者なら苛つかずにはいられない。
奴がセイア以上の、つまり最強のレプリロイド以上の力を持つというなら尚更だ。
「どうせ君だって疑問に思ってるんでしょう?『何故滅びた筈のリミテッドが存在しているのか』とね」
「――・・!」
「図星だね。君は根っからの科学者だ。こうして自ら闘いに出向くより、ボク達の出所を考える方が余程楽しい。
ボク達を倒そうと考えるなら、尚更出所を知りたかったんじゃない?」
「ふん、教えてくれるなら願ったりだ。そこまで云うなら教えて貰おうか、貴様等リミテッドの出所を」
なるべく話を繋ぎ、奴等にセイアを解放させなければならない。そう思う反面、イクセの云うとおりウィドは知りたかったのかもしれない。
数年前に消滅した筈のリミテッドが何故今こうして存在しているのか。
何故またあの悪夢が現れ、セイアを喰らい、このような三体の悪魔を創り出したのか。
壁に背を預け、イクセは語らい始める。その姿は、その声は、その表情はさながら雑談するセイア。
確かにこれは余り気持ちのいい光景ではないと思う。磔にされ、首をもたれるセイアを見つめ直し、ウィドは自分を奮い立たせた。
「ま、とは云っても何から話そうか。そうだな、君はアルバート・W・ワイリーの名を知っているかい?」
「・・20XX年代にて幾度も世界征服を目論み、その度に伝説のロックマンによって阻止されてきた天才科学者。
現在の21XX年代でも彼とその対となるDr.ライトの技術に追い付いた者はいないと云われている」
「詳しいね。流石は天才少年科学者だ。そう、君の云うとおりDr.ワイリーは幾度もロックマンによって倒された哀れな天才科学者。
あのゼロの制作者でもあり、カウンター・ハンターのサーゲス、そしてアイゾックの正体も彼だ」
サーゲス。アイゾック。名前くらいは聞いたことがあるが、ウィドにとってはさして興味のない存在だった。
「・・あれれ、驚かないね。ゼロがワイリーナンバーズだって知ってたのかい?」
「あぁ。知っている」
「意外だね。だけどその割にはセイアと仲良くしてるけど、恐くないのかい?」
「貴様等とセイアを一緒にするな!」
ウィドの怒声は心底怒りに満ちていたが、イクセ達にとっては単なる怒鳴り声としか受け取れないらしい。
暫くキョトンとしたあと、イクセはまたニコリと目を細めて笑った。
「これは失礼。君の神経を逆撫でる気はなかったんだ。謝るよ」
ぬけぬけと云ってのけるイクセに殺意すら沸いてくる。だが今のまま闘っても勝てる見込みは零以下だ。
理解している分、ウィドにとってそれは拷問に近かった。
「そしてDr.ワイリーは一年前、再び現世に蘇った。あのVAVAを蘇らせ、もう一体のゼロを創り、
ロックマンの後継者であるエックスを倒そうとね」
「・・だが目論みと結果は違う。エックスにはセイアという隠し玉があった。ゼロは生きていたが、既にワイリーにとってそんなことはどうでもよかった。
奴の標的が二つになった。エックスとセイア。ロックマンの名を継ぐ者だ」
イクセの言葉を継いだイクスを、更にレイが続けた。そしてまたローテンションでイクセが口を開く。
「彼は天才だった。ボクが思うに彼はとうにDr.ライトを越えていたんだ。
彼が勝てなかったのはロックマンという個体がロボットという粋を超えて強かった。たったそれだけのことだったのさ。
結局ワイリーは復讐を果たすと同時に消滅した。皮肉だよね?最高傑作ゼロの血を引くセイアに斬られて死ぬなんてさ」
その瞳に感情はない。あるとすればそれは嘲笑だった。
「・・何が云いたい。そんなことを語って一体何になる?」
「まあそう苛つかないで。せっかちだね、君は。なら話をもっと簡単にして上げようか。
君の持つデータではボク達リミテッドは既に消滅した存在だ。違うかい?」
「そうだ。リミテッド並びにハイパー・リミテッドは数年前の闘いで消滅が確認されている。
だからこそ貴様等がそうして存在していることが疑問なんだ」
「うん、結構。頭のいい君ならそろそろ気付いてもいいんじゃないかな、ボクの云いたいこと」
半瞬の思考の後、ウィドはハッとした。今まで意味なくイクセが連ねていた言葉の真意をようやく掴みかけたからだ。
しかし――いや、だが・・そんなことが有り得るというのか。決定打を打ち損ねるウィドの様子に気が付いたのか、
イクセはさっきとは打って変わって楽しそうに笑った。そしてその顔とは裏腹に冷たい声で云う。
「アハ。気付いたかい?そろそろ遠回りに云うのも飽きてきたし、君が耐えられそうにもないから種明かしをしよう。
そう、ボク達新型リミテッド――正式名称はデス・リミテッドって云うんだけどね――はDr.ワイリーがリミテッドのデータを元に創り上げた試作品。
だけど余りにも不安定で出力が高過ぎる所為でワイリー自身が封印した悪魔のプログラムさ」
「ワイリー自身が封印したプログラム・・」
「そう。彼自身にも操ることが出来なかったのさ。だから来るべく決戦にボク達は投入されなかった。
ボク達はワイリーが死んだことで束縛から解放され、世界に放り出された。その最初の犠牲者はウェブ・スパイダスの亡骸だったっけね」
ウェブ・スパイダス・リミテッドのことはウィドもよく覚えている。そもそもウィドがセイアと知り合うきっかけとなった事件だ。
そう、確かアレは半年程前の話だった。任務中に思いがけないダメージを受けたセイアはベースとの通信手段も、移動手段であるライド・チェイサーも失い、行き倒れた。
それを救ったのはウィドだった。幸いなことにセイアが倒れたのはウィドの研究所の近くだったのだ。
前々からロックマン・セイヴァーという存在に興味があったウィドは彼を介抱することに決めた。
目を開けたロックマン・セイヴァーは噂よりもずっと幼い男の子で、彼自身とそう変わらない年頃に見えた。
最初はセイヴァーというイレギュラー・ハンターに興味があっただけのウィドは、彼と触れ合う内にセイアという一人の少年と友達になっていた。
破壊されたアーマーを修復するまでの数日間。それはウィドの人生の中でも特に充実した日々だったと思う。いや、間違いなくそうだったであろう。
そしてアーマーが修復され、セイアとの別れが来た。本当ならばここで別れ、それっきりだったに違いない。
けれどセイアにとってもウィドにとっても運命とは奇妙なものだった。その時、不意に二人の前に意外な敵が現れたのだ。
それがイクセの云うウェブ・スパイダス・リミテッド。レプリフォース大戦時にセイアの兄が撃破したレプリフォースの一員であり、
当然ながら既に破壊されている故人。思えばあの時既にここでこうなることは決まっていたのかもしれなかった。
スパイダスは強かった。ワイリーを倒したセイアでさえも苦戦し、ウィドのサポートがなければどうなっていたか判らない。
ワイリー自身が恐れた力だということが容易に納得出来る。その出来事がセイアとウィドの初めての出逢いであり、この闘いへの伏線だったのだ。
「あの時――いやあの時よりもずっと前から、この闘いは始まっていたということか」
「そういうことだ。もっと大きく云えばロックマンとワイリーとが闘いを始めたその時から、今ここでこうなることは決まっていた」
「疑問は解消された筈だ、小僧。そろそろ宴を始めよう」
「今宵は真ん丸のお月様が見守る最高の夜。きっと素晴らしいパーティーになるよ」
「――ッ・・!」
パチンと弾かれたイクセの指。反響の良いトレーニング・ルームに木霊する乾いた音と共に、磔にされていたセイアの身体が不意に重力に引かれた。
ウィドはイクセ等に注意を払いつつもセイアの元へと走った。ウィドの牽制は殆ど意味のないものだったが、イクセ達に攻撃の意思はないらしく、
アッサリとウィドが眼前を通ることを許してくれた。
「セイア、セイア!セイア、目を醒ませ!セイア!」
「くっ・・――・・つぅ・・」
二、三度身体を揺らすとセイアはすぐに目を開けた。いや既にボンヤリと意識を取り戻していたのだろう、
セイアは頭を片手で抑えながらにゆっくりと身体を起こした。未だに視界が安定しないらしくその目は歪められていたが、
一先ずのセイアの無事にウィドは敵前ということすら忘れてホッと胸を撫で下ろした。
「セイア・・」
「やあ、おはようセイア。疲れた身体に長い眠りは心地よかったかい?」
「ウィド・・どうして、ここに」
ブンブンと頭を振ったあと、セイアはウィドの肩に手を回した。急速に意識を繋げられて頭がハッキリとしないのかもしれない。
セイアの腕を掴んで彼を支えつつ、ウィドは答えた。それと共にレーザー銃を三体のリミテッド達へと向ける。
「お前を助けに来た。それだけだ」
「・・・ありがとう、ウィド。途中からある程度聞こえてたよ。ボクが倒したDr.ワイリーの・・遺産」
意識がハッキリしたらしくウィドの手を離れたセイアの全身から、ぶわっと闘気ともいえるものが噴出するのをウィドは確かに感じた。
それはイクセに対する怒りなのか、それとも兄を殺したDr.ワイリーの置きみやげに対する憎しみなのか。
どちらにしても今まで以上に凄まじい闘気だということは、傍にいるウィドには肌で感じられた。泣いても笑っても決戦の時はきたのだ。
「・・へえ、この間校庭で逢った時の甘ちゃんとは一味違うということか」
同じように三つの闘気・・いや殺気が飛んでくる。だがレイの評した通りにセイアの闘気は前以上に凄まじい。
この三人を前にしても竦まないセイアの視線に、イクスは意外そうに呟いた。
「成る程。君もロックマンの一人。この僅かな時間で大きく成長したのか」
「けど、ボク達には敵わない」
「・・!」
ウィドはまるで強風に吹き飛ばされそうな錯覚を覚えた。一際大きな殺気が飛んできて、それだけで押し潰されそうになったからだ。
その殺気を放つのは中心のイクセだ。イクセと対峙するのは今日で二度目だが、闘う意思のなかったあの時とは比べ物にならない程の殺気を感じる。
成る程セイアが手玉に取られてしまうわけだと、ウィドは笑い出しそうになる膝を必死で抑えながらに思った。
四つの闘気がその場で拮抗する。ほんのちょっとのきっかけさえ与えればすぐにでも爆発しそうな状況で、ウィドはようやく自分が呆然としていることに気が付いた。
ウィドは科学者だ。確かにレーザー銃の腕には自信があり、
それでセイアを助けたことも数回程あるが、特A級を軽く越えるだろうレベルを持つ四人の前では戦闘力の低さを実感せざるをえない。
それでもウィドは震える腕に気合を込めなおし、レーザー銃を向け直した。気持ちの面で負けていては勝負は闘う前から決している。
いつか誰かがそう云っていた。
「ウィド、下がれ」
「セイア・・」
それはいつものセイアの声だった。しかし逆らえない。有無を云わさぬ何かがそこにはあった。
イクセ等の宿主だっただけのことはあるというのか、それともこれがウィドの知らない戦闘者としてのセイアなのか。
その答えがどちらだったとしても、気が付けばウィドはセイアの云う通りに引き下がっていた。
そしてウィドが射程外に出たことを確認するやいなや、セイアはゼット・セイバーの刃を具現化させた。
それに伴ってイクセ達の闘気も更に威圧感を増す。そして燃え上がる殺気の中で彼等は笑んだ。
「これで心置きなく闘えるか?」
「ウィド君――足手纏い――も消えたことだしな」
「じゃあ、君がこの短期間でどれだけ強くなったか見せて貰うよ!」
「イクセ!」
そして誰が止める間もなく闘いが始まった。
三体のリミテッドが瞬時に三方向へと散開する。セイアは一瞬戸惑ったが、すぐにダッシュで前方へと跳んだ。
そしてセイアが体制を立て直すよりも前に頭上からのレイの剣撃がセイアを襲う。が、紙一重で避けていた。
床に手をつくことでダッシュを無理矢理に停止させたセイアは、すぐにその軸腕を中心に身体を翻し、レイの頬を蹴り飛ばす。
更に二撃目の蹴りをレイの胴に叩き込み、それを足場にして更に跳ぶ。
後方へと持っていかれる途中、空円舞を使い直角の軌道を以て上空へとセイアは飛翔した。
「いい動きだ。だが、空円舞と飛燕脚は同時使用出来まい?」
「イクス!」
空中へと上昇を続けるセイア。それを狙ったのはイクスだった。
地上からタップリとエネルギーを込めたバスターほこちらに向けている。
悔しいがイクスの云うとおり一度空円舞を使ってしまっては更に姿勢移動をすることは不可能だ。
セイアの上昇エネルギーが尽き、ピタリと空中で静止した瞬間にイクスのバスターが爆ぜた。
セイア自身のフルチャージとほぼ遜色ない巨大なエネルギーが一片の狂いもなくセイアを目指す。
目と鼻の先になったエネルギー弾!イクスはクリーンヒットを確信し、ニヤリと口もとに笑みを浮かべた。だが!
「おぉぉぉ!」
「なにっ・・!」
バスターは直撃した。そのエネルギー量は辺りに耳をつんざく程の爆風を残した程だ。
が、その爆風の中から姿を現わしたセイアは無傷だった。いや、無傷とは違う。
バスターへと転換した右手から氷の盾が発生しているのだ。ピキピキと音を立ててヒビを入れる氷の盾に目もくれず、
セイアは着地すると共にイクスの懐まで飛び込んだ!
「フロスト・シールドか!だが!」
しかしイクスも驚愕に躍らされていたわけではない。二発目のチャージ・ショットを既にその腕に込め、
真っ向から向かってくるセイアへと放っていたのだ。
セイアは再びフロスト・シールドによって閃光を受け止める。が、二発のチャージ・ショットを受け止められる程その氷は強固ではない。
バラバラと辺りへ四散していくフロスト・シールド。今からでは武装の転換に隙が出来ると踏んだイクスは、もう一発バスターを放とうと構える。
が、その胴に今度は強烈な回転エネルギーと共に突起が捻り込まれた。高音を発する回転力の正体は、ドリルだった。
「喰らえっ!」
「くっ・・!トルネード・ファング・・!」
既にセイアはフロスト・シールドの下にトルネード・ファングを潜ませていたのだ。
ギリギリと胴体へ侵食してくるドリルを止めることも出来ず、かといってセイアの左手に宿った炎を消すことも出来ず、
イクスはそのまま顎先に強烈なアッパー・カットを叩き込まれた。巨大なセイアの腕力に押されて、イクスはドリルを引き抜かれると共に空へと舞った。
その隙にセイアへと斬り掛かろうと飛び込んできたレイも、
セイアが右腕から射出したトルネード・ファングを受けた後に波動拳で追撃をされ、イクスと同じく後方へと吹っ飛んでいった。
「小僧・・!」
呻くレイの言葉も無視し、セイアはすぐに気配を探った。イクスとレイの戦闘力は見る限りそれ程脅威ではない。
だが一番の問題は奴なのだ。そう、三人の中で最も強力であろうイクセだ。あの電脳空間内での闘いの時のことを考えると、最大の脅威はイクセただ一人。
「どこだ・・イクセ」
「ここだよ」
「っ!?」
何が起こったのかセイアには判らない。気が付いた時、既に自分の身体が壁に減り込んでいたということだけしか、彼には知覚することが出来なかった。
イクセは笑っていた。今までセイアが立っていただろう場所で。奴は、セイアの背後から攻撃を仕掛けてきたのだ。
背後――ならいつ背後に回られたのか。常に背後にも注意を怠らなかった筈だというのに。
いや、少なくともレイを吹き飛ばした瞬間背後には誰もいなかった筈だ。つまり奴はレイを捌き、イクセの姿を捜した半瞬の中で自分の後ろに回ってきたことになる。
「くっ・・・っ」
「ほら早く起き上がってきなよ。まさか優しく叩いただけでギブアップなんてことはないよね、セイア?
強くなったんでしょう。その力を見せてよ」
ソウル・ボディやダーク・ホールド等という小細工では決してない。奴は純粋なスピードで背後に回ってきたのだ。
それは奴の口ぶりから察せられる。奴の性格上何か小細工をすれば糞真面目に解説を寄越す筈なのだから。
セイアはバラッと崩れた壁によって地面に放り出された。なんとか手をついて持ち直すが、イクセの元には既にイクスとレイが戻ってきているのが見える。
セイアは戦慄した。やはり奴等は強い。強すぎる。電脳空間内でイクセに勝てたのは、クロス・アーマーのお蔭に過ぎなかったのだ。
次に三対一で攻められれば防ぐ手立てはない。その気になればイクセはいつでもセイアの首を刎ねることが出来るのだ。
「イクスとレイを捌いていたらイクセを躱しきれない・・。どうすれば・・」
「驚いた。まさか俺とレイを同時に捌くなんて離れ業をやってのけるなんてな。君は強くなった、セイア」
「だが小僧。調子に乗るなよ」
イクスのバスターとレイのセイバーがセイアを粉砕しようと再び向けられる。
セイアはくっと息を飲みながらに思考した。奴等全員を一気にの捌ききる為に必要な技は、特殊武器はなんだ。
考えろ。考えろ。考えろ。よく考えれば必ず何か手がある筈だ。何か。
「イクス兄さん、レイ兄さん!」
が、セイアの思考とイクスとレイの闘気を止めたのは意外にもイクセの声だった。
突然呼ばれたことに驚く二人をよそに、イクセはつかつかと数歩前に出た。
セイアとイクセの視線がぶつかり合う。こうしているとまるで内側全てを見透かされたような可笑しな気分になってくる。
そして同時に言い様のない嫌悪感が走る。やはりイクセの云うとおり、人――セイアはレプリロイドだが――は自分を見ると不愉快になる・・のだろうか。
「ふふん、セイア。強くなったのはいいけど、やっぱり三人同時に相手にするのは君でも不可能みたいだね」
「・・その気になれば一人でも充分みたいな云い方だな」
「そういったつもりはないんだけど、不愉快にさせたなら謝るよ。っと、ここで一つ提案があるんだ」
「提案?」
「そう。ねえ兄さん達、ボクにセイアと一対一で闘わせて貰えないかな?」
視線を向けられた二人は顔を見合わせたか、拒否の意思はないらしかった。
「好きにしろ。どうせ結果は変わらない」
「ただし、俺達にも暇つぶしさせて貰うよ」
「ふふ、こっちの方は承諾したみたいだね。君はどうだい、セイア?」
再び視線がセイアへと向く。その視線から提案の意味を見出せないセイアは再び身構えた。
相変わらず人を小馬鹿にしたように笑うイクセは構えすら取らない。それが気に入らなくて、セイアは思わず声を荒らげた。
「相手が貴様一人だろうがどうでもいい!ボクと闘いたいんだろ、早くかかってきたらどうだ!?」
「全く君って人はどうしていつもいつもこう興奮するのかな。まあ当然だろうね。ボクが君を見て滑稽だと思うように、君もボクを見て不愉快になってる」
「だ、黙れ!!」
「ふふ。サシの勝負の始まりだ。全力でかかっておいでよ、宿主!」
セイアの放った蒼と紅のチャージ・ショットは反対側から放たれた全く同出力のエネルギーによって相殺された。
それが弾けるとほぼ同時に真っ向から突っ込んでいく両者。セイアのゼット・セイバーとイクセのサーベルが凄まじい余波を辺りに吐き散らしながらに激突した。
その余波はトレーニングルームの防護ガラスに風圧だけでヒビを入れる程だ。
隅っこでことの顛末を見届けていくウィドは、危うくそれだけで吹き飛ばされてしまいになった。
「イクセ・・!」
「楽しいよセイア。君とこうして闘っている時だけ、ボクはボク自身の存在意義を見出すことが出来るんだ」
セイアの左の拳とイクセの右の拳がぶつかりあう。ガン、ガン、ガン。三回拳がぶつかった次の瞬間には、
セイアとイクセの両者の膝が凄まじい金属音を響かせながら拮抗していた。その威力においては両者ともにほぼ同等だったが、
一手イクセの方が素早かった。イクセの強烈なブロウを頬に受けて、セイアはロケットのような衝撃と共に後方へと吹っ飛んだ。
クルリと空中で姿勢を整え、後方に壁に着地する。
つーっと口の端からオイルが垂れてくるのが判った。それをグイッと拭い取ったセイアは、必要以上に息を荒らげていく自分に気が付いた。
体力を消耗しているわけではない。単に興奮しているに過ぎないのだ。殴り飛ばされたことでほんの少し平静を取り戻したセイアは、
今の自分の状況にようやく気が付いた。
「君はイレギュラー・ハンターとしてボクと闘っているかもしれない。もしかしたら感情だけで闘っているかもしれない。
或いはワイリーの遺産であるボクを倒す為かもしれない。どれにせよ君は大義名分を持っている。
感情的になるのはボクが君と同じ姿、同じ声をしているからに過ぎないよ」
「・・何の話しだ。大体、貴様等の本当の目的は一体なんなんだ」
記憶の底に眠る長い金の髪の青年に叱り飛ばされた気がして、セイアの呼吸が鎮まりを見せ始めた。
それに伴って言動も少しずつ感情的なものから分析的なものへと変わっていく。
セイアのその様子に感心したのか驚いたのか、イクセはパチパチと瞬きをしたあと、ニコリと笑って続けた。
「へぇ、少しは真面な会話が出来るようになったみたいだね。・・なんて軽口を叩くとまた君がお話をしてくれなくなっちゃうから、話を続けようか」
イクセの姿が消えた。それに続いてセイアもその場から瞬発的に跳ぶ。
目にも止まらぬ早さで振り下ろされたイクセのサーベルが裂いたのはセイアの残像だけだった。
瞬時に真後ろに回り込んだセイアは超至近距離で特大のチャージ・ショットを放つが、それを貫いたのもイクセの残像のみ。
すぐに頭上を見上げたセイアは空中で波動拳を放とうとエネルギーを集中させるイクセの姿に、
渾身の力を込めた神龍拳を打ち上げた!
「君はボク達の目的を知りたいらしいね。それについて教えて上げようか」
「くっ・・・!」
神龍拳の出よりも波動拳の方が半瞬早かった。波動拳によって地面へと逆戻りさせられたセイアは再び跳躍し、イクセの懐へと飛び込む。
その場で拳と蹴りの応酬が巻き起こった。もはやA級の凄腕ハンターですら捉えられない程のスピード。
端から見ればほぼ互角の打ち合いに見えることだろう。けれど実際にはイクセの方が数段素早かった。
「ボク達の・・デス・リミテッドの開発コンセプトは君も知っての通りエックスの抹殺だ。
ワイリーはデス・リミテッドを自分に使用して更に強力な力を得ようと考えていた。
けど、目的は既に達されている。エックスは既にこの世にいないんだから」
「なら何故貴様等はまだこうして存在しているんだ!それともワイリーを倒したボクに復讐したいって云うのか!?」
「半分正解で半分は間違い。元来リミテッドに個々の意思はない。ボクがこうして話しているのも君という宿主が元になっているからに過ぎない。
じゃあボク達の目的は一体何なのか。答えを云っちゃうとそんなものは・・ない」
「無い・・だと・・・・ぐあっ!!」
遂にセイアのラッシュの勢いが競り負けた。イクセの強烈なパンチ・ラッシュを全身に叩き込まれたセイアは地面に転がった。
所々のアーマーが割れ、破片が飛び散る。破壊された箇所がバチバチとスパークを上げる様は、最強のハンターとしては何と情けないことだろう。
イクセはゆっくりとセイアへと歩み寄ってきた。ここでバスターを放てば勝負がつこうものを、彼はそれをせずに話を続ける。
「そう。無いんだ。ボク達に確固たる目的なんて、ね。強いて言うなら君と闘うことかな」
「ボクと闘うことが目的って・・どういうことだ」
「君が強いからさ。ボクの基本人格は君を元にしているから、必然的にボク達は強い者を求める。闘いたいんだよ、凄くね」
「ボクが、ボクが闘いを求めているとでも云うのか!?」
立ち上がり、拳を捻り込むセイア。だがその拳はいとも簡単に受け止められた。
ギリッとアーマーが軋むほどの握力が込められる。そのまま腕を砕かれてしまうような錯覚を覚え、セイアは思わず呻いた。
「ぐっ・・・ぁっ」
「君だって気付いてる筈だ。イレギュラー・ハンターを続けていく内に、リミート・レプリロイドと闘ううちに。そしてワイリーを倒し。
闘うために少しずつ少しずつ理由を捜し始める。飛び散る血だけを見たくなってくるのさ」
「ボクが・・戦闘狂だって・・云うのか」
「別に恥ずべきことじゃあないよ。闘いの中で高揚を覚えるのは戦闘者の特徴だからね。君のゼロ兄さんだって立派な戦闘狂だった。
そしてそんな君から生まれたボク達も、闘いを生きがいにしている」
戦闘狂――そう云われて初めて、闘いの中で高揚を覚え始めていた自分を自覚する。
強い敵と闘う度に。自分が強くなっていく度に。どうしようもない高揚を知る自分。
ハンターとして。エックスとゼロの弟として。イレギュラーを、リミート・レプリロイドを倒してきた。
そして今、目の前のデス・リミテッド達を倒そうとしている。それは何故だ。ワイリーの遺産を倒す為か、相手がイレギュラーだからか。
違う――自分は、自分はリミテッド達との闘いを楽しんで・・いるのか?
「別にエックスもゼロもワイリーも、何もかももうどうでもいいんだよ。こうして君と対峙する瞬間がボクにとって最も大切なんだ。
どんどん強くなる君と闘って、闘って、闘って。君を侵食し始めている腐食部分こそボク自身なのさ!」
「腐食部分・・!?」
「君だってとっくに理解している筈だよ、セイア。レプリロイドのためとか、
人間のためとか、そうやって理由をつけて闘う内に心のどこかが確実に腐り始めていることを。
もう素直になったらどうだい。ボクは今まで君が闘ってきた者達の中で最も強い。君の欲求を最も満たすことは出来るのは、このボクだ」
自分の欲求。それは強い者と闘うことなのか。それとも、本当にエックスとゼロの意思をつぐことなのか。
その答えは――ほんの昨日までなら胸を張って答えられただろう答えは、今となっては口を動かしてはくれない。
迷っているのだ。目の前の自分と同じ顔のイレギュラーに核心をつかれ、セイア自身が把握していない自分を曝け出され、困惑しているのだ。
セイアの拳を押し込む力が弱まった。それを見計らったようにイクセのバスターがセイアの胴に叩き付けられ、彼の身体を数m吹き飛ばし、
床へと転がせる。つかつかと歩み寄ってくるイクセの姿を見据えつつも、セイアは立ち上がることが出来なかった。
「頑固者だな、君は。それとも自分で思ってたほど自分が綺麗な存在じゃなくて困惑しているのかな。
どっちにしても手加減はしないけどね。どうせボクが本気で君を殺そうとすれば、君は真の姿を曝け出す」
「あ・・・あ・・ぁ」
立ち上がることも、バスターを向けることも出来ないまま、セイアは身を退け始めてしまった。
さっきまで全身を包んでいた闘気も、鋭く射抜く眼光もそこにはない。ただ認めたくないものを眼前に突き付けられたちっぽけな少年が、
その事実に脅えているだけだった。セイアにもう戦意はない。それを判った上で、イクセはサーベルを喉元へと添えた。
もう逃げられない。イクセがほんの少しサーベルを押し込むだけで、自分は死ぬのだ。
こんな状況になっても殺意も戦意も沸いてこない。戦闘狂ならば、こんな時どうするのだろう。ついこの前の自分なら、立ち上がって闘っていた筈だ。
自分は戦闘狂でもなければ、盲目的に自分の意思を信じる強者でもない。それを理解したとき、イクセはサーベルを振りかぶっていた。
「安心しなよ。すぐには殺さない。もっともっと君の真の強さを見せてもらうよ。・・どんな手を使ってでもね」
「――・・!」
「さぁ見せてみろ。最強の戦闘狂の力を!」
が、イクセの斬撃は中断された。中断せざるをえなかった。
イクセは振り向いた。自らの背から立ち昇る煙を見たあとに、それの原因となった人物を、銃口を見る。
ウィドだった。震える手でレーザー銃を握り締め、それでも強い瞳でこちらを見据えている。
突然の飛び入りに口の端をつり上げるイクセと、驚いたまま目を見開くセイア。ウィドが最初に呼んだ名は、情けない親友の名だった。
「セイア!!」
「・・・ウィ、ド」
「何をしているんだセイア。そんな奴の口車に乗って、それで戦意喪失か。よく思い出せ、お前はいつだってエックスとゼロの意思を継いで闘うと云っていた筈だ。
学校の友達が常に笑っていられる世界にしたいと云っていた筈だ。その言葉は嘘だったのか、ただの口先から出たポーズに過ぎなかったのか。答えろセイア!!」
その台詞に、セイアは頭をガンと殴りつけられた気がした。今まで光を失っていたセイアの瞳に、一瞬にして炎が舞い戻る。
セイアは立ち上がった。立ち上がると共に拳をイクセの頬に叩き付ける。そして怯んだ矢先に鳩尾に膝を入れ、屈んだ上に強力なチャージ・ショットを叩き付ける。
セイアの闘気が舞い戻っていた。さっきと同じ、いやそれ以上の闘気が。
対してイクセは怯んだ姿勢のまま顔を上げた。今までとは違う、狂気的な笑みがそこにあった。
「そうだ・・。ボクは、ボクはロックマン・エックスとゼロの弟だ。彼等の意思を継ぐ者だ。ボクには兄さん達に託された希望がある。
ボクは・・ボクは戦闘狂なんかじゃない。イレギュラー・ハンター・・ロックマン・セイヴァーだ!
そしてイクセ、お前は・・イレギュラーだ!」
「ふふふふふ、はははははは。あーっはっはっはっはっは」
エックスは死んだ。ゼロも、もはやセイアの目の前にはいない。
そうだ。地球を幾度となく護ってきた英雄はもういない。同時に自分を叱り付けてくれる者も、護ってくれる者も、不始末を拭ってくれる者もいない。
そして――自分の代わりに闘ってくれる人もいない。
エックスは死ぬ直前になんと云ったのだろう。セイアは燃え上がる戦意の中でも、薄らとそれを思い出す。
『お前は俺の弟だ』
それが絶対の言葉。ロックマン・エックスが。英雄が。何より兄が自分に向かって云った言葉。
それを思い出して、セイアはやっと理解した。イクセの言葉なんかより、余程盲目的に信じてきたのはいつだって兄の姿だった。
確かに云われてみればセイアは戦闘に身を置くことが多い。闘うことは嫌いではないし、もっと強くなりたいといつだって思う。
けれどそれは闘うために理由を捜しているのではない。エックスのように、ゼロのようになりたかったのだ。
既に皆からエックスとゼロを越えたと称賛されるセイアだが、自分ではそんなこと微塵も思ってはいない。
だから強くなりたかった。闘って闘って闘い抜いて、強くなりたかった。兄に追い付きたかった。
そう、イレギュラー・ハンターとして。イレギュラーを・・倒すために!
「あははは。まさかウィド君のそんな一言で闘志が蘇るなんて思ってもみなかったよ。そのまま大人しくしていれば楽に死ねたのにさ。
全く、君はいつもいつも邪魔ばかりしてくれるね、ウィド・ラグナーク。あの電脳世界での闘いの時もそうだった」
「貴様なんかにセイアをやらせてたまるか。セイアをここまで侮辱した罪は重いぞ」
「・・やっぱり君は邪魔者だ。その減らず口を、いい加減閉ざして上げるよ。
イクス兄さん、レイ兄さん。二人の暇つぶしは彼でいいかな?」
さっきまで一体どこにいたのか。イクセに名を呼ばれたイクセとレイは半瞬後にはウィドの背後に立っていた。
不意に現れた気配に振り返るウィド。すぐにレーザー銃を構えるが、イクスとレイはそれを見ても眉すら動かそうとしなかった。
「俺に異論はないな。レイはどうだ?」
「少々不満だが我慢してやろう。だがこの小僧を始末したらそっちに参加させて貰うぞ」
「はいはい。だけどボクも楽しみたいから、程々に焦らして上げてね」
とんでもないことをさらりと云ってのけ、イクセは再びセイアへとサーベルを向けた。
ウィドは一旦間合を取り、レーザー銃を構える。持っている武装はこれと、あとは懐に入っているビーム・メス程度だ。
どう考えても勝率は低い。が、もはや逃げ道はないのだ。
「ウィド!」
「おっと、君の相手はこのボクだよ。他人の心配していられるほど、余裕はないんじゃないかな」
「・・悔しいがそいつの云うとおりだ、セイア。コイツ等は俺が食い止める。お前はイクセを倒すことだけを考えろ」
「ほら。彼もそう云っていることだし、そろそろ第二ラウンドを始めようか。見せてよ、吹っ切れた君の力を!」
「くっ・・・!!」
そして再びセイアとイクセ、そしてウィドとイクスとレイの闘いが始まった。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
一方のハンターベースで、Dr.ゲイトは珍しく焦っていた。
他の隊員も同じように焦ってはいたが、事の重大さはゲイトが取り乱していることからも充分推測出来るだろう。
ともかくゲイトは焦っていた。セイアが行方不明になったこともあるが、それに続いてウィドまで姿を消してしまったからだ。
さっきまでベースの隅々までを捜したけれど、その姿はどこにもなかった。
喫茶室にも、オペレータルームにも、セイアの自室にも、総監室にも、談話室にもいない。
女性隊員に変態扱いされてまで女子トイレを捜索したが、彼の姿はどこにも見当たらなかった――というよりもそこで見つかることはそれはそれで問題だが――
結局焦りを残したままに研究室に戻ってきたゲイトは、奇妙なものを見つけた。
ウィドのモバイル端末だ。別にそれ自体には何の変哲もない端末だが、いつも彼はこれを持ち歩いている。
こんなところに置き去りにされているとは考えづらい。端末は電源が入りっぱなしで放置されていた。
彼の性格上有り得ない状態で置かれていた端末を、ゲイトは飛び込むようにして開き、そして焦りの上に驚愕を上乗せされた。
ディスプレイを開いた端末に表示されていたのは、メーラーだった。
送信者はイクセ。それはいうなれば脅迫状の類だった。
セイアを預かった。返して欲しくば旧ハンターベースまで来い。
そしてこれを最後の決戦としよう。要約すれば、こういった内容だ。
ゲイトは焦っていた。今の弱体化したイレギュラー・ハンターにセイア達の闘いに割って入れる程の実力者はいない。
だからといってゲイト自身にも彼等と闘う力はないだろう。ナイトメア・アーマーを使ったところで勝負は見えている。
ゲイトは考えた。考えたが、結論は出なかった。この状況を打破する考えは、天才と云われた彼ですら捻り出すことが出来なかった。
それでもふと考えたゲイトは、慌ててある物を捜した。が、それも無駄に終わった。
完成直前のクロス・アーマーのチップが消えていたのだ。恐らくウィドが持っていたのだろうが、
もしアレを使うようなことがあれば未だ不完全なアーマーはセイアの身体にも支障をきたすだろう。
もはや頼れるものはない。ガラにもなく勝ち目のない闘いに飛び込もうとすら考えたゲイトは、完全に手詰まりだった。
「なんてことだ。こんなことになるとは、やはりあの時セイアを向かわせるべきではなかったのか」
ゲイトの口から弱音が漏れたことをセイアが知れば、きっと飛び上がって驚くに違いない。
けれどそうなっても仕方がないのだ。ゲイトにはどうしようもなかったのだ。恐らくこのまま何も無ければ、ゲイトは闘いの場へと突っ込んでいったに違いない。
「こんなときに君達がいれば。エックス、ゼロ」
そんなゲイトの小さな願いも今となっては叶わない。
絶望的な感情に襲われ、ついに闘いの場へと向かおうと決意したゲイトを引き留めたのは、
意外にも突然ディスプレイに割り込んできた通信だった。
『君らしくもなく取り乱しているようですね、Dr.ゲイト』
「・・!き、君は」
特別セキュリティの厚いゲイトのメインコンピュータに苦もなく侵入した画面の向こうの科学者型レプリロイドは、
困惑するゲイトを見てそう云った。突然のショックでゲイトは驚いたが、そのお蔭でなんとか少し平静を取り戻すと、
ゲイトはディスプレイに向かってこう返した。
「・・『Dr.バーン』。君から連絡をよこすとは、全く予想外だね」
『なにせ非常事態ですからね』
「その様子では、ウィド君の端末のメールを読んだんだね。おおかたウィド君のメーラーに届いたメールは自分のところにも転送されるように仕組んでいたんだろう?」
『相変わらずあなたは勘がいいですね。その通りですが、今はそれよりあのリミテッド達への対処を考えましょう』
「君にしては一手遅かったね。もうセイアもウィド君もあっちで闘ってるよ。ボク達に出来ることはないんだ」
自分の口でそんな台詞を云うことに酷い嫌悪感を催しつつも、分析力の高いゲイトには紛れもない真実だった。
そしてゲイトがそう云った以上、その計算を疑うことはしないバーンは、それに対しては何も抗議をしないままに続けた。
『・・開発途中であった新アーマーは?』
「ウィド君が持っていってしまったよ。あのまま使えばセイアの身体にも異常が起きるというのに」
『ウィドが何か武器を持っていった様子は?』
「・・?いや、彼は自前のレーザー銃があるから、それ以外持っていった形跡はないよ」
『・・そうですか』
目に見えてバーンの顔が歪むんだのを、ゲイトは見逃さなかった。
「どうかしたのかい」
『気になることが一つ』
「気になること?」
『最近ウィドに変わった様子はありませんでしたか』
訊ねられ、ゲイトは顎に手を当てて思い返した。
ここ数日はウィドと研究室にこもっていたものだから、誰よりもウィドの様子を見ていた自信がある。
一日一日の記憶を遡り、注意深く分析していく。そしてその中からようやく共通点を見つけたゲイトは、半秒後にぽんと手を叩いた。
「そういえばしきりに右腕を抑えていたようだったよ。どうしたと聞いても、腕が疲れたとだけ云っていたけど」
『・・やはり』
「・・。やはり?今、やはりと云ったのかい?」
バーン自身も思わず漏らしてしまった言葉だったのだろう。一瞬しまったという顔をしたあと、彼は観念したように頷いた。
ゲイトと同等かそれ以上の科学力を持ち、冷静さも持ち合わせている彼にしては珍しい表情であったが故に、ゲイトも思わず眉をひそめる。
敢えて何も云わず、バーンが口を開くのをゲイトは待った。
『Dr.ゲイト。もしやとは思いますが、ウィドはセイヴァー君と共に出撃していたりは・・』
「残念だけどしているよ。彼のスナイプ能力はかなりのものだからね。セイアもそれで幾度か助けられたと云っていた」
『あのレーザー銃を使ったのですね』
「ウィド君がいつも持っているレーザー・ガンのことかい?アレはよく整備されていて、あのサイズでは考えられない程の出力を持ち合わせ・・」
そこまでいってゲイトはハッとした。あのレーザー銃はウィド自身が改造し、出力やら速射性やらを向上させたと聞いているが、
アレは元々人間用に出来ている武装であり、並の人間に扱えるギリギリのレベルを保たれたものだ。
ウィドは人間だ。今まで共に研究をしていたり、セイアと肩を並べてリミート・レプリロイド達と闘っていたことで失念していたが、
彼は間違いなく人間なのだ。彼の生立ちは遺伝子改造型人間だが、頭脳を除いて身体能力は抜群の運動神経以外並の人間と大差ないのだ。
そんな彼が人間が扱えるギリギリの武装を更に出力を上げて使用していたということは、つまり・・。
『忠告はしました。ウィドの身体強度ではあのレーザー銃を使い続けることは出来ないと。しかし、あの子は忠告を守らなかったようですね』
「Dr.バーン。もし、このままウィド君が決戦の中でレーザー銃を乱発した場合、一体・・?」
訊ねるまでもなかった。が、ゲイトは半ば縋っていたのかもしれなかった。
勝てる筈のない敵にセイアを奪われ、たった一人でウィドを向かわせ、その他のハンターは全く役立たず。
自分が行っても恐らく、いや確実になんの役にも立たないだろうこの状況で、ほんの少しでも救いを求めてしまう。
ゲイトはバーンにこう云って欲しかったのかもしれない。ウィドは大丈夫だ。セイアは無事に帰ってくる・・と。
だがゲイトが珍しく見せた弱音とは裏腹に現実とは無情なものである。バーンは俯き、フルフルと首を振った。
『今のままでも危険領域を出ないのです。もし、今回の敵を相手に最大出力の攻撃を加えた場合・・・』
「・・・・」
『最悪はウィド自身の身体が破壊され、再起不能になるでしょう。スナイパーとしても研究者としても。そして、人間としても――』
「――・・・!!」
ゲイトは声にならない声を上げながら目の前のコンパネに両拳を当てた。
コンパネは破壊され、バチバチとショートする回路が露出する。元々それ程頑丈に出来ていないゲイトの拳からもつっとオイルが零れ落ちた。
これがかつてナイトメア事件を引き起こした張本人とは思えない程に無様な姿を晒す彼に、バーンは何も云わなかった。いや、云えなかった。
彼がどれ程自らの息子に愛情を注いでいるか、一番よく知っているのはバーンかもしれなかったからだ。
知り合ったその日から、彼が自分の息子達に注ぐ愛情を知らずにはいられなかった。今それはロックマン・セイヴァーに、
そしてバーンの息子であるウィドをも対象として注がれていることも知っている。
『Dr.ゲイト・・・』
「なんてことだ・・!ボク達は彼等を助けることも出来ないだなんて!もう耐えきれない、ボクは・・!」
『Dr.ゲイト!』
条件は同じだというのに、冷静に物事を見詰めてしまう自分を、バーンは内心で嘲笑った。
バーンもゲイトと同じように息子達の為に感情を爆発させられたらどれだけいいのだろう。
大切な息子の為に無茶を云うことの出来るゲイトがいつも羨ましかった。
もしかしたらバーンはセイアのこともウィドのことも作品の一つとしか捉えていないのかもしれない――気づき始めてしまった自らの醜悪な本性を認めつつも、
バーンは冷静さを失うゲイトに声を荒らげた。
この科学者は、親友は優しい男だ。対して自分は何故これ程までに冷たいのだろう。
技術を互角以上に競いつつも決して越えることも出来ない壁を感じるバーンは、それから目を背けるようにゲイトを叱咤した。
『他のハンター隊員を向かわせることも出来ない者達を相手に、君は何をしようというのですか。
あなたがしようとしていることは絶望に耐えかねた自殺行為に過ぎません。彼等が無事に帰ってきたときのことを、あなたは考えていますか』
「・・・!」
バーンの口ぶりは酷く冷静であり、同時に冷めていたが、今のゲイトにはそれすら究極の正論に聞こえてしまう。
ゲイトはギリッと拳を握り締めたまま目を背けた。自分の無力さから、この絶望的な状況から逃げ出すように。
『リミテッド達を相手に通常のハンター隊員では死に行くだけのようなものです。そして今のあなたにはクロス・アーマーもない。
勿論私にもあなたにも彼等を止める力はない。ならば、信じて待つしかありません』
「・・信じて、待つ・・」
『えぇ。信じましょう。ロックマン・セイヴァーとウィドを』
言い放ったバーンをよそに、ゲイトはもう一度コンパネを叩いた。
今度こそ止めを刺されたコンパネは完全に破壊されて、ディスプレイに映されていたバーンの顔も消え去る。通信も途絶えてしまったようだった。
「――エックス、ゼロ・・」
ゲイトは生まれて初めて祈った。神にではなく、かつての英雄達に――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「くっ・・!」
「遅いな。やはり人間風情ではこれが限界か」
瞬時に二連射された光の線は、双方二つの目標に到達する寸前にそれを失い、虚しく虚空を裂く。
完全に捉えた筈の狙撃なのだが、彼等はそんな常識など知ったことではないと云うように、
半瞬後にはウィドの懐まで飛び込んできていた。
「違うよ。単にこれが俺達と彼の決定的差・・ってことさ!」
「ちっ!」
しかしウィドの反応もそれに負けじと素早い。もう片手に握り締めていたビーム・メスの刃で、捻り込まれるイクスの拳を受ける。
が、押し切られた。圧倒的な衝撃エネルギーを加えられたウィドはそのままロケットのような勢いで後方へと吹き飛び、
まだ奇跡的に無事だったトレーニングルームの壁へと叩き付けられる。
呼吸が止まる程の鋭い痛み。ずるりと床に滑り落ち、膝をついたウィドだったが、骨折がないことを幸いとしながら足腰に力を込めた。
ここで例え一秒でも倒れているわけにはいかないのだ。奴等相手に、その一瞬の隙でさえ命取りとなる。
「・・一瞬は早く俺の拳をビーム・メスで受け止め、ダメージ覚悟で受け止めたのか?」
「いや、それだけじゃあない。自ら後ろに跳んで衝撃を大きく半減したようだ。この小僧、動きだけはなかなかのものだ」
「勝手な・・勝手なことを云いやがって」
ペッと口の中に溜まったものを吐き出す。血とも唾液とも云えないものがべちょっと床に粘り付く。
多分喉の粘膜まで吐き出してしまったんだろうという錯覚に陥りつつも、ウィドはそれに気を配ることすら許されない。
再びレーザー銃を正面に構え、もう片手でビーム・メスを握り締める。このまま二対一で闘った場合、勝率はほぼ零に等しいだろう。
それでもこうして構えることしか出来ないのだ。死ぬまでの時間を伸す為なのか、それとも零に等しい勝率に期待しているのか。
それはウィド自身にも判らないし、そんなことを考えている余裕もない。けれど、一つだけ確かなことがあった。
「ただの人間の少年だと思っていたけど、この暇つぶしはかなり楽しめそうだよレイ」
「お前も相変わらず余興好きだな。確かに動きがいいことは認めるが、この程度の小僧を殺すことなど造作もないこと」
「君もよく云うよレイ。だったら最初の一撃で首を斬ってしまえば良かったのに」
「ふんっ・・」
以前セイアからリミテッドのデータを採取し、過去のデータベースにアクセスしたとき、
リミテッド体或いはリミート・レプリロイドについての考察が幾つかあったことを思い出す。
その大半はリミテッドによるパワーアップ率や変化等を示した文章であり、ウィドにとってどうでもいいことであったが、
その中でも彼の目を引くものが一つだけあった。そう、奴等の弱点だ。
セイアにも既に伝えているが、奴等リミテッド体の動力源は全て体内のリミテッドだ。
セイアに取り付いたものと同じデス・リミテッドの塊を中心にその全身を形成している故、それを破壊すればその形を留めることが出来ずに崩壊する。
「俺は貴様等の玩具ではない・・!」
ウィドは思う。奴等が自分との闘いを長引かせ、楽しんでいるうちが最大のチャンスであると。
スパイダス・リミテッドとの闘いから、このレーザー銃の出力で充分デス・リミテッドを破壊することが可能だということが判っている。
奴等の弱点は頭部だ。頭部にこのレーザーを一撃でも加えることが出来れば・・ウィドの勝ちだ。
「いいだろう、イクス。お前の余興にもう少し付き合ってやろう。しかし飽きたら即座に殺すぞ」
「はいはい、判ってますよ。さて準備はいいかい、ウィド君。次はもう少し優しくいくから安心するといい」
「そうやって遊んでいられる内が華だな、イクス・・レイ!」
端から見れば完全に負け惜しみの一言を、ウィドは躊躇いもなく吐く。普段の彼ならばそんな負け犬じみた言葉は吐かないだろう。
これは計算だった。敢えて負け惜しみの言葉を放つことで、相手に優越感を与え、遊びの範囲を伸すことでチャンスを待つのだ。
たった一発――いや二発だろうか――奴等の頭部にレーザーを撃ち込むことが出来れば・・。
そのチャンスまでなんとしてでも生き延びなければ。
ウィドは部屋の反対側で闘っているセイアとイクセの方をチラリと見た。
――セイア・・頼んだぞ。
「余所見をしていて次が躱せるかな、ウィド君!」
イクスの声にハッとしたウィドは、直ぐ様身を躱した。イクスのチャージ・ショットとレイの電刃零が同時にウィドの足元を掘り返す。
その光景に内心で肝を冷やすが、着地までの僅かな時間までをも奴等は許さない。空中からのレイの踵落しを受け、ウィドは地面に激突した。
いや、直前でバック転によって衝撃を殺し、受け身を取っていた。だが再び足が地面につく前にイクスの肘打ちを腹部に押し込まれ、
ウィドは溜まらずに腹部を抑えて踞った。
「っ・・くっ・・・・・!」
人間というものは脆いものだとウィドは思う。これがセイアならばどうということはない衝撃だろうに、人間であるウィドは視界がぶれ始めている。
顎先を蹴り上げられ、仰向けになって床を滑る。安定感が殆どない身体を起こすが、軽い脳震盪を起こしているのか上手く立ち上がれない。
セイアとイクセの闘いがふとぶれた視界に入る。いい勝負だ。いや、いい勝負というよりもどんどんセイアの力が増しているように見える。
もしかしたらまだセイアの体内にリミテッドが残っているのかもしれない。だとしたら、このままでもイクセに勝てるだろう。
その一方で自分のこの様はなんだ。弱点を知っていてもそれを突くことも出来ない、弱い自分。
相手がリミテッド体という強力な相手だからという言い訳は通用しない。これは殺し合いなのだ。負けた者は死ぬしかない。
ランク分けされたトレーニングとは違うのだ。
「ほらほら、早く立ち上がりなよ。このまま君を蒸発させることも出来るんだぜ?」
「お前が強く殴りすぎた所為だ。このまま呼吸困難で死ぬかもしれんぞ」
相変わらず勝手なことを云う二人だ。ウィドは咽せる胸を押さえ込みつつ心の中で毒づいた。
本当に残酷で、勝手な二人・・二人・・・――二人?
「・・・?」
ようやく視界が安定し始めたというのに、ウィドは立ち上がることも忘れて目を擦った。
イクスとレイ。確かに二人だ。だが、今の一瞬チラリと三人目が見えたような気がしたのは錯覚なのだろうか。
イクセでもセイアでもない三人目。無論自分でもなければ、イクスとレイの姿がだぶっての幻覚でもない三人目の姿。
「アレは・・一体・・」
イクスとレイは気が付いていないようだ。ウィドはもう一度大きく咳き込んでから、涙で揺れる視界のままになんとか身体を持ち上げた。
もういない三人目。ほんの一瞬だけ、イクスとレイの頭上の壁に貼り付いていたような・・気がするのだが・・。
「お、立ったね。さあウィド君。こっちから攻めるのだけでは申しわけなくなってきた。次は君から撃ってくるといい」
「貴様・・!」
「撃てるチャンスがある内に撃った方がいい、小僧。バラバラになった後ではトリガーを引くことも出来ないのだからな」
「舐めやがって!」
腕を振り上げる様に二発!ウィドのレーザー銃が吠えた。狙うはイクスとレイの頭部。デス・リミテッド本体だ。
が、やはり当たらない。直撃する寸前で残像となった二人の姿を砕くだけで、奴等はまたウィドの視界の外まで瞬時に飛び出した。
ウィドはすぐに後ろへ跳んで壁に背をつけた。これなら正面と頭上からしか攻撃を加えられることはない。
ほんの少しでも動きを捉えられる可能性が高くなるからだ。
頭上と正面に向けてウィドは撃った。攻めてくるべく場所が二箇所しかない上、奴等の実力を考えればタイミングが速過ぎるということはない筈だ。
手応えは――ある。が、軽い。正面に現れたのはレイだ。
振り上げるレイのセイバーの龍炎刃がウィドを襲う!ウィドはもう片手のメスで燃え沸るセイバーを受け止めた!
「くうっ・・・!?」
「飛び上がれ。宇宙船のようにな」
セイバーが身体に食い込むことは阻止出来ても、レイの腕力を相殺することなど出来ない。
文字どおり宇宙船のような圧力で空へと放り出されたウィドは、なんとか空中姿勢を立て直しつつも思った。
――まずい。このままでは空中で待機しているだろうイクスに追い打ちをかけられて・・。
「・・・!?」
が、ウィドは追い打ちを喰らうことなく天井に着地――着天というべきか――した。
そのまま身体が落下する際に壁にメスを突き刺し、体制を維持する。打ち上げたレイ自身も意外だったのか、見下ろした彼の顔は珍しく驚いた風だった。
「どうした、何をしているイクス!冗談はやめて出てこい」
「・・何・・?」
「イクス!返事をしろ、イクス!」
レイは狼狽していた。冷静沈着な彼とは思えぬ口ぶりだが無理もないと云えるだろう。
ここにイクスがいなくなる要素など何も無いからだ。セイアはイクセと闘うことに夢中だし、ウィドがイクスを倒すことなどほぼ不可能だ。
更に本人の冗談でもないとすれば、それは有り得ないことであり、計算高い彼が驚いてしまうのも納得だ。
計算高い者故の脆さだ。百%と自分で計算したものが意外にも失敗したりすると、計算高い者は驚く程狼狽える。
レイも例外ではなかったらしい。ウィドを舐めきっているのか、はたまたイクスという存在が彼の中でそれ程までに大きいのか、
レイは頭上のウィドを放ってイクスの姿を捜し始めた。
「馬鹿な、どこへ行ったと云うのだ!?イクス!」
そしてウィドは見た。いや、見上げた。ポタリポタリと頭上から滑り落ちてくる何かの液体を。
血液か?いや、これはオイルだ。匂いと滑り方でよく判る。
「イクス・・・!」
ウィドは思わず叫んでしまった。別にレプリロイドがオイルを流すところを見るのが苦手なわけではない。
単に信じられない光景がそこにあったからだ。それを先に見つけてしまったウィドは、レイと同じように口をポカンと開けた。
それはイクスだった。天井に頭部をビーム・セイバーでくし刺しにされ、ぷらんぷらんと身体を揺らす・・イクス。
機能は完全に停止している。当たり前だろう。弱点である頭部を完膚無きまでに貫かれているのだから。
・・・やがてビーム・セイバーのエネルギーが消失し、ぼとりと力無くイクスが地面にばらまかれた。
「・・!い、イクス・・・」
レイは呆然と落下してきたイクスの亡骸を見詰めていた。ウィドもそれを呆然と見る。
一体、何が起こったのだろう――セイアと自分は少なくとも何もしていない筈だ。なら、一体誰がイクスを仕留めたのか。
「ま、まさか・・さっきの・・!!」
それしか考えられなかった。ぶれる視界の中で見た『三人目』。奴が、奴がイクスを仕留めたのだ。
馬鹿げた発想だが、これしか考えられなかった。自分とセイアの力を合計しても、今の一瞬でイクスを仕留めることなど出来はしない。
「だとしたら、今しかない!」
その『三人目』が仮に本当に存在しそれが味方だったとして――ウィドはそこで思考を切る。
壁に突き刺して身体を支えていたビーム・メスを引き抜き、自由落下に身を任せる。
レイが狼狽えている今が最大のチャンスなのだ。今の一瞬でレイの頭部を撃ち抜けば、ほぼ零の勝率が自分に傾いてくれる。
ウィドはレーザー銃に備えつけられたダイヤルを捻る。出力をノーマルからマキシマムに移行。
この一撃に全てをかけるのだ。失敗は・・許されない!
「レイ!!」
「小僧!貴様ぁぁぁ!!」
ウィドは着地すると同時に銃を構えた!が、憤慨したレイのセイバーの方が一手素早い!
奴の居合は超高速だ。ウィドが引き金を引くよりも先にウィドを斬るなど造作もないこと。しかしウィドは躊躇うことも、身を躱すこともなかった。
「ウィド!!」
蒼と紅の閃光が迸った。部屋の正反対から飛んできた超密度のエネルギー波は、今まさにウィドを斬り裂こうとするレイのセイバーを彼の腕ごと吹き飛ばす。
イクセと闘いながらもセイアはずっと見ていたのだ。ウィドとレイの闘いを。そして放った。ウィドがレイを倒すことの出来る一瞬を作るために!
「セイア、貴様!?」
「勝負だレイ!!」
『いいですか、ウィド。もしその銃を使い続けるようなことがあれば、人の身であるあなたの身体は・・・――』
いつか父に言付けられた場面を想う。だが、そんな父の言葉ですら今のウィドを止めることなど出来なかった。
心無しかスローモーションに見える世界の中で、ウィドの指がトリガーを引く。
銃口にほんの半瞬、光が収束し始めたと思うと、一瞬後に極太の光の線が空を駆けた。
「――・・・!」
ウィドとレイ、二人の声にならない悲鳴が大気を震わせる。そして同時にレイの頭部がレーザーによって撃ち抜かれた・・いや、吹き飛ばされた。
ウィドとレイ。二人の身体が殆ど同じタイミングで地面に崩れ落ちる。頭部を失ったレイは痙攣しながら。
放った右腕の骨の殆どが砕けたウィドは絶叫しながら。
「ぐっ・・あああぁぁあぁぁぁぁぁっ!!」
ウィドの悲痛な叫びが、旧ハンターベースのトレーニングルームに木霊するその様は、つい先日までの世界とは裏腹に地獄のようだった。
骨が弾け、皮膚が破裂した右腕から鮮血の噴水が勢いよく噴出し、破壊されたトレーニングルームの床を朱に染める。
それはまさに酷い光景だった。絶叫を続け、右腕から止めどなく流血するウィドの傍らには、頭部を貫かれたイクスと、頭そのものを失ったレイ。
ビクビクと未だ痙攣する二体のリミテッドの痛みすら代返するように、ウィドは肺が壊れてしまうのではないかと思う程に絶叫し続けた。
「ああぁあぁあぁぁぁっあぁっぁっぁ!!」
「ウィド!ウィドぉ!!」
セイアのウィドを呼ぶ声すら彼には届かない。やがて彼は握り締めていたビーム・メスを自分の右腕の傷口に押し付けた。
ジュゥゥと血液が蒸発する異臭を発しながら、その傷口はビーム・メスのエネルギーに焼かれる。そして出血が止まった。
想像を絶する痛みと高熱に苛まれたウィドは、その痛みのショック故か、それとももはや痛みすら感じないのか、はたまた声が枯れてしまったのか。
やがて口を閉じた。ごろりとセイアの方を向く首。そこに埋まっている眼球はヒクヒクと痙攣していて、口からは血とも唾液ともつかないものを垂れ流し、
それでも尚意識が繋がっているのか、彼は枯れきった声でセイアの名を呼んだのだった。
「セ・・・イ・・・ア」
「ウィド!今助け・・!」
「君の相手はこのボクだろう?間違えてもらっちゃあ困るね」
ウィドへと走り寄ろうとしたセイアに、イクセの強烈な飛びげりが決まる。その衝撃でウィドへの走路を断たれたセイアはくるくると空中で回転し、着地する。
その間にイクセはウィドを背にするように回り込んでいた。まるで苦しむウィドを助けられずに更に苦しむセイアを見て楽しむかのように。
「どけ・・イクセ」
「ふふふ。嫌だね」
「邪魔だ、どけぇ!!」
飛び込んだセイアのゼット・セイバーがイクセを真っ二つに斬り裂く。いや、寸前で全く同じものがそれを阻んでいた。
雄々しく猛るセイアのセイバーはイクセには届かない。さっきまでの差と較べれば確かに実力差は拮抗しつつあるが、
それでもイクセの方がほんの少し上回っている。容易く剣線を崩され、隙だらけとなった腹部にイクセのバスターが爆ぜた。
「くぅっ・・!!」
後方へと吹き飛ばされつつもセイアは諦めない。受け身を無視したフルムーンⅩ。
それがイクセの肩アーマーを吹き飛ばす。炸裂した――いや、炸裂していたのはセイアの方だ。
「――・・!?」
イクセと同じくセイアの肩アーマーも吹き飛んだ。いや、吹き飛んだなんて生優しいものではない。爆裂したのだ。
ウィル・レーザーの強烈な閃光がセイアの肩を掠め、それをこそぎ取っていた。アーマーを削られたイクセに対して、
肩を完全に破壊されたセイアの方がダメージは大きいのは当たり前だった。
よもやここまで読んでいるとは思わぬ切り返しに、セイアは思わず膝をつく。
ポタリポタリと肩から滑り落ちてくるオイルが床を濡らす。反対方向でウィドの流した鮮血が床を染める。
皮肉にも同じ右腕を破壊されたセイアとウィドの今の姿はなんと痛々しいことだろう。それでもイクセの辞書に容赦の文字は存在しえなかった。
「まさかイクス兄さんとレイ兄さんをウィド君が倒すなんて意外だったな。それとも何か奥の手を使ったのかな?
どっちにしろ・・・・君はこのまま死なせて上げないけれどね」
「やめ・・ろ・・」
イクセの感覚範囲にどうやら例の『三人目』は存在していなかったらしく、奴は二人をウィドが倒したと思い込んでいる。
勿論セイアも薄々その存在に気が付いていた。気が付いていたが、それが何かを考えよりも現状の方を優先したいのは明らかだった。
イクセの顔は歪んでいる。さっきまでの楽しそうな顔とは違う。まるで、まるでそう――Dr.ワイリーに兄を殺された瞬間のセイアのように。
奴は怒っているのだ。兄を殺されたことに。大切な兄を殺されたことに。セイアは、そんなイクセを見て思わずハッとしてしまった。
「痛いかい右腕が?でもね、そんなものじゃ済ませて上げない」
「ぐっ・・ああっ・・あ」
残酷無比な笑みと共に繰り出されるイクセの蹴りを受けても、もはや叫び声すら上げられないのか、ウィドは掠れた呻きを上げるだけだった。
既にボロボロだった全身に止めを差されたウィドの骨組は、ボキッと不気味な音を立てて断ち切られていく。
血を吐き、呻きを上げるウィド。セイアはそんなウィドを見詰めながら、ふらりと立ち上がった。もはや破壊された右肩のことなど気にならなかった。
「あはははははは。本当に、本当に計算外だった。君が、こんなひ弱な君が兄さん達を倒してしまうなんてねぇ!」
「やめろ・・・っ」
セイアのか細い制止の声を聞いたのか、それともウィドの姿をセイアに見せつける為か、イクセの動きがピタリと止まる。
そしてセイアに向かって笑った。冷たい笑みだった。きっと昨日までのセイアならそれだけで脅え、竦んでしまうかのような。
強烈なプレッシャーと威圧。そして、怒り――ぶらりと空を掻く右腕を抑えつつ、セイアはそれを認めた。
「「やめろ」だって?やめろって云ったのかい、セイア?」
「イ・・クセ!」
「ふふ、あはははは。コイツは大笑いだ。「やめろ」だって?君にそんなことが云えるのかい。君だってエックスを殺したワイリーに憤慨したくせに、
ボクにはやめろとほざくのか。正義の味方も所詮はエゴの塊だな!」
「っ・・!」
イクセの言葉は、間違ってなどいない。何故ならイクセの言葉は同時にセイアの迷いと直結するからだ。
一年前、セイアはワイリーを倒した。正義の為でも、ハンターの仕事の為でも、過去からの因縁の為でもない。
そうイクセの云うとおりエックスを殺したワイリーが憎かったからだ。全てを奴の所為にして、それを怒りと憎しみに任せて消し去りたかったからだ。
確かにイクセは敵だ。しかし同時に自分の分身でもある。兄を失った怒りと悲しみは、イクセとて同じこと――
セイアはここにきて迷ってしまった。ウィドを痛めつけるイクセの姿が完全に一年前の自分と重なってしまったからだ。
しかし気付きはしなかった。イクセを伐つことが出来なければ、セイアもまた一年前と同じ未熟者のままであるということを。
「よしよし良い子だ。この子を料理したらすぐに君も消して上げるよ。戦意喪失した君なんて、ただの鉄くず同然だからね」
「セ・・イア・・!ぐぁぁっ!!」
そしてまたイクセはウィドを痛めつけ始めた。砕けた右腕を足でふみつけ、蹴り上げ、ウィドの絶叫に笑みを浮かべる。
辺りにはウィドの流す鮮血が舞う。床を濡らし、壁を濡らし、イクセの頬を濡らす真っ赤な・・血。
それでもウィドはセイアを呼んでいた。それは助けを求める声でも、断末魔でもない。再びセイアの戦意を取り戻そうとする、必死の声だった。
「・・・・っ・・」
セイアは左手の拳を握り締めた。再びイクセに対しての怒りが込み上げてくる。
自分勝手な怒りだと、彼は自覚している。けれどそれを止められなかった。止めようともしなかった。
例え敵が自分と同じ立場にあったとしても・・敵は敵だ。奴はイレギュラーだ。セイアはハンターだ。
なら、倒すしかない。自分と同じだからといってイクセを哀れむことは・・許されないのだ!
「やめろ・・やめろ、イクセ!!」
セイアの左手のバスターが爆ぜた。蒼と紅の閃光は一つとなり、ウィドをけり続けるイクセの頭部を直撃し、その先の壁をも貫通して彼を外へと追いやる。
セイアは静かに歩み始めた。吹き飛んだイクセを無視し、もはや無残な姿へと変わったウィドを抱き起こす。
彼は、辛うじて生きていた。力のない手でセイアの左肩を掴むと、ウィドは血だらけの顔で笑った。
「馬鹿・・野郎・・。躊躇うなと、云っただろ・・う?」
「ウィド・・」
「躊躇うな・・。お前は、勝てる・・筈だ。アイツに・・」
一言話すことにも苦痛の表情を訴えるウィドの言葉は、最後までは紡がれなかった。それをイクセは許してくれなかったのだ。
ガラガラと瓦礫の中から姿を現わすイクセ。そしてウィドを静かに床に降ろし、ゼット・セイバーを構えるセイア。
ぼやけ始めている視界の中でウィドは思う。最後の決着が今まさにつこうとしている、と。
「セイ・・ア」
「・・判ってる」
「どうやらそんなに先に料理して欲しいみたいだね。なら、もう遠慮なく首を斬らせて貰うよセイア!!」
「イクセ、もう終わりにしよう。貴様を倒す!」
そしてセイアとイクセの姿がその瞬間、掻き消えた。
「セイアっ!!」
「イクセっ!!」
紅の鎧と翠の鎧が交差した。
そして静寂。
「・・・ぐあっ・・・!!」
先に伏したのはセイアの方だった。胸を袈裟切りにザックリと斬り裂かれ、真っ赤なオイルを噴出させながら。
膝をつき、掌をつく。もはや戦闘不能。振り返り、認めたイクセは・・立っていた。
「ふふふふ・・」
イクセは笑っていた。セイアを見下すように。ウィドを見下すように。自らの勝利を誇示するように。
「あーはっはっはっはっはっ!!!」
「・・・もう、終わりだ」
ウィドが呟いたその言葉は、己等の終焉に向けてなのか、彼の破滅に向けてか。
間もなくその言葉は確かに現実のものとなる。床に伏したセイアは、その終わりを確かに見た。
「ははは・・・あははははははは!!」
「・・・イク・・セ」
狂ったように笑うイクセの胴に、不意に斬り傷が走る。いや、胴が裂けた。
上半身と下半身に瞬時に両断されたイクセは、その笑い声を止めぬまま、やがて・・爆裂した。
彼に相応しい終わりだったのかもしれない。もしかしたらあっけない終わりだったのかもしれない。
けれどそれを意識することはセイアもウィドもしなかった。イクスが倒れ、レイが倒れ、イクセが倒れ。
勝つことはほぼ不可能だと云われていた最凶の三人は、伏したのだ。事実はたったそれだけで良かった。
「ウィド・・・っ」
ぼろりとヘルメットが崩れ落ちることも気にせず、セイアはよろよろとウィドの元へと向かう。
その無残な姿とは裏腹に、ウィドは笑っていた。きっとアドレナリンやらの分泌でもう痛みを感じていないのだろうと、セイアは中途な知識ながらも思う。
ウィドを抱き起こす。ウィドはもはや自分で立つことが出来ない程に傷ついていた。砕けた右腕も・・もはや直視出来ない程に・・。
「ウィド、腕が・・・」
「こんなもん、義手にでもなんでもすればいい・・さ。生きてれば・・な」
「うん・・帰ろう。ベースに」
「・・あぁ」
しかし運命というものはいつだって非常なものだ。セイアもウィドもいつもそれを知っていたつもりでいたけれど、今回ばかりはそれを実感せずにはいられなかった。
ゴォッと風が吹いた。死の匂いを、オイルの匂いを、錆びの匂いを含んだ奇怪な風だった。
「なにっ・・!?」
セイアの呻きに似た悲鳴が、もはや絶望を思わせる悲鳴が響く中で、それは止まることを知らずに始動する。
倒れ伏した三体のリミテッド体・・イクス、レイ、イクセの身体がビクビクと痙攣したかと思うと、そこから粘液をまき散らす不気味なユニットが離脱する。
デス・リミテッド本体だ。呆然とするセイアとウィドはそれを撃つことすら出来ずに見送った。もしかしたらこれが最大のミスだったのかもしれない。
「あ・・ぁぁ・・」
「馬鹿・・な・・」
あっと言う間に一箇所に集まった三体のデス・リミテッドは・・互いが互いに組み合わさり、グチャリと不気味な音を立てながら一つとなった。
吹き飛ばされそうな程の死の風が舞う。圧倒的なその存在に脅えるように、暗雲が空へと立ちこめ、強烈な雷を鳴らす。
あたかも空間自体がそれに圧迫されているようだった。セイアもウィドも、今回ばかりは動けない。セイアとウィド、そして空間自体が見守る中で、
それは静かに静かに形を成した。これから始まる地獄を現わすかのような、地獄の番犬・ケルベロス。それが奴の姿だった。
「・・・ウィド、クロス・アーマーのチップを渡せ」
「・・・し、しかしアレはまだ未完成で・・」
「早くっ!!」
セイアの剣幕は異常だった。逆らえば強引に奪われかねないと悟り、ウィドはなんとか持ち上げた左手で懐から一枚のチップを取り出す。
クロス・アーマー。かつてセイアが電脳世界内でイクセと対峙した際に装着した鎧であり、ウィドとゲイトが対リミテッド用に開発した究極のアーマー。
秘められし力は未知数。未完成の現状でセイアに与える負担もまた未知数だが、セイアは悟ったのかもしれない。それでもこれを使わなければならない、と。
ケルベロスは――いや、デス・リミテッドは動かずにそれを待っていた。まるで何をしても無駄だと云うように、その瞳には余裕すら伺える。
静かにチップを腕に埋めたセイアは、もはや闘うことなど不可能な身体で立ち上がり、振り向かぬままに呟いた。
「ウィド・・先に帰っててくれ」
「なっ・・くっ・・ば、馬鹿な、セイア・・何を云って・・」
「今の君を護りながら闘うなんてボクには出来ない!君がいれば邪魔になるんだ!!」
それは事実以外の何者でもない。ウィドは黙ってしまった。
セイアはふと剣幕を緩め、声を和らげた。しかし、彼は最後まで振り向かなかった。
「・・・ボクは必ず帰る。だから、待っててくれウィド」
「セイ・・ア。俺はまだ、お前と何もしちゃ・・いない。闘ってばかりで・・ロクな思い出もない。学校・・っだって、まだ一年・・ある。
お前は・・お前は、エックス・・とゼロの跡を継ぐんだろ・・?こんなところで、死ぬなんて・・許さん・・ぞ」
――本当は喋ることだって辛かった筈だ。それでも一生懸命なウィドの言葉が、セイアは嬉しかった。
振り返れなかった。振り返れば、泣いてしまいそうだった。逃げ出してしまいたくなりそうだった。弱音を吐くことになりそうだった。
だからセイアは振り返らなかった。だから見ることもなかった。ウィドの瞳に浮かんだ涙を・・セイアは知らなかった。
「・・判ったよ。続きは、また後で話そう」
セイアが自らのアーマーから剥がした転送装置によって、ウィドは光に包まれた。
ウィドが最後にまた何か云っていたようだったが、もう聞こえない。振り向きそうになる衝動を必死で抑えつつ、セイアは云った。
「・・さよなら・・ウィド」
『友達ヘノオ別レハ済ンダノカ』
見計らったように、デス・リミテッドが口を開いた。イクセ達とは全く違う、酷く機械的な冷たい声。
セイアはキッと声と同じく感情のない瞳を見詰める。セイアの翠の瞳の眼光を受けた三つの首、六つの瞳は全く動じなかった。
『ソウイキリタツ必要ハナイ。スグニ彼モオ前ト同ジトコロヘ行クノダカラ』
「黙れ!貴様は、貴様はボクがこの命に代えてもここで倒す!それが・・貴様を生み出したボクの責任だ!」
『面白イ。ソノ死ニ損ナイノ身体デドコマデ闘エルカ、見セテモラオウカ』
「舐めるなぁ・・!」
セイアが腕の中に埋めたクロス・アーマーのチップを今まさに発現させようとした瞬間、それを制止するものがあった。
「セイヴァー。お前のそれは勇気とは云えない。そんな闘い方はただの無謀だと、エックスに教わらなかったのか」
セイアもデス・リミテッドも全く予測していなかった乱入者。一本の翠の閃光としてそれは、セイアとデス・リミテッドの間に静かに降り立った。
「ふんっ。随分と醜悪な姿になったものだな」
程なくそれは人型を形成し、デス・リミテッドを一瞥するとこう云った。振り返ったそれとセイアの視線がぶつかる。
それは意外なことにセイアに似た姿をしていた。いや、寧ろエックスに似ていると云った方がいいのだろう。
ボディカラーは・・そう、イクセ達と同じ翠色。肩アーマーと胴体部分の境が存在しない奇妙な鎧が特徴的で、顔には電撃の刺青が走っている。
一瞬また新たなリミテッド体が誕生したのかと身構えたセイアだったが、それが自分に向けての敵意を持っていないことから、
少なくとも敵ではないことを理解した。
「き、君は・・!?」
「これならまだあの生意気な三体の時の方がマシだった」
狼狽えるセイアを余所に、それは再びデス・リミテッドを卑下する。
怒ることも哀しむこともないデス・リミテッドはそんな蔑みなど一切気にせず、自らの評価だけを口にした。
『貴様・・オリジナルイクス。リターン・イクスダナ。裏デ暗躍シテイタノハ貴様ダッタノカ』
「暗躍とはご挨拶だ。二人の坊やに三人でかかった卑怯者共に云われる筋合いはない。
それに私と同じ顔をした奴がいては目障りだったのでね」
そしてリターン・イクスと呼ばれた彼はポイッとセイアに何かを投げ渡した。慌ててそれを受け取ると、意外なことにそれはエックス・サーベルに違いなかった。
慌てて自分のバックパックに手を伸す。今までゼット・セイバーだけを使っていたので気が付かなかったが、確かにそこにエックス・サーベルはなかった。
「無断で借用したお前のサーベルだ。今更だが返そう」
「し、しかしどうしてこれを・・」
しかし相変わらずリターン・イクスはセイアに素性を話さない。必死にリターン・イクスに何かを云おうとするセイアを無視して、
またリターン・イクスはデス・リミテッドへと向き直った。
『フン、マアイイ。大方リミテッドノ気配ヲ感ジテ現レタトイウコトカ。イイダロウ、貴様モ我ガ一部トシテクレル』
「生憎だがお断りだ。貴様のようなおぞましいだけの下等生物と一緒にされては困る」
『オリジナルイクス。貴様ハ優秀ナリミテッド体ダ。我ト融合スレバ今以上ノ力ヲ手ニ出来ルノダ、悪クナイ話ダロウ』
一連の話にセイアはついていけそうにもなかった。代わりにいつかデータベースで見た資料を思い出す。
『オリジナルイクス』。その言葉が脳内で反響する。いた。確かにデータベースに存在していたのだ。リターン・イクスという名の過去のリミテッド体が。
かつて・・そうデス・リミテッドの元となったリミテッド、並びにハイパー・リミテッドの騒動の際に生まれたエックスの分身・イクス。
一度はエックスとの闘いで敗北し、消滅したイクスだったが、再びハイパー・リミテッドの力によって復活を果たした。それがリターン・イクス。
「冗談。同じリミテッド戦士として貴様程癪に障る者はいない」
兄達からリターン・イクスについての話を聞いたことは一度もなかった。
しかしデータの上ではリターン・イクスはリミテッド騒動の最終決戦にて現れたシグマ・リミテッドとの闘いの際にエックス達に協力している。
その後の彼の行方は結局判らず終いであったが、今まさにここに存在していることだけは紛れもない事実だった。
「おいセイヴァー。力を貸してやる。コイツを抹消する為にな」
「リターン・イクス・・。君は、味方なのか?」
「正直そう捉えられることには抵抗があるが、今はそう認識して貰って差し支えはない」
口ではそう言い放つリターン・イクスだったけれど、セイアはその瞳の中に確かにエックスと同じ暖かさを見た。
ふとセイアは口もとに笑みを浮かべ、再びデス・リミテッドを見据える。まるで兄が傍にいるように、疲れきった身体に再び闘志が燃えた。
リターン・イクスも同じように醜悪なケルベロスを見上げた。そんな二人にデス・リミテッドは三つの口元をニヤリと歪めた。
感情の伴わない下衆な嘲笑だった。
『愚カナ。貴様等二人ナラ勝テルト思ウカ。貴様等ノヨウナ雑魚ガ何人集マロウト勝チ目ナド存在セヌワ!』
「勝てるさ」
無遠慮なプレッシャーを与えるデス・リミテッドの言葉を、リターン・イクスはぴしゃりとその一言だけで斬り捨てて見せた。
横に並んだセイアが見るリターン・イクスの目に迷いはない。その横顔はいつも憧れてやまなかった兄の顔だった。
「セイヴァーと貴様では見詰めているものが違う。例えどれ程強力になろうと、貴様は最初から負けている」
「イクス・・兄、さん」
思わずセイアはリターン・イクスを兄と呼んでいた。言葉も動作も乱暴で、取っつきにくい印象しか受けないリターン・イクスだけれど、
その瞳と言葉にはエックスと同じ強さと暖かみがあったからだ。まるでずっとセイアを知っていたかのように振る舞うリターン・イクスは迷わない。
兄と呼ばれたリターン・イクスは横目でセイアを見たあと、再びデス・リミテッドを見る。その一瞬の視線の中に笑みがあったことを、セイアは勿論知っていた。
「貴様のようにただ本能のみで生きている下等生物には判るまい」
「デス・リミテッド。貴様が僕から生まれた存在だとするのなら、今ここで・・僕は僕を越える!これが最後の闘いだ!」
「私とて元はエックスと同じ身。生きる目的はとうに見据えているわ」
そして閃光が輝く。セイアの左腕を中心に、彼を蒼と紅の光が静かにゆっくりと・・そして力強く包み込む。
あの時と同じだ。あの電脳世界内での闘いの時と同じ光。そしてあの時よりも強く、輝かしい。
ボロボロだったセイアの鎧が、光に包まれて変化を遂げた。更に鋭く。更に力強く。二人の兄に抱かれるセイアは、
最後に形成されたヘルメットによって再びロックマン・セイヴァーの輝きを取り戻した。
クロス・アーマー。エックスとゼロの心を継ぐセイアにのみ装着することが許された究極の鎧だ。
『ソノ程度ノ輝キ、塗リ潰シテクレル。貴様ハ所詮太陽ノ前デ朽チルイカロスニ過ギントイウコトヲ思イ知レ』
「見せてやるがいいロックマン・セイヴァー。現代のイカロス神話は太陽をも越えるということをな」
「あぁ、闘おう!これを最後の闘いにする為に。力を貸してくれ、イクス兄さん!」
「ふむ・・よもや兄と呼ばれる日がくるとは思わなかった。が、悪くない・・」
そして三人目の兄の力が更に交差する。
リミテッド特有の能力で姿を変えたリターン・イクスが、セイアのクロス・アーマーを包み込むように更に融合を果たす。
胴に、腕に、足に、頭に。そして心に――三人目の兄の心が交差した。
そうしてようやくクロス・アーマーは完成を果たす。遂に不完全なままだった箇所を、リターン・イクスが埋めたのだ。
「暖かい・・・これが、僕の兄さん達の・・力。太陽を越えるイカロスの力!!」
そしてセイアは・・ロックマン・セイヴァーはイカロスとなった。
太陽に等しい力を持つデス・リミテッドに挑む為に。いや・・紛い物の太陽を打ち砕き、己が真の太陽となる為に。
エックスの、ゼロの、ウィドの、ゲイトの、彼等が護ってきた沢山の人々の、そして・・イクスの輝きの中で、セイアは剣を抜いた。
そして叫ぶ。願わくば・・これが最後の闘いとなるように。
『リミテッド戦士トアロウ者ガ馴レ合イオッテ。小賢シイ!ナラバソノ闘志モ輝キモ骨ノ髄マデ砕ケルガイイ!』
「行くぞっ!勝負だデス・リミテッド!!」
――果たして・・・。
――果たして、どれだけの者がこの闘いを知っていたのだろう。
――果たして、どれだけの者がロックマン・セイヴァーの闘いを知っていたのだろう。
――果たして、どれだけの者が人知れぬ場所で自らの為に闘ってくれている者がいることを知っていただろう。
――いやきっと、誰も知らない。
――現代のイカロスを、誰も知らない。
――誰に支えられずとも、挫けず闘った戦士のことを、誰も知らない。
――それでもいつかは伝わるだろうか。
――ロックマン・セイヴァーという英雄の意思を継ぐ者が、誰も知らない場所で闘っていたことを。
――それでも・・いや、きっと伝わっているに違いない。
――ロックマン・セイヴァーを、そして徳川健次郎を待つ人々が思いの外多いことを。
――今はまだ伝わらないかもしれない。
――それでも・・いつか、彼の闘った軌跡はきっと輝くだろう。
――現代のイカロス神話と共に・・・。
それから数時間後・・旧ハンターベースに存在していた膨大なエネルギー反応が完全にロストしたのだった・・・。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『――であります。卒業生一同様の益々のご発展をお祈りし、ここに締めさせて頂きます』
『卒業生・在校生起立。礼、着席』
ガタガタっと騒々しい椅子が擦れる音。立ち上がる生徒達。自分では最高り演説を演じたつもりの市長。
淡々とプログラムを進めるナレーター。既に泣き出してしまっている父兄。
そして、伝統に基づいて綺麗に飾りつけられた体育館。普段の空間とは一線を覆す、華やかな場所。
そんな体育館内には所狭しと椅子やテーブルが並べられ、それと同じ数だけの人間・レプリロイド達が座っている。
ステージの天井から吊るされたプレート。体育館の側面に控えた吹奏学部。ここぞとばかりに着飾った者達。
窓の外を見ればガラス面いっぱいの桜の花を見ることが出来るだろう。三年前、今まさに祝われている生徒達が見たものと同じ、蔓延の桜を。
彼は市長の長い癖にそれ程内容のない、最悪テンプレートにしか聞こえない演説がようやく終わったのをいいことに、思わず大あくびをかいてしまった。
昨晩はこんな行事の前日だというのにやるべきことに追われ、睡眠時間をたっぷりととっていなかった所為なのかもしれないが、
彼はあくまで市長の演説がつまらなかったことの所為にするつもりだった。
こつん。流石に目立ったのか、隣に座っているクラスメイトに肘でつつかれた彼は、慌てて姿勢を正す。
幸いに次のプログラムに以降する為にその他大勢が慌だしかったお蔭で、彼の怠惰は周りには勘づかれていなかった。
「卒業式くらい、しゃんとしろ」
「う、うん」
小声で耳打ちされ、睨まれる。流石に言い返す言葉がないので、彼は小さく返すと縮こまってしまった。
そういえば入学式――ではないが、それに近い式がかつてあった――の時も同じように前日夜更かしをしてしまい大あくびをかき、
隣に座っていた兄に肘でつつかれたことがあった。それを思い出すと途端に顔が熱くなってしまい、彼は片手で顔面を覆った。
ああなんて恥ずかしいのだろう。と。
「――卒業式」
ようやく顔の火照りがおさまった彼は、ふと顔を上げてステージに吊るされたプレートに目をやった。
『第八回フロンティア学園卒業証書授与式』の文字が大きく描かれたプレートはなんということはない、ただのプレートだ。
だが彼にとってはそれだけでも大きな意味があった。
もう死んでしまった、大切な人が自分の為に無理を云って入学させてくれた学校。
沢山の友達と出逢い、ぶつかり、それでも楽しかった学校。
自分一人では判らなかったことを、沢山教えてくれた学校。
一時は卒業出来ないとまで覚悟した学校だったのに、今彼はこうしてここにいる。卒業生の列の中で座っている。
それはなんて奇跡で、素敵なことだろう。それを思い彼はふわりと口もとに小さな笑みを浮かべた。
『卒業証書授与』
そしてようやく準備が整ったらしく、ナレーターが次のプログラムを続ける。この卒業式というイベントの中でもメインのメイン。
これをする為に卒業式という儀式があるのだというコアの部分。ついにそれが始まるのだ。
思えばここまで漕ぎ着けるのに随分と時間があった。無駄に長い話をする校長先生。出だしを失敗してやり直しになった校歌。
どこぞのお偉いさん方の演説。無論さっきの市長もそれに含まれているが。
本当ならばこれを一番じっくりとこなさなければならないというのに、ここまで来るのに一時間弱とはまた困ったものだ。
この後もプログラムはずらりと並んでいる。きっと他の生徒達は心底うんざりしていることだろう。
けれど彼は違う。今まで散々焦らされた分、このプログラムが来ることへの期待感がどんどんと大きくなっていったのだ。
『三年A組起立』
卒業証書は立体映像装置によって手渡される。
渡された機器を操作することで映像の卒業証書が表示され、それをいつでも劣化なく見ることが出来るという寸法だ。
機器をPC等のデジタル機器に接続すればデータ保存も簡単ということで、最近ではそれが一般化しつつある。
呼び出されたA組の生徒達。一人一人の名が呼ばれ、それに返事をし、彼等は壇上へと上がっていく。
そして一人一人が校長と顔を合わせ、手渡しで卒業証書を渡されるのだ。
それが常識。数百年前から普通のことだが、彼にはとても素晴らしいものに見えた。
校長という最も権限の高いものが、生徒という何百人も存在する者達と一人一人顔を合わせ、証書を渡す。
生徒一人一人の存在を認め、それに祝いの念と共に渡すのだ。たった一人の生徒の為に、僅かでも時間を割いて。
生徒達はそれに向き合って受け取る。三年間自分達が学び、頑張った印を。そしてこれから先の未来へと歩きだす切符とも云える証書を。
『三年B組起立』
壇上を降りていく生徒達の中には、泣き出してしまっている者達もいる。それぞれの沢山の想い出が頭を巡ったかのように。
そんな者達を見て、彼も思わず涙が溢れそうになったのを必死で堪えた。まだ泣くときじゃあない。その涙は彼等のものであって、
自分が流す涙は別にある。今日流す涙は、誰の為のものでもない。自分の為に流すものだから。
途中で隣に座っているクラスメイトが彼の様子を心配して横目で声をかけたが、彼はふるふると首を振って笑った。
哀しいのではない。ただ、嬉しいだけなのだ。そう伝える為に。
その笑顔にクラスメイトも釣られて笑い、また壇上を見上げた。
ボーッとしていると波のように過ぎていってしまう生徒達。一枚、また一枚と消えていく卒業証書。
彼はその光景を目に焼きつけるようにジックリと見た。証書を受け取り、それぞれの表情で壇上を降りていく生徒達の顔も、姿も全て。
学校だけではない。彼の三年間を彩ってくれた者達、全てを忘れない為に。
『三年C組起立』
そして最後の号令がかかる。彼を含めた周りの生徒がその声に一斉に立ち上がった。
思えばクラスが三つとは随分と少なくなったものだ。彼が入学した時は少なくとも五つはクラスがあったというのに。
辞めていった者もいる。転校していった者もいる。しかし何より減ったのは教室だった。
イレギュラーが学校に現れたことで被害を受けたのだ。仕方なしにクラスが幾つか統合され、今のクラス数となったのだ。
しかし今となっては昔の話だ。実際に死傷者が出たわけではなく、学校が傷ついただけだというのは幸いだったと、
さっきの校長の長い話の中でも云われていたことだ。彼もそれでいいと思っている。
『――』
程なくして出席番号順に生徒の名が呼ばれ始めた。並べられた椅子の端っこから壇上へと昇り、証書を受け取っていく。
さっきまでと全く同じ光景。同じパターン。しかし三年間付き合ってきた者の多いクラスメイト達が証書を受け取っていくのは、
さっきに増して不思議な感じだった。
『クリストファー・ケビン』
「はい」
クラスメイトのクリスが名を呼ばれ、壇上へと昇っていく。
一旦校長の前まで歩いたクリスは、礼儀よくお辞儀をすると、左手、右手と順番に証書に手をかけ、もう一度お辞儀をし、壇上を降りていく。
思えばクリスはこの学校に入って、彼に初めて声をかけた生徒だった。
学校という空間に慣れない彼をよく助けてくれた。宿題をする時間がなかった時にこっそり映させてくれた。
それがばれて二人で廊下に立たされたこともあった。隠し事がばれても、彼女は何も云わずにそれを受け入れてくれた。
別に彼女とはどうという関係ではなかったが、ただいい友達だった。彼女はこの先この学校の高等部に進むと云っていたが、
成績優秀な彼女ならきっと素晴らしい道を開いていけるだろう。
『フレッド・ミルド』
「ういす」
次はフレッドだ。
思えば彼は二年前はいわゆる不良生徒だった。世の中を斜めに見て、なにかといちゃもんをつけて。
なんだってこの学校に在籍しているのか本当に謎の生徒だった。
しかし彼は変わった。いや、本当の彼を曝け出したというのだろうか。
彼は本当は優しい少年だった。正義漢や勇気を人一倍持った、純粋な少年だった。
ただそれを理解してくれる人が周りにいいなかっただけだったのだ。この三年間で、彼は自分の居場所を見つけられたのかもしれない。
壇上を降りる時に目が合ったフレッドは、彼に向かってニッと笑った。彼も肩を竦めてそれに笑顔を返す。
いつの間にかこんな関係が出来ていた。初めて出逢った時はいちゃもんをつけられ、喧嘩をふっかけられた仲だというのに。
フレッドは自分に助けられたといつも云っていたが、それは違うと彼は思う。
フレッドは彼が自分を見失った時、一番初めに引き留めに来てくれた友達だったからだ。
下手をすれば傷つけるだけでは済まなかったというのに。あの時のフレッドの勇気は、今でも彼の記憶に鮮明に残っている。
『――ウィド・ラグナーク』
「ん」
彼が証書を渡される者達一人一人に想いを抱いている内に、終わりが近付きつつあった。
校長の手元に残っている証書はもう最後といってもいい。それは同時に卒業式の一番の山であるプログラムが、もう終わるということを意味していた。
名を呼ばれたウィド・ラグナークはゆっくりと壇上へと上がった。あれ程注意したというのに直っていない不作用な礼をし、ウィドは証書を受け取る。
ギシギシとまだ馴染みきっていない義手が音を立てた。一年前の闘いで負傷した腕は回復が見込めず、結局義手になってしまったとウィドは云っていた。
その時に受けたウィドの痛みは彼には計り知れない。が、今では殆ど日常生活には差し支えなく振る舞っていることから、
もう殆ど大丈夫なのだろう。
彼もまたこの学校に来て変わった者の一人だったと思う。
人付き合いが苦手で、気を許した相手にしか表情すら変えない、そんな少年だったウィド。それがこの学校に来て、このクラスに触れ、除々に変わっていった。
今でもまだ人付き合いは苦手だとウィドは云うけれど、それでも一年前に転校してきた時の彼とは違う。
自然に笑みを零せるようになったウィドは、立派なクラスの一員だった。
「・・・」
ウィドが席に戻り、三年C組の生徒達が腰を降ろす。校長の手元の卒業証書入れも空っぽだ。
しばしシンとその場に静寂が走る。二秒、いや三秒か。そしてその沈黙を破るべく、ナレーターが次の言葉をマイクにぶつけた。
『そして卒業生代表・徳川健次郎』
「・・はい!」
彼――徳川健次郎が椅子から立ち上がった。この学校を巣立っていく卒業生――その代表として。
三年C組の端っこの席に座っていた健次郎は、壇上に昇る為、必然的に全ての列を前を通る。
つまり卒業生全員の視線に晒されることとなるのだ。
普通ならばとても緊張する行為だろう。無論健次郎自身この瞬間、とても緊張すると覚悟を決めてきた。
けれど、本当は違う。健次郎の心を埋めたのは緊張よりも喜びだったからだ。
「みんな・・」
思わず言葉が漏れてしまう。
何故なら健次郎を見送る生徒達の視線がとても優しく、暖かだったからだ。
健次郎は胸の内が暖かくを通り越えて熱くなるのを感じながら、壇上への階段に足をかけた。
たった五段の階段。たったそれだけの数に過ぎない段数。だが、今まで過ごしてきた三年間と同じくらいの重さが、この五段にはあるのだ。
一段――登校日数が極端に少ない自分が、こうしている卒業式を皆と共に迎えられるとは、なんて素晴らしいことなのだろう。
二段――その為に沢山助力をしてくれた仲間達、先生達。きっと健次郎は彼等を生涯忘れないだろう。
三段――何度もイレギュラーの手から護った学校。破損は何度もしてしまったけれど、今こうしてここにあるのは、自分がここを護ったからだと胸を張って云える。
四段――エックスとゼロの弟であるということは誇りである。が、ここはそれ以外の自分をも創り出してくれた、大切な場所。
五段――卒業生代表として生徒達によって選ばれた健次郎は・・きっと、いやとても幸せ者に違いない。
「卒業おめでとう。徳川君」
「はい。慎んでお受けします」
礼を交わし、校長と向き合う。実際に校長と会話をしたのはこれが初めてだったが、この一瞬でもこの校長の人間性が確かに判る。
目を細め、小さく笑んだ校長先生。セイアは静かに左手を出し、右手を出し、卒業生代表用に別途用意された証書を受け取る。
「立派になったものだ。君だけではないよ。ここにいる卒業生全員が、君と同じように立派になった」
そう云う校長の目は健次郎を通して、後ろの卒業生全員に向けられていることが判る。
健次郎はそれに笑みで応えた。きっと、そう入学したばかりだったハンターとしてもレプリロイドとしても未熟な彼には出来なかった笑みで。
そして健次郎は頭を下げた。この学校を巣立つという、最後の儀式を。けれど頭を上げても校長が返礼をした気配はない。
何事かと首を傾げると、校長はまるで何か愛おしいものを見るかのような顔で囁いた。
「徳川君。振り向きたまえ」
「えっ・・・?」
健次郎が振り向いた瞬間に、ナレーターが、次のプログラムを、口にした。
『卒業生・在校生斉唱』
そして健次郎が知らない間に用意を完了していた吹奏楽部が、壇上の隅っこのピアノの前に座っている教師が、一斉にそれを奏で始める。
それはよくある卒業の歌でもなければ、洒落たポップスでもない。
プログラムシートに書かれていない――健次郎は全く知らなかった、イレギュラーなプログラム。
それでも彼等は歌い出した。いつか音楽の時間か何で健次郎も聞いたことのある、健次郎が一番好きだった合唱曲を。
マイバラードを――
――みんなで歌おう 心をひとつにして
悲しいときも つらいときも
みんなで歌おう 大きな声を出して
はずかしがらず 歌おうよ
心燃える歌が 歌がきっと君のもとへ
きらめけ世界中に ぼくの歌を乗せて
きらめけ世界中に 届け愛のメッセージ
みんなで語ろう 心をなごませて
楽しいときも うれしいときも
みんなで語ろう 素直に心開いて
どんな小さな 悩みごとも
心痛む思い たとえ君を苦しめても
仲間がここにいるよ いつも君を見てる
僕らは助け合って 生きてゆこういつまでも
心燃える歌が 歌がきっと君のもとへ
きらめけ世界中に ぼくの歌を乗せて
きらめけ世界中に 届け愛のメッセージ
届け愛のメッセージ――
「みん・・な。みんな・・・ありが・とう」
今日は流さないと決めた涙が、健次郎の頬を伝わっていった。
そしてこれが、現代でセイアが最後に流す涙――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
遂にイレギュラー・ハンター上層部の決定が揺らぐことはなかった。
客観的に見てその決定は至極当然のことだろう。
イレギュラー・ハンターがイレギュラー・ハンターである限り、始める前から方針は決まっていたようなものだ。
それでも少年が残してきた功績は偉大だった。最後の最後で処分が軽くなったことは奇跡に近い。
いや、今まで奇跡を起こし続けてきた少年だからこそ、最後の最後で自らの為の奇跡を起こしたと云ってもいい。
それが本人にとって奇跡と呼べるかどうかは定かではない。寧ろ少年の心を晴らすには余りにも稚拙過ぎていた。
少年は言い渡された処分をただ静かに受け入れたという。
その瞳の奥にどんな色が宿っていたのか、一番近くに座っていた彼の父ですらわからない。
その日の少年の顔は永遠に謎になってしまった。
小さな希望を訊ねられたとき、少年は猶予を彼等に求めた。
それは無意味な時間にしがみつく為の足掻きでなく、彼の最も大切な者に示すけじめの為の時間。
少年が終始纏っていた服装からも、それは明白だったことだろう。
時間は与えられた。高く歌う北風が柔らかな春風に変わるまでの、ほんの僅かな時間が。
そして今日が最後の日だった。少年が待ち焦がれ、また最も恐れていた時が来てしまった――
――徳川健次郎。正式名称ロックマン・セイヴァー。第十七精鋭部隊の副隊長にして最強のイレギュラー・ハンター。
エックスを殉職にまで追い詰めたDr.ワイリー。並びにその遺産であるデス・リミテッド。
レッド・アラートを名乗る自衛団との小競り合い。フォース・メタルを巡るギガンティスでの闘い。それらを終結させた名誉隊員。
・・そして今後イレギュラー化が大きく懸念される危険分子。
上層部が彼に下した処分は――
「それは一体どういうことだっ!」
滅多に声を荒らげないウィドの怒号が研究室内に騒々しく響いた。普段殆ど大きな声を出さないウィドの怒号は途中で裏返る程のものだったけれど、
それを向けられた健次郎は――セイアは怯むことなく真っ直ぐにウィドの瞳を見詰めたままだった。
「どういうことも何も、言葉通りだ」
「言葉通りだと?ふざけるな!」
キリキリと金属音を立てるウィドの義手がセイアの胸ぐらを掴んだ。生身の腕とは比べ物にならない腕力で壁に叩き付けられるも、
セイアは未だに冷静な顔を崩そうとしなかった。
セイアの真っ直ぐな視線に射抜かれて、ウィドは更に表情を歪める。しかも流石の機械腕の腕力もセイアには全く通じず、容易く振りほどかれてしまったものだから、
ウィドはただセイアを睨むことしか出来なかった。
セイアは二、三歩歩いて窓に手を当てた。紅のアーマーを身につけた彼の後姿は凜々しいが、今はなんだか小さく見えるような気がした。
「セイア・・あれからもう一年だ。あれ以来お前の身体に特に異常はなかった筈だ!それなのにどうして・・!」
「・・・・」
振り返り、セイアはウィドの顔を見た。その瞳に感情はない。ただ淡々と見返す瞳だけがそこにはあった。
「セイア・・!!」
「僕の体内にはリミテッドが残っているんだ。検査結果はいつも同じ。何度やっても取り除くことはできなかった。
取り除く為には、長い年月をかけてゆっくりとやるしかない。君だって判っているだろう・・?」
握り締められた鎧の胸部が軋みを上げる。いっそ砕けてしまえばどれだけ楽だったことだろう。
セイアがどれだけ力を入れても決して壊れないアーマーが、まるでその奥にあるものの根深さを暗示しているようにも見えた。
「・・・何故、黙っていたんだ。何故だ、答えろっ!」
「・・云い出せなかったんだ」
蚊の鳴くような小さな声で答えるセイアの頬を、ウィドの鉄拳が殴りつける。セイアは抵抗することなくそれを受け入れた。
二度三度殴られて壁に押し付けられても、ただ黙って身を任せる。ウィドにはそれが悔しくて仕方なかった。
「云い出せなかっただと・・!?貴様・・!」
「隠すつもりはなかったんだ。ずっと云おう云おうと思っていた。でも、いざ云おうとするとどうしても無理だったんだ。
なんて云えばいいかわからなかった。本当は・・・!」
言葉を最後まで紡ぐ前に、セイアは顔を背ける。
これ以上口を開けば逃げ出してしまいそうになるからだ。決して流さないと決めた涙が溢れそうで、必死にそれを押しとどめた。
ウィドにはそれが痛みを堪えているようにしか思えない。自らを置いて消えようとする少年の心など、彼にはもはや関係のないことだった。
「博士、もう時間ですね」
「・・そうだね。そろそろ始めようか」
押し黙っていたDr.ゲイトが息子の呼びかけに口を開く。
普段の軽い印象などどこにもない。二つや三つ挟んでもおかしくなかった言葉すらなかった。
既に用意されていた休眠カプセルは口を開けている。棺おけと称するべき、休眠カプセルが。
「待て、待てセイア!俺達は友達じゃなかったのか、またお前は俺を置いていくのか!?待ってくれ、セイアっ!!」
「ウィド・・・」
カプセルへ入り、寝そべるセイア。それが封印されているゼロの姿に重なって、ウィドは半狂乱になって叫ぶ。
「ごめん、ウィド」
セイアはウィドの名を呼んだ。もうスイッチを軽く押し込むだけで封印という名の闇に陥れられる状態で、
セイアは最後に云う。セイアが最後に向ける、ウィドへの・・親友への言葉だった。
「君を、忘れない」
セイアの瞳から一粒の涙が滑って落ちる。
ウィドの目にそれは映らなかった。
「セイ・・!!」
「それじゃあ始めるよ、セイア。予定では約百年後の夏頃に封印が解ける筈」
「・・はい。お願いします、博士」
「待・・!!」
「お休み、セイア。ボクの最後の息子」
そしてウィドの制止も聞かず、ゲイトはスイッチを押し込んだ。
「お休みなさい」と呟いたセイアの姿を、ゆっくりゆっくりカプセルの蓋が覆っていく。
ウィドが見ているスピードよりも蓋が閉じる速度は速かった。
ウィドがカプセルの蓋にかじり付いた時、既に内部にはレプリロイドの活動を停止させる霧が噴出した後だった。
「セ・・・イア」
半透明の蓋から見えるセイアの姿は、本当にただ眠っているかのように静かで、綺麗だった。
ウィドは糸が切れたようにその場に崩れ落ちた。
セイアが消えてしまった。セイアが目の前からいなくなってしまった。セイアが、もう自分の名を呼ぶこともない。ウィドにとっては――永遠に。
沈黙。
ただ沈黙だった。
俯くゲイト。膝をついて崩れ落ちたウィド。眠るセイア。誰も口を開かない。
低く唸る様々な機械の駆動音も、廊下から聞こえてくる雑音も、何もかも聞こえない。
世界は真っ白になってしまった。真っ白になって、何も見えない。
「・・・・・セイア」
その名を呼ぶ声を、ウィドとゲイトは聞いていた。無意識に呟くウィドのそれでなく、そう云ったのはゲイトの方だった。
「体内にリミテッドを残留させるロックマン・セイヴァーはいつまたイレギュラー化するかわからない。
誕生した三体のリミテッド体の戦闘力を計算に入れれば、次もまた勝てる保証などどこにもない。
一歩間違えばセイア自身がボク等の最大の敵になる危険性だってある。
・・懸念した上層部の決定さ。勝手なものさ、今までセイアに頼りきりだったのに、アクセルが入った途端に危険分子は排除するなんて」
「何故、誰もそれを俺に云わなかった」
「・・極秘だからさ。他の隊員は何も知らない。セイアは殉職したとでも伝えるんだろうね。・・・それにこれはセイアの意思だ」
あの幼い少年が自らに課せられた運命とどれだけ闘ったか、ゲイトだけが知っていた。
一体セイアはどう思ったのだろう。最強のハンターとして無遠慮に自らを戦火に投入しつつ、最後には己を消そうとする組織に対して。
いつか伝えなければならない親友への別れを、少年がどれだけ恐れていたのか。
ゲイトの白衣をぐしょ濡れにするまで泣いた幼い息子の顔を、ゲイトは生涯忘れることはないだろう。
「あーあ、思ったとおり。二人して湿っぽい顔してる」
場違いな明るい声。反射的に振り返ると、呆れた顔の少年レプリロイドが立っていた。アクセルだった。
「セイアは――そうか、もう寝ちゃったんだね。全くボクに挨拶もなしに寝ちゃうなんて水臭い」
重苦しい雰囲気を逃がすようにドアを開け放ち、アクセルがセイアの眠るカプセルに歩み寄る。
そっとそれに手をあてて、中に眠る少年の顔を見た彼は、振り返らないままに言い放つ。
「羨ましいよ。二人がね」
「羨ましいだと・・?」
「ああ、羨ましいね」
全力で殺気をまき散らすウィドに、アクセルは変わらぬ口調でそう返す。
それどころかウィドに顔を近づけて、小さく口の端を持ち上げて見せた。
「ボクはセイアに一言も別れの挨拶をして貰えなかった。それに較べて君はどうだい、ウィド?」
「黙れ!貴様に何がわかる・・!」
「わからないよ。ああ、わからない。わかりたくもないね、そんな自分勝手な気持ち」
掴み掛かってきたウィドを軽く躱し、アクセルは尚も云う。
擦れ違いざまに足を引っ掛けられたウィドは、受け身も取れずに床に倒れ込んだ。
「・・それとも君みたいに取り乱して見せれば満足?」
「貴様・・!」
「そりゃ悲しいさ、ボクだって。ゲイト博士だってそうに決まってる。それとも不幸なのは自分だけだとでも思った?」
レプリロイドは泣かない。泣く機能を持っているのはエックスとセイアだけだからだ。
それはアクセルも例外ではない。それでもアクセルは泣いていた。感情を押し殺したまま泣いていた。涙声のまま、ウィドに囁いていた。
「セイアはボクに一言も云わずに眠っていった。でも君にだけは別れを告げていったんだ。それがどれだけ辛かったか、君にはわからない?」
「・・・」
「そりゃセイアは勝手だよ。せめて別れの挨拶くらいして欲しかった。君の気持ちだってわからないわけじゃない。
でも・・きっとセイアだって必死に闘って」
「もういい」
ウィドが立ち上がった。ヒヤリと冷たい声を放ちながら。これがあのウィドかと思う程、哀しく声を響かせながら。
その瞳には、生気がなかった。まるで自分の中の全てを奪われたように、その目は酷く機械的で・・。
「もういい。もう、いい」
「ウィド」
バグった音楽プレイヤーのように、ただその一言を繰り返すウィド。アクセルは目を細めて彼の姿を見た。
ウィドはなんの感情も宿さなくなった瞳で、ゲイトの机の上にまとめて置いてあったセイアの武装のうち、一本のサーベルを手にとった。
いつもセイアが愛用していたエックス・サーベル。それを懐にしまい込むと、ウィドはひたひたと幽霊のように出口へと向かっていった。
「ウィド君、どこへ行くんだ!」
ウィドは答えない。
「ウィド!」
ウィドの肩を掴んだゲイトの腕を、閃光が斬り落とした。ウィドが振り抜いたエックス・サーベルによる斬撃だった。
途端にゲイトの肩からオイルが勢いよく噴出し、床を染める。
至近でそうされたウィドも当然オイルを浴びるが、何も云うどころか表情すら変えなかった。
「ウィド、何を・・!」
「邪魔を、するな」
アクセルの制止も振り切って、ウィドは行方を眩ませた。
そして二度と帰ってくることはなかった。
この世から処分されたロックマン・セイヴァーは、目の前の惨劇にも目覚めることなく、ただ静かに眠り続けていた。
その後ゲイトの必死の捜索にもウィドは見つからず、何年もの時が過ぎていく。
ゲイトはその後ベースの担当研究員の任を降りた。最後の息子までをも失ってしまった自分にけじめをつける為に。
抹消されたロックマン・セイヴァーは未だ眠り続けている。いつ目覚めるともわからない、永遠の時を。
その後も大きな闘いは何度もあったけれど、決してセイアは起きなかった。アクセルを始めとする現存のハンター達がそれをおさめていったからだ。
やがてシグナスが任を降り、エイリアが退職し、ダグラスは戦火へと消え、セイアが存在していた頃の世界は少しずつ姿を消していった。
それでもウィドは見つからなかった。ウィドを知る者さえ、少しずつ少しずつ消えていく。
そしてセイアとウィドの存在を知る者が全ていなくなった頃、世界は大きな変化をとげるのだった。
ネオ・アルカディアという、大きな変化を・・・。
ありがとう 兄さんへ――
あなたは沢山のことを教えてくれました 沢山のものをくれました
ありがとう 兄さんへ――
あなたは強い心をくれました あなたは僕に剣をくれました
ありがとう――友人達へ
あなた達は僕を受け入れてくれました あなた達は僕に笑顔をくれました
ありがとう――みなさんへ
あなた達がいてくれたから 僕は楽しかったです
とてもとても楽しかったです
暖かな人生を歩めました 全てが僕の想い出です
ごめんなさい――親友へ
あなたを置いていく僕をどうか許してください
あなたと過ごした時間は 僕の宝物だから...
さようなら――親友へ
君を忘れない
ロックマンXセイヴァーⅡ~己との闘い~
――完――
あなたは沢山のことを教えてくれました 沢山のものをくれました
ありがとう 兄さんへ――
あなたは強い心をくれました あなたは僕に剣をくれました
ありがとう――友人達へ
あなた達は僕を受け入れてくれました あなた達は僕に笑顔をくれました
ありがとう――みなさんへ
あなた達がいてくれたから 僕は楽しかったです
とてもとても楽しかったです
暖かな人生を歩めました 全てが僕の想い出です
ごめんなさい――親友へ
あなたを置いていく僕をどうか許してください
あなたと過ごした時間は 僕の宝物だから...
さようなら――親友へ
君を忘れない
ロックマンXセイヴァーⅡ 最終章~君を忘れない~
「なあ、セイア」
ウィド・ラグナークがふとロックマン・セイヴァーに声をかけたのはいつだったか。
確かウィドが忙しくキーボードを叩いている様を見詰めている時だったように思う。
彼の邪魔にならないように、とこちらから話しかけることを避けていたセイアは驚いた風に返した。
その拍子にぶちまけってしまった砂糖の塊がコーヒーの黒い波の中に呑み込まれる。
もう手遅れだなと諦めつつ、セイアはそれを自分で飲むことに決めた。
「何、ウィド?」
「お前は一番の願いが何かと聞かれたら、どう答える?」
「一番のお願い?」
カチャカチャとスプーンでコーヒーを掻き混ぜ、一口口に含んでみる。
ミルクも入れていないブラックコーヒーは、余程身を投じた砂糖の量が多かったらしい。
甘党のセイアでもうぇっと顔を顰める程に甘かった。こんなものをブラック派のウィドに渡してしまったらと思わず肝を冷やす。
きっとコーヒー独自の味わいが失われただの、豆の美味さを台なしにしているだの云われるのだろう。
幸いウィドはキーボードを叩いた姿勢のまま振り向かないので、その事実は雲隠れしてしまいそうだが。
何やらカチャカチャと慌ただしいセイアの様子をいぶかしげに思ったのか、振り向こうとするウィド。
セイアは慌てて手の中の甘すぎるコーヒーを飲み下した。ウィドが見たのはうぇーと顔を顰めるセイアの顔だけだった。
「・・何してんのお前」
「え、た、たまにはコーヒーでも飲んでみようかなって」
「なんでまたコーヒーなんか飲んでいるんだ、そんなしかめっ面までして」
「えーっと・・ちょっぴり大人さ!みたいな?」
今の答え方は随分だったらしい。呆れたように溜息をつくウィドは、また振り返ってキーボードをたたき始めてしまった。
自分でも今の答え方はないだろうと内心苦笑しつつ、セイアはもう一個のマグカップにコーヒーメーカーからコーヒーを注いだ。
もうかれこれ数時間はキーボードを叩いている友人への労いの為だった。
「・・で?」
暫くの間をおいて、ウィドの疑問の声が飛んでくる。見やるとまたウィドはキーボードを叩いているようだったが、
きっとさっきの質問の続きをしているんだろうとセイアは思った。
「・・・。僕の一番のお願いごとか」
「あぁ」
「なんでまたそんなことを?」
「ただの興味だ。答えたくなければ答えなくてもいい」
不貞腐れたような云い方をするウィドの表情は、セイアには見えない。
だからセイアはきっと自分が答えるのを手間取った為にウィドが機嫌を損ねてしまったんだと思って、
慌てて答えようと口をぱくつかせる。改めて考えた、自分の一番のお願いはなんなんだろうと。
「僕の、僕の一番のお願いは」
「・・・・」
いつの間にかウィドはキーボードを叩くのを止めていた。けれどそのことにセイアは気付かない。
俯くように、そして天井を見上げるようにセイアは云った。ウィドにその顔は見えなかったが、
きっとセイアは心底本音を云ったんだろうと彼は思った。
「落第しないでちゃんと進級して、学校を卒業することかな」
「学校を卒業すること?」
「うん。みんなと一緒に進路はどうしただとか、テストがどうしただとか、
そんな風に普通の会話をしながら学校に行って、みんなと一緒に卒業したいんだ」
ウィドは思わずプッと吹き出した。その答えが最強のイレギュラー・ハンターの発するものだとかは信じ難く、
それと同時に実にセイアらしい答えだったからだ。
本当は腹を抱えて笑いたかったけれど、流石にまずいだろうと懸命に肩を震わせるウィドだが、
笑っていることがばれないわけがない。しっかり答えたつもりのセイアは、顔を真っ赤にしながら怒鳴り声を上げた。
「ちょっと!人が折角本音で答えたってのに笑うことないでしょ!」
「くくくく、いやいやすまん、実にお前らしい答えだと思ったら・・。くっくっくっ」
「全く。もうウィドに何か聞かれても真面目に答えて上げないよ」
べえと舌を出すセイアに、ウィドは振り返って手を合わせた。
それでも彼はなかなか許してくれず、結局その日は仕事が進まなかった。
その所為で次の日は学校に遅刻してしまい、二人揃ってクラスメイトに笑われた。
その時は気付かなかった。その時のセイアの顔に憂いがあったことを、今になってようやく思い出す。
何故あの時は彼はそれを云わなかったのか、ウィドには理由が判らなかった。
その時既にリミテッドは出現していたけれど、まだ比較的危機感を持っていなかったからかもしれない。
「そういうウィドの一番のお願いごとは?」
「秘密さ。人には黙秘権というものがある」
「ちょっ、人に喋らせておいてそりゃーないでしょ!」
「黙秘権の公使は自由権限だ」
ウィドの一番の願いごとは、ゼロを目覚めさせることだった。
「セイア、今思えばあの時お前は何を云いたかったんだ・・?」
今まさにスプリット・マシュラーム・リミテッドの心臓部を貫いたレーザー銃を静かに降ろしながら、
ウィドはあの時の出来事を思い出すように呟いた。煙を上げる銃口とは裏腹に、ウィド自身の意識は全壊したマシュラームへ一片たりとも注がれてはいない。
ウィドの瞳に映っているのはその先の光景だけだった。
余りに自然という単語からかけ離れた世界。木々は一本たりとも生えず、辺りにはもはやレプリロイドだったと判別することも出来ない機械の破片の山。
乾いた風は破片の隙間を通り抜けて不気味に音を発する。それはさながら使者の悲鳴のようで、常人にはお世辞でも居心地がいいと云える場所ではない。
つい十年と少し前までは活気で賑わっていたこの場所は、今はもはや現世の阿鼻叫喚と云えた。
旧イレギュラー・ハンターベース跡。今とは違い、部隊数も隊員数も圧倒的に多かった頃。そう、あのシグマがまだ第十七精鋭部隊の隊長を務めていた頃、
イレギュラー・ハンター達が籍を置いていた場所だ。今となっては見る影もないが、昨今に較べ、
あの頃のイレギュラー・ハンターはなんと安定していたことだろう。そう思うことすら、今となっては虚しい思考に過ぎない。
さりとて旧イレギュラー・ハンターに所属していたわけでもなく、シグマの反乱を目にしたわけでもないウィドにとっては、
そんなことは眼中にすら入らない。ただただ静かに足を進め、一歩一歩とそびえ立つ廃墟へと歩いていく。
巷ではもはや心霊スポットと騒がれることすらない程に不気味な廃墟。深夜に訪れる者なら、その光景を見ただけで背筋を凍りつかせるだろう。
事実、あそこには沢山の魂が散乱しているに違いない。魂というものが実在するかどうかウィドには判断しかねるが。
旧ハンターベース跡で命を落とした者は数知れない。ある者は反乱する者達を止めようと。ある者は反旗を翻し、かつての同胞に撃たれ。
ある者は襲撃を試み、返り討ちにされ。そして襲撃され、闇討ちされた者。
ここが魂の集積所でなければなんなのか。それを形容する言葉も見つからず、さしてや形容する気もなく、ウィドはただ真っ直ぐに歩いていた。
「・・待っていろよ、セイア」
囚われた親友を想う。この先には囚われの親友と最凶の敵がいるのだ。
そう、つい数時間前にウィドはその事実を知らされた。知らされたというよりも一方的に突き付けられたという方が正しかったかもしれない。
マザー内でイクセを退けたクロス・アーマーを現実のものとして完成される為には、材料が圧倒的に不足していたのだ。
鎧の剛性を確保する合金。出力を高めるジェネレータ。安全性を保証するプログラム。その全てが足りなかった。
中でも入手が難しかったのがオリハルコンである。エネルギー出力を増幅させる恰好の材料であると同時に、
鎧の剛性を上げ、更にはその他の資源とは比べ物にならない廃熱力。かつてギガ粒子袍エニグマに利用されただけのことはある、別名奇跡の宝石。
当初オリハルコンを使用する予定はなかったのだが、急速にクロス・アーマーを組み立てるには必要不可欠だった。
更にはマザー内でセイアが使用した奥義・ソウル・ストライクに剛性が追い付いていない事実が発覚し、どちらにせよオリハルコンを使用せざをえなかった。
だがオリハルコンを手に入れさえすれば話は簡単だった。マザーの電脳世界での闘い以来、身体に無理を強いてまで完成させたプログラム、
鎧の型も既に出来ている。あとは鎧を構成する材料があれば良かった。
そしてオリハルコン使用の有効な副産物も発生した。エネルギー増幅力と廃熱力をいかし、ソウル・ストライクのエネルギーの連続的な維持。
つまり事実上の連射が可能となる可能性が出来たのだ。そうなればリミテッド達に勝利する確立もグッと上がる。
なんとしてでもオリハルコンという素材を入手せねばならなくなったのだ。
『大丈夫。すぐ戻ってくるよ』
そう言い残して、セイアは出ていった。オリハルコンを入手する為だ。
オリハルコンが残っている可能性があったのは、廃棄されたレプリフォースの巨大トレーラー。
オリハルコンの輸送中にユーラシア事件に遭い、そのまま廃棄されていた事実が今更になって判ったのだ。
ユーラシア落下の影響で使い物にならなくなっている可能性も否定は出来なかったが、僅かな可能性でも縋る必要があった。
危険性は未知数だった。リミート・レプリロイドが襲ってくる可能性があったからだ。
しかしそれでもセイアは出撃していった。クロス・アーマーを完成させ、リミテッド達を倒したいと思っていたのは、誰よりも彼だったのだ。
出撃の途中、案の定リミート・レプリロイドは姿を現わした。通信機からセイアが漏らした名はビストレオ。
スラッシュ・ビストレオ・リミテッドだった。
レプリフォースの中でもトップクラスの実力者だったビストレオのリミテッドは手強かった。
データを元に弱点をついて闘うセイアだったが、かなりの苦戦を強いられた。が、結果的にビストレオを撃破したセイアは、
予測通り残っていたオリハルコンを入手したと報告をくれた。オリハルコンは一足先にベースに転送装置にて転送され、
セイア自身もすぐにベースへと戻ろうとした矢先。ウィドが予想しながらも考えることを避けていた事態が起きてしまった。
ロックマン・セイヴァーからのイレギュラー・ハンターベースへの連絡が不意に途絶えた。
通信機の故障とは思えなかった。予備の通信機に呼びかけても反応はない。人工衛星を使用して反応を追ったが、セイアの反応は完全にロストしてしまっていた。
『今から帰る』
それがベースに、ウィドに届いたセイアの最後の言葉だった。
別のリミート・レプリロイドが現れたのか。それとも何か別の出来事に巻き込まれたのか。
セイアの反応が消えてから十数時間。使用者不在のクロス・アーマーがようやく完成の兆しを見たとき、ウィドのモバイルが叫び声を上げたのだった。
普段聞いたこともないその音はメール着信音。セイアだろうかと慌てて開いてみると、差出人の欄には彼に似ても似つかぬ翠の悪魔の名前があった。
「イクセ・・・」
タイトルは『焦っているようだね』。人とを小馬鹿にしたような態度は文面でも変わらない。
震える手で本文を開く。ウィドを戦慄させるには充分な文章だった。
『 こんにちは、ウィド・ラグナーク君。
毎日部屋に籠もっての研究ご苦労様。ボク達を倒す打算はまとまったかい?
それともセイアがいなくなって研究どころじゃなく焦っているのかな。おっと確信めいたことを云っておいて問いかけるのはまずかったね、謝るよ。
む、ここで機嫌を損ねてメールを閉じたりしないでね。でないときっと後悔するよ。
いいかい?ここから下の文章は君一人で読むこと、ウィド・ラグナーク。もし別の誰かに見せたりしたら、ボクが機嫌損ねちゃうからね。
しっかり周りに誰もいないことを確認したなら、下にスクロールするといいよ。 』
周りを見る。誰もいない。ゲイトは今ごろクロス・アーマーの制作を続けているのだろう。
奥の方から素材を削る高音が聞こえてくる。彼はどうやらセイアを信じて黙々と制作を続けるつもりらしかった。
もう一度辺りを確認する。やはり誰もいない。ほんの少しの動揺を必死で隠しながら、ウィドはスペースで埋め尽くされた文章を一気にスクロールさせた。
『 頭のいい君ならきっとこれを読んでくれると期待していたよ。あんまり気分がいいからお礼を云うよ、ありがとう。
最も君にとっては焦燥感でどうにかなりそうな状況なんだろうけど、すぐにその焦りを解放して上げよう。
君の大切なお友達、そしてボクにとっては愛しい宿主。セイアはボクのすぐ傍にいるよ。
おっと君の自尊心を傷つけるつもりはないから断るけど、単にボクがセイアを一方的に預かっただけだから安心してよ。
昔のドラマっぽいでしょ?人質を返して欲しくば・・って奴さ。
あ、だからってお金が欲しいわけじゃないし、君に無抵抗で殺されろと云うつもりもない。
要求はただ一つ。セイアを返して欲しいならボク達のところへ一人で遊びにおいで。勿論あのクロス・アーマーとかいう厄介な鎧も持ってくるといい。
場所は旧イレギュラー・ハンターベース。座標くらいは調べればすぐに割り出させるでしょう?とてもロマンチックな場所さ。
心配はいらないと思うけど、先に忠告しておくよ。ボク達が呼んだのは君一人。余計な誰かをくっつけてくるんじゃあないよ。
因みに君が来なくても別に構わない。君を追って行って殺すつもりはないからね。
ただ明日の正午までに君が来なかった場合、君のお友達の身の安全は保証出来ないな。
それじゃあ、君と逢えることを楽しみにしているよ。それじゃあ、バイバイ
P.S.そろそろ君達と遊ぶのも飽きてきた。そろそろ決着をつけよう Byイクセ 』
旧イレギュラー・ハンターベース。その中でも最も広い空間を誇るA級トレーニングルーム。
A級のと現わすことは現存のハンター達には違和感だろう。何故ならバーチャルトレーニングは設定によってランクが上下するのみであり、
基本的な設備はどの部屋も同じだからである。
しかし技術も現在と較べて劣り、ハンターの絶対数も多かった旧ベースは違った。下からC級、B級、A級とランク別にそれぞれトレーニングルームを与えられ、
それぞれ違った設備が施されていたのだ。
現在と較べてなんと贅沢で、無駄の多い施設だったことだろう。
パッと不意に輝いた照明に照らされ、目を細めながらも、ウィドはそんなことを心の隅で考えた。
冷静、とは少し違う。何か理論的なことを考えていれば気持ちが落ち着くからだ。本当ならはらわたが煮えくり返る直前だ。
眼球が光に慣れ、ようやく目を開けられるようになった頃、見計らったように聞き慣れた声が飛んできた。
いや違う。聞き慣れた声と同じながらも、それとは全く違う・・憎悪の対象としか受け取れない声だった。
「やあ、やっぱり来てくれたねウィド。君が来てくれると信じてたよ」
「イクセ・・」
ウィドに対して部屋の丁度反対方向に立っている三体のリミテッド。イクセ、レイ、イクス。
実際に目にするのはこれで二度目だが、奴等の狂気と威圧感を知るには充分過ぎる回数だろう。
リミテッドの三人はそれぞれが口もとに笑みを賛え、ウィドを見詰めている。
だがウィドは三人分の殺気に晒されながらも、イクセ達三人が眼中にないかのように視線を上にした。
恐らく奴等の趣味か何かなのだろう、まるで教会に飾ってあるキリストの絵画のように、十字架に磔にされたセイアの姿がそこにはあった。
「見た所やはり一人か。約束を守る律義な輩なのか、或いはただの馬鹿なのか」
「それは違うさレイ。彼はイクセの言いつけ通りに一人で来たんだ。要はセイアを助ける為さ」
「ふん。成る程な」
「ウィド・ラグナーク。我々の言いつけ通りに一人で来たことを褒めて上げよう。いらっしゃい、旧ハンターベースへ」
ウィドを嘲るレイに対して、イクスは逆にウィドを庇護しているようだった。丁寧に紳士的な挨拶をするイクス。
端から見れば優雅かつ端麗な姿に見えることだろうが、今のウィドにはそれがなんだろうと関係ない。
磔にされたセイアは生きている。微かに呼吸――最もレプリロイドに呼吸は必要ないが――で腹部が上下しているからだ。
見た所目立ったダメージもない。ビストレオと闘った際のものだろう、小さな傷は要所に垣間見ることが出来るが。
ウィドは腰のレーザー銃を抜いた。抜群の狙撃力を誇る銃口が、三体のリミテッド達へと向けられる。
距離にして三十m。決して外す距離ではない。無言のウィドに対しては、イクセは嘲笑を込めた苦笑で応えた。
「随分血の気が盛んなんだね、ウィド君。それはなんのつもりだい?」
「何のつもりだ、だと?訊ねるまでもないだろう。約束通り一人で来てやったんだ。
今すぐにセイアを降ろせ」
「口に気をつけろ、小僧。マシュラーム・リミテッドを倒したことで図に乗っているようだが、貴様一人でオレ達三人を相手にするつもりか」
「レイの云うとおり、君一人で俺達三人の相手をするのは少しばかり力不足だ。ここは大人しくしていた方がいい。
・・その気になれば半瞬後に君の首を飛ばすことだって出来るんだからな」
イクスは至って笑みを崩さずに言い放ったのだったが、それが嘘ではないことはウィドにも判る。
悔しいがリミテッド達の云うことは間違いない。頭に血が上ったウィドは猛りすぎている。
レイの云う通りマシュラーム・リミテッドを撃破したことで少々図に乗っていたのかもしれない。
一瞬強風が吹いたと錯覚する程のリミテッドの殺気にあてられて、ウィドはゾッとするような怖気を感じると共に、それを理解した。
一瞬にして熱を冷まされたウィドは渋々銃を降ろした。それが満足なのかうんうんと嫌味ったらしく頷くイクセは、
いちいち神経を逆撫でする明るい声で続けた。
「うんうん。素直に云うことを聞いて、良い子ちゃんだねえウィド君」
「・・・何か話があるなら手短に済ませたらどうだ」
「うーん、恐いなあそんな事云って。イクス兄さんの云うとおり、君をバラバラの細切れにして上げてもいいけど、それじゃあ折角君を呼んだ意味がない。
ちょっと気乗りしないけど、ボク達とお話する気はない?」
「・・・」
ちっとウィドは想わず舌打ちをした。気乗りしないのはあっちよりもこちらの方だと云ってやりたかったが、
これ以上奴等を刺激すれば結果は見えている。ようやくいつもの計算力を取り戻したウィドは、大人しく奴等の話に乗るしかないと結論づけた。
「・・いいだろう。ただしセイアに危害を加えることはしないと約束しろ」
「うん、いいよ。どうせ後で闘うことになるんだし、セイアが起きたところでボク達には絶対勝てないからそんな約束は意味ないんだけどね」
いちいち勘に障る野郎だ。ウィドは心の隅で吐き捨てた。
これではセイアがあれだけ向きになって斬り掛かっていく理由が判る気がする。真面な神経をした者なら苛つかずにはいられない。
奴がセイア以上の、つまり最強のレプリロイド以上の力を持つというなら尚更だ。
「どうせ君だって疑問に思ってるんでしょう?『何故滅びた筈のリミテッドが存在しているのか』とね」
「――・・!」
「図星だね。君は根っからの科学者だ。こうして自ら闘いに出向くより、ボク達の出所を考える方が余程楽しい。
ボク達を倒そうと考えるなら、尚更出所を知りたかったんじゃない?」
「ふん、教えてくれるなら願ったりだ。そこまで云うなら教えて貰おうか、貴様等リミテッドの出所を」
なるべく話を繋ぎ、奴等にセイアを解放させなければならない。そう思う反面、イクセの云うとおりウィドは知りたかったのかもしれない。
数年前に消滅した筈のリミテッドが何故今こうして存在しているのか。
何故またあの悪夢が現れ、セイアを喰らい、このような三体の悪魔を創り出したのか。
壁に背を預け、イクセは語らい始める。その姿は、その声は、その表情はさながら雑談するセイア。
確かにこれは余り気持ちのいい光景ではないと思う。磔にされ、首をもたれるセイアを見つめ直し、ウィドは自分を奮い立たせた。
「ま、とは云っても何から話そうか。そうだな、君はアルバート・W・ワイリーの名を知っているかい?」
「・・20XX年代にて幾度も世界征服を目論み、その度に伝説のロックマンによって阻止されてきた天才科学者。
現在の21XX年代でも彼とその対となるDr.ライトの技術に追い付いた者はいないと云われている」
「詳しいね。流石は天才少年科学者だ。そう、君の云うとおりDr.ワイリーは幾度もロックマンによって倒された哀れな天才科学者。
あのゼロの制作者でもあり、カウンター・ハンターのサーゲス、そしてアイゾックの正体も彼だ」
サーゲス。アイゾック。名前くらいは聞いたことがあるが、ウィドにとってはさして興味のない存在だった。
「・・あれれ、驚かないね。ゼロがワイリーナンバーズだって知ってたのかい?」
「あぁ。知っている」
「意外だね。だけどその割にはセイアと仲良くしてるけど、恐くないのかい?」
「貴様等とセイアを一緒にするな!」
ウィドの怒声は心底怒りに満ちていたが、イクセ達にとっては単なる怒鳴り声としか受け取れないらしい。
暫くキョトンとしたあと、イクセはまたニコリと目を細めて笑った。
「これは失礼。君の神経を逆撫でる気はなかったんだ。謝るよ」
ぬけぬけと云ってのけるイクセに殺意すら沸いてくる。だが今のまま闘っても勝てる見込みは零以下だ。
理解している分、ウィドにとってそれは拷問に近かった。
「そしてDr.ワイリーは一年前、再び現世に蘇った。あのVAVAを蘇らせ、もう一体のゼロを創り、
ロックマンの後継者であるエックスを倒そうとね」
「・・だが目論みと結果は違う。エックスにはセイアという隠し玉があった。ゼロは生きていたが、既にワイリーにとってそんなことはどうでもよかった。
奴の標的が二つになった。エックスとセイア。ロックマンの名を継ぐ者だ」
イクセの言葉を継いだイクスを、更にレイが続けた。そしてまたローテンションでイクセが口を開く。
「彼は天才だった。ボクが思うに彼はとうにDr.ライトを越えていたんだ。
彼が勝てなかったのはロックマンという個体がロボットという粋を超えて強かった。たったそれだけのことだったのさ。
結局ワイリーは復讐を果たすと同時に消滅した。皮肉だよね?最高傑作ゼロの血を引くセイアに斬られて死ぬなんてさ」
その瞳に感情はない。あるとすればそれは嘲笑だった。
「・・何が云いたい。そんなことを語って一体何になる?」
「まあそう苛つかないで。せっかちだね、君は。なら話をもっと簡単にして上げようか。
君の持つデータではボク達リミテッドは既に消滅した存在だ。違うかい?」
「そうだ。リミテッド並びにハイパー・リミテッドは数年前の闘いで消滅が確認されている。
だからこそ貴様等がそうして存在していることが疑問なんだ」
「うん、結構。頭のいい君ならそろそろ気付いてもいいんじゃないかな、ボクの云いたいこと」
半瞬の思考の後、ウィドはハッとした。今まで意味なくイクセが連ねていた言葉の真意をようやく掴みかけたからだ。
しかし――いや、だが・・そんなことが有り得るというのか。決定打を打ち損ねるウィドの様子に気が付いたのか、
イクセはさっきとは打って変わって楽しそうに笑った。そしてその顔とは裏腹に冷たい声で云う。
「アハ。気付いたかい?そろそろ遠回りに云うのも飽きてきたし、君が耐えられそうにもないから種明かしをしよう。
そう、ボク達新型リミテッド――正式名称はデス・リミテッドって云うんだけどね――はDr.ワイリーがリミテッドのデータを元に創り上げた試作品。
だけど余りにも不安定で出力が高過ぎる所為でワイリー自身が封印した悪魔のプログラムさ」
「ワイリー自身が封印したプログラム・・」
「そう。彼自身にも操ることが出来なかったのさ。だから来るべく決戦にボク達は投入されなかった。
ボク達はワイリーが死んだことで束縛から解放され、世界に放り出された。その最初の犠牲者はウェブ・スパイダスの亡骸だったっけね」
ウェブ・スパイダス・リミテッドのことはウィドもよく覚えている。そもそもウィドがセイアと知り合うきっかけとなった事件だ。
そう、確かアレは半年程前の話だった。任務中に思いがけないダメージを受けたセイアはベースとの通信手段も、移動手段であるライド・チェイサーも失い、行き倒れた。
それを救ったのはウィドだった。幸いなことにセイアが倒れたのはウィドの研究所の近くだったのだ。
前々からロックマン・セイヴァーという存在に興味があったウィドは彼を介抱することに決めた。
目を開けたロックマン・セイヴァーは噂よりもずっと幼い男の子で、彼自身とそう変わらない年頃に見えた。
最初はセイヴァーというイレギュラー・ハンターに興味があっただけのウィドは、彼と触れ合う内にセイアという一人の少年と友達になっていた。
破壊されたアーマーを修復するまでの数日間。それはウィドの人生の中でも特に充実した日々だったと思う。いや、間違いなくそうだったであろう。
そしてアーマーが修復され、セイアとの別れが来た。本当ならばここで別れ、それっきりだったに違いない。
けれどセイアにとってもウィドにとっても運命とは奇妙なものだった。その時、不意に二人の前に意外な敵が現れたのだ。
それがイクセの云うウェブ・スパイダス・リミテッド。レプリフォース大戦時にセイアの兄が撃破したレプリフォースの一員であり、
当然ながら既に破壊されている故人。思えばあの時既にここでこうなることは決まっていたのかもしれなかった。
スパイダスは強かった。ワイリーを倒したセイアでさえも苦戦し、ウィドのサポートがなければどうなっていたか判らない。
ワイリー自身が恐れた力だということが容易に納得出来る。その出来事がセイアとウィドの初めての出逢いであり、この闘いへの伏線だったのだ。
「あの時――いやあの時よりもずっと前から、この闘いは始まっていたということか」
「そういうことだ。もっと大きく云えばロックマンとワイリーとが闘いを始めたその時から、今ここでこうなることは決まっていた」
「疑問は解消された筈だ、小僧。そろそろ宴を始めよう」
「今宵は真ん丸のお月様が見守る最高の夜。きっと素晴らしいパーティーになるよ」
「――ッ・・!」
パチンと弾かれたイクセの指。反響の良いトレーニング・ルームに木霊する乾いた音と共に、磔にされていたセイアの身体が不意に重力に引かれた。
ウィドはイクセ等に注意を払いつつもセイアの元へと走った。ウィドの牽制は殆ど意味のないものだったが、イクセ達に攻撃の意思はないらしく、
アッサリとウィドが眼前を通ることを許してくれた。
「セイア、セイア!セイア、目を醒ませ!セイア!」
「くっ・・――・・つぅ・・」
二、三度身体を揺らすとセイアはすぐに目を開けた。いや既にボンヤリと意識を取り戻していたのだろう、
セイアは頭を片手で抑えながらにゆっくりと身体を起こした。未だに視界が安定しないらしくその目は歪められていたが、
一先ずのセイアの無事にウィドは敵前ということすら忘れてホッと胸を撫で下ろした。
「セイア・・」
「やあ、おはようセイア。疲れた身体に長い眠りは心地よかったかい?」
「ウィド・・どうして、ここに」
ブンブンと頭を振ったあと、セイアはウィドの肩に手を回した。急速に意識を繋げられて頭がハッキリとしないのかもしれない。
セイアの腕を掴んで彼を支えつつ、ウィドは答えた。それと共にレーザー銃を三体のリミテッド達へと向ける。
「お前を助けに来た。それだけだ」
「・・・ありがとう、ウィド。途中からある程度聞こえてたよ。ボクが倒したDr.ワイリーの・・遺産」
意識がハッキリしたらしくウィドの手を離れたセイアの全身から、ぶわっと闘気ともいえるものが噴出するのをウィドは確かに感じた。
それはイクセに対する怒りなのか、それとも兄を殺したDr.ワイリーの置きみやげに対する憎しみなのか。
どちらにしても今まで以上に凄まじい闘気だということは、傍にいるウィドには肌で感じられた。泣いても笑っても決戦の時はきたのだ。
「・・へえ、この間校庭で逢った時の甘ちゃんとは一味違うということか」
同じように三つの闘気・・いや殺気が飛んでくる。だがレイの評した通りにセイアの闘気は前以上に凄まじい。
この三人を前にしても竦まないセイアの視線に、イクスは意外そうに呟いた。
「成る程。君もロックマンの一人。この僅かな時間で大きく成長したのか」
「けど、ボク達には敵わない」
「・・!」
ウィドはまるで強風に吹き飛ばされそうな錯覚を覚えた。一際大きな殺気が飛んできて、それだけで押し潰されそうになったからだ。
その殺気を放つのは中心のイクセだ。イクセと対峙するのは今日で二度目だが、闘う意思のなかったあの時とは比べ物にならない程の殺気を感じる。
成る程セイアが手玉に取られてしまうわけだと、ウィドは笑い出しそうになる膝を必死で抑えながらに思った。
四つの闘気がその場で拮抗する。ほんのちょっとのきっかけさえ与えればすぐにでも爆発しそうな状況で、ウィドはようやく自分が呆然としていることに気が付いた。
ウィドは科学者だ。確かにレーザー銃の腕には自信があり、
それでセイアを助けたことも数回程あるが、特A級を軽く越えるだろうレベルを持つ四人の前では戦闘力の低さを実感せざるをえない。
それでもウィドは震える腕に気合を込めなおし、レーザー銃を向け直した。気持ちの面で負けていては勝負は闘う前から決している。
いつか誰かがそう云っていた。
「ウィド、下がれ」
「セイア・・」
それはいつものセイアの声だった。しかし逆らえない。有無を云わさぬ何かがそこにはあった。
イクセ等の宿主だっただけのことはあるというのか、それともこれがウィドの知らない戦闘者としてのセイアなのか。
その答えがどちらだったとしても、気が付けばウィドはセイアの云う通りに引き下がっていた。
そしてウィドが射程外に出たことを確認するやいなや、セイアはゼット・セイバーの刃を具現化させた。
それに伴ってイクセ達の闘気も更に威圧感を増す。そして燃え上がる殺気の中で彼等は笑んだ。
「これで心置きなく闘えるか?」
「ウィド君――足手纏い――も消えたことだしな」
「じゃあ、君がこの短期間でどれだけ強くなったか見せて貰うよ!」
「イクセ!」
そして誰が止める間もなく闘いが始まった。
三体のリミテッドが瞬時に三方向へと散開する。セイアは一瞬戸惑ったが、すぐにダッシュで前方へと跳んだ。
そしてセイアが体制を立て直すよりも前に頭上からのレイの剣撃がセイアを襲う。が、紙一重で避けていた。
床に手をつくことでダッシュを無理矢理に停止させたセイアは、すぐにその軸腕を中心に身体を翻し、レイの頬を蹴り飛ばす。
更に二撃目の蹴りをレイの胴に叩き込み、それを足場にして更に跳ぶ。
後方へと持っていかれる途中、空円舞を使い直角の軌道を以て上空へとセイアは飛翔した。
「いい動きだ。だが、空円舞と飛燕脚は同時使用出来まい?」
「イクス!」
空中へと上昇を続けるセイア。それを狙ったのはイクスだった。
地上からタップリとエネルギーを込めたバスターほこちらに向けている。
悔しいがイクスの云うとおり一度空円舞を使ってしまっては更に姿勢移動をすることは不可能だ。
セイアの上昇エネルギーが尽き、ピタリと空中で静止した瞬間にイクスのバスターが爆ぜた。
セイア自身のフルチャージとほぼ遜色ない巨大なエネルギーが一片の狂いもなくセイアを目指す。
目と鼻の先になったエネルギー弾!イクスはクリーンヒットを確信し、ニヤリと口もとに笑みを浮かべた。だが!
「おぉぉぉ!」
「なにっ・・!」
バスターは直撃した。そのエネルギー量は辺りに耳をつんざく程の爆風を残した程だ。
が、その爆風の中から姿を現わしたセイアは無傷だった。いや、無傷とは違う。
バスターへと転換した右手から氷の盾が発生しているのだ。ピキピキと音を立ててヒビを入れる氷の盾に目もくれず、
セイアは着地すると共にイクスの懐まで飛び込んだ!
「フロスト・シールドか!だが!」
しかしイクスも驚愕に躍らされていたわけではない。二発目のチャージ・ショットを既にその腕に込め、
真っ向から向かってくるセイアへと放っていたのだ。
セイアは再びフロスト・シールドによって閃光を受け止める。が、二発のチャージ・ショットを受け止められる程その氷は強固ではない。
バラバラと辺りへ四散していくフロスト・シールド。今からでは武装の転換に隙が出来ると踏んだイクスは、もう一発バスターを放とうと構える。
が、その胴に今度は強烈な回転エネルギーと共に突起が捻り込まれた。高音を発する回転力の正体は、ドリルだった。
「喰らえっ!」
「くっ・・!トルネード・ファング・・!」
既にセイアはフロスト・シールドの下にトルネード・ファングを潜ませていたのだ。
ギリギリと胴体へ侵食してくるドリルを止めることも出来ず、かといってセイアの左手に宿った炎を消すことも出来ず、
イクスはそのまま顎先に強烈なアッパー・カットを叩き込まれた。巨大なセイアの腕力に押されて、イクスはドリルを引き抜かれると共に空へと舞った。
その隙にセイアへと斬り掛かろうと飛び込んできたレイも、
セイアが右腕から射出したトルネード・ファングを受けた後に波動拳で追撃をされ、イクスと同じく後方へと吹っ飛んでいった。
「小僧・・!」
呻くレイの言葉も無視し、セイアはすぐに気配を探った。イクスとレイの戦闘力は見る限りそれ程脅威ではない。
だが一番の問題は奴なのだ。そう、三人の中で最も強力であろうイクセだ。あの電脳空間内での闘いの時のことを考えると、最大の脅威はイクセただ一人。
「どこだ・・イクセ」
「ここだよ」
「っ!?」
何が起こったのかセイアには判らない。気が付いた時、既に自分の身体が壁に減り込んでいたということだけしか、彼には知覚することが出来なかった。
イクセは笑っていた。今までセイアが立っていただろう場所で。奴は、セイアの背後から攻撃を仕掛けてきたのだ。
背後――ならいつ背後に回られたのか。常に背後にも注意を怠らなかった筈だというのに。
いや、少なくともレイを吹き飛ばした瞬間背後には誰もいなかった筈だ。つまり奴はレイを捌き、イクセの姿を捜した半瞬の中で自分の後ろに回ってきたことになる。
「くっ・・・っ」
「ほら早く起き上がってきなよ。まさか優しく叩いただけでギブアップなんてことはないよね、セイア?
強くなったんでしょう。その力を見せてよ」
ソウル・ボディやダーク・ホールド等という小細工では決してない。奴は純粋なスピードで背後に回ってきたのだ。
それは奴の口ぶりから察せられる。奴の性格上何か小細工をすれば糞真面目に解説を寄越す筈なのだから。
セイアはバラッと崩れた壁によって地面に放り出された。なんとか手をついて持ち直すが、イクセの元には既にイクスとレイが戻ってきているのが見える。
セイアは戦慄した。やはり奴等は強い。強すぎる。電脳空間内でイクセに勝てたのは、クロス・アーマーのお蔭に過ぎなかったのだ。
次に三対一で攻められれば防ぐ手立てはない。その気になればイクセはいつでもセイアの首を刎ねることが出来るのだ。
「イクスとレイを捌いていたらイクセを躱しきれない・・。どうすれば・・」
「驚いた。まさか俺とレイを同時に捌くなんて離れ業をやってのけるなんてな。君は強くなった、セイア」
「だが小僧。調子に乗るなよ」
イクスのバスターとレイのセイバーがセイアを粉砕しようと再び向けられる。
セイアはくっと息を飲みながらに思考した。奴等全員を一気にの捌ききる為に必要な技は、特殊武器はなんだ。
考えろ。考えろ。考えろ。よく考えれば必ず何か手がある筈だ。何か。
「イクス兄さん、レイ兄さん!」
が、セイアの思考とイクスとレイの闘気を止めたのは意外にもイクセの声だった。
突然呼ばれたことに驚く二人をよそに、イクセはつかつかと数歩前に出た。
セイアとイクセの視線がぶつかり合う。こうしているとまるで内側全てを見透かされたような可笑しな気分になってくる。
そして同時に言い様のない嫌悪感が走る。やはりイクセの云うとおり、人――セイアはレプリロイドだが――は自分を見ると不愉快になる・・のだろうか。
「ふふん、セイア。強くなったのはいいけど、やっぱり三人同時に相手にするのは君でも不可能みたいだね」
「・・その気になれば一人でも充分みたいな云い方だな」
「そういったつもりはないんだけど、不愉快にさせたなら謝るよ。っと、ここで一つ提案があるんだ」
「提案?」
「そう。ねえ兄さん達、ボクにセイアと一対一で闘わせて貰えないかな?」
視線を向けられた二人は顔を見合わせたか、拒否の意思はないらしかった。
「好きにしろ。どうせ結果は変わらない」
「ただし、俺達にも暇つぶしさせて貰うよ」
「ふふ、こっちの方は承諾したみたいだね。君はどうだい、セイア?」
再び視線がセイアへと向く。その視線から提案の意味を見出せないセイアは再び身構えた。
相変わらず人を小馬鹿にしたように笑うイクセは構えすら取らない。それが気に入らなくて、セイアは思わず声を荒らげた。
「相手が貴様一人だろうがどうでもいい!ボクと闘いたいんだろ、早くかかってきたらどうだ!?」
「全く君って人はどうしていつもいつもこう興奮するのかな。まあ当然だろうね。ボクが君を見て滑稽だと思うように、君もボクを見て不愉快になってる」
「だ、黙れ!!」
「ふふ。サシの勝負の始まりだ。全力でかかっておいでよ、宿主!」
セイアの放った蒼と紅のチャージ・ショットは反対側から放たれた全く同出力のエネルギーによって相殺された。
それが弾けるとほぼ同時に真っ向から突っ込んでいく両者。セイアのゼット・セイバーとイクセのサーベルが凄まじい余波を辺りに吐き散らしながらに激突した。
その余波はトレーニングルームの防護ガラスに風圧だけでヒビを入れる程だ。
隅っこでことの顛末を見届けていくウィドは、危うくそれだけで吹き飛ばされてしまいになった。
「イクセ・・!」
「楽しいよセイア。君とこうして闘っている時だけ、ボクはボク自身の存在意義を見出すことが出来るんだ」
セイアの左の拳とイクセの右の拳がぶつかりあう。ガン、ガン、ガン。三回拳がぶつかった次の瞬間には、
セイアとイクセの両者の膝が凄まじい金属音を響かせながら拮抗していた。その威力においては両者ともにほぼ同等だったが、
一手イクセの方が素早かった。イクセの強烈なブロウを頬に受けて、セイアはロケットのような衝撃と共に後方へと吹っ飛んだ。
クルリと空中で姿勢を整え、後方に壁に着地する。
つーっと口の端からオイルが垂れてくるのが判った。それをグイッと拭い取ったセイアは、必要以上に息を荒らげていく自分に気が付いた。
体力を消耗しているわけではない。単に興奮しているに過ぎないのだ。殴り飛ばされたことでほんの少し平静を取り戻したセイアは、
今の自分の状況にようやく気が付いた。
「君はイレギュラー・ハンターとしてボクと闘っているかもしれない。もしかしたら感情だけで闘っているかもしれない。
或いはワイリーの遺産であるボクを倒す為かもしれない。どれにせよ君は大義名分を持っている。
感情的になるのはボクが君と同じ姿、同じ声をしているからに過ぎないよ」
「・・何の話しだ。大体、貴様等の本当の目的は一体なんなんだ」
記憶の底に眠る長い金の髪の青年に叱り飛ばされた気がして、セイアの呼吸が鎮まりを見せ始めた。
それに伴って言動も少しずつ感情的なものから分析的なものへと変わっていく。
セイアのその様子に感心したのか驚いたのか、イクセはパチパチと瞬きをしたあと、ニコリと笑って続けた。
「へぇ、少しは真面な会話が出来るようになったみたいだね。・・なんて軽口を叩くとまた君がお話をしてくれなくなっちゃうから、話を続けようか」
イクセの姿が消えた。それに続いてセイアもその場から瞬発的に跳ぶ。
目にも止まらぬ早さで振り下ろされたイクセのサーベルが裂いたのはセイアの残像だけだった。
瞬時に真後ろに回り込んだセイアは超至近距離で特大のチャージ・ショットを放つが、それを貫いたのもイクセの残像のみ。
すぐに頭上を見上げたセイアは空中で波動拳を放とうとエネルギーを集中させるイクセの姿に、
渾身の力を込めた神龍拳を打ち上げた!
「君はボク達の目的を知りたいらしいね。それについて教えて上げようか」
「くっ・・・!」
神龍拳の出よりも波動拳の方が半瞬早かった。波動拳によって地面へと逆戻りさせられたセイアは再び跳躍し、イクセの懐へと飛び込む。
その場で拳と蹴りの応酬が巻き起こった。もはやA級の凄腕ハンターですら捉えられない程のスピード。
端から見ればほぼ互角の打ち合いに見えることだろう。けれど実際にはイクセの方が数段素早かった。
「ボク達の・・デス・リミテッドの開発コンセプトは君も知っての通りエックスの抹殺だ。
ワイリーはデス・リミテッドを自分に使用して更に強力な力を得ようと考えていた。
けど、目的は既に達されている。エックスは既にこの世にいないんだから」
「なら何故貴様等はまだこうして存在しているんだ!それともワイリーを倒したボクに復讐したいって云うのか!?」
「半分正解で半分は間違い。元来リミテッドに個々の意思はない。ボクがこうして話しているのも君という宿主が元になっているからに過ぎない。
じゃあボク達の目的は一体何なのか。答えを云っちゃうとそんなものは・・ない」
「無い・・だと・・・・ぐあっ!!」
遂にセイアのラッシュの勢いが競り負けた。イクセの強烈なパンチ・ラッシュを全身に叩き込まれたセイアは地面に転がった。
所々のアーマーが割れ、破片が飛び散る。破壊された箇所がバチバチとスパークを上げる様は、最強のハンターとしては何と情けないことだろう。
イクセはゆっくりとセイアへと歩み寄ってきた。ここでバスターを放てば勝負がつこうものを、彼はそれをせずに話を続ける。
「そう。無いんだ。ボク達に確固たる目的なんて、ね。強いて言うなら君と闘うことかな」
「ボクと闘うことが目的って・・どういうことだ」
「君が強いからさ。ボクの基本人格は君を元にしているから、必然的にボク達は強い者を求める。闘いたいんだよ、凄くね」
「ボクが、ボクが闘いを求めているとでも云うのか!?」
立ち上がり、拳を捻り込むセイア。だがその拳はいとも簡単に受け止められた。
ギリッとアーマーが軋むほどの握力が込められる。そのまま腕を砕かれてしまうような錯覚を覚え、セイアは思わず呻いた。
「ぐっ・・・ぁっ」
「君だって気付いてる筈だ。イレギュラー・ハンターを続けていく内に、リミート・レプリロイドと闘ううちに。そしてワイリーを倒し。
闘うために少しずつ少しずつ理由を捜し始める。飛び散る血だけを見たくなってくるのさ」
「ボクが・・戦闘狂だって・・云うのか」
「別に恥ずべきことじゃあないよ。闘いの中で高揚を覚えるのは戦闘者の特徴だからね。君のゼロ兄さんだって立派な戦闘狂だった。
そしてそんな君から生まれたボク達も、闘いを生きがいにしている」
戦闘狂――そう云われて初めて、闘いの中で高揚を覚え始めていた自分を自覚する。
強い敵と闘う度に。自分が強くなっていく度に。どうしようもない高揚を知る自分。
ハンターとして。エックスとゼロの弟として。イレギュラーを、リミート・レプリロイドを倒してきた。
そして今、目の前のデス・リミテッド達を倒そうとしている。それは何故だ。ワイリーの遺産を倒す為か、相手がイレギュラーだからか。
違う――自分は、自分はリミテッド達との闘いを楽しんで・・いるのか?
「別にエックスもゼロもワイリーも、何もかももうどうでもいいんだよ。こうして君と対峙する瞬間がボクにとって最も大切なんだ。
どんどん強くなる君と闘って、闘って、闘って。君を侵食し始めている腐食部分こそボク自身なのさ!」
「腐食部分・・!?」
「君だってとっくに理解している筈だよ、セイア。レプリロイドのためとか、
人間のためとか、そうやって理由をつけて闘う内に心のどこかが確実に腐り始めていることを。
もう素直になったらどうだい。ボクは今まで君が闘ってきた者達の中で最も強い。君の欲求を最も満たすことは出来るのは、このボクだ」
自分の欲求。それは強い者と闘うことなのか。それとも、本当にエックスとゼロの意思をつぐことなのか。
その答えは――ほんの昨日までなら胸を張って答えられただろう答えは、今となっては口を動かしてはくれない。
迷っているのだ。目の前の自分と同じ顔のイレギュラーに核心をつかれ、セイア自身が把握していない自分を曝け出され、困惑しているのだ。
セイアの拳を押し込む力が弱まった。それを見計らったようにイクセのバスターがセイアの胴に叩き付けられ、彼の身体を数m吹き飛ばし、
床へと転がせる。つかつかと歩み寄ってくるイクセの姿を見据えつつも、セイアは立ち上がることが出来なかった。
「頑固者だな、君は。それとも自分で思ってたほど自分が綺麗な存在じゃなくて困惑しているのかな。
どっちにしても手加減はしないけどね。どうせボクが本気で君を殺そうとすれば、君は真の姿を曝け出す」
「あ・・・あ・・ぁ」
立ち上がることも、バスターを向けることも出来ないまま、セイアは身を退け始めてしまった。
さっきまで全身を包んでいた闘気も、鋭く射抜く眼光もそこにはない。ただ認めたくないものを眼前に突き付けられたちっぽけな少年が、
その事実に脅えているだけだった。セイアにもう戦意はない。それを判った上で、イクセはサーベルを喉元へと添えた。
もう逃げられない。イクセがほんの少しサーベルを押し込むだけで、自分は死ぬのだ。
こんな状況になっても殺意も戦意も沸いてこない。戦闘狂ならば、こんな時どうするのだろう。ついこの前の自分なら、立ち上がって闘っていた筈だ。
自分は戦闘狂でもなければ、盲目的に自分の意思を信じる強者でもない。それを理解したとき、イクセはサーベルを振りかぶっていた。
「安心しなよ。すぐには殺さない。もっともっと君の真の強さを見せてもらうよ。・・どんな手を使ってでもね」
「――・・!」
「さぁ見せてみろ。最強の戦闘狂の力を!」
が、イクセの斬撃は中断された。中断せざるをえなかった。
イクセは振り向いた。自らの背から立ち昇る煙を見たあとに、それの原因となった人物を、銃口を見る。
ウィドだった。震える手でレーザー銃を握り締め、それでも強い瞳でこちらを見据えている。
突然の飛び入りに口の端をつり上げるイクセと、驚いたまま目を見開くセイア。ウィドが最初に呼んだ名は、情けない親友の名だった。
「セイア!!」
「・・・ウィ、ド」
「何をしているんだセイア。そんな奴の口車に乗って、それで戦意喪失か。よく思い出せ、お前はいつだってエックスとゼロの意思を継いで闘うと云っていた筈だ。
学校の友達が常に笑っていられる世界にしたいと云っていた筈だ。その言葉は嘘だったのか、ただの口先から出たポーズに過ぎなかったのか。答えろセイア!!」
その台詞に、セイアは頭をガンと殴りつけられた気がした。今まで光を失っていたセイアの瞳に、一瞬にして炎が舞い戻る。
セイアは立ち上がった。立ち上がると共に拳をイクセの頬に叩き付ける。そして怯んだ矢先に鳩尾に膝を入れ、屈んだ上に強力なチャージ・ショットを叩き付ける。
セイアの闘気が舞い戻っていた。さっきと同じ、いやそれ以上の闘気が。
対してイクセは怯んだ姿勢のまま顔を上げた。今までとは違う、狂気的な笑みがそこにあった。
「そうだ・・。ボクは、ボクはロックマン・エックスとゼロの弟だ。彼等の意思を継ぐ者だ。ボクには兄さん達に託された希望がある。
ボクは・・ボクは戦闘狂なんかじゃない。イレギュラー・ハンター・・ロックマン・セイヴァーだ!
そしてイクセ、お前は・・イレギュラーだ!」
「ふふふふふ、はははははは。あーっはっはっはっはっは」
エックスは死んだ。ゼロも、もはやセイアの目の前にはいない。
そうだ。地球を幾度となく護ってきた英雄はもういない。同時に自分を叱り付けてくれる者も、護ってくれる者も、不始末を拭ってくれる者もいない。
そして――自分の代わりに闘ってくれる人もいない。
エックスは死ぬ直前になんと云ったのだろう。セイアは燃え上がる戦意の中でも、薄らとそれを思い出す。
『お前は俺の弟だ』
それが絶対の言葉。ロックマン・エックスが。英雄が。何より兄が自分に向かって云った言葉。
それを思い出して、セイアはやっと理解した。イクセの言葉なんかより、余程盲目的に信じてきたのはいつだって兄の姿だった。
確かに云われてみればセイアは戦闘に身を置くことが多い。闘うことは嫌いではないし、もっと強くなりたいといつだって思う。
けれどそれは闘うために理由を捜しているのではない。エックスのように、ゼロのようになりたかったのだ。
既に皆からエックスとゼロを越えたと称賛されるセイアだが、自分ではそんなこと微塵も思ってはいない。
だから強くなりたかった。闘って闘って闘い抜いて、強くなりたかった。兄に追い付きたかった。
そう、イレギュラー・ハンターとして。イレギュラーを・・倒すために!
「あははは。まさかウィド君のそんな一言で闘志が蘇るなんて思ってもみなかったよ。そのまま大人しくしていれば楽に死ねたのにさ。
全く、君はいつもいつも邪魔ばかりしてくれるね、ウィド・ラグナーク。あの電脳世界での闘いの時もそうだった」
「貴様なんかにセイアをやらせてたまるか。セイアをここまで侮辱した罪は重いぞ」
「・・やっぱり君は邪魔者だ。その減らず口を、いい加減閉ざして上げるよ。
イクス兄さん、レイ兄さん。二人の暇つぶしは彼でいいかな?」
さっきまで一体どこにいたのか。イクセに名を呼ばれたイクセとレイは半瞬後にはウィドの背後に立っていた。
不意に現れた気配に振り返るウィド。すぐにレーザー銃を構えるが、イクスとレイはそれを見ても眉すら動かそうとしなかった。
「俺に異論はないな。レイはどうだ?」
「少々不満だが我慢してやろう。だがこの小僧を始末したらそっちに参加させて貰うぞ」
「はいはい。だけどボクも楽しみたいから、程々に焦らして上げてね」
とんでもないことをさらりと云ってのけ、イクセは再びセイアへとサーベルを向けた。
ウィドは一旦間合を取り、レーザー銃を構える。持っている武装はこれと、あとは懐に入っているビーム・メス程度だ。
どう考えても勝率は低い。が、もはや逃げ道はないのだ。
「ウィド!」
「おっと、君の相手はこのボクだよ。他人の心配していられるほど、余裕はないんじゃないかな」
「・・悔しいがそいつの云うとおりだ、セイア。コイツ等は俺が食い止める。お前はイクセを倒すことだけを考えろ」
「ほら。彼もそう云っていることだし、そろそろ第二ラウンドを始めようか。見せてよ、吹っ切れた君の力を!」
「くっ・・・!!」
そして再びセイアとイクセ、そしてウィドとイクスとレイの闘いが始まった。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
一方のハンターベースで、Dr.ゲイトは珍しく焦っていた。
他の隊員も同じように焦ってはいたが、事の重大さはゲイトが取り乱していることからも充分推測出来るだろう。
ともかくゲイトは焦っていた。セイアが行方不明になったこともあるが、それに続いてウィドまで姿を消してしまったからだ。
さっきまでベースの隅々までを捜したけれど、その姿はどこにもなかった。
喫茶室にも、オペレータルームにも、セイアの自室にも、総監室にも、談話室にもいない。
女性隊員に変態扱いされてまで女子トイレを捜索したが、彼の姿はどこにも見当たらなかった――というよりもそこで見つかることはそれはそれで問題だが――
結局焦りを残したままに研究室に戻ってきたゲイトは、奇妙なものを見つけた。
ウィドのモバイル端末だ。別にそれ自体には何の変哲もない端末だが、いつも彼はこれを持ち歩いている。
こんなところに置き去りにされているとは考えづらい。端末は電源が入りっぱなしで放置されていた。
彼の性格上有り得ない状態で置かれていた端末を、ゲイトは飛び込むようにして開き、そして焦りの上に驚愕を上乗せされた。
ディスプレイを開いた端末に表示されていたのは、メーラーだった。
送信者はイクセ。それはいうなれば脅迫状の類だった。
セイアを預かった。返して欲しくば旧ハンターベースまで来い。
そしてこれを最後の決戦としよう。要約すれば、こういった内容だ。
ゲイトは焦っていた。今の弱体化したイレギュラー・ハンターにセイア達の闘いに割って入れる程の実力者はいない。
だからといってゲイト自身にも彼等と闘う力はないだろう。ナイトメア・アーマーを使ったところで勝負は見えている。
ゲイトは考えた。考えたが、結論は出なかった。この状況を打破する考えは、天才と云われた彼ですら捻り出すことが出来なかった。
それでもふと考えたゲイトは、慌ててある物を捜した。が、それも無駄に終わった。
完成直前のクロス・アーマーのチップが消えていたのだ。恐らくウィドが持っていたのだろうが、
もしアレを使うようなことがあれば未だ不完全なアーマーはセイアの身体にも支障をきたすだろう。
もはや頼れるものはない。ガラにもなく勝ち目のない闘いに飛び込もうとすら考えたゲイトは、完全に手詰まりだった。
「なんてことだ。こんなことになるとは、やはりあの時セイアを向かわせるべきではなかったのか」
ゲイトの口から弱音が漏れたことをセイアが知れば、きっと飛び上がって驚くに違いない。
けれどそうなっても仕方がないのだ。ゲイトにはどうしようもなかったのだ。恐らくこのまま何も無ければ、ゲイトは闘いの場へと突っ込んでいったに違いない。
「こんなときに君達がいれば。エックス、ゼロ」
そんなゲイトの小さな願いも今となっては叶わない。
絶望的な感情に襲われ、ついに闘いの場へと向かおうと決意したゲイトを引き留めたのは、
意外にも突然ディスプレイに割り込んできた通信だった。
『君らしくもなく取り乱しているようですね、Dr.ゲイト』
「・・!き、君は」
特別セキュリティの厚いゲイトのメインコンピュータに苦もなく侵入した画面の向こうの科学者型レプリロイドは、
困惑するゲイトを見てそう云った。突然のショックでゲイトは驚いたが、そのお蔭でなんとか少し平静を取り戻すと、
ゲイトはディスプレイに向かってこう返した。
「・・『Dr.バーン』。君から連絡をよこすとは、全く予想外だね」
『なにせ非常事態ですからね』
「その様子では、ウィド君の端末のメールを読んだんだね。おおかたウィド君のメーラーに届いたメールは自分のところにも転送されるように仕組んでいたんだろう?」
『相変わらずあなたは勘がいいですね。その通りですが、今はそれよりあのリミテッド達への対処を考えましょう』
「君にしては一手遅かったね。もうセイアもウィド君もあっちで闘ってるよ。ボク達に出来ることはないんだ」
自分の口でそんな台詞を云うことに酷い嫌悪感を催しつつも、分析力の高いゲイトには紛れもない真実だった。
そしてゲイトがそう云った以上、その計算を疑うことはしないバーンは、それに対しては何も抗議をしないままに続けた。
『・・開発途中であった新アーマーは?』
「ウィド君が持っていってしまったよ。あのまま使えばセイアの身体にも異常が起きるというのに」
『ウィドが何か武器を持っていった様子は?』
「・・?いや、彼は自前のレーザー銃があるから、それ以外持っていった形跡はないよ」
『・・そうですか』
目に見えてバーンの顔が歪むんだのを、ゲイトは見逃さなかった。
「どうかしたのかい」
『気になることが一つ』
「気になること?」
『最近ウィドに変わった様子はありませんでしたか』
訊ねられ、ゲイトは顎に手を当てて思い返した。
ここ数日はウィドと研究室にこもっていたものだから、誰よりもウィドの様子を見ていた自信がある。
一日一日の記憶を遡り、注意深く分析していく。そしてその中からようやく共通点を見つけたゲイトは、半秒後にぽんと手を叩いた。
「そういえばしきりに右腕を抑えていたようだったよ。どうしたと聞いても、腕が疲れたとだけ云っていたけど」
『・・やはり』
「・・。やはり?今、やはりと云ったのかい?」
バーン自身も思わず漏らしてしまった言葉だったのだろう。一瞬しまったという顔をしたあと、彼は観念したように頷いた。
ゲイトと同等かそれ以上の科学力を持ち、冷静さも持ち合わせている彼にしては珍しい表情であったが故に、ゲイトも思わず眉をひそめる。
敢えて何も云わず、バーンが口を開くのをゲイトは待った。
『Dr.ゲイト。もしやとは思いますが、ウィドはセイヴァー君と共に出撃していたりは・・』
「残念だけどしているよ。彼のスナイプ能力はかなりのものだからね。セイアもそれで幾度か助けられたと云っていた」
『あのレーザー銃を使ったのですね』
「ウィド君がいつも持っているレーザー・ガンのことかい?アレはよく整備されていて、あのサイズでは考えられない程の出力を持ち合わせ・・」
そこまでいってゲイトはハッとした。あのレーザー銃はウィド自身が改造し、出力やら速射性やらを向上させたと聞いているが、
アレは元々人間用に出来ている武装であり、並の人間に扱えるギリギリのレベルを保たれたものだ。
ウィドは人間だ。今まで共に研究をしていたり、セイアと肩を並べてリミート・レプリロイド達と闘っていたことで失念していたが、
彼は間違いなく人間なのだ。彼の生立ちは遺伝子改造型人間だが、頭脳を除いて身体能力は抜群の運動神経以外並の人間と大差ないのだ。
そんな彼が人間が扱えるギリギリの武装を更に出力を上げて使用していたということは、つまり・・。
『忠告はしました。ウィドの身体強度ではあのレーザー銃を使い続けることは出来ないと。しかし、あの子は忠告を守らなかったようですね』
「Dr.バーン。もし、このままウィド君が決戦の中でレーザー銃を乱発した場合、一体・・?」
訊ねるまでもなかった。が、ゲイトは半ば縋っていたのかもしれなかった。
勝てる筈のない敵にセイアを奪われ、たった一人でウィドを向かわせ、その他のハンターは全く役立たず。
自分が行っても恐らく、いや確実になんの役にも立たないだろうこの状況で、ほんの少しでも救いを求めてしまう。
ゲイトはバーンにこう云って欲しかったのかもしれない。ウィドは大丈夫だ。セイアは無事に帰ってくる・・と。
だがゲイトが珍しく見せた弱音とは裏腹に現実とは無情なものである。バーンは俯き、フルフルと首を振った。
『今のままでも危険領域を出ないのです。もし、今回の敵を相手に最大出力の攻撃を加えた場合・・・』
「・・・・」
『最悪はウィド自身の身体が破壊され、再起不能になるでしょう。スナイパーとしても研究者としても。そして、人間としても――』
「――・・・!!」
ゲイトは声にならない声を上げながら目の前のコンパネに両拳を当てた。
コンパネは破壊され、バチバチとショートする回路が露出する。元々それ程頑丈に出来ていないゲイトの拳からもつっとオイルが零れ落ちた。
これがかつてナイトメア事件を引き起こした張本人とは思えない程に無様な姿を晒す彼に、バーンは何も云わなかった。いや、云えなかった。
彼がどれ程自らの息子に愛情を注いでいるか、一番よく知っているのはバーンかもしれなかったからだ。
知り合ったその日から、彼が自分の息子達に注ぐ愛情を知らずにはいられなかった。今それはロックマン・セイヴァーに、
そしてバーンの息子であるウィドをも対象として注がれていることも知っている。
『Dr.ゲイト・・・』
「なんてことだ・・!ボク達は彼等を助けることも出来ないだなんて!もう耐えきれない、ボクは・・!」
『Dr.ゲイト!』
条件は同じだというのに、冷静に物事を見詰めてしまう自分を、バーンは内心で嘲笑った。
バーンもゲイトと同じように息子達の為に感情を爆発させられたらどれだけいいのだろう。
大切な息子の為に無茶を云うことの出来るゲイトがいつも羨ましかった。
もしかしたらバーンはセイアのこともウィドのことも作品の一つとしか捉えていないのかもしれない――気づき始めてしまった自らの醜悪な本性を認めつつも、
バーンは冷静さを失うゲイトに声を荒らげた。
この科学者は、親友は優しい男だ。対して自分は何故これ程までに冷たいのだろう。
技術を互角以上に競いつつも決して越えることも出来ない壁を感じるバーンは、それから目を背けるようにゲイトを叱咤した。
『他のハンター隊員を向かわせることも出来ない者達を相手に、君は何をしようというのですか。
あなたがしようとしていることは絶望に耐えかねた自殺行為に過ぎません。彼等が無事に帰ってきたときのことを、あなたは考えていますか』
「・・・!」
バーンの口ぶりは酷く冷静であり、同時に冷めていたが、今のゲイトにはそれすら究極の正論に聞こえてしまう。
ゲイトはギリッと拳を握り締めたまま目を背けた。自分の無力さから、この絶望的な状況から逃げ出すように。
『リミテッド達を相手に通常のハンター隊員では死に行くだけのようなものです。そして今のあなたにはクロス・アーマーもない。
勿論私にもあなたにも彼等を止める力はない。ならば、信じて待つしかありません』
「・・信じて、待つ・・」
『えぇ。信じましょう。ロックマン・セイヴァーとウィドを』
言い放ったバーンをよそに、ゲイトはもう一度コンパネを叩いた。
今度こそ止めを刺されたコンパネは完全に破壊されて、ディスプレイに映されていたバーンの顔も消え去る。通信も途絶えてしまったようだった。
「――エックス、ゼロ・・」
ゲイトは生まれて初めて祈った。神にではなく、かつての英雄達に――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「くっ・・!」
「遅いな。やはり人間風情ではこれが限界か」
瞬時に二連射された光の線は、双方二つの目標に到達する寸前にそれを失い、虚しく虚空を裂く。
完全に捉えた筈の狙撃なのだが、彼等はそんな常識など知ったことではないと云うように、
半瞬後にはウィドの懐まで飛び込んできていた。
「違うよ。単にこれが俺達と彼の決定的差・・ってことさ!」
「ちっ!」
しかしウィドの反応もそれに負けじと素早い。もう片手に握り締めていたビーム・メスの刃で、捻り込まれるイクスの拳を受ける。
が、押し切られた。圧倒的な衝撃エネルギーを加えられたウィドはそのままロケットのような勢いで後方へと吹き飛び、
まだ奇跡的に無事だったトレーニングルームの壁へと叩き付けられる。
呼吸が止まる程の鋭い痛み。ずるりと床に滑り落ち、膝をついたウィドだったが、骨折がないことを幸いとしながら足腰に力を込めた。
ここで例え一秒でも倒れているわけにはいかないのだ。奴等相手に、その一瞬の隙でさえ命取りとなる。
「・・一瞬は早く俺の拳をビーム・メスで受け止め、ダメージ覚悟で受け止めたのか?」
「いや、それだけじゃあない。自ら後ろに跳んで衝撃を大きく半減したようだ。この小僧、動きだけはなかなかのものだ」
「勝手な・・勝手なことを云いやがって」
ペッと口の中に溜まったものを吐き出す。血とも唾液とも云えないものがべちょっと床に粘り付く。
多分喉の粘膜まで吐き出してしまったんだろうという錯覚に陥りつつも、ウィドはそれに気を配ることすら許されない。
再びレーザー銃を正面に構え、もう片手でビーム・メスを握り締める。このまま二対一で闘った場合、勝率はほぼ零に等しいだろう。
それでもこうして構えることしか出来ないのだ。死ぬまでの時間を伸す為なのか、それとも零に等しい勝率に期待しているのか。
それはウィド自身にも判らないし、そんなことを考えている余裕もない。けれど、一つだけ確かなことがあった。
「ただの人間の少年だと思っていたけど、この暇つぶしはかなり楽しめそうだよレイ」
「お前も相変わらず余興好きだな。確かに動きがいいことは認めるが、この程度の小僧を殺すことなど造作もないこと」
「君もよく云うよレイ。だったら最初の一撃で首を斬ってしまえば良かったのに」
「ふんっ・・」
以前セイアからリミテッドのデータを採取し、過去のデータベースにアクセスしたとき、
リミテッド体或いはリミート・レプリロイドについての考察が幾つかあったことを思い出す。
その大半はリミテッドによるパワーアップ率や変化等を示した文章であり、ウィドにとってどうでもいいことであったが、
その中でも彼の目を引くものが一つだけあった。そう、奴等の弱点だ。
セイアにも既に伝えているが、奴等リミテッド体の動力源は全て体内のリミテッドだ。
セイアに取り付いたものと同じデス・リミテッドの塊を中心にその全身を形成している故、それを破壊すればその形を留めることが出来ずに崩壊する。
「俺は貴様等の玩具ではない・・!」
ウィドは思う。奴等が自分との闘いを長引かせ、楽しんでいるうちが最大のチャンスであると。
スパイダス・リミテッドとの闘いから、このレーザー銃の出力で充分デス・リミテッドを破壊することが可能だということが判っている。
奴等の弱点は頭部だ。頭部にこのレーザーを一撃でも加えることが出来れば・・ウィドの勝ちだ。
「いいだろう、イクス。お前の余興にもう少し付き合ってやろう。しかし飽きたら即座に殺すぞ」
「はいはい、判ってますよ。さて準備はいいかい、ウィド君。次はもう少し優しくいくから安心するといい」
「そうやって遊んでいられる内が華だな、イクス・・レイ!」
端から見れば完全に負け惜しみの一言を、ウィドは躊躇いもなく吐く。普段の彼ならばそんな負け犬じみた言葉は吐かないだろう。
これは計算だった。敢えて負け惜しみの言葉を放つことで、相手に優越感を与え、遊びの範囲を伸すことでチャンスを待つのだ。
たった一発――いや二発だろうか――奴等の頭部にレーザーを撃ち込むことが出来れば・・。
そのチャンスまでなんとしてでも生き延びなければ。
ウィドは部屋の反対側で闘っているセイアとイクセの方をチラリと見た。
――セイア・・頼んだぞ。
「余所見をしていて次が躱せるかな、ウィド君!」
イクスの声にハッとしたウィドは、直ぐ様身を躱した。イクスのチャージ・ショットとレイの電刃零が同時にウィドの足元を掘り返す。
その光景に内心で肝を冷やすが、着地までの僅かな時間までをも奴等は許さない。空中からのレイの踵落しを受け、ウィドは地面に激突した。
いや、直前でバック転によって衝撃を殺し、受け身を取っていた。だが再び足が地面につく前にイクスの肘打ちを腹部に押し込まれ、
ウィドは溜まらずに腹部を抑えて踞った。
「っ・・くっ・・・・・!」
人間というものは脆いものだとウィドは思う。これがセイアならばどうということはない衝撃だろうに、人間であるウィドは視界がぶれ始めている。
顎先を蹴り上げられ、仰向けになって床を滑る。安定感が殆どない身体を起こすが、軽い脳震盪を起こしているのか上手く立ち上がれない。
セイアとイクセの闘いがふとぶれた視界に入る。いい勝負だ。いや、いい勝負というよりもどんどんセイアの力が増しているように見える。
もしかしたらまだセイアの体内にリミテッドが残っているのかもしれない。だとしたら、このままでもイクセに勝てるだろう。
その一方で自分のこの様はなんだ。弱点を知っていてもそれを突くことも出来ない、弱い自分。
相手がリミテッド体という強力な相手だからという言い訳は通用しない。これは殺し合いなのだ。負けた者は死ぬしかない。
ランク分けされたトレーニングとは違うのだ。
「ほらほら、早く立ち上がりなよ。このまま君を蒸発させることも出来るんだぜ?」
「お前が強く殴りすぎた所為だ。このまま呼吸困難で死ぬかもしれんぞ」
相変わらず勝手なことを云う二人だ。ウィドは咽せる胸を押さえ込みつつ心の中で毒づいた。
本当に残酷で、勝手な二人・・二人・・・――二人?
「・・・?」
ようやく視界が安定し始めたというのに、ウィドは立ち上がることも忘れて目を擦った。
イクスとレイ。確かに二人だ。だが、今の一瞬チラリと三人目が見えたような気がしたのは錯覚なのだろうか。
イクセでもセイアでもない三人目。無論自分でもなければ、イクスとレイの姿がだぶっての幻覚でもない三人目の姿。
「アレは・・一体・・」
イクスとレイは気が付いていないようだ。ウィドはもう一度大きく咳き込んでから、涙で揺れる視界のままになんとか身体を持ち上げた。
もういない三人目。ほんの一瞬だけ、イクスとレイの頭上の壁に貼り付いていたような・・気がするのだが・・。
「お、立ったね。さあウィド君。こっちから攻めるのだけでは申しわけなくなってきた。次は君から撃ってくるといい」
「貴様・・!」
「撃てるチャンスがある内に撃った方がいい、小僧。バラバラになった後ではトリガーを引くことも出来ないのだからな」
「舐めやがって!」
腕を振り上げる様に二発!ウィドのレーザー銃が吠えた。狙うはイクスとレイの頭部。デス・リミテッド本体だ。
が、やはり当たらない。直撃する寸前で残像となった二人の姿を砕くだけで、奴等はまたウィドの視界の外まで瞬時に飛び出した。
ウィドはすぐに後ろへ跳んで壁に背をつけた。これなら正面と頭上からしか攻撃を加えられることはない。
ほんの少しでも動きを捉えられる可能性が高くなるからだ。
頭上と正面に向けてウィドは撃った。攻めてくるべく場所が二箇所しかない上、奴等の実力を考えればタイミングが速過ぎるということはない筈だ。
手応えは――ある。が、軽い。正面に現れたのはレイだ。
振り上げるレイのセイバーの龍炎刃がウィドを襲う!ウィドはもう片手のメスで燃え沸るセイバーを受け止めた!
「くうっ・・・!?」
「飛び上がれ。宇宙船のようにな」
セイバーが身体に食い込むことは阻止出来ても、レイの腕力を相殺することなど出来ない。
文字どおり宇宙船のような圧力で空へと放り出されたウィドは、なんとか空中姿勢を立て直しつつも思った。
――まずい。このままでは空中で待機しているだろうイクスに追い打ちをかけられて・・。
「・・・!?」
が、ウィドは追い打ちを喰らうことなく天井に着地――着天というべきか――した。
そのまま身体が落下する際に壁にメスを突き刺し、体制を維持する。打ち上げたレイ自身も意外だったのか、見下ろした彼の顔は珍しく驚いた風だった。
「どうした、何をしているイクス!冗談はやめて出てこい」
「・・何・・?」
「イクス!返事をしろ、イクス!」
レイは狼狽していた。冷静沈着な彼とは思えぬ口ぶりだが無理もないと云えるだろう。
ここにイクスがいなくなる要素など何も無いからだ。セイアはイクセと闘うことに夢中だし、ウィドがイクスを倒すことなどほぼ不可能だ。
更に本人の冗談でもないとすれば、それは有り得ないことであり、計算高い彼が驚いてしまうのも納得だ。
計算高い者故の脆さだ。百%と自分で計算したものが意外にも失敗したりすると、計算高い者は驚く程狼狽える。
レイも例外ではなかったらしい。ウィドを舐めきっているのか、はたまたイクスという存在が彼の中でそれ程までに大きいのか、
レイは頭上のウィドを放ってイクスの姿を捜し始めた。
「馬鹿な、どこへ行ったと云うのだ!?イクス!」
そしてウィドは見た。いや、見上げた。ポタリポタリと頭上から滑り落ちてくる何かの液体を。
血液か?いや、これはオイルだ。匂いと滑り方でよく判る。
「イクス・・・!」
ウィドは思わず叫んでしまった。別にレプリロイドがオイルを流すところを見るのが苦手なわけではない。
単に信じられない光景がそこにあったからだ。それを先に見つけてしまったウィドは、レイと同じように口をポカンと開けた。
それはイクスだった。天井に頭部をビーム・セイバーでくし刺しにされ、ぷらんぷらんと身体を揺らす・・イクス。
機能は完全に停止している。当たり前だろう。弱点である頭部を完膚無きまでに貫かれているのだから。
・・・やがてビーム・セイバーのエネルギーが消失し、ぼとりと力無くイクスが地面にばらまかれた。
「・・!い、イクス・・・」
レイは呆然と落下してきたイクスの亡骸を見詰めていた。ウィドもそれを呆然と見る。
一体、何が起こったのだろう――セイアと自分は少なくとも何もしていない筈だ。なら、一体誰がイクスを仕留めたのか。
「ま、まさか・・さっきの・・!!」
それしか考えられなかった。ぶれる視界の中で見た『三人目』。奴が、奴がイクスを仕留めたのだ。
馬鹿げた発想だが、これしか考えられなかった。自分とセイアの力を合計しても、今の一瞬でイクスを仕留めることなど出来はしない。
「だとしたら、今しかない!」
その『三人目』が仮に本当に存在しそれが味方だったとして――ウィドはそこで思考を切る。
壁に突き刺して身体を支えていたビーム・メスを引き抜き、自由落下に身を任せる。
レイが狼狽えている今が最大のチャンスなのだ。今の一瞬でレイの頭部を撃ち抜けば、ほぼ零の勝率が自分に傾いてくれる。
ウィドはレーザー銃に備えつけられたダイヤルを捻る。出力をノーマルからマキシマムに移行。
この一撃に全てをかけるのだ。失敗は・・許されない!
「レイ!!」
「小僧!貴様ぁぁぁ!!」
ウィドは着地すると同時に銃を構えた!が、憤慨したレイのセイバーの方が一手素早い!
奴の居合は超高速だ。ウィドが引き金を引くよりも先にウィドを斬るなど造作もないこと。しかしウィドは躊躇うことも、身を躱すこともなかった。
「ウィド!!」
蒼と紅の閃光が迸った。部屋の正反対から飛んできた超密度のエネルギー波は、今まさにウィドを斬り裂こうとするレイのセイバーを彼の腕ごと吹き飛ばす。
イクセと闘いながらもセイアはずっと見ていたのだ。ウィドとレイの闘いを。そして放った。ウィドがレイを倒すことの出来る一瞬を作るために!
「セイア、貴様!?」
「勝負だレイ!!」
『いいですか、ウィド。もしその銃を使い続けるようなことがあれば、人の身であるあなたの身体は・・・――』
いつか父に言付けられた場面を想う。だが、そんな父の言葉ですら今のウィドを止めることなど出来なかった。
心無しかスローモーションに見える世界の中で、ウィドの指がトリガーを引く。
銃口にほんの半瞬、光が収束し始めたと思うと、一瞬後に極太の光の線が空を駆けた。
「――・・・!」
ウィドとレイ、二人の声にならない悲鳴が大気を震わせる。そして同時にレイの頭部がレーザーによって撃ち抜かれた・・いや、吹き飛ばされた。
ウィドとレイ。二人の身体が殆ど同じタイミングで地面に崩れ落ちる。頭部を失ったレイは痙攣しながら。
放った右腕の骨の殆どが砕けたウィドは絶叫しながら。
「ぐっ・・あああぁぁあぁぁぁぁぁっ!!」
ウィドの悲痛な叫びが、旧ハンターベースのトレーニングルームに木霊するその様は、つい先日までの世界とは裏腹に地獄のようだった。
骨が弾け、皮膚が破裂した右腕から鮮血の噴水が勢いよく噴出し、破壊されたトレーニングルームの床を朱に染める。
それはまさに酷い光景だった。絶叫を続け、右腕から止めどなく流血するウィドの傍らには、頭部を貫かれたイクスと、頭そのものを失ったレイ。
ビクビクと未だ痙攣する二体のリミテッドの痛みすら代返するように、ウィドは肺が壊れてしまうのではないかと思う程に絶叫し続けた。
「ああぁあぁあぁぁぁっあぁっぁっぁ!!」
「ウィド!ウィドぉ!!」
セイアのウィドを呼ぶ声すら彼には届かない。やがて彼は握り締めていたビーム・メスを自分の右腕の傷口に押し付けた。
ジュゥゥと血液が蒸発する異臭を発しながら、その傷口はビーム・メスのエネルギーに焼かれる。そして出血が止まった。
想像を絶する痛みと高熱に苛まれたウィドは、その痛みのショック故か、それとももはや痛みすら感じないのか、はたまた声が枯れてしまったのか。
やがて口を閉じた。ごろりとセイアの方を向く首。そこに埋まっている眼球はヒクヒクと痙攣していて、口からは血とも唾液ともつかないものを垂れ流し、
それでも尚意識が繋がっているのか、彼は枯れきった声でセイアの名を呼んだのだった。
「セ・・・イ・・・ア」
「ウィド!今助け・・!」
「君の相手はこのボクだろう?間違えてもらっちゃあ困るね」
ウィドへと走り寄ろうとしたセイアに、イクセの強烈な飛びげりが決まる。その衝撃でウィドへの走路を断たれたセイアはくるくると空中で回転し、着地する。
その間にイクセはウィドを背にするように回り込んでいた。まるで苦しむウィドを助けられずに更に苦しむセイアを見て楽しむかのように。
「どけ・・イクセ」
「ふふふ。嫌だね」
「邪魔だ、どけぇ!!」
飛び込んだセイアのゼット・セイバーがイクセを真っ二つに斬り裂く。いや、寸前で全く同じものがそれを阻んでいた。
雄々しく猛るセイアのセイバーはイクセには届かない。さっきまでの差と較べれば確かに実力差は拮抗しつつあるが、
それでもイクセの方がほんの少し上回っている。容易く剣線を崩され、隙だらけとなった腹部にイクセのバスターが爆ぜた。
「くぅっ・・!!」
後方へと吹き飛ばされつつもセイアは諦めない。受け身を無視したフルムーンⅩ。
それがイクセの肩アーマーを吹き飛ばす。炸裂した――いや、炸裂していたのはセイアの方だ。
「――・・!?」
イクセと同じくセイアの肩アーマーも吹き飛んだ。いや、吹き飛んだなんて生優しいものではない。爆裂したのだ。
ウィル・レーザーの強烈な閃光がセイアの肩を掠め、それをこそぎ取っていた。アーマーを削られたイクセに対して、
肩を完全に破壊されたセイアの方がダメージは大きいのは当たり前だった。
よもやここまで読んでいるとは思わぬ切り返しに、セイアは思わず膝をつく。
ポタリポタリと肩から滑り落ちてくるオイルが床を濡らす。反対方向でウィドの流した鮮血が床を染める。
皮肉にも同じ右腕を破壊されたセイアとウィドの今の姿はなんと痛々しいことだろう。それでもイクセの辞書に容赦の文字は存在しえなかった。
「まさかイクス兄さんとレイ兄さんをウィド君が倒すなんて意外だったな。それとも何か奥の手を使ったのかな?
どっちにしろ・・・・君はこのまま死なせて上げないけれどね」
「やめ・・ろ・・」
イクセの感覚範囲にどうやら例の『三人目』は存在していなかったらしく、奴は二人をウィドが倒したと思い込んでいる。
勿論セイアも薄々その存在に気が付いていた。気が付いていたが、それが何かを考えよりも現状の方を優先したいのは明らかだった。
イクセの顔は歪んでいる。さっきまでの楽しそうな顔とは違う。まるで、まるでそう――Dr.ワイリーに兄を殺された瞬間のセイアのように。
奴は怒っているのだ。兄を殺されたことに。大切な兄を殺されたことに。セイアは、そんなイクセを見て思わずハッとしてしまった。
「痛いかい右腕が?でもね、そんなものじゃ済ませて上げない」
「ぐっ・・ああっ・・あ」
残酷無比な笑みと共に繰り出されるイクセの蹴りを受けても、もはや叫び声すら上げられないのか、ウィドは掠れた呻きを上げるだけだった。
既にボロボロだった全身に止めを差されたウィドの骨組は、ボキッと不気味な音を立てて断ち切られていく。
血を吐き、呻きを上げるウィド。セイアはそんなウィドを見詰めながら、ふらりと立ち上がった。もはや破壊された右肩のことなど気にならなかった。
「あはははははは。本当に、本当に計算外だった。君が、こんなひ弱な君が兄さん達を倒してしまうなんてねぇ!」
「やめろ・・・っ」
セイアのか細い制止の声を聞いたのか、それともウィドの姿をセイアに見せつける為か、イクセの動きがピタリと止まる。
そしてセイアに向かって笑った。冷たい笑みだった。きっと昨日までのセイアならそれだけで脅え、竦んでしまうかのような。
強烈なプレッシャーと威圧。そして、怒り――ぶらりと空を掻く右腕を抑えつつ、セイアはそれを認めた。
「「やめろ」だって?やめろって云ったのかい、セイア?」
「イ・・クセ!」
「ふふ、あはははは。コイツは大笑いだ。「やめろ」だって?君にそんなことが云えるのかい。君だってエックスを殺したワイリーに憤慨したくせに、
ボクにはやめろとほざくのか。正義の味方も所詮はエゴの塊だな!」
「っ・・!」
イクセの言葉は、間違ってなどいない。何故ならイクセの言葉は同時にセイアの迷いと直結するからだ。
一年前、セイアはワイリーを倒した。正義の為でも、ハンターの仕事の為でも、過去からの因縁の為でもない。
そうイクセの云うとおりエックスを殺したワイリーが憎かったからだ。全てを奴の所為にして、それを怒りと憎しみに任せて消し去りたかったからだ。
確かにイクセは敵だ。しかし同時に自分の分身でもある。兄を失った怒りと悲しみは、イクセとて同じこと――
セイアはここにきて迷ってしまった。ウィドを痛めつけるイクセの姿が完全に一年前の自分と重なってしまったからだ。
しかし気付きはしなかった。イクセを伐つことが出来なければ、セイアもまた一年前と同じ未熟者のままであるということを。
「よしよし良い子だ。この子を料理したらすぐに君も消して上げるよ。戦意喪失した君なんて、ただの鉄くず同然だからね」
「セ・・イア・・!ぐぁぁっ!!」
そしてまたイクセはウィドを痛めつけ始めた。砕けた右腕を足でふみつけ、蹴り上げ、ウィドの絶叫に笑みを浮かべる。
辺りにはウィドの流す鮮血が舞う。床を濡らし、壁を濡らし、イクセの頬を濡らす真っ赤な・・血。
それでもウィドはセイアを呼んでいた。それは助けを求める声でも、断末魔でもない。再びセイアの戦意を取り戻そうとする、必死の声だった。
「・・・・っ・・」
セイアは左手の拳を握り締めた。再びイクセに対しての怒りが込み上げてくる。
自分勝手な怒りだと、彼は自覚している。けれどそれを止められなかった。止めようともしなかった。
例え敵が自分と同じ立場にあったとしても・・敵は敵だ。奴はイレギュラーだ。セイアはハンターだ。
なら、倒すしかない。自分と同じだからといってイクセを哀れむことは・・許されないのだ!
「やめろ・・やめろ、イクセ!!」
セイアの左手のバスターが爆ぜた。蒼と紅の閃光は一つとなり、ウィドをけり続けるイクセの頭部を直撃し、その先の壁をも貫通して彼を外へと追いやる。
セイアは静かに歩み始めた。吹き飛んだイクセを無視し、もはや無残な姿へと変わったウィドを抱き起こす。
彼は、辛うじて生きていた。力のない手でセイアの左肩を掴むと、ウィドは血だらけの顔で笑った。
「馬鹿・・野郎・・。躊躇うなと、云っただろ・・う?」
「ウィド・・」
「躊躇うな・・。お前は、勝てる・・筈だ。アイツに・・」
一言話すことにも苦痛の表情を訴えるウィドの言葉は、最後までは紡がれなかった。それをイクセは許してくれなかったのだ。
ガラガラと瓦礫の中から姿を現わすイクセ。そしてウィドを静かに床に降ろし、ゼット・セイバーを構えるセイア。
ぼやけ始めている視界の中でウィドは思う。最後の決着が今まさにつこうとしている、と。
「セイ・・ア」
「・・判ってる」
「どうやらそんなに先に料理して欲しいみたいだね。なら、もう遠慮なく首を斬らせて貰うよセイア!!」
「イクセ、もう終わりにしよう。貴様を倒す!」
そしてセイアとイクセの姿がその瞬間、掻き消えた。
「セイアっ!!」
「イクセっ!!」
紅の鎧と翠の鎧が交差した。
そして静寂。
「・・・ぐあっ・・・!!」
先に伏したのはセイアの方だった。胸を袈裟切りにザックリと斬り裂かれ、真っ赤なオイルを噴出させながら。
膝をつき、掌をつく。もはや戦闘不能。振り返り、認めたイクセは・・立っていた。
「ふふふふ・・」
イクセは笑っていた。セイアを見下すように。ウィドを見下すように。自らの勝利を誇示するように。
「あーはっはっはっはっはっ!!!」
「・・・もう、終わりだ」
ウィドが呟いたその言葉は、己等の終焉に向けてなのか、彼の破滅に向けてか。
間もなくその言葉は確かに現実のものとなる。床に伏したセイアは、その終わりを確かに見た。
「ははは・・・あははははははは!!」
「・・・イク・・セ」
狂ったように笑うイクセの胴に、不意に斬り傷が走る。いや、胴が裂けた。
上半身と下半身に瞬時に両断されたイクセは、その笑い声を止めぬまま、やがて・・爆裂した。
彼に相応しい終わりだったのかもしれない。もしかしたらあっけない終わりだったのかもしれない。
けれどそれを意識することはセイアもウィドもしなかった。イクスが倒れ、レイが倒れ、イクセが倒れ。
勝つことはほぼ不可能だと云われていた最凶の三人は、伏したのだ。事実はたったそれだけで良かった。
「ウィド・・・っ」
ぼろりとヘルメットが崩れ落ちることも気にせず、セイアはよろよろとウィドの元へと向かう。
その無残な姿とは裏腹に、ウィドは笑っていた。きっとアドレナリンやらの分泌でもう痛みを感じていないのだろうと、セイアは中途な知識ながらも思う。
ウィドを抱き起こす。ウィドはもはや自分で立つことが出来ない程に傷ついていた。砕けた右腕も・・もはや直視出来ない程に・・。
「ウィド、腕が・・・」
「こんなもん、義手にでもなんでもすればいい・・さ。生きてれば・・な」
「うん・・帰ろう。ベースに」
「・・あぁ」
しかし運命というものはいつだって非常なものだ。セイアもウィドもいつもそれを知っていたつもりでいたけれど、今回ばかりはそれを実感せずにはいられなかった。
ゴォッと風が吹いた。死の匂いを、オイルの匂いを、錆びの匂いを含んだ奇怪な風だった。
「なにっ・・!?」
セイアの呻きに似た悲鳴が、もはや絶望を思わせる悲鳴が響く中で、それは止まることを知らずに始動する。
倒れ伏した三体のリミテッド体・・イクス、レイ、イクセの身体がビクビクと痙攣したかと思うと、そこから粘液をまき散らす不気味なユニットが離脱する。
デス・リミテッド本体だ。呆然とするセイアとウィドはそれを撃つことすら出来ずに見送った。もしかしたらこれが最大のミスだったのかもしれない。
「あ・・ぁぁ・・」
「馬鹿・・な・・」
あっと言う間に一箇所に集まった三体のデス・リミテッドは・・互いが互いに組み合わさり、グチャリと不気味な音を立てながら一つとなった。
吹き飛ばされそうな程の死の風が舞う。圧倒的なその存在に脅えるように、暗雲が空へと立ちこめ、強烈な雷を鳴らす。
あたかも空間自体がそれに圧迫されているようだった。セイアもウィドも、今回ばかりは動けない。セイアとウィド、そして空間自体が見守る中で、
それは静かに静かに形を成した。これから始まる地獄を現わすかのような、地獄の番犬・ケルベロス。それが奴の姿だった。
「・・・ウィド、クロス・アーマーのチップを渡せ」
「・・・し、しかしアレはまだ未完成で・・」
「早くっ!!」
セイアの剣幕は異常だった。逆らえば強引に奪われかねないと悟り、ウィドはなんとか持ち上げた左手で懐から一枚のチップを取り出す。
クロス・アーマー。かつてセイアが電脳世界内でイクセと対峙した際に装着した鎧であり、ウィドとゲイトが対リミテッド用に開発した究極のアーマー。
秘められし力は未知数。未完成の現状でセイアに与える負担もまた未知数だが、セイアは悟ったのかもしれない。それでもこれを使わなければならない、と。
ケルベロスは――いや、デス・リミテッドは動かずにそれを待っていた。まるで何をしても無駄だと云うように、その瞳には余裕すら伺える。
静かにチップを腕に埋めたセイアは、もはや闘うことなど不可能な身体で立ち上がり、振り向かぬままに呟いた。
「ウィド・・先に帰っててくれ」
「なっ・・くっ・・ば、馬鹿な、セイア・・何を云って・・」
「今の君を護りながら闘うなんてボクには出来ない!君がいれば邪魔になるんだ!!」
それは事実以外の何者でもない。ウィドは黙ってしまった。
セイアはふと剣幕を緩め、声を和らげた。しかし、彼は最後まで振り向かなかった。
「・・・ボクは必ず帰る。だから、待っててくれウィド」
「セイ・・ア。俺はまだ、お前と何もしちゃ・・いない。闘ってばかりで・・ロクな思い出もない。学校・・っだって、まだ一年・・ある。
お前は・・お前は、エックス・・とゼロの跡を継ぐんだろ・・?こんなところで、死ぬなんて・・許さん・・ぞ」
――本当は喋ることだって辛かった筈だ。それでも一生懸命なウィドの言葉が、セイアは嬉しかった。
振り返れなかった。振り返れば、泣いてしまいそうだった。逃げ出してしまいたくなりそうだった。弱音を吐くことになりそうだった。
だからセイアは振り返らなかった。だから見ることもなかった。ウィドの瞳に浮かんだ涙を・・セイアは知らなかった。
「・・判ったよ。続きは、また後で話そう」
セイアが自らのアーマーから剥がした転送装置によって、ウィドは光に包まれた。
ウィドが最後にまた何か云っていたようだったが、もう聞こえない。振り向きそうになる衝動を必死で抑えつつ、セイアは云った。
「・・さよなら・・ウィド」
『友達ヘノオ別レハ済ンダノカ』
見計らったように、デス・リミテッドが口を開いた。イクセ達とは全く違う、酷く機械的な冷たい声。
セイアはキッと声と同じく感情のない瞳を見詰める。セイアの翠の瞳の眼光を受けた三つの首、六つの瞳は全く動じなかった。
『ソウイキリタツ必要ハナイ。スグニ彼モオ前ト同ジトコロヘ行クノダカラ』
「黙れ!貴様は、貴様はボクがこの命に代えてもここで倒す!それが・・貴様を生み出したボクの責任だ!」
『面白イ。ソノ死ニ損ナイノ身体デドコマデ闘エルカ、見セテモラオウカ』
「舐めるなぁ・・!」
セイアが腕の中に埋めたクロス・アーマーのチップを今まさに発現させようとした瞬間、それを制止するものがあった。
「セイヴァー。お前のそれは勇気とは云えない。そんな闘い方はただの無謀だと、エックスに教わらなかったのか」
セイアもデス・リミテッドも全く予測していなかった乱入者。一本の翠の閃光としてそれは、セイアとデス・リミテッドの間に静かに降り立った。
「ふんっ。随分と醜悪な姿になったものだな」
程なくそれは人型を形成し、デス・リミテッドを一瞥するとこう云った。振り返ったそれとセイアの視線がぶつかる。
それは意外なことにセイアに似た姿をしていた。いや、寧ろエックスに似ていると云った方がいいのだろう。
ボディカラーは・・そう、イクセ達と同じ翠色。肩アーマーと胴体部分の境が存在しない奇妙な鎧が特徴的で、顔には電撃の刺青が走っている。
一瞬また新たなリミテッド体が誕生したのかと身構えたセイアだったが、それが自分に向けての敵意を持っていないことから、
少なくとも敵ではないことを理解した。
「き、君は・・!?」
「これならまだあの生意気な三体の時の方がマシだった」
狼狽えるセイアを余所に、それは再びデス・リミテッドを卑下する。
怒ることも哀しむこともないデス・リミテッドはそんな蔑みなど一切気にせず、自らの評価だけを口にした。
『貴様・・オリジナルイクス。リターン・イクスダナ。裏デ暗躍シテイタノハ貴様ダッタノカ』
「暗躍とはご挨拶だ。二人の坊やに三人でかかった卑怯者共に云われる筋合いはない。
それに私と同じ顔をした奴がいては目障りだったのでね」
そしてリターン・イクスと呼ばれた彼はポイッとセイアに何かを投げ渡した。慌ててそれを受け取ると、意外なことにそれはエックス・サーベルに違いなかった。
慌てて自分のバックパックに手を伸す。今までゼット・セイバーだけを使っていたので気が付かなかったが、確かにそこにエックス・サーベルはなかった。
「無断で借用したお前のサーベルだ。今更だが返そう」
「し、しかしどうしてこれを・・」
しかし相変わらずリターン・イクスはセイアに素性を話さない。必死にリターン・イクスに何かを云おうとするセイアを無視して、
またリターン・イクスはデス・リミテッドへと向き直った。
『フン、マアイイ。大方リミテッドノ気配ヲ感ジテ現レタトイウコトカ。イイダロウ、貴様モ我ガ一部トシテクレル』
「生憎だがお断りだ。貴様のようなおぞましいだけの下等生物と一緒にされては困る」
『オリジナルイクス。貴様ハ優秀ナリミテッド体ダ。我ト融合スレバ今以上ノ力ヲ手ニ出来ルノダ、悪クナイ話ダロウ』
一連の話にセイアはついていけそうにもなかった。代わりにいつかデータベースで見た資料を思い出す。
『オリジナルイクス』。その言葉が脳内で反響する。いた。確かにデータベースに存在していたのだ。リターン・イクスという名の過去のリミテッド体が。
かつて・・そうデス・リミテッドの元となったリミテッド、並びにハイパー・リミテッドの騒動の際に生まれたエックスの分身・イクス。
一度はエックスとの闘いで敗北し、消滅したイクスだったが、再びハイパー・リミテッドの力によって復活を果たした。それがリターン・イクス。
「冗談。同じリミテッド戦士として貴様程癪に障る者はいない」
兄達からリターン・イクスについての話を聞いたことは一度もなかった。
しかしデータの上ではリターン・イクスはリミテッド騒動の最終決戦にて現れたシグマ・リミテッドとの闘いの際にエックス達に協力している。
その後の彼の行方は結局判らず終いであったが、今まさにここに存在していることだけは紛れもない事実だった。
「おいセイヴァー。力を貸してやる。コイツを抹消する為にな」
「リターン・イクス・・。君は、味方なのか?」
「正直そう捉えられることには抵抗があるが、今はそう認識して貰って差し支えはない」
口ではそう言い放つリターン・イクスだったけれど、セイアはその瞳の中に確かにエックスと同じ暖かさを見た。
ふとセイアは口もとに笑みを浮かべ、再びデス・リミテッドを見据える。まるで兄が傍にいるように、疲れきった身体に再び闘志が燃えた。
リターン・イクスも同じように醜悪なケルベロスを見上げた。そんな二人にデス・リミテッドは三つの口元をニヤリと歪めた。
感情の伴わない下衆な嘲笑だった。
『愚カナ。貴様等二人ナラ勝テルト思ウカ。貴様等ノヨウナ雑魚ガ何人集マロウト勝チ目ナド存在セヌワ!』
「勝てるさ」
無遠慮なプレッシャーを与えるデス・リミテッドの言葉を、リターン・イクスはぴしゃりとその一言だけで斬り捨てて見せた。
横に並んだセイアが見るリターン・イクスの目に迷いはない。その横顔はいつも憧れてやまなかった兄の顔だった。
「セイヴァーと貴様では見詰めているものが違う。例えどれ程強力になろうと、貴様は最初から負けている」
「イクス・・兄、さん」
思わずセイアはリターン・イクスを兄と呼んでいた。言葉も動作も乱暴で、取っつきにくい印象しか受けないリターン・イクスだけれど、
その瞳と言葉にはエックスと同じ強さと暖かみがあったからだ。まるでずっとセイアを知っていたかのように振る舞うリターン・イクスは迷わない。
兄と呼ばれたリターン・イクスは横目でセイアを見たあと、再びデス・リミテッドを見る。その一瞬の視線の中に笑みがあったことを、セイアは勿論知っていた。
「貴様のようにただ本能のみで生きている下等生物には判るまい」
「デス・リミテッド。貴様が僕から生まれた存在だとするのなら、今ここで・・僕は僕を越える!これが最後の闘いだ!」
「私とて元はエックスと同じ身。生きる目的はとうに見据えているわ」
そして閃光が輝く。セイアの左腕を中心に、彼を蒼と紅の光が静かにゆっくりと・・そして力強く包み込む。
あの時と同じだ。あの電脳世界内での闘いの時と同じ光。そしてあの時よりも強く、輝かしい。
ボロボロだったセイアの鎧が、光に包まれて変化を遂げた。更に鋭く。更に力強く。二人の兄に抱かれるセイアは、
最後に形成されたヘルメットによって再びロックマン・セイヴァーの輝きを取り戻した。
クロス・アーマー。エックスとゼロの心を継ぐセイアにのみ装着することが許された究極の鎧だ。
『ソノ程度ノ輝キ、塗リ潰シテクレル。貴様ハ所詮太陽ノ前デ朽チルイカロスニ過ギントイウコトヲ思イ知レ』
「見せてやるがいいロックマン・セイヴァー。現代のイカロス神話は太陽をも越えるということをな」
「あぁ、闘おう!これを最後の闘いにする為に。力を貸してくれ、イクス兄さん!」
「ふむ・・よもや兄と呼ばれる日がくるとは思わなかった。が、悪くない・・」
そして三人目の兄の力が更に交差する。
リミテッド特有の能力で姿を変えたリターン・イクスが、セイアのクロス・アーマーを包み込むように更に融合を果たす。
胴に、腕に、足に、頭に。そして心に――三人目の兄の心が交差した。
そうしてようやくクロス・アーマーは完成を果たす。遂に不完全なままだった箇所を、リターン・イクスが埋めたのだ。
「暖かい・・・これが、僕の兄さん達の・・力。太陽を越えるイカロスの力!!」
そしてセイアは・・ロックマン・セイヴァーはイカロスとなった。
太陽に等しい力を持つデス・リミテッドに挑む為に。いや・・紛い物の太陽を打ち砕き、己が真の太陽となる為に。
エックスの、ゼロの、ウィドの、ゲイトの、彼等が護ってきた沢山の人々の、そして・・イクスの輝きの中で、セイアは剣を抜いた。
そして叫ぶ。願わくば・・これが最後の闘いとなるように。
『リミテッド戦士トアロウ者ガ馴レ合イオッテ。小賢シイ!ナラバソノ闘志モ輝キモ骨ノ髄マデ砕ケルガイイ!』
「行くぞっ!勝負だデス・リミテッド!!」
――果たして・・・。
――果たして、どれだけの者がこの闘いを知っていたのだろう。
――果たして、どれだけの者がロックマン・セイヴァーの闘いを知っていたのだろう。
――果たして、どれだけの者が人知れぬ場所で自らの為に闘ってくれている者がいることを知っていただろう。
――いやきっと、誰も知らない。
――現代のイカロスを、誰も知らない。
――誰に支えられずとも、挫けず闘った戦士のことを、誰も知らない。
――それでもいつかは伝わるだろうか。
――ロックマン・セイヴァーという英雄の意思を継ぐ者が、誰も知らない場所で闘っていたことを。
――それでも・・いや、きっと伝わっているに違いない。
――ロックマン・セイヴァーを、そして徳川健次郎を待つ人々が思いの外多いことを。
――今はまだ伝わらないかもしれない。
――それでも・・いつか、彼の闘った軌跡はきっと輝くだろう。
――現代のイカロス神話と共に・・・。
それから数時間後・・旧ハンターベースに存在していた膨大なエネルギー反応が完全にロストしたのだった・・・。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『――であります。卒業生一同様の益々のご発展をお祈りし、ここに締めさせて頂きます』
『卒業生・在校生起立。礼、着席』
ガタガタっと騒々しい椅子が擦れる音。立ち上がる生徒達。自分では最高り演説を演じたつもりの市長。
淡々とプログラムを進めるナレーター。既に泣き出してしまっている父兄。
そして、伝統に基づいて綺麗に飾りつけられた体育館。普段の空間とは一線を覆す、華やかな場所。
そんな体育館内には所狭しと椅子やテーブルが並べられ、それと同じ数だけの人間・レプリロイド達が座っている。
ステージの天井から吊るされたプレート。体育館の側面に控えた吹奏学部。ここぞとばかりに着飾った者達。
窓の外を見ればガラス面いっぱいの桜の花を見ることが出来るだろう。三年前、今まさに祝われている生徒達が見たものと同じ、蔓延の桜を。
彼は市長の長い癖にそれ程内容のない、最悪テンプレートにしか聞こえない演説がようやく終わったのをいいことに、思わず大あくびをかいてしまった。
昨晩はこんな行事の前日だというのにやるべきことに追われ、睡眠時間をたっぷりととっていなかった所為なのかもしれないが、
彼はあくまで市長の演説がつまらなかったことの所為にするつもりだった。
こつん。流石に目立ったのか、隣に座っているクラスメイトに肘でつつかれた彼は、慌てて姿勢を正す。
幸いに次のプログラムに以降する為にその他大勢が慌だしかったお蔭で、彼の怠惰は周りには勘づかれていなかった。
「卒業式くらい、しゃんとしろ」
「う、うん」
小声で耳打ちされ、睨まれる。流石に言い返す言葉がないので、彼は小さく返すと縮こまってしまった。
そういえば入学式――ではないが、それに近い式がかつてあった――の時も同じように前日夜更かしをしてしまい大あくびをかき、
隣に座っていた兄に肘でつつかれたことがあった。それを思い出すと途端に顔が熱くなってしまい、彼は片手で顔面を覆った。
ああなんて恥ずかしいのだろう。と。
「――卒業式」
ようやく顔の火照りがおさまった彼は、ふと顔を上げてステージに吊るされたプレートに目をやった。
『第八回フロンティア学園卒業証書授与式』の文字が大きく描かれたプレートはなんということはない、ただのプレートだ。
だが彼にとってはそれだけでも大きな意味があった。
もう死んでしまった、大切な人が自分の為に無理を云って入学させてくれた学校。
沢山の友達と出逢い、ぶつかり、それでも楽しかった学校。
自分一人では判らなかったことを、沢山教えてくれた学校。
一時は卒業出来ないとまで覚悟した学校だったのに、今彼はこうしてここにいる。卒業生の列の中で座っている。
それはなんて奇跡で、素敵なことだろう。それを思い彼はふわりと口もとに小さな笑みを浮かべた。
『卒業証書授与』
そしてようやく準備が整ったらしく、ナレーターが次のプログラムを続ける。この卒業式というイベントの中でもメインのメイン。
これをする為に卒業式という儀式があるのだというコアの部分。ついにそれが始まるのだ。
思えばここまで漕ぎ着けるのに随分と時間があった。無駄に長い話をする校長先生。出だしを失敗してやり直しになった校歌。
どこぞのお偉いさん方の演説。無論さっきの市長もそれに含まれているが。
本当ならばこれを一番じっくりとこなさなければならないというのに、ここまで来るのに一時間弱とはまた困ったものだ。
この後もプログラムはずらりと並んでいる。きっと他の生徒達は心底うんざりしていることだろう。
けれど彼は違う。今まで散々焦らされた分、このプログラムが来ることへの期待感がどんどんと大きくなっていったのだ。
『三年A組起立』
卒業証書は立体映像装置によって手渡される。
渡された機器を操作することで映像の卒業証書が表示され、それをいつでも劣化なく見ることが出来るという寸法だ。
機器をPC等のデジタル機器に接続すればデータ保存も簡単ということで、最近ではそれが一般化しつつある。
呼び出されたA組の生徒達。一人一人の名が呼ばれ、それに返事をし、彼等は壇上へと上がっていく。
そして一人一人が校長と顔を合わせ、手渡しで卒業証書を渡されるのだ。
それが常識。数百年前から普通のことだが、彼にはとても素晴らしいものに見えた。
校長という最も権限の高いものが、生徒という何百人も存在する者達と一人一人顔を合わせ、証書を渡す。
生徒一人一人の存在を認め、それに祝いの念と共に渡すのだ。たった一人の生徒の為に、僅かでも時間を割いて。
生徒達はそれに向き合って受け取る。三年間自分達が学び、頑張った印を。そしてこれから先の未来へと歩きだす切符とも云える証書を。
『三年B組起立』
壇上を降りていく生徒達の中には、泣き出してしまっている者達もいる。それぞれの沢山の想い出が頭を巡ったかのように。
そんな者達を見て、彼も思わず涙が溢れそうになったのを必死で堪えた。まだ泣くときじゃあない。その涙は彼等のものであって、
自分が流す涙は別にある。今日流す涙は、誰の為のものでもない。自分の為に流すものだから。
途中で隣に座っているクラスメイトが彼の様子を心配して横目で声をかけたが、彼はふるふると首を振って笑った。
哀しいのではない。ただ、嬉しいだけなのだ。そう伝える為に。
その笑顔にクラスメイトも釣られて笑い、また壇上を見上げた。
ボーッとしていると波のように過ぎていってしまう生徒達。一枚、また一枚と消えていく卒業証書。
彼はその光景を目に焼きつけるようにジックリと見た。証書を受け取り、それぞれの表情で壇上を降りていく生徒達の顔も、姿も全て。
学校だけではない。彼の三年間を彩ってくれた者達、全てを忘れない為に。
『三年C組起立』
そして最後の号令がかかる。彼を含めた周りの生徒がその声に一斉に立ち上がった。
思えばクラスが三つとは随分と少なくなったものだ。彼が入学した時は少なくとも五つはクラスがあったというのに。
辞めていった者もいる。転校していった者もいる。しかし何より減ったのは教室だった。
イレギュラーが学校に現れたことで被害を受けたのだ。仕方なしにクラスが幾つか統合され、今のクラス数となったのだ。
しかし今となっては昔の話だ。実際に死傷者が出たわけではなく、学校が傷ついただけだというのは幸いだったと、
さっきの校長の長い話の中でも云われていたことだ。彼もそれでいいと思っている。
『――』
程なくして出席番号順に生徒の名が呼ばれ始めた。並べられた椅子の端っこから壇上へと昇り、証書を受け取っていく。
さっきまでと全く同じ光景。同じパターン。しかし三年間付き合ってきた者の多いクラスメイト達が証書を受け取っていくのは、
さっきに増して不思議な感じだった。
『クリストファー・ケビン』
「はい」
クラスメイトのクリスが名を呼ばれ、壇上へと昇っていく。
一旦校長の前まで歩いたクリスは、礼儀よくお辞儀をすると、左手、右手と順番に証書に手をかけ、もう一度お辞儀をし、壇上を降りていく。
思えばクリスはこの学校に入って、彼に初めて声をかけた生徒だった。
学校という空間に慣れない彼をよく助けてくれた。宿題をする時間がなかった時にこっそり映させてくれた。
それがばれて二人で廊下に立たされたこともあった。隠し事がばれても、彼女は何も云わずにそれを受け入れてくれた。
別に彼女とはどうという関係ではなかったが、ただいい友達だった。彼女はこの先この学校の高等部に進むと云っていたが、
成績優秀な彼女ならきっと素晴らしい道を開いていけるだろう。
『フレッド・ミルド』
「ういす」
次はフレッドだ。
思えば彼は二年前はいわゆる不良生徒だった。世の中を斜めに見て、なにかといちゃもんをつけて。
なんだってこの学校に在籍しているのか本当に謎の生徒だった。
しかし彼は変わった。いや、本当の彼を曝け出したというのだろうか。
彼は本当は優しい少年だった。正義漢や勇気を人一倍持った、純粋な少年だった。
ただそれを理解してくれる人が周りにいいなかっただけだったのだ。この三年間で、彼は自分の居場所を見つけられたのかもしれない。
壇上を降りる時に目が合ったフレッドは、彼に向かってニッと笑った。彼も肩を竦めてそれに笑顔を返す。
いつの間にかこんな関係が出来ていた。初めて出逢った時はいちゃもんをつけられ、喧嘩をふっかけられた仲だというのに。
フレッドは自分に助けられたといつも云っていたが、それは違うと彼は思う。
フレッドは彼が自分を見失った時、一番初めに引き留めに来てくれた友達だったからだ。
下手をすれば傷つけるだけでは済まなかったというのに。あの時のフレッドの勇気は、今でも彼の記憶に鮮明に残っている。
『――ウィド・ラグナーク』
「ん」
彼が証書を渡される者達一人一人に想いを抱いている内に、終わりが近付きつつあった。
校長の手元に残っている証書はもう最後といってもいい。それは同時に卒業式の一番の山であるプログラムが、もう終わるということを意味していた。
名を呼ばれたウィド・ラグナークはゆっくりと壇上へと上がった。あれ程注意したというのに直っていない不作用な礼をし、ウィドは証書を受け取る。
ギシギシとまだ馴染みきっていない義手が音を立てた。一年前の闘いで負傷した腕は回復が見込めず、結局義手になってしまったとウィドは云っていた。
その時に受けたウィドの痛みは彼には計り知れない。が、今では殆ど日常生活には差し支えなく振る舞っていることから、
もう殆ど大丈夫なのだろう。
彼もまたこの学校に来て変わった者の一人だったと思う。
人付き合いが苦手で、気を許した相手にしか表情すら変えない、そんな少年だったウィド。それがこの学校に来て、このクラスに触れ、除々に変わっていった。
今でもまだ人付き合いは苦手だとウィドは云うけれど、それでも一年前に転校してきた時の彼とは違う。
自然に笑みを零せるようになったウィドは、立派なクラスの一員だった。
「・・・」
ウィドが席に戻り、三年C組の生徒達が腰を降ろす。校長の手元の卒業証書入れも空っぽだ。
しばしシンとその場に静寂が走る。二秒、いや三秒か。そしてその沈黙を破るべく、ナレーターが次の言葉をマイクにぶつけた。
『そして卒業生代表・徳川健次郎』
「・・はい!」
彼――徳川健次郎が椅子から立ち上がった。この学校を巣立っていく卒業生――その代表として。
三年C組の端っこの席に座っていた健次郎は、壇上に昇る為、必然的に全ての列を前を通る。
つまり卒業生全員の視線に晒されることとなるのだ。
普通ならばとても緊張する行為だろう。無論健次郎自身この瞬間、とても緊張すると覚悟を決めてきた。
けれど、本当は違う。健次郎の心を埋めたのは緊張よりも喜びだったからだ。
「みんな・・」
思わず言葉が漏れてしまう。
何故なら健次郎を見送る生徒達の視線がとても優しく、暖かだったからだ。
健次郎は胸の内が暖かくを通り越えて熱くなるのを感じながら、壇上への階段に足をかけた。
たった五段の階段。たったそれだけの数に過ぎない段数。だが、今まで過ごしてきた三年間と同じくらいの重さが、この五段にはあるのだ。
一段――登校日数が極端に少ない自分が、こうしている卒業式を皆と共に迎えられるとは、なんて素晴らしいことなのだろう。
二段――その為に沢山助力をしてくれた仲間達、先生達。きっと健次郎は彼等を生涯忘れないだろう。
三段――何度もイレギュラーの手から護った学校。破損は何度もしてしまったけれど、今こうしてここにあるのは、自分がここを護ったからだと胸を張って云える。
四段――エックスとゼロの弟であるということは誇りである。が、ここはそれ以外の自分をも創り出してくれた、大切な場所。
五段――卒業生代表として生徒達によって選ばれた健次郎は・・きっと、いやとても幸せ者に違いない。
「卒業おめでとう。徳川君」
「はい。慎んでお受けします」
礼を交わし、校長と向き合う。実際に校長と会話をしたのはこれが初めてだったが、この一瞬でもこの校長の人間性が確かに判る。
目を細め、小さく笑んだ校長先生。セイアは静かに左手を出し、右手を出し、卒業生代表用に別途用意された証書を受け取る。
「立派になったものだ。君だけではないよ。ここにいる卒業生全員が、君と同じように立派になった」
そう云う校長の目は健次郎を通して、後ろの卒業生全員に向けられていることが判る。
健次郎はそれに笑みで応えた。きっと、そう入学したばかりだったハンターとしてもレプリロイドとしても未熟な彼には出来なかった笑みで。
そして健次郎は頭を下げた。この学校を巣立つという、最後の儀式を。けれど頭を上げても校長が返礼をした気配はない。
何事かと首を傾げると、校長はまるで何か愛おしいものを見るかのような顔で囁いた。
「徳川君。振り向きたまえ」
「えっ・・・?」
健次郎が振り向いた瞬間に、ナレーターが、次のプログラムを、口にした。
『卒業生・在校生斉唱』
そして健次郎が知らない間に用意を完了していた吹奏楽部が、壇上の隅っこのピアノの前に座っている教師が、一斉にそれを奏で始める。
それはよくある卒業の歌でもなければ、洒落たポップスでもない。
プログラムシートに書かれていない――健次郎は全く知らなかった、イレギュラーなプログラム。
それでも彼等は歌い出した。いつか音楽の時間か何で健次郎も聞いたことのある、健次郎が一番好きだった合唱曲を。
マイバラードを――
――みんなで歌おう 心をひとつにして
悲しいときも つらいときも
みんなで歌おう 大きな声を出して
はずかしがらず 歌おうよ
心燃える歌が 歌がきっと君のもとへ
きらめけ世界中に ぼくの歌を乗せて
きらめけ世界中に 届け愛のメッセージ
みんなで語ろう 心をなごませて
楽しいときも うれしいときも
みんなで語ろう 素直に心開いて
どんな小さな 悩みごとも
心痛む思い たとえ君を苦しめても
仲間がここにいるよ いつも君を見てる
僕らは助け合って 生きてゆこういつまでも
心燃える歌が 歌がきっと君のもとへ
きらめけ世界中に ぼくの歌を乗せて
きらめけ世界中に 届け愛のメッセージ
届け愛のメッセージ――
「みん・・な。みんな・・・ありが・とう」
今日は流さないと決めた涙が、健次郎の頬を伝わっていった。
そしてこれが、現代でセイアが最後に流す涙――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
遂にイレギュラー・ハンター上層部の決定が揺らぐことはなかった。
客観的に見てその決定は至極当然のことだろう。
イレギュラー・ハンターがイレギュラー・ハンターである限り、始める前から方針は決まっていたようなものだ。
それでも少年が残してきた功績は偉大だった。最後の最後で処分が軽くなったことは奇跡に近い。
いや、今まで奇跡を起こし続けてきた少年だからこそ、最後の最後で自らの為の奇跡を起こしたと云ってもいい。
それが本人にとって奇跡と呼べるかどうかは定かではない。寧ろ少年の心を晴らすには余りにも稚拙過ぎていた。
少年は言い渡された処分をただ静かに受け入れたという。
その瞳の奥にどんな色が宿っていたのか、一番近くに座っていた彼の父ですらわからない。
その日の少年の顔は永遠に謎になってしまった。
小さな希望を訊ねられたとき、少年は猶予を彼等に求めた。
それは無意味な時間にしがみつく為の足掻きでなく、彼の最も大切な者に示すけじめの為の時間。
少年が終始纏っていた服装からも、それは明白だったことだろう。
時間は与えられた。高く歌う北風が柔らかな春風に変わるまでの、ほんの僅かな時間が。
そして今日が最後の日だった。少年が待ち焦がれ、また最も恐れていた時が来てしまった――
――徳川健次郎。正式名称ロックマン・セイヴァー。第十七精鋭部隊の副隊長にして最強のイレギュラー・ハンター。
エックスを殉職にまで追い詰めたDr.ワイリー。並びにその遺産であるデス・リミテッド。
レッド・アラートを名乗る自衛団との小競り合い。フォース・メタルを巡るギガンティスでの闘い。それらを終結させた名誉隊員。
・・そして今後イレギュラー化が大きく懸念される危険分子。
上層部が彼に下した処分は――
「それは一体どういうことだっ!」
滅多に声を荒らげないウィドの怒号が研究室内に騒々しく響いた。普段殆ど大きな声を出さないウィドの怒号は途中で裏返る程のものだったけれど、
それを向けられた健次郎は――セイアは怯むことなく真っ直ぐにウィドの瞳を見詰めたままだった。
「どういうことも何も、言葉通りだ」
「言葉通りだと?ふざけるな!」
キリキリと金属音を立てるウィドの義手がセイアの胸ぐらを掴んだ。生身の腕とは比べ物にならない腕力で壁に叩き付けられるも、
セイアは未だに冷静な顔を崩そうとしなかった。
セイアの真っ直ぐな視線に射抜かれて、ウィドは更に表情を歪める。しかも流石の機械腕の腕力もセイアには全く通じず、容易く振りほどかれてしまったものだから、
ウィドはただセイアを睨むことしか出来なかった。
セイアは二、三歩歩いて窓に手を当てた。紅のアーマーを身につけた彼の後姿は凜々しいが、今はなんだか小さく見えるような気がした。
「セイア・・あれからもう一年だ。あれ以来お前の身体に特に異常はなかった筈だ!それなのにどうして・・!」
「・・・・」
振り返り、セイアはウィドの顔を見た。その瞳に感情はない。ただ淡々と見返す瞳だけがそこにはあった。
「セイア・・!!」
「僕の体内にはリミテッドが残っているんだ。検査結果はいつも同じ。何度やっても取り除くことはできなかった。
取り除く為には、長い年月をかけてゆっくりとやるしかない。君だって判っているだろう・・?」
握り締められた鎧の胸部が軋みを上げる。いっそ砕けてしまえばどれだけ楽だったことだろう。
セイアがどれだけ力を入れても決して壊れないアーマーが、まるでその奥にあるものの根深さを暗示しているようにも見えた。
「・・・何故、黙っていたんだ。何故だ、答えろっ!」
「・・云い出せなかったんだ」
蚊の鳴くような小さな声で答えるセイアの頬を、ウィドの鉄拳が殴りつける。セイアは抵抗することなくそれを受け入れた。
二度三度殴られて壁に押し付けられても、ただ黙って身を任せる。ウィドにはそれが悔しくて仕方なかった。
「云い出せなかっただと・・!?貴様・・!」
「隠すつもりはなかったんだ。ずっと云おう云おうと思っていた。でも、いざ云おうとするとどうしても無理だったんだ。
なんて云えばいいかわからなかった。本当は・・・!」
言葉を最後まで紡ぐ前に、セイアは顔を背ける。
これ以上口を開けば逃げ出してしまいそうになるからだ。決して流さないと決めた涙が溢れそうで、必死にそれを押しとどめた。
ウィドにはそれが痛みを堪えているようにしか思えない。自らを置いて消えようとする少年の心など、彼にはもはや関係のないことだった。
「博士、もう時間ですね」
「・・そうだね。そろそろ始めようか」
押し黙っていたDr.ゲイトが息子の呼びかけに口を開く。
普段の軽い印象などどこにもない。二つや三つ挟んでもおかしくなかった言葉すらなかった。
既に用意されていた休眠カプセルは口を開けている。棺おけと称するべき、休眠カプセルが。
「待て、待てセイア!俺達は友達じゃなかったのか、またお前は俺を置いていくのか!?待ってくれ、セイアっ!!」
「ウィド・・・」
カプセルへ入り、寝そべるセイア。それが封印されているゼロの姿に重なって、ウィドは半狂乱になって叫ぶ。
「ごめん、ウィド」
セイアはウィドの名を呼んだ。もうスイッチを軽く押し込むだけで封印という名の闇に陥れられる状態で、
セイアは最後に云う。セイアが最後に向ける、ウィドへの・・親友への言葉だった。
「君を、忘れない」
セイアの瞳から一粒の涙が滑って落ちる。
ウィドの目にそれは映らなかった。
「セイ・・!!」
「それじゃあ始めるよ、セイア。予定では約百年後の夏頃に封印が解ける筈」
「・・はい。お願いします、博士」
「待・・!!」
「お休み、セイア。ボクの最後の息子」
そしてウィドの制止も聞かず、ゲイトはスイッチを押し込んだ。
「お休みなさい」と呟いたセイアの姿を、ゆっくりゆっくりカプセルの蓋が覆っていく。
ウィドが見ているスピードよりも蓋が閉じる速度は速かった。
ウィドがカプセルの蓋にかじり付いた時、既に内部にはレプリロイドの活動を停止させる霧が噴出した後だった。
「セ・・・イア」
半透明の蓋から見えるセイアの姿は、本当にただ眠っているかのように静かで、綺麗だった。
ウィドは糸が切れたようにその場に崩れ落ちた。
セイアが消えてしまった。セイアが目の前からいなくなってしまった。セイアが、もう自分の名を呼ぶこともない。ウィドにとっては――永遠に。
沈黙。
ただ沈黙だった。
俯くゲイト。膝をついて崩れ落ちたウィド。眠るセイア。誰も口を開かない。
低く唸る様々な機械の駆動音も、廊下から聞こえてくる雑音も、何もかも聞こえない。
世界は真っ白になってしまった。真っ白になって、何も見えない。
「・・・・・セイア」
その名を呼ぶ声を、ウィドとゲイトは聞いていた。無意識に呟くウィドのそれでなく、そう云ったのはゲイトの方だった。
「体内にリミテッドを残留させるロックマン・セイヴァーはいつまたイレギュラー化するかわからない。
誕生した三体のリミテッド体の戦闘力を計算に入れれば、次もまた勝てる保証などどこにもない。
一歩間違えばセイア自身がボク等の最大の敵になる危険性だってある。
・・懸念した上層部の決定さ。勝手なものさ、今までセイアに頼りきりだったのに、アクセルが入った途端に危険分子は排除するなんて」
「何故、誰もそれを俺に云わなかった」
「・・極秘だからさ。他の隊員は何も知らない。セイアは殉職したとでも伝えるんだろうね。・・・それにこれはセイアの意思だ」
あの幼い少年が自らに課せられた運命とどれだけ闘ったか、ゲイトだけが知っていた。
一体セイアはどう思ったのだろう。最強のハンターとして無遠慮に自らを戦火に投入しつつ、最後には己を消そうとする組織に対して。
いつか伝えなければならない親友への別れを、少年がどれだけ恐れていたのか。
ゲイトの白衣をぐしょ濡れにするまで泣いた幼い息子の顔を、ゲイトは生涯忘れることはないだろう。
「あーあ、思ったとおり。二人して湿っぽい顔してる」
場違いな明るい声。反射的に振り返ると、呆れた顔の少年レプリロイドが立っていた。アクセルだった。
「セイアは――そうか、もう寝ちゃったんだね。全くボクに挨拶もなしに寝ちゃうなんて水臭い」
重苦しい雰囲気を逃がすようにドアを開け放ち、アクセルがセイアの眠るカプセルに歩み寄る。
そっとそれに手をあてて、中に眠る少年の顔を見た彼は、振り返らないままに言い放つ。
「羨ましいよ。二人がね」
「羨ましいだと・・?」
「ああ、羨ましいね」
全力で殺気をまき散らすウィドに、アクセルは変わらぬ口調でそう返す。
それどころかウィドに顔を近づけて、小さく口の端を持ち上げて見せた。
「ボクはセイアに一言も別れの挨拶をして貰えなかった。それに較べて君はどうだい、ウィド?」
「黙れ!貴様に何がわかる・・!」
「わからないよ。ああ、わからない。わかりたくもないね、そんな自分勝手な気持ち」
掴み掛かってきたウィドを軽く躱し、アクセルは尚も云う。
擦れ違いざまに足を引っ掛けられたウィドは、受け身も取れずに床に倒れ込んだ。
「・・それとも君みたいに取り乱して見せれば満足?」
「貴様・・!」
「そりゃ悲しいさ、ボクだって。ゲイト博士だってそうに決まってる。それとも不幸なのは自分だけだとでも思った?」
レプリロイドは泣かない。泣く機能を持っているのはエックスとセイアだけだからだ。
それはアクセルも例外ではない。それでもアクセルは泣いていた。感情を押し殺したまま泣いていた。涙声のまま、ウィドに囁いていた。
「セイアはボクに一言も云わずに眠っていった。でも君にだけは別れを告げていったんだ。それがどれだけ辛かったか、君にはわからない?」
「・・・」
「そりゃセイアは勝手だよ。せめて別れの挨拶くらいして欲しかった。君の気持ちだってわからないわけじゃない。
でも・・きっとセイアだって必死に闘って」
「もういい」
ウィドが立ち上がった。ヒヤリと冷たい声を放ちながら。これがあのウィドかと思う程、哀しく声を響かせながら。
その瞳には、生気がなかった。まるで自分の中の全てを奪われたように、その目は酷く機械的で・・。
「もういい。もう、いい」
「ウィド」
バグった音楽プレイヤーのように、ただその一言を繰り返すウィド。アクセルは目を細めて彼の姿を見た。
ウィドはなんの感情も宿さなくなった瞳で、ゲイトの机の上にまとめて置いてあったセイアの武装のうち、一本のサーベルを手にとった。
いつもセイアが愛用していたエックス・サーベル。それを懐にしまい込むと、ウィドはひたひたと幽霊のように出口へと向かっていった。
「ウィド君、どこへ行くんだ!」
ウィドは答えない。
「ウィド!」
ウィドの肩を掴んだゲイトの腕を、閃光が斬り落とした。ウィドが振り抜いたエックス・サーベルによる斬撃だった。
途端にゲイトの肩からオイルが勢いよく噴出し、床を染める。
至近でそうされたウィドも当然オイルを浴びるが、何も云うどころか表情すら変えなかった。
「ウィド、何を・・!」
「邪魔を、するな」
アクセルの制止も振り切って、ウィドは行方を眩ませた。
そして二度と帰ってくることはなかった。
この世から処分されたロックマン・セイヴァーは、目の前の惨劇にも目覚めることなく、ただ静かに眠り続けていた。
その後ゲイトの必死の捜索にもウィドは見つからず、何年もの時が過ぎていく。
ゲイトはその後ベースの担当研究員の任を降りた。最後の息子までをも失ってしまった自分にけじめをつける為に。
抹消されたロックマン・セイヴァーは未だ眠り続けている。いつ目覚めるともわからない、永遠の時を。
その後も大きな闘いは何度もあったけれど、決してセイアは起きなかった。アクセルを始めとする現存のハンター達がそれをおさめていったからだ。
やがてシグナスが任を降り、エイリアが退職し、ダグラスは戦火へと消え、セイアが存在していた頃の世界は少しずつ姿を消していった。
それでもウィドは見つからなかった。ウィドを知る者さえ、少しずつ少しずつ消えていく。
そしてセイアとウィドの存在を知る者が全ていなくなった頃、世界は大きな変化をとげるのだった。
ネオ・アルカディアという、大きな変化を・・・。
ありがとう 兄さんへ――
あなたは沢山のことを教えてくれました 沢山のものをくれました
ありがとう 兄さんへ――
あなたは強い心をくれました あなたは僕に剣をくれました
ありがとう――友人達へ
あなた達は僕を受け入れてくれました あなた達は僕に笑顔をくれました
ありがとう――みなさんへ
あなた達がいてくれたから 僕は楽しかったです
とてもとても楽しかったです
暖かな人生を歩めました 全てが僕の想い出です
ごめんなさい――親友へ
あなたを置いていく僕をどうか許してください
あなたと過ごした時間は 僕の宝物だから...
さようなら――親友へ
君を忘れない
ロックマンXセイヴァーⅡ~己との闘い~
――完――