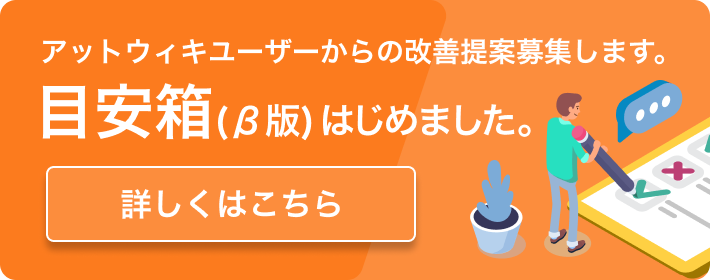「桃ちゃん編 12」(2008/10/06 (月) 23:45:43) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
小さいときから勉強ばかりしていた舞波にとって、自分がアイドルになるなんて夢のまた夢だったらしい。
「僕がたまたまテレビをつけた時、自分よりもちょっとお姉さんたちが歌って踊っていたんだ。
それをみて、自分もやってみたいなんて思ってしまってさ。最初は馬鹿げてるとわかっていたんだけど、女装してみたら案外いけるかもって。
お母さんも初めはすごく驚いていたなぁ。結局、受かるわけないんだし、やってみようって言ってくれて受けてみたんだ。
それで気づいたら、どんどんオーディションを進んでいって受かっちゃったってわけ」
オーディションからそんなに月日がたったわけでもないのに、舞波はとても懐かしそうに語ってくれた。
彼には何だか遠い日に夢をみていた頃が、幸せだったとでもいうように切ない表情をしている。
こういう時、私は話に聞き入って静かにしてしまうよりも大きいリアクションを取って反応をしたがる。
自分でも賑やかな方が私らしい気がするもん。
「そっか~舞波も千聖と同じってわけなんだ。あ、あのね、これは本当は皆には内緒なんだけど、千聖も男の子なんだって。
だからね、舞波の話を聞いたときも他にもいたんだって意味で驚いたよ。うん、本当に」
千聖には内緒にしてね、って言われてはいたけど、舞波を信用してついしゃべってしまった。
言っておきますが別に私、嗣永桃子がおしゃべりな口の軽い女だからってわけじゃないんですからね。
「えぇと、千聖も男の子ってそれ本当?」
小学四年生の子供に似合わず、寂しそうな顔ばかりしていた舞波が、ここにきてようやく好奇心に満ちた表情をみせてくれた。
ぐいっと顔を近づけてきて、答えを聞くまでは決して帰さないとでも言いたげである。
こんな調子の舞波を見るのは初めてだったものだから、どう反応していいかわからず、首を縦に振るしか出来ない。
「そ、そっか~そうだったんだ。よかった~自分以外にも仲間がいたって嬉しいよ。桃子、ありがとう」
「ど、どういたしまして。本当はバラしちゃいけないんだろうけどさ、あははは」
「それくらい僕だって同じ立場だからわかるよ。平気、誰にも言わないよ。本人には確認してみるかもしれないけどさ」
これがきっかけかはわからないけど、舞波と千聖の仲は一気に縮まった。
千聖にとって、舞波は同じ夢をみた仲間であり、良い相談相手のお兄さんとなったみたいだ。
逆に舞波には、手をやかせるやんちゃで可愛い弟が出来たみたいなものだったらしい。
二人の仲良く遊んだり、勉強を教えてもらっている場面は本当の兄弟に見えて、微笑ましかった。
何かあるとすぐに舞波を見るのが当たり前になっていた私は、キャプテンに言われるまで自分がそこまでしていると気付けなかった。
「桃、ニヤニヤして何してるの?」
「う、うわぁぁ。え、や、やだなぁ~何でもないって。全然何もないからね。気にしないで」
「桃はダンス遅れてるんだから、ちゃんと練習するんだよ。」
キャプテンをうまく誤魔化しはしたものの、自分の中にある疑問が生まれてもいた。
あれ、私ってそんなにも舞波ばかり見ていたのだろうか?、と。
舞波をみて嬉しそうに観察している自分の顔が鏡に映し出される。
私ってば、舞波をこんな顔して観察してたんだ。
「バカバカ、そんな顔しないの。まるで舞波を好きみたいじゃん・・・好きみたいじゃなくて、好きなのかな?」
鏡に映る自分にそう問いかけても、答えはまるでなし。
自分と全く同じ動きをするもう一人の自分が映し出されるだけで、おとぎ話とはまるで違う。
可愛いって問いかけたわけじゃないんだから、答えてくれたっていいのに。
「桃、そんな顔してどうしたの? レッスンでついていけないところでもあったとか?」
「きゃ!! ま、舞波。お、驚かさないでよぉ。びっくりしたじゃん」
私はずっと背後から近づく舞波に気づかずに夢中で鏡と睨めっこをしていたようで、突然のことに驚いて悲鳴をあげた。
舞波も舞波で私が悲鳴をあげたものだから、つられて驚いている。
「ご、ごめん。驚かすつもりはなかったんだけどさ。鏡みて首傾げたりしてたから、どうしたのかなって」
「う、うん。いやぁ~鏡がたまには自分と別の動きしないかなって思ってさ。す、するわけないよね」
「うん。鏡はただ単に自分と同じ動きを映すだけだからね」
「だよね~」
もう自分でも笑うしかなかった。
まじまじと不思議なものをみる目を向けてくる舞波に、自分の気持ちを気づかれたくなかったから。
そう、私はこの時点で自分の気持ちに気づいてしまっていたんだと思う。
私は舞波を好きなんだってことを。
「千聖、さっきキスしたことは冗談として。舞美とのことは真剣なの?」
「い、いきなり何言うかな。真剣だよ」
千聖からおどけた調子が一気に抜けて、久々に真剣な顔がみられた。
真剣な顔になると、やっぱり男の子だけあって凛々しい。
こういうところでも全力投球できるなら、私と舞波のようにはならないかもしれない。
「何があっても好きでいられる?」
「な、何さ。何で桃ちゃん相手にそんなことを言わなきゃならないのさ」
「いいから、好きでいられるかどうか言いなさい。それによってはこっちも本気で応援するかどうか決められないじゃん」
「・・・わ、わかったよ。僕は何があっても舞美ちゃんを好きでいるよ」
私の真剣さが伝わったか、千聖も本音で話してくれた。
舞美を何があっても好きでいる、とは言葉にしてしまうとものすごく陳腐だ。
確かにカッコいいとは認めるのだけど、それも舞波とのことがなければの話だ。
私は既にこういう言葉が陳腐に聞こえてしまうような体験をし、そんなものに心躍るほど乙女でもない。
アイドルの仕事柄、そういった受け答えはする場合もあるにはある。
それはあくまでアイドル嗣永桃子であって、ホントのじぶんではない。
私だって女の子だから、千聖の言葉を信じてあげたい。
でも信じられないのは、自分たちは厳しい現実にぶつかって諦めた恋の先輩だからだ。
「本当に信じていいんだね?」
「うん」
「わかった。真剣なあんたに免じて、舞美に本気なのは信じてあげる」
「ありがとう、桃ちゃん」
「信じてあげる。ただし、あんたたちには今から話す二人にはなってほしくないの。私と舞波みたいには」
私は決心をしていた。
グループ内での恋愛をしてしまった舞美には、自分と同じ悲しい別れだけはしてほしくないから、全てを話そう。
千聖には舞美に悲しい思いをさせたくなんかなかったから。
[[←前のページ>桃ちゃん編 11]] [[次のページ→>桃ちゃん編 13]]
小さいときから勉強ばかりしていた舞波にとって、自分がアイドルになるなんて夢のまた夢だったらしい。
「僕がたまたまテレビをつけた時、自分よりもちょっとお姉さんたちが歌って踊っていたんだ。それをみて、自分もやってみたいなんて思ってしまってさ。最初は馬鹿げてるとわかっていたんだけど、女装してみたら案外いけるかもって。お母さんも初めはすごく驚いていたなぁ。結局、受かるわけないんだし、やってみようって言ってくれて受けてみたんだ。それで気づいたら、どんどんオーディションを進んでいって受かっちゃったってわけ」
オーディションからそんなに月日がたったわけでもないのに、舞波はとても懐かしそうに語ってくれた。
彼には何だか遠い日に夢をみていた頃が、幸せだったとでもいうように切ない表情をしている。
こういう時、私は話に聞き入って静かにしてしまうよりも大きいリアクションを取って反応をしたがる。
自分でも賑やかな方が私らしい気がするもん。
「そっか~舞波も千聖と同じってわけなんだ。あ、あのね、これは本当は皆には内緒なんだけど、千聖も男の子なんだって。だからね、舞波の話を聞いたときも他にもいたんだって意味で驚いたよ。うん、本当に」
千聖には内緒にしてね、って言われてはいたけど、舞波を信用してついしゃべってしまった。
言っておきますが別に私、嗣永桃子がおしゃべりな口の軽い女だからってわけじゃないんですからね。
「えぇと、千聖も男の子ってそれ本当?」
小学四年生の子供に似合わず、寂しそうな顔ばかりしていた舞波が、ここにきてようやく好奇心に満ちた表情をみせてくれた。
ぐいっと顔を近づけてきて、答えを聞くまでは決して帰さないとでも言いたげである。
こんな調子の舞波を見るのは初めてだったものだから、どう反応していいかわからず、首を縦に振るしか出来ない。
「そ、そっか~そうだったんだ。よかった~自分以外にも仲間がいたって嬉しいよ。桃子、ありがとう」
「ど、どういたしまして。本当はバラしちゃいけないんだろうけどさ、あははは」
「それくらい僕だって同じ立場だからわかるよ。平気、誰にも言わないよ。本人には確認してみるかもしれないけどさ」
これがきっかけかはわからないけど、舞波と千聖の仲は一気に縮まった。
千聖にとって、舞波は同じ夢をみた仲間であり、良い相談相手のお兄さんとなったみたいだ。
逆に舞波には、手をやかせるやんちゃで可愛い弟が出来たみたいなものだったらしい。
二人の仲良く遊んだり、勉強を教えてもらっている場面は本当の兄弟に見えて、微笑ましかった。
何かあるとすぐに舞波を見るのが当たり前になっていた私は、キャプテンに言われるまで自分がそこまでしていると気付けなかった。
「桃、ニヤニヤして何してるの?」
「う、うわぁぁ。え、や、やだなぁ~何でもないって。全然何もないからね。気にしないで」
「桃はダンス遅れてるんだから、ちゃんと練習するんだよ。」
キャプテンをうまく誤魔化しはしたものの、自分の中にある疑問が生まれてもいた。
あれ、私ってそんなにも舞波ばかり見ていたのだろうか?、と。
舞波をみて嬉しそうに観察している自分の顔が鏡に映し出される。
私ってば、舞波をこんな顔して観察してたんだ。
「バカバカ、そんな顔しないの。まるで舞波を好きみたいじゃん・・・好きみたいじゃなくて、好きなのかな?」
鏡に映る自分にそう問いかけても、答えはまるでなし。
自分と全く同じ動きをするもう一人の自分が映し出されるだけで、おとぎ話とはまるで違う。
可愛いって問いかけたわけじゃないんだから、答えてくれたっていいのに。
「桃、そんな顔してどうしたの? レッスンでついていけないところでもあったとか?」
「きゃ!! ま、舞波。お、驚かさないでよぉ。びっくりしたじゃん」
私はずっと背後から近づく舞波に気づかずに夢中で鏡と睨めっこをしていたようで、突然のことに驚いて悲鳴をあげた。
舞波も舞波で私が悲鳴をあげたものだから、つられて驚いている。
「ご、ごめん。驚かすつもりはなかったんだけどさ。鏡みて首傾げたりしてたから、どうしたのかなって」
「う、うん。いやぁ~鏡がたまには自分と別の動きしないかなって思ってさ。す、するわけないよね」
「うん。鏡はただ単に自分と同じ動きを映すだけだからね」
「だよね~」
もう自分でも笑うしかなかった。
まじまじと不思議なものをみる目を向けてくる舞波に、自分の気持ちを気づかれたくなかったから。
そう、私はこの時点で自分の気持ちに気づいてしまっていたんだと思う。
私は舞波を好きなんだってことを。
「千聖、さっきキスしたことは冗談として。舞美とのことは真剣なの?」
「い、いきなり何言うかな。真剣だよ」
千聖からおどけた調子が一気に抜けて、久々に真剣な顔がみられた。
真剣な顔になると、やっぱり男の子だけあって凛々しい。
こういうところでも全力投球できるなら、私と舞波のようにはならないかもしれない。
「何があっても好きでいられる?」
「な、何さ。何で桃ちゃん相手にそんなことを言わなきゃならないのさ」
「いいから、好きでいられるかどうか言いなさい。それによってはこっちも本気で応援するかどうか決められないじゃん」
「・・・わ、わかったよ。僕は何があっても舞美ちゃんを好きでいるよ」
私の真剣さが伝わったか、千聖も本音で話してくれた。
舞美を何があっても好きでいる、とは言葉にしてしまうとものすごく陳腐だ。
確かにカッコいいとは認めるのだけど、それも舞波とのことがなければの話だ。
私は既にこういう言葉が陳腐に聞こえてしまうような体験をし、そんなものに心躍るほど乙女でもない。
アイドルの仕事柄、そういった受け答えはする場合もあるにはある。
それはあくまでアイドル嗣永桃子であって、ホントのじぶんではない。
私だって女の子だから、千聖の言葉を信じてあげたい。
でも信じられないのは、自分たちは厳しい現実にぶつかって諦めた恋の先輩だからだ。
「本当に信じていいんだね?」
「うん」
「わかった。真剣なあんたに免じて、舞美に本気なのは信じてあげる」
「ありがとう、桃ちゃん」
「信じてあげる。ただし、あんたたちには今から話す二人にはなってほしくないの。私と舞波みたいには」
私は決心をしていた。
グループ内での恋愛をしてしまった舞美には、自分と同じ悲しい別れだけはしてほしくないから、全てを話そう。
千聖には舞美に悲しい思いをさせたくなんかなかったから。
[[←前のページ>桃ちゃん編 11]] [[次のページ→>桃ちゃん編 13]]
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: