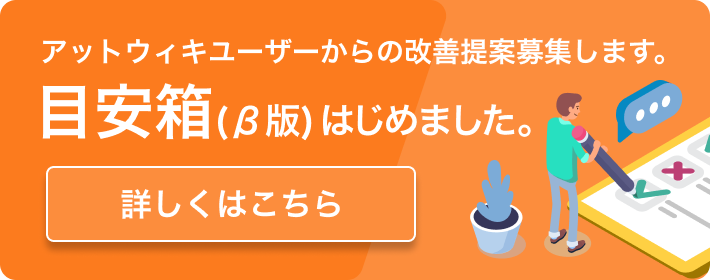もしも℃-uteの岡井ちゃんが本当に男の子だったら
りーたん編 7
最終更新:
okaishonen
-
view
僕らが目の前で抱きついたりしているのに、愛理は笑って観察を続けている。
とくに注意やとめに入ることもなく、お二人さんは熱いねぇ~などとからかう以外には何もしてこない。
りーちゃんも愛理には構わず、大きな胸を押し付けて密着しているのに、気にはとめていない。
胸だけでも僕にはとても刺激的なのに、りーちゃんからは女の子特有のいい匂いが体中から漂ってきている。
やばい、今下半身に体のどこかが触れてでもしたら、りーちゃんは驚くだろうな。
えりかちゃんたちが特別なだけで、大抵の女の子は男の子のこういう変化を不潔と思ったりしないか心配だ。
とくに注意やとめに入ることもなく、お二人さんは熱いねぇ~などとからかう以外には何もしてこない。
りーちゃんも愛理には構わず、大きな胸を押し付けて密着しているのに、気にはとめていない。
胸だけでも僕にはとても刺激的なのに、りーちゃんからは女の子特有のいい匂いが体中から漂ってきている。
やばい、今下半身に体のどこかが触れてでもしたら、りーちゃんは驚くだろうな。
えりかちゃんたちが特別なだけで、大抵の女の子は男の子のこういう変化を不潔と思ったりしないか心配だ。
「千聖、一緒のお布団に潜りこんじゃったし、今夜はこのまま寝ちゃおうよ」
「え、えぇ~そ、それはまずくないか? りーちゃんがいくらよくても無理だよ」
「いいじゃん。ねぇ~いいでしょ~」
「え、えぇ~そ、それはまずくないか? りーちゃんがいくらよくても無理だよ」
「いいじゃん。ねぇ~いいでしょ~」
参ったな、こんな顔と顔が数センチも離れていないような距離でこれは拒否できないじゃないか。
しゃべる度に吹きかけられる息が、顔にあたるとくすぐったくなって考える力が奪われていく。
愛理さん、これは事件です。
しゃべる度に吹きかけられる息が、顔にあたるとくすぐったくなって考える力が奪われていく。
愛理さん、これは事件です。
「ちょ、ちょっと~愛理何とか言ってよ。年ごろなんだし、一緒だとまずいじゃん」
「やれやれ、君はりーちゃんを襲わないって誓ったんでしょ。なら、まずいことは何もないじゃん。ね、りーちゃん」
「うん、そうだよ。襲わないなら一緒に寝ても問題ないでしょ」
「やれやれ、君はりーちゃんを襲わないって誓ったんでしょ。なら、まずいことは何もないじゃん。ね、りーちゃん」
「うん、そうだよ。襲わないなら一緒に寝ても問題ないでしょ」
君に助けを求めた僕が馬鹿でした。
愛理は助けるどころか今の状況を楽しんでさえいるタイプの人間だったんだ。
最近は割と仲が良くなってきたから助けてくれるかな、と期待していたけど、こうなってみると愛理は愛理なんだってある意味で安心する。
とりあえず、安心している場合じゃないのは確かなのだ。
愛理は助けるどころか今の状況を楽しんでさえいるタイプの人間だったんだ。
最近は割と仲が良くなってきたから助けてくれるかな、と期待していたけど、こうなってみると愛理は愛理なんだってある意味で安心する。
とりあえず、安心している場合じゃないのは確かなのだ。
「まずは冷静になろう。えぇと、りーちゃんはどうして僕と一緒に寝るのかってことなんだけど」
「ふふっ、その前に君が冷静になるべきだろう。ちっさー、観念しなさい。中学生が一緒に寝たって問題はないでしょ」
「い、いや、でもさ~僕ら年頃なんだよ。一応、体だって大人になってきてるんだしさ」
「それはりーちゃんが大人の体だっていいたいの? それとも君が大人の体なのかな?」
「ふふっ、その前に君が冷静になるべきだろう。ちっさー、観念しなさい。中学生が一緒に寝たって問題はないでしょ」
「い、いや、でもさ~僕ら年頃なんだよ。一応、体だって大人になってきてるんだしさ」
「それはりーちゃんが大人の体だっていいたいの? それとも君が大人の体なのかな?」
やっぱりどんなことを言っても愛理には口では勝てないんだって悟った。
僕がどんなに正しいことを言おうとも、愛理は黒を白にかえる力で言いくるめてしまう。
なので、りーちゃんは今は僕の隣も隣にいて、りーちゃんが入るならと愛理まで密着してきた。
つまり、僕らは三人が一つの布団に固まって寝ている状態になっている。
僕がどんなに正しいことを言おうとも、愛理は黒を白にかえる力で言いくるめてしまう。
なので、りーちゃんは今は僕の隣も隣にいて、りーちゃんが入るならと愛理まで密着してきた。
つまり、僕らは三人が一つの布団に固まって寝ている状態になっている。
「うちらがキッズに入ってから今ままでもう六年以上も経つんだね」
しみじみと思い出に浸りながら、愛理は天井を見上げて話し出した。
「うん、もう六年も経ったんだね。あの時さ、私は腕折って吊るしたまま、オーディション受けたんだよ」
腕折ったなんてただ事じゃないのに、りーちゃんは笑いながら平然と話す。
そういえば、りーちゃんは怪我をしていたなとおぼろげにあの時の姿が思い出される。
最終選考に残った中では腕を吊るしていたこともあって、結構印象深い。
それでも、腕よりも先にルックスに目がいくのはあの時から可愛い、と思っていたからだ。
愛理は抜群に歌のうまい子がいたな、とお父さんが録画してくれたもので意識をするようになった。
僕はというと、まだ歌もうまくなければ、ダンスだって踊れなかった頃だ。
そういえば、りーちゃんは怪我をしていたなとおぼろげにあの時の姿が思い出される。
最終選考に残った中では腕を吊るしていたこともあって、結構印象深い。
それでも、腕よりも先にルックスに目がいくのはあの時から可愛い、と思っていたからだ。
愛理は抜群に歌のうまい子がいたな、とお父さんが録画してくれたもので意識をするようになった。
僕はというと、まだ歌もうまくなければ、ダンスだって踊れなかった頃だ。
「ちっさーは男の子みたいな女の子だって、すぐに目についたな。後から本当の男の子だって知って、驚いたけどね」
「あれはあれで女の子にみえるようおしゃれしたつもりだったのに」
「愛理じゃないけど、私も男の子がいるって思っちゃった。だから、本当に男の子って知ったときも別に驚かなかったよ」
「あれはあれで女の子にみえるようおしゃれしたつもりだったのに」
「愛理じゃないけど、私も男の子がいるって思っちゃった。だから、本当に男の子って知ったときも別に驚かなかったよ」
さっきまでは僕の心臓もはちきれそうなくらいにバクバク高鳴っていたのに、今は落ち着いてくれている。
女の子が密着している状態だけど、思い出話に花を咲かせているなら僕は割と平気みたいだ。
我慢するにしても、なかなか無理だと心配だったけど、このまま寝るなら何も起きることはないはずだ。
よかった、誓いは裏切らずにすみそうだ。
僕にはまだ舞美ちゃんに舞ちゃん、どちらにも決められない好きな女の子がいるというのに、りーちゃんまで好きになったら大変だ。
誰も傷つけられず、答えが出せないまま悩み続けてしまう。
そうなった時、一番傷つくのは僕なんかではなく、りーちゃんたちなのだ。
ふぅ~今回はりーちゃんたちのお風呂場での光景といい、今日は誘惑の甘い罠が多いな。
眠るまで、ずっとこのままでいられたらいいのに、よりによってお風呂場から下着のことを思い出してしまった。
そう、お風呂場の前ではりーちゃんたちの下着までみてしまったんだった・・・
どっちの下着がどっちのものだったか、なんて考えてしまっていた。
それがいけなかった、僕はまた顔が焼けそうなくらい熱くなり、二人を妙に意識しだしていた。
女の子が密着している状態だけど、思い出話に花を咲かせているなら僕は割と平気みたいだ。
我慢するにしても、なかなか無理だと心配だったけど、このまま寝るなら何も起きることはないはずだ。
よかった、誓いは裏切らずにすみそうだ。
僕にはまだ舞美ちゃんに舞ちゃん、どちらにも決められない好きな女の子がいるというのに、りーちゃんまで好きになったら大変だ。
誰も傷つけられず、答えが出せないまま悩み続けてしまう。
そうなった時、一番傷つくのは僕なんかではなく、りーちゃんたちなのだ。
ふぅ~今回はりーちゃんたちのお風呂場での光景といい、今日は誘惑の甘い罠が多いな。
眠るまで、ずっとこのままでいられたらいいのに、よりによってお風呂場から下着のことを思い出してしまった。
そう、お風呂場の前ではりーちゃんたちの下着までみてしまったんだった・・・
どっちの下着がどっちのものだったか、なんて考えてしまっていた。
それがいけなかった、僕はまた顔が焼けそうなくらい熱くなり、二人を妙に意識しだしていた。