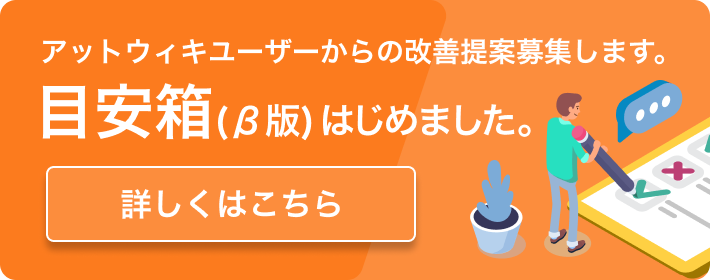「夢と現実の狭間で見た夢」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「夢と現実の狭間で見た夢」(2008/09/04 (木) 20:57:11) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
夢と現実の狭間で見た夢
俺達は何のために生きている…?
生きている証は何だ!?
考えても答えなどで出ない。むしろ無いのかもしれないとすら思えてくる。
そんな自問自答を繰り返しながらどれだけ意味の無い日々をすごしたのだろうか。いや… そんなことどうだっていい。事実だけは変わらない。
この場所に今存在している…
それだけは絶対的に変わらない事実。どんなに足掻いても、消すことのできない事実。だがその事実に何の意味がある?
所詮、心という名のプログラムを与えられた機械に過ぎない俺達に、存在する意味はあるのか?。
自問自答などまるで意味が無い…。事実だけは変わらない…答えが帰ってくるわけでもない。
俺は…一体何のために闘っているんだ…
アイリス…
静寂
沈黙だけが支配する静寂な空間が広がっている。その中の一部屋、カプセルルームらしき場所に彼はいた。
無機質な機械音が響いた。一つのカプセルがその音と共に開く。
中から彼は上半身を起こし、少し乱れた己の長い髪を軽く撫でる。
「…」
周りの静寂に便乗してか、彼もまた無言のままだ。傍らに置いてあったヘルメットをかぶった、そしてその体を起こす、背中に手を回せば愛用の武器が収納されていた。そこは薄暗く、彼の髪の色や瞳の色、そして身を覆う鎧の色はよく見えない。
薄暗いカプセルルームから出て、ひたすら伸びた道を歩ていく。やがて彼を光が照らす、その体は真紅の鎧に包まれ、鎧と同様に真紅のヘルメットからは金糸の長い髪が流れている、鋭く光る蒼い瞳と、整った男性特有の顔つきを見なければ、女性と間違えてしまいかねない。
「…誰もいないのか…?」
沈黙が支配する空間に彼の声が響いた。いつもと違う場景…此処、ハンターベースは異常な程の静寂に包まれていた。彼が先ほど入れた通信ですら誰も応答する者は居なかった。
一応ヘルメットに内臓された通信機をチェックするも、異常はまったく無いようだ。むしろ通信の状態は良好、通信障害から起こる雑音すらまったく聞こえなかった。
「いや…誰も居ないはずが無いが…」
唯でさえここ最近は、彼らハンター《処分者》が処分する対象であるイレギュラー《故障者》が頻繁に多発していて、何時も慌しかった。
大量のイレギュラー発生でハンター全員が出払っていたとしても、必ずオペレーターやライフセーバーがベースに残っているはず。
事情を知ろうと、オペレーションルームなどを回るも、人の影…動く物の気配はまったく感じることは無い。
ふいに彼は少し前の出来事を思い出す。正確に言えば少し前と言うよりは、記憶が途切れる前の出来事だ。どれだけ眠っていたのかが自分自身では分からない。
何故、自分があの場所に居たのかすら彼は知らなかった。
葛藤
「…本当か!?」
思わず彼は大声を出した。叫ばずにはいられなかった。
彼の目の前にいる、科学者に向かって大声で詰め寄った。流石に急に詰め寄られたせいか、彼の目の前にいる科学者は、ぐちゃぐちゃに絡まったコードにつまずき、ガタンという音を立てて後ろ向きに転んだ。
「…っ…すまん」
「い…いえ…、お気持ちは…分かります」
科学者はゆっくりと起き上がりながらそう言った。彼が科学者から告げられた言葉…、それは…
-アイリスを復活させることができる-
その一言を告げられた。
彼にとって思いもよらない言葉だった。そして、彼にとって願っても無い事だった。
しかし、歓喜と同時に不安もまた彼の脳裏をよぎった。そう…何か…、何か大事なことが抜けている…。それが彼の脳裏によぎった不安だ。
『葛藤』
彼女を復活させることができるということに、彼はすぐに返事を返さなかった。いや…返せなかった。
歓喜と不安が葛藤を続ける。
そんなさなか、不意に科学者からもう一つの事柄を告げられた。
-……し……記…ま…は…-
彼はほとんどその言葉が聞こえ無かった。そこで記憶が途切れたからだ。
しかし、彼は聞いたはずだった。その事柄を聞いていたはずだった。しかし、彼にその記憶は無い。
「…手がかりは…無し…か…」
溜息混じりに彼は言う。結局、今の状況になった理由の手がかりは無い。溜息が出ても仕方が無いだろう。
それは、彼の記憶が途切れる前のやり取りだった。
夢境
しばらく歩くと広場に着いた。
広い円状のその空間は、天窓からこぼれる光で晴れた日の昼間は照明を必要としない唯一の場所だ。
ハンターベース内で、時間の流れをゆっくりと感じることができる場所だ。人工的に植えられた木々が、光を反射し青緑色の色を更に引き立てている。
「…ここにも誰も居ないのか…」
いつもなら、暇さえあれば沢山のレプリロイドたちが集まるこの広場も、今は不気味なほどの静けさを持っている。
「…!?」
広場の中央部をしっかりと見た時、彼は驚愕した。先ほど彼が一通り見回した時は誰も居なかったはずだった。しかし、今は中央に一人の少女がたたずんでいる。
「…アイ…リス…」
そして…彼は、その蒼い瞳に映った少女の名を確認するように、そして…確かめるように彼女の名を呼ぶ。
天窓から差し込む日の光に照らされ、彼女はそこに居た。誰かを待つかのように、はるか高くにある天窓を見上げながら。
-ここにいるはずかない-
かすかな思考が、長い時間に感じる…あまりにも短くて長い時間。疑問だけが思考を支配していく。しかし、答えが出ることは無い。
「…ゼロ…?」
夢想
ゆっくりと振り返った彼女の口から彼の名が微かに漏れた。
これは夢だろうか?幻なのだろうか?自問自答は続く。
「…アイリス…なのか…?」
当然のような疑問。蒼い瞳を大きく開き、その姿をしっかりと確認しようとする。
その瞳に映る姿も声も彼女そのものだった。
「…ゼロ…」
また名を呼ばれた。少しずつ二人の間の距離は縮まっていく。彼の足は自然と彼女に向かって、一歩一歩確実に足を前に踏み出す。レプリロイド独特の足音が静寂な空間に響いた。
一歩分の距離すらないほどまでに詰め寄り、お互い見つめあうようにして視線を合わせ、静かにその瞳を見つめあう。
「アイリス…これは…夢なのか…?」
そして彼は率直に疑問を述べた。まさか自分が《夢》という言葉を使うとは思っていなかっただろう。内心彼は微かな笑みをこぼしていた、夢という言葉を否定し続けた彼自ら…夢という言葉を使用していたからだ。
「…どっちだと思う?」
静かに、そして優しく微笑みながら彼女はそう言った。
過去に失われたはずの微笑み…それが今、彼の目の前にある。彼女は夢であることを否定することも肯定することもなく、唯彼の目の前で微笑んでいた。
夢…それでもいいと彼は思った。たとえ夢であっても…夢だからこそ、それは偽者ではないからだ。
実体のない思考の中に存在する彼女自身であることに変わりはない。
夢と言う人間特有の物…それが何故自分にあるかという疑問は今の彼にとって、気に留めることではなかった。
怖気
静寂が続いた。
ただただ静かな時が過ぎていく。二人とも口を開くことなく肩を並べて座っていた。
今の彼らには言葉を交わす必要は無い。ただそこにいる存在を実感していた。
ありえないはずの存在。永久に続くことの無い時間…たとえ偽りだろうとも…
償いきれない罪…二人の間に作り出された壁はなおも深く二人を束縛していた。
「怨んではいないのか…?」
ふと出た一言。此処で出会ったときから彼が聞きたかったことだった。彼女の命を奪ったのは彼だ、そして彼が奪わなくてはならなかった要因は一つ…。彼女の兄を彼は《処分者》として破壊したからだった。
そして彼女は彼の前に姿を現した…《故障者》として…。
「…あの時は…すごく怨んでいた…。今も本当はまだ怨んでるかもしれない…でも…」
そこで言葉は途切れた。
信じられない光景が目の前に広がっていたからだ。言葉を失ってしまうほどの光景が…。
「アイリス…下がっていろ。すぐに片付ける」
そういって彼は彼女を庇うように前に立った。
無限とも思えるほど大量の《故障者》を前にして
戦意
ガシャンガシャンと機械と機械がぶつかる音が大量に聞こえる。
大量などという言葉ではすまないかもしれない。その数は百・・・二百・・・千すら越えるかもしれない。
意思を持たない無数の瞳が不気味に赤く光った。それらは皆、腕の糸だけが切れた操り人形のように腕はだらんと地に垂れ下がっている。
そう…それらは操り人形だった。《故障者》と言う名の意思を持たない操り人形。本当に誰かに操られているのだろうか、それともそれらもまた彼の夢が作り出した産物なのだろうか…。
襲い掛かってこようものなら容赦はしないと言うように、彼は背中に収納してある己の名の一部を称したビームサーベル-Zセイバー-に手をかけようとする。
「…!?」
しかし、その手の先には愛用のセイバーは存在しなかった。カプセルから起き上がった時には有った筈だった。収納中はしっかり固定されているため落としたという確率は限りなく0%に近い。かつて愛用していたエネルギーの塊を打ち出す銃-バスター-は今はもう使うことは出来ない。その回路自体が壊れてしまったためだ。
彼は、大量の《故障者》を目の前にして、丸腰という最悪の事態に陥った。
守戦
どれだけ時間がたっただろうか。
彼の肩から鎧が落ちた。ガシャンという落ちた音すら無数の《故障者》の達が奏でる機械音によってかき消されていく。
先ほどから彼は、ずっと防戦を強いられていた。《故障者》達の手により、肩の鎧は砕け落ち、ヘルメットもまた砕かれ金糸の前髪が露わになっている。
逃げるという道は存在しなかった。彼女を護るうちに壁際に追い詰められていたからだ。彼は戦法を誤ってしまった、自ら逃げ道という最終手段を失う道を選んでしまったから。
彼女はすでに彼にかける言葉を失っていた。逃げるという言葉も今は無駄に等しい。
彼は苛立っていた。《護る》という行為の難しさを痛感している、文字通り《痛み》を伴って。下手に攻撃すれば反撃を受け大ダメージを負いかねない。
―これが…護るということか―
苛立ちとともに、彼の脳裏には深い青色の鎧を装備した戦友の姿が映っていた。
あくまでも戦いを望まず、護るという甘さを残した戦い方をしている。
その戦い方は本当に甘かったのだろうか…?-できることなら誰も倒したくない-それは確かに甘いのかもしれない。しかしそれは至極困難なのかもしれない…。
そんな考えを知ることもなく、《故障者》達はただただ命令を忠実に遂行するかのように容赦なくその腕を振り上げた。
夢魂
やがて限界が来た。彼の膝は支える力を失い崩れ落ち、腕は機械部が露出していてダラリと力なく垂れ下がっている。
数がまったく減らないままの《故障者》達は我先にと、抵抗する力すらほとんど残っていない彼に群がった。
此処であきらめるのはらしくないとは思いながらも、この状況から脱する術は残されていなかった。
しかし、術も力も無くしてなおあきらめ切れなかったのか、彼はもはやほとんど動かない腕を必死に支えとして立ち上がろうとした。
「ゼロ…もうやめて…」
悲痛な表情をした彼女が呟く。
彼は立ち上がった。立ち上がることを《故障者》達に邪魔されつつも、何度も倒れつつも …立ち上がった。
咆哮しながらボロボロになった腕を《故障者》達に向け叩き込む。そうしたことで結果は変わらないだろう、そう思いつつも足掻く。
―かつて俺はこんなにも足掻くことがあっただろうか?
―感化されたのかもしれないな…
―アイツに…
―死ぬまで足掻いてやろう…
―この体が壊れても―
終局
もう何度倒れ、立ち上がっただろうか…。
すでに限界は超えているはずだった。手足の感覚も残っていないはずだった…。
彼の目の前には今、信じられない光景が広がっている。
「…これは…」
唖然としながらも彼は周りを見回す。その視線の先にアレだけ溢れていた《故障者》の姿は無い。床を見ても自分が殴り壊した残骸も残っていない。それどころか、彼の壊れていたはずの腕や砕けた肩の鎧…それら全てが巻き戻ったかのように…何事もなかったかのように綺麗なままで存在していた。
そしてもう一つ気付いた事がある…
「…アイリス…?」
彼女の姿はそこにはなかった。
「…アイ…リス…」
もう一度彼女の名を呼ぶ。しかし返事は帰ってこなかった。
沈黙が続く…果てしない沈黙
機械音が少しずつ大きく聞こえた…
彼にとって聞きなれた音だった…
現実
無機質な機械音が規則正しく聞こえる。薄暗く周りを見渡しても薄っすらとしか回りを見ることが出来ない。
いくつかのカプセルが並んでいる。どうやらこの場所はカプセルルームらしい。
その中のカプセルが一つ開いた。その中から金糸の髪をした青年が起き出してくる。
―夢…か…
起きてすぐ彼は一つの思考に浸った。まるで精神統一をするかのようにまぶたを閉じ、考えに浸る。
夢にしてはリアルな夢だったからだ。もちろんありえないことが起った、それは夢と片付けても問題は無いだろう。しかし、その《ありえない出来事》で受けた傷は確かに痛みを伴っていた。
―夢…と現実の狭間…の夢…?
結論は出ない。しかし彼はその思考に妙に納得していた。
夢であって現実の痛みを伴う…それでもそれは夢だった。
夢でしかありえない出来事、現実でしか伴わない痛み…。
果ての無い思考を止め、彼はゆっくりとまぶたを開く。その瞳は強い意志を示すかのように凛とした蒼い色をしていた。
思考
「ゼロ…どうしたんだ?そんなにボーっとして」
戦友の声が聞こえる。その声は少し心配しているような声にも聞こえた。戦友の蒼い鎧は太陽の光を受けて更に美しい蒼色となっていた。
「…ん?あぁ、すまない。少し考え事を…」
彼はまたあの夢のことを考えていた。しかしその考えは今までの考え方とは違う。あの夢が残してくれたものについてだ。
戦友は答えにかすかに苦笑した。聞くまでも無い、彼らしい答えだったからだろう。
「…エックス…お前はレプリロイドが見る夢というものを信じるか?」
戦友―エックス―は一瞬驚いた顔をする。無理も無い、現実主義の傾向が強い彼の口から《夢》等という言葉が出たのだ。
「…俺は信じている。レプリロイドだって生きているんだ、夢くらい見たって不思議じゃないだろう?」
ゼロはふっと笑う。いかにもエックスらしい答えが聞けたからだ。もしかしたら彼はその答えが聞きたかったのかもしれない。不思議な安心感が彼の心を包む。
エックスはゼロに聞いた事があった。
彼女―アイリス―を復活させることができるというチャンスを何故自ら手放したのか…と。もちろん彼がその道を選ぶことは最初から百も承知の上だった。それでも彼女を失って戻ってきた彼の様子の事を思い出すと聞かずにはいれなかった。
『アイリスが生き返ったところでカーネルは生き返らない。…元をたどれば俺がカーネルを《イレギュラー》として排除してしまったからだ…。それに、終わってしまった出来事を引きずってばかりではどうにもならないからな…』
それが彼の答え。エックスはその答えに彼らしい答えだと納得した。
道標
アイリスは兄・カーネルの仇をとるためにゼロの前に《イレギュラー》として立ちはだかった。そして…ゼロはアイリスを《故障者》として討った。
生き返らせることでそのときできてしまった溝は埋めることはできない。
記憶も、メモリーの破損故、生き返らせたところで戻る事は無い。彼女がかつてのことを忘れたとしても、ゼロの記憶にはそのことがしっかりと残っているのだ。
そしてそれは「夢と現実の狭間で見た夢」で叶った。
夢の産物であってもあやまることが出来たから…。
―彼は振り返らない
―過去を捨てているわけじゃない。過去を振り返らないだけだ
―そして新たな道を切り開いていく
―それが《彼》だ―
戦友とともに彼は歩いた。かすかな風が彼の金糸の髪を撫でる。
一歩一歩確実に大地を踏み締めて戦友と友に歩く。
その先に何があるのかはわからない。
それでも…彼らは歩くだろう。
―過去を振り返らずに・・・未来を見つめて―
夢の終わりに
―ありがとう…ごめんなさい―
―本当は分かっていたの…でも避けられなかった―
―だから…―
―もう楽になって…苦しまなくてもいいから…―
―でもたまには…私のことを思い出してほしい―
―さようなら…ありがとう―
それは夢の終わりに聞こえた言葉だった
-fin-
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: