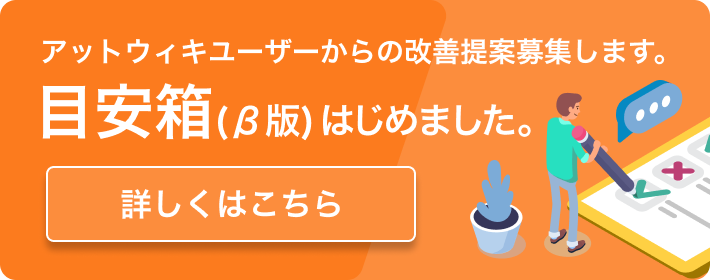76 :トリップ忘れた 1/11:2009/02/03(火) 00:26:40 ID:kD/rp+DB
「ふぁぁう…やぁううっ!はぅうう…!…やだようっ、やさしくなんてやだぁぁ……
すごく疼いて、お尻が火傷しちゃいそうなのに、なんでガツガツしてくれないのぉ……」
正常位で組み敷いている小さな身体は、捻じ込み、引き抜く度に、断末魔の痙攣を打った。
腹の中には既に二回ほど灼熱の汚液を蒔いている。内部の肉襞は、粘膜同士が触れ合うだけで理性が溶解してしまう。
下手に性感が得られないように肉の塊を根元まで食わせたまま動きを止め、
楔のようにベッドへ縫い付けている最中にも、剛直に吸い付く柔毛が更に正気を破壊する。
俺が果てるまで、この悪循環は止めどない。
「ね、いじめてぇ、いじめてよぉぉ……。はやく…痛くして…下さいぃ……痛いのがいいのに……」
熱い疼きに狂わされた少年は卑しく淫らで、貪欲だ。僅かな隙を見付けては自ら腰をくねらせて、浅ましく快楽に耽ろうとする。孔が裂けるか擦り切れるまでの蹂躙に晒されなければ、いつまで経っても満たされない体にまで成り果ててしまっていた。
「そうかよ。……口、開けろ。」
口の奥で震えて縮こまっている舌を何度か小さく突付けば、それに誘われてか、唇の辺りまで必死に伸びて来る。寄り縋ってくる喜色ばんだそれに前歯を立てて、噛む。
「ぅぃぎいいいいいいいいいい!!!!!!!」
甘噛みなどという生易しいものではない。鋭利な歯先が舌の裏表に深々と刺さったのだ。
口の中で一気に鉄錆の味が広がる。嫌な生臭さが鼻腔を突き、噎せそうになった。
上下の顎を左右互い違いに、弾力のある肉も軽々と挽く動きは、鋸によく似ている。
「ぃいぃ、いいいい!!!ぎっ!!いひいいぃいぃっ!!!!」
やがて、舌裏側の傷が最も酷くなった。
やっと念願通りの物を貰えた華奢な体は、腸内を引き攣らせながら軽い絶頂に震える。
こんな事が起こるのは、てっきり膣ばかりだと思っていた。
男もどきとのアナルセックスだろうと、きちんと肉の痙攣を味わえたというのも初めての経験だが、さして驚くには値しない。
「ふぁぁう…やぁううっ!はぅうう…!…やだようっ、やさしくなんてやだぁぁ……
すごく疼いて、お尻が火傷しちゃいそうなのに、なんでガツガツしてくれないのぉ……」
正常位で組み敷いている小さな身体は、捻じ込み、引き抜く度に、断末魔の痙攣を打った。
腹の中には既に二回ほど灼熱の汚液を蒔いている。内部の肉襞は、粘膜同士が触れ合うだけで理性が溶解してしまう。
下手に性感が得られないように肉の塊を根元まで食わせたまま動きを止め、
楔のようにベッドへ縫い付けている最中にも、剛直に吸い付く柔毛が更に正気を破壊する。
俺が果てるまで、この悪循環は止めどない。
「ね、いじめてぇ、いじめてよぉぉ……。はやく…痛くして…下さいぃ……痛いのがいいのに……」
熱い疼きに狂わされた少年は卑しく淫らで、貪欲だ。僅かな隙を見付けては自ら腰をくねらせて、浅ましく快楽に耽ろうとする。孔が裂けるか擦り切れるまでの蹂躙に晒されなければ、いつまで経っても満たされない体にまで成り果ててしまっていた。
「そうかよ。……口、開けろ。」
口の奥で震えて縮こまっている舌を何度か小さく突付けば、それに誘われてか、唇の辺りまで必死に伸びて来る。寄り縋ってくる喜色ばんだそれに前歯を立てて、噛む。
「ぅぃぎいいいいいいいいいい!!!!!!!」
甘噛みなどという生易しいものではない。鋭利な歯先が舌の裏表に深々と刺さったのだ。
口の中で一気に鉄錆の味が広がる。嫌な生臭さが鼻腔を突き、噎せそうになった。
上下の顎を左右互い違いに、弾力のある肉も軽々と挽く動きは、鋸によく似ている。
「ぃいぃ、いいいい!!!ぎっ!!いひいいぃいぃっ!!!!」
やがて、舌裏側の傷が最も酷くなった。
やっと念願通りの物を貰えた華奢な体は、腸内を引き攣らせながら軽い絶頂に震える。
こんな事が起こるのは、てっきり膣ばかりだと思っていた。
男もどきとのアナルセックスだろうと、きちんと肉の痙攣を味わえたというのも初めての経験だが、さして驚くには値しない。
牡の精に穢された体の、汚染され尽くした血潮を、一滴たりとも逃すまいと吸い立てる。正直、血液はとても不味いと思う。この塩梅では、人間などさして美味いものでもなさそうだ。まともに咽を通りそうな体など、こいつの血肉くらいしか思い付かない。
(んむううーー!みゅうっ!ふみゅううう!んむぅっ、うう、みゅふううっ!)
嬌声は決してまともな声にはならない。単なる酸素を求める嘆願と喉の震えを、肉伝いに俺に叫んでいる。
まだ未成熟の幼い腸内だけでなく、マシュマロのように柔らかい唇をも、深々と貪り喰らう。
長く伸びた後ろ髪を右手で引き掴んで上を向けさせ、左手は華奢な肩を掻き抱いていた。
また奥に引き篭もった短い舌に絡んで締め上げれば、古い火傷で変形した箇所を幾度も味わわされる。
故意に緩慢で長々とした時間を掛け、こうして執拗に責め抜く行為が、楽しい。
蕩けきった粘膜を征服しつつあるときに不意に敏感な肉を抉ろうものなら、それだけで達したかのような激しい痙攣に襲われてしまう。自分を食い千切られかねない締め付けにも構わず、或いは探り当てた部分を徹底して追い詰めるように、一定の速度で往復を続けるのだ。
流石というか、俺自身に与えられる快感は、暴力じみた突き込みで味わう悦びとは比較にならない弱いものだが、どれほどの時を費やしても、その経過さえ忘れさせる幸福感、積年の孤独を満たして余りある充実感は、何物にも変え難い愉しみの一つになっていた。
(んむううーー!みゅうっ!ふみゅううう!んむぅっ、うう、みゅふううっ!)
嬌声は決してまともな声にはならない。単なる酸素を求める嘆願と喉の震えを、肉伝いに俺に叫んでいる。
まだ未成熟の幼い腸内だけでなく、マシュマロのように柔らかい唇をも、深々と貪り喰らう。
長く伸びた後ろ髪を右手で引き掴んで上を向けさせ、左手は華奢な肩を掻き抱いていた。
また奥に引き篭もった短い舌に絡んで締め上げれば、古い火傷で変形した箇所を幾度も味わわされる。
故意に緩慢で長々とした時間を掛け、こうして執拗に責め抜く行為が、楽しい。
蕩けきった粘膜を征服しつつあるときに不意に敏感な肉を抉ろうものなら、それだけで達したかのような激しい痙攣に襲われてしまう。自分を食い千切られかねない締め付けにも構わず、或いは探り当てた部分を徹底して追い詰めるように、一定の速度で往復を続けるのだ。
流石というか、俺自身に与えられる快感は、暴力じみた突き込みで味わう悦びとは比較にならない弱いものだが、どれほどの時を費やしても、その経過さえ忘れさせる幸福感、積年の孤独を満たして余りある充実感は、何物にも変え難い愉しみの一つになっていた。
そんな微弱な快楽であっても、時間の流れが溶けてしまう程のストローク数をこなせば、
自分でもいつ暴発を迎えてしまうかどうか解らないくらいの瀬戸際に立たされてしまえる。
俺の背中にしがみついている健気な指の力が、徐々に、だがはっきりと弱くなりつつあるのが分かれば、
そろそろいいか、という気分にもなるのだ。
ペニスの根本からは少しの距離的な余裕を残して、両の太腿を僅かに持ち上げる。
互いのフィニッシュに、速く小刻みなピストンを齎せば、限界を越えた快楽に溺れる小柄な背が電気ショックに当てられたように上下して弾けた。
俺の腹には、熱く火照った半固形物が断続的に打ち上げられる。
前立腺が軟らかく蠢いて射精に耽る、腸粘膜の淡い蠕動が、抗い様の無い射精感をこみ上げさせた。
呼吸を許してやるべく、唇の繋ぎ止めを明け渡す。様々に暗闇に爛々と艶めく、銀糸の橋が縦に掛けられる。
「いいな?」
声は掛けれども、相手からの返事など全く期待していない。
二人分の体重で金属質の悲鳴を上げるベッドを無視して、波打つシーツと俺の質量の合間に挟み込み、まるでプレス機のように押し潰した。
右肩の上にやっと顔の上半分が出るくらいの配慮をしてやれば、俺達にはそれで十分だ。
こいつだって、こうしてやれば悦ぶ筈だと独り合点して、何度も強引なピストンを繰り返す。
縋り付くようなものから一転、堰を切ったように背中を激しく掻き毟る、しなやかな指先が寧ろ心地良い。毎夜のように丁寧に爪を切り揃える行為など無駄とばかり決め付けていた、過去の荒んだ自分が恨めしく思えるほどに。
「んんん… ひゃ、ん、ぁぅ、あ、ふぅあっ、ぅああ!んあ…、あー、ゎうぁあああぁー!!!!」
甘ったるい高音の嬌声が喉の下辺りから飛んで、内耳をこそばゆくくすぐる。
咄嗟に、眼下で白く眩く輝く、柔らかそうな喉仏を噛み千切ってやりたい衝動に駆られたが、この体位では決して届きそうもなかった。
自分でもいつ暴発を迎えてしまうかどうか解らないくらいの瀬戸際に立たされてしまえる。
俺の背中にしがみついている健気な指の力が、徐々に、だがはっきりと弱くなりつつあるのが分かれば、
そろそろいいか、という気分にもなるのだ。
ペニスの根本からは少しの距離的な余裕を残して、両の太腿を僅かに持ち上げる。
互いのフィニッシュに、速く小刻みなピストンを齎せば、限界を越えた快楽に溺れる小柄な背が電気ショックに当てられたように上下して弾けた。
俺の腹には、熱く火照った半固形物が断続的に打ち上げられる。
前立腺が軟らかく蠢いて射精に耽る、腸粘膜の淡い蠕動が、抗い様の無い射精感をこみ上げさせた。
呼吸を許してやるべく、唇の繋ぎ止めを明け渡す。様々に暗闇に爛々と艶めく、銀糸の橋が縦に掛けられる。
「いいな?」
声は掛けれども、相手からの返事など全く期待していない。
二人分の体重で金属質の悲鳴を上げるベッドを無視して、波打つシーツと俺の質量の合間に挟み込み、まるでプレス機のように押し潰した。
右肩の上にやっと顔の上半分が出るくらいの配慮をしてやれば、俺達にはそれで十分だ。
こいつだって、こうしてやれば悦ぶ筈だと独り合点して、何度も強引なピストンを繰り返す。
縋り付くようなものから一転、堰を切ったように背中を激しく掻き毟る、しなやかな指先が寧ろ心地良い。毎夜のように丁寧に爪を切り揃える行為など無駄とばかり決め付けていた、過去の荒んだ自分が恨めしく思えるほどに。
「んんん… ひゃ、ん、ぁぅ、あ、ふぅあっ、ぅああ!んあ…、あー、ゎうぁあああぁー!!!!」
甘ったるい高音の嬌声が喉の下辺りから飛んで、内耳をこそばゆくくすぐる。
咄嗟に、眼下で白く眩く輝く、柔らかそうな喉仏を噛み千切ってやりたい衝動に駆られたが、この体位では決して届きそうもなかった。
早くこの柔らかい内臓洞の中で、我が物顔で何度も伸び上がり、心行くまで存分な量を撒き散らしたい。
馬鹿馬鹿しい強さの洋酒のように、こいつの甘い肉襞は俺の神経を芯から灼き焦がしているというのに。
出したくないときは早漏な癖に、こうして早く果てたいときに限ってなかなか吐き出せないものだ。
また不必要に股関節が外れなければいいが。今夜は目的があって、こんな懇な抱き方をしているのだから。
「出そうだぞ。どこに欲しい」
「なかにぃ!!!なかにだしてぇぇ!!!」
「いい子だ」
殊勝な反応に薄く笑って。肌に指が埋まるぐらいに強く、華奢な躯を抱き締めた。
「…かっ…はっ!、……うっ……ぐ…。」
馬鹿馬鹿しい強さの洋酒のように、こいつの甘い肉襞は俺の神経を芯から灼き焦がしているというのに。
出したくないときは早漏な癖に、こうして早く果てたいときに限ってなかなか吐き出せないものだ。
また不必要に股関節が外れなければいいが。今夜は目的があって、こんな懇な抱き方をしているのだから。
「出そうだぞ。どこに欲しい」
「なかにぃ!!!なかにだしてぇぇ!!!」
「いい子だ」
殊勝な反応に薄く笑って。肌に指が埋まるぐらいに強く、華奢な躯を抱き締めた。
「…かっ…はっ!、……うっ……ぐ…。」
ごぶびゅるううう!!!ぶううううううっ!!!!びゅうううっ!!ぶぶぶううううーー!!!
「っっっきゃぁあああああああぁぁ!!!!!!!あづいいいっ!!!!おにゃかあづいのおおおお!!!
いぐのぉ!いっでるのにまだいぐのぉぉ!!いぐっ!いぐっいぐっ!いぐぅぅっ!
いぐいぐいぐいぐうううううう!!!!!!」
いぐのぉ!いっでるのにまだいぐのぉぉ!!いぐっ!いぐっいぐっ!いぐぅぅっ!
いぐいぐいぐいぐうううううう!!!!!!」
抑圧されていた射精衝動がいざ放たれるときは、その勢いも継続力も堪らなかった。
迸るマグマは熱く粘りつき、睾丸の根本から尿道の放出口まで燃え上がってしまいそうな熱量を感じる。
何も知らない生殖器官だけが、性感の昂ぶる、若く健康的な恋人を孕まそうと、懸命に精を放っていた。
何百回…いやきっと、千回を越えてぶち撒けているのかも知れない。
こいつの全細胞が、俺の吐き出した精子で置き換えられる位の数はとっくの昔に及んでいるだろう。
ぶぶううー… びゅうううー… ぶじゅうううー… びゅううううーー…
「あー!!!!! ああーー!!!!! ひやぁっ、うやぁぁ!!!!! んきゃぁあぁーー!!!!」
ペニスがしゃくり上げる時、精液が腸のS字を叩いた時、
ドロドロのゲル液が腹の中に広がり、亀頭のざらつきが精液を無理矢理に腸壁へと塗り込める時。
そういった、俺の射精に伴う何もかもに少年はただひたすら達きまくり、胸板の下でトチ狂ったようにのたうち回る。
決して逃げられないように、この手中から離れられないように、腕力も握力も限界まで引き絞って、
あどけない少年に行われる種付けは、永遠に終わりそうもないように思えた。
ぎいぎい、ぎしぎしと明らかに、幼い関節が、或いは骨格が軋んでいる事を示す耳障りな音色は、
まるで瀕死の虫けらのようだった。
迸るマグマは熱く粘りつき、睾丸の根本から尿道の放出口まで燃え上がってしまいそうな熱量を感じる。
何も知らない生殖器官だけが、性感の昂ぶる、若く健康的な恋人を孕まそうと、懸命に精を放っていた。
何百回…いやきっと、千回を越えてぶち撒けているのかも知れない。
こいつの全細胞が、俺の吐き出した精子で置き換えられる位の数はとっくの昔に及んでいるだろう。
ぶぶううー… びゅうううー… ぶじゅうううー… びゅううううーー…
「あー!!!!! ああーー!!!!! ひやぁっ、うやぁぁ!!!!! んきゃぁあぁーー!!!!」
ペニスがしゃくり上げる時、精液が腸のS字を叩いた時、
ドロドロのゲル液が腹の中に広がり、亀頭のざらつきが精液を無理矢理に腸壁へと塗り込める時。
そういった、俺の射精に伴う何もかもに少年はただひたすら達きまくり、胸板の下でトチ狂ったようにのたうち回る。
決して逃げられないように、この手中から離れられないように、腕力も握力も限界まで引き絞って、
あどけない少年に行われる種付けは、永遠に終わりそうもないように思えた。
ぎいぎい、ぎしぎしと明らかに、幼い関節が、或いは骨格が軋んでいる事を示す耳障りな音色は、
まるで瀕死の虫けらのようだった。
上体を反らして、冷えた空気に煮え滾った半身を曝す。
深く落ち着いた呼吸は茹だった脳髄を鮮明にさせる。蜃気楼の只中だった視界が開けると、そこは見慣れた自分の寝室だった。
少年とは、未だに繋がったままでいる。
薄い胸は、薄暗がりの中でもはっきりと判るくらい大きく上下して、必死に酸素を摂り入れているようだった。
恍惚とした表情を浮かべて性感の余韻に浸っている少年は、やはり奇麗だと思う。
両腕は中途半端に肘の曲がったバンザイの形で弛緩し、頬は紅潮して、瞳は焦点を失う、黒い虹彩は靄がかって澱んでいる。
殆ど陽に当たらないきめ細やかな肌は、白無垢に薄紅を掛けたようだった。
頬にはどこか痛々しい、壊れた微笑みが張り付いて、震えを伴った悩ましい喘ぎを漏らしている。
シーツの上で扇のように広がる、烏の濡れ羽色の長さが、同時に、俺達の関係の深さをも表していた。
大昔こそ小汚く、抜け毛も多かったそれは、今では生まれ変わったように美しく艶めいている。
本当は、いいところのお嬢…いや、お坊ちゃんなんだ。今までは素材をドブに捨ててただけだ。
平安貴族とか、こんなんじゃなかったか。俺は、かぐや姫ぐらいしか知らんが。
……あれは、確か、月に帰ってしまったな。今は、よそう。
深く落ち着いた呼吸は茹だった脳髄を鮮明にさせる。蜃気楼の只中だった視界が開けると、そこは見慣れた自分の寝室だった。
少年とは、未だに繋がったままでいる。
薄い胸は、薄暗がりの中でもはっきりと判るくらい大きく上下して、必死に酸素を摂り入れているようだった。
恍惚とした表情を浮かべて性感の余韻に浸っている少年は、やはり奇麗だと思う。
両腕は中途半端に肘の曲がったバンザイの形で弛緩し、頬は紅潮して、瞳は焦点を失う、黒い虹彩は靄がかって澱んでいる。
殆ど陽に当たらないきめ細やかな肌は、白無垢に薄紅を掛けたようだった。
頬にはどこか痛々しい、壊れた微笑みが張り付いて、震えを伴った悩ましい喘ぎを漏らしている。
シーツの上で扇のように広がる、烏の濡れ羽色の長さが、同時に、俺達の関係の深さをも表していた。
大昔こそ小汚く、抜け毛も多かったそれは、今では生まれ変わったように美しく艶めいている。
本当は、いいところのお嬢…いや、お坊ちゃんなんだ。今までは素材をドブに捨ててただけだ。
平安貴族とか、こんなんじゃなかったか。俺は、かぐや姫ぐらいしか知らんが。
……あれは、確か、月に帰ってしまったな。今は、よそう。
白く濁った泥濘がこいつの腹の上に広がっているのに、やっと気付いた。
一回の射精にしては、どうしたって多過ぎる。飛び散る飛沫は点々と続き、欠片は喉まで及んでいるが、それでも不自然なバランスだ。
……トコロテンが続いていたのだろうな。犯ってる間、延々と達きっぱなしだったのか。
無意識に頬が歪んだ。これが笑みだと気付いた人間など、世界中でこの少年以外に何者が居るだろう。
半分が獣に成り代わった意識は、俺の首から下を支配している。再び鎌首を擡げ始めた欲望の捌け口を求めて、俺を扇情して止まない、愛しい淫らな少年の上へと覆い被さった。
「ふぁあぁ、せんぱぃぃ、らめぇ、らめらよう、らめ、らめぇ……
もう、おなかぁ、ぱんぱんなのぉ……孕んでるのに…、膨らんでるのにぃ……」
またっ、ごりごりして、びゅーびゅー出されたら……おにゃか、はれぇ、はれつっ、しちゃ……あぁっ!!あきゃあああああ!?!?!?」
「知るか。俺が足りないんだ。」
腹筋も脂肪も薄い、白濁に塗れ尽くした陶磁の肌の下でぐるぐる巡る、不浄のチューブごと横隔膜を押し上げれば、
一瞬呼吸が途切れた後に、少年の形をした単なる奇麗な物体が、浅ましい熱病を再び始め出した。
細い両足が腰に巻き付いて、縋り付いた両手は背に回り、肩甲骨の上をくすぐったく掻き回す。
これを繋ぎ止める理由だって、有り余る若い欲望の処理具と言い訳するのも限界に近くなっている。
間違ってはいない。こいつになら、何発出したって飽き足らない。
この性欲がつまりは愛情なのだと自分を偽れば、夜は一向に更けることがないのだ。
一回の射精にしては、どうしたって多過ぎる。飛び散る飛沫は点々と続き、欠片は喉まで及んでいるが、それでも不自然なバランスだ。
……トコロテンが続いていたのだろうな。犯ってる間、延々と達きっぱなしだったのか。
無意識に頬が歪んだ。これが笑みだと気付いた人間など、世界中でこの少年以外に何者が居るだろう。
半分が獣に成り代わった意識は、俺の首から下を支配している。再び鎌首を擡げ始めた欲望の捌け口を求めて、俺を扇情して止まない、愛しい淫らな少年の上へと覆い被さった。
「ふぁあぁ、せんぱぃぃ、らめぇ、らめらよう、らめ、らめぇ……
もう、おなかぁ、ぱんぱんなのぉ……孕んでるのに…、膨らんでるのにぃ……」
またっ、ごりごりして、びゅーびゅー出されたら……おにゃか、はれぇ、はれつっ、しちゃ……あぁっ!!あきゃあああああ!?!?!?」
「知るか。俺が足りないんだ。」
腹筋も脂肪も薄い、白濁に塗れ尽くした陶磁の肌の下でぐるぐる巡る、不浄のチューブごと横隔膜を押し上げれば、
一瞬呼吸が途切れた後に、少年の形をした単なる奇麗な物体が、浅ましい熱病を再び始め出した。
細い両足が腰に巻き付いて、縋り付いた両手は背に回り、肩甲骨の上をくすぐったく掻き回す。
これを繋ぎ止める理由だって、有り余る若い欲望の処理具と言い訳するのも限界に近くなっている。
間違ってはいない。こいつになら、何発出したって飽き足らない。
この性欲がつまりは愛情なのだと自分を偽れば、夜は一向に更けることがないのだ。
起き抜けには既に、あれは冬場の猫のように俺にひっついていた。
朝っぱらから発情しているのを隠そうともせず目を爛々と光らせて擦り寄る子供は、物理的に引き剥がすだけなら容易である。
「今日はお休みの日ですよ。折角お尻がぬるぬるなのに。」
「いいから風呂行け。朝から精液臭えんだよお前は。」
我ながら稚拙な根拠だ。不思議そうに此方を見上げる瞳に迂闊に惹き込まれそうになって、慌てて顔面を張り倒す。
無言の威圧で追い立てられ、ぺたぺた急ぎ浴室へ向かう足取りは、比較的しっかりしている。
内股を伝って流れ落ちる精の雫は粘度も低く、透明に見えた。あれの後始末は、長く掛かるだろう。
朝っぱらから発情しているのを隠そうともせず目を爛々と光らせて擦り寄る子供は、物理的に引き剥がすだけなら容易である。
「今日はお休みの日ですよ。折角お尻がぬるぬるなのに。」
「いいから風呂行け。朝から精液臭えんだよお前は。」
我ながら稚拙な根拠だ。不思議そうに此方を見上げる瞳に迂闊に惹き込まれそうになって、慌てて顔面を張り倒す。
無言の威圧で追い立てられ、ぺたぺた急ぎ浴室へ向かう足取りは、比較的しっかりしている。
内股を伝って流れ落ちる精の雫は粘度も低く、透明に見えた。あれの後始末は、長く掛かるだろう。
たっぷり一時間半は掛けて湯上がったあれに、まだ体が温かい内に手渡したものがある。
「あ、あの…。いかがでしょうか。」
自信無さ気に、心なしか紅潮した頬と、上擦った声でおずおずと披露されても、
女物の合う合わないに心得の無い俺ごときに、気の効いた文句は都合良く浮かぶ訳もない。
それにしても、目の端が心なしか潤んでいるのに苛立たされる。どこまでも面倒臭い奴だった。
「ああ……前と後ろは、間違ってないんじゃないか。」
今までこいつは、毛布かシーツを一枚だけ体に巻き付けた、大昔の地中海人じみた、服とは言えない服装ばかりだった。褒めたつもりもないのに声を殺してすすり泣く顔が微妙に綻んでいるのには、嫌でも苦笑いを誘われる。
「じゃ、行くか。」
「はい?」
「休みだからな。天気もいい。久し振りに、外に出してやる。」
あからさまに唖然と口を開け、間の抜けた面相を作った。
此方が不愉快そうに眉を顰めても、あれは構わず蒼褪め、首を横に往復させる。顔の忙しい奴だ。
「だっ、だめです!明るいうちに外なんて、絶対だめ!もしばれたら、先輩捕まっちゃいます!」
俺の鼻息一つで、キャンキャン吠えるだけの反論モドキは止んだ。
女モドキのゴミ虫は、さも申し訳なさそうに背筋を縮こめて、甚だ俯いて、何言やらぼそぼそと呟いている。
首根っこを引っ掴んで、姿見の方へ向き合わせた。一人の世界に篭っている脳味噌など、背中を引っ叩けばそれでいい。
「自分の目で見てみろ。昔のお前とは、てんで似ても似つかないだろ。」
鏡に映る人間は、強張った表情で怪訝そうに大きな瞳を見開き、自分の頭の天辺から爪先までを信じ難い物を見るように眺め続けている。
頬や服の裾、袖をあちこち摘んでは息を飲み、疑い深く自分で自分を睨み付ける様子など、肩越しに見ていて思わず噴き出しそうな程だった。
徹底して地味に統一された揃えだった。冬用の女物を見るのは、こいつも初めてではなかろうに。いや、初めてなのかも知れないが。
丈の長めのスカートを穿かせたって、膝小僧の辺りの少年らしい骨っぽさはどうしたって隠せるものではないが、上にコートでも羽織らせれば誤魔化せるだろう。
防寒具の色合いは暖色と言えなくもないが、これではむしろ、枯れ木や落ち葉の色を連想してしまうのだけれども。
「あ、あの…。いかがでしょうか。」
自信無さ気に、心なしか紅潮した頬と、上擦った声でおずおずと披露されても、
女物の合う合わないに心得の無い俺ごときに、気の効いた文句は都合良く浮かぶ訳もない。
それにしても、目の端が心なしか潤んでいるのに苛立たされる。どこまでも面倒臭い奴だった。
「ああ……前と後ろは、間違ってないんじゃないか。」
今までこいつは、毛布かシーツを一枚だけ体に巻き付けた、大昔の地中海人じみた、服とは言えない服装ばかりだった。褒めたつもりもないのに声を殺してすすり泣く顔が微妙に綻んでいるのには、嫌でも苦笑いを誘われる。
「じゃ、行くか。」
「はい?」
「休みだからな。天気もいい。久し振りに、外に出してやる。」
あからさまに唖然と口を開け、間の抜けた面相を作った。
此方が不愉快そうに眉を顰めても、あれは構わず蒼褪め、首を横に往復させる。顔の忙しい奴だ。
「だっ、だめです!明るいうちに外なんて、絶対だめ!もしばれたら、先輩捕まっちゃいます!」
俺の鼻息一つで、キャンキャン吠えるだけの反論モドキは止んだ。
女モドキのゴミ虫は、さも申し訳なさそうに背筋を縮こめて、甚だ俯いて、何言やらぼそぼそと呟いている。
首根っこを引っ掴んで、姿見の方へ向き合わせた。一人の世界に篭っている脳味噌など、背中を引っ叩けばそれでいい。
「自分の目で見てみろ。昔のお前とは、てんで似ても似つかないだろ。」
鏡に映る人間は、強張った表情で怪訝そうに大きな瞳を見開き、自分の頭の天辺から爪先までを信じ難い物を見るように眺め続けている。
頬や服の裾、袖をあちこち摘んでは息を飲み、疑い深く自分で自分を睨み付ける様子など、肩越しに見ていて思わず噴き出しそうな程だった。
徹底して地味に統一された揃えだった。冬用の女物を見るのは、こいつも初めてではなかろうに。いや、初めてなのかも知れないが。
丈の長めのスカートを穿かせたって、膝小僧の辺りの少年らしい骨っぽさはどうしたって隠せるものではないが、上にコートでも羽織らせれば誤魔化せるだろう。
防寒具の色合いは暖色と言えなくもないが、これではむしろ、枯れ木や落ち葉の色を連想してしまうのだけれども。
「街って、人が多いんですね。みんな、僕を見て哂ってるみたいで、少しだけ、怖いです……」
「はぁ……?……お前の鬱のせいだろ。気にし過ぎだ。」
こいつを連れて、県境を超えるまで遠出した覚えはない。
住み慣れた土地とは倍も活気の違う大都市の通りは、この時季柄、菓子会社の走狗を実に立派にこなしている最中だ。
繋いでいた左手は、何時の間にか肘の上まで、両腕でしがみ付かれている。
手は繋いでおけ、とは確かに言い付けた覚えがあるが、元から脚に障害がある上に、歩幅もまるきり違うのだ。動き辛くて仕方がない。
「はぁ……?……お前の鬱のせいだろ。気にし過ぎだ。」
こいつを連れて、県境を超えるまで遠出した覚えはない。
住み慣れた土地とは倍も活気の違う大都市の通りは、この時季柄、菓子会社の走狗を実に立派にこなしている最中だ。
繋いでいた左手は、何時の間にか肘の上まで、両腕でしがみ付かれている。
手は繋いでおけ、とは確かに言い付けた覚えがあるが、元から脚に障害がある上に、歩幅もまるきり違うのだ。動き辛くて仕方がない。
かつてのこれは、落ち窪んだ目とひび割れた唇を持ち、背筋は曲がり、削げた贅肉と、隠れて目立たなくても無数に広がる傷の痕、負のオーラを無自覚に撒き散らす、存在自体が不自然な生き物だった。
だが、今は。ほんの少し顔を寄せただけで、俺の精の匂いが仄かに分るくらいに心身を穢され尽くされているのに……、纏う雰囲気は、無垢そのものだ。
少しの風が通り過ぎただけで、冬空の彼方へ溶け去ってしまいそうな儚さを覚える。
唇を強く引き結んで辺りの様子を窺い、肩を窄めて怯えて縮こまる清楚な背筋は、何故か鬱陶しく思えない。
五分に一回のペースで、天気や菓子の話を側の野郎に投げている。こんな馬鹿げた話があるものか。
少しの風が通り過ぎただけで、冬空の彼方へ溶け去ってしまいそうな儚さを覚える。
唇を強く引き結んで辺りの様子を窺い、肩を窄めて怯えて縮こまる清楚な背筋は、何故か鬱陶しく思えない。
五分に一回のペースで、天気や菓子の話を側の野郎に投げている。こんな馬鹿げた話があるものか。
一時間もうろつけば、建物がゴミゴミしていない地区に出る。
品のいい喫茶店とコーヒー屋を交互に何件か遣り過ごして、図書館を臨むようになると、
まるでそのタイミングを見計らったかのように、奴の足取りが覚束無くなる。
「歩き過ぎたな。お前でも好きそうな、向こうで休むか。」
ロビーのソファに横たえようとしても首を振って嫌々をする癖に、顔は紅潮して、息をするのも辛そうだ。
「どうした。……寒いか?熱でも出したか?」
「ちがうの、ちがうの……」
「……スカートは冷えるからな。腹でも下したか。」
「せんぱぃ……えっちしたいよぅ……」
「………………………………」
無言で舌を引っ張ってやれば、脳味噌精液漬けの色情狂は声も出せずに悶絶して黙りこくる。
こつをこうまでしてしまったのを誰のせいにも転嫁できないのが、何よりも腹立たしい。
不幸中の幸いか、館内に人気は殆ど無さそうだった。
受験を控えた連中の溜まり場となっているイメージがあったが、時と場所によりけりなのだろうか。
「確か……トイレがあったな。念の為だ、二階行くか。」
「そんなぁ……、それじゃぜんぜん、足りないです……」
「うるせえ」
品のいい喫茶店とコーヒー屋を交互に何件か遣り過ごして、図書館を臨むようになると、
まるでそのタイミングを見計らったかのように、奴の足取りが覚束無くなる。
「歩き過ぎたな。お前でも好きそうな、向こうで休むか。」
ロビーのソファに横たえようとしても首を振って嫌々をする癖に、顔は紅潮して、息をするのも辛そうだ。
「どうした。……寒いか?熱でも出したか?」
「ちがうの、ちがうの……」
「……スカートは冷えるからな。腹でも下したか。」
「せんぱぃ……えっちしたいよぅ……」
「………………………………」
無言で舌を引っ張ってやれば、脳味噌精液漬けの色情狂は声も出せずに悶絶して黙りこくる。
こつをこうまでしてしまったのを誰のせいにも転嫁できないのが、何よりも腹立たしい。
不幸中の幸いか、館内に人気は殆ど無さそうだった。
受験を控えた連中の溜まり場となっているイメージがあったが、時と場所によりけりなのだろうか。
「確か……トイレがあったな。念の為だ、二階行くか。」
「そんなぁ……、それじゃぜんぜん、足りないです……」
「うるせえ」
上の口に注いでやるのは、俺の気が向いた特別な場合に限っている。
誉めてやりたい時に使える、互いに利のある褒賞の、一つの形だった。
「熱くて、おっきい、ふぁああ、すっごく硬いよう……。こんなに素敵なのが、たくさん、何度も、僕のお腹のいちばん奥まで、入ったんですよね……。」
頬擦りと顔擦りから始めるのが、二人の間では暗黙の決め事だった。
赤黒く浮き出て脈動する血管に沿い、幹を上下しつつ、唇と舌を這わせている。
端整な鼻梁と涼やかな目元は湧き出る先走りで生温く潤み、毛だらけの袋と根本は唇によって啄まれる。
頬の柔らかい産毛は、いつも反則だと思う。
亀頭は飲み込ませない。いつもの寝室であれば、口遣いと言えばイラマチオが常であったが、
この場で髪や服を汚すのも、顎関節の付け外し遊びも御免蒙りたい。
誉めてやりたい時に使える、互いに利のある褒賞の、一つの形だった。
「熱くて、おっきい、ふぁああ、すっごく硬いよう……。こんなに素敵なのが、たくさん、何度も、僕のお腹のいちばん奥まで、入ったんですよね……。」
頬擦りと顔擦りから始めるのが、二人の間では暗黙の決め事だった。
赤黒く浮き出て脈動する血管に沿い、幹を上下しつつ、唇と舌を這わせている。
端整な鼻梁と涼やかな目元は湧き出る先走りで生温く潤み、毛だらけの袋と根本は唇によって啄まれる。
頬の柔らかい産毛は、いつも反則だと思う。
亀頭は飲み込ませない。いつもの寝室であれば、口遣いと言えばイラマチオが常であったが、
この場で髪や服を汚すのも、顎関節の付け外し遊びも御免蒙りたい。
「喉にぶち当たったら噎せるだろ。まずは舌で堰き止めて、口の中に溜めろ。それから飲め。」
手扱きの往復も下手だ。射精するまで扱きは徐々に速くし続けろと教えても、俺が出すまでに腕が疲れるのか、実践で満足できた試しはない。泣きそうな顔で此方の顔色を窺いだせば、舌打ちを一つ残して諦めた。何故こうして自分の手を使わねばならんのか。
「出すぞ。」
前触れに言っておいた言葉と同時か、それよりも早いくらいか。
びぐん!と跳ねようとしても、それの主が幹に手を添えていれば、抑えるに容易い。
溜め込んだ原液が管を押し広げて走り抜ける快楽は、それでもそれなりのものでしかなく、
眦に雫を浮かべて懸命に喉を鳴らす姿に、頬袋を張らせたリスを思い出した。
これでもし吐き出しでもすれば、空気がどうなるかは互いに熟知している。
仕置きには大喜びでも、俺の期待を裏切る事には、心の底から恐怖しているようだから。
手扱きの往復も下手だ。射精するまで扱きは徐々に速くし続けろと教えても、俺が出すまでに腕が疲れるのか、実践で満足できた試しはない。泣きそうな顔で此方の顔色を窺いだせば、舌打ちを一つ残して諦めた。何故こうして自分の手を使わねばならんのか。
「出すぞ。」
前触れに言っておいた言葉と同時か、それよりも早いくらいか。
びぐん!と跳ねようとしても、それの主が幹に手を添えていれば、抑えるに容易い。
溜め込んだ原液が管を押し広げて走り抜ける快楽は、それでもそれなりのものでしかなく、
眦に雫を浮かべて懸命に喉を鳴らす姿に、頬袋を張らせたリスを思い出した。
これでもし吐き出しでもすれば、空気がどうなるかは互いに熟知している。
仕置きには大喜びでも、俺の期待を裏切る事には、心の底から恐怖しているようだから。
脈打つ高熱が小康を迎えて、張り詰めた頬の膨らみもやがては治まる。
尿道の残り物も吸い尽くしてから漸く口を離した少年は、げっぷよりも先に、涙を拭いながら俺に詫びた。
この醜態には慰めの言葉も掛けられない。せいぜい、顎の下を指先で擦ってやるのが関の山だった。
尿道の残り物も吸い尽くしてから漸く口を離した少年は、げっぷよりも先に、涙を拭いながら俺に詫びた。
この醜態には慰めの言葉も掛けられない。せいぜい、顎の下を指先で擦ってやるのが関の山だった。
「せ、せんぱぃぃ、ごめんなさぃ。ごめんなさい……。」
こいつが泣いているのは、欲情している証拠だ。泣きさえすれば抱いて貰えると、無意識で反応するのか。
「まずは……見たいな。スカート持ち上げろ。自分で晒せ。」
「……ごめんなさい……。」
おずおずと地味なスカートをたくし上げる。誘っているとは解るが、半べそに劣情を催されるのが忌々しい。
串刺しにして火で炙れば、今すぐにでも焼いて食えそうな白い太腿が殊更目に毒だった。
純白のショーツが、女物には有り得ない不自然な膨らみを見せた所で、堪忍できなくなった。
こいつが泣いているのは、欲情している証拠だ。泣きさえすれば抱いて貰えると、無意識で反応するのか。
「まずは……見たいな。スカート持ち上げろ。自分で晒せ。」
「……ごめんなさい……。」
おずおずと地味なスカートをたくし上げる。誘っているとは解るが、半べそに劣情を催されるのが忌々しい。
串刺しにして火で炙れば、今すぐにでも焼いて食えそうな白い太腿が殊更目に毒だった。
純白のショーツが、女物には有り得ない不自然な膨らみを見せた所で、堪忍できなくなった。
光の加減が輪っかを作る、無駄に質の良い前髪を掴んで、タイル張りの壁に後頭部を叩き付ける。
「いっ!……ひっ……。ぅ……ぅぅ……」
「てめえ……それ、どういうつもりだ。」
ショーツからはみ出して屹立する青臭いチンポは、無毛の根本からしっかりと薄紅色のコンドームで覆っている。ご丁寧に、ゴムの上から念入りに、乱雑な巻き方で雁字搦めに縛り上げてもいた。いつだかに買って来たレース付きのフリルリボンを使ってだ。
「だって、だってぇ……。朝から、いっぱいして下さるって思ってたのに、お預けで……
おちんちん、びんびんだったのに、女の子の格好までさせて貰えて、もっとえっちな気分になって、
穿いてみたら……スカートの裏地が……擦れて、歩くだけで……もう、もう……
このままじゃ絶対、お洋服汚しちゃうって、思ったから……。」
「いっ!……ひっ……。ぅ……ぅぅ……」
「てめえ……それ、どういうつもりだ。」
ショーツからはみ出して屹立する青臭いチンポは、無毛の根本からしっかりと薄紅色のコンドームで覆っている。ご丁寧に、ゴムの上から念入りに、乱雑な巻き方で雁字搦めに縛り上げてもいた。いつだかに買って来たレース付きのフリルリボンを使ってだ。
「だって、だってぇ……。朝から、いっぱいして下さるって思ってたのに、お預けで……
おちんちん、びんびんだったのに、女の子の格好までさせて貰えて、もっとえっちな気分になって、
穿いてみたら……スカートの裏地が……擦れて、歩くだけで……もう、もう……
このままじゃ絶対、お洋服汚しちゃうって、思ったから……。」
「……そうかよ。後ろ向いて、尻、上げろ。」
左手で口を塞ぐ。鏡で相向かい合う、歪なペニスをそそり立たせた女装の瞳には、明らかな恐怖が満ち満ちて、顔面は蒼白になっている。
上質のシルクショーツに包まれる不自然な膨らみに触れれば、薄く汗の滲む皮膚にぴくりと震えが走った。
二つの柔らかい睾丸を利き手の中に握り込み、ピーナッツの殻でも割るように握力を収斂させれば、
(むぎゅううううううううううううううう!!!!)
咽から吹き上がる反射的な苦鳴は厚い左手に遮られ、外に漏れ出すことを決して許されない。
スカートの裾をきつく握りしめているせいで、火照っていた筈の指は色が真っ白になっていた。
つま先立ちのまま、ぴんと張り詰めた背筋は弓形に反りかえる、見開いた瞳から一気に涙が溢れ出て、口を塞ぐ手の甲は塩辛い水で濡らされる。
「はん。すぐには出ないか。おい、虫。家畜。気分はどうだ?」
二つの小さなゴムマリを互いにぶつけ合うようにして、嚢の内部でごりごりと転がす。
(ぐううっ、ぎゅふっ!!ぎっ、ぐぎいっ、ぐぎゅふむぅぅぅっ!!!)
今度は目玉を剥いた。瞳孔が開き、白目の毛細血管が千切れて鬱血が始まる。
それは縛り首のビデオによく似ている。
「まだ出ないな。そりゃあそうか。」
玉ころを片方選び、哀れなそのたった一つだけに、割増しした握力で以って全力で圧搾を始める。
(げうっっ!!!ぎゃううう!!ぐううう、ぐぎゅむふううううう!うぐふうう!!!!)
十秒も経たない内に、白目を剥いて意識を失ってしまう。
少年の吐き出した泡が指の隙間に滲んで、ぬるぬるした。
不快だが、嘔吐しなかっただけマシだ。ぐったりと倒れかかった所を慌てて抱き留める。床や調度品への激突は避けられたが、こうなると些か面倒だ。
「この野郎。……仕方ない奴だ。」
大用の個室に連れ込んで、介抱してやるしかないのか。
左手で口を塞ぐ。鏡で相向かい合う、歪なペニスをそそり立たせた女装の瞳には、明らかな恐怖が満ち満ちて、顔面は蒼白になっている。
上質のシルクショーツに包まれる不自然な膨らみに触れれば、薄く汗の滲む皮膚にぴくりと震えが走った。
二つの柔らかい睾丸を利き手の中に握り込み、ピーナッツの殻でも割るように握力を収斂させれば、
(むぎゅううううううううううううううう!!!!)
咽から吹き上がる反射的な苦鳴は厚い左手に遮られ、外に漏れ出すことを決して許されない。
スカートの裾をきつく握りしめているせいで、火照っていた筈の指は色が真っ白になっていた。
つま先立ちのまま、ぴんと張り詰めた背筋は弓形に反りかえる、見開いた瞳から一気に涙が溢れ出て、口を塞ぐ手の甲は塩辛い水で濡らされる。
「はん。すぐには出ないか。おい、虫。家畜。気分はどうだ?」
二つの小さなゴムマリを互いにぶつけ合うようにして、嚢の内部でごりごりと転がす。
(ぐううっ、ぎゅふっ!!ぎっ、ぐぎいっ、ぐぎゅふむぅぅぅっ!!!)
今度は目玉を剥いた。瞳孔が開き、白目の毛細血管が千切れて鬱血が始まる。
それは縛り首のビデオによく似ている。
「まだ出ないな。そりゃあそうか。」
玉ころを片方選び、哀れなそのたった一つだけに、割増しした握力で以って全力で圧搾を始める。
(げうっっ!!!ぎゃううう!!ぐううう、ぐぎゅむふううううう!うぐふうう!!!!)
十秒も経たない内に、白目を剥いて意識を失ってしまう。
少年の吐き出した泡が指の隙間に滲んで、ぬるぬるした。
不快だが、嘔吐しなかっただけマシだ。ぐったりと倒れかかった所を慌てて抱き留める。床や調度品への激突は避けられたが、こうなると些か面倒だ。
「この野郎。……仕方ない奴だ。」
大用の個室に連れ込んで、介抱してやるしかないのか。
洋式便座に腰掛けて、どうするべきかと思案した。
目に付いた所は、馬鹿のようにひん剥いた紅白の瞳だった。苛立ちを紛らそうと、指先で、その元白目の部分を撫ぜる。
生温いゼリーそのものの触感を愉しめたのは、ほんの数秒でしかない。
「ぎゃああああ!?」
「起きたか。」
痛みのお陰で跳ね起きた寝坊助を軽く睨んだ。
吐いている息はぜえぜえと上がり、涙の溢れる真っ赤な目を押さえて盛んに擦っている。
「大人しくしてろ。……急所は耐えられないんだな。何だかんだで、男か。」
逃げようとする気配を感じたので、すかさず腕の中に捕えて、温い背に腹をくっつける。
「抱き心地いいな、お前。ちまっこくて、サイズが丁度いい。」
こうして膝の上に座らせると、顎の下辺りに頭の旋毛が見下ろせる按配になる。
細く小さな体を包む冬用の繊維質は弾力的で軟らかく、このまま抱いて眠りたくなる程だった。
露骨に怯えの仕草を伴いながら、おずおずと俺を見上げて来る。「ごめんなさい」と、震える唇が小さく謝罪の言葉を紡いだ。
「帰りに…首輪でも買ってくか。」
「え?なんですか?」
「ベッドに繋ぐんだよ。少なくとも、ぶっ続けで三日は犯しまくる。」
腕の中の少年は、赤く頬を染めて俯く。
「何時ものように、ケツが擦り切れるだけで済むと思うな。初めての時があったろ。……はらわたがズタズタになるまで犯してやる。」
「でも…それじゃ…、ご飯が…作れないし……食べれないです……」
「俺のスペルマじゃ嫌か?」
「………いっぱい、下さいね。」
「…もう、勃ってるだろ。スカート持ち上げて、股開け。」
「あっ、あの!」
「……何だ。チンポはやんねえけど、今度はまともに達かせてやるよ。早くしろ。」
目に付いた所は、馬鹿のようにひん剥いた紅白の瞳だった。苛立ちを紛らそうと、指先で、その元白目の部分を撫ぜる。
生温いゼリーそのものの触感を愉しめたのは、ほんの数秒でしかない。
「ぎゃああああ!?」
「起きたか。」
痛みのお陰で跳ね起きた寝坊助を軽く睨んだ。
吐いている息はぜえぜえと上がり、涙の溢れる真っ赤な目を押さえて盛んに擦っている。
「大人しくしてろ。……急所は耐えられないんだな。何だかんだで、男か。」
逃げようとする気配を感じたので、すかさず腕の中に捕えて、温い背に腹をくっつける。
「抱き心地いいな、お前。ちまっこくて、サイズが丁度いい。」
こうして膝の上に座らせると、顎の下辺りに頭の旋毛が見下ろせる按配になる。
細く小さな体を包む冬用の繊維質は弾力的で軟らかく、このまま抱いて眠りたくなる程だった。
露骨に怯えの仕草を伴いながら、おずおずと俺を見上げて来る。「ごめんなさい」と、震える唇が小さく謝罪の言葉を紡いだ。
「帰りに…首輪でも買ってくか。」
「え?なんですか?」
「ベッドに繋ぐんだよ。少なくとも、ぶっ続けで三日は犯しまくる。」
腕の中の少年は、赤く頬を染めて俯く。
「何時ものように、ケツが擦り切れるだけで済むと思うな。初めての時があったろ。……はらわたがズタズタになるまで犯してやる。」
「でも…それじゃ…、ご飯が…作れないし……食べれないです……」
「俺のスペルマじゃ嫌か?」
「………いっぱい、下さいね。」
「…もう、勃ってるだろ。スカート持ち上げて、股開け。」
「あっ、あの!」
「……何だ。チンポはやんねえけど、今度はまともに達かせてやるよ。早くしろ。」
少年がおずおずとチェックスカートを持ち上げれば、眩いばかりの太腿が露わになる。
在るとも思えぬゴムの隙間から逃げ出した液体は、ショーツにたっぷりと染みを描いていた。
煽情的なリボンを解いただけで、ゴム先端の汁溜りがじわりと膨らむ。香る汗の匂いが途端に甘くなった。
期待で濡れそぼった視線をわざと射られつつ、陶器のように白く美しい太腿に指を這わせ、撫で擦りながら臀部へと向かう。
さきほど痛めつけた小ぶりな袋の下をまさぐると、驚いた事に、そこは既に潤滑液に塗れていた。
「お尻、変になっちゃってます……痺れて、むずむずして、もう駄目なのに!早く、早くぅ!」
自分で散々遣い込んだ肉孔だと思えば、不思議な事ではない。こんな生殖器でもない薄い粘膜を、今までどれだけ引き裂いたことだろう。つぷり、と汁気たっぷりの音を立てて、何時の間にか作り上げていた名器に易々と中指が吸い込まれてしまう。
「ふぁああああぁぁ……ほんとにぃ、入れてくれたぁ…。気持ちいい、気持ちいいよう……」
浅い入り口は、こいつにとって比較的経験が少ない。
忽ちの内に押し寄せて来る肉襞の隙間に滑り込み、爪で割り拓きつつ、じりじりと奥を目指す。
この位置は、とっくの昔に既知だった。
尿道を取り巻く、こりこりとした器官。
「ひん!ひいいいん!そんなにぐりゅぐりゅされたら、みゆくもれちゃうのにぃぃ!
でちゃうぅー!でちゃうのぉ!」
「馬鹿野郎、声でかいぞ。」
「ばかはっ、せんっ、ぱいっ、だよぅ!
…いっつも、そこ、そこばっかりぃ、すりゅのぉっ!すっ、すりゅんだからぁ!!」
在るとも思えぬゴムの隙間から逃げ出した液体は、ショーツにたっぷりと染みを描いていた。
煽情的なリボンを解いただけで、ゴム先端の汁溜りがじわりと膨らむ。香る汗の匂いが途端に甘くなった。
期待で濡れそぼった視線をわざと射られつつ、陶器のように白く美しい太腿に指を這わせ、撫で擦りながら臀部へと向かう。
さきほど痛めつけた小ぶりな袋の下をまさぐると、驚いた事に、そこは既に潤滑液に塗れていた。
「お尻、変になっちゃってます……痺れて、むずむずして、もう駄目なのに!早く、早くぅ!」
自分で散々遣い込んだ肉孔だと思えば、不思議な事ではない。こんな生殖器でもない薄い粘膜を、今までどれだけ引き裂いたことだろう。つぷり、と汁気たっぷりの音を立てて、何時の間にか作り上げていた名器に易々と中指が吸い込まれてしまう。
「ふぁああああぁぁ……ほんとにぃ、入れてくれたぁ…。気持ちいい、気持ちいいよう……」
浅い入り口は、こいつにとって比較的経験が少ない。
忽ちの内に押し寄せて来る肉襞の隙間に滑り込み、爪で割り拓きつつ、じりじりと奥を目指す。
この位置は、とっくの昔に既知だった。
尿道を取り巻く、こりこりとした器官。
「ひん!ひいいいん!そんなにぐりゅぐりゅされたら、みゆくもれちゃうのにぃぃ!
でちゃうぅー!でちゃうのぉ!」
「馬鹿野郎、声でかいぞ。」
「ばかはっ、せんっ、ぱいっ、だよぅ!
…いっつも、そこ、そこばっかりぃ、すりゅのぉっ!すっ、すりゅんだからぁ!!」
玩具が馬鹿になるスイッチを見付けた所で、さっさと達かせに薬指も加えた。
スカートを保持する意義は既に失われていたが、命令を取り下げていないので、未だ律儀に摘んでいた。
二本の指で挟み、ほんの少しだけ寄せ上がった粘膜の膨らみを爪で突つき、引っ掻く。
「あ、はふ、はふぁあ、ひぃん、はひぃん!にゃあ、ふぁぁう……ぁあ!ひゃあああ!!!」
徐々に威力を強めてやれば、快楽に操られるがまま体が、数秒スパンで繰り返し軽いアクメを貪っていた。
窮屈な肉洞が奥へ奥へと引き摺り込みにかかった。歓喜に震えながら、指に吸い付いて来る。
「……そろそろ、イっていい。」
根本が埋まるまで刺し込まれた二本の指のせいで、前立腺がひしゃげて押し潰された。
「きゃう」
同じ男とは思えない無垢なペニスがわななく度に、ゴムの形は水風船のように膨らむ。
ひくん、ひくんと精を吐き出すペースに合わせて、前立腺を揉みしだく。
そのまま、指が疲れるまで愛撫を続けていた。
射精に付き合っていたのか、射精をさせていたのか、どちらが正しかったかは分らない。
「あっ、あっ、あ、ああ……あ……
先輩ぃ。僕、先輩が好き。大好きです……。好きすぎて、おかしくなって、こわれて、しんじゃう……。」
「……俺もだ。好きだよ。家畜。」
スカートを保持する意義は既に失われていたが、命令を取り下げていないので、未だ律儀に摘んでいた。
二本の指で挟み、ほんの少しだけ寄せ上がった粘膜の膨らみを爪で突つき、引っ掻く。
「あ、はふ、はふぁあ、ひぃん、はひぃん!にゃあ、ふぁぁう……ぁあ!ひゃあああ!!!」
徐々に威力を強めてやれば、快楽に操られるがまま体が、数秒スパンで繰り返し軽いアクメを貪っていた。
窮屈な肉洞が奥へ奥へと引き摺り込みにかかった。歓喜に震えながら、指に吸い付いて来る。
「……そろそろ、イっていい。」
根本が埋まるまで刺し込まれた二本の指のせいで、前立腺がひしゃげて押し潰された。
「きゃう」
同じ男とは思えない無垢なペニスがわななく度に、ゴムの形は水風船のように膨らむ。
ひくん、ひくんと精を吐き出すペースに合わせて、前立腺を揉みしだく。
そのまま、指が疲れるまで愛撫を続けていた。
射精に付き合っていたのか、射精をさせていたのか、どちらが正しかったかは分らない。
「あっ、あっ、あ、ああ……あ……
先輩ぃ。僕、先輩が好き。大好きです……。好きすぎて、おかしくなって、こわれて、しんじゃう……。」
「……俺もだ。好きだよ。家畜。」
いつからか、少年の口から溢れた涎が、清流の筋を滴らせていた。
ぽっかりと物欲しそうに開いた唇に、解いたゴムを銜え込ませ、中身が垂れ落ちるまま舐め取らせる。
膝の上で深い余韻に喘ぐ少女のような少年の媚態に、ここまで思考を日和らされては目を細めざるを得ない
「先輩とえっちすると、さっきのが、ずうっと続くんです。おちんちんでも、指でもそう。
僕、おちんちんもたまたまも小さいから、男の子らしい射精なんて、少しで終わっちゃってませんか?
……そのあと…。お尻が…すごく気持ちよくなって……。イったまま、いつまでも降りられなくて……。
そのまま先輩にナカ出しまでされたら、お仕舞いなんです。
真っ白な綿雲の中で、いっぱいの幸せに、途切れなく揉みくちゃにされてるみたい。」
正面に腸液でてらてらと濡れ光る指を翳してやれば、少年は短い舌を伸ばし、絡ませ、愛しそうに、執拗に舐めしゃぶる。
背筋の奥から押し寄せてくる、甘くこそばゆい幸福感には何をしても抗いようがなく。
そういう訳の分からない強敵に対してはあっさりと降伏して、随分と長い間、身も心もそれに委ねていた。
ぽっかりと物欲しそうに開いた唇に、解いたゴムを銜え込ませ、中身が垂れ落ちるまま舐め取らせる。
膝の上で深い余韻に喘ぐ少女のような少年の媚態に、ここまで思考を日和らされては目を細めざるを得ない
「先輩とえっちすると、さっきのが、ずうっと続くんです。おちんちんでも、指でもそう。
僕、おちんちんもたまたまも小さいから、男の子らしい射精なんて、少しで終わっちゃってませんか?
……そのあと…。お尻が…すごく気持ちよくなって……。イったまま、いつまでも降りられなくて……。
そのまま先輩にナカ出しまでされたら、お仕舞いなんです。
真っ白な綿雲の中で、いっぱいの幸せに、途切れなく揉みくちゃにされてるみたい。」
正面に腸液でてらてらと濡れ光る指を翳してやれば、少年は短い舌を伸ばし、絡ませ、愛しそうに、執拗に舐めしゃぶる。
背筋の奥から押し寄せてくる、甘くこそばゆい幸福感には何をしても抗いようがなく。
そういう訳の分からない強敵に対してはあっさりと降伏して、随分と長い間、身も心もそれに委ねていた。
図書館のWCに篭っているだけで、日は大方暮れてしまっていた。
夕日が照っている間にホームセンターに立ち寄れば、店を出る頃には街灯がでしゃばり出す夜闇になっていた。店員に頼んで、無駄に豪勢なラッピングを施して貰うのに大層な時間を食わされたせいだが。
変に遣り過ごそうとせず、堂々と購入することで逆にカムフラージュできるという計画は、俺一人が仕組んだ浅知恵であって欲しい。
店から出た瞬間に左腕へ頬を摺り寄せて来る甘ったれの色狂いが、平気で自分の荷物を持とうとしなかったのが、そのコストだろう。
夕日が照っている間にホームセンターに立ち寄れば、店を出る頃には街灯がでしゃばり出す夜闇になっていた。店員に頼んで、無駄に豪勢なラッピングを施して貰うのに大層な時間を食わされたせいだが。
変に遣り過ごそうとせず、堂々と購入することで逆にカムフラージュできるという計画は、俺一人が仕組んだ浅知恵であって欲しい。
店から出た瞬間に左腕へ頬を摺り寄せて来る甘ったれの色狂いが、平気で自分の荷物を持とうとしなかったのが、そのコストだろう。
帰路の駅前。何本ものコンクリートの塊が悠々と線路を飛び越えて、空中で立体に交差する歩道橋がある。
立橋の通路が長い直線となる台形の天辺の中央で、平然と何も告げぬまま立ち止まった。
深呼吸をすると、廃ガスの臭いが薄く、塵が舞っていない、冷たく澄んだ空気が肺に心地良い。
勝手に漏れる欠伸に連れられた、涙腺の滲みを拭い取る。朧な視界がゆっくりと戻ると、そこには、
三日月以外の全てが黒い、ぞっとする闇夜を見上げながら、俺の胸ほどまである鉄柵によじ昇っている奴が居る。無駄に息を飲みこんだ。
「何してんだ。」
「?……んんー…、先輩の…、お顔が見たかったんですよー。」
「本当か?」
どこか名残惜しそうに手摺りから身を離した奴は、派手な包装の小袋を両手で捧げ持つと、濡れた瞳を爛々とさせて、高い声で強請るのだ。
「ね、先輩。着けて下さい。」
「はぐらかすな。自分でやれ。……襟ん中入れて、家までは隠してろよ。」
踵を返して、正しい帰り道である筈の、使い慣れた順路を往く。
雑音の殆どしない静かな月夜にわしゃわしゃ鳴り響く紙の音と、歩幅の短い軽い足音は、確かに俺を追って来ていた。
立橋の通路が長い直線となる台形の天辺の中央で、平然と何も告げぬまま立ち止まった。
深呼吸をすると、廃ガスの臭いが薄く、塵が舞っていない、冷たく澄んだ空気が肺に心地良い。
勝手に漏れる欠伸に連れられた、涙腺の滲みを拭い取る。朧な視界がゆっくりと戻ると、そこには、
三日月以外の全てが黒い、ぞっとする闇夜を見上げながら、俺の胸ほどまである鉄柵によじ昇っている奴が居る。無駄に息を飲みこんだ。
「何してんだ。」
「?……んんー…、先輩の…、お顔が見たかったんですよー。」
「本当か?」
どこか名残惜しそうに手摺りから身を離した奴は、派手な包装の小袋を両手で捧げ持つと、濡れた瞳を爛々とさせて、高い声で強請るのだ。
「ね、先輩。着けて下さい。」
「はぐらかすな。自分でやれ。……襟ん中入れて、家までは隠してろよ。」
踵を返して、正しい帰り道である筈の、使い慣れた順路を往く。
雑音の殆どしない静かな月夜にわしゃわしゃ鳴り響く紙の音と、歩幅の短い軽い足音は、確かに俺を追って来ていた。
「そろそろ、街を出る。」
「はい。早く帰って、いっぱいしましょう。」
「違えよ馬鹿。県外だ。……どこの大学かは、決まってる。」
「……???」
何か、ぞっとした。振り返った後ろには、微笑を保ったまま、小首を右斜め十五度に傾げて、
色付きの雪女が顔面蒼白で凍り付いている。光を反射しない瞳の焦点はどこにも合っていない。
しっかりと嵌めた首輪を大事そうに握っている姿を装って、自分の爪で自分の咽を、白い肉が見えるまで掻き毟り始めた所を見逃さなかった。
寒風に晒されたのか、真っ赤に染まった左耳朶を抓り、遠慮なく腕を引いてやる。
それの重心も関節も、急な引っ張られる動きについてこれず、ただの棒切れになっていた両足は簡単にバランスを崩した。かつてなら、ここで鳩尾に膝を入れるのが礼儀のような関係だった。だが、今こんな所で吐瀉でもされては台無しだ。
丁度俺の鳩尾に、それの顔面が突っ込んで来る。
「連れてくぞ。下手に野良にして、バラされでもしたら堪ったもんじゃないからな。」
鼻水を啜り上げる、嫌な音もする。
「じゃ、じゃあ……。先輩がお嫁さん貰うまでは、一緒に居させて下さい。」
「嫁ができたら、どうすんだ。」
「……邪魔に……なりますから……。」
「……そうだな。好きにしろ。」
じき、俺の尻の辺りを行儀悪く撫で始める頃合いに、どうにも慣れない辛気臭い話を切り上げて、下りの坂道を降りることにした。
「はい。早く帰って、いっぱいしましょう。」
「違えよ馬鹿。県外だ。……どこの大学かは、決まってる。」
「……???」
何か、ぞっとした。振り返った後ろには、微笑を保ったまま、小首を右斜め十五度に傾げて、
色付きの雪女が顔面蒼白で凍り付いている。光を反射しない瞳の焦点はどこにも合っていない。
しっかりと嵌めた首輪を大事そうに握っている姿を装って、自分の爪で自分の咽を、白い肉が見えるまで掻き毟り始めた所を見逃さなかった。
寒風に晒されたのか、真っ赤に染まった左耳朶を抓り、遠慮なく腕を引いてやる。
それの重心も関節も、急な引っ張られる動きについてこれず、ただの棒切れになっていた両足は簡単にバランスを崩した。かつてなら、ここで鳩尾に膝を入れるのが礼儀のような関係だった。だが、今こんな所で吐瀉でもされては台無しだ。
丁度俺の鳩尾に、それの顔面が突っ込んで来る。
「連れてくぞ。下手に野良にして、バラされでもしたら堪ったもんじゃないからな。」
鼻水を啜り上げる、嫌な音もする。
「じゃ、じゃあ……。先輩がお嫁さん貰うまでは、一緒に居させて下さい。」
「嫁ができたら、どうすんだ。」
「……邪魔に……なりますから……。」
「……そうだな。好きにしろ。」
じき、俺の尻の辺りを行儀悪く撫で始める頃合いに、どうにも慣れない辛気臭い話を切り上げて、下りの坂道を降りることにした。
「そういえばこれ、何用の首輪でしたっけ。犬でしょうか?ねこさんかな?」
「お前…どこを見てたんだ。猛犬用だ。ドーベルマンとかああいう。デカめで強そうな連中の。
とにかく頑丈で、壊れにくそうなの選んだんだろ。」
「わー…………。……ぼ、僕。別に強くないし、逃げませんよ?」
「どうだか。攫われそうだ。」
何だか知らんが感極まったのか、慣れてもなさそうな突進の体勢で、ちんたら駆けて突っ込んで来るから、
踵を後ろに振って脛を軽く蹴突いてやれば、それだけで真下に屈み込み、下痢の時みたいにひぃひぃ呻き始める。
「お前…どこを見てたんだ。猛犬用だ。ドーベルマンとかああいう。デカめで強そうな連中の。
とにかく頑丈で、壊れにくそうなの選んだんだろ。」
「わー…………。……ぼ、僕。別に強くないし、逃げませんよ?」
「どうだか。攫われそうだ。」
何だか知らんが感極まったのか、慣れてもなさそうな突進の体勢で、ちんたら駆けて突っ込んで来るから、
踵を後ろに振って脛を軽く蹴突いてやれば、それだけで真下に屈み込み、下痢の時みたいにひぃひぃ呻き始める。
そうして、頬の引き攣れたようなニヤケ笑いで俺等を見下している、半分以上が大きく欠けた下品な月を仰ぎ見て、あからさまな苦笑を返したのだ。