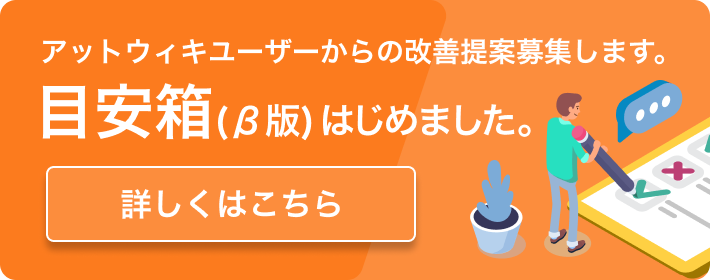「43」(2008/08/11 (月) 17:14:29) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
六月になってまず待ち遠しいなと思うのは、何よりも僕の誕生日前にソロイベントがあることだ。
僕の為に集まってくれたお客さんを前にして唄うのだから、いい歌を聞いて帰ってほしい。
だから、僕はこの日唄う歌をどれも大好きな三曲に悩んで選び、暇がある時は練習を重ねた。
二曲目の『駅前の大ハプニング』はモノマネもする先輩の藤本美貴さんの歌だから、特に練習には熱が入る。
緊張するな、大好きな先輩の歌だし、上手く唄えなかったらどうしようか、不安になってしまう。
考えても仕方ないし、僕はやれる事をやるだけだ。
夜中まで練習しすぎて授業中に眠くなるのだけは、先生に申し訳ない気持ちがあるんだけど、眠気には勝てない。
ごめんね、先生。
そんな夢の中に落ちていく僕に、ついこの間あった川口でのイベントの事が思い出された。
ファンクラブの会員の人たち限定で行われたイベントは順調に進み、もう終わりに差し掛かった時、事件が起こった。
お客さんが突然、僕の為にハッピーバースデーを唄いだしたのだ。
これは予想していなかったから、僕はお客さんの歌声が聞こえてきた途端、溢れる涙を堪えることができなくなった。
皆、僕をお祝いしようとマイクもないのに、精一杯唄ってくれている。
もう泣くなっていう方が無理なプレゼントに、つられてなっきぃまで泣き出していた。
イベントが終わった後、なっきぃが楽屋に戻っていく途中、「よかったね、ちっさー」と声をかけてくれた。
僕は涙を流しながら、うんと返事するのがやっとだった。
メンバーもこのプレゼントには皆喜んでくれたのかと思ったら、一人そうでもない人がいた。
栞菜は誕生日が同じ六月で、日にちは栞菜の方がイベントに近いのに祝ってもらえなかったのだ。
「何でちっさーばっかり。私だって誕生日近いんだよ。なのに、私だけハブんだよぉ」
楽屋に戻ると、栞菜の怒りが爆発した。
ぶすっとした顔でソファに座り、僕の方をちっとも見ようとはしてこない。
僕をちらっとでも見てしまえば、怒りがもっと溢れ出してきそうだと言わんばかりに顔を背けている。
怒る栞菜を見ていたら、お祝いされたと浮かれていた自分に罪悪感を感じてしまった。
本来なら、栞菜だってお祝いされておかしくないのに、してもらえなかったのだから当然だと思う。
僕のせいじゃないんだけど、それでも居心地の悪さがあるのが辛い。
その栞菜を慰めようと、愛理は隣に座って「そんなに怒らないの。後でお祝いしてもらえるって」と励まし出した。
「怒りたくもなるじゃん。だって、栞菜の名前はちっとも出なかったんだよ。馬鹿馬鹿しいじゃん」
「明日もイベントがあるでしょ。その時に用意してくれているんだって。期待してなよ」
「でも・・・それにしたって、酷いよ。握手だけじゃなく、こんな時でもハブるんだ。酷いよ」
握手会でのことは僕らメンバーも頭を悩ませる問題だ。
やたら、栞菜だけ握手をしないで帰る人たちが多く、終わった時にスタッフさんに注意される。
注意を受けた後、栞菜はとても寂しそうに溜息をついて帰ることが多い。
そんな姿をみているだけに、僕も少しでも励まそうとすると話しかけてみた。
「愛理の言う通りだよ。明日があるよ。だから、そんなに落ち込まないでよ」
僕は栞菜の為を思って言ったのに、栞菜にはむしろ鬱陶しいものに感じられてしまったらしい。
僕が声をかけた途端、栞菜は睨み殺すような視線を向けてきた。
火に油を注ぐってこういう事を言うのかな。
栞菜の怒りがさらに膨れ上がった気がして、僕は思わずたじろいだ。
「わかったような振りしないで。同情なんかまっぴらなんだから。あんたはどうして私の幸せをぶち壊すの?」
栞菜の心の声がぶちまけられた瞬間だった。
「皆が千聖はいい子だっていうけど、あんたがいっつもへらへらしてて嫌い。あの人たちまで千聖、千聖って」
「か、栞菜。いいすぎだよ。ちっさーは別に栞菜を怒らせようと思ったわけじゃないでしょ」
「愛理までそうやってかばう。皆して私よりちっさーが好きなんだ」
・・・嫌い、今、栞菜は僕の事を嫌いだって言った?
あれ、どうしたんだろうな、急に涙がまた溢れてきてしまった。
今度は嬉しくてなんかじゃない、悲しくて涙が溢れてきた。
まさか、栞菜からこんな言葉を言われるとはちっとも思っていなかったから、僕は結構傷ついていた。
「ご、ごめんよ。無神経だった。ごめん」
僕は顔も上げられないまま、走って楽屋を出た。
目的地なんてなかった。
ただ、栞菜の前からいなくなった方がお互いの為だと思って、僕は走っていた。
夢中で走った、後ろは振り向かないでひたすら走った。
涙で目の前がよく見えなかったし、スタッフさんに何度もぶつかりそうになりながら、楽屋から逃げた。
自分でも足が速い方だと自信があったから、僕に追いつく足を持つ人がいるとは思えなかった。
でも、僕は忘れていただけで、メンバー一の俊足を持つあの人なら追いついてもおかしくはない。
「千聖、待って。栞菜を慰めようとしてたんだよね、あんたは。偉いよ」
「あ、ありがとう」
紛れもない舞美ちゃんの声だ。
聞き間違えようもなく、聞き間違えを起こしたらとんでもなく失礼な僕らのリーダーの声。
優しい声をかけてくれただけじゃなく、僕を壊れそうな強い力で抱きしめてくれている。
舞美ちゃんの鼓動が僕の背中越しに聞こえてくる。
どれくらい僕らはくっついた状態で、どんな場所にいるんだろうな。
それにしても、舞美ちゃんは僕が困った時にはいつも力になってくれているんだって実感できた。
僕も抱きしめてくれる舞美ちゃんに応えるように、手を握り締めた。
「千聖、あのね、えぇと、どうしようっかな。何か恥ずかしいな。元気出してほしいし、今言っちゃおうかな」
「な、何を言う気なの?」
「えぇ~ちょっと待ってね。どうしようっかな~えぇい、もうここで言っちゃおう」
僕には舞美ちゃんが何を言おうとしているのか、てんで想像がつかなかった。
千聖が栞菜に「嫌い」だといわれ、楽屋を出て行った時、舞は真っ先に飛び出していった。
栞菜もメンバーであるから気がかりだが、それ以上に千聖が気になるのは恋の力によるところが大きい。
千聖、待ってて、すぐにあんたのところにいってあげるから。
舞は決して走りに自信があるわけではないが、それでも千聖に追いつこうと必死に走った。
あの馬鹿、こんな時に限って全力で走るなんて信じられないと悪態をつきながらも、方々を探した。
しかし、なかなか見つけることが出来ず、息を切らせながらとうとう歩き出してしまった。
額から流れる汗を拭き取りながら、舞はようやくそれらしい姿をみつけ出すことに成功した。
やっとみつかった安心感からか、声をかけようと近づいていったその瞬間、見てはいけないものを見た。
千聖を後ろから抱きしめる舞美の姿だ。
これだけなら、まだ舞には慰めにきただけと思えたのだが、舞美が語りだした内容には言葉を失っていた。
「千聖、私ね、好きになっちゃった。千聖のこと。好きだよ、千聖」
これが幻聴だと思いたかったが、何度も繰り返される言葉が染み付いて事実だと無情にも告げた。
馬鹿な、舞美が千聖を好きだなんて信じられるか。
舞美の言葉を受け、千聖は抱きしめる腕を解いて振り返る。
振り返った千聖の顔は、明らかに自分が見たことのない。
あれは自分が千聖を好きなのと同じ恋をしている人間の瞳だ。
では、千聖もまた舞美を好きだという事になるのだろう。
そうなると、こんなタイミングでこんな場所にまで来ていた自分はとんだ道化だ。
間抜けにも程がある、涙が溢れそうになるのを堪え、影に隠れ、舞は二人から目を離せなかった・・・
六月になってまず待ち遠しいなと思うのは、何よりも僕の誕生日前にソロイベントがあることだ。
僕の為に集まってくれたお客さんを前にして唄うのだから、いい歌を聞いて帰ってほしい。
だから、僕はこの日唄う歌をどれも大好きな三曲に悩んで選び、暇がある時は練習を重ねた。
二曲目の『駅前の大ハプニング』はモノマネもする先輩の藤本美貴さんの歌だから、特に練習には熱が入る。
緊張するな、大好きな先輩の歌だし、上手く唄えなかったらどうしようか、不安になってしまう。
考えても仕方ないし、僕はやれる事をやるだけだ。
夜中まで練習しすぎて授業中に眠くなるのだけは、先生に申し訳ない気持ちがあるんだけど、眠気には勝てない。
ごめんね、先生。
そんな夢の中に落ちていく僕に、ついこの間あった川口でのイベントの事が思い出された。
ファンクラブの会員の人たち限定で行われたイベントは順調に進み、もう終わりに差し掛かった時、事件が起こった。
お客さんが突然、僕の為にハッピーバースデーを唄いだしたのだ。
これは予想していなかったから、僕はお客さんの歌声が聞こえてきた途端、溢れる涙を堪えることができなくなった。
皆、僕をお祝いしようとマイクもないのに、精一杯唄ってくれている。
もう泣くなっていう方が無理なプレゼントに、つられてなっきぃまで泣き出していた。
イベントが終わった後、なっきぃが楽屋に戻っていく途中、「よかったね、ちっさー」と声をかけてくれた。
僕は涙を流しながら、うんと返事するのがやっとだった。
メンバーもこのプレゼントには皆喜んでくれたのかと思ったら、一人そうでもない人がいた。
栞菜は誕生日が同じ六月で、日にちは栞菜の方がイベントに近いのに祝ってもらえなかったのだ。
「何でちっさーばっかり。私だって誕生日近いんだよ。なのに、私だけハブんだよぉ」
楽屋に戻ると、栞菜の怒りが爆発した。
ぶすっとした顔でソファに座り、僕の方をちっとも見ようとはしてこない。
僕をちらっとでも見てしまえば、怒りがもっと溢れ出してきそうだと言わんばかりに顔を背けている。
怒る栞菜を見ていたら、お祝いされたと浮かれていた自分に罪悪感を感じてしまった。
本来なら、栞菜だってお祝いされておかしくないのに、してもらえなかったのだから当然だと思う。
僕のせいじゃないんだけど、それでも居心地の悪さがあるのが辛い。
その栞菜を慰めようと、愛理は隣に座って「そんなに怒らないの。後でお祝いしてもらえるって」と励まし出した。
「怒りたくもなるじゃん。だって、栞菜の名前はちっとも出なかったんだよ。馬鹿馬鹿しいじゃん」
「明日もイベントがあるでしょ。その時に用意してくれているんだって。期待してなよ」
「でも・・・それにしたって、酷いよ。握手だけじゃなく、こんな時でもハブるんだ。酷いよ」
握手会でのことは僕らメンバーも頭を悩ませる問題だ。
やたら、栞菜だけ握手をしないで帰る人たちが多く、終わった時にスタッフさんに注意される。
注意を受けた後、栞菜はとても寂しそうに溜息をついて帰ることが多い。
そんな姿をみているだけに、僕も少しでも励まそうとすると話しかけてみた。
「愛理の言う通りだよ。明日があるよ。だから、そんなに落ち込まないでよ」
僕は栞菜の為を思って言ったのに、栞菜にはむしろ鬱陶しいものに感じられてしまったらしい。
僕が声をかけた途端、栞菜は睨み殺すような視線を向けてきた。
火に油を注ぐってこういう事を言うのかな。
栞菜の怒りがさらに膨れ上がった気がして、僕は思わずたじろいだ。
「わかったような振りしないで。同情なんかまっぴらなんだから。あんたはどうして私の幸せをぶち壊すの?」
栞菜の心の声がぶちまけられた瞬間だった。
「皆が千聖はいい子だっていうけど、あんたがいっつもへらへらしてて嫌い。あの人たちまで千聖、千聖って」
「か、栞菜。いいすぎだよ。ちっさーは別に栞菜を怒らせようと思ったわけじゃないでしょ」
「愛理までそうやってかばう。皆して私よりちっさーが好きなんだ」
・・・嫌い、今、栞菜は僕の事を嫌いだって言った?
あれ、どうしたんだろうな、急に涙がまた溢れてきてしまった。
今度は嬉しくてなんかじゃない、悲しくて涙が溢れてきた。
まさか、栞菜からこんな言葉を言われるとはちっとも思っていなかったから、僕は結構傷ついていた。
「ご、ごめんよ。無神経だった。ごめん」
僕は顔も上げられないまま、走って楽屋を出た。
目的地なんてなかった。
ただ、栞菜の前からいなくなった方がお互いの為だと思って、僕は走っていた。
夢中で走った、後ろは振り向かないでひたすら走った。
涙で目の前がよく見えなかったし、スタッフさんに何度もぶつかりそうになりながら、楽屋から逃げた。
自分でも足が速い方だと自信があったから、僕に追いつく足を持つ人がいるとは思えなかった。
でも、僕は忘れていただけで、メンバー一の俊足を持つあの人なら追いついてもおかしくはない。
「千聖、待って。栞菜を慰めようとしてたんだよね、あんたは。偉いよ」
「あ、ありがとう」
紛れもない舞美ちゃんの声だ。
聞き間違えようもなく、聞き間違えを起こしたらとんでもなく失礼な僕らのリーダーの声。
優しい声をかけてくれただけじゃなく、僕を壊れそうな強い力で抱きしめてくれている。
舞美ちゃんの鼓動が僕の背中越しに聞こえてくる。
どれくらい僕らはくっついた状態で、どんな場所にいるんだろうな。
それにしても、舞美ちゃんは僕が困った時にはいつも力になってくれているんだって実感できた。
僕も抱きしめてくれる舞美ちゃんに応えるように、手を握り締めた。
「千聖、あのね、えぇと、どうしようっかな。何か恥ずかしいな。元気出してほしいし、今言っちゃおうかな」
「な、何を言う気なの?」
「えぇ~ちょっと待ってね。どうしようっかな~えぇい、もうここで言っちゃおう」
僕には舞美ちゃんが何を言おうとしているのか、てんで想像がつかなかった。
千聖が栞菜に「嫌い」だといわれ、楽屋を出て行った時、舞は真っ先に飛び出していった。
栞菜もメンバーであるから気がかりだが、それ以上に千聖が気になるのは恋の力によるところが大きい。
千聖、待ってて、すぐにあんたのところにいってあげるから。
舞は決して走りに自信があるわけではないが、それでも千聖に追いつこうと必死に走った。
あの馬鹿、こんな時に限って全力で走るなんて信じられないと悪態をつきながらも、方々を探した。
しかし、なかなか見つけることが出来ず、息を切らせながらとうとう歩き出してしまった。
額から流れる汗を拭き取りながら、舞はようやくそれらしい姿をみつけ出すことに成功した。
やっとみつかった安心感からか、声をかけようと近づいていったその瞬間、見てはいけないものを見た。
千聖を後ろから抱きしめる舞美の姿だ。
これだけなら、まだ舞には慰めにきただけと思えたのだが、舞美が語りだした内容には言葉を失っていた。
「千聖、私ね、好きになっちゃった。千聖のこと。好きだよ、千聖」
これが幻聴だと思いたかったが、何度も繰り返される言葉が染み付いて事実だと無情にも告げた。
馬鹿な、舞美が千聖を好きだなんて信じられるか。
舞美の言葉を受け、千聖は抱きしめる腕を解いて振り返る。
振り返った千聖の顔は、明らかに自分が見たことのない。
あれは自分が千聖を好きなのと同じ恋をしている人間の瞳だ。
では、千聖もまた舞美を好きだという事になるのだろう。
そうなると、こんなタイミングでこんな場所にまで来ていた自分はとんだ道化だ。
間抜けにも程がある、涙が溢れそうになるのを堪え、影に隠れ、舞は二人から目を離せなかった・・・
[[←前のページ>42]] [[次のページ→>44]]
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: